『心霊写真 1』
63 :心霊写真1 ◆oJUBn2VTGE :2013/02/23(土) 23:28:22.68 ID:dTAVLjsO0
師匠から聞いた話だ。
大学二回生の春だった。
僕はその日、バイト先である興信所に朝から呼ばれ、掃除と電話番をしていた。
掃除は鼻歌をうたっている間に終わり、あとは電話番という不確かな仕事だけが残った。
窓の方に目をやると、『小川調査事務所』と書いてあるシールがガラスに張り付いている。
もちろん外から見てそう見えるように書いてあるので、こちら側からは左右が反転している。
何度目かの欠伸をした。
ぽかぽかした陽気に、昼前の気だるい気分。待てども一向に鳴らない電話。
いったい自分がなにをしにここへ来ているのか、だんだんと分からなくなってくる。
デスクには僕の他に二人の人間が座っている。
一人はアルバイトの服部さんという二十代半ばの先輩で、この興信所では小川所長の右腕的な存在だ。
もう一人は同じくアルバイトの加奈子さんという、服部さんと同年輩の女性で、
僕をこの興信所でバイトさせている張本人だった。
オカルト全般に強く、霊視のようなことも出来るので、
この業界では『オバケ』と呼ばれる不可解な事案専門の調査員をしている。
僕のオカルト道の師匠でもあるところの彼女は、今日は非番だったはずだが、なぜかふらりと事務所に顔を出して、
「暇で楽なバイトだろう」と僕をからかっていたかと思うと、
自分のデスクに腰を据えて、読みかけの雑誌をつぶさに読み始めていた。
服部さんの方は、朝から市内で調査が入っていたはずなのだが、もう終わったのか、帰って来るなり無言で席に着き、
それからずっとカタカタとワープロのキーを一定のリズムで叩き続けている。
小川所長からは「留守電が壊れてるし、午前中誰もいなくなるから、頼むよ」と言われてやって来たのに、
これでは電話番など必要なかったではないか。
そもそも電話の一本も掛かってこないのだ。
実に街は今日も平和だ。いいことだ。
探偵家業にはつらいことだろうが、僕には何の関係もなかった。
服部さんは無口で、話しかけられない限り自分から口を開くことはないし、
いや、話しかけられても、なにもなかったかのように無視することさえあるし、
師匠の方は服部さんのことが嫌いらしく、一緒にいると同じように黙り込むことが多かった。
平和だ。
実に。
暇つぶしに自分の名刺でトランプタワーのようなものを拵えようと何度目かのチャレンジをしている時、
何の前触れもなくドアが開いた。
「小川さん、いるか」
この陽気だというのに、季節はずれのコートを身に着けた三十歳前後の男が、戸口に立って荒い息をしている。
その様子に僕は違和感を覚える。
格好のことではない。
確かにハンチング帽などかぶり、この部屋の誰よりも探偵じみた格好ではあったが、そのことではないのだ。
本当に何の前触れもなくドアは開いた。つまり階段を上ってくる足音がしなかった。
この小川調査事務所の入る雑居ビルは、家賃相応の“たてつけ”をしているのに。
つまりそのたてつけを補って余りあるほど、完全に足音を殺していたということだ。
なのに、この目の前の男はまるで階段を二足飛ばしで駆け上がってきたばかりのように、苦しそうに肩で息をしている。
この不一致が違和感の正体だった。
「所長は留守をしていますが」
僕がとっさにそう答えると、男は油断のない動きで室内に入り込み、
デスクの影や来客用のパーティションの向こうに誰もいないことを確認すると、
それまで小刻みだった息をようやくひとつにまとめて、「そうか、留守か」と言った。落胆した様子だった。
「所長の友だちか。それとも小川調査事務所への用か」
加奈子さんが雑誌を置きながらそう訊ねると、
男は「まぶしいな。ブラインドを閉めてくれ」と言って、顔をしかめて見せた。
いったいどこの地底から来た人間なのか分からないが、とりあえず言うとおりにすると、
少し薄暗くなった室内で男は苦しそうに顔を歪めながら、
「小川さんに、田村が、いや田村の弟が会いたがっていると伝えてくれ」と言った。
そうして、「他の誰にもこのことを言うな。分かったな」と付け加えた。
余裕のない口ぶりだった。
「所長はどこに行けばあんたに会えるんだ」と加奈子さんが訊くと、
男は顔を強張らせながら「いきつけのバーでもつくっておけばよかったな」と言ったあと、もごもごと口ごもり、
「やっぱり忘れてくれ。さっき言ったことも、全部だ。俺はここに来なかった」と宣言した。
そうして入ってきたばかりのドアの方へ向かおうとする。
足を引きずっているように見えた。その靴の先が、赤い線を引いている。
血だ。
そう思った瞬間、男はつんのめるようにして転がった。そうなる可能性のある電気コードはまだその先だというのに。
どすん、という音がする。
「おい、大丈夫か」
師匠が駆け寄る。
抱き起こそうとすると、男はうめき声を上げた。師匠はコートの裾をつかんで広げた。
シャツのわき腹のあたりに生地が切れた箇所があり、そこから血がにじみ出ていた。
「救急車」
師匠が端的に僕に指示を飛ばす。
すぐにデスクの上の電話に手を伸ばそうとしたが、「待て」という鋭い声に止められた。
「待ってくれ」
男はコートで傷口を隠しながら言う。
「救急車はだめだ」
「だめな救急車じゃないのを寄越すよう言ってやるよ」
「頼む」
血の気が失せて震えている唇で、男はそう懇願した。
師匠は返事の代わりに、「所長の友だちなのか、客なのか」とさっきと同じことを訊ねた。
「迷惑をかけてばかりだ。どっちでもない」
男は立ち上がろうとした。
「今、外へ出ると一階まで転がり落ちるぞ」
師匠はそう言って僕に目配せをし、男をおしとどめる役をバトンタッチするや、デスクの受話器を取り上げた。
1・1・9
ではなかった。
もっと長い。市内局番から始まっている。
相手が電話に出た途端、師匠はいきなり声色を変えて喋り始めた。
「わたし。ごめん。ヘタうった。腹のあたり、ナイフで刺された。抜けてる。うん。はやく来て。お願い。
救急車はだめ。絶対。友だちが間違って刺したから、事件にしたくない。ボストンの上の事務所」
受話器を置いた瞬間、さっきまでの苦しそうな声とは打って変わってあっけらかんとした声で言う。
「去年、市内の救急車の平均到着時間は七分半だったってよ。さあどのぐらいで来るでしょうか」
男はその師匠の様子を見ながら、ほっとしたように力を抜いた。その瞬間にまた痛みに襲われたのか、顔をしかめる。
僕は来客用のソファに男の身体を横たえ、師匠の指示でそのまま湯を沸かしにかかる。
師匠の方は雑巾を片手にドアの外に出て、床を拭いている。どうやら男の血を拭き取っているらしい。
そのまま下まで降りて、戻ってきた時、同時に階段を駆け上って来る足音が聞えてきた。
「ちょっと、大丈夫なの」
大きな救急箱を抱えた女性が事務所の中に飛び込んできた。年齢は五十歳くらい。肩と言わず、全身で息をしている。
その横で師匠が、パン、と顔の前で手のひらを打ち、「ごめん」と謝った。
事務所の時計の針を見ると、電話を切ってから十分あまりが経っていた。
「ほんとごめん、って」
「話しかけないで。手元が狂うから」
女性は謝る、というより半ば邪魔している師匠をあしらいながら、テキパキとした動きで男の傷口を処置していった。
後で聞いたところによると、野村さん、という名前の看護婦らしい。
以前ある病院に入院していた師匠の看護をして以来の腐れ縁で、今でも交流が続いているそうだ。
いつも無茶ばかりする、自分の娘のような年の師匠を心配してあれこれと世話をやいてくれるのを、
当の師匠の方は狡猾に利用しているようだった。
夜勤明けのところを叩き起こされたことに目をつぶるとしても、今回の出来事はさすがに迷惑の度を越えていたのか、
真っ青な顔をして、それでもするべきことはしてくれた。
男も無言でされるがままになっている。
応急処置を終え、肩をいからせながら野村さんは立ち上がった。
なにか説明をしようとする師匠の口をふさぐようにして捲くし立てる。
「なにも聞きたくない。どうせろくでもないことに決まってるから!
傷は深くない。血管をそれてて出血も多くない。この程度で貧血になるなんて、普段から栄養が足りてない証拠!
あと寝不足ならちゃんと寝なさい。以上!」
救急箱を乱暴に持ち上げて、野村さんはあっという間もなくドアの方へ向かった。
そしてくるりと振り返ると、
「その傷は縫合がいるから、なるべく早く正規の手順で医者に掛かりなさい。
あと、私はここに来なかった!いいわね」
と言ってから、出て行った。
野村看護婦が去って行った事務所のドアを見つめながら、師匠は苦笑して言った。
「やたらと人がここに来なかったことになるな」
そうして腹に包帯を巻かれた男を見る。
男の顔はうっすらと無精ひげが生え、目元にはクマがあった。
腹の傷がなくても倒れそうなほど疲労しているように見えた。
それでも顔を上げ、僕らの方を見ながら口を開いた。
「小川さんのところの調査員か」
「バイトだよ。こいつはその助手」
「そうか」
ソファに身体を横たえたまま、男は天井を仰いだ。
「金じゃなく、人を使えるやつは、いい探偵だ」
ぼそりとそう言うのを無視して、師匠は男を詰問する。
「あんた所長の情報屋か」
それを聞いて、くっくっく、と男は笑う。
「ルポライターだ。売文屋と言ってもらってもいい」
「ようするに情報屋だろう。所長に用なら、出直したらどうだ。とっとと病院へ行け」
「小川さんには世話になったよ。いや、迷惑のかけどおしだった」
「迷惑だと思ってるなら、もう出てってくれないか」
「あの人は凄い探偵だ。あの人と、兄貴のコンビには誰もかなわかった。本当に。いつだってかっこよかった。
高谷さんのお嬢さんが、あんなことになるまでは……」
男の言葉は途中からうわ言のようになり、だんだんと何を言っているのか分からなくなった。
ギシリ。
僕がデスクの椅子に腰掛けた瞬間、男の目が開いた。
「もう一人は?」
そう言いながら身を起こす。一瞬、痛そうなそぶり。
「もう一人の男は?」
繰り返して訊かれ、師匠は服部さんのいなくなったデスクに目をやる。
「面倒ごとの匂いを嗅ぎつけて、さっさと帰ったよ」
デスクの上には、完成した報告書の束があった。
「タレ込む気か」
男は唸るような声を出してソファから立ち上がった。
「おい。落ち着けよ。そんなわけないから」と言う師匠の声にも耳を貸さずに、男は喚く。
「看護婦はいい。だが、あの男はだめだ」
「救急車の次くらいにか」
師匠の軽口に舌打ちをして、男は壁にかけておいたコートに手を伸ばす。
「興信所の人間は信用できん」
「こちら、良く分かってらっしゃる」
おほほ、と口元に手をやって笑う師匠を睨みつけると、男は手早くコートを身につけ、ハンチング帽を目深にかぶった。
「おっと、本当に礼も言わずに帰る気か」
師匠が行く手に立ちふさがる。
男はドン、と肩で師匠にぶつかりながら言った。
「ありがとよ、バイトのお嬢さん」
そうしてその脇をすり抜けながら、ふらつく足元のままドアの向こうへ消えて行った。
そんなことがあった以外は、じつに平和に時間は過ぎた。
僕と師匠はさっきの出来事をぽつぽつと話題にしながら、お茶などを飲んでいた。
やがて時計の針が正午を過ぎるころ、小川所長が帰ってきた。
「あれ、なにかあった?」
ネクタイを首から外しながら、ひくひくと鼻を動かしている。
そう言われて僕も真似をすると、消毒に使ったアルコールの匂いが部屋に残っていることが分かった。
「血の匂いがするよ」
それは気づかなかった。知っていたはずの僕でさえ。
師匠がさっきの出来事をかいつまんで説明する。所長は難しい顔をして聞いていた。
「田村か」
聞き終わったあと、ぼそりと言った。深い溜め息までついている。
「情報屋なのか」
師匠がそう訊くと、所長はあいまいに頷いた。
「七つ上の兄がいてな。その兄は優秀な情報屋だった。僕も色々と助けてもらったよ。だけど四年前に死んだんだ」
デスクの上に腰掛けながら、灰皿を引き寄せて煙草に火をつける。
「自動車事故だったな。確か。早すぎる。惜しい人を亡くした」
煙がわっかになって飛んでいく。
「優秀な兄に憧れるばかりだった弟は、自分の中でその死を乗り越えられず、一番安直な道を選んだ。
ようするに跡を継ごうと決意した。
努力は認めるよ。僕でもしり込みするようなトコロへ揚々と乗り込んでいく勇気も。だけどそれだけだった。
センスがないと言えばそれまでだが……
首根っこ引っつかんででも、別の道を進ませる甲斐性が僕にあれば、
今ごろはもっとまっとうな人間になっていただろうけど」
子どものことをさも知ったように語る保護者のような口ぶりだった。
なんだか掬われない気がして、僕は言ってやりたくなった。
『あの人は、ただ優秀な兄貴に憧れたんじゃなく、あなたと組んで輝いていた兄貴に憧れたんだ』と。
黙ったままじっと見ていると、小川所長は灰を落として僕らの方に顔を向けた。
「田村がどんな危ないヤマに首を突っ込んだのか知らないけど、君たちはもう関わるな」
言われなくても。
「薄暗いな」
所長がそう言って初めて、僕は窓のブラインドを下ろしたままだったのに気づいた。
立ち上がろうとした時、電話が鳴った。
「はい、小川調査事務所」
所長が近くの受話器を取った。朝から電話番をしていて、今日初めての電話を僕は取れなかったことになる。
師匠もそう言いたげに笑っている。
「あ、これはどうも。え?そうですよ。今帰ったところです。怖いなあ。見てたんですか」
口調は軽いが、所長の言葉が緊張を帯びている。
それに気づいて僕は、虫の知らせのようなものを感じてギクリとした。
「田村?知りませんねえ。ここしばらくは見てないですよ。あいつなにかやったんですか」
所長はそう言いながら、電話機を持ち上げてスルスルとケーブルを引きずりながら窓際に向かった。
「え?ですから見ませんって。本当です。匿うって、そんな、松浦さん」
所長はブラインドを上げて、窓をそっとすかせた。
気持ちのよい風が、アルコールや血の匂いの充満した室内に入り込んでくる。竿竹売りの声が聞える。
松浦。
僕はその名前に聞き覚えがあった。ヤクザの名前だ。
小川調査事務所は『まっとうな』興信所だが、こういう業界にはどうしても暴力団の影がちらついている。
単純に金主筋、というわけでなくても、多かれ少なかれそうした反社会的組織の影響はあるのだろう。
アンダーグランドな調査であればあるほど。
師匠の顔も強張っている。
師匠は異常なほどのヤクザ嫌いだ。本人に面と向かってもそう断言するほど嫌いなので、僕は気が気ではなかった。
「すみませんね。お役に立てなくて。いえいえ。もし見かけたら、一報しますよ。それじゃ」
所長は電話を切るや否や、僕らに向かって「早く逃げろ」と言った。
「え?」と、うろたえる僕を師匠は小突いて、「行くぞ」と言う。
「電話口から竿竹屋の声がした。近くから掛けてる。くそ、田村の野郎やっかいごとを」
僕と師匠が連れ立って事務所のドアを出て、階段を駆け下りていると、同じくらいの勢いで駆け上って来る一団があった。
「はいはい。ストップ」
見るからに堅気の人間ではございません、と主張するような服装をした数人の男たちだった。
「あがって、あがって」
長めの髪の毛を茶色に染め、ど派手な紫のジャケットを着た先頭の男が、身振りを交えてそう言う。
チンピラ風だが、後方の連中はもっと本格的な暴力団スタイルをしていた。
思わずその場で硬直していると、
「あがれって、言ってるでしょ」と茶髪の男が、ニッコリとえびすのように目を細めて僕の腹に拳を置いた。
そっと、触れるか触れないか、という軽い拳だったが、僕は未知の暴力への恐怖に背筋が凍った。
「わかったかい。わかったら、もう一回わかれ」
どぶん。
腹に重いものが落ちてきた。一瞬で息が詰まる。
「さあさあ。後ろがつかえてるんだから。早くあがってあがって」
殴られた。殴られた。
僕の頭の中は混乱の嵐だった。
忌々しそうにしながらもしぶしぶ元きた階段を上り始める師匠を見て、何も考えずに付き従う。
戻ってきた僕らと、その後ろからゾロゾロと現れた男たちを見て、小川さんは顔を覆った。
「ごめん」
謝る師匠に、「いや、ごめんはこっちだ」と小川さんは力なく返した。
ドアから次々と入ってくる男たちの最後に、一際地味な格好をした男が入ってきた。
黒いダブルのスーツだったが、他の男たちほど胸元を広げておらず、下のシャツも白の無地で、
ネックレスの類も身につけていなかった。
さすがにネクタイこそしていなかったが、髪型もパンチなどではなく、控えめな長さのオールバックだった。
そして黒縁の眼鏡をしている。
この小川調査事務所がらみで、何度か見たことがある男だ。確か『石田組』という名前の暴力団の男。
その中でも、普通に街で遊んでいるだけではそうそうお目にかかれない、真に暗い場所に生息している人間だった。
「松浦さん、これはなんだ」
所長がその男に鋭い口調で言う。
「電話で言ったとおりだ。田村を探している」
「こちらも電話で言ったとおりだ。ここしばらく見ていない」
言い返した所長に、茶髪の男が喚き声を上げる。
アニキになんて口ききやがる。
そう言ったのだろうが、あまりに頭の悪そうなドスの利かせ方をして、ほとんど何を言っているのか分からない。
「小川さん。あなたが知らなくてもこちらは一向に構わない。
この事務所は、田村と何の関係もない。それが分かればいいんです」
松浦というヤクザは顎をしゃくって見せた。確か石田組の若頭補佐という役職だったはずだ。
男たちが室内に散る。台所やトイレ、ロッカー。
人間一人隠せる場所など限られている。あっという間に男たちは手持ち無沙汰になった。
「いないのは間違いないようですね。では彼について知っていることをお訊きしましょうか」
そうして、松浦は僕と師匠とに交互に目をやった。
「松浦さん、それはだめだ」
所長は今日一番の低い声を出した。そしてじっと相手の目を見つめる。
「だからてめえはだれにくちきいてんだっつってんだ」
茶髪が頭を上下に振りながら一歩前に出た。そのそばにいたゴリラのような顔の背の高い黒服がそれを押しとどめる。
その時、僕にもう少し余裕があったなら、よく聞く『良い警官と悪い警官』の話のように、
乱暴な若者と、それをなだめて穏やかに話を訊き出すベテランの、
それぞれの役割をこの場でも演じていると感じたかも知れない。
それにしても、茶髪の若者は一番チャラい格好をしていて、本職というよりは街のチンピラのようで、
どちらかというと、あのゴリラ顔の男の方に『悪い警官』役をやられると、僕の心臓はもっと縮み上がったに違いない。
「話をややこしくするな」
ゴリラ顔の男は茶髪の頭を小突いた。小突かれた方は恨めしそうにしている。
「そう。話はシンプルに行きましょう。田村は来たのか、来なかったのか」
松浦はそう言って、時計を見た。ゴツイ時計だ。
どうせオメガだかロレックスだとか言う名前で、
無駄にダイアモンドを散りばめて、精密時計並に値を吊り上げた不精密時計なのだろう。
「あまり長居もしてらないのでね。あと三分半くらいでお願いします」
それは、僕らが口を割るまでの時間なのか、それとも割らせるまでの時間なのか気になった。
あの田村という男にはなんの義理立てもないので、ゲロするのに全くやぶさかではなかったのだが、
一度「知らない」と答えている小川さんの立場がどうなるのか、それだけが気になって僕はなにも言い出せないでいた。
師匠と目配せしようにも、その不自然な動きだけであっという間にとっつかまって拷問を受けそうな気がしてならない。
「来ましたよ。来ました」
小川さんは白旗、という風に両手を上げた。
茶髪の男がまたなにか喚いて、ゴリラ男に肩を押さえつけられている。
「話はシンプルにお願いします」
松浦は静かにそう言った。
「私が留守の時に、私を訪ねてきたようです。一時間半くらい前です」
そうして小川さんは淡々と事実の説明をした。
バイトの調査員をやっかいごとに巻き込ませたくない一心で『知らない』とウソをついたことまで。
ほぼすべて事実だった。だが事実のすべてではなかった。
野村看護師の出番は、師匠の見よう見まねの応急処置にとって代わられた。
一応は手伝っていたので、なまじウソでもない。これ以上無関係の人間を関わらせたくないからだろう。
「なかなか、分かりやすい話でした」
松浦はカツカツと、顔が写りそうなほど磨かれた革靴の音を響かせながら、窓際にある小川所長のデスクに腰を乗せた。
デスクの上には、本来のそのデスクの電話機とは別のものが、ケーブルをずるずると延ばして乗っかっている。
松浦は事務所の主に断りも入れず、その受話器を持ち上げると電話を掛け始めた。
「私だ。情報は?」
そう言った後、じっと聞き役に回っていたかと思うと、「頼むよ」と一言いって受話器を置いた。
最後の言葉は、字面からは想像もつかないほど寒気のするような響きだった。頼まれた相手もきっとそう思っただろう。
他のヤクザたちは乱暴にさっきの所長の言葉の裏づけを取っている。
つまり、血をぬぐったガーゼや消毒液の染み込んだコットンをゴミ箱から見つけては、無造作にそれを床に投げていくのだ。
他人の家の床が汚れることなんて屁とも思っていないらしい。
「彼の怪我はどうでしたか」
松浦が師匠に声を掛けた。
田村を介抱したことになっている師匠は、
今まで一言も発しなかったのが自らの戒めであったかのように、その禁を破って静かに言った。
「致命傷ではなかった。自分で立って歩いて帰れるくらいの怪我だ。だけど疲労困憊って感じで、声もかすれ気味だった」
答え自体は簡潔なものだった。しかしその口調は、デリケートな相手に対してするべきものではなかった。
案の定、茶髪が口の利き方がどうだとか言って吼えている。
そのころになると、ようやく僕もこのひと騒動が無事に終わりそうな気配を感じて、
浮き足立っていた足も地に着き、周囲を観察する余裕が出てきていた。
部屋にいるヤクザは全部で五人。
若頭補佐の松浦という男は三十台後半くらいで、後は一人だけかなり年嵩の眠そうな顔の男がいたが、他はもっと若い。
中でも茶髪の男は二十代前半だろう。
そして全員の胸元を見てみたが、よく耳にするような金バッジはつけていなかった。
だからといってこいつらがヤクザではないのかも知れない、などという希望的観測はさらさら湧いてこなかったのであるが。
「あの怪我は、刃物の傷だ。どこでどうやってついたのやら」
師匠がさらに挑発するように言う。
松浦はずい、と上半身を乗り出した。
「ちょっとした勘違いがありましてね。
田村はうちの若いのと一瞬もみ合いの様な形になったらしくて、その時お互いが怪我をしたようなんです。
まあよくある間違いですよ。お互い様というやつです。
ビジネスの話が途中だったので、
そんなことは水に流してさあもう一度話し合いを、というところで彼の行方が分からなくなりましてね。
困ってるんです」
松浦がそう言った。
「お互いが怪我?」
師匠は眉をひそめて、宙に視線を漂わせる。
僕もその意図を悟って、師匠の視線の先に意識を集中した。
田村はあれだけの大怪我をしていて、なお追われている。
そのわざわざ口にしたもみ合いが本当なら、相手はただの怪我ではないのではないか。そう思ったのだ。
だが、僕がどれほど目を凝らしても、彼らの周囲に真新しい死の影は見当たらなかった。
「そのもみ合った若いのっては、死んではいないみたいだな」
師匠はぼそりと言う。
松浦は怪訝な顔をしたが、すぐになにか気づいた表情を浮かべて笑った。
「聞いたことがありましたよ。『オバケ』専門の探偵さん。あなたでしたか。いやいやこんなにお若いとは」
他のヤクザたちは狐につままれたような顔をしている。
「私は、こんな商売をしていると自然と敵が多くなりましてね。そのせいか、努力が全く報われないことが多いんですよ。
同業者には占い師なんかに血道を上げて、
その努力が努力の通り報われるようなご助言をいただこう、という連中もいます。
しかし、私はどうもそういうのが嫌いでねえ」
松浦が目を細めた。
今までは、ただ自分の役割を演じていただけの男が、一瞬で脱皮し、蛇のような冷たい本性を現したかのようだった。
「うそは、いけません。うそは。
うそは簡単に人を幸せにしますが、見破られたときの不幸は、周囲のすべてを巻き込みます。
霊能力者と名乗る連中も同じですよ。
テレビであれだけ騒がれても、うそが暴露され、さらし者になる。
一番不幸なのは、そいつらを信じて身代を投げ打った無辜の民です。
なのにまた、前任者のさらし首が乾かないうちに、次の霊能者がブラウン管を賑わせる」
ひたひた、という滑らかな口調で松浦は続ける。
「あなたがそんなうそを言う人間でなければいいが。心からそう願ってやみません」
松浦は腰掛けていたデスクから降り、師匠の前に歩み寄った。
そして手を伸ばせば触れるか触れないかという距離で立ち止まると、口を開いた。
「私は、占い師や霊能者を名乗る者に出会うと、必ずこう訊くようにしています。
『私には誰か守護霊がついて見守ってくれてはいませんか』と。
彼らは一瞬困ったような顔をした後、こう言います。
『お母様が守護霊としてついていてくださいますよ』と。
あるいはこうです。
『お父様が見守ってくれていますよ』と」
松浦は師匠の顔を正面からじっと見つめている。
師匠もその視線をそらさず、真っ向から見つめ返している。
「私の年齢ならば、父や母はまだ生きている可能性は十分ある。生きていたとしたらその時点でペテンだと露呈します。
なのに、安全に祖父や祖母の話を持ち出さなかったのは、彼らもまたある種のプロフェッショナルだということです。
ホットリーディング、と言うんですか。
顧客の情報を事前に可能な限り仕入れておいて、さも今霊視しているように演じる、あれです。
この私どもの業界は、人の口には戸を立てられない、というのを地で行く典型的な噂社会でしてね。
ちょっと知ってる風の三下にそれなりのものを掴ませれば、簡単に聴けるんですよ。
私の父が本家、立光会の先代だってことや、母はその何人目かの愛人で、
私は中学校を卒業するまでは私生児として育てられたってことをね。
そしてどちらももう死んでいて、この世にいないことも」
表情を全く変えずに、松浦は師匠に問い掛けた。
「公然の秘密というやつです。それを踏まえた上で、あなたにも問いたい。
『私には誰か守護霊がついて見守ってくれてはいませんか』と」
さっきまでのヤバさと全く次元の違うヤバさだ。
ひしひしとそれを感じる。
同じような感触を得ているであろう他のヤクザどもも、緊張した面持ちで動けないでいる。
松浦の満足するような答えが返ってこなかった場合、いったいどうなるのか。
想像するなと言われても、想像しようとしてしまう自分がいる。
「さあ。どうです」
これが最後の問いだ、と言わんばかりに松浦は口を引き結んだ。
能面のような顔だ。ふと僕はそう思った。
師匠がゆっくりと口を開く。
「いないね。誰も。あんたの後ろにあるのは虚無だ」
めんどくさそうに言って、鼻で笑った。
松浦は一瞬、呆けたような顔をして、それからゆるやかにまた脱皮をし、元の蛇のような表情に戻った。
師匠がぼそりと言う。
「霊の話をしてると、寄って来るって言うだろう。来てるよ、ほら」
師匠が窓の方を見た瞬間に、松浦もまたそちらを見た。
そして窓から目を逸らすと、二人で見詰め合った。驚いたような顔だった。
しようもない手口で脅かされた松浦の方は、顔を真っ赤にしてもおかしくない場面なのに。
不思議な沈黙が流れて、僕らは息が詰まった。
誰も動かない状況を破ったのは、ふいに鳴った電話だった。
取ろうとした小川所長を目で制し、松浦はそのまま年嵩の男に目配せする。男はすっと動いて受話器に手を伸ばした。
「はい。小川調査事務所」
抑揚のない声でそう告げると、電話の向こうは関係者からだったらしく、松浦の方に向き直って受話器を下げ、
「見つけたそうです」と簡潔に報告した。
「分かった。お前ら先に行け」
松浦がそう言うと、年嵩の男、ゴリラ男、そしてもう一人長い顔をしたパンチパーマの男が頭を下げて部屋から出て行った。
後には、小川調査事務所の三人と、松浦、そして茶髪の男が残された。
表でベンツだかBMWだかの車のエンジンが重低音を響かせたかと思うと、その音があっという間に遠くなっていった。
残った茶髪の男は松浦付きの運転手なのだろう。
さっきから何が楽しいのかニヤニヤと無意味に笑っている。本当に頭の悪そうな顔だ。
僕はさっき殴られた腹が急に痛み出し、二対三という数字上の優位をたてに軽く睨みつけてやった。
茶髪はその視線に気づいて、からかうように顔をしかめてみせている。そしてまたヘラヘラと笑う。
「で、捕まった田村はこのあとどうなるんだ」
師匠がなんでもないことのようにそう問い掛けると、
これまで師匠に任せようとばかり沈黙を貫いていた小川所長が、「おい」とたしなめる。
「そちらには関係ありませんよ」
つまらなそうにそう言って、近くにあったティッシュで鼻をかんだ。
しかし目的は達成したとはずだというのに、すぐに去ろうとしないのは、
なにかまだ言い足りないことでもあるのに違いなかった。
師匠は距離感を図ろうともせずに、さらに懐へ飛び込む。
「あいつはなんで追われてたんだ」
そう問うと、松浦はティッシュをゴミ箱に投げ入れた。狙いは外れなかった。
「……そうですね。株式会社角南建設。知ってますかね」
急に僕でも知っている中大手ゼネコンの名前が出てきて少し驚いた。
この市内に本社を構えていて、地元ではトップ企業の一つだ。よくテレビCMを目にする。
「そこの今の会長は創業者一族の重鎮でしてね、角南盛高(すなみもりたか)。御年七十一歳。
そしてその兄が、一族の現当主にして県議会議員の角南総一郎。御年七十三歳。当選十回の、泣く子も黙る古狸です」
松浦はまたティッシュを鼻にやった。
茶髪がソファを引きずってきて、後ろに据えると、何も言わず当然のように腰をかける。
「まあ、この角南一族というのは、戦前から海運業などで財を成した言わば財閥で、
さまざまな分野にその根を張り巡らせています。
例えば」
松浦は有名な地元製薬会社の名前を上げた。
「あそこの株主の中でも、主要なところは角南家に抑えられています。名前は直接出てきませんがね」
今度のティッシュは的を外した。あ~あ、という感想が漏れる。
茶髪は、拾うべきか拾わざるべきか悩んでいる顔をしながら、一応という表情で拾いに行って、ゴミ箱に入れた。
「そして地元でも、もはやまともに立ち向かってくるもののいない、権威と権力、そして金を手にしている彼ら一族ですが、
次の衆院議員選に、その秘蔵っ子を出してくるらしいんです」
喫茶店でゴシップ話でもするように松浦は続ける。
「二区でね。一騎打ちですよ」
秘蔵っ子とやらの一騎打ちの相手とは、次期首相候補と噂される代議士のことだ。
地元出身ではない僕でも名前は知っていた。
「今まで有形無形の様々な形で応援していたのが、手のひらを返して対立候補を立ててくるんです。ただごとじゃない。
その秘蔵っ子は、そうですね。角南盛高か、総一郎のどちらかの息子とだけ言っておきましょう。
まあ、こんな情報はそこらの週刊誌にも出てるような話です。話半分に聞いておいて下さい。
まあ事実上一騎打ちと言っても、今の中選挙区制では次点でも落ちることはありません。
しかし、万が一、新人の後背に甘んじるようなことになれば、確実に顔は潰れます。次期総裁の座も危ない。
と、こういう図式です。
問題は勝算があるのかどうか、ということですよ。あるいはただのブラフかも知れない。
ブラフだとしても、こんな情報が市井に出回っている時点で、一定以上の効果はあるでしょう。
出ちゃおうかな、出ないでくれ。そういう交渉が水面下で続いているのかも知れない。
その見返りの『算盤のケタ』の問題を詰めている最中なのかも知れない。
さて、私ども凡俗の人間には分かりかねる世界ですが……」
松浦はそこで言葉を切って、それまで向いていた師匠ではなく、所長の顔を見て言った。
「出ます。十中八九ね」
あっさりとそう断言するのだ。
「そして出るからには勝ちに来ます。間違いなく。一族を上げて。そこで怖いのは、スキャンダルです。
今まで中央政界で散々もまれて来た某代議士センセイと違って、
ほぼ初めて一般の方の目に触れる箱入りのお坊ちゃんだ。
もっとも、ハーバード大学卒業から始まるキャリアは大変なものですがね。
ともあれそんな大事なお坊ちゃんには、まだスキャンダルの洗礼の余地が十分にあるんですよ。
立候補の告示日の翌日には落選確実の一報が入るような、恐ろしい一撃がね」
黙って聴いていた小川さんは、やっと口を開いた。
「いったいなんの話なのか分かりませんが。
そう言えば角南県議は今でも角南建設の顧問でしょう。株も相当数保有しているんじゃないですか。
常々思っていたんですが、あれは、地方自治法上の……何条でしたっけ。
とにかく兼業禁止規定に引っ掛からないんですかね」
まるで話を逸らすような内容だったが、松浦はそれについても解説を加えた。
「角南建設は確かに、県発注の公共工事を多数落札し、施工しています。
一見すると、議員の自治体からの請負を禁じた、九十二条に引っ掛かりそうなものですが。
実は本人が請け負うと即アウトなんですが、法人の場合、
その法人にとってその議員がどういう役職にあるか、実体としての影響力を持っているか、に掛かってきます。
そして支配的な地位を持っていると認定されても、請負の額の問題が発生します。
判例にもよりますが、まあだいたい、
法人の年間受注額全体における県発注工事の占める割合が、五十パーセントを越えなければセーフですね。
それに、兼業禁止にかかる発議権は、議員に専属しています。
お仲間たちに無駄な声を上げさせない力を持っていれば、そんな問題自体が発生しないんですよ。
検察だって手が出せません」
ところが、と松浦は話をまた元に戻す。
「そんな兼業禁止規定だなんていう抜け穴だらけの有名無実な禁則事項よりも、もっと危険で即効性のある『毒』が、
ある男からもたらされたんですよ」
「それが田村なのか」
松浦はそれには答えなかった。喋りすぎていないかどうか慎重に吟味しているような顔をしていた。
そもそも僕にはなぜ松浦が、そんな裏の情報をここで口にするのかさえ、さっぱり分からなかったのだが。
「老人って、なんのことだ」
師匠が何気なく漏らした一言に、松浦の顔つきが変わった。
茶髪の男が師匠の背後に回ろうとして、その間に小川所長が身体を割り込ませる。
「静かに」
その動きを制して、松浦はゆっくりと問い掛けた。
「どこで、それを」
「この事務所で倒れてから傷口を洗うまで、田村は気を失ってたんだ。
アルコールをぶっかけた途端、喚いて目を覚ましたけどな。
その気絶している間に、呟いたんだよ。うわごとみたいに。なあ、老人って誰のことだよ」
「田村は老人が、どうした、と言っていたのです」
「知らん。老人、っていう言葉しか聞き取れなかった」
松浦は射るような目つきで師匠の顔を眺めた。そうして「老人は」と、口を開く。カパリと。
「総一郎、盛高の父です。先代当主ということになりますか。もう十年以上前に亡くなっています。
老人……そう。彼は、ただ『老人』と呼ばれています。畏敬をもって。
その息子たちが、そう呼ばれて久しい年齢になっているというのに。
角南大悟(だいご)。本名をそう言いました」
松浦の言葉に、一瞬小川さんが驚いたような顔をした。どうやら知っているらしい。
そちらに一瞥を加えてから続ける。
「時代を超え、ただ、その名のみをもって今なお人を畏怖させる。日本戦後史の暗部にうごめくフィクサーの一人です」
「その老人とやらにまつわるスキャンダルだってのか」
師匠が鋭く切り込んだ。
松浦はソファから立ち上がった。
「さて、どうでしょう。
ただ、地元に根を張る我々としては、仮にそんなものがあったとしたら、
東から来る仁義の欠片もないヤカラどもと違い、郷土の英雄を守りたいという義憤にかられるのではないでしょうか」
もう話は終わりだ。そう言いたげに、松浦は茶髪の方に顎をしゃくってみせる。
最後に、事務所を荒らされ放題にされた格好の小川さんが短く言った。
「そちらと、角南一族とは縁が切れていたと思ってましたがね。例の産業団地がらみで何人逮捕されたか考えれば」
松浦は目を細め、すっと半歩だけ近寄って顔を突き出しながら言った。
「組織が大きいとね、色々あるんですよ」
まるでそれまでの話よりもよほど重大な秘め事を明かすかのような口調で。
そうして、蛇のような男は、青白い顔の印象を強く残しながらドアの方へ向かった。
「あ、そうそう。その『毒』ですがね。どうもおかしなところがあるようなんです。まだよく分からないのですが。
この次は探偵を頼る客として来ることがあるかも知れない。
その際はご指名しますよ、お嬢さん。
次に会う日までに、年長の人間と話す時の作法を身に着けておくと、もっといい」
こちらを振り向かずにそう言うと、松浦はドアの向こうへ消えた。
後を追う茶髪がその去り際、ふらりと近寄って来ると、いきなり僕の頭を軽く抱えて、ぼそぼそと言った。
「おい。兄ちゃん、俺の顔を見て笑ったろ。人をよう、見かけで判断しちゃダメだって、教わらなかったんか」
そして、さっき階段のところで食らわしたのと同じパンチをボディに入れてきた。
こっちからずっと睨んでいた腹いせに違いなかった。
重い痛みが芯に響き、身体が九の字に折れそうになる。
茶髪は、その前歯が一本欠けた間抜けな顔をすっと遠ざけ、じゃあなと言って、ドアの向こうへ去って行った。
また外車特有のエンジンの音を響かせ、その音が遠ざかっていくのを聞いた後、僕ら三人は一人残らずへたり込んだ。
「寿命が縮むよ」
小川さんが師匠を恨めしそうに見ている。
「ヤクザ、怖えぇな。やっぱ」
師匠は今さらのようにそう一人ごちる。
僕はというと、殴られた腹を手で押さえながら、もういい加減にこのバイトを辞めようと心に誓ったのだった。
「あ。お嬢さんて、今日二回も言われた」
師匠が妙に嬉しそうにそう言った。
[完]
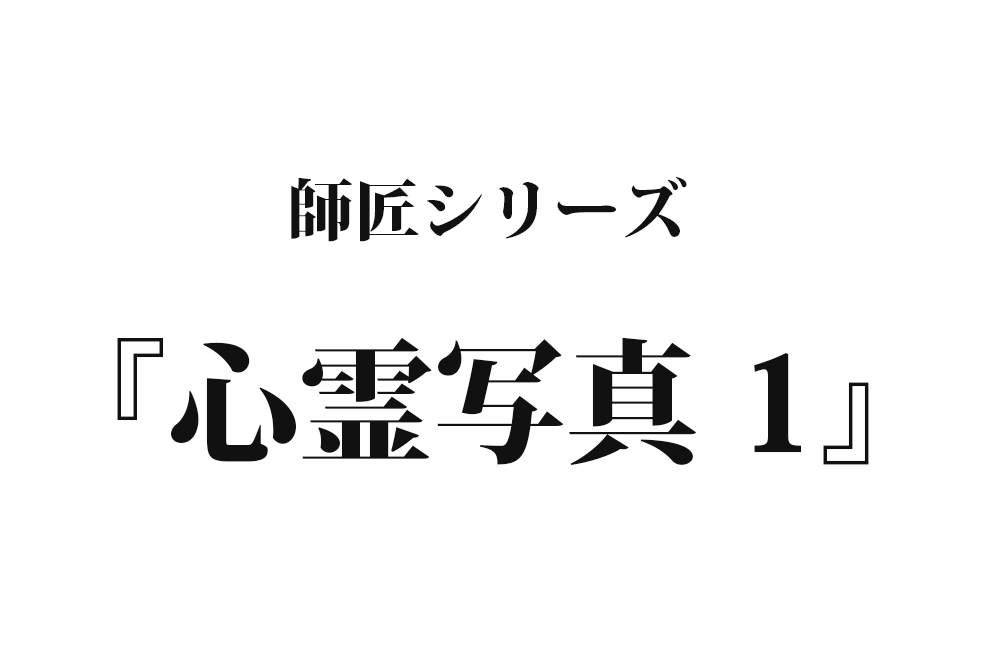
コメント