藍物語シリーズ【3】
『入学式と卒業式』
上
入学式の日は快晴だった。時折強い南風が吹き抜ける。春一番。
姫は新入生では無く転入生だが、新入生と一緒に入学許可をもらうために
入学式には参加するという。言われてみれば成る程、道理だ。
雨なら体育館2階のアリーナに集合だったが、晴れなので新入生は中庭に集まっている。
姫は新入生の列から少し離れた場所に並び、係の先生の話を聞いていた。
姫を入れて列に並んでいるのは5人、あれが転入生の列なのだろう。
中庭のスピーカーから保護者の入場を促すアナウンスが流れたので、
俺たちは入学式の会場になっている体育館の入り口に向かって歩き出した。
Sさんは白いブラウスに黒いスーツ、タイトスカート。胸元に真珠のコサージュを飾っている。
ぴいんと伸びた背筋に結い上げた黒髪が映える。改めて見ると、本当に美しい人だ。
端正な横顔に見惚れていると、Sさんが肘で俺の背中を小突く。
「ね、こうして歩いてると私たち夫婦に見えるかしら?」
「夫婦も何も、26才の女性に16才の娘がいる訳な、痛!」
思い切り二の腕をつねられた。
「『親子に見える?』なんて聞いてませんけど。」 まずい、怒らせた。
「あ、多分、夫婦に見えますよ。いや、絶対夫婦に見えます。
新入生の、え~と、姉夫婦が式に出席するんだなって感じに。絶対見えます。」
「へえ~、やっぱり勘が良いのね。これ見て。」 取り敢えず危機は脱したようだ。
Sさんは入学式の後に提出する書類の入った大きな封筒の中から1枚の紙を取り出した。
『家庭環境調査票』という書類だ。姫の名前、住所、生年月日、お屋敷への簡単な地図。
貼り付けられた写真の姫は、少し緊張した顔でとても可愛い。そして家族構成の欄。
姫(16才)・本人、姫の姉(23才)・自営業、姉の夫(21才)・自営業。
「...何で3つも鯖読んでるんですか。おまけに僕は1つ水増しですよ。それに夫婦って。
住民票も提出するのに、住民票と違ってたらまずいんじゃ、あっ!」
Sさんはニコニコしながらもう一枚の紙をつまんでヒラヒラさせている。住民票抄本だ。
急いで受け取ると、思った通り家庭環境調査票と同じ内容が記入されている。
「こういうの、有印公文書偽造って言うんですよね?」
「人聞きの悪いこと言わないで。ちゃんと役所で発行してもらった『本物』よ。」
「だって事実と全然違ってるじゃないですか。一体何処から手を回したんです。」
まさか役所の内部にまで影響力があるとは想像もしていなかった。
「だから人聞きの悪い言い方はやめてよ。家族が『後見人』と『後見人の内縁の夫』じゃ
担任の先生がどんな家庭だか色々詮索してくるに決まってるでしょ。夫婦にしたって
26才と20才より23才と21才の方が自然だし。これから2年間、Lの高校関係では
あなたは『Sさんの名字』+『R』、私の夫よ。今21才、忘れないでね。」
書類を封筒に戻しながら、Sさんは何だかとても嬉しそうだった。
体育館で入学式が始まった。教頭先生の『開式の言葉』に続き
厳粛な雰囲気の中で、起立した新入生と転入生が校長先生から『入学許可』を受ける。
生徒達が揃って一礼すると会場は大きな拍手に包まれ、俺とSさんも一生懸命拍手した。
地域では名門の1つに数えられている高校だからなのか、
新入生にも保護者にも、感極まって目頭を押さえる姿が彼方此方に見える。
転校生の列の2番目に並ぶ姫の後ろ姿も、何となく嬉しそうに見えた。
『入学許可』のあとは校長先生の『式辞』、PTA会長の『祝辞』と続く。
これは正直退屈で、俺は欠伸をかみ殺すのに難儀していた。
Sさんは何か興味深そうに会場をあちこち見回している。
姫が転入した高校は女子校なので男子の姿は当然見えない。
女子校の式典に参加したのは初めてだが、むさ苦しくなくて大変結構だ。
突然、Sさんが俺の耳に小声で囁いた。
「こんなに沢山の女子高生がセーラー服着てたらさぞかし壮観でしょうね。」
「何もこんな所で。誰かに聞かれたらどうするんです。」
周りを気にしながら言い返したところで、
眼を輝かせたSさんの視線が、ある一点に注がれているのに気付いた。
そろそろとSさんの視線を辿る、その先に異様なものを見た。
着席して話を聞いている新入生達の向こう側、職員席から少し離れた壁際に
セーラー服を着た女生徒が1人でポツンと立っているのだ。
新入生の列を見つめている。所在なげに、そして羨ましそうに。
式の参列者なら家族か職員に注意されるだろう。それどころか会場の誰も
あの女生徒に気付いている様子が無い。俺にははっきりと見えているのに。
おそらくあれは生身の人間ではない。全身の毛が逆立つのが判る。
「あの、あれ。」声が掠れる。 「今は駄目よ。『鍵』を掛けておいて。」
Sさんの指示を守り、その少女に注意を向けないようにして入学式が終わるのを待つ。
入学式が終わり新入生と転校生が退場すると、短いPTA入会式が行われ
それが終わると全ての日程が終了。俺たちは他の保護者に混じって体育館を出た。
それとなくさっきの壁際を見たが、既にセーラー服の少女の姿は無かった。
新入生はこの後各クラスの教室に集合し、クラス開きなどがあるのだが、
転入生は皆同じ教室で簡単な注意事項を聞いてから帰宅することになっている。
式に出席していた生徒会役員以外、基本的に2・3年生は登校していないからだ。
俺たちは持参した書類を事務室の窓口に提出してから校舎に向かった。
一階の教室が見渡せる中庭の一角にSさんと並んで立ち、姫が出て来るのを待つ。
俺たちの正面に校舎の窓の列が見える。連なる窓越しに教室の様子が垣間見えた。
一階の窓の列を右側に辿り、列がとぎれた所に正面玄関がある。
おそらく姫はそこから出てくるはずだ。
姫を待つ間、さっきのセーラー服の女生徒についてSさんに尋ねようと思ったところで
一瞬強い風が吹いた。俺は不意をつかれてよろめき、校舎の窓から視線を外した。
「凄い風でしたね。」 Sさんの顔を見ると、Sさんは眼を輝かせて校舎を見つめている。
「ほら、あれ。まだ『鍵』は掛けたままで。」
恐る恐る視線を移すと、一階の窓の列、その中程にセーラー服の少女の後ろ姿が見えた。
ポニーテール。窓にもたれて教室の中を見つめている。どこか羨ましそうに。
その時、列の左端に近い窓に女生徒2人の姿が見えた。転入生たちだ。
2人並んで右側に向かって歩いて行く。セーラー服の女生徒との距離が詰まる。近い。
『ぶつかる!』と思った瞬間、2人はセーラー服の女生徒と重なって、すり抜けた。
窓側を歩いていた女生徒は一瞬立ち止まって振り返ったが
すぐにもう1人の女生徒の後を追った。
また1人、列の左端に近い窓に女生徒の姿が見えた。姫だ。
どきん、と心臓が高鳴る。姫にはきっとセーラー服の少女が見えるだろう。
「あの、Lさんが。」 「大丈夫、このままで。」Sさんが呟く。
姫は歩く、窓の列の向こうを左から右へ。セーラー服の女生徒との距離が詰まる。
と、姫はセーラー服の女生徒のすぐ手前で立ち止まった。距離は1mも無い。
姫は窓に向かって立ち、鞄を窓枠に置く。鞄の中に視線を落とし、右手で鞄の中を探る。
そのすぐ隣にセーラー服の少女、異様な光景だ。ぞわぞわと寒気がする
姫の後ろから歩いてきた女生徒が姫をよけるように歩いていく。続いてもう1人。
彼女たちは姫をよける事で、結果的にセーラー服の少女をよけたことになる。
姫は鞄の中の何かを探す様子で立ったままだ。何を探しているのだろうか。
セーラー服の少女がゆっくりと姫の方を向いた。色白の横顔、また心臓が高鳴る。
姫は鞄の中に視線を落としたままだ。口を小さく動かしているように見える。
何を言っているのか、まさか『あの声』で? そして。
突然、セーラー服の少女の姿が消えた。まるで、最初からそこには誰もいなかったかのように。
姫は鞄を持ち、向きを変えて再び歩き出した。まるで、探し物を見つけて安心したかのように。
「Lさんは『あの声』を?」 あの術の名前は教えて貰っていたが
出先で術の名前を口に出すのは禁じられていた。当然の禁忌だ。
「まさか。こんなところで『あれ』を使ったらとんでもないパニックが起こる。
Lが集団生活を通して学ばなければならないのは、強い術を使わずに怪異に対処する方法。
それから、大多数の『力を持たない人々』とのつきあい方。
今回はどちらも及第点、合格ね。」 Sさんは満足そうに微笑んだ。
姫が玄関から出て来た。俺たちの姿を見つけて嬉しそうに走り寄って来る。
Sさんが優しく話しかけた。「最初のお友達が出来たみたいね。」
『友達』って、あれが?どういう意味だ。
「はい、今日は無理でしたけど、その内分かってくれると思います。」
「え、消えたんじゃないんですか?」
「はい、『拡散』しただけです。入学式という場の力や、参加した人々の想いに反応して
あの人の心が『凝集』したんですね。学校ではあまり強引なことは出来ませんから、
少し時間がかかるかもしれません。それに、結構新しい方みたいでしたし。」
「新しい?」 セーラー服の女生徒が亡くなった時期が、ということか。
「この学校の制服が替わったのが5年前だから、9年前から6年前の間ね。」
「今度聞いてみます。」姫とSさんが駐車場に向けて歩き出したので俺も後を追う。
5年前に制服が替わったなら、9年前ってのは一体?10年前でも良いんじゃないのか?
聞きたいことは沢山有ったが、既に姫とSさんの話題は昼食の事に移っていた。
「緊張したせいかお腹がすきました。もう、ペコペコです。」
「そうね、もうすぐ1時だし。どこかで食べて帰ろっか。」 「賛成です。」
ぴた、と、Sさんが立ち止まった。姫もSさんの横で立ち止まる。
俺はようやく2人に追いついた。
Sさんの正面に身長190cm近くありそうな長身で細身の老人が立っていた。
黒いスーツに白いネクタイ。柔和な眼が眼鏡越しにSさんを見下ろしている。
老人はSさんに向かって深く深く最敬礼をした後、口を開いた。
「これはこれは、随分とお久し振りにお目にかかります。
あなたさまが御出とは露知らず、大変失礼を致しました。
一言事前にお知らせ下されば。」
「いいえ、お構いなく。」 心なしかSさんの声は冷ややかだ。
「それで本日はどのようなご用件でこちらへ?」
「妹がこの高校に転入したので入学式に参りました。」
「ほう。妹君が。」 老人はしげしげと姫を見つめた。 姫が軽く会釈をする。
「これはこれは美しい姫君。私どもは皆、心から妹君を歓迎いたします。」
「2年間、妹を宜しくお願いします。」
「勿体ないお言葉。万事私どもにお任せ下さいませ。」
老人は眼を細めて微笑み、もう一度深々と頭を下げた。
つい、と、Sさんは老人の横をすり抜けて歩き出した。姫が続く。俺も後を追う。
すれ違いざま、老人の呟く声が聞こえた。「何故、あのお方が...」
「あの、どなただったんですか?」歩きながら姫がSさんに尋ねた。
「この高校を運営する学校法人の理事長、この高校の創立者で初代の校長だった。」
「何故、この高校にSさんの知り合いがいるんですか?」俺も尋ねた。
Sさんは、遠い時の彼方の懐かしいものを見るような眼をしていた。
「ここが、私の母校だからよ。」
中
姫が高校に通い始めて2週間程が過ぎた頃、確か4月下旬の金曜日だったと思う。
その日は昼過ぎからSさんが仕事でマセラティを使って外出していたので、
俺はロータスで姫を迎えに出た。ロータスはマセラティよりかなり車高が低く、
乗り心地も硬い。姫は『周りの車のタイヤがすごく近くにみえて息苦しい』と言い、
通学でロータスに乗るのはあまり好きでは無いのだが、今日は仕方無い。
姫の高校は裏門も比較的大きな通りに面している。
最寄りの駅に接続するバスの停留所が表門側にあり、部活動が盛んな事もあって、
4時の終業のチャイム直後に裏門を出てくる生徒はまばらだ。
広い路肩に車を停め、裏門から出てくる姫を待つのが俺の日課だった。
いつも同じように生徒の下校を待つ車が他にも何台か停まっている。
終業のチャイムが鳴り、暫くして姫が裏門から出てきた。珍しく2人連れだ。
裏門を出たところで、姫はもう1人の女生徒に向かって小さく左手を挙げた。
姫は裏門を出ると右に向かい、歩道を車まで歩いてくる。
もう1人の女生徒は裏門のすぐ近くに立ち止まって姫を見送っていた。
「友達かな?」と思ったところで全身に鳥肌が立った。何故気付かなかった?
あれは、セーラー服だ。
何故、あの女生徒が姫と。俺はセーラー服の女生徒から眼が離せなくなった。
「Rさん、Rさん。」 姫の声で我に返る。ほとんど反射的にバックミラーを確認して
車を降り、助手席側のドアを開けて姫の鞄を受け取る。
「ありがとうございます。」 姫は軽く会釈をして車に乗り込んだ。
あまりに車高が低いのでロータスに乗る時は姫の左手を支えて補助をする。
姫の体が助手席に収まり、助手席側のドアを閉めた所で思い出した。
恐る恐る裏門を見る。セーラー服の女生徒の姿は既に無かった。
運転席に座り車を発進させた後、いきなり左腕をつねられた。
「痛!どうして。」 姫はいたずらっぽい笑顔を浮かべていた。
「いくら美人だからって、私以外の女の子を見つめてちゃ駄目ですよ。」
「でも、あの子は...あ、ごめんなさい。」
「冗談です。でも、これからは迎えに来たら、いつも『鍵』を掛けておいて下さい。
あの人、この頃良く姿を見せるんです。Rさんにもあの人が見えている訳だから
意識が共振するかもしれません。注意しておいた方が良いです。」
「共振するとどうなるんですか?」
姫は少し考えてから言った。
「知らない方が良いと思いますけど、どうしても知りたいですか?」
「いえ、結構です。質問は取り消します。」
姫はにっこり笑って頷いた。 危ない危ない、どうも軽率な質問をする癖が直らない。
「ええと、じゃ別の質問なんですが、もしまずかったらさっきのように教えて下さいね。」
「はい。私に答えられる質問なら。」
「さっきの女の子はこの頃良く姿を現すって言ってましたけど、
これまでも、その、2人並んで一緒に歩いたりしたことがあるんですか?」
姫は指を折りながら少し考えている様子だ。
「あの人とお話したのは、入学式から数えて今日で6回目、だと思います。
そのうち、今週だけで4回。やっぱり増えてますね。」
新学期になって2週間と言っても実際に登校したのは10日程度。
10日で6回となれば2日に1回を越えるペースだ。
「そんなにしょっちゅう現れたら他の生徒にも気付かれませんか?」
虚空を見つめて1人で何事か呟いている所を見られたら、どう考えてもまずいだろう。
「いつもはお昼休みに現れるんです。私、雨の日以外は毎日図書館の裏手のベンチで
1人でお弁当を食べるので、大抵はそのベンチで隣に。
それにお話しするって言っても、声を出す訳じゃないから他の人には気付かれません。
誰かが見てる時にはさっきみたいな挨拶もしないし。」
「あの女生徒が現れるのが分かってて、何故1人でお弁当を?」
「私、待ってるんです、あの人を。何とか学校から出してあげたいと思って。」
「他に人がいない時なら『あの声』が使えませんか?」
「あの人は悪意を持った異界のモノとは違います。出来れば自分で納得して貰って
それから然るべき場所へ行ってもらいたいんです。色々お話ししている内に
今の自分の状態は分かって貰えたみたいなんですけど。」
「それは、自分が既に死んでいるってこと、ですか?」
「はい、ただあの人にはあのセーラー服と小物以外の記憶が全くないんです。
自分の名前も、いつ死んだのかも、何故死んだのかも覚えていない。
だから原因が分からなくて納得出来ない。それに『帰れない』って言うんです。
『だから学校にいるしかない』って。」
「何故、何処に『帰れない』のかも記憶がない?」 「はい、全然。」
「それなのに現れる回数が増えているのは
あの子自身もこのままではいけないと思っているということなんですか?」
「恐らく、そうだと思います。だから私、Sさんに頼んでみようと思って。」
「何を頼むんですか?」
「ええと、学校法人の、あの理事長さんなら何か手がかりを知ってるんじゃないかと。
Sさんは『あの人とは知り合い』だって言ってましたよね?」
「確かに、あの人なら何か知ってるかも知れませんね。」
俺はあの長身の老人の、柔和な眼を思い出していた。
「L、1人でよく頑張って偉かったわね。でも今度からはもう少し早目に相談して頂戴。」
次の日の朝、朝食後に姫の話を聞いたSさんは優しく姫の髪を撫でてから言った。
「記憶を無くしている場合のほとんどは、とても辛い思いをした人よ。
記憶も、自分自身も全部、この世から消してしまいたくなるくらい、辛く悲しい思いをね。」
「じゃ、やっぱりあの人は自殺を?」 姫の表情は硬く緊張している。
「多分間違いない。もし不用意にそんな人の記憶を戻したら、
無意識に封印していた激しい感情が爆発して、悪しき縁に囚われてしまう。
そうなるといわゆる悪霊や地縛霊といわれる存在になって他の人にも影響が及ぶ。
多分あの子の魂は無意識にそれを恐れて記憶を封印したんだと思う。」
「分かりました。これからは気を付けます。」 姫が力なく眼を伏せた。
「もう少し勉強したら1人でも対応できるようになるし、
Lがあの子を何とかしてあげたいと思ったのはとても良いことよ。
私はLのそういう優しい所、すごく好き。」
「...ありがとうございます。」
姫はうっすらと涙を浮かべていたが、もう俯いてはいなかった。
「でも、今はまだこの件に関してはL1人では荷が重い。私のやり方をよく見ててね。」
「はい。」 姫の眼に力が戻っていた。
Sさんはその後短い電話をかけた。恐らくあの老人への電話だ。
「今日の午後、2時に校長先生に会わせてくれるって。R君も一緒に来てくれる?」
「僕が行って役に立つなら喜んで。」
「うん、良い返事。Lもその方が心強いでしょ?」 「はい。」
学校に着くとあの長身の老人が駐車場で俺たちを待っていた。
老人は俺たちに深々と最敬礼したあと、無言で俺たちを先導し、校長室に案内した。
俺たちが一礼してソファに腰掛けると、老人と校長先生も一礼して向かいに座った。
「この御方々は特別だから、御質問には包み隠さず御答えするように。」 「はい。」
校長先生は緊張した様子で落ち着かない。まあ、それがあたりまえの状況ではある。
「お話しする前に、この部屋に結界を張ります。」
「全てあなたさまの御心のままに。」 長身の老人が深く頭を下げる。
Sさんは立ち上がり、部屋の四方の壁に手を触れたあと戻ってきて再びソファに座った。
この部屋で彼女のことについて話せば、おそらく彼女がこの部屋に引きつけられる。
そして彼女の自殺の真相が明かされればこの部屋で彼女の感情が爆発する。
それを避けるための処置だと言うことは容易に想像できた。
「じゃ、L、あなたの聞きたいことを質問して。」 姫が頷く。
「この高校で、卒業できずに亡くなった生徒の中に『○本』という名字の生徒がいたら、
何故その生徒が亡くなったのか知りたいんです。9年前から6年前の間に。」
校長先生の顔が真っ赤になり、次いで真っ青になった。
「その期間で、卒業前に亡くなった生徒は1人だけです。先代の校長の時に。失礼します。」
校長先生は席を立ち、黒い表紙のノートを持って戻ってきた。震える手でページをめくる。
「ありました、○本明美。7年前、3年生に在籍していました。」
○本という名字の女生徒が本当に在籍していた、しかも7年前に亡くなっている。
姫とSさんの言った通りだ。姫とSさんを信じてはいたが、全身に鳥肌が立って寒気がする。
「何故、亡くなったんでしょう?」 「自殺とありますがそれ以上は。」
「そこからは私がお答えいたします。」 長身の老人が話を引き継いだ。
「その生徒は校舎の屋上から身を投げて自殺しました。
本校では開学以来そのようなことは初めてでしたから、当時は大騒ぎになりました。
その後、家族からの要請で死亡による除籍ではなく
自殺する以前の日付で依願退学の手続きが取られ、受理されたと記憶しております。」
そこからは姫に代わってSさんが質問を続けた。
「進路やイジメに悩んでの自殺だとしたら、そんな処理の仕方にはなりませんね。」
「はい。家族から『学校に申し訳ないので是非』と要望があったと聞いております。」
「何故『申し訳ない』と?」 辺りの空気がぴいんと張りつめた。
「それは...その生徒が妊娠していたからです。それで家族は学校の名を汚したくない、と。」
しばらくの間、校長室は沈黙に包まれた。
沈黙を破ったのはSさんだ。
「その場所に案内してください。彼女が飛び降りた場所に。」
老人は鎖で幾重にも厳重に封鎖された扉の鍵を開けた。屋上へ通じる扉。
「ここからは私だけで行く。R君、Lをお願いね。」 「はい。」
突然老人が正座をした。額を床に付けてピクリとも動かない。
Sさんが右手で上着のポケットから人型を取り出すのが見えた。扉を抜けて歩いていく。
迷うことなく左側奥の手すりに向かい、手すりの前で膝をついて床に左手を触れた。
静かに時間が過ぎていく。俺も姫も息を詰めてSさんを見詰める。
突然空気が裂けて、耳がきーんとなるような悲鳴が聞こえたような気がした。
「許せない!」姫が屋上に向かって走り出そうとする。俺は必死で姫を抱き止めた。
「離して!離してっ、殺してやる!!」 今まで見たことのない姫の顔だ。
「駄目です。離しません。あの子の意識に共振し過ぎてます。」
「お願い...離して。」姫の体からぐったりと力が抜ける。
姫の体を支えながらSさんの方を見る。Sさんは右手で人型を掲げていた。
やがてSさんは人型をポケットにしまい、ゆっくりと戻ってきた。
数分後、俺たちは再び校長室のソファに座っていた。
やはり沈黙を破ったのはSさんだ。
「校長先生にお願いがあります。」 「何でしょうか?」
「件の生徒、○本明美さんの御家族の住所を教えて下さい。
それから、彼女は何ら学校の名を汚すことはしていません。彼女は被害者です。
この件についての調査が終わり、御家族から名誉回復の訴えがあった場合、
依願退学の処置を取り消し、御家族の参列の下、彼女の卒業式を挙行して下さい。」
「それは...」 校長先生が老人の顔を見る。 老人が代わって答えた
「分かりました。謹んでお約束いたします。お任せ下さい。」
「あの子のことは、もう忘れました。」
○本広明、あの女生徒の父親は冷たい表情で言った。
○本氏の住むマンションの部屋は綺麗に片付いていたが、生活感がほとんど無く
どこか空虚な雰囲気が漂っていた。娘を亡くした事が原因なのは明らかだ。
「妻を亡くしてからは男手一つであの子を育てて、必死で良い学校に通わせて、
それなのにあんな、あんなふしだらな。時々帰りが遅くなって、それを娘は放課後の講座だと
嘘を言って私を騙していたんです。本当はこそこそ男と会って、妊娠まで...
もう二度と思い出すまいと思っていました。お願いですから放っておいてください。」
Sさんは溜息をついた後、穏やかに、しかし厳しく彼に告げた。
「あなたには、私達の話を聞く義務があります。」
「何故ですか?」 「彼女は被害者で、あなたがそれを知らないからです。」
「被害者?」 「そうです。」
「それで、あなた方はどうやってそれを知ったのですか?あの娘はもう死んでいるのに。」
父親は疑わしそうな、皮肉な笑みを浮かべて問いかける。まあ無理もない。
姫が静かに口を開いた。
「私、彼女と同じ高校に転入しました。そして、入学式の日に彼女に会ってお話ししたんです。」
「降霊術とか何とかいう奴ですか。馬鹿馬鹿しい。何が目当てなんです?
見ての通り、うちには金なんてありませんよ。」
「彼女は記憶を無くしています。自分の名前すら憶えていません。
私、あの人がいつも持っているハンカチの刺繍で『○本』という名字を知りました。
それを手がかりに、彼女が私と同じ高校に在学していた事を突き止めたんです。」
父親の顔色が変わった。
「ハンカチに名字の刺繍が?」 「はい、花柄のハンカチです。その端に。」
父親は席を立ち、別室から2枚のハンカチを持って戻ってきた。ハンカチをテーブルに置く。
水色とピンク、綺麗にたたまれた花柄のハンカチの端に『○本』という名字の刺繍。
父親の声は少し震えている。
「娘が使っていたハンカチです。娘が小学校に入学する時、妻が名字を刺繍しました。
娘はこれをとても大事にしていました。それで、あなたが見たのはどちらですか?」
「どちらでもありません。花柄と刺繍は同じですが、彼女が持っているのは白いハンカチです。」
「そんな馬鹿な。」 父親は両手で顔を覆い、背もたれにぐったりと体を預けた。
「白いハンカチは...白いハンカチは娘が自殺した時に持っていたんです。
遺体と一緒に焼きました、私がこの手で...血で真っ赤に。」
父親は突然体を起こして姫の手を両手で掴んだ。
「教えて下さい。娘が被害者ってどういう事ですか?何故娘は今でもあの高校に?」
同時に腰を浮かせた俺を見て、父親は手を離した。 「すみません。つい。」
「彼女を心から愛していたあなたにとっては、どちらにしても辛い話だと思います。」
湧き上がってくる激情を押さえ込むような、姫の静かな口調が胸に突き刺さる。
「彼女はある日下校途中に拉致され、乱暴されました。そしてそれをもとに脅迫され
その後も継続的に肉体関係を強要されていたんです。あなたを心から敬愛していた彼女は
あなたに相談する事も出来ないまま、やがて妊娠しました。妊娠している事を知った日の夜
彼女は家に帰ることが出来ず、衝動的に屋上から飛び降りたんです。」
「娘はふしだらではなかった、娘は悪くなかったんですね?」
「彼女は何ひとつ悪くありません。ただ。」 姫が言いにくそうに続けた。
「彼女は『帰れないから学校にいる』と言っていました。」
「何故帰れないんですか?」
「あなたが彼女をふしだらな娘だと思い、彼女の全てを忘れようとしていたからです。」
「...明美...」 父親は俯き、大粒の涙を流した。
暫くして涙を拭った父親の眼に、憎悪の火が灯っていた。
「娘を乱暴した男は今何処にいるんですか?」
「いけません。あなたが憎しみに囚われれば、彼女は不幸の輪廻に取り込まれてしまいます。
非道な行いをする者には必ず相応の報いがありますから、今はその男を憎むより
あなたは彼女の事だけを考えてあげるべきです。」
Sさんが穏やかに父親を諭した。
「あなたが以前のように彼女を受け入れることができれば、彼女も以前の彼女に戻れます。
死者は自ら望む姿でいられますから、乱暴もされず、自殺もしていない元通りの彼女にね。
だからどうか、あなたは彼女を受け入れてあげて下さい。彼女は本当に素敵な女性です。」
「本当に、元通りのあの子に戻れるんですか?」
「戻れます。だからあなたからも彼女に伝えて下さい。いつも彼女を思い出して、
彼女がどんなに可愛くて素敵な女性だったか、あなたがどんなに彼女を愛しているかを。」
「判りました。」
「今、彼女の退学を取り消して正式な卒業生として認定するように高校側と交渉しています。
もし許可が下りたら、式に参列して彼女の代わりに卒業証書を受け取って頂けますね?」
「願ってもないことです。どうか宜しくお願いします。」
下
リビングで夕食後のコーヒーを飲んだ後、テーブルを綺麗に拭き清めてから
Sさんは白い布で作られた小さな袋をテーブルの上に置いた。
光沢のある白い糸で美しい模様が刺繍されていて、袋の口は赤い糸で縛られている。
「彼女の魂は、今この中に封印してあるの。一時的にね。
記憶を取り戻して、当然だけど彼女の怒りと哀しみの感情が爆発したから、
彼女の魂が悪しき縁に取り込まれないようにするにはこれしかなかった。」
袋の中には、あの日Sさんが校舎の屋上で掲げていた人型が納められているのだろう。
「犯人達の末路と父親の愛情を彼女に伝え、憎しみと哀しみの感情を鎮めてから
彼女の魂の封印を解く。それで彼女にも道が開く、中有への道が。」
父親ですら彼女が被害者である事を知らなかったのだから警察が動いた筈は無い。
「犯人達って、複数犯なんですね。ソイツ等はもう既に報いを受けていて
その末路がどうだったのかを彼女に伝えるって事ですか?」
「報いを受けさせるのはこれからよ。犯人達にふさわしい報いをね。」
「私にやらせて下さい。」 姫が何時になく強い調子で言った。
「L、気持ちは分かるけど未成年の女の子に手を汚させることは出来ないわ。
特に、あなたがR君と結ばれる前は絶対にそんなことさせられない。
その代わり、報いの前にはこの袋をあなたに託す。彼女の意識と同調して
犯人達の末路を彼女に伝えて欲しいの。やって貰える?」
「はい、分かりました。」 姫は大きく頷いた。
「でも、どうやってソイツ等を探し出すんです。何か手がかりがあるんですか?」
「校舎の屋上、あの場所には、飛び降りる前の彼女の記憶が焼き付いてた。
衝動的に自殺を決めた瞬間、燃え上がった心の熱が記憶をそこに焼き付けたのね。
その記憶を解放したから、彼女に何があったのか全部分かったわ。
犯人たちの名前も電話番号も。犯人の1人は今も当時と同じ電話番号を使ってる。
油断してる証拠。事件の真相を知ってる者がいる筈は無いって、甘く見てるのね。
式を飛ばして住所も突き止めたし、後は報いを受けさせるだけ。
そうね、彼女の卒業式は5月3日だから、その前夜祭にふさわしいイベントじゃない?」
Sさんの頬に微かな笑みが浮かんでいた。
鬼畜どもに苛烈な報いを与え、破滅をもたらす絶対零度の微笑。
5月2日の午後、俺はSさんに指示された番号に電話を掛けた。
犯人2人のうち当時と同じ電話番号を使っている男、ソイツの名は『ノブ』。
発信音の後に続く呼び出し音。数秒の後、電話が繋がった。
「もしもし、あんたノブだな?」
「知らない番号だな。お前誰だ?俺がノブなら何だってんだ。用でもあるのか?」
「お前、馬鹿だろ。用があるから電話してるんだよ。」軽く挑発する。
「うるせえ、俺は忙しいんだ。」 電話を耳元から離す気配。
俺は大きな声で彼女の名前を告げた。
「○本明美。」
ノブが電話を耳元に戻した。声を潜めて聞き返してくる。
「お前、何でその女の名前を知ってるんだ?用ってのはその女の事か?」
「俺は何でも知ってるよ。お前が兄貴分の『ヒデ』とつるんで彼女に何をしてたか、
彼女は何故自殺したのか、他にも色々と、な。」
ひゅっ、と息を呑む音が聞こえた。数秒間の沈黙。
「それでお前、警察に話すつもりなのか?」
「警察に話すかどうかはお前達の態度次第さ。お前と『ヒデ』に会いたいって
そう言ってる人達がいるんだ。今夜、8時きっかりに俺はその人達と『ヒデ』の部屋に行く。
お前も『ヒデ』の部屋に行って2人で待ってろ。それからこちらは俺をいれて3人だ。
大事なお客様が座れるようにしとけよ。立ち話は御免だからな。」
「おい、ヒデさんの部屋に簡単に行ける訳無いだろ。しかも今日すぐになんて無理だ。
それにヒデさんの部屋って、お前ヒデさんの部屋知ってるのかよ?」
「無理かどうかはお前等の都合だろ。そんなの俺には関係ないんだよ。
それに彼女を弄んでた時、お前等はいつでも2人一緒だった。
彼女についての話なのに無理だと言うほど『ヒデ』が馬鹿だとは思えんがな。
まあ、どっちにしろ今夜8時、『ヒデ』の部屋にお前等2人がいなければ警察に行くだけさ。
それにな、俺は『ヒデ』の部屋もお前の部屋も知ってる。お前の部屋は狭いから
『ヒデ』の部屋にしたんだ。部屋だけじゃない。お前等の本名も知ってる。
見張りもいるぞ、今夜の内に高飛びしようとしたら即警察に通報、一巻の終わりだ。」
「おい」 「じゃ、今夜な。8時きっかりだ。」 俺は電話を切った。
「こんな感じで良かったですか?」 「うん、上出来。R君、中々の役者ね。」
Sさんは、あの冷たい微笑を浮かべた。
午後7時50分、俺は『ヒデ』の住むマンションの近くにある有料駐車場に車を停めた。
並んで歩きながら、Sさんがハンドバッグからあの白い袋を取り出して姫に手渡す。
「L、お願いね。くれぐれも気をつけて。」 「はい、任せて下さい。」
8時きっかりに俺は『ヒデ』の部屋の呼び鈴を押した。
すぐにドアが開き、男が顔を出す。髪を赤く染めた薄汚い男だ。 「本当に来やがった。」
「電話でもそう言ったろ。俺は全部知ってるって。ヒデも中にいるんだろうな?」
「いるよ...あと2人ってのはその女たちか?」
Sさんと姫を見て、ノブは目を細めた。下卑た薄笑い。救いようの無い下衆だ。
思い切りぶん殴ってやりたい衝動を俺は必死で抑えた。
「おい。大事なお客様をいつまで立たせてるんだ。さっさと案内しろよ。」
「入れ、こっちだ。」 ノブに続いて俺たちはヒデの部屋に入った。
部屋中に染み付いた煙草の臭いが鼻につく。パチンコ屋の前を通った時のような
変に甘ったるい臭い。吐き気がする。姫も顔をしかめていた。
趣味の悪いリビングルームのソファに男が座っている。
「ヒデさん、コイツ等です。」 「本当に来たのか。」
俺の後について部屋に入ったSさんと姫を見て、ヒデの表情が変わった。コイツも同類だ。
彼女は自殺したのに、こんな腐れ外道どもがのうのうと...怒りに眼が眩む。
俺たちはヒデの向かいのソファに並んで座った。ノブがヒデの右隣に座る。
「初めに言っておくが、妙な気を起こすなよ。前にも言ったがこの部屋には見張りをつけてる。
1時間経っても俺たちが出てこなかったら、仲間が警察に通報する。」もちろんハッタリだ。
「お前、ヒデさんがどんな人か分かってそんな口聞いてるのか?え?
ヒデさんは組の若頭なんだぞ。その気になればお前等なんか。」
ノブが必死で凄んで見せるが、脅えは隠せない。微かに声が震えている。
「大体お前等何者なんだよ。俺とヒデさんがあの女に」
ヒデが右手の甲でノブの顔を殴った。空手でいう裏拳だ。
ノブが両手で顔を覆って俯く。押さえた手から赤黒い血がポタポタと滴った。
「余計な事喋るな、馬鹿が。録音されてたらどうするんだ。黙ってろ。」
成る程、コイツは多少頭が切れる。間違いなくあの娘の他にも被害者はいるだろうが
コイツの卑劣な脅しや小細工で被害者達は泣き寝入りさせられる訳だ。
「それで、お前等の目的は何だ?金か?お前等の持ってる証拠によっては
それなりの値で買い取っても良い。話が折り合えばな。口止め料って奴だ。」
「証拠なんて必要無い。私たちは彼女から直接聞いたんだから。」
初めてSさんが口を開いた。静かな口調だが、去年出会って以来
これ程の怒りを秘めた表情のSさんは初めて見る。
「何度か彼女をこの部屋にも連れてきて...お前達、本当に最低ね。人でなし。」
「何とでも言えよ、死んだ人間から話を聞いたなんて、誰が信じるんだ?
それに証拠が無ければ警察も手は出せんぞ。」ヒデの表情に安堵が混じる。
「警察に任せるつもりなら、初めからそうしてる。」
「じゃ、目的は何だ。証拠が無いならこっちも考えがあるぞ。」
「報いを受けてもらう。お前達にふさわしい報いをね。」
「綺麗なお姉さんのお仕置きかい?楽しみだね。」
ヒデの顔にあからさまな好色の表情が浮かんだ。つくづく哀れな男だ。
それがますますSさんと姫を怒らせるとも知らず、卑しい想像に浸っている。
隣に座ったSさんから、ぞっとするような冷気を感じた。 始まる。
「本当は地獄に送ってやりたいけど、生身の人間は地獄には行けない。
だからって直ぐに殺すと私たちの気が済まない。死ぬまでたっぷり苦しんでもらわないとね。」
ヒデが警戒の表情で俺を見る。 「殺す?お前ら、銃でも持ってるのか?」
「銃なんて要らない。これで充分。」 Sさんが上着のポケットに右手を入れた。
腰を浮かし掛けたヒデは、Sさんが取り出したものを見て呆れたように再び腰を下ろした。
「何だよ。そんな紙っ切れでどうしようってんだ。」
「こうするの。」
Sさんは小声で何事か呟いた後、掌に乗せた紙片に強く息を吹きかけた。
紙片は2枚、何の形かはわからない。ヒデとノブに向かってひらひらと飛んで行く。
突然、ヒデとノブは目を見開いたまま動かなくなった。完全に硬直している。
2枚の紙片がそれぞれ2人の眉間に貼り付いた。
そして、まるで男達の顔に吸い込まれるように、消えた。跡形もなく。
「終わらない悪夢、地獄の夢。コイツ等の心の中の『悪意』、
今まで他人に向けられていた憎悪と侮蔑のエネルギーを悪夢に換え、
コイツ等の魂をその夢の中に封じた。自分たちの悪意が作り出した地獄の中で、
他人に与えてきた肉体の痛み、心の痛み、そして恐怖を味わってもらう。
魂がこの夢の中に囚われている限り、コイツ等にとって『最も怖ろしい事』、『最も辛い事』が
いつまでも続く。本当の地獄へ行く前に、この世の地獄を体験してもらうの。
水も食べ物も口にできず、衰弱した肉体が滅びるまで、ずっとね。そろそろかしら。」
硬直した男達の表情が恐怖に歪んでいた。
「よせ、俺は裏切ってない。俺は悪くないんだ。」
ヒデは何度も呟いたあと、弱々しい悲鳴を上げた。 「痛ぇ、痛ぇよ。止めてくれ。」
ノブは血にまみれた顔に涙をボロボロ流しながら呟いている。
「やめろ。来るな。」 突然笑い出す、また泣き出す。 「来るな、来るなよ。」
「あの紙はこの術の、代だったんですね。」
「今夜も冴えてるわね。じゃ、代を使った術を解く前に必要な事は?」
「この場合は、代を破るか、燃やすこと、ですか?」
「ご名答。でも、この術の代はコイツ等自身の体内に封じた。
だからこの術は、コイツ等が死んでその肉体が焼かれるまで絶対に解けない。絶対にね。」
「このままの状態で食事も水も口にできないのでは、3日保てば良い方ですね。」
「運良くこのままだとしたら、2日も保たない。」 運良くこのまま?どういう事だ。
「でも、もっと派手に悲鳴を上げるようになったら、マンションの住人が通報するでしょうね。
そしたら肉体は病院で拘束され、点滴や人工栄養のチューブを繋がれて生かされたまま、
魂はずっと地獄の夢の中をさまよう事になる。コイツ等にふさわしい報いだわ。
最悪の恐怖は体に相当な負担を掛けるから、それでも保って一ヶ月かそこらだと思うけど。
それ位なら15年とか刑務所に入れるより税金の無駄遣いも少なくて済むし。」
そういう事か。確かに通報されるのはむしろコイツ等に取っては運が悪い。最悪だ。
「もし、通報が、されなかったら。」
「もちろん私が通報するわ。警察にも知り合いはいるし。」
もうコイツ等に『幸運』が訪れることはない。これまでの非道に対する、当然の、報い。
「ふふ、ふふふふふ。」 突然、笑い声がした。 姫だ。いつの間にか立ち上がっている。
「良い気味ね。本当にいい気味だわ。」 頬をつたう一筋の涙。
「私、嫌で嫌で堪らなかった。痛くて、辛くて、恥ずかしくて。憎んで、気が狂うほど憎んだ。
この手でこの男達を殺してやりたかった。でも、出来なくて、この男達の思うままに...」
Sさんも立ち上がり、姫の肩をしっかり抱きしめた。
「ごめんね、明美。守ってあげられなくて、助けてあげられなくて、本当にごめんね。」
違う、これはSさんの声じゃない。
「でも見えるでしょ? 今、この男達もあなたと同じく、死ぬより辛い目にあってるの。
だからあなたを酷い目に遭わせたり脅したりする男はもういない、分かる?」
SさんはSさんのではない声で、一言一言言い聞かせるように話す。姫が小さく頷いた。
「それとね、明美がとても辛い思いをしたって聞いて、お父さんがすごく心配してるの。」
「お父さん...」 姫が顔を上げた。懐かしい記憶を思い出そうとするように。
その瞬間、Sさんは小声で何事か呟いた後、姫の頭を抱き寄せた。
姫の体がぐったりと崩れ落ちる。 「R君、お願い!」
俺は姫の体を支えて抱き上げ、ソファに横たえた。
姫の手から白い袋が落ちる。Sさんはそれを拾ってハンドバッグにしまった。
「さて、戦利品を持って帰らないと。」 Sさんはリビングの飾り棚の戸を開けて中を探った。
「やっぱり有った。」 重そうに取り出したのは大型の手提げ金庫だ。メモが貼ってある。
「こんな奴らはやましい方法で手に入れた現金や貴金属を大抵自宅で保管してる。
開け方のメモもあるし、簡単だろうとは思ってたけど、予想通り過ぎてちょっと拍子抜け。」
Sさんがメモを見ながら手早くダイヤルを廻すと、あっけなく金庫の蓋が開いた。
中には沢山の札束、指輪やブレスレットなどの貴金属類、それに大きな封筒が幾つか。
Sさんはハンドバッグの中から折りたたまれた某デパートの紙袋を取り出した。
広げた紙袋に金庫の中身を手際よく放り込んでいく。
「お葬式をやり直す事になるかも知れないし、○本氏にはお金が必要だわ。遅くなったけど
れっきとした慰謝料ね。これで良し。すごい事になってきたから、さっさと引き揚げましょ。」
確かに、男達が失禁したせいで部屋中に耐え難い悪臭が満ちてきていた。
姫を抱いたままマンションの出口に向かう途中で、マンションの住人と鉢合わせになった。
心配そうに声を掛けてくる。「あの、その人大丈夫ですか?」 くっそ、余計なお世話だ。
「ああ、大丈夫です。知人の部屋でパーティーしてたんですけど、妹が間違って
僕のお酒飲んで酔っぱらっちゃって。心配なんで早目に連れて帰る所なんですよ。」
「そうなんですか。気を付けて下さいね。」 「どうも。」 何とかやり過ごした。
「全く、役者なんだから。」 Sさんの微笑に温もりが戻っていた。
「そういえばさっきのSさんの声って。」 「ああ、私、声色(こわいろ)は結構得意なの。」
「声色?物真似って事ですか?」 「そう、彼女の母親の声。」
「彼女は飛び降りる瞬間、母親の事を思い出してた。怪我をして泣いている時、
手当てしながら慰めてくれた母親の優しい顔と温かい声をね。」
この人は...本当に、底の知れない人だ。
翌日、5月3日の午前10時、○本明美さんの卒業式が高校の体育館で挙行された。
生徒席には彼女の父親と姫、来賓席には高校を運営する法人の理事など12人。
もちろん1列目にはあの老人も座っている。
俺とSさんは少し離れた場所で、小さな机に設えた祭壇を守っていた。
祭壇には、あの小さな白い袋と、大きな二枚貝の貝殻が安置されている。
卒業式は司会を兼ねる教頭先生の開式の言葉で始まった。
「本日、○本明美さんの名誉を回復し、彼女の卒業を認定できますことは、
彼女の御家族だけでなく本校にとっても、誠に喜ばしい事であります。
それでは、卒業式の開式を宣言致します。」
続いて校長先生が登壇し、卒業認定が行われる。教頭先生の声に続いて父親が起立した。
「本日この場で、○本明美さんが本校の全課程を修了した事を確認し、卒業を認定します。」
参列者全員が大きな拍手を贈る。俺とSさんも一生懸命拍手した。
「続いて卒業証書授与、卒業生代理の方は壇上にお上がり下さい。」
父親が立ち上がり、舞台に向かって歩き出す。
「もう良いわね。」 Sさんは祭壇に安置された袋の中から人型を取り出し、
大きな貝殻の中に入れた。右手を貝殻の上にかざすと人型が燃え上がる。
『御焚き上げ』だ。 「これで良し。」Sさんは満足そうに呟いた。
舞台に視線を戻すと、父親が校長先生の前に立った所だった。そして。
父親と並んで、女生徒が1人、舞台に立っている。
その後ろ姿はセーラー服ではなく、白いシャツにチェックのスカート、紺のブレザー。
姫と同じ、この高校の現在の制服だ。新しい制服にポニーテールが良く似合っている。
「○本明美、右の者が本校の普通科を卒業した事を認め、証書を授与してこれを証する。
平成△年5月3日、卒業台帳番号第×038×号。おめでとうございます。」
父親は一礼して卒業証書を受け取り、とうとう堪えきれず舞台の床に両膝をついた。
「...明美、済まない。私は、私はお前を...」
会場は静まりかえり、父親のすすり泣く声だけが響く。もらい泣きをする参列者も多かった。
泣き続ける父親の傍らで、あの子が気遣うように父親の肩に手を添えている。
俺自身も涙が溢れるのを我慢できなかった。
「セーラー服じゃなくて残念だったわね。」
「いや、むしろセーラー服じゃなくて良かったですよ。」
「何故?」 Sさんの目も赤く潤んでいた。
「だって、新しい制服は、彼女が旅立つ覚悟を決めた事の証ですよね?」
「...あなたを好きになって、本当に良かった。」
Sさんは俺の涙をハンカチでそっと拭いてくれた。
もう一度舞台に視線を戻した時、既に彼女の姿は無かった。
短い卒業式は無事に終了した。○本氏は既に落ち着いていて、
俺達が生徒席で彼にお祝いの言葉をかけると、彼も俺達に礼を言った。
「本当に何とお礼を言って良いか分かりません。こんな立派な式を開いて頂いて、
その上娘を正式な卒業生として認定して頂けるなんて、今でも信じられません。
本当にありがとうございました。」
「さっき、お父さんが卒業証書を受け取られた時、明美さんも一緒でしたよ。」
にっこり笑う姫の言葉に○本氏は大きく頷いた。
「やはりそうでしたか。何だかそんな気がしていたんです。泣いている途中で何故か
とても暖かい気持ちになりましたから。娘は、娘は笑っていましたか?」
「はい、笑っていました。明美さんはもう旅立ちましたが、
最後までお父さんを心配していました。そして『宜しく伝えて欲しい』と。」
「そうですか。」 ○本氏は静かに涙を拭った。
Sさんが○本氏の前に進み出て一礼した。
「どうしても気になると思いますのでお話ししておきます。」 「はい。」
「私たちの調査で、犯人は既に判明しています。ある団体の構成員でした。
『でした』と言ったのは、犯人が既に死亡している事を確認したからです。
法で裁かれた結果ではありませんが、犯人は自分の非道な行いの報いを受けた訳です。
事件の性質上、お父さんとしても事実を今更表沙汰にする事は避けたいでしょうし、
この件の調査はこれで終了して、敢えて刑事事件とはしない方向で如何でしょうか?」
「本当に犯人は死んだのですね。」 「はい、信頼できる確実な情報です。」
正確には『死んだも同然』で『死ぬより辛い状態』だが、
直接手を下した本人が言うのだから、確かにこれ以上確実な情報は無い。
『犯人達』ではなく『犯人』と言ったのもSさんの心遣いだろう。本当に優しい人だ。
「それなら結構です。死人を恨むより、娘の冥福を祈りたいと思います。」
Sさんの眼が一瞬鋭く光ったが、すぐに穏やかな表情に戻った。
「立派な心掛けです。それでこそ明美さんも安心できると思います。そして。」
Sさんは祭壇の下に置いてあった布袋の中から、分厚い紙包みを取り出した。
「犯人が所属していた、ある団体からこれを預かってきました。
この件を刑事事件にはしないと確認が取れましたからお渡しします。
示談金、または慰謝料にあたるものです。どうぞお受け取り下さい。」
○本氏は暫く考えて首を振った。
「もし、明美が私に相談してくれていたとしても、私はあの娘を慰めるだけで
結局は泣き寝入りするしかなかったと思います。だからそれを私が受け取る道理は
ありません。むしろこの件に関わる調査には大変なご苦労がお有りだった筈です。
しかし私はそれに見合うお礼を用意することができません。
今回のあなた方のご苦労へのお礼として、どうかそれはあなた方がお納め下さい。」
「明美さんの為に役立てた方が良いのではありませんか?」
「いいえ。今更どれだけお金を使っても、明美は喜ばないでしょう。」
○本氏は少しためらってから、意を決したように言った。
「実は私、この式が終わったら娘の所へ行くつもりでした。」
「娘さんを守ってあげられなかった、信じてあげられなかった。
あなたはそう考えて、その責めを負う気だったんですね。」
「はい、でも先程、式の途中で娘の温かい気配を感じて、考え直しました。
少しは蓄えもありますし、娘の事を想いながら、余生を過ごすつもりです。」
Sさんは深く息を吸った後、ゆっくりと眼を閉じた。
「広(ひろ)さん、明美は私に任せて頂戴、もう大丈夫よ。
そして私達のためにも、広さんは頑張って生きて。お願い。」
「裕美...」 ○本氏の目に涙が溢れた。
Sさんが眼を開ける。 「奥様の声、聞こえましたか?」
「はい、確かに。確かに裕美、妻の声でした。私に『生きて』と。」
「生きている者には、亡くなった家族を供養する義務があります。忘れないで下さい。」
「肝に、命じます。」
泣き止むのに少し時間がかかったが、○本氏は晴れ晴れとした顔で高校を後にした。
結局、彼は『示談金』を受け取らなかった。
「あれも、声色なんですか?」
声色だとしたら、何故Sさんは『広さん』という呼び方を知っていたのだ?
「我ながら良い出来だった、神懸かりって言っても良い位。」
「本当に良く似ていたのでびっくりしました。」 姫が微笑む。
ああ、そうだったのか。Sさんは○本氏の意識を。
「そう、式の間中、彼はずっと奥さんと娘さんの記憶に浸ってた。
きっと娘さんも奥さんも、彼にとってかけがえの無い素敵な女性だったのね。」
え、今、俺喋ってない。
「彼が自殺を考えている事も分かってた。こういう事例では良くある事。
そんな人は一度思い直しても、何かのきっかけで再び自殺願望に囚われる。」
「だから娘さんだけでなく、奥さんも彼が生きる事を望んでいると。」
「これくらいの方便を咎める神様はいない。少なくとも陰陽道にはね。」
「じゃ、あとは最後に残った大切なお仕事ですね。」 姫が歩き出した。
『最後に残った大切なお仕事』って、これで全て終了では無いのか?
「どんな事情があったとしても、一度宿った命を軽んじてはいけない。
あの子の記憶を封じ、あの子の魂をこの学校に縛り付けていたもうひとつの理由。」
Sさんの言葉が俺の胸を貫く。そうだ、この事件の犠牲者は2人。
Sさんからの要請に応じ、この日高校は式の関係者以外立ち入り禁止になっていた。
高校側からあらかじめ通達されていたため、他の生徒の姿を含めて校内に人影はない。
姫とSさんが歩みを止めたのは中庭の端、花壇の前だった。
そこは、屋上のあの場所の真下。おそらく彼女の遺体が発見された場所。
Sさんは花壇の端にあの貝殻を置き、ハンドバッグから白い小さな袋を取り出した。
綺麗な模様の刺繍と口を縛る赤い糸、あの袋と同じだ。
Sさんは赤い糸を解き、中から取り出した小さめの人型を貝殻の中に置いた。
そうか、あの時、Sさんが屋上で取り出した人型は大小2枚あったのだ。
でも何故Sさんは校長室で話を聞く前に2枚の人型を準備していたのか?
「女子高生が『自宅じゃなく高校で』自殺した。こういう事例で家に帰れない理由って
たいていの場合望まない妊娠だもの。真面目な女の子ほど、そうだわ。」
また喋る前に。
Sさんが左手を胸に当てて眼を閉じる。深く息を吸い、ゆっくりと右掌を地面に向けた。
澄んだ声で、歌うように、古い言葉を紡いでいく。意味はよく分からない。でも、それは
おそらく、生まれる事のできなかった小さな命を慰め、その怒りを鎮めようとする言葉。
姫が人型に向かって一礼し、ブレザーの内ポケットから水色のハンカチを取り出した。
両手でハンカチを額の高さに捧げ持ち、目を閉じて何事か呟く。Sさんの言葉が続いている。
姫はハンカチを広げ、貝殻の中の人型をふわりと覆った。ハンカチの端の『○本』の刺繍。
彼女のハンカチで胎内を、小さな命を守るゆりかごを模しているのだろう。
また涙で視界が歪む。もう一度、今度は幸せに生まれてきて欲しい、心からそう思う。
やがて、Sさんが眼を開け、左手を胸に当てたまま右手を貝殻の上にかざした。
ハンカチと人型が燃え上がり、信じられない程大きな炎が上がる。
俺は思わずSさんに駆け寄り、その体を抱き寄せて庇った。
「ありがと、私は大丈夫よ。」 辺りに漂う微かな煙の匂い。
姫が微笑む。「もう、これで、本当に全部済みましたね。」
「こんな哀しい事件、世の中から全部無くなれば良いのに。」
そう言ってからSさんは大きく伸びをした。
「ん~。ねぇL、お腹空いたんじゃない?」 「はい、もうペコペコです。」
「じゃ帰りに何処かで美味しいもの食べて、それから荷物持って出かけましょ。」
「あの、何処に出かけるんですか?」 姫もぽかんとしてSさんを見ている。
「あれ、言ってなかったっけ?山奥のね、温泉宿を予約してあるの。良い所よ。
あ、確か近くに釣り場も有ったわ。『ヤマゴ』が釣れるんだって。」
え~っと、それは多分『ヤマメ』か『アマゴ』ですね。
「結構な臨時収入もあったし、少し疲れたから皆で温泉、良いでしょ?」
「あのお金、貰っちゃって良いんですか?」 姫は心配そうだ。
「『お納め下さい』って言ってたし...でも、まあ半分くらいは
後で彼の口座に振り込んで置けば夢見が良いかもね。振込人名義は『○本明美』にして。
それで本当にこの件は全部終了。それでどう?」
「賛成です。」 「僕も賛成です。」
「ならこれで一件落着。昼ご飯は何が良い?」
結
ひゅっ! しゅるるるるる。 小さなルアーがキラキラと光りながら彼方へ飛んでいく。
続いて遠くに微かな水音。 リールを巻く手の動きに合わせて聞こえる衣擦れの音。
時折彼方此方で魚が跳ねる。ゆっくりと、穏やかに時間が過ぎていく。静かな休日の午後。
俺と姫は並んでルアーを投げていた。
Sさんの提案で、温泉で有名な某県の秘湯、古い温泉旅館に小旅行に来ている。
5連休となるゴールデンウィークは、この温泉でのんびり過ごす予定だった。
ここは旅館に併設された管理釣り場。平たく言えば高級な釣り堀だ。
近くの清流を引き込んでニジマスやヤマメ、イワナやアマゴを養殖している。
スチールだのブラウンだの、やたらに外国産の魚を導入していないのも俺には好印象。
各種の釣り具もレンタルしていてとても便利、俺と姫はルアーのタックルを選んだ。
ただし、ルアーはエサと同じ扱いでレンタルではなく購入しなければならない。
20cm~30cmの魚がほとんどの釣りだから本当は1~2gくらいのルアーの方が
良く釣れるのだろうが、軽過ぎるルアーは姫には投げにくいと思ったので
柔らかい竿に5gのルアーを使っていた。姫のキャスティングも中々さまになっている。
2人で既に10尾余りを釣り上げ、夕食は十分確保出来ていた。
Sさんは岸壁に座り、水面に向かって両の素足を投げ出したまま遠くを見つめている。
そして時折魚が釣れると大喜びで拍手してくれた。
華やかな笑顔を照らす柔らかな日差し。時折吹き抜ける風がSさんの長い髪を揺らす。
静かな休日に、ゆっくりと夕暮れが迫っていた。
不意に、姫が口を開いた。
「明美さんって、本当に素敵な人でしたね。まるでお姫様みたいに。」
「何故、お姫様みたいだと思ったんですか?」
「彼女、最後は私に『ごきげんよう』って挨拶してくれたんです。
『ごきげんよう』って、お姫様が『さようなら』の代わりに使う言葉ですよね?
だから私も挨拶したんです。『ごきげんよう』って。」
...姫が微笑んで『ごきげんよう』。 萌え、むしろ萌え全開。頭がくらくらする。
「え、Lさんは何て言ったんですか?さっきはちょっと聞いて無くて。」
「だから、『ごきげんよう』って、私もそう言ったんです。心の中で。」
「あの、もう一度だけ、あ痛っ!!」
Sさんに思いっきり左腿をつねられた。
「変態!!」
「変態って何ですか?」
「女の子にセーラー服着せたり、『ごきげんよう』って言わせたりして
はあはあ興奮する馬鹿な男の事よ。」
「え、じゃあRさんって変態なんですか?」
「違います。誤解です、本当に聞き逃しただけなんです。」
「嘘つき。」 もう一度左腿をつねられた。
「だから痛いですって、反省してます。ごめんなさい。」
Sさんと姫の軽やかな笑い声が、静かな水面に響いていた。
『入学式と卒業式』 完
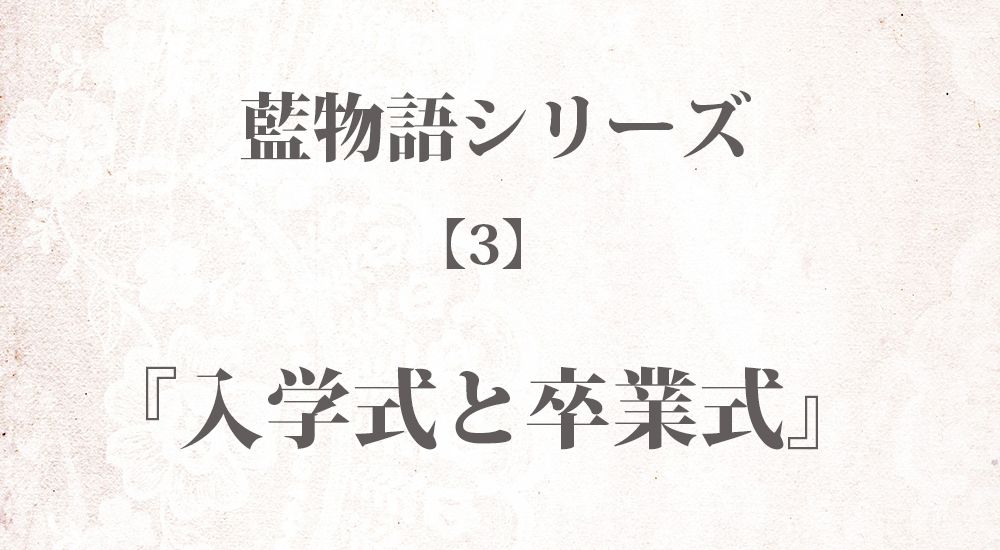
コメント