藍物語シリーズ【34】
『護符』
柔らかい午後の日差しの中、心地よいエンジン音が山道に響いている。
「ずっとこんな道なら、この車も最高に気持ち良いのに。」
姫は窓から吹き込む風に眼を細めた。
残念ながらあと1・2分で山道を抜け、幹線道路に入る。依頼の場所は市街地の一角。
「本当にずっとこんな道を走り続けられたら気持ちいいでしょうね。
その、何時でも僕たち二人一緒なら。」
姫は少しだけ驚いた顔をした後、微笑んで俺の右肩に頭をもたせかける。
「嬉しい、です。」 最後の連続コーナーに向け、少しだけアクセルを踏み込んだ。
その依頼を受けたのは3日前、いつも通り『上』からのFAX。
特に指名は無かったのだが、是非にとSさんに頼んで俺がその依頼を受けた。
依頼主はあるレストランの店長。俺が大学を休学→中退する前にバイトしていた店で、
明るく和やかな雰囲気と美味しい料理が評判だった。同じ大学の学生も良く来てたっけ。
季節毎の洒落た飾り付けや楽しいイベントは今でも続いているだろうか。
古い知人達がそうであるように、修行で面変わりした俺に、きっと店長は気付かない。
それでも、バイト中は何かと良くしてくれたからこの機会に恩返しが出来れば。
その思いにはきっと、過ぎ去った時への感傷も混じっていただろう。
感傷的になり過ぎたが故の事故を心配したSさんが、姫に俺の後方支援を命じた。
市街地、繁華街の一角にその店はある。狭い駐車場は店の裏手。
駐車場の雰囲気はあの頃のまま。駐車場奥のフェンスが俺の駐輪場所だった。
2時までのランチが終わって一旦閉店、ディナーの開店は6時から。それも変わっていない。
客足の途絶える時間帯に、依頼された仕事を片付ける事が出来れば良いのだが。
ドアを開けるとカウベルが鳴った。重く、乾いた音。これもあの頃と同じ。
ただ、不思議な程に俺の心は平静だった。もちろん懐かしい気持ちは有る。
だが、何処か現実感が無いような、まるで他人事のような感覚。
もう、あの頃の俺とは違うという事なのだろうか。何より今日は『仕事』なのだ。
「こんにちは、昨夜電話したRです。依頼の件で参りました。」
「はい、ただいま。」
奥から出てきた初老の男性。間違いない、あの店長だ。
「私がこの件を担当するRです。こちらはLさん。」
「Rさんだけでも大丈夫ですが、万一に備えての助っ人です。今日は宜しくお願いします。」
爽やかな笑顔で姫が差し出した右手を、店長は躊躇いがちに握り返した。
「此方こそ、どうぞ宜しくお願い致します。」
一礼した後、店長は俺の顔を見つめて怪訝そうな表情を浮かべた。
...まさか、俺の顔を。いや、Sさんは『心配要らない』と。
実際、偶々数年ぶりに会った親戚や旧友の誰にも俺だと気付かれたことはない。
「あの、どうかしましたか?」
姫が声を掛けると店長は気まずそうに頭を掻いた。
「あ、いや。Rさんが、何だか初対面じゃ無いような気がしたので。」
「どなたかお知り合いに似た方が?」
「はい。もう何年も前、この店でバイトしてた子に。名前も確かRと、それで。」
どうやら店長には少し『力』があるようだ。あまり深入りしない方が良い。
「興味深い偶然ですが、依頼の話を。出来れば今日で始末をつけたいので。」
「そうですね。ではこちらの席に。今、営業日誌を持ってきます。」
勧められたテーブルの椅子を引く。「どうぞ。」
「ありがとうございます。」 腰掛けた姫の、悪戯っぽい笑顔。
「折角、昔のRさんの事、聞くことが出来そうだったのに。」
「その話は後です。僕が感傷的になり過ぎないように監視するのがLさんのお仕事ですよ。」
「でもお仕事は。」
店長がホットコーヒーの用意をして戻ってきたので姫は続く言葉を飲み込んだ。
コーヒーの香りが店の空気に溶けていく。ふと、店の片隅に小さな気配。
店の壁際、大きな窓を背にして立つ。多分小さな男の子のシルエット。
「ああ、なるほど。確かに一体、いるようですね。」
俺が呟くと、テーブルに日誌を並べていた店長の左頬がピクリと動いた。
「本当に分かるんですか?この店に入ってからずっと?」
「いいえ。今コーヒーを淹れて貰ってるうちに。何処からか突然現れた感じです。」
「コーヒーを淹れたから...やはりお客さんに反応するのでしょうか?」
まるで独り言のように、店長は小さな声で呟いた。
店長は分厚い営業日誌をめくりながらポツリポツリと事情を説明してくれた。
開店後暫くして、時折店の中に不思議な気配を感じるようになったこと。
当初は営業に支障が無かったので放置していたが、
3年ほど前から希に支障が出るようになったこと。
「家族連れのお客様でした。お子様が突然泣き出したと思ったら、
過呼吸のような感じでそのまま意識が無くなって、それで救急車を呼びました。
病院ではすぐに回復されたようですし、この店に原因があるかどうかも...。
ただ、その後も、同じようなことが二度起きています。」
「計三度、お客さんの子供に障りが出たということですね?」
「はい。開店から11年、開店当初大学生だった常連さんが家庭を持って
ご家族と一緒に御来店下さることも多くなってます。
今後も同じような支障が出るのでは安心できません。それで今回の依頼を。」
この件と俺、いや、店長と俺に何かの縁があるのだろう。
この店の常連に一族の者がいて、たまたま『事件』に出くわした。
それでその人が『上』への依頼を取り持ったのがこの仕事の発端。
その人と俺たちの面識はないから、特に俺たちが推薦された訳では無い。
たまたま近場で手の空いている術者が俺たちで、だからこれは本当の偶然。
そうでなければ店長の依頼を俺が受けることは無かった筈だから。
「まあ私としては、以前のように、営業に支障が出なくなればそれで良いんですけど。」
相変わらず心の広い人だ。胸の奥から、温かな感情が込み上げる。
多くの人は事情も分からぬまま、そのような存在を忌み嫌う。
それに、『上』からの指示とは言え、無理矢理に始末を付けるのが哀しい事例も有る。
「営業に支障が出ないなら、共存しても構わない。そう解釈して良いですか?」
店長は暫く俺の顔を見つめ、やがて溜息をついた。
「私にはそれが何なのか分かりません。だから少し、怖いような気もします。
でもそれが今までずっとこの店にいたものなら、お客様に悪い影響が出ないのなら、
このままこれからも此所にいてくれて良い。そんな気がするんですよ。
客商売をする人間としては、失格なのかも知れませんが。」
開店して暫くしてから、それが店長の記憶違いでないのなら、
俺がバイトをしていた頃には既に、それはこの店にいたことになる。
小さな男の子の姿がハッキリしてくるほど、人間離れした特徴も目に付く。
体全体がゆらゆらと波打つように動き、顔の造作が絶え間なく変化する。
もし、当時の俺がそれを見たら間違いなくパニックになって腰を抜かしただろう。
俺の仕事は主に皿洗いだったから、11時頃まで厨房に一人でいることも多かった。
もしもそんな時にこの姿を見ていたら...
思わず、笑顔が浮かぶ。あの頃とは、随分違った自分を俺は生きている。
「男の子です。5~6歳位の。だから希に小さな子供に反応・干渉して、
加減を忘れてしまう事がある。そんな感じでしょうね。
この店から祓うとしたら、その由来を調べて入念に準備をする必要がありますが、
あなたが共存しても良いと仰るので有れば、お祀りするだけで十分です。」
「お祀り?」
「はい、あなたやお客さんに対する悪意を持った存在ではないのですから、
しっかりお祀りしてこちらの好意と願いを示せば、きっと応えてくれると思います。」
一体、見えないということは、不幸なのか幸福なのか。
俺の正面に座った店長の背後、すぐ右側に、小さな男の子の姿をしたそれが立っている。
俺と姫を交互に見つめる、不安そうな表情。その眼には悪意も悲しみも感じられない。
「先ほど『小さな男の子』と言いましたが、所謂幽霊では有りません。
どちらかというと妖精に近いもので、それが男の子の姿をとっています。
ハッキリした意思を感じませんから、おそらく記憶を封じているのでしょう。
それが何かの拍子にあなたか、それとも店のお客さんに憑いてきて、ここに落ち着いた。」
「それなら、何処かに本当の居場所があるということですか?」
その優しさに少し、胸が詰まる。
「大昔ならともかく、近代以降は妖精の住める場所はどんどん減っています。
それに、詳しく事情を調べたら却ってマズい事になるかも知れません。
例えば住処を人間に破壊されて、それを思い出したら怒りと悲しみに囚われるとか。」
調べたとしてそれの正体が判明するか分からない。ただ、人の姿を取っているのだから
もともと人に親しみを感じていた存在なのだろう。もしも、人に住みかを破壊されてもなお、
『人を恨みたくない』『人を憎みたくない』 そんな気持ち故に記憶を封じたのなら、哀しい。
「確固とした意思を感じないので、おそらく自我も姿の通り幼い子供のレベルでしょうね。
退行した原因は分かりませんし、結局あなたや此所との相性が良いとしか。」
「そう、ですか。なら結構です。此所に居た方が良いというなら、ずっと居てもらっても。」
「分かりました。では早速用意をします。暫く、そうですね。30分程時間を下さい。」
茶色い皮の鞄、My『お出かけセット』から必要な道具を取り出す。
この子への親しみを編み込み、同時に、この店とお客さんを護ってくれように願を編み込む。
ホームセンターで調達し、白い封筒に小分けした結束バンド。今回使うのは赤・白・緑・青。
俺はSさんと違い、紙を使うのが得意ではない。
加工する必要がなく、容易に結び目を作れる結束バンドは本当に役に立つ。
「あの、それは?」 「特別に、僕の師匠に清めて貰った、護符の材料です。」 「へぇ。」
すい、と姫が視線を逸らして窓の外を見た。 笑いを堪える、可愛い表情。
まあ、時には嘘というか方便も必要だ。
ただの結束バンドだと言ったら、信じる気持ちは薄れ、護符の効果も弱くなる。
「一目一目、想いを込めて編みます。その子のために、このお店とお客さんのために。」
「ありがとう、ございます。」
「ところで店長さん。」 突然姫が口を開いた。 店長の戸惑った顔、「はい?」
「さっきの話が気になっているんですが。Rさんと同じ名前の、アルバイトの方の。」
「ああ、あの子は...もう5年前ですね。」
店長は再び営業日誌をめくった。目配せしようとしたが、姫は知らん顔だ。
事情は聞いたし、既に護符作成にかかっている。
『後の話』をしても問題はない。俺はただ、護符作成に集中すれば良いのだから。
「とても真面目に働いてくれて、卒業したら正式に採用したいと思っていたんですよ。
でも、急に辞めてしまって。残念でした。故郷に帰ると言ってましたね。」
その話なら既に姫も知っている。『田舎に帰って見合いをする』というのが筋書きだった。
「その人、Rさんはどんなお仕事をなさっていたんですか?」
「食器洗いと、時々は食材の下ごしらえの手伝いも。
そうそう、季節ごとの飾り付けも任せてました。何時も見事な出来でしたよ、とても器用な子で。」
二人の話を聞いても、心は不思議な程平静で、特別な感傷は湧かなかった。
もう、あの頃の俺とは違う。新しい家族と新しい人生を歩んでいる。
昔の話を聞くほど、その感覚が強くなり、むしろ気持は静まっていく。
それもあって、護符の作成は思っていたより順調に進んだ。
重要なのは、結び目の数と、それをまとめる色の意味。
次第に形を取る、大きな花弁と、それを取り巻く艶やかな葉。
『命の喜び』、そして『心からの願い』を意味する護符。
一目毎、結び目に俺の『力』を編み込んでいく。確か3年の修行の成果。
いつの間にか、全ての音も情景も、俺の心から消え去っていた。
それからどれ程の、いや、多分予定通り。30分前後の時間。
これで良い。額の汗を拭い、ふう、と息をつく。 「出来ました。」
「これは...綺麗だ。何というか、如何にも御利益が有りそうですね。」
Sさんから習った護符の1つ。赤・白の花弁と緑・青の葉を象った意匠。
「これをどこか、店の中に置いて下さい。引き出しの中とかで構わないので。」
「いや、それでは勿体ない。これは是非、ああそうだ、飾り棚に。」
店長は受け取った護符を手に、壁の飾り棚に向かった。
ガラス戸を開け、棚の上段にそっと護符を置く。もう一度護符に触れてからガラス戸を閉めた。
ふわりと浮き上がり、店長の背後からそれを見つめる男の子。嬉しそうな、笑顔。
もう、大丈夫だ。
「お礼にディナーをご馳走したいので、このままもう少し。」
俺がテーブルの片付けを終えたタイミング、間髪を入れず姫が頭を下げた。
「申し訳ありません。店長さんのお気持ちは嬉しいのですが、
既に料金の精算は済んでいると聞いています。
それなら、仕事以外の理由で長居するのは禁忌なんです。」
失礼無く、依頼主の申し出を断るとしたらこれ以上の方便はない。流石に姫だ。
「そう、ですか。それなら。」 店長は足早に店の奥に入り、暫くして出てきた。
「せめてこれをお持ち下さい。」 綺麗な紙に包まれた、洋酒の瓶?
「ありがとう御座います。頂きます。では、私たちはこれで。」
店長に見送られて店を出る。男の子の姿はない。
飾り棚に両手をついて、あの護符を見つめる姿が目に浮かぶ。
無事に仕事をやり遂げた充実感。それこそが術者にとって、何よりの幸福だと思う。
今度俺がこの店を訪れるとしたら、それはかなり先のことになるだろう。
車の窓からじっと景色を眺めていた姫が、不意に口を開いた。
「何だか、とても嬉しいです。私、信じていましたから。」
信じていた? 俺が護符を作ったのは初めてじゃない。護符の事でないとしたら。
「信じていたって、何を、ですか?」
「昔の話をしてもRさんはもう感傷的になったりしないって。」
「そりゃ僕はもう昔の自分とはかなり変わりましたから。あまり感傷的には。
でも、感傷的にならない方が良いのなら、あの時わざわざ昔の話をしなくても。」
「Rさんが『昔の自分じゃ無い』って自覚することが必要だったんです。お仕事、ですから。」
??? 自覚? 仕事? でも姫の仕事は。
「あの、御免なさい。話の内容が理解出来ないんですが。」
「あの子をあの店に連れてきたのはRさんです。何時何処から、それはもう分かりませんけど。」
「へ?僕が?」
「はい。Rさんに憑いてきて、偶々あの店と店長さんの気配に馴染んだ。
だからあの子があの店で安定した状態を保つには、店長さんとRさんの気配が必要なんです。」
いや、しかし俺があの店でのバイトを辞めたのはもう5年も前だ。
その後あの店でバイトした人間は沢山いた筈だし、既に俺の気配など。それなのに。
「店長さんのことは分かります。でも、僕の気配が今もあの店に?
もう5年も前ですよ?幾ら何でもそんなに長くは。」
「だってあのお店には『身代わり』が。忘れちゃったんですか?」
「あ。」
そうだ、姫に仕込まれた術の件。『分家』の術者を攪乱するために、
姫が作ってくれた身代わりをあの店にも隠した。確か更衣室とトイレ、厨房の戸棚の奥。
「いくら身代わりでも、本物がすぐ傍にいたら効果がありません。
そしたらあの子はまた、Rさんに憑いてきてしまうかもしれないと思ったんです。」
「だから昔の話をして、僕が昔の自分とは違うとハッキリ自覚するように?」
「はい。もしかしたらSさんはRさんがこの依頼を受けると決めた時に
何か予感していたのかも知れませんね。だからきっと今日私を一緒に。
でもSさん自身で無く私を。それならSさんも信じていたんです。
Rさんはきっと大丈夫。絶対に過去に囚われる事は無いって。」
...姫も、Sさんも、一体どれ程の。
術者としての時間を積み重ね、自分が力を付けるほどに、二人の力の凄さを思い知る。
でもそれは何だか小気味よく、そして嬉しい。笑いが込み上げた。
「どうしたんですか?何だか楽しそう。」
「楽しいです。だって二人の凄さが分かる度、『僕にはやるべき事が沢山ある』って
自覚できますから。そう、明日からまた、頑張りますよ。」
黙って微笑みを浮かべた姫の横顔は、とても美しかった。
「お礼がこのシャンパン?しかもロゼ。こんな高価なお酒を普通に在庫してるなんて、
そのレストランかなり繁盛してるのね。妙な事があったのに、お客は減らなかったのかしら。」
「子供たちの事例は食中毒とかが原因じゃないのが明らかで、それについて
店の責任を問う声は無かったようです。店長の対応にも問題は無かった訳ですし。
むしろそれ以外の妙な事、不思議な気配や何かが話題になって、
口コミでお客は少しずつ増えていたようですね。
『その店で食事すると恋が叶う』とか、『大きな商談にはその店が絶対』って。」
それは多分、座敷童の出没する宿に宿泊したがる人々に似た心理なのだろう。
「Rさんが作った護符が有りますから、今後は稀な障りもなくなる筈。
これからはお客さんに、もっともっと良い影響が出ると思います。」
「それならこれ飲んでも罰は当たらないわね。早速冷やして夕食に。楽しみ~。」
Sさんはそのお酒を持ってリビングを出て行った。軽やかな足音。
姫の言葉通り、その店は大いに繁盛し、今では地元でも評判の名店に数えられている。
未だ不思議な噂も絶えないらしいが、それがまたオカルト好きの大学生たちや
小さな子供のいる家族連れには大評判だと聞いた。
もちろん料理も美味しいし、何より店長の度量が有ってこそ実現した一種の奇蹟。
100年程前なら、そんな場所が普通に存在していたと聞いた。
人と人ならぬモノが自然に交流する不思議な場所。 『交差点』。
きっと現代にも一軒くらい、そんなレストランが有っても良い。
Sさんも姫も、同じ意見だ。
ただ、万一の事を考えると俺はその店に行かない方が良い訳で。
それだけが少し残念なのだけれど。
その店の名は『◎×◆』。
『護符』 完
藍物語シリーズ【全40話一覧】
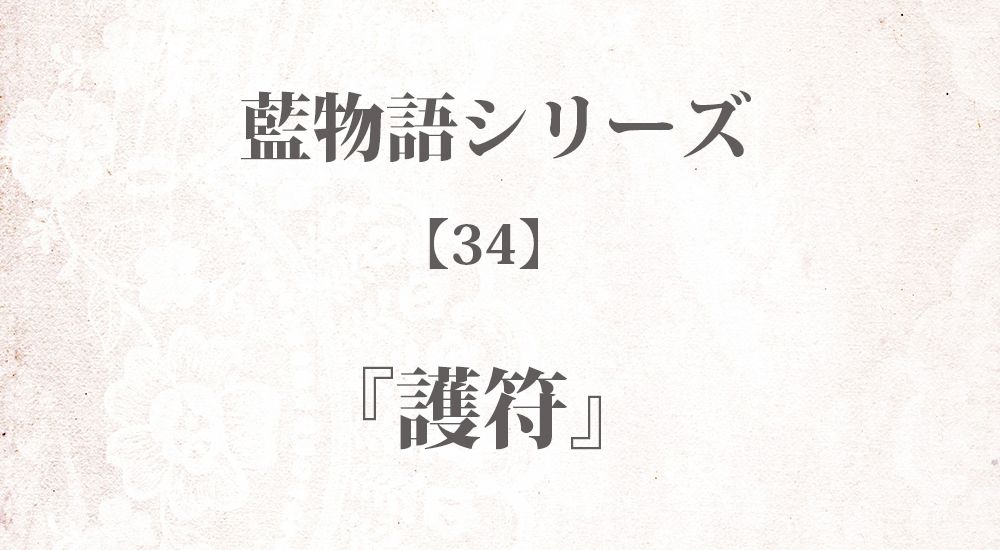
コメント