電車にて
会社帰りの体験談
全部で五日間。実体験を100%増量で事実と捏造半々でお届けします。
一日目。この日は前日からの残業が早朝まで続き、仮眠をとってまた仕事というハードワーク明け。ふらふらだった。
椅子に座れた幸運を喜びながら、梅雨時に缶詰で臭う自分の体臭に辟易としていた。
俺の下車駅まで、あと10いくつだかある頃に、乳母車を抱えた女性とその旦那さんが、混雑した車内に入ってきた。
さっと立って席を開け、どうぞと手で席を指し示した。少しやつれてみえたからか、遠慮されてしまった。
すると、すぐ斜め前にいた中学生位の子が、やっと、ありがとうございますと言いながら
赤ちゃんを抱き上げて、席に座ろうとした奥さんの目の前で、嫌がらせのようにどかりと座った。
車内に、なんとも言えない空気が漂った。
こいつ、マジかよ。何やってんだ。最低。
そんな視線がその子に集まり、幾人かはきつい視線を送ったあと、自分だけではないことを周りを見渡して確認していた。
その中学生とおしゃべりしていた友達らしき子が凄く恥ずかしそうにしながら
「おい、お前何やってんだよ」
「何って、座ってんだよ」
「いいから立てって」
「座りたいんだよ」
返事は妙に間延びしてた。表情は空白。
普通本気で嫌味でやるつもりだったら、悪意の一つも表情に浮かぶんだが、それがないことが逆に不気味だった。
結局、俺が座っていたのと反対側に座っていた、五十代位の女性が、こっち、こっちさおいでなさいと夫婦を招き、奥さんに席を譲っていた。
二日目。日照りのきつい日の夜。俺はこの時は結構元気だった。
同僚と飲んだ帰りで、新宿にいたので、西武新宿から電車に乗った。
日本見過ごし、がらんとした車内の、どの席も選び放題の最前列にならべた。
上石神井の手前で、見覚えのある夫婦が乗ってきた。またも、車内は混雑していた。
今日は、以前よりも、爽やかに席を譲ろうと思った。
「そこのご夫婦さん。席お譲りしますから。どうぞ」
そういって笑顔で立ち上がろうとした瞬間。頭をガツンと殴られたような衝撃が襲った。
わけがわからなかった。何にもぶつけてない。
急速に息苦しくなって、目の前の人がつかっていたつり革にすがるように手を伸ばした。
訝しげで、迷惑そうな表情をされた。でも、膝ががくんと力を失ってしまうと、指先からも力が抜けた。
まったくわけもわからないまま、意識がはっきりした状態で、俺は倒れた。
倒れこんだところで、俺の頭をまたぐ、足が見えた。一瞬だが確かに見えた。
車内は騒ぎになった、周りじゅうの人が俺を気遣ってくれた。
席を譲ろうとして立ち上がったら、いきなり倒れるなんて、なんて後味の悪い真似を、ご夫婦にしてしまったんだろう。
申し訳なく思いながら、ご夫婦に済みませんといった。旦那さんは、俺の顔をみて、あ、と一言発した。
どうやら前にも席を譲ろうとしたことを覚えていたようだった。
「いえ、こちらこそ。立ちくらみですか?急に立ち上がるとなりますよね」
凄くさわやかな好青年といったかんじだ。渋さも併せ持ったバリトンがとても心地よかった。
俺は立ちくらみということにして、大丈夫ですと周りの方々に謝罪と感謝を述べた。
この時は、俺の隣にこしかけていた、女子大生ぽい方が立ち上がって、奥さんに席を譲ろうとした。
すると、息苦しさと、ずきずきと痛む頭が嘘のように楽になった。
足が見えていた俺は、咄嗟に女子大生風の子を見上げた。彼女はなんともない様子だった。
奥さんと俺と俺が腰掛け、目の前の方が場所を譲って下さったので、旦那さんと女子大生さんが並んだ。
さっきはびっくりしました、という女子大生のとても可憐な声が聞こえた。
そういえば、倒れそうになったとき、腰をおもいきり支えようとしてくれたことを思い出した。
それとともに、やわらかいものが腰に触れた感触が蘇ってきた。
ごめんなさい。優しいお嬢さん。俺は、結構野獣なんです。性的な意味で。
三日目。この時の俺は、かなり不機嫌だった。
讒言めいた告げ口で、常務からの呼び出しを食ったせいで、残業するはめになったからだ。
常務には、外回り中にサボりなんてやっていないと理解してもらえたが、奮然たる思いは残っていた。
ムカムカとした気分でいると、上石神井に着いた。
また、あの夫婦が見えた。よく会うなと思いながら、振り返ると、見れば階段すぐ側の立地だ。
よくよく考えてみると、このご夫婦も結構周りに配慮がない。
乳母車や赤ちゃんがいるなら、駆け込み乗車の多い階段側は避けるべきだ。
それが、ひいては、赤ちゃんの身の安全も守る。
すぐに声をかけた。
「席、お譲りしますよ」
「え?ああ…ご縁がありますね」
少々考えが足りないところがあるが、ご主人はとてもさわやかな笑顔を浮かべた。
そして立ち上がろうとした時、俺は、またも、気分が悪くなった。
肩が重くなり、首筋から脳天にかけて痛みが駆け登っていく。
奥歯まで痛みだして、なんだか、テレビでみた、血管系の病の症状にもにていた。
まさかひょっとしてと思いながら、俺は、人を押しのけてこっちにやってくる、巨漢をみつけた。
巨漢は俺の肩をばしっと叩いた。
「おい、気分悪そうだぞ」
巨漢がこう言う頃には、叩かれた瞬間から嘘のようにあの変な痛みと苦しさがひいていた。
「ひょっとして、またですか?」
旦那さんが心配そうに言うが、なんともない。
「いえいえ。今日ちょっと仕事場で嫌なことがありまして。人相、悪くなってたのかもしれません。
元の出来が悪いからなおさらみなさんに心配かけてしまうんですよ。ははは」
「そ、それは笑っていいのやら」
「いつもありがとうございます」
奥さんがうれしそうに微笑みながら、俺の空けた席に腰掛けた。
巨漢は、赤ちゃんをみて、太りすぎて腫れぼったい眼のために、悪人面となった顔をたちまち崩した。
奥さんが慈愛のこもった眼差しで見るのを、嬉々として見つめた後、旦那さんを見て、すっと表情をひきしめた。
この変化を俺は、変だと感じ取っていた。
巨漢は、小平で下りた。俺はまだ先だったが、巨漢に続いて下りた。
「あの…」
「あの旦那さんにはかかわらないほうがいいよ」
「え?」
「ありゃ、相当なろくでなしだ」
「…実は前にも席を譲ろうとしたら、倒れてしまって…」
「あんた優しい人だろ」
「いや、そうでもないですよ」
そう言いながら、疲れてる時でも、自然と席を譲ろうとする変な習性のことも思いだした。
でも、それは優しいとは違うような気がした。なのであらためて首を左右に振った。
「優しくなんて」
「まあいいや。俺の目にはな。あんたの霊体の、髪の毛やら服やらひっぱる、四人の子供が見えたんだよ」
「は?」
ぞくっとした。そういえば、ありもしない足を見ていた。
「奥さんの方は、ありゃ嘘がないな。けどあの旦那さんは、ありゃ相当曲者だよ。やつ憑かれてて、しかもタフだから周りに迷惑かける」
「私には、とてもそんな風には」
そう言いながら、前に見た足を思い出して、語尾が震えた。
「憑かれてる理由も大方あの亭主が、あの子供達になんかやったからだな。性別もわからないくらいにぼやけてたし。
多分ありゃ水子だな。大方、女遊びしまくった挙げ句に方方で堕ろさせでもしたんだろう」
「……足が」
「足?」
「最初に倒れた時、足が見えて」
「そりゃいけないな。あんた、優しいから、受け入れかけてるんだ」
「受け入れる?」
「一つの体に魂一つ。これが原則なんだよ。ツカレルってのはツカレルもんなんだ」
「ええと」
「取り憑かれるってのは、疲労するってことだよ」
「ああ…」
「世間一般でいう霊障とかよか、おっそろしいぞ。
なんせ、一度受け入れたら目には見えない、自分じゃ気づくこともできない。んで疲れまくる」
「……どうしたらいいんでしょうか」
「しんじんは?」
「しんじん?」
「信仰でもいいや」
「ああ、信心か。クリスマスには似非クリスチャンで、正月には似非神道、普段から何も信じてません」
「じゃ、心を強く持つんだな」
「え?ちょっと…」
何やら、医者に匙投げられたような感。
「いや、俺もそんなかんじだし。携神様とかいりゃその教えを頭の中で唱えろとかいうんだけどさ」
「ああ。投げやりにってわけじゃないんですね」
「とにかく、あんたはほんと気をつけた方がいい」
巨漢はこういって、肩をぽんぽんと叩いて立ち去った。
「良かったらもう少し詳しくご教授ねがえませんか」
そういってみると
「それはやめとくわ。実は俺ゲイなんでな。あんた、良い男だからさ。あんまり一緒にいるとその気になっちまうよ」
「てっきり霊能者かと思いましたが、ご職業はゲイ人でしたか」
「うははは。こりゃ傑作だ。そうそうそんなかんじで明るくしてりゃ大丈夫。じゃあな」
「陽気は妖気を打ち消すって考えでいいんですね」
「あっはははは。今度からそれ使わせてもらうわあ」
四日目。この日、本当に必要なものは、必要なときにはないのだと俺は思い知った。
最初にあの夫婦とあってから、一冬を越し、春になっていた。
その顔を見た時点で、半ば反射的に立ち上がった。
「どうぞ」
「え? ああ。お久しぶりです」
奥さんが、こちらをぼんやりと見上げた。そして、ほんの少し微笑みかけてきた。
なんだか生気がない。
「あれ…」
奥さんは赤ちゃんを抱いてもいなかったし、乳母車もなかった。
「車内で…する話ではないので」
俺が何を言いたいかを察して、旦那さんが機先を制した。
奥さんの顔をみやると、奥さんがきゅっと唇を噛んだのが見えた。
死んだのだ、と直感的に思った。
その途端、スラックスの裾を、スーツの袖を引く感触がまざまざと感じられた。
いるはずのないものだ。隣には、両隣には他のお客さんが座っている。
袖なんてひかれるはずがない。でも、その感触がする。
おそるおそるみてみると、服はなんともなってない。なのに腕がゆらゆらと引かれる感触に従って動く。
異変はそれだけではおさまらなかった。袖を引く力が、俺の前方へと引きずるようなベクトルへと変わった。
「…っ…」
全身総毛立っていた。何かとんでもないことになってる。
もしかして、子供たちか?明るく明るく。ファーンキーヒャッッハーと頭の中で叫ぶ。
俺の意識が子供たちへと向いた瞬間に、見えた。
一人を除いて、全員灰色のぼやけた靄のようだ。子供だとわかるのはその背丈から。
残る一人は、俺の膝の上にいた。白い。輪郭がそれと教える。赤ん坊だ。
「……っ、な ん だ、こ れ」
本気で怯えると、声を出すのもつらい。途切れ途切れの声は、電車のがたんごとんいう音に勝てなかった。
俺の様子がおかしいと気づき、旦那さんがはじめて、笑みを消して、すっと鋭い眼差しをおくってきた。
「どうか、なさいましたか」
気遣いの心なんて篭ってない声。ぐいっと袖をひっぱる力が強まった。
俺はなげだされるように目の前の会社員の股間に頭突きをするようにして倒れこんだ。
会社員は男性シンボルのガードを辛くも成功させてくれた。
ありがとうと言いたい。もし頭突きでタマ破裂なんてしたなんてことになったら、俺は、会社にいられなかった。
「こ、子供が、見える」
俺がこういったのは、なりふりかまっていられなかったからだ。
アナウンスからもうじき次の駅だと知れた。何かうしろめたいことがあるなら降りると思った。
両手を床について無理やり座席に戻りながら、目の前の会社員の男性が向けてくる怒り顔に、申し訳ありませんと頭を垂れた。
「あなた、この五人の子供に、何したんですか?」
普通なら、頭がおかしい、と思われてもおかしくない言葉だ。
けれど、はっきりと、ありありと、怒気もこめた俺の声に、旦那さんの顔に怯えが浮かんだ。
ごくごくあたりまえの、帰路につく人々を載せた車内。
「な…何を、頭おかしいんじゃ……」
「一人は、赤ちゃん。後の四人はぼやけてる。何って聞きたいのはこっちですよ」
「よ、に? …ひっ……ひァっ!……」
旦那さんが怯えだした。明らかに俺の言った人数に、心当たりがあるようだ。
そのとき、ホームの側のドアが開いた。旦那さんが奥さんを突き飛ばすようにして、二人して降りていった。
俺の目には、旦那さんの体にまとわりついた黒い靄が見えた。どれも、ひっしにママにしがみつこうとしている赤ん坊を、蹴ったり、殴ったりしている。
それで、体を襲っていた変調が止んだ。俺と旦那さんのやりとりを聞ける位置にいた人すべてが、俺を凝視していた。
少なくとも、旦那さんのおびえっぷりが、俺が単なる頭のおかしいやつではないという信ぴょう性を与えていた。
「あの、子供が見える、とか…聞こえたんですが」
恐る恐る声を発したのは、さっきあやうくタマを潰しかけた会社員さんだ。迷惑をかけておいて事情も言わないのは失礼なのでと前置きをして。
「俺自身信じがたいんですけど。はい。というより、体を引っ張られてて…さっきはすみません」
そういったとたんにおじさんがひっといって一歩後に下がった。
体を引っ張られていたというのが余程、恐ろしかったらしい。
よくある普通の満員電車で、夫婦の片割れが、目の前のくたびれた、どこにでもいるサラリーマンの言葉に怯えて逃げ出した。
そのサラリーマンが、まだ怯えの残る、硬い表情でこんなことを言うのだ。聞く側の立場を慮ってみると、うん、こわいわ。
少なくとも日常の場に、こんな、心霊とかいった、不気味なものは持ちだして欲しくない。俺自身がそうだ。
俺の両隣の席の人が立ち上がって、人をかきわけて離れていった。疲れているだろうに、申し訳ない気持ちで見送った。
「…それは、大変。災難でしたね。で、もう大丈夫なんですか?」
「ああ、あの人が降りたらついていきました」
「…そうですか。おとなり、よろしいですか」
「ええ、どうぞ。気持ち悪くなければ」
「ああ、いや、霊能者さんがそう仰るなら」
「私、ただの一般人ですよ。こんな体験、はじめてです」
「そうなんですか?」
「はい。二度と、御免ですね」
俺は、あの巨漢が今日このばにいてくれなかったことをとても、心細く思った。
その時の心境はこうだ。あいにく俺は掘られたくない。
だが、この霊障からすくうかわりに、手で擦ってくれといわれたなら、間違いなくうんといっていた。
この日、俺はものすごい悪夢に悩まされた。旦那さんが俺にむかって、目撃者は死ねと喚きながら、襲いかかってくる夢だった。
目覚めた時の、なんとも言いがたい気持ち悪さの中で、視界に灰とか黒の靄がかすめたような気がした。
この日から俺は神社仏閣の前を通るときは、常に一礼する癖がついた。それほど怖かったのだ。
5日目。その日は、俺は立っていた。その前日もだ。
前回、あの夫婦を見かけて以来、一度も座席に座っては居ない。
上石神井でドアが開き、降りる人たちに押されてドアの外にはじき出された。
そのすぐ横に、見た顔があった。夫婦の奥さんだ。おれはすぐに周囲を見渡した。あの男だけは勘弁だ。
あの男は、本当に、今更ながらに思うが、不吉な感覚がする。とに
逃げ出すつもりで周りを見渡したが、あの不愉快な顔はなかった。黒い靄も見えない。
「あの、ひょっとして」
奥さんが俺を見上げて、俺がたちまち怯えた表情であたりを見渡したことについてたずねてきた。
彼女は俺のスーツの裾をひいた。俺はそれがあの黒い靄の子供のように感じて、びくっと体を震わせて振り払おうとしてしまった。
それが奥さんの手に寄るものと気づいて、恥ずかしさが募り、赤面してから、すみませんと呟いた。
奥さんは俺にどこに住んでいるのかと尋ねた。
俺は、八坂ですと答えた。奥さんは自分が西武遊園地が最寄りだと言った。
「前にお会いした時のこと、詳しく、教えていただけませんか?お茶くらいしかごちそうできませんが」
奥さんが俺の手を握ってきた。何か違和感を感じたので、それとなく視線を落とした。
左右の手のどちらにも指輪がはまっていない。
そして、彼女の胸元にすがりつくように、赤ん坊の幻影が見えた。
幻影であったほしかった。見た瞬間、ものすごい悲しみが押し寄せてきた。
気づいて、貰えない。抱きしめて、貰えない。呼んで、貰えない。
これが、波長が合うということなのだと気づいた時には、不覚にも涙がこぼれていた。
「あの…」
「わかりました。お付き合いします」
電車にのっている間中、俺は、つとめて平静を装った。
みんなも試して欲しい。奥歯をおもいっきりかみしめて。舌を上顎につけたじょうたいで 口の中から空気を抜くようにする。
舌に圧迫をおぼえるまでだ。眉間より少し上に力がこもるようにして、左右の耳を後ろ方向に動かすと、硬い表情の出来上がりだ。
まちがっても、鼻をふくらませてはいけない。耳を動かす時に鼻が動く人も多いので注意しよう。
これが、私が社会人の啓発セミナー(あぶないところではない)で教えられた、性感さを装う顔つきだ。
西武遊園地についてから、彼女がタクシーを拾った。
私は、夜の湖を見ていた。奥さんが多摩湖ですと言った。
「夜の湖とは、ミステリアスで、デンジャラスな雰囲気がしますね」
平静を取り戻したあとにやってきたのは、ドキドキだ。奥さんはとても綺麗な方で、そして俺は、Cherry Boy!
仲良い女性がいなかったわけではない。青春の甘酸っぱさを感じた経験がとぼしいのともちがう。だが、すべてが良い友達という評価だった。
甘酸っぱいマイナス甘。酸っぱい思い出とでもいうべきだな。
まったくその気になれない相手から好きだと告げられた事が、幸運であったと気づく年齢に、俺はなっていた。
ここで巨漢の言葉を思い出した。明るくしてりゃ、大丈夫。少なくとも、さっきの悲しみはもうどこにもない。
ついでに、青春の中でやってきていたささやかな幸せを見逃した悲しみも、きっとすぐフライアウェイ。現実逃避というなかれ。
招かれてお宅にお邪魔した。結構古びた一軒家だったが、車二台入りそうな駐車スペースをはじめ、広々としていた。
居間にとおされたところで、線香の残り香が感じられた。仏壇はどこだと見渡して、閉じられたそれをみつけ、真っ先にそこに向かった。
開いてみると、生前のあかちゃんの屈託の無い笑顔の他に、あの旦那さんの顔写真もかざられていて、位牌が2つあった。
薄々、感じていたことだ。あの黒い靄は、明らかに、害する目的でいた。
「前回あったあとから、主人が、動く靄が見えるんだと喚くようになりまして」
「……そうですか」
奥さんの方は極力みないように、出された珈琲に口をつけた。結構良い豆をつかっているように感じられた。
少なくとも、セールで500g298円の格安豆に慣れた俺の味蕾には、高尚がすぎる。意訳するとさっぱり味の良さがわかりません。
「四人見えるとおっしゃいましたよね」
「そうでしたっけ」
赤ちゃんの心を知ればこそだ。だからこそ鬼にならなければならないと思った。
気づいてもらえず、抱いても貰えず、呼んでも貰えず。このうち2つは俺が教えることで解消される。でも、抱きしめるのは無理だろう。
俺のように見えるようになるなら良いが、あれだけ人数がいて、見えたのは俺とゲイ人さんだけだったのだ。
奥さんが見えるようになるという前提で、教えるのは、奥さんを不幸にするだけだと思った。
そしてそれは、ママを慕う赤ちゃんにとっても、けして幸福なことではないとも思った。
自分が辛いことを言いたくないための言い訳に過ぎないかもとも思って、自分が嫌になりもした。
「確かに、後一人、赤ちゃんもと」
やはりきたかと、心は身構えた。
「ああ、そうでしたね」
「その赤ちゃんは…今は?」
「見えません」
嘘をつくとき、人はおもってもみない行動をする。
視線を避けてきたこの俺が、よりにもよって、嘘をいってないと証明するために、奥さんの目をまっすぐ見つめた。
奥さんはすぐに違和感に気づいた様子で、それを見て、おれが挙動不審であったことを理解した。自分の馬鹿を呪った。
「見えていらっしゃるんですね。では、先ほど泣いてらしたのは」
「それは、ですから、あの四人の黒い靄の子達が成仏したこ…」
俺の意識がそこに及んだ時、全身を悪寒が包んだ。母にすがりつくあかちゃんの一部が黒く霞む。
そのかすみがかった源泉をたどって、俺はまたも、あの黒い人形のもやをみた。四人。いや、四匹だ。そう呼ぶべきだと思った。
悪いが、俺はこの奥さんに同情していた。この赤ちゃんにだってそうだ。
俺の、鈍い勘が、この四匹が、あの男と、赤ちゃんの死に関わっているとささやいていた。
不幸を呼ぶものに違いないと、先入観まみれで結論づけた。
今でも強く思いだすのは、この時の俺は只管頭の中で馬鹿みたいなくっだらない妄想とかを繰り広げていたことだ。
明るく、明るく、前向きに、その感情のためならなんだって想像した。
お決まりの奥さん助けてゴールイーンなんてものじゃない。
俺は昔セザールの宣伝が大好きだったので、そういえば自己紹介まだだし、うまくおわったら、セザールって答えてやろうとか思ってた。
そんくらい必死になっていた。まあ、その甲斐も全くなかったんだけどな。
「…実は、私にも、見えるんです」
「え?」
「あの人が、交通事故で運ばれた日に、病院にかけつけたら。見えたんです」
「…はっきり、言ってもらえませんか。どんなものが、見えたんですか」
「黒っぽい靄のようなものです。それから、時々…。
……まあちゃんは、突然体調を崩して、お医者様も原因がわからないといっているうちに、すごく咳き込んで、苦しんで。
そういえば、その時も、病室が靄に包まれていたような気がします」
まあちゃんというのが赤ちゃんの渾名だと理解する。
咳き込んでというところに、俺が感じた息苦しさを思い出させられた。
「ご迷惑だと、思って、本当は挨拶だけにしようと…すみません」
「いいえ。縋りたくなる気持ちは、わかります」
「どう、すれば……」
「私は、霊能者ではないんです。すみません。見えてしまった不運なサラリーマンです」
「…そんな。では……」
黒い靄が、奥さんに群がるように見える。奥さんの体がぴくりと震えた。
「でも、本物の方にアドバイスは貰いました」
「え?」
「私にご主人に気をつけるようにと教えてくださった方です」
「うちのに、ですか」
「はい。私も漠然とですが、この黒い靄が、あの人を恨んでいるのを感じていました」
「……表裏の激しい人だと、結婚して割と早くに気づいていました」
「失礼ですが、女性関係も相当…乱れていたのでは?」
「遅く帰る事も…」
「詮索でした。許してください。その先はいわなくてもいいです。
アドバイスですが、明るくいこう、です」
「明るく? そんな、主人が意味深な死に方をして、まあちゃんもいなくなって」
ここでふと直感的に間違っていた事に気がついた。
彼女はすでに生きる希望を失っている。遠からずあの黒い靄に取り殺されるように思えた。
本当に良いんだろうか。悩んだ末に口を開いた。まとわりつく黒い靄が見える。
「まあちゃんは、生きて、今も、あなたを守ってます」
「え?」
「私がさっき泣いたのは、あなたの胸にすがる赤ちゃんが、気づいてもらえず、抱いてもらえず、呼んでもらえない悲しみに…
でも、今、私の目には、黒い靄に叩かれて、蹴られて、それでも奥さんの胸にすがりついている光景が見えるんです。
この子が、健在なうちは、奥さん、大丈夫です。彼は、ママが大好きなあなたの守護霊なんですよ」
奥さんの両目に大粒の涙が浮かんだ。
黒い靄が、わっとひるんだように遠ざかった。
「いるんですか?ここに」
彼女はふくよかな胸元を自らの手でおさえて、歓喜のあまりに滑舌も悪く、ほとほとと涙を顎から滴らせた。
見ているものを、前向きな解釈で述べたまでだ。赤ん坊は、今も、ただ寂しがっている。その感情がたたきつけられてくる。
でも、俺に救うことができるのは、生きている人間だけだ。
赤ん坊に語り聞かせることなんて、俺には無理だ。
「見えませんか」
「見えません。でも、いるんですね。だから、あなたは泣いた」
「はい」
「ああ。まあちゃん。まあちゃん」
赤ん坊の幽体が膨らんだようにみえた。いや、膨らんでるのではない。
まあちゃん、いるのね?ママよと呼ばれる旅に、白さが増していく。黒い靄が一斉に奥さんの顔めがけて殺到した。
赤ちゃんの光がはじけた。黒い靄の一体が俺の顔面めがけてすっとんできて、俺の息子がちょっとだけ汗をほとばしらせた。
「あら?…黒い、靄が…一瞬見えたような」
「………………………トイレ、借りてよろしいですか」
「何か、ご覧にでも?」
「その件は後ほど」
トイレをかりて、カバンの中の真新しい下着に着替えた。あやういところでスラックスにはしみずにすんでいた。
営業にいくもの、常に清潔な下着を持ち歩くべしだ。
おかげで大のおとなにもなっておばけみてしょんべんちびったことがバレずに済んだ。
トイレから出てきたときには、奥さんは落ち着きを完全に取り戻していた。
黒いのがいると気づいてからたちっぱなしだった鳥肌もおさまっていた。
墓前に向かって、手をあわせていて、真新しい線香の臭いが鼻をくすぐった。
「…今、凄く晴やかな気分です」
そういえば、まーちゃんの幽霊はどこだと部屋の中を見渡した。
そして、見てしまった。
墓前に向かう、母のその膝の上、かそけく消えかかった白い光が、爆ぜて消えた。もう無理だ。
あかちゃんは最後まで、母親のふくよかな胸に手をのばそうとしていた。俺はもう涙腺様をどうこうすることを諦めた。涙より先に鼻水が垂れた。
黒い靄も、赤ん坊の幽霊も最初からいなかったように、安穏とした空気が漂っている。
たんなるサラリーマンに何があったかなんてわからない。
見たまま、まさしく魂を萌え散らせて母を守った光景にしかみえなかった。
大好き、という思いが俺の心にこみ上げた。同調したのだと気づいた。
目の前の奥さんが、奥さん?違う、まま、大好き。皮膚の感覚が失せていった。
俺の体が勝手に動く。そして奥さんに背後から抱きついた。
「あんまぁ。あんま…あまー。どぅふふふふふ」
俺の口から出た言葉が、信じられないような音色で、本物の赤ん坊の声にドスきかせたようなものだった。
体の自由を取り戻すなり、押し倒してしまった奥さんに頭を下げて、飛び退いた。
「え?あんまって…」
「…す、すみません!すみません!こんなことするつもりじゃなかったんです!信じてください」
「おちついてください。あんまって、何故ご存知なんですか?」
「へ?いや、の、乗り移られたみたいで」
消える瞬間に同調したなんて、言えない。言いたくない。やっと前向きになった女性に涙は似合わない。
「…では、今はあなたのなかにまあちゃんが?」
「あ、え…」言えないんだよド畜生!
「おいでまあちゃん」
奥さんが胸のボタンを一つ一つはずして、ブラをずらしおっぱいを露出させた。
俺は、薄茶色の先端をぼけっとながめながら、股間が盛り上がっていくのを感じた。
俺の野獣が目覚めてしまいそうだ。目覚めたい。目覚めたいけどそりゃいかんだろう。
「あ…いや……いや。もう、そちらに戻っていらっしゃいますよ」
まあ、ちゃんと機能するのね、我が息子。そんなダジャレで息子の沈静化を測った。
青くなったり赤くなったりしてたとおもう。
「ぷっ」奥さんが吹き出した。奥さんの目線が股間に向かっていたことは気づかなかった方が幸せだった。
「いるって嘘をついてしったほうが、良かったのではないですか?」
「うーその手もあったか」嘘とうーそをかけて、息子よ静まれと只管念じた。弱みにつけこむようなクズにはなりたくない。
「くすくすくす。笑わせて元気にさせようと?」
「あのアドバイスくれた人。師匠がですね。ゲイ人だったもので」
未亡人に俺は俺にアドバイスをくれた人が、男色家、ゲイだといっていたと告げた。
彼女はお腹を抱えて笑った。
彼女はおっぱいをしまおうとはしなかった。俺に向けられている目が、好意に満ちていた。勘違いではなさそうだった。
得体のしれない亭主の過去。裏表のある男の影。対照的に、俺は、裏表はあんまないと思う。ただし自覚ありで開き直ってる変人だけど。
一人寝の寂しい一夜を共にする相手として合格とみられたのだと、頭では理解していた。だからこそ我慢した。
収入もさほど多くもなく、会社もけして安泰ではない。ただ偶然で出会ったというだけで、享受していいほど、彼女は安くない様に見えた。
俺は、すぐさま荷物をまとめた。そして、その時がきた。
玄関まで送ってもらったところで彼女がいった。
「あ、そういえばまだお名前をうかがっていませんでした」
「……セザァー√ル!」
昔大好きだったCMのものまねを大音声ではりあげて、後ろは振り返らずに歩んだ。
後ろで、くすくす笑う声が聞こえていた。満足だ。
かくして、俺の生涯ではじめての経験は終わった。
俺は、子供の霊と波長があうようになってしまって、今もよく見る。
とはいっても、霊は消えるものらしいので、そう頻繁に出くわすわけでもない。
ただ、見えるときは決まって、かなり感応してしまって、好意的にせよそうでないにせよこっぱずかしい目にあう。
嬉し恥ずかし初体験よりはすこしマシに対応できるようになってきたけど。
パンツの替えは欠かせません。
□ □ □
二人もリクエストがあっちゃ、見過ごすのもあれなので簡単に。
セザールさんが普通の生活に戻って二ヶ月程してだな。
深酒してふらふらになりながら、八坂の改札を出た時にだ。
「こんばんは、セザールさん」という声が聞こえた。
セザール?ってかんじで改札周辺でたむろしてる人が
ちらちらこっちを見ているのが分かって、そういえばセザールなんて名乗ったこともあったなあ。
……あれ?それって…。
振り向いてみると、なんとも朗らかな、影のない表情をした、未亡人がいた。
セザールさんは、本当にバカでな。最寄り駅を教えてしまっていたこと、その時まで失念していた。
さすがに、二ヶ月も経ってやってきた意味は分かったよ。吊り橋効果ではなさそうだ、と。
挨拶を済ませた途端、彼女が横に寄り添ってきて、腕を絡めてきた。
肘が、肘がなんかやらかいものに触れとる。酔いが一気に醒めた。
野獣のくせに、結構堅物だと自認していたんだけど。まあ、風俗すらいかずにCherry君だったからね。
それに比べ、俺なんかよか、よっぽど彼女のほうが野獣だった。
初体験はもう、犯されたっていってもいいくらい、凄い誘惑攻勢から…そうなった。
恋人として一年近くつきあって、ある日、彼女が俺の室内を見渡して言った。
「荷物が少なくて楽そうだわ」と。
そんなわけで、多摩湖まで徒歩五分程度の、広い家が今の住処。
□ □ □
俺はあんまり長く生きられないことに、彼女との再会後に気がついた。
アドバイスは2つあったんだよな。すっかり忘れてたよ。
明るくしてりゃ、大丈夫。そして、受け入れちゃいけない。
同調っていう言葉でごまかして、やっちゃってたんだ。気づいた時には手遅れだった。
ロストチェリーした夜、すやすや寝入ってる彼女を見つめながら、甘酸っぱい想いに寝付けずにいた。
人生はじめての春が名残惜しかったのかもしれん。
翌日仕事なのにと思いながら、相手が寝てる分素直になれて、頬に口付けとかしたっけな。
お母さん、取っちゃってごめんなっていう気持ちになって、意識がそちら側に傾いた。
最近わかったんだけど、俺は周波数を変えるダイヤルを回すみたいにして、無意識に見る見ないをコントロールしてるらしい。
そして、見えたんだ。俺の胸のあたりに、半分体埋まってる赤ちゃんがいて、なんだか笑っている様子。
憑かれるっていうのは、本当に疲れる。けれど、悪いものでないだけに、どうしようという気も起きない。
それどころか、この子もまた、被害者であるわけで。せっかく拾った健在を、俺がどうこうするのは、いくらなんでも、なあ。
思い出したよ、はっきりと。あの師匠のこと。
彼がなんで下手なジョークを交えてまで逃げたか、今は断言できる。
赤ちゃんの前ではだらしなく笑ってたいた。奥さんのことも、凄く好感をおぼえていた様子だった。
肩一発叩いただけで、俺を一時なりとも助けてくれた御人だ、力のある方だったんだと思う。
それでも、彼が、敢えて俺たちを見捨てたのは、彼自身、この赤ちゃんを受け入れてしまう性格をしていたからさ。
受け入れてしまったら、追い出す気にもなれないんだと、彼は自覚があったんだろうな。
「優しい人」っていう彼の言葉が思い出されて、耳が痛い。
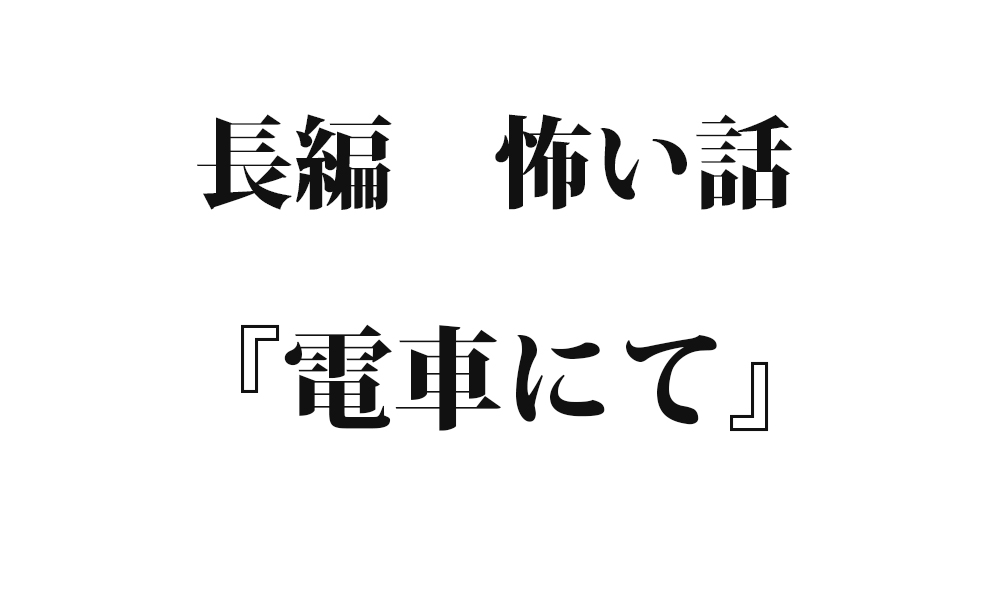
コメント