地方の小さな町
俺は、あるデパートのバイヤーをしているのだが、ある日、買いつけの契約のためにとある地方の小さな町を訪れた。
駅員が一人でやっているJRの小さな駅を降りると、駅前は見るからにうらぶれた、死に行く街という風情だった。
小さな、申し訳程度のロータリーとバス停、端に客待ち顔の運転手のタクシーが1台。
商店街と言えるようなものはなく、小さな喫茶店とラーメン屋、薄汚れた洋品店に美容院という、まあ日本全国どこにでもありそうな小さな街である。
驚いたのは、こんなところにもコンビニがあることだった。
契約をする農家までタクシーに乗っていく。
仕事自体は単に契約するだけなのだが、ここに来るまでに一日の大半を使ってしまったために、今日はここで一泊しなければならない。
駅前に戻ると、すでに最終列車は出てしまった後だった。タクシーで隣町まで行くと、軽く1日の出張費を超えてしまう。
仕方なく、コンビニの店員に聞いて、この街で1軒だけ営業しているという民宿まで歩いて行くことにした。
昔は街道筋の中継点でもあったこともあるらしく、民宿は思ったよりしっかりした造りだった。
ただ、客はあまりいないらしく、私の他は長期逗留している50歳くらいの男性が一人、とのことだった。
着いたのが遅かったため、今日の夕食はもう終わってしまったとのことだったのだが、気の毒に思ったのか女将が、近くの定食屋の地図を書いてくれた。
そこならまだ食事できるはずだ、と…
教えてくれた女将が、すこしためらい気味に地図を渡してくれたのが気にはなったが、空腹には勝てず、今夜はそこで遅めの夕食をとることにした。
ビールくらいはあるだろう…と思い、歩いて店に行くことにした。
5分ほど歩くと、それらしい店に着いた。
もう何年も客が来ていないかのようなうらぶれた雰囲気に、少し気後れしたものの、ここまで来てコンビニの弁当は食べたくない。
第一、コンビニはここからかなり遠い。まあ、死ぬようなことはないだろうと思い、覚悟を決めて店のがたつく扉を開けて中に入った。
そのときには、まさかこんなことになるとは想像もしていなかったのだった…
店に入った瞬間、生暖かい風が体の横を通り抜けていったような感覚があり、その直後に背筋に「ざわっ…」という悪寒が走った。
嫌な予感がしたが、店自体は割とどこにでもある古ぼけた定食屋という感じだった。
薄暗い店内は、人の気配がしない。もう終わったのかと思ったのだが、外に暖簾がかけたままであることを考えると、聞いてみるくらいならいいだろう。
「すみません…」
厨房に誰かいないかと呼んでみたところ、奥から年の頃70歳くらいの老婆がゆっくりと無言で出てきた。
「まだ、食事できますか…?」
そう尋ねると老婆は、黙って頷いて店内に2つあるテーブルのひとつを指差した。座れ、ということらしい。
どうやら何か食べさせてくれるようだ。薄気味悪い感じはしたものの、空腹には勝てない。
どうせ明日には出て行くんだし、帰ってから話の種にもなるし…と思い、促されたテーブルに座り、気を取りなおして壁のメニューを眺めてみた。
メニューそのものは、よくある定食屋のそれだ。
和洋中華、ひととおり揃ってはいるが、店も店だしあまり当たり外れの無さそうなものにしておいた方がよさそうだ。
結局、野菜炒め定食とビールを注文した。場所柄、野菜は新鮮なものが揃っているだろうと思ったからだ。
老婆が、分速10mくらいの動きでビールとグラスを持ってきてくれた。
やれやれ、この調子だと少し待たされるかもしれないな…と思いつつ、先ほどの妙な予感も忘れ、グラスにビールを注いだ。
間が持たないので、もうひとつのテーブルに置いてあった新聞を読ませてもらうことにした。
「あれ…?」
記事を読みながら、妙な感覚に囚われる。変だな…。今になって思うのだが、この時が最後のチャンスだったのだ。
あの時、この感覚の理由をもっと考えておけばよかったのだ…
仕事柄、新聞は毎日読んでいる。
今日の朝刊も、ここへ来る列車の中で読んでしまっていたので、あまり目新しさはないと思ったのだが、記事には見覚えの無いものが多かった。
版が新しいか、地方版だからだろうくらいにしか思わなかったのだが・・・
今日の仕事がうまくいったのと、ビールの酔いがほどよく回ってきた頃、老婆が食事を持ってきてくれた。
あまり期待していなかったのだが、さすがに産地だけのことはあり、食事はうまいものだった。俺は、今日の仕事の成功を確信した。
もうそろそろ宿に帰ろうと思い、老婆に代金を支払って出ようとしたところで、初めて老婆が口を開いた。
「出口はこちら…そっちはもう出られないからね…」
おや…と思った。少なくとも俺が入ってから、あの扉に鍵をかけたり、誰かが入ったりした覚えはなかったのだが…。
まあ、郷に入れば郷に従えというし、言われたとおりにしておいたほうがいいだろう。
厨房を通って、裏の通用門から外に出る。出るときに老婆が、
「またね…」
と意味深な表情でつぶやいた。もうここに来ることはないのだが、俺も
「ああ、また来るよ」
と返事をして店を出た。
最後に老婆は、俺を哀れむような、懐かしむような複雑な表情をしたように思えたが、まあ皺の具合なのだろう。
外は風が生暖かく、今夜は冷房を入れないと寝苦しそうだな…と思いながら宿への道を戻った。
宿へ戻る道は、何か懐かしい風景で溢れていた。
漆喰の壁に木製の電信柱、時代遅れの自動車…まあ、時間の流れから置き去りにされたような地方の小さな町とはこういうものなのだろう。
宿に着くと、女将が出迎えてくれた。もう遅い時間なのだが、待っていてくれたようだ。
「お風呂、まだ沸いてますから…」
そう言った女将の顔をふと見ると、出るときよりも心なしか若返っているような気がした。
こんな大きな娘がいるようには見えなかったが…まあ、酔いのせいなのだろう。
ゆっくりと湯船につかり、明日以降の仕事のことを考えてみる。
明日は帰るだけで時間の大半を遣ってしまうだろうから、社に顔を出して上司に報告…明後日以降、別の取引先に出かけ…などと考えているうちに、
どうやら眠り込んでしまったらしい。気がつくと、部屋の布団の上に寝かされていた。
「あら、気がつきました…?」
女将と、宿の番頭が心配そうに覗き込んでいる。どうやら湯あたりしたらしい。
「お疲れでしたのね。お仕事、大変なんでしょう?せっかくですから、ゆっくりしていってください…」
そう言って女将は、にっこりと笑って出て行った。なんだか、
ずっとここに居たいような、そんな気分になってきた。
いつのまにか眠り込んでいたらしく、気がついたら翌朝になっていた。
社に連絡を入れてから帰ろう、と思って携帯をかけてみたが、通じない。
まあ、今日は直帰してもいいとの指示を受けていたから、連絡はいいだろう。
緊急の用なら連絡があるだろうし…
帰り支度をして、フロントへ行くと女将がなにやら帳簿をつけていた。俺に気づくと、にっこりと笑った。
やはり、若くなっているようだ。惚れたかな…などと考えながら、代金を支払い、タクシーを呼んで貰った。
「またいつでもどうぞ…お待ちしてますから」
別れ際に女将はそう言って、親しみのある表情で送ってくれた。
もしかして、俺に気があるのかな…などと考えながら、運転手に「駅前まで」と告げると、黙って車を走らせる。
仕事以外でここに来るのも悪くない…などと妄想にふけっていると、ミラーから運転手の視線を感じた。
にやけてるのを見られただろうか…咳払いをしてごまかした。
ほどなく、見覚えのある駅前のロータリーに着いた。代金を払って、車を降りる。
次の電車の発射時刻を見ようと思い、駅に向かったがなにやら様子がおかしい。人の気配がしないのだ。
ストか…?まさかそんな…と思って駅舎に行くが、どうやらそういうものではないらしい。
改札も封鎖されて何年も経っているような寂れ方だ。周りを見渡しても、通行人も見当たらない。まるで、ゴーストタウンだ…
とにかく、調べなくては…と思い、喫茶店に入ってカウンターに座る。とりあえずコーヒーを注文して、マスターにそれとなく聞いてみる。
「ねえ、今ストでもやってんの…?」
マスターは一瞬、ぴくっと肩のあたりがこわばったが、ゆっくりと、自分に言い聞かせるように答えてくれた。
「ああ、あの駅はもう、だいぶ前に廃線になってから使われてないんですよ…」
???俺は確かに、昨日あの路線の電車に乗ってここまで来たのだが…
どういうことなんだ?
マスターは目をそらしたまま、一心にグラスを磨いている。しかし、意識はこちらに集中させているのがありありとわかる。
これは、何か知ってるな…そして、聞いても答えてくれないだろう。そう思った俺は、あきらめて店を出ようとした。
コーヒー代を受け取ったマスターは、最後にぽつりと、
「ここも慣れるといいところですよ」
と言い、ぎこちなく笑った。俺は無言で店を出た。
とにかく、会社に連絡を入れなければ…と思い、公衆電話を探すが、一向に見当たらない。
コンビニに行けばあるだろうと思い、昨日の場所へ行ってみると、そこはただの民家が建っている。
何だ…いったいどうなってるんだ……
今俺は、ここへ来るときに契約した農家で働いている。うまい野菜を作っているのだ。
農家では、同じようにここへ迷い込んで出られなくなった男たちが働いている。
彼ら…いや、俺たちが、毎日丹精こめて育てているからここの野菜はうまいのだ。
俺は、民宿の女将と一緒になり、民宿の空いている部屋に長期逗留している。
そう、ここへ来たときに俺が見た50歳くらいの男は…
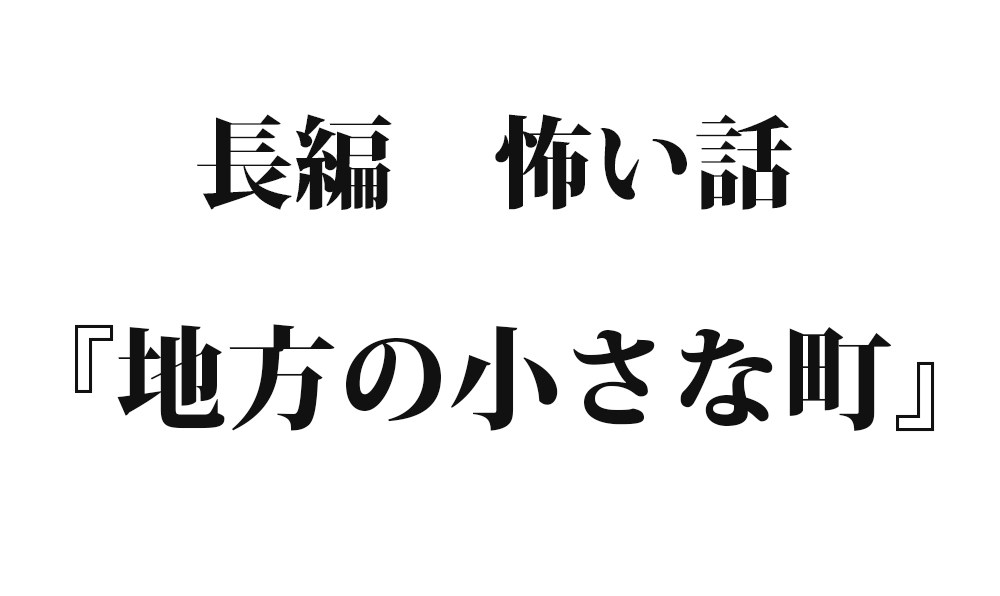
コメント