母親の泣ける話 – 感動エピソード【10】
ぼくがいるよ
※第5回日本語大賞 小学生の部で文部科学大臣賞を受賞した小学校4年生の男の子が書いた作文です。
お母さんが帰ってくる!
一ヶ月近く入院生活を送っていたお母さんが戻ってくる。
お母さんが退院する日、ぼくは友だちと遊ぶ約束もせず、寄り道もしないでいちもくさんに帰宅した。
久しぶりに会うお母さんとたくさん話がしたかった。
話したいことはたくさんあるんだ。
帰宅すると、台所から香ばしいにおいがしてきた。
ぼくの大好きなホットケーキのはちみつがけだ。
台所にはお母さんが立っていた。
少しやせたようだけど、思ったよりも元気そうでぼくはとりあえず安心した。
「おかえり」いつものお母さんの声がその日だけは特別に聞こえた。
そして、はちみつがたっぷりかかったホットケーキがとてもおいしかった。
お母さんが入院する前と同じ日常が僕の家庭にもどってきた。
お母さんの様子が以前とちがうことに気が付いたのはそれから数日経ってからのことだ。
みそ汁の味が急にこくなったり、そうでなかったりしたので、ぼくは何気なく
「なんだか最近、みそ汁の味がヘン。」
と言ってしまった。
すると、お母さんはとても困った顔をした。
「実はね、手術をしてから味と匂いが全くないの。だから料理の味付けがてきとうになっちゃって……」
お母さんは深いため息をついた。
そう言われてみると最近のお母さんはあまり食事をしなくなった。
作るおかずも特別な味付けが必要ないものばかりだ。
しだいにお母さんの手作りの料理が姿を消していった。
かわりに近くのスーパーのお惣菜が食卓に並ぶようになった。
そんな状況を見てぼくは一つの提案を思いついた。
ぼくは料理が出来ないけれどお母さんの味は覚えている。
だから、料理はお母さんがして味付けはぼくがする。
共同で料理を作ることを思いついた。
「ぼくが味付けをするから、一緒に料理を作ろうよ。」
ぼくからの提案にお母さんは少しおどろいていたけど、すぐに賛成してくれた。
「では、ぶりの照り焼きに挑戦してみようか」
お母さんが言った。
ぶりの照り焼きは家族の好物だ。
フライパンで川がパリッとするまでぶりを焼く。
その後、レシピ通りに作ったタレを混ぜる。
そこまではお母さんの仕事。
タレを煮詰めて家族が好きな味に仕上げるのがぼくの仕事。
だいぶ照りが出てきたところでタレの味を確かめる。
「いつもの味だ。」
ぼくがそう言うと久しぶりにお母さんに笑顔が戻った。
その日からお母さんとぼくの共同作業が始まった。
お父さんも時々加わった。
ぼくは朝、一時間早起きをして一緒に料理を作るようになった。
お母さんは家族をあまり頼りにしないで一人でなんでもやってしまう。
でもね、お母さん、ぼくがいるよ。
ぼくはお母さんが思っているよりもずっとしっかりしている。
だから、ぼくにもっと頼ってもいいよ。
ぼくがいるよ。
いつか、お母さんの病気が治ることを祈りながら心のなかでそうくり返した。
沢山食べなさい
俺は小学生の頃に母の作った炊き込みご飯が大好物だった。
特にそれを口に出して言った事は無かったけど母は判っていて
誕生日や何かの記念日には我が家の夕食は必ず炊き込みご飯だった。
高校生位になるとさすがに「又かよっ!」と思う様になっていたのだが
家を離れるようになっても、たまに実家に帰ると待っていたのは母の
「炊き込みご飯作ったよ。沢山食べなさい」の言葉だった・・・
会社に電話が来て慌てて向かった病室には既に近くの親戚が集まっていた。
モルヒネを打たれ意識の無い母の手を握り締めると母の口が動いた。
何かを俺に言いたそうだった。母の口元に耳を近づけると
「炊きこ・・・たよ。たくさ・・・・さい」と消え入りそうな声で言っていた。
それが最後の言葉だった。
「ママの作ったスパゲッティー大好き!」口の周りを赤くして
スパゲッティーを食べる娘とそれを幸せそうな目で見つめる妻を見る度に
母の炊き込みご飯が食べたくなる
最後まで
亡くなる前の1週間前の話です。
僕は結婚して子供、妻を連れて帰郷し、病院に母の看病に行っていました。
その頃すでに母は、食べ物を食べては吐き、1日に口にできるものはスプーン一杯のアイスクリームだけでした。
夜7時、夕食が運ばれてきました。
母はそれに気づかず、つらそうに眠っていました。
そして午後8時になって、食器を片付ける音が聞こえてきたので、僕は母をそっと起こし、少しでもいいから食べて寝るよう勧めました。
母は、ゆっくり起き上がると、茶碗を手に持って、目をぎゅっとつむって、おかゆをかきこみ初めました。
僕が、「そんなに急いで食べたら、また吐いちゃうからゆっくり食べて」というと、母は僕にこういいました。
「だって、自分が早く食べて、栄一を家に帰してやらなきゃあ、家で待ってる美枝子や孫がかわいそうだ。」
それを聞いて、僕は頭が真っ白になりました。
病室では泣けず、母を寝かせて病院の駐車場の車のなかで声を上げて泣きました。
母は最後まで、そういう母でした。
大丈夫だからね
抗がん剤も効果なく「これ以上の治療は、ただ体力を削るだけだ」と医者から宣告され、 予後をただ穏やかに過ごすために、母は私の働く病院に入院しました。
夜勤に入る前に早めに行って、いつも通り話をしてると、 「あんたがいてくれて良かった」て急に言われた。
徐々に弱って、胸水が溜まり始めてたから
「ちょ、やめて!フラグ立てないで!」って、ちらっと思ったんだ。
まあ、でも、またとりとめのない話を続けてる内に不安を忘れ、いつも通り夜勤も終了。
仕事が終わった途端、急に母が苦しみだした。
職業柄、その先が見えた。
ああ、ついにきた…。
覚悟は決めてた。
いずれ、こうなることもわかってた。
「どうにかして・・・」
すがるように母が私を見た。
不安にさせないように笑顔で居ることが私の役割。
いつも通り「大丈夫」って擦ってあげればよかった。
でも、私は動くことができず、なんとか笑おうとしても、どうしても顔が引きつってしまい、涙がこぼれた。
「やばい!泣いたらだめだ。」
慌てて、母から顔を逸らす。
いたたまれなくなり、背中を向けようとしたとき、ぐっと手首を掴まれて引き戻された。
「大丈夫、大丈夫だからね。」
目の焦点さえも、私にあわせられていないのに。
手首を掴む手も、力強い声も、昔の強いお母さんでした。
それ以降、母は苦しいとも辛いとも言わずに、2時間後に亡くなりました。
「大丈夫。」
それは私が言ってあげなければならない言葉だったのに。
私は看護師失格で、母から「キツイ」「苦しい」の言葉を奪ってしまった。
でも最後に子供でいられた。
どんなに子供が大人になろうとも、経験を積んで立派になろうとも、母親には敵わないと思った。
バカなことしちゃいけない
私は今、15歳です。
中学校を卒業し、高校も決まりました。
そんな私が、中学時代に体験した話です。
私はクラスで軽いいじめにあっていました。
誰が助けてくれることもなく、ただただ悪口を言われ、無視をされる。
そういう『いじめ』でした。
そんな私は、今日も1人‥
クラスにいても誰とも話さない。
それが当たり前になってきた頃でした。
私は、日記をつけ始めたんです。
人を傷つけないように、日記に書いてストレスを発散しようと考えました。
1日目
「今日は無視された。辛い辛い辛い。どうして私なの?助けて、助けて。幸せになりたい。」
2日目
「今日もやっぱり無視された。辛いよ。私がいなくなればいいのかな?」
3日目
「もう辛いよ。疲れちゃった‥。こんなになるなら死にたい。私なんて要らないでしょ?必要ないでしょ?」
こんなことばっかり書いていました。
それでも辛い時は、1人で泣いていました。
そんな時、日記が母にバレてしまいました。
昔、『私の母は子供が出来ない』と言われていたそうです。
『それでもいいよ』と父が言い、結婚したと聞きました。
そんな時、母が言ったんです。
「子供ができないって言われた時、凄い悲しかった。
でも、あなたがお腹にできた時、こんなにも幸せな事無いってぐらい嬉しかったの。
なのに、お腹を痛めて産んだのに、どうして『死にたい』なんて言うの?」
それを聞いた時、私は泣いてしましました。
「何があってもお母さんはあなたの味方。
あなたがどんなことをしたって、嫌いになることはないし、責めることもないのよ。
私の娘は、あなただけだもの。」
そう笑顔で言ってくれたんです。
『その時、こんなに愛されてるんだ。』
『私は生きてるだけで、ここにいるだけで幸せなんだ』
って、思えました。
もし、あなたに何かあったとしても『死にたい』なんて言わないでください。
少しでも両親の気持ちになって考えれば、『バカなことしちゃいけない』って、思えるはずです。
お母さん。
心配かけてごめんね。
そして、ありがとう。
いつまでたっても忘れることのない出来事です。
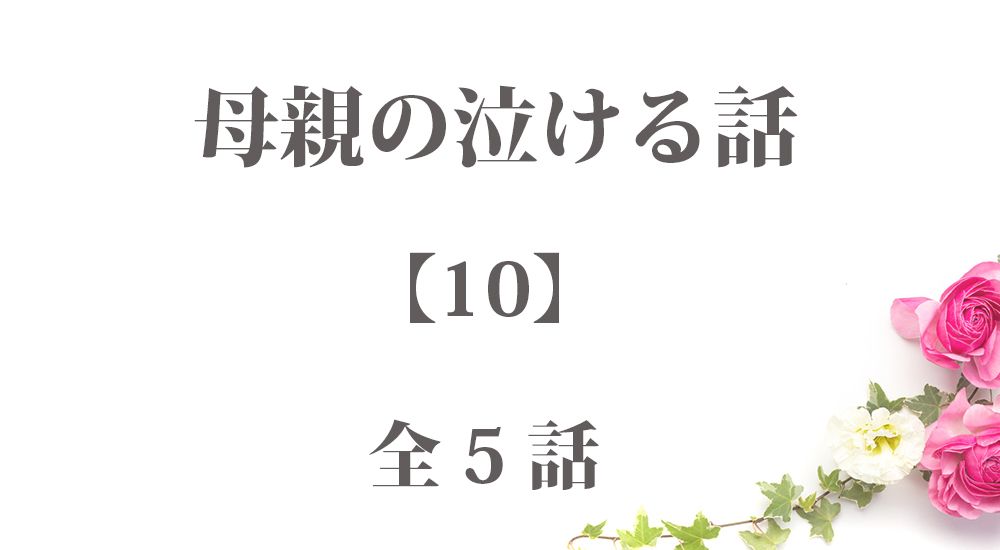
コメント