なりすまし
小学2年になって引っ越すまで住んでいた家について、いろいろと不思議な体験がある。
片田舎というほどでもなくそこそこ拓けた新興住宅地の片隅にある賃貸の平家だった。
一年中じめじめとした、いつも陰影をまとったような情景が思い浮かぶ。
背の高い土蔵のような隣家に挟まれ、庭にひしめくように植えてあるビワの木のせいで
日中も陽が当たらない。
「もともとあそこは田んぼだった」という母の言葉を後年聞いて、なるほどと思ったものだ。
床板や柱はどれも黒ずみ朽ちやすく、そしてどこからともなくカビのような臭いが漂う、そんな家だった。
記憶が定かではないが小学生に上がる前の年、夏の夕方ことだった。
その日は昼前から新興住宅の区画に住んでいる友達Yちゃんの家で遊び、夕飯前にという親の言いつけを
忠実に守って帰宅したところで母が呆れたように言う。
「あんた、また遊びに行ってたの?」
「ううん、ずっとYんとこにいってた」
また、といわれて不思議だった。母は弟と一緒に午後から出かけていたという。
帰宅して母の友人から電話があった際に、電話に出たのが私だというのだ。
私が一度家に帰ってきて電話を取ったと思ったらしい。
「おかしいねぇ…だれが電話でたのかね」奇妙な出来事ではあったが、その話題はそれでおしまいだった。
数日後、また同じような出来事があった。
今度は家族全員で外出していた。翌日、前回と同じ母の友人がまたこんなことをいった。
「N君(私)が留守番してて、みんないませんって」
「そのおばちゃん、適当なこといってるんじゃないか?」父は母の友人が嘘をついているではないかと
冗談まじりに言ったが、その友人と長い付き合いである母は釈然としなかった。
「でも…いろいろNと話したっていうのよ」電話に出たという私は、近所の友達のことや飼い猫のことを
ハキハキと答えたらしい。それらは母が友人に話したこともない具体的なもので、とても作り話とは思えなかったという。
私はそんな両親の話に聞き耳をたてながら、玄関の黒電話を横目で見ていた。もうひとりの自分らしき子供が薄暗いそこで、
電話に向かっているたたずんでいる空想が、ひどく気分を悪くさせた。
「そう、あとこんなことも言ってたの、電話の向こうがすごいガヤガヤしてて、テレビの音を下げてほしいって何度もNに言ったって…」
「テレビって…聞こえるか?」父は首を傾げていた。
狭い平屋とはいえ、テレビのある六畳の居間と電話は対角線の端と端というほど離れていた。壁まで挟んでいて、
通話に差し障るほど聞こえるというのは考えにくい。
そして3週間ほどの間にこの出来事はもう一度あった。
その時は父の会社の人間からであり、母の友人の嘘という疑惑は自動的に消えた。この家に来てからというもの、
こうした奇妙な出来事はこれが初めてではなく、両親もこの話題を避けるようになった。まだ小さい弟の世話に
忙殺されてそれどころではなかったように思う。
とはいえ、この家でひとり留守番することへの嫌悪感は次第に募っていき、母が外出する時はなるべく家に寄りつかないようにしていた。新築のYちゃんの家はあの粘りつくような臭いや湿気とは無縁で、よく避難場所として長居していた。
二人でいつものように遊んでいると、Yちゃんがポツリと言った。
「Nちゃん、昨日、家いた?」
「ううん、ずーっといんかった」
「昨日さ、カブ取り行こうとおもってママに電話してもらったら、Nちゃんいるって、ママにわたされた」
「そんで…?」超合金ロボを持つ手が、止まった。
「…Nちゃんじゃないのがでた。へんな声、うしろウーウー言ってて聞こえにくかった」
ぞくりとして、一瞬にして体中の毛穴が広がっていく。Yちゃんがなにを話したのか気になって、
絞り出すような声で先をうながした。
「Nちゃん…出してくださっ…いっ…ていった」
「……」
Yちゃんの言葉に嗚咽がまじりだした。見れば大きく口をあけて上を向き、顔を歪ませながらポロポロと涙が頬を伝っていく。
「…ぼくのなまえよんで、みんな…であそぼっていって・・笑って、たくさんになって、きれた……」
いつのまにか、あの粘り気がこの家にまで忍び込んでいるような気がした。その後Yちゃんは大泣きし、
私もうつむいたまま泣き出していた。そして互いにようやく落ち着いて、その後の話をしてくれた。
電話が切れた後、心配になったYちゃんは急いで私の家に来てくれたという。
あの赤く染まった夕暮れをぽっかり切り抜いたような黒い家。インターホンを2回押し、ドアの前に立ったときに
足が震えて急な吐き気におそわれたということだった。
ああ、家に着いたときに門の脇にあったのゲボはそれだったのかな?…あとおかしなことといえば、
掛けて出たはずの家の鍵が開いていて、お母さんが不思議がっていたっけな…
蝉の声を遠くに聞きながら、怖さよりもなにか途方もない無力感のなかで、そんなことを繰り返し考えていた。
その夏の終わりにかけて、Yちゃんはリンゴ病に発症したとのことで、まったく会えなくなった。
そしてそのまま私の前から消えるように新築の家と父親だけ残して母子は引っ越してしまった。
不思議と、「私らしき誰か」の留守番現象を聞くことはなくなっていた。終息したのか、
それとも親の気遣いで私にまったく伝えなかったのかはわからない。
ひょっとしたらYはあの時、ドアを開けてしまったんじゃないだろうか…?
夏、あの泣き顔が記憶の片隅からよみがえった時にふと、そんなふうに思うことがある。
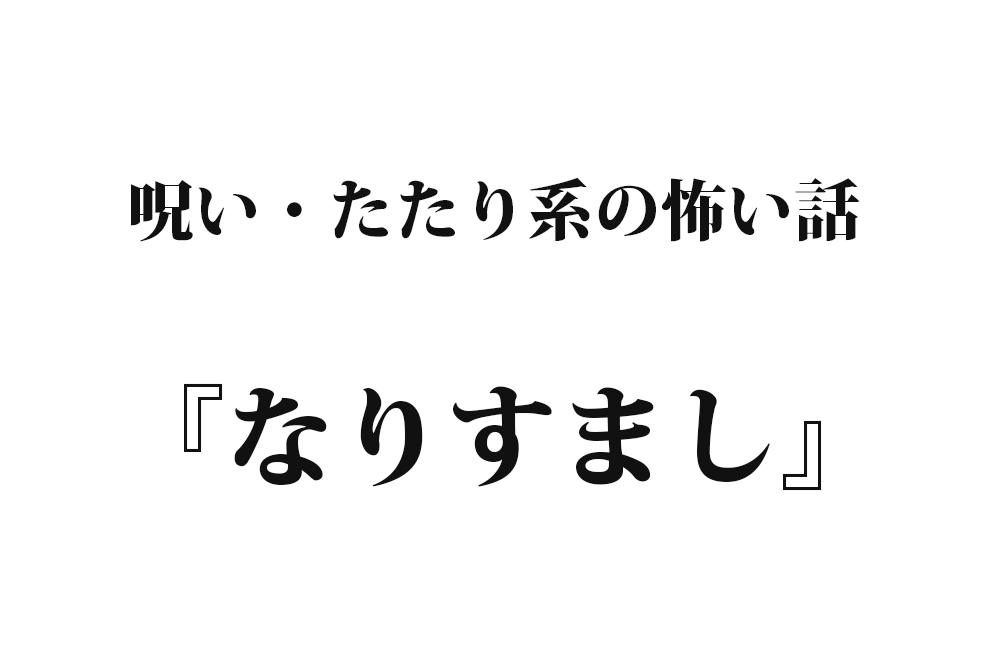
コメント