向こう側の少女
一年の秋。
その頃俺は遅刻を罪と思っていなかった。
別に出席時数だけ取れていればいいので困ることは無かったが、一時期頻繁に遅刻をかましていた。
原因はネットにハマったことなのだが、俺はそれをちょっとかっこいいと思っていた。
あー全然寝てねーわー、だとか、ちょっと自慢げに言っていたような気がする。
我ながらとんでもなく馬鹿だと思うが、とにかく一ヶ月ほど殆ど毎日遅刻していたのだ。
大体一時間目をスルーして登校していたのだが、ある日ふと気付く。
同じ時間に登校している女の子がいたのだ。
いつも彼女は徒歩で、俺は自転車だったから、いつも追い抜いていた。
白くて、細くて、なんというか、病院の窓から葉が落ちるのを眺めていそうな、そんな女の子だった。
女の子というが、恐らく年上だった。
彼女は同級生にいなかったから、多分先輩なんだろう。
鮮明に覚えている。
押せば倒れそうな後ろ姿も、ポニーテールにしていた黒い髪も、すれ違う寸前見た白いうなじも。
追い抜いてから振り向いたことは無かったから、どんな顔をしていたのかはわからない。
ただ、なんとなく綺麗な顔をしているように思っていた。
ある日、俺はまた遅刻した。
いつものように自転車を走らせていると、あの人が逆側の歩道にいた。
いつもと違う。
俺は少しがっかりした。
今日は彼女の後姿を見ることが出来ない。
俺は気になって仕方なかった。
仕方なかったから、ついやってしまったのだ。
俺は彼女を通り過ぎて、すぐ振り向いた。
俺は彼女の顔が見たかった。
俺の想像の中にいる、綺麗な顔と一致しているか確かめたくて。
しかし、振り向いた先には、誰もいなかった。
□ □ □
「見たことありませんか。その人。一年じゃないみたいなんですけど」
放課後、俺は先輩に彼女の特徴を伝えた。
もしかしたら三年生かもしれないと思ったからだ。
「ああ、あるよ」
先輩は事も無げに答えた。
俺は多少拍子抜けした。
「あ、そうですか・・・・・・何年なんです?あの人」
先輩は驚いた顔をしている。
「え・・・・・・なにか」
「いや、お前も大概にっぶいなあと思ってな。わからなかったのか。そいつがいるのっていつもあそこじゃなかったか。立体交差の、次の交差点辺り」
その通りだった。
「知ってるんですか。じゃあ先輩も会ったことが?」
今度は呆れ顔だった。
「あのな。お前、いくら同じくらいの時間帯だって、毎日毎日全く同じ場所ですれ違うのはおかしいと思わんのか」
あ。
俺は馬鹿だ。
俺が彼女を見かけるポイントは、時間に関わらず同じ場所だった。
つまり、ということは、まさか、もしかして。
「・・・・・・えっと、そっち系ですか」
先輩はうんうんと頷いている。
全く考えてなかった。
俺にあんなにはっきり見える幽霊がいるなんて。
「いつだったかなあ、最初は。俺が一年の年にはもう居たと思う。それから、あれはずっとあそこにいるよ」
「でも、俺にそんなにはっきり見えるなんてことありますかね。先輩ならともかく」
先輩はにやりと笑う。
最近わかってきたのだが、この表情をした時、先輩は俺に想像もつかないような黒い事を言う。
□ □ □
「アメーバって知ってるだろ。それが物を侵食する・・・・・・食作用、って言うんだがな。まあ、連中の食事だ。その時、仮足と呼ばれる突起を出す。偽足とも言うが」
何の話だろうか。
俺は生物は好きじゃない。
理数系ではあるが、どちらかというと物理が得意なのだ。
「その突起で物を侵食するんだよ。飲み込むんだ。じわじわとな。あの女は、それだ」
「つまり、ルアーとか、そういう物だと考えていいんですか。あの人は」
「お、いい例えだ。先駆けだな。お前には見えないんだろうが、あいつの後ろにはわけのわからん物がいるぞ。黒くて、どろどろした、取り込まれた奴らの固まりがな」
彼女に興味を持ってしまうと、引き込まれるのだろうか。
より多くの人を引き込む為に、少しでも感覚の鋭い人には見えるようになっているのだろうか。
わからないことばかりだ。
「あいつらは仲間を探してるんだ。一人でも多く。あの交差点、結構事故多いだろ。つまり、そういうこと」
俺はなんだか嫌だった。
あの人がそんな事の為に存在していると思いたくない。
「でも、それなら俺に近い歩道で居た方がいいんじゃないですか。今日は逆側に移動してましたけど」
先輩は鼻で笑う。
「あいつらの考えてることなんてわからないよ。お前があれにどんな感情を持っているかは知らん。けど、俺は事実を言っただけだ。アドバイスは『関わるな』だよ」
□ □ □
帰り道、俺はあの交差点を通った。
彼女は見えない。
俺はもしかしたら、顔も知らない彼女に恋をしていたのかもしれない。
それは、人を取り込む為の能力が俺に影響していたのか、それとも俺自身の感情だったかはわからない。
横断歩道の向こう、今朝彼女が歩いていた歩道を眺める。
俺はその光景を目に焼き付けてそっと目を閉じる。
瞼の裏の残影には、こちらを向いて寂しそうに笑う彼女が映っていた。
「・・・・・・じゃあね」
俺は、横断歩道の向こうに手を振った。
瞼に残った彼女の顔は、やっぱり、とても綺麗だった。
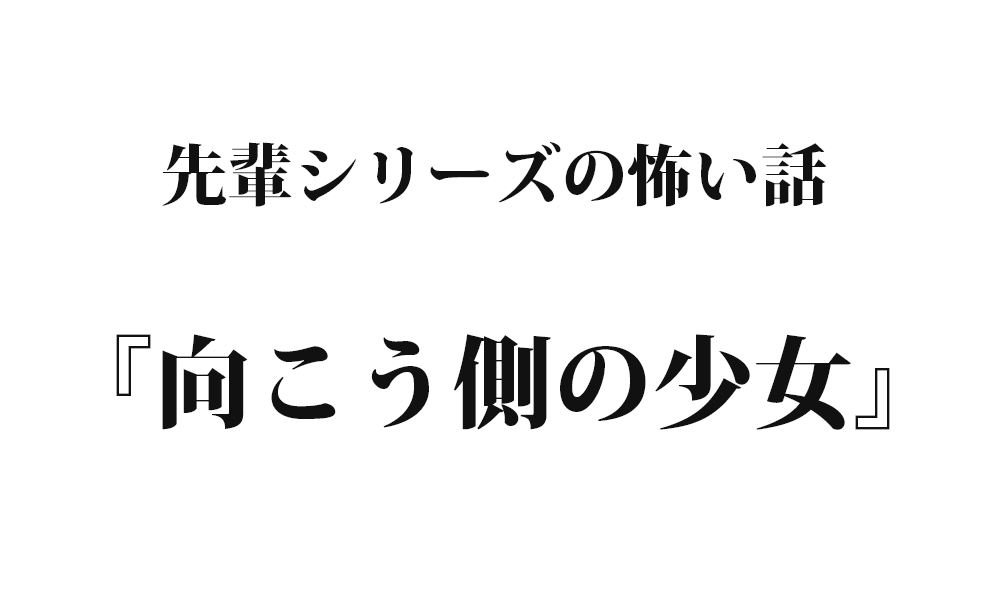
コメント