『心霊写真 3』
127 :心霊写真3 ◆oJUBn2VTGE :2013/03/08(金) 21:00:22.68 ID:j7MpCWDL0
それから僕らは連れ立って小川調査事務所を後にした。
師匠は「餅は餅屋だ」とだけ言って、行き先は告げなかった。僕はただそれについて行った。
JRの駅に向かったので少しドキドキしたが、ロッカーには近寄りもせず、切符を買って改札を抜けた。
一番安い切符だった。
普通列車はさほど混んではいなかった。
師匠が乗車口の近くで吊り革につかまって立っていたので、僕もそうする。
どこへ行くのだろうと思っていると、出発のチャイムが鳴り出した。
そしてドアが閉まり始めた瞬間だった。
「降りるぞ」
師匠はそう言いざま僕の手を掴み、無理やり引っ張って、閉まるドアをすり抜けるように電車から飛び降りた。
乗る電車を間違えたのかとも思ったが、師匠はホームに降りた瞬間、左右を素早く見回した。
「誰も、降りなかったな」
「ええ」
師匠はふん、と頷いた。
まさか、と思ったが、今のは尾行をまく時の手ではないだろうか。
「尾行されてたんですか」
「いや、念のためだ」
師匠が言うには、松浦が尾行をつけさせた可能性があったのだという。
こちらが田村とつながっていることを疑い、泳がせておいて接触したところを押さえる腹かも知れないのだと。
確かに、結果的にあわやそうなるところだったわけだから、そんな馬鹿なとは僕も言えなかった。
しかし尾行者はいないようだった。
「お前はまだ素人だからな。
尾行のことを話せば、もし本当にされていた場合、こちらが気づいたことを相手に気取られる危険性があった。
そうなると、こんな電車を使った古い手が通用しないことも考えられたけど……
まあ、取り越し苦労だったと思っていいだろう」
本当に熟達したやつの尾行は警戒していても簡単には見抜けない、と師匠は言った。
この世界を多少なりと覗いた師匠が言うのだから、僕は頷くしかなかった。
それから僕らは電車に乗ることなく、そのまま買った切符で駅を出て、繁華街の方へ向かった。
途中、師匠は自販機の前で立ち止まった。あまり見ない、サンガリアの自販機だった。
そこでメロンソーダを三本も買ったので、どうするのかと訊くと、差し入れだという。
「あのデブ、これが好きだからな」
その一言で、これから向かう所がどこなのか分かってしまった。
それから僕らは繁華街から少し裏へ入った通りを進み、
薄汚れた小さなアパート、いやアパートのようなマンションの前で止まり、中へ入っていった。
なんだか小汚い印象のエレベーターを使い、三階の中ほどにある部屋が目的地だった。
表札はない。新聞の勧誘や訪問販売の人間につけられたのか、小さなシールがドアの端に幾つか貼られている。
『写真屋』と呼ばれる男の部屋だった。
本名は確か、天野と言ったか。
通り名のとおり、写真を生業にしている男だったが、いわゆる普通の写真屋ではなかった。
街なかの普通の写真屋に持ち込んだのでは、フィルムを現像してもらえないような種類の写真を、
少々割高な値段で何も言わずに現像してくれるという類の、そういう商売だ。
いや、僕も最初のころは単純にそう思っていた。
この『写真屋』は、小川調査事務所も浮気調査に関する証拠写真などの現像で贔屓にしているのだが、
師匠は個人的にもこのアンダーグラウンドな世界の住人と仲が良く、悪友とも言える関係を築いていた。
「写真屋、いるか」
師匠はチャイムを鳴らした後、ガンガンとドアを叩く。
中から物音がしたかと思うと、しばらくしてドアが細く開けられる。
「ぼくがいないことがあったか」
眼鏡の奥の暗い目がドアの隙間から覗く。
ドアチェーンが外され、僕らは部屋の中に招き入れられた。
中に入ると、異臭としか言いようのない匂いが鼻をつく。
部屋中のいたるところにゴミが散らかっているが、匂いの原因はそれだけではない。
この部屋の主人は、その一室を暗室に改造して、そこで現像作業をしているのだ。
その時に使う液体の匂いがこの異臭の主たる原因だった。
『写真屋』はその暗室のドアの前を通り過ぎ、片方の足を引きずりながら部屋の奥に進むと、
三台のパソコンに囲まれた机にとりつくようにして座った。
「差し入れだ」
師匠が三本のメロンソーダを差し出すと、彼は薄っすらと笑いながらそれを受け取った。
いや、笑っているというより、癖なのだろう。
喋っている間もずっと、しゃっくりあげるように変な笑い声のような空気が漏れるのだ。「ひ」「ひ」という具合に。
髪は伸び放題で、見るからに風呂にもめったに入っていないような不潔感がある。
そしてはち切れんばかりに膨れた腹や顎、そして二の腕の肉。
部屋に満ちているのか、自身の身体から漂ってきているのか、その匂いも含め、
すべてが生理的な嫌悪感を抱かせる男だった。
「今日は助手君も一緒か、探偵」
僕はこの男を好きになれないのだが、どうも、と当たり障りのない挨拶をする。
「今日はちょっと訊きたいことがあって来た」
師匠は背負っていたリュックサックを下ろし、その中をガサガサと漁る。
「おっと、その前に、報酬を決めようじゃないか」
「あん?」
師匠が手を止め、険悪な顔をして睨みつけた。
こういう悪そうな顔をさせると、師匠は本当に様になっている。
「どうせやばいネタなんだろう。
僕の口を硬くするのは金の額だけだ。
金は要らないなんていう『写真屋』に、誰が人間の真実の姿が写り込んだフィルムを持ち込むもんか」
「なにが人間の真実の姿だ。変態どもがお前のところに持ち込んでるのは、ただのエロ写真だろうが」
「失礼だな、それも真実の姿の一つさ。
アホなカップルが街なかで顔をくっつけ合ってイ、エーイって間抜け面晒して写ってる写真に、
本当に写るべきものは一本の棒と一つの穴だ」
ひ、ひ。と喋る合間にも空気が漏れる音が混ざる。
「だけど、最も奥深い所にある、人間の真実とは……ひ……そんな下劣なものとは程遠い、神秘的なものだよ」
こんな風に。
『写真屋』は机から一枚の写真を取り出して見せた。
何が写っているのか察した僕は咄嗟に目の焦点を合わさないようにしたが、それでも少し見えてしまった。
人間の頭が砕けて、血と脳がアスファルトの上に飛び散っている写真だった。
この『写真屋』の本当の商売がこれだ。
二倍程度の料金を払って、普通の写真屋では現像してくれないエロ写真の類を現像する仕事が世の中にはある。
しかし、その特殊な写真屋でも現像してくれない、本当にアンダーグラウンドな写真がこの世にはあり、
さらにその数倍の料金を受け取ってそれを現像する、
現行法からも、そして常識からも掛け離れた倫理観を持つ『写真屋』。
それがこの男の生業だった。
「おい、それが写真屋の守秘義務か」
師匠がそう突っ込んだが、『写真屋』はそれを仕舞いながら「これはぼくの私物さ」と言った。
まあどうでもいいけど。
師匠は溜め息をついた後、「なあ、アマノちゃん」と声色を変えた。
「わたしとお前の仲じゃないか。硬いこと言わずに協力してよ。な」
「いや、駄目だ。ケジメは大切だ。僕は金しか信用しない」
さっきの松浦と同じようなことを言っているが、その二人の人間性やビジュアルの差を思うとなんだかおかしかった。
「いや、駄目だ。ひ。ケジメは大切だ。ひ。僕は金しか信用しない。うひ」
師匠が『写真屋』の言葉を真似して、それを大袈裟に再現して見せた。馬鹿にするためだ。
からかわれて、さすがに『写真屋』は鼻白んだ。
なにか言い返そうとした瞬間、師匠はその開きかけた口を右手の手のひらで押さえ込んだ。
アイアンクローのような格好だった。
「おい、てめぇがわたしの写真でせ○ずりこいてんの知ってんだぜ。
ご大層な理念を掲げるのは結構だが、その写真、燃やされたくなかったら黙って言うこと聞け、この野郎」
瞬間的な迫力、とでも言うべきか。
いきなり豹変したような勢いで脅しつけられ、『写真屋』は目を泳がせながら、とっさに頷いてしまった。
その顔に、しまった、という表情が浮かんだが、もう取り繕えないようだった。
「あ~あ、汚ったな」
師匠は『写真屋』の口元の涎がついた右手を振って、机の上のティッシュを数枚抜き取った。
「くそう」
写真屋はなにかぶつぶつ言っていたが、
机の上を片付け始め、そして折り畳み椅子を出してきたかと思うと、二つ並べて置いた。
「で、なにが訊きたいんだい」
諦めたように溜め息をついて、『写真屋』は切り出した。
空気が澱みきっているが、窓を開けていないどころかカーテンも締め切っており、
それもどこで買ったのかというような厚手なので、電球の明かりの下、一体今が昼なのか夜なのか分からなくなる。
時計を見ると、まだ昼の十二時を少し回ったころだった。
「これなんだけど。専門家の意見を訊きたい」
師匠はリュックサックの中から封筒を取り出し、その中から写真を抜き出した。
田村の持っていたものと、松浦から預かった四枚。合わせて五枚すべてを。
引き出しから薄い手袋を取り出して両手にはめ、『写真屋』はそれらを手に取る。
「心霊写真かい。専門家は……ひ……そっちじゃないか」
「まあそう言うな。心霊写真は苦手なんだよ」
「ふうん」
すべてに軽く一瞥をくれてから、机の端に並べて置いた。
そして春だというのに身体を動かしもしないまま汗を額に浮かべて、差し入れのメロンソーダの蓋を開けて勢いよく呷る。
「おい、貴重な写真もあるんだ。汚すなよ」
「ふん。もう見終わったよ」
そう言って大袈裟な仕草で写真から椅子ごと遠ざかる。
「ええと。まず、飲み会の写真だけど。これは煙草の煙だろうね。
ほら、このハゲ親父が、テーブルの上に不自然に右手を伸ばしてる」
遠くから芋虫のような指で写真を指し示す。
「手前の人の身体で見えないけど、この隠れた手の先に灰皿があるのさ。
そこから上がって来てる煙が、ストロボで浮かび上がって見えてるだけだ。
それが人間の顔のように見えるのは、まあ偶然だろう」
「ほう」
師匠はやけに熱心に頷いている。
「あと、この海辺の家族連れの写真。
たぶん、右膝が消えてるとか言って、心霊写真扱いされてるんだろうけど、よくある勘違いだね。
これは撮影速度が遅いせいで、男の子が右足を動かした瞬間に、透けたように見えているだけだ。
こっちの手をごらん。お父さんの腰のあたりを掴んでいる。
ここで重心の変化を支えているから、足以外はぶれてないんだ。そのせいで余計に足が透けているのが目立っている」
『写真屋』は解説を続けながら、二本目のメロンソーダの缶を手に取った。
「……それから、と。カップルの写真はどうかな。これはイタズラの可能性が高いね。
二人の背後に、ちょうど人間一人くらい隠れられる。
二人の身体が離れている部分があるから、
そこを上手く避けて、となるとかなりアクロバティックな格好になるけど、不可能じゃない。
偶然なはずはないから、こういう写真を撮ろうとして三人で遊んでたんだろう。
あと、この家の窓に男の上半身が薄っすら見えてるのは、どうだろうな。
二重露光にも思えるし、室内灯の光の当たり具合が良く分からないけど、単にそこに人がいたという可能性もある。
少なくとも、幽霊なんてものを持ち出さなきゃならない写真には思えないな」
彼は二本目を半分ほども飲んだところで、ゲップをした。長いゲップだった。
師匠は良くこんな生理的に気持ちの悪い男と一緒にいて平気だなと感心する。
「最後は、なんだこりゃ。年代ものだけど、普通の写真じゃないか。どこが心霊写真なの」
逆に訊ねられた。
「この中の誰かに、不自然なところはないか」
師匠にそう言われ、もう一度写真に顔を近づける。しばらく唸ったあと、彼はやはり同じ答えを出した。
「古い写真は得意じゃないけど、別におかしなところはないと思うよ。影のでき方なんか見てもね」
そう言って二本目の缶の残りを飲み干す。
僕ももう一度まじまじと、その戦時中に撮られたという白黒写真を眺める。
整然とした和室に、和服を着た初老の男が腕組みをして座り、その周囲に軍服姿の青年たちが正座をしている。
彼らは二十八、九から三十歳くらいのはずだったが、どの顔も現代の同じ年齢の日本人よりもどこか幼く見えた。
だが、誰一人として笑いもせず、唇を引き結んで、正面を見据えている。
画質のせいなのか、彼らのその相貌がやけに青白く見えた。
「こいつはどうだ」
師匠はついに、左隅にいた正岡大尉を名指しした。先入観を持たせないために、ここまであえて避けていたのだろう。
だがその問いにも『写真屋』は大した関心を示さず、「おかしなところはないね」という答えを繰り返しただけだった。
だが師匠は諦めず、表現を変えて質問を続ける。
「偽造の可能性は」
「偽造?写真の加工ってこと?」
『写真屋』は鼻で笑った。
「おかしなところは……ひ……ないって、いったろ」
「こいつが、実際にはここにいなかったのに、いるように見せるのは無理か」
「このくらい違和感のないフェイクを作るのは難しいね。ネガの編集にしても、プリント後の加工にしてもね。
今の技術でも、難しいんだ。当時のテクじゃ無理だろう」
まあ、これからはこいつが……と、『写真屋』はパソコンの箱を手のひらで叩いて見せた。
「あらゆる写真を自由自在に編集するようになっていくだろうけど」
そのころはワープロがやっと普及してきた時期であり、パソコンなど持っている人はまだまだ少なかった。
僕自身、キーボードに触ったことすらなかった。
「撮影は戦時中でも、偽造を施すためにプリント時期を偽っている可能性は」
師匠はまだ粘っている。
「最近プリントしたってことか。ふん。紙質にも違和感はないね。それ相応の年代モノだよ」
それを聞いて、ようやく納得したように一つ頷くと、師匠は背中を掻いた。
「ここに来ると、なんか痒くなるんだよな。ダニとか、ノミとか、飼ってるんじゃないか、お前」
「ノミは知らないけど、水虫は飼ってる」
うへ、という顔をして師匠は後ずさる。
「うつされる前に退散するが、あと一つだけ教えてくれ」
そう言って師匠は封筒に指を入れ、まだ中に残っていた一枚の紙を取り出した。
松浦に預かったコピーの方だ。
それを『写真屋』の方に向け、こう訊ねた。
「このコピーと、その写真は、同じものか」
ふいに、僕の中に疑念が湧く。
なぜ師匠はそんなことを言うのだろう。コピーだと今自分でも言ったではないか。
それに言うまでもなく、同じ構図、同じ男たちなのだ。
『写真屋』は両者を見比べ、つまらなさそうにぼそりと言った。
「コピーは専門外だけど。全く同じに見えるね。この写真をコピーしたんだろう。この中央は焼きミスだね。
もしかして、同じネガの別プリント写真のコピーじゃないかってことか?だとしたら分からないとしか言いようがない」
師匠はその答えを反芻するように、しばらく頷いていた。
そして、「よし」と言って膝を打ってから立ち上がった。
「邪魔したな」
「あ、もう帰るの」
あれほどただ働きを嫌がっていたのに、『写真屋』はなぜか名残惜しそうに口を尖らせた。
師匠はそれを見て、ニコリと笑うと「またな」と優しい声で言った。
異臭にも少し慣れつつあったそのマンションの一室から出た直後、僕は師匠に耳打ちをする。
「その、せん……の写真って、盗撮でもされたんですか」
「なんだって?ああ、わたしの写真か。盗撮といえば盗撮だな」
「取り返した方が良くないですか」
「いいよ、めんどくさい。どうせ焼き増しして、分かんないところに隠してんだろ」
師匠が良くても僕は困る。
「良くないですよ。あの変態にそんな写真持たれて、何されるか分かったもんじゃないですよ」
「なんだ。酷い言われようだな、あいつ。そんな写真って、どんな写真だと思ってんだ」
「え」
僕は思わず口ごもった。
そういう写真に決まっているではないか。古式ゆかしい表現で言うところの、無防備な……
いやまて、もっと凄い写真かも知れない。え、うそ。まじで。
想像が頭の中をぐるぐると回る。
ええ?そういう写真なの。いやでもまさか、ああいう写真とか。まずいまずい。実にまずい。まずいですぞ、これは。
「おい。大丈夫か。とっとと出るぞ、こんな水虫屋敷」
そう言って師匠はエレベーターの方に向かって歩き出した。
マンションの外に出ると、日差しが目に沁みた。
締め切った部屋の人工の明かりは、やはり太陽光線よりも弱いものらしい。
師匠は時計を確認してから、近くの電話ボックスに入った。
そしてどこかに電話を掛け、出てくるなり「一度家に戻るぞ」と言う。
ハンドルを握るジェスチャーをしていたのから、車を取りに行くらしい。
「次はどこに」
「寺だ」
寺。
ピンと来た。
行ったことはなかったが、師匠がよくオカルト関係の怪しいモノを仕入れてくる寺があると聞いていた。そこに違いない。
焚き上げ供養で密かに有名な寺らしいのだが、
その裏では燃やしたはずの曰くつきの物件をマニアに横流ししているという、とんでもない悪徳坊主がいるそうだ。
それを買う方も買う方だが、
師匠に連れられて、そういうアイテムばかり売っている胡散臭い市(いち)に行った時、
僕もそこに出ていたクマのぬいぐるみが気に入って買ってしまったので同罪だった。
そのぬいぐるみは、夜中に時どき歯軋りのような音や、すすり泣く様な声を出して、
僕を不安な気持ちにさせるお茶目なやつだった。
途中でスーパーに寄っておにぎりや菓子パンを買い込んでから、僕らは師匠の家に到着した。
休む暇もなく、すぐに駐車場に止めてあった年代物の軽四に乗り込む。
僕は助手席に座ってシートベルトを締め、スーパーの袋をガサガサと漁る。
目の前をスケートボードでノロノロと横切ろうとしていた子どもに容赦なくクラクションを鳴らして、師匠は軽四を発進させる。
「シートベルト。シートベルト締めて下さいよ」
僕が指摘すると、
師匠は「わたしが免許取った時には、そんな義務なかった」とぶつぶつ言いながら、めんどくさそうにベルトを引っ張った。
こういう時に、僕は師匠の間のジェネレーションギャップを感じる。
おにぎりやアンパンをお茶や牛乳で流し込みながら車を走らせ続け、僕らは北へ北へと向かった。
「結局、あの将校たちの写真は、心霊写真なんかじゃないんですかね」
道路沿いに商店や民家が少なくなっていく景色が走り去っていくのをぼんやりと眺めながら、僕はなにげなく訊いてみた。
どうせ答えてくれないだろうと半ば分かっていながら。
「さあなあ。『写真屋』は、普通の写真だろうって言ってたな」
師匠は人ごとのようにそう言う。
「どうしてそんなに他人ごとなんですか。自分こそ専門家でしょう。家にも一杯心霊写真集めてるのに」
「好きなんだけどな。それぞれが本物かどうかは自信がないな。
わたしは生で見るのが得意なタイプなの。写真はなあ……
仮に死者が怨念だから執念だかで、フィルムに写りこんだとしても、だ。
そのフィルムが現像され、ネガをプリントした場合、その写真一枚一枚にまで、怨念が乗っかってないんだよな。
撮影場所とは関係ないどこか遠い場所でさ、何ヵ月後か、何年後か、そして何枚も何十枚もプリントされてさ。
その全部に怨念がこびりついて残っている道理がない気がする。
結局のところ、その写真がヤバいかどうかは、視覚的な情報に頼るしかないんだ。
ありえない位置に人の顔があるとか、逆に人の顔がないとか。
でもそういう写真って、偽造でも再現できるケースがあるじゃないか。だから、どうにも心霊写真ってやつは苦手なんだ」
そういうものか。
納得しかけたが、以前師匠がえらそうに心霊写真について語っていたこともあった気がして、釈然としないものが残った。
言ったもん勝ちかよ。と、そう思ったのだ。
「まあ餅は餅屋。蛇の道は蛇だ」
「なんですかそれ」
「だから専門家に訊きに行くんだよ」
「心霊写真のですか」
そんな、供養を頼まれた写真をマニアに横流しするような悪徳坊主に訊きに行ったところで、役に立つとも思えなかった。
そんな馬鹿にしたような僕の口調を咎める様に、師匠は意味深な言葉を吐いた。
「世の中にはな。説明のつかないことってやつは、確かにあるんだ」
説明のつかないこと?
それと悪徳坊主となんの関係があるのか。
「まあ、行けば分かる」
師匠は口笛を吹きながら、開け放った車の窓から入ってくる風を気持ちよさそうに顔に受けている。
車は蛇行しながら山に登り始め、僕が助手席で車酔いしそうになったころ、ようやくそれらしい山門が見えてきた。
周囲には山の斜面にも関わらず、畑がたくさんあった。段々畑というやつか。
舗装もされていない駐車スペースがあったので、そこに車を止める。ザリザリザリというタイヤが砂を噛む音が響いた。
山門の左右には板壁がついているが、それも申し訳程度で、その外側は大きな木が生い茂っている。
その板壁の端のあたりに石柱が立っていて、『不許葷酒入山門』という文字が縦に彫られていた。
それを見ながら「禅宗の寺ですか」と訊くと、「違う」という答え。
「本来は禅宗の戒めだがな。割と節操なく他の宗派でも見るよ。ただ、ここのはちょっと趣旨が違うんだ」
「なんですか、それ」
師匠は石柱の文字を指さしながら、「なんて読むと思う」と訊く。
「葷酒(くんしゅ)、山門に入(い)るを許さず、でしょう」
葷酒、つまりニンニクやネギなどの匂いの強い野菜や酒の類は僧侶の修行の妨げになるので、持ち込んではいけない、
という戒めの言葉だ。
現代なら、餃子にビールというところか。
しかし師匠は「違うなあ」とニヤニヤ笑う。
「葷酒、許されざるも山門に入る、だ」
見えない返り点の位置を指で示しながらそう言った。
入っちゃうんだ……
僕の頭の中で住職がどういう人物か、さらに補強された。
山門をくぐると、杉木立の中に参道があり、射し込んで来る陽光に照らされて新緑が目に映えた。
地所は広い。参道はあまり長くなく、向こうに本堂の屋根は見えているが、その周囲にも庭園や池が広がっている。
「真宗の寺だよ」と師匠は言った。
え、と思って訊き返す。
「真宗で、心霊写真の焚き上げ供養ですか」
それはおかしい。他の宗派ならいざ知らず、浄土真宗はそのあたり徹底しているはずだ。
香典の御霊前の文字を使わせず、御仏前とすることにこだわっているくらいだ。
「お、さすがに寺のことは多少知ってるな」と師匠は嫌らしい笑みを浮かべた。
「そうだ。霊魂不説ってやつだ。
釈尊が霊魂と肉体の同異について語っていないのだから、
滅びる肉体と、不滅の実体たる霊魂なんていう二元論は、本来ありえないっていう考えだな。
あくまでもすべては無自性(むじしょう)であり、空(くう)だ。
特に臨終即往生、往生即成仏の真宗においては、当然人間が死んだ後はすぐに仏になるのだから、
霊なんてものになって世に迷ってる暇はない」
参道の苔むした石畳の上を歩きながら、師匠は右手を広げて身体の前でぐるりとかざした。
「しかし、この日本では神仏習合や、古来よりの山岳信仰、祖霊崇拝などと結びつくことで、
仏教の思想も様々に分かれ、変化する。
宗派の中でも、分派や一寺院、あるいは僧侶一個人として霊の存在を認める場合もある。
だいたい、仏教独特の説である輪廻転生ってやつを考えた時、
転生する主体、つまり不滅の実体を想定せざるを得ないんだから、それを仏性と説こうが、どうしたって……」
「分かってますよ」
長くなりそうだったので、遮った。
それよりも、なにか人の視線のようなものを感じて、僕は周囲を見回した
薀蓄に気分が乗って来たところでそっけなく遮られ、憮然とした師匠は、
「ここ、本当は真言宗の寺だよ。それも分派も分派。各山会、十八本山にもかすってない、なんとか派だ。……ぺろぺろ派」
適当なことを言って欠伸をした。
僕は、ハッとして立ち止まる。
右手側に小山のように高くなっている場所があり、その斜面の上にこちらを伺っている人影があった。
女の子?
青いワンピースを着た、小さな女の子がそこにいた。
すぐそばのヒノキの幹の後ろに隠れて、そしてまたそろそろと顔を出してくる。
「アキちゃんやあい。おくすりの時間だよう。アキちゃんやあい」
本堂を挟んで遠く反対の方向から、そんな呼び声が聞えて来た。妙に間の抜けた調子の、年配の男性の声だった。
女の子はその声に興味を示さず、じっと僕らを見ている。いや。見ているのは師匠だ。
師匠は斜面に取り付くと、木の根を伝って小山の上に登った。思わず僕も続く。
登ってきた僕らを警戒するように、女の子はヒノキの後ろに隠れた。そしてまた、ちらりと顔だけを覗かせる。
何歳くらいだろう。小学校生なのは間違いなさそうだ。十歳くらいだろうか。
色白で、手足など折れそうなほどほっそりしている。
ストレートの髪の毛を肩口で切り揃えていて、賢そうな黒目がちの瞳が印象的だった。
「またきた」
女の子はそう言った。可愛らしい声だった。
師匠は、わたしのこと?とばかりにおどけて自分を指さす。
「またきたね」
女の子は、ひそひそとした声で真横を向いて囁いた。そうしてうんうんと頷いている。
なんだか変だった。その子が向いている場所には、誰もいない。
「そうだよ。また来たよ。今日はとっても大事な用があるんだ。お兄ちゃんはいる?」
師匠は猫なで声でそう訊ねながら、ヒノキの向こうからこちらに近づいてくる人影に気づいて顔を上げた。
僕もそちらを見て、驚いた。長身のガッシリした体格の男が歩いて来る。
黒谷夏雄だ。
我が小川調査事務所の小川所長の甥で、かつては師匠と組んで『オバケ』絡みの依頼を請け負っていたという男。
僕や師匠と同じ大学のはずだが、ほとんどキャンパスには姿を見せず、
『M.C.D.』というハードなパンクバンドを組んでいたと思うと、
ふらりと中国へ旅立ってそのまま何ヶ月も帰って来ないというような、無軌道な男だった。
なぜやつがここに。
身構える僕に目もくれず、黒谷は女の子の横で立ち止まると、師匠に向かって「早かったな」と言った。
「ああ。夏雄がいてくれて良かったよ。親父の方だと話がややこしくなる」
写真屋のマンションを出た後、電話をしていたのはこいつだったのか。
アキちゃんやあい。
アキちゃんやあい。
遠くでまだ探している声が続いている。
僕は状況をそれなりに飲み込んだ。あれが親父の方か。つまり、夏雄はこの寺の悪徳住職の息子というわけだ。
「じゃあ、この子は」
恐る恐る、僕がそう訊ねると、師匠は頷いた。
「今呼ばれてる、そのアキちゃん。夏雄の妹」
ヒノキの幹のそばで二人並んでいるのを見比べ、そのあまりの違いに僕は唖然とする。
かたや見上げるような長身に服の上からでも分かるくらいの分厚い胸板。首筋から覗く龍のタトゥ。
吊り上がった眉と鋭い目つきには、思わず目を逸らしてしまいそうな厳つい男。
かたや線が細く病弱そうな色の白い黒髪の少女。
しかも夏雄の方は大学五年目の二十二、三歳のはずなので、
女の子が小学校の三年生か四年生くらいだとすると、少なくとも十コ以上は歳が離れている。
僕の戸惑いに、師匠が「戸籍上はな」と付け加える。
あ、やっぱり。
そう思ったが、師匠は笑って「うそうそ、ホントに血が繋がってるんだって」と言い、
夏雄の方は不愉快そうに睨みつけている。
僕らは心霊写真の専門家を尋ねてきたはずだ。
住職が山師のインチキ親父だとすれば、専門家というのはこの黒谷のことか。
僕は以前、『M.C.D.』のライブの最中に現れた霊を、この夏雄が壁ごと殴りつけて撃退したことを思い出した。
そんな粗暴な男に、心霊写真の鑑定など出来るのか。
思ったことを口にすると、師匠は笑って「違う違う」と手を振った。
「用があるのは、この子の方にだよ」
そうして少し屈みながら身を乗り出し、アキちゃんという女の子に微笑みかけた。
「ね」
しかしアキちゃんは首を左右に振ると、警戒したように夏雄の背中の後ろに回って身を隠した。
「嫌われてんだよ。これが」
師匠は憮然として上半身を起こす。
アキちゃんは夏雄の後ろから出てこない。
「この子、完全になんとかコンプレックスだし」
師匠は意味深な視線を夏雄に投げかける。
ブラコンか。
あの見るからに恐ろしい男が、妹には優しいというところを想像しようとして、うへえ、という気持ちになる。
あれ?
「この子の方に用があるって、どういうことですか」
そう訊くと、師匠は夏雄の腰の辺りから髪の毛だけが見えているアキちゃんを指さして、言った。
「この子は、わたしや夏雄なんか及びもつかない、正真正銘の霊能力者だよ」
アキちゃんやあい。
アキちゃんやあい。
呼び声が続く。
山間の木々の中を走る爽やかな春の風が、一瞬止まったような気がした。
[完]
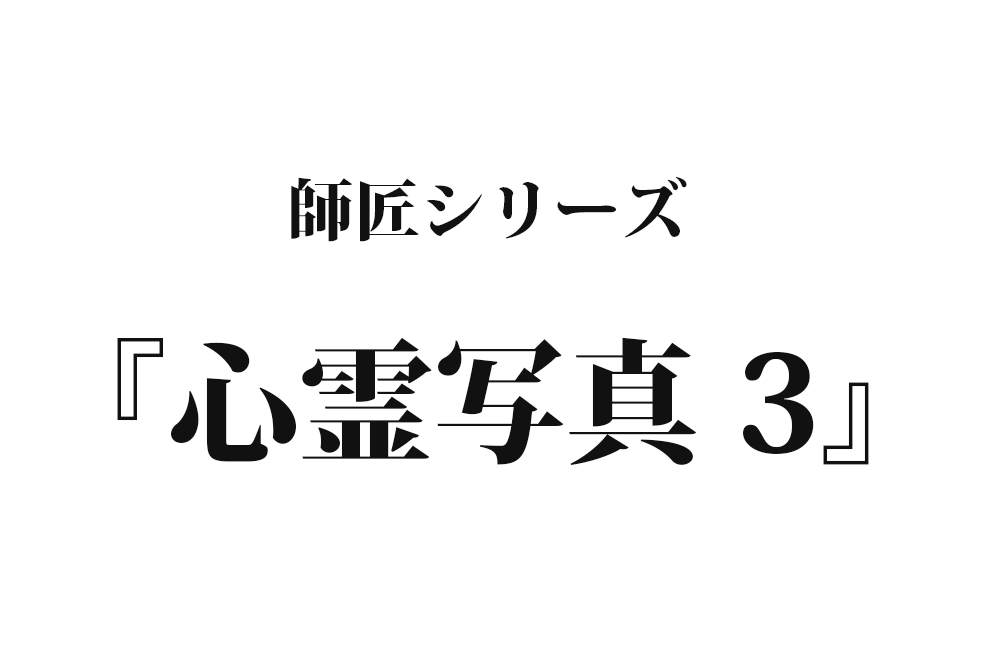
コメント