藍物語シリーズ【33】
『契』
上
皆で午後のお茶を飲んだ後、俺は庭の落ち葉を掃き集めた。
やや力を失った陽光に、秋の気配を感じる。もうすぐ、紅葉と落葉の季節。
出来ればこまめに庭の手入れをするのが理想。しかし。
翠、藍、丹。
小さな子が3人もいればさすがに忙しい、どうしても庭の手入れは後回しになりがち。
もちろんSさんの式に手伝ってもらう事もできるが、出来ればそれは避けたかった。
珍しく子供達3人が揃って機嫌が良い。一種奇跡的な、穏やかな、ある日の午後の事。
突然の違和感。胸騒ぎのような、嫌な予感のような。何だろう、これは?
庭の掃除をしながら突然感じた理由のない焦燥、掃除を切り上げて玄関へ急いだ。
「Rさん!」 玄関のドアを開けた姫は丹を抱いていた。緊張した顔。まさか子供達に何か?
「Rさん、お母様から電話が有りました。成る可く早く電話して欲しいって。」
違和感と胸騒ぎの原因はこれか...ケイタイのボタンを押す間がもどかしい。
「犬のことで大げさだけど、御免ね。雪が、もう長くないみたい。
でも、お前にはあんなに懐いていたから、せめて知らせるだけでもと思って。」
雪は俺の実家で飼っている雌の秋田犬、今年で15歳になる。
今年の正月、家族揃って実家を訪れた時、老いて衰えた様子を心配したのだが。
覚悟していた時期が、かなり近いらしい。
「大げさって、雪は俺を...知らせてくれて本当にありがとう。今仕事はそんなに忙しくないし、
多分時間は作れる。様子を見に行けるようにみんなと相談してから、また電話するよ。」
「ありがとう、お願いね。」
「雪ちゃん、もう長くないかもって、どんな様子なんですか?」
丹を抱いた姫は、とても心配そうだ。
「エサをほとんど食べないって言ってましたから...あと数日、ですかね。」
俺が子供の頃に貰われてきた雪は、まだほんの小さな子犬で、とても寂しがり屋だった。
夜、勝手口の三和土で心細そうに鳴き続ける雪が可哀相で、
枕と毛布を持っていって勝手口で一緒に寝たことが何日もあった。
それからの色々な思い出が一気に蘇り、胸が詰まる。
「今急ぎの仕事はないし、一週間くらいなら何とでもなる。
家の事は私とLに任せて行ってらっしゃい。大事な、家族なんでしょ?」
「有り難う御座います。取り敢えず3日間の予定で行って来ます。その後は様子を見て。」
「みどりもいっしょに行く。お父さん、つれていって。」
ソファの上で翠が上体を起こしていた。さっきまで、藍の隣でぐっすり寝ていたのに。
「みどりも、ゆきちゃんに会いたい。」
正月、翠はすぐに雪と仲良くなった。撫でてやったり、狭い庭を一緒にゆっくりと散歩したり。
雪も翠に良く懐き、お屋敷に戻る時には翠の後を付いてきて、俺たちの車を見送っていた。
話を聞かれてしまった以上、翠をお屋敷に残して出掛けるのは難しい。
Sさんは微笑んでソファに歩み寄り、翠を抱き上げた。
「遊びに行くんじゃなくてお見舞いよ。御祖父様と御祖母様の御迷惑にならないように、
お父さんの言う事をちゃんと聞けるって、約束出来る?」
「うん、約束する。」
「お父さん、翠も一緒に連れて行って。お願い。ほら、翠も。」 「おねがい、します。」
父と母は翠を猫可愛がりだから問題は無いだろう。
それに翠がいれば、もし『その時』が来ても皆の気が紛れるかも知れない。父母も、勿論俺も。
「分かった。今夜準備して明日の朝早く出発するから、早起きしてね。」
「うん、早起きする。」 真剣な表情。思わず小さな肩を抱き締めた。
翌朝、少し早起きをして軽い朝食を食べた。翠もしっかり起きている。
実家までは車で約半日。7時にお屋敷を出れば、昼過ぎには到着出来る筈。
Sさんが作ってくれたサンドイッチを持って、予定通り7時丁度に出発した。
途中で一度サンドイッチ休憩を挟み、実家に着いたのは1時半過ぎ。
車の音を聞きつけて母が玄関から顔を出した。翠が母に駆け寄る。
母は微笑んで翠を抱き上げた。
「いらっしゃい、翠ちゃん。雪のお見舞いに来てくれて、有難うね。」
「おばあさま、ゆきちゃんは?だいじょうぶ?」
「今、寝てるけど。やっぱりエサを食べなくて...。」 「そうなの。心配、だね。」
トランクから荷物を降ろし、2人に続いて玄関のドアをくぐる。
車はあとで移動するとして、取り敢えず雪の様子を。廊下から台所の勝手口に急ぐ。
...三和土にぐったりと横たわる雪の体。目を閉じて、寝ているようだ。
想像以上に痩せた姿に、言葉が出ない。これではあと数日どころか、今日明日も。
寝ているのを起こすのは可哀相なので、そっと居間へ移動した。
「今の内に車を移動してくるよ。いつもの所でしょ?」 「そう。今朝電話しておいたから。」
馴染みの有料駐車場に車を移動して戻ってくると、雪は起きていた。
勝手口の床に頭をもたせかけ、翠が頭を撫でている。俺もそっと背中を撫でた。
雪は俺と翠の顔を交代で見つめていたが、暫くすると安心したのか、また寝てしまった。
「お医者さんは『老衰だから治療は出来ない。』って。
頭はしっかりしてるみたいだし、朝と夕方は自分でトイレに行って、水も、飲むんだけど。」
母はハンカチで目尻を押さえた。
「どこか痛がったり呼吸が苦しそうなら可哀相だし、こっちも辛い。
でも、そんなんじゃないから少し気が楽だね。でも、あの様子だと今夜を乗り切れるかどうか。」
「夜はみどりがゆきちゃんのおうえんするから大丈夫。」
「応援?」 「そう、ここでいっしょにねるの。ゆきちゃんも、みどりといっしょにいたいって。」
母は泣き笑いのような表情を浮かべた。
「お父さんもね、此処に寝て雪を応援したことがあるの。今度は翠ちゃんも、お願いね。」
夕方6時前、母の言葉通り雪はふらふらと立ち上がった。
勝手口のドアに頭を擦りつけた後、俺たちの顔を見つめる。
見慣れた、『外へ出たい』という意思表示。翠を連れ、庭から勝手口へ廻った。
外からドアを開けると、雪は少しよろめきながらドアをくぐり、ゆっくりと歩き出す。
元気な時は外階段を上った屋上がトイレの場所だったが、もう階段は上れないと聞いていた。
庭の外れでオシッコをしたあと、自分用の水桶へ向かう。
専用の水桶に新しい水を入れると、少し多めに水を飲んだ。
その後暫く庭の方を見つめていたが、勝手口へ歩き出そうとしてよろめいた。力無く座り込む。
俺が手を出すより早く、翠がしゃがんで雪の頭を撫でた。
「大丈夫だよ、ゆきちゃん。ここで少し休んで、それからかえろう。
みどりが、ずっと一緒にいる。大丈夫だよ。おうえんも、たのむから。ね。」
まるで頷くように俯いた後、雪は暫く目を閉じた。
「オシッコの量は普通、かな。でも、戻る途中でよろけて。体力がかなり消耗してる。」
「何か食べてくれたら良いのにね。一応エサは用意するけど。」
7時前に父が帰って来ると雪は目を開け、小さく尻尾を振った。しかしエサは食べず、
俺たちが夕食を食べている間も、目を閉じて三和土に横たわっていた。
三和土からじっと母を見つめる『ご飯頂戴』アピールはあんなに必死で可愛かったのに。
翠と母がお風呂に入っている間、俺は台所のテーブルと椅子を移動して布団を敷いた。
雪はじっと横になったままでピクリとも動かない。何度も呼吸を確かめる程だった。
翠が布団に入ったのは9時前。
『今夜はずっとおうえんしてるからね。』と声を掛けた後、10分もしないうちに寝息が聞こえた。
母は洗い物を終えて明日の準備をしている。俺は冷蔵庫から缶ビールを2本取り出した。
ナイトゲームの実況が、居間から微かに聞こえて来る。
「何だ、巨●、負けてるじゃない。」
缶ビールを一本父の前に置き、もう一本のプルタブを開ける。
父は薄く笑った。「まあ見てろ、次の回に逆転する。△伸が、打つからな。」
表情と声がいつもより控えめなのは、やはり雪のことが気に掛かっているからだろう。
父の斜め向かい、一人がけのソファに腰を下ろした。缶ビールを半分程、一気に飲む。
「で、どうだ?何か、分かったか?」 「何かって、何?」
「雪の寿命とか、延命の方法とか。色々あるだろ。お前は陰陽師、なんだから。」
「人の寿命も分からないのに犬の寿命が分かる訳ないよ。
それに医者も老衰で手の打ちようが無いって言ってるんだから、延命なんて無理。」
父は俺の眼をじっと見つめた。TVの明るいCMソングは、場違いなBGM。
「それは、Sさんでも、Lさんでも同じか?」
「死期が予測できるのは特別な場合だけ。雪の正確な寿命は、多分2人にも予測出来ない。
それより今夜を乗り切れるかどうかが心配な位なんだけど。」
「そうだな。」 父は中継が再開された画面に視線を移した。
ポツリと呟く。 「もう15歳。仕方、ないか。」 寂しそうな、横顔。
雪の死、その実感がじわりと胸にのしかかってくる。
「あ、でも、今夜は多分大丈夫だよ。」 「何故分かる?」
「翠がそう言ってたからね。あの子が鋭いのは特別だから、信じても良いと思う。」
半分は親父への、残り半分は俺自身への、気休め。
「そう願いたいな。今夜を乗り切ってくれたら、明日と明後日は俺も一日家にいられるし。」
沈黙。静かな居間に、歯切れの良い実況だけが小さく響いている。
突然、鋭い打球音が響いた。興奮したアナウンサーが叫ぶ。
「ほら。言った通りだろ?」
いつもなら派手なガッツポーズが出る場面だが、父は微笑んだだけだった。
空き缶を持って台所へ戻ると、母が翠の枕元に座り雪の頭を撫でていた。
「この頃、あんまり寝てないでしょ?今夜は翠と俺に任せてゆっくり寝てよ。」
いくら雪が俺に懐いていて、父には絶対服従だとしても、
一番長い時間を雪と共有したのは母だ。今の雪の姿を見て一番辛いのも母だろう。
「そうだね。そうさせて、もらおうかな。」 母は手を洗い、そっと翠の頬を撫でた。
「お休み。雪のこと、お願いね。」 「うん、お休みなさい。」
寝室に向かう母を見送った後、缶ビールをもう一本飲んだ。
やはり落ち着かないが、翠の言葉通り今夜を乗り切れば、『その時』は多分明日。
今は体を休めておいた方が良い。翠の隣、布団に入ったのは10時半を過ぎていた。
半日運転した疲れとビールの酔いのせいか、俺はすぐに眠りに落ちた。
全身に感じる、風の圧力。 体に粘り着く空気を力尽くで切り裂く。
これは、夢? はるか空の高みから見下ろす夜景が凄い勢いで後方へ流れ去っていく。
『もう目的地は目の前。一刻も早く姫君の下へ。』
その時、少し前方の夜景の中に徴が見えた。 『あれだ。』
気配を消しつつ、徴を目掛けて急降下。 夜景がどんどん大きくなる。
四角い屋根の縁に向けて着陸体勢。注意深く、速度を殺す。
梟や木菟たちとは違うし、翼の細かな制御は不得手。
抑え損ねた風が、庭の木々を揺らす音を聞いた。
「お父さん。お父さん、おきて。外に、何かいる。」
...翠の声、これも夢? いや、違う。慌てて上体を起こした。
翠は布団から出て勝手口の三和土に足を下ろし、庇うように雪の背中を擦った。
ドアの向こう。憎悪に満ちた、低い唸り声。 全身が総毛立つ。 これは、何だ?
深呼吸、感覚を最大限に拡張する。激流のように流れ込む、激しい感情と映像。
地面すれすれの視点。目の前に数頭の犬。その背後から此方を見下ろす男。
耐えがたい痛み、断末魔の苦しみ。 犬たちと男に対する激しい憎悪。
...狩りの情景?
男が携えた銃に見覚えがある。いつか読んだ本の旧い写真。確か、●田銃。
大きな破裂音と同時に、暗転。
「ゆきちゃんはずっとこのうちでそだったから、動物たちをころしてない。
それに、ゆきちゃんが年をとってからこんなこと、ひきょうだよ。
ゆきちゃんが元気なあいだは何もしなかったのに。」
?? 翠がドアの向こうに語りかけている。 唸り声の意味を感知しているのか?
再び唸り声。苛立ったような調子が不吉だ。そっと翠の肩を抱いた。
翠は俺に頓着せず、ドアの外の気配に語りかける。
「それにね。くまさんだってほかの動物をたべるでしょ?
思い出して。たべられた動物たちはよろこんでいた?」
ドアの向こうの気配が大きく揺らいだ。しかし唸り声が含む憎悪は増している。
言語を伴う思考が伝わってこないのだから、気配の主は人間ではない。
翠の言葉からすると、猟師に撃ち殺された熊の、幽霊?
いや、動物でも幽霊に成り得る霊質を持つのは稀な筈だし、
狩りで殺された動物たちが幽霊になって祟るなら、猟師や猟犬はとうに絶えている。
恐らく妖。狩りで殺された熊や、その他の動物たちの怒りや苦しみ。
山の妖の1つがそれらと共振し、強い憎しみと悪意を宿した存在へと変化したモノ。
父方の祖父は、若い頃猟師だったと聞いた。雪は祖父の飼っていた猟犬の子孫にあたる。
その体に流れる濃い猟犬の血が、血迷った妖を引きつけた。それが何時かは分からない。
雪が元気な間は何も起きなかったのだから、猟犬や猟師に対する恐怖は残っていたのか。
雪の寿命が尽きかけたのを察知して恐怖は薄れ、憎しみが恐怖に勝った。だから、今夜。
母が張った結界を越えられないようだが、結界越しの妖気でも弱った雪には毒だ。
「お父さんがいってたよ。動物はほかの生きものの命をいただいて生きてるって。
動物はみんな同じことしてるのに、うらむのはおかしい。ずっとこのうちにいて、
動物たちをころしたことがないゆきちゃんをうらむのは、もっとおかしい。」
ドアの外の気配は益々濃く、既に実体を現出したのでは無いかと感じる程だ。
残念ながら翠の説得は効果を上げていない。というか、むしろ逆効果。
このままでは濃度を増す妖気が雪の体を更に弱らせる。
この執着の強さからして、結界越しに祓うのは難しい。
だからと言って、相手の正体や力が分からない状態で母の結界を解くのは危険過ぎる。
鎮魂の詞歌で慰める方法はあるが、相手を特定できなければ効果は薄い。
何種類もの動物の魂を引き寄せ混ざり合い、妖を芯として寄り集まった集合体。
1つ1つ特定するなんて、俺には無理...いや待て、さっき翠は『くまさん』と。それなら。
「翠、外の妖、どんな動物の魂を取り込んでるか分かる?くまさんの他に。」
「うん、分かる。どうして?」
「憎しみに狂った動物たちに普通の言葉は通じないから、『言霊』で慰めてみるよ。
でも相手がどんな動物か分からないと効き目がない。
お父さんの術が始まったら、どんな動物たちの魂を感じるか教えてくれる?」
「分かった。」
深く息を吸い、下腹に力を入れた。心を込めて鎮魂の詞歌を詠唱する。
動物の姿を強く、鮮明に想い浮かべ、そのイメージを歌詞に織り込む。
最初は熊。ツキノワグマだ。大きく、力強い姿。その魂を慰め、憎しみと執着を解く。
植物から草食動物へ、さらに肉食動物へ。繋がる命の道理。
猟師達を始め、人間も動物の命を有り難く頂いて生きている。感謝と、鎮魂の祈り。
詠唱は一区切り、其処此処に浮かぶ色とりどりの花が見えた。次々に開いては散る。
散った花びらは光る軌跡を残して...大丈夫、『言霊』はちゃんと。
「しかさん。」 翠は俺の意図を理解していた。 詞歌の一区切り毎に動物を。
「きつねさん。」 「うさぎさん。」 「たぬきさん。」 「いのししさん...」
何度繰り返したか分からない。しかし確実に、ドアの外の悪意は薄れている。
? 翠はドアの向こうを凝視したまま、黙っている。
一区切りついたタイミングなのに?? 取り敢えず詠唱を中断する。
「お父さん、分からない。あれは、見たことない、から。」
見たことがない? そうか! これが最後。もう鎮魂でなく、祝詞を奉る時。
泣きそうな顔の翠をしっかり抱き締めた。
「翠のお陰で助かったよ。大丈夫。残ってるのはきっと、山の妖だから。」
動物たちを愛するが故に、猟師に殺された動物たちの怒りと共振し、
我を忘れて同じような魂を次々に取り込んだ妖、外の気配の『芯』。
しかし、それは事故のようなもの。本来は人に災いをなす事を意図する存在ではない。
動物たちの憎しみが解けた今こそ、元の姿で野山に帰って頂くのが筋。
「其処に座って。これで最後だよ。」 ドアに正対し、翠と並んで座る。
眼を閉じて背筋を伸ばした。深呼吸。
『詫びに1つ、礼にもう1つ。』
澄んだ声に続いて、俺たちの目の前に青い小さな鬼火が2つ、並んで浮かんだ。
そうか、憎しみと悪意が消えたから結界を抜けて。 しかしそれなら何故家の中へ?
『その名に縁ある季節を二度、迎えられるように。』
次の瞬間、気配が消えると同時に鬼火も消えた。 『雪』に縁の有る? 二度の、冬?
「お父さんすご~い。あれも、ことだまの術なんだね?すごく、きれいだった。」
「そうだけど、翠だってあの妖と話をしてたでしょ。怖くなかったの?」
「ぜんぜんこわくなかったよ。だって、お父さんがいっしょだし。」
翠は目をぱちぱちと瞬いて、如何にも眠そうだ。
「それに、みどりのお友だちは、とっても、つよい、から。」
お友達???
「ちょっと翠、お友達って。」 翠の体から力が抜けた。完全に熟睡している。
直後。窓ガラスが大きく揺れた。 突然の強い風。 空気を震わせる、羽音?
そうか、鵬。 きっとSさんが。
「お前が一人前の術者だなんて。SさんとLさんには本当に感謝しなきゃね。」
振り向くと台所の入り口に母が立っていた。
「私の力では、お前をそこまで導くなんて到底出来なかった。」
「もちろん2人には感謝してるよ。ただ俺なりに、長い間修行してきた。
でも、翠は修行する前から、俺には関知できない妖の気配を感知してた。どういうことかな?
翠はまだ5歳だし、得体の知れない人外との接触が多過ぎるのは、ちょっと心配なんだ。」
「『式使い』の適性を持っていれば、修行と関係なく、どうしても人外との接触は多くなる。
親がしっかりと見守れば良い。恐れず気を抜かず、親の義務を果たすだけ。
それより、きっとその子は並外れた術者になる。
あの妖が説得に応じなかった時に備えて、式をこの家の屋根に配置した。
妖が勝手口に近づく前にね。それからその子の『●識△』。
融合した多くの魂を1つ1つ見分ける力。そしてお前の『言霊』。
2人の力と術が補い合い高め合って『分業』の術が発動した。
未熟ではあるけれど、あれは紛れもなく『分業』の術。」
『分業』? その術を使える術者は限られる。いわゆる、『奥義』の1つ。
恐らく現在は、当主様と桃花の方様のみ。Sさんでさえ。それを、俺と翠が??
「実際に見たのは初めて。『●識△』はその基になる力だけど、
お前の助けを借りたとは言え、あの歳で...本当に、驚いた。」
母はゆっくり、深く息を吸った。
『R。』
これは、言霊...そうか、俺の適性は母から。
「何だよ、急に改まって。わざわざ言霊を使わなくても俺は。」
『きっとこれが、私が今生で使う最後の術。心して、聞きなさい。』
今まで見た事のない、母の表情。台所の空気が凍った。
『遠からず、お前にこの子を支える資質が有るかどうかが問われる。
この子はお前の子であると同時に、優れた術者の命脈を繋ぐ一族の子。』
翠を支える資質を問われる? それは。
「あら、雪、どうしたの?」
母の視線を辿り、勝手口を振り返る。雪がお座りをして母を見つめていた。
ついさっきまで、ぐったりと横になったままだったのに。
「もしかして、何か食べたいのかな?」 「そうね。雪、ちょっと待って。」
母は作り置きのお粥を冷蔵庫から取り出した。鍋に水を加えて少し温める。
母の作ったお粥に一握りの削り節、それは雪の大好物。
少しずつ、なめるようにお粥を食べる雪の背中をそっと撫でる。
俺の顔も母の顔も、涙でぐちゃぐちゃになっていた。
翌朝、雪はしっかりとした足取りでトイレに行き、水を飲んだ。
それからまた少しエサを食べ、昼過ぎまで寝ると、見違えるように元気になった。
夕方前には翠と一緒に庭を歩き回り、エサもいつもの半分ほどの量を完食。
更に翌日、朝から近くの公園へ散歩が出来るまでに回復した。
俺と翠が実家を後にしたのはその日の昼過ぎ。雪は最後まで俺たちを見送っていた。
深夜のリビングに涼しげな音が響く、Sさんが作ってくれたハイボール。
Sさんが夕食の後片付けをしている間、Sさんの部屋で翠と藍を寝かしつけた。
その後、丹が熟睡するまで姫の部屋にいて、リビングに戻ったのが10時少し前。
今夜はどうしても、Sさんと話がしたかった。もちろん『分業』の術、そして母の言葉の意味。
「美味しい。喉が渇いてると、気分良く話が出来ないし。」
ハイボールを一口、もう一口、Sさんは俺の隣で微笑んだ。
「『分業』の術の基本は寄り集まった『業』や『魂』を見分けること。
それをもとに『業』の一部を別人に分けたり、迷った『魂』を中有に誘導する。
だから、あなたと翠が使ったのは確かに『分業』の術の1つ。
ただ、術者2人の力と術を組み合わせてそれを発動するなんて、聞いたことも無い。
普通の父娘以上の絆で結ばれた2人だからこそ、よね。ちょっと、妬けちゃうかも。」
Sさんは悪戯っぽく笑って俺の肩に頭を預けた。
「冗談は止めて下さい。その絆を結び合わせたのはSさんの術なんですから。
それより、翠と僕が使ったのが本当に『分業』の術なら、
母の言葉はそれと関係してるのかも知れませんね。」
「お母様は何て?」
「『僕に翠を支える資質が有るかどうかが問われる。』って。
「翠が最後まで式に指示を出さなかったのは、あなたへの信頼が深かったから。
『お父さんなら何とかしてくれる。』 『お父さんがどうしようもないって言うまでは。』
その抑制が効かず、一度でも力が暴走したら、翠は即『上』の監視対象になってしまう。
あの歳で式の使役を許されたのは、あの子が『私とあなたの子』だからよ。
私もあなたも、『上』から範士として認定されている。翠の教育を任せても良いって事。
ただ、その力が暴走するのを防ぎつつ、あの子の資質を全て実現するのは並大抵じゃ無い。」
Sさんは体を捻って俺の唇にキスをした。
「でも、それがあなたと私と、そしてLの望み。それで良い?」
僅か5歳の子。もし...いや、怖れることなどない。母はそう言った。
「『子供を作ろう』って相談した時のこと、憶えてますか?」
Sさんは小さく頷いた。出会った時と変わらない、いや、もっと美しい横顔。
「あなたは『力があろうとなかろうと、持って生まれたものと向き合う人生以外有り得ない。
幸せになる方法を2人で教えてあげれば良い。』って。私、本当に泣きそうだった。」
「それは今も変わりません。ただ、変えなきゃいけないことがあって。」 「何?」
「『僕は少し頼りないかも知れないけど、Sさんが母親だから絶対に大丈夫。』そう言いました。
でもSさんに頼り切りじゃなく、僕も少しは父親らしい父親になりたいんです。
今なら少しは術者としても、そして父親としても。」
Sさんはハイボールのグラスをテーブルに置いて、俺の左隣に座った。
俺を見つめる、黒い双眸。
「あなたはもう一流の術者。名指しの仕事、増えてるでしょ?
それに、父親としては超一流。丹が生まれた時のことも式のことも、
翠があなたを信頼しきってるからこそ上手くいった。ただ...あの術だけは。」
突然、Sさんの眼から涙が零れた。俯いて、両手で顔を覆う。 ??? 一体これは。
いつの間にか、姫がリビングの入り口に立っていた。雰囲気が、いつもとは全然違う。
「『奥義』を使う術者には、その結果に責任を負う覚悟と、ふさわしい『器』が求められます。
翠ちゃんは子供ですから、この場合は翠ちゃんを支え、その力を補う術者に。」
そういう、事か。
俺の評価が多少上がったとしても、当然Sさんや姫の評価には遠く及ばない。
俺と翠、二人でその『奥義』を使ったとして、その結果の責任を俺が負うのは当たり前。
「つまり、今後も翠を育てる資格があると、僕自身が証明しなければならない。」
「3日後、です。明日から食を絶って準備を整えた後、『上』が迎えが。
『五日行』。それを成就出来れば、Rさんは今まで通りに翠ちゃんと...」
その時、姫がお盆を持っていることに気が付いた。小さなガラスの御猪口が3つ。
「Rさんの五日行が成就する事を願って乾杯しましょう。どうぞ。」
一口飲んだ後、俺は事態の重さを理解した。
中
『上』が用意した車がお屋敷に着いたのは、ピッタリ打ち合わせ通りの午前九時。
大きな黒塗りのワゴン。運転していたのはサングラスとマスクの男性。
術者なのだろうが、身振りで俺を促しただけ。何だか話しかけちゃいけない雰囲気。
ただ、行の内容についてはSさんや姫も知らないと言っていたから、この術者も多分知らない。
行を修めるのは山の中の小さな庵、そこに案内と指南の術者待っているらしい。
事前に知らされた情報はそれと、あの乾杯。
とんでもない重圧をひしひしと感じている状況で、あれこれ話す気にもなれなかった。
数時間の後、着いたのは寂れた登山口のような場所。濃い霧。重い湿気が辺りを覆っている。
県境を越えてからは俺の知らない道を通ってきたので、ここが何処なのか分からない。
車を降りて数歩。霧の向こうに人影が見えた。背後で、車が走り去る音。
『久しいな。』 柔らかな声、いや、それより『久しい』って...
「R、です。宜しくお願いします。」 声を掛けてさらに数歩。その姿がハッキリと見えた。
アオザイ?に似た服。上着は漆黒の生地に、艶やかな、黒い絹糸の刺繍。
ズボンはネットとかTVで見るより細身で、活動的というか実用的。
それに何より、キリリと結い上げた髪が印象的な美形。
姫よりは年上で、Sさんより年下。なら多分、二十代後半。
これが、案内&指南役? まさか、女性とは思わなかった。
でも、何だか、懐かしい雰囲気。 『久しいな』という言葉通り、初めてという気がしない。
それはこの女性のまとうオーラなのか、それとも声の響き、か。
「あの、以前何処かで。」
「御影、だ。この姿で会うのは初めてだから、分からなくても無理はないな。」
!? まさか...一族最強の式。それにどうして、人の姿?
「この場所は特級の霊域、今様に言えば最高のパワースポット。」
確かに。車を降りた瞬間から、この辺りに満ちる濃厚な気に圧倒されていた。
「しかし『聖域』とは違う。『聖域』を支配しているのは『秩序』だが、
この場所を支配しているのは『混沌』。だから正邪・陰陽を問わず、全ての怪異が力を増す。
ここでなら、我も人の姿に化生することが出来る。
ただ、もう二度と、人の姿を取る事など無いと思っていた。」
その女性、御影さんは少し寂しそうに見えた。
「さて、着いて参れ。」 「あ、はい。」
濃い霧の中、御影さんの背中を追いかける。
細い砂利道は段々と傾斜がきつくなる。やはり登山道?
15分ほど歩いた所で、御影さんの足が止まった。 「あれ、だ。しかし、何故。」
白い手が指し示す先に小さな建物が見える。古い、庵? しかし、あの気配は。
さらに数分、その建物から20m程の距離。
やはり、そうだ。建物の周りにも中にも、かなりの数の気配を感じる。
これでは修行場と言うより、妖の巣窟。人はとても、こんな所に長くは居られない。
「あの年寄りは、何故管理を怠っているのだ。今回の話も通っている筈なのに。」
御影さんは薄く笑った。 「人の身では...面倒だな。」
面倒も何も、これだけの数を祓うには下手をすればそれだけでゆうに3日。
すい、と前へ踏み出した。2歩、3歩。其処此処で妖の気配がざわめく。
御影さんは立ち止まり、そのまま右足を横に踏み出した。両足の幅は、肩幅くらい?
深く息を吸いながら右手が肩の高さに...天に向けた掌が反って地面に向かい、
右足は地面を掃きながら左足に揃った。御影さんの体が膨らんだように見える。
次の瞬間。重力に逆らうように軽々と、ゆっくりと、その右足が高く上がった。
ぴいんと伸びた右足のつま先はほぼ真上を、天を指している。
そして掴むようにしっかりと、地面を踏みしめた左足。
天と地から、『正気』が御影さんに集まるのを感じる...これは、四股。
「... ..」 微かな呟きが聞こえた後、右足が落ちてきた。
そう、切られた大木が倒れるような、圧倒的な迫力と重量感。
地面が揺れる。 Sさんより少し背が高い分体重は、しかし幾ら何でもこんな。
続いて左足。地面を踏みしめる地響きが、完全に空気を変えた。
まるで嘘のように庵の周りの霧が晴れ、妖の気配も一つ残らず消えている。
小さな庵はしん、と静まって、先程までとは全く違う建物のように見えた。
「5日は楽に保つだろう。何をボンヤリしてる。行くぞ。」
「あの、御影さん。今の四股は。」
「元々我は一族で武術を指南していた家の出。
だからこそ当主様は我に任せたのだ。5日間この庵を護り、お前の世話をし、
更に修行の相手をする。そんな事が出来る人間は、術者は、もう3人といないから。
荷物を解いたら直ぐに行を始める。5日はあっという間だ。」
...痛、息が出来ない。思わず膝をつく。
「我は武門の出と言った筈だ。こと武術に関して、他人に遅れを取ったことはない。
女子だと思って甘く見ていると、そのうち死ぬぞ。」
それは古武術で言う当て身の一種、左脇腹へのボディーブロー。
襟元で艶やかに光る瑪瑙の飾り細工。 「これを取れ。」と御影さんは言った。
「そのためなら何をしても良い」と。 ただし御影さんの反撃は投げと
腹への打撃だけと言われていて、当然警戒していたのに、為す術がない。
その動きはあまりに迅く、強かった。
これでは瑪瑙を取るどころか、触れる事すら出来る気がしない。
「御影さん、相手に、甘く見たりなんか。」
まだ、まともに息も...
「なら、少しは工夫する事だ。参れ。」 涼しい顔で、御影さんは構えを取った。
裂帛の気合いと共に、御影さんが視界から消えた。
派手に視界が回転し、腰から床に叩き付けられる。まともに受け身も取れない。
もう何度目? 3日前から始めた絶食のせいにする気にもなれない程の、技量の差。
「今日はこれで終いだ。今夜まで食を絶って此所に体を慣らせば、
明日の朝からは食事を取れるだろう。それで少しは。風呂を沸かしておく。」
最初の修行は『体』。3段階の行の内、第1段階からこれでは、先が思いやられる。
小さな湯船に浸かっていると、不思議な事に気付いた。
あれだけの打撃と投げ、でも体の何処にも痛みがないし、痣もない。
道着を着ていても、肘や膝に擦り傷の一つくらいは出来る筈なのに。
ふと、微かな声が聞こえた。 澄んだ、優しい声。 歌、だ。
風呂場を出る。声の聞こえる方へ、庵の奥へ進む。
台所らしい土間、障子を開け放った大きな窓に、御影さんが座っていた。
「何か、用か?」 「ああ、いや。あの、歌が。とても良い声だったので。」
少し照れたような微笑。何だか、可愛い。 「昔、習った。遠い、遠い昔に。」
しかし、御影さんの微笑みはすぐに陰った。
「今夜は早く休め。明日中に進展がなければ、行の完成自体が危うい。」
そうだ...『五日行』。既にその一日は過ぎてしまったし、未だ何の進歩も。
御影さんが用意してくれたのだろう。俺の部屋には布団が敷かれていて、
潜り込むと途端に眠くなった。やはり、疲れてる。布団の中は、少しだけ黴臭かった。
2日目の行が終わっても目立った進歩は無かった。
自分なりに色々工夫しているつもりだが、伸ばした腕を取られて投げ飛ばされるか、
そうでなければ腕を弾かれて腹に打撃をくらう。これでは昨日と何も変わらない。
行を成就出来なければ、俺は『失格』だ。それでは今後、翠の...
暗い気持ちで夕食を食べ終わり、風呂に入った。やはり気持ちは晴れない。
風呂から出ると、歌が聞こえてきた。心を決めて台所へ向かう。
「何か、用か?」
「はい。助言をしてもらおうと思って。」 「助言?」
「どうしたら、御影さんの動きに対応できるのか。助言は、禁止されていませんよね?」
「助言、か...」 御影さんは窓の外の景色に視線を移した。遠い目。
「お前の適性を活かす方法を考えろ。
前にも言ったように、此所では正邪・陰陽を問わず、全ての怪異が力を増す。
勿論お前の体も、その適性も。さて、明日も早い。もう休め。」
そうは言われたものの、明日中に進展が無ければ行の完成が危うい状況。
到底寝付ける筈もない。布団の中で考えを巡らす。俺の適性を活かす方法とは。
どの位そうしていたのか。
自分の呼吸音がやけに大きく聞こえてきた。やがて、心臓の音も。
他にほとんど音がない場所、例えば砂漠の真ん中で野宿すると、
そんな風に感じると聞いたことがある。確かに此所は、いや、幾ら何でも音がデカい。
そうか。『此所では正邪・陰陽を問わず、全ての怪異が力を増す。』
此の場所の力を得て聴覚が力を増し、普段は聞こえない音を捉えているのか?それなら...
やはりそうだ。『気配』を探る時のように、チャンネルを合わせるイメージ。
まるで俺の聴覚が庵全体に拡大したように、注意を向けた場所の音を聞くことが出来る。
『言の葉』の適性を持つ術者が力を発揮できるのは『会話』が成り立つ場面。
だから『話す』前に『聞く』ことが不可欠。そして、それは俺の何よりの得意分野。
思わず上体を起こした。右手に注意を向ける。深呼吸、そっと眼を閉じた。
拳を握る...聞こえた。種々の雑音に混じって、何かが軋むような、微かな音。
拳をゆっくりと正面に突き出す。雑音に続いて、今度はもっと低い、大きな、音。
もう一度、今度は思い切り拳を突き出そうとした時に、
『それ』が雑音の中からハッキリと聞こえた。
チューニングがズレたラジオのような音。 多分、これだ。 もう一度。
『それ』の後に、軋むような音や低い音が混じって聞こえてくる。
軋むような音や低い音は筋肉と関節が発する音。なら、『それ』は神経が発する音だ。
最初の行は『体』。御影さんが術を使うのでは『体』の行にならない。
それに化生している以上は、此所では御影さんも生身。
それなら幾ら技量の差が有っても、体を動かすしくみは俺と同じ。
つまり筋肉が動く前に...次の瞬間、俺は音の洪水に飲み込まれた。
神経を流れる電流、筋肉の動き。体中を巡る血液の音は、まるで滝の音のようだ。
体全体を震わせる心臓の拍動、それから嵐のような呼吸音。
信じられないほど多彩に、絶え間なく変化する音は『意識』そのものか。
体中の細胞が『生きている!!』と叫んでいる。
まるでそれらは、全ての生命活動が渾然一体となって織りなす、音の、極光。
『生きている』とはどういうことか、それをまた1つ体得したのかも知れない。
それだけで、此所に来た意味がある。
構えを取った御影さんの体に、注意を向ける。深呼吸。
...聞こえた。音の高さは俺と違うが、組み合わせは大体同じだ。
そして『それ』が聞こえた直後。
「どうした。じっとしていては、進歩は無いぞ。」
間違いない。これが、鍵。
それからの約一時間、俺は繰り返し『チューニング』を続けた。
投げと打撃、左構えと右構え。注意深く、御影さんの音を俺の音からより分ける。
「駄目、だな。むしろ昨日より反応が遅い。昼食の後で休憩、続きはその後だ。」
「ちょっと、待って下さい。」 振り向いた御影さんは怪訝な顔をした。
「昼食の前に、あと1回だけ。やっと、分かった事があるんです。」
少し目を細めた後、御影さんの表情が引き締まった。
「良いだろう。参れ。」
深呼吸、肩の力を抜いて右腕を軽く振る。
全速で右足を踏み込みながら右腕を伸ばした。勿論これはフェイント。
御影さんがフェイントに反応しないのを確かめてから左腕を。 『それ』に耳を澄ます。
聞こえた! この音は、俺の左腕を弾いて、右拳の打撃。思い切り体を左に捻った。
腹をかすめた右拳を、右手で。速い、僅かに上方にずらすのが精一杯。
ずらして出来た隙に左腕を伸ばす。しかし、瑪瑙の冷たい感触で無く、柔らかで温かな。
予想以上の力で左手が巻き取られ、跳ね上げられる。投げ。
堪えて距離を詰めれば背後から右手で。踏み込んだ分、投げの形が崩れた。
しかし、バランスが。まずい。
右のこめかみと肩に鈍痛。少し、吐き気がする。
「大事ないか!」 珍しく、御影さんの声が慌てていた。それが何だか可笑しい。
「大、丈夫です。でも、もう少し。」
「受け身も取らずに、敵を庇うなど...馬鹿か、お前は。」
「いや、御影さんは敵じゃ無いし。それに、御免なさい。あの、さっき、胸に。」
御影さんはそれを俺の右掌に握らせた。冷たく、硬い感触。瑪瑙の、飾り細工。
「適性を活かした、見事な工夫。第一段階は終了だな。今日は、もう休め。」
御影さんは軽々と俺を立たせ、肩を貸してくれた。
夢を、見ていた。
旧いお屋敷の庭に咲き誇る赤い花。咽せるような、良い香り。
眼が、覚めた。枕元、すぐ傍に人影。 誰?
その人は俺の枕元に膝をついた。帯を解いて黒い着物をするすると脱ぐ。真っ白な素肌。
何の躊躇も無く、その人は布団の中に滑り込んできた。
滑らかな、暖かい感触が俺の頬を包む。大きな、黒い瞳が俺を見詰めていた。
...御影さん。
「あの、どうして?」
「健康な男子が此処にただ1人。過ごす内に肉欲が積もるのは当然。
そこにつけ込まれぬように。夜伽も、仕事の内だから。」
...ちょっと、待って。確かに、先刻胸に触れた時は少しだけ、でも。
「夜伽って、そんな。」 「気に病むことはない、何も。」
「いや、でも。」 「我では、不足か?」
「不足だなんて。御影さんはとっても綺麗だし魅力的です。
だけど、いくら仕事だからって、御影さんが望んでもいないことを。
御影さんにも、好きな人がいるかも知れないのに。」
御影さんは動きを止めた。ホッと息をつく。ギリギリ、セーフ。
『ならば、今、我がそれを望んでいると言えば良いのか?』
...全然、セーフじゃない。
『望むとか望まないじゃなくて。仕事でも、こんなことしちゃ駄目なんです。
それに、御影さんは凄く綺麗だから、御影さんに恋人がいたら、
その人はそれをとても誇りに、幸せに思ってる筈です。なのに、こんな...』
『御前は真の、言霊遣いなのだな。
以前、お前と同じ適性を持つ術者に出会った時と同じだ。
その言葉を聞くと不思議に温かく、同時に不安な心持ち。』
褒められてるのか貶されてるのか、俺は。
『我は口下手だし、未だ旧い想いの熱も冷めぬ。
だから我の記憶を御前に見せる。お前と同じ適性を持つ術者に出会った時の記憶。
その上での判断は、御前に任せよう。』
目の前の、澄んだ瞳。細い腕が俺の頭を抱く。
閉じた瞼にキスの感触を感じた後、意識が遠のいた。
頭が、痛い...召喚?
随分と長い間、寝ていたような気がする。最後に働いたのは何時だったろう。
呪文は続いている。止めてくれ。頭が、割れるようだ。
正直、これなら死んだ方が余程...鬱陶しいが、『契約』は全てに優先する。
「契約に基づき、汝に命ずる。」
見たことの無い顔。という事は、長の代替わりがあったのか。では、○明は。
「我が契約したのは●◇の家。お前と契約したのではない。」
「私は◆明、●◇の家の長だ。●◇の式を使役する正統な権限を継承している。」
やはり、○明は死んだのか。なかなかに力のある術者で、見所のある男だったが。
「話は聞くが、受けるかどうかは私が決める。」
「もしも、契約に基づく依頼を断ればどうなるか」
「何時でも消える覚悟はある。式となっても、我は殆ど一族の為に働いていないから。
契約に背いた罰則で我を縛れるなどと、思わない方が良い。」
男の右頬がピクリと動いた。伝わってくる、荒い波長。 こんな男が●◇の家の長とは。
暫く寝ている間に、一族には何が起こっていたのだろう。
「その、まさに一族の為の仕事だ。一族の命運を左右する、重要な任務。」
「他の式でなく、我を召喚したのだから、相応の覚悟があるのだろうな。」
「次の当主が決まった。しかしその男は、術者を軽んじ一族の未来を危うくする
危険な思想の持ち主だ。術者の誇りを、一族を守るために、その男を殺して欲しい。」
「そんな思想を持つ者を、『上』と『眼』が次期当主として認証するとは思えないが。」
「術者の育成を巡る考えの違いで、●◇の家は一族を離れた。
その後、奴等の中で術者を軽んじ、力を持たぬ者を重視する輩が力を増した。
『新しい時代に対応した一族の在り方』などと詭弁を弄して、な。
私は、術者の力を尊重し、術者の力で一族の未来を開きたい。力を貸してくれ。」
「次の当主となれば相応の力、返り討ちになる可能性も有るだろう。
しかも式を使って一族の者を殺めれば、お前には血縁相克の大罪。
どちらにとっても割に合う仕事では無いな。」
「割に合う、報酬を約束しよう。成功すれば、契約を解く。つまりこれが、最後の仕事だ。」
「我自身が、報酬か。面白い。」
今更自由を得ても人の身には戻れない。だが、面白いのは、依頼の対象。
それがどんな人間なのか、何故術者を軽んじるのか、知りたい気もする。
そう、今のままではあまりに、退屈だから。
「依頼を受けよう。しかし勝負は時の運。成功の保証は出来ない。
日が沈む。完全に夜の帳が下りるのを待って目的地に移動した。夜こそ、我の時間。
小さな、屋敷。2階建て、部屋の数はせいぜい8つ...本当に、次の当主が、此所に?
屋敷を護る結界はなく、護衛の姿もない。あまりに不用心ではないか。
罠? いや、我に罠など。 笑止...返してみせる。
灯りの点る窓は3つ、2階にはそのうちの1つ。あれが、仕事の舞台。
闇に融けて壁を抜け、家の中に入り込む。そして部屋へ。部屋の中にも護衛はいない。
大きな机、革張りの椅子に背中を預けた後ろ姿。この時間、護衛なしで暢気に本を?
気配を抑えたまま、ゆっくりと近付く。やはり罠ではない。
少なくとも、相応の警戒をするように『上』からの指示があった筈だ。何故、この男は?
じりじりと、距離が詰まる。もう、十分。万が一にも
「少しだけ、待ってくれないかな。」
!? 今、我に、呼びかけたのか? この男は。
「そう、君だよ。どうして僕を殺すのか、理由を聞いてみたいと思ってね。」
その男は椅子ごと、くるりと体を回した。人の良さそうな顔に、悪戯っぽい笑顔。
その目はしっかりと我を見つめている。 閉じた本を机の上に。
『見えるのか、我が?』
「ああ、見えるよ。僕はそういうのが、ちょっと得意なんだ。だけど、『◇話』は苦手。
だから出来れば、声を出して話してくれると有り難い。このままだと、疲れる。」
夜、侵入してきた式と対峙して、それが自分を殺しに来たと知っていながら...『疲れる』?
「自分の置かれた状況は、理解している筈だが?」
「勿論理解してるさ。あっさり君の侵入を許し、その気になれば君は僕を殺せるかも。」
その男は笑った。押し殺した声で、如何にも可笑しそうに。
「これ、かなりマズいよね。」
「何故、笑う?」 罠も、護衛もなし。この状況からどうやって我を。
「だって、僕が今夜あっさり殺されたら、僕を次の当主に選んだお偉い方々の間違いだろう?
だから、『なんであんなのを選んだ?』って大騒ぎになるよ。笑っちゃうね。」
「他人事だな、まるで。」 本当に、その神経は一体どんな。
「確かに、今でも他人事みたいだ。僕が次の当主だなんて。」
また、男は笑った。去勢を張っているようにも、自棄にも見えない。晴れやかな笑顔。
「あ、それで君も此所へ来たんだろう?
僕が次の当主に決まったから、僕を殺せと頼まれた。ね、君にそれを頼んだのは誰だい?」
「馬鹿げた質問だ。その質問には答えを得られないと、分かってるだろう。」
「そう、だね。まあ、大体予想は付いているし。ただ、確かにその人の指示なら、
おとなしく殺されても良いかなと思ってて、だから確かめたかった。」
この家に結界がなく、この部屋に護衛がいないのは。
「わざと、我を侵入させたのか?」
「わざとって言われると心外だな。かなりの手間をかけて君を止める結界を張っても、
ずっと結界に閉じこもる訳には行かない。そして僕が結界を出て襲われれば他人を巻き込む。
それに、無駄死にになるって分かってるのに護衛の術者を置くのは可哀相だろう?
あ、ちょっと失礼。」
ドアの外、廊下を近づいてくる気配...とうに気付いていた。恐らく高位の術者。
もしこの男がそれを隠していたら、術者が加勢に入った瞬間に、まとめて殺すつもりだった。
「○さま、凪です。先程から微かに不審な気配が。念のためお部屋の警戒を。」
「ああ、来客だよ。心配要らない。下がって休みなさい。」 「しかし、今夜来客の予定は。」
男は我を横目で見て、悪戯っぽい笑みを浮かべた。
「妙齢の美しい御婦人でね。夜の密会という訳だ。後は察してくれ、朝まで。」
溜息、遠ざかる気配。我の気配に気付くなら相当な術者だが、それよりも。
「本当に、見えているのだな。我の姿が。『妙齢の』と『美しい』は余計だったが」
「見えるって、はじめにそう言ったろ。それに、僕は余計な事なんて言ってない。
僕たちとは年の取り方が違うから、見かけで判断するしかないんだけど。
そうだな、二十代前半、第一級の美人。まあ、勇ましすぎる服が玉に瑕かな。」
「...お前と話してると妙な気分だ。何だか自分の感覚に、自信が持てなくなる。」
「いや、君は自信を持って良い。僕は美人が大好きで、要求水準がかなり高いからね。
あ、そうだ。」 男はまた椅子ごと体を回して机の上から写真立てを取った。
「ほら、凄い美人だろう?これが僕の妻で、娘のSが3歳の時の...御免、脱線し過ぎた。」
「分かれば良い。それで、もう一度聞くが。」 「何、かな?」
「わざと、いや、分かっていて我を侵入させたのは、
本当に『おとなしく殺されても良い』と思ったからか?」
「そうだよ。今も、そう思ってる。」
「当主なら、一族の為に、自身の命を大切にするべきだろう。お前が死ねば、それは。」
駄目、だ。やっぱり感覚がおかしくなってる。我はこの男を殺しに来たのではなかったか。
「僕はまだ当主じゃ無い。それに、君を寄越した人が僕の予想通りなら、
僕が殺される事でその人の憎しみが少しは緩むんじゃないかと思ってね。」
「本家と分家の争いは承知している。普通に考えて、分家に勝ち目はない。多勢に無勢。
戦いを長引かせるだけで、分家はやがて瓦解する。憎しみを緩める目的が分からない。」
「憎しみが緩み争いが終わるなら、それこそが望むべき結果。
一刻も早く争いを終わらせ犠牲者を減らす。それより優先すべきものが有るとは思わない。」
...『犠牲者を減らす。』 前に、同じ言葉を聞いた事がある。何時?
「争いを終わらせるために、お前自身が最後の犠牲者に、なると言うのか?」
「僕たちがどんなに手を尽くしても争いを終わらせる事が出来ないのは、
あの人の憎しみが解けないことも大きな原因だろう、だから。
勿論死ぬのは怖いし、未練もある。特に妻と娘を残していくのは...娘は、まだ6歳だ。」
愛する妻と大切な娘を残して、それでも自らの命を捧げて、争いを終わらせると?
頭が、痛い。心の底に沈んでいた記憶が浮かび上がり、心の旧い傷が。
「何故だ?言っただろう。戦うなら夜を、我の帰りを待てと、あれ程。」
弱々しい咳。我の腕の中で、その人は真っ赤な血を吐いた。
「太陽が地平線に隠れた直後、敵襲...夜まで待てば、村に残った人達を、だから。」
黄昏時に力を発揮できる亡者が混じっていたのか。一体、どうやって?
「でも、村の人々に、被害は出なかった。力を持たぬ人々の、犠牲を増やしてはならない。
成る可く早く戦いを終わらせ、彼我の、力を持たぬ人々の犠牲を最小限に。
だから、俺と共に戦った術者達は納得してくれたと思う。だが。」
「だが、何だ?」
「お前は、褒めてくれるか?俺たちは村の人々を守ったと。」
「ああ、お前達は、お前は良くやった。お前の力も我が教えた術も、全て越えて。良くやった。」
「そうか、なら」
我の腕の中で、あっけなく、その人の体から力が抜けた。
何故だ? 何故だ...
村の人々を守っても、お前を失ってしまったら、我はどうすれば良い? これから。
「今、一体何と?近しい者を奪われた憎しみに呑まれれば、結局お前も闇に。」
「いいえ。憎しみに呑まれてなどおりません。ただ、あの御方の言葉を実現するために。」
そう、あの人は言った。『成る可く早く戦いを終わらせ、彼我の犠牲を共に最小限に。』と。
「どうか『黒の宝玉』を我に。宝玉の力で変化し、成る可く早くこの戦を終わらせましょう。
敵味方に関わらず、力を持たぬ人々の犠牲を最小限に、それが、あの御方の願いでした。」
「いくら類い希な『適性』を持つとは言え、女子の身で、其処までせねばならぬとは。
それにもし失敗すれば其方は、それではあまりに、過酷な...」
「女も男も、問題ではありませぬ。当主様のお慈悲は、どうか、あの御方と我の菩提の為に。」
「承知した。戦が終わったら◎×とお前を偉大な先達の列に。」
「有り難う、存じます。」
遠い、記憶。あれから、どれだけの時が流れたのか。
まさか今また、同じ言葉を。ならば我は。
「家族の話を聞いたから言うのではないが、犠牲などという考えは止めた方が良い。
あの男の頭の中には争いを終わらせるなんて考えは全くない。
あの男は本家の人間を殲滅して争いに勝つ事しか考えていないから。
それはあの男が組織した戦闘集団の術者たちも同じ。完全に洗脳されている。」
「そうか、なら別の手を...あれ?
君は僕を殺しに来たんだろう?どうして僕にそんな事を。」
「お前を殺すのは、気が進まない。正直に言えば、お前を殺したくない。」
「でも、契約に基づく仕事だから、もし違反したら君は。」
「我が消えても大した影響はないが、お前が死ねば、一族は未来を失う。そんな気がする。」
そう、もう潮時かも知れない。あの戦いの為に変化したが、
戦いの後、人外と成り果てた我が身を式としたのは、偏に一族を守るため、それなのに。
我の力を恐れる術者は、我に任務を与えることをも恐れた。
大した仕事も出来ず、挙げ句の果てに、一族の者の暗殺を請け負うなど、本末転倒。
長い時間の内に、我の感覚は曇っていたのだろう。
「『●△の大難』から一族を救った式を失うのは惜しい。君が美人だからと言う訳でなく。」
「お前は我を、知っているのか。」 背筋が冷える、それなら事前に対策することも。
「君を寄越した人の予想が付けば、寄越す式の予想も付く。分家、いや、一族最強の式。
一族の大難に際し、黒の宝玉を身に着けて変化となり、多くの敵を倒した。
敵の反撃で黒の宝玉が欠け、変化を解くことは出来なくなったが、
それでもなお一族を守護する誓いを立て、自ら式となった。真に偉大な術者。
その功績と名誉は今も大切に、確実に伝承されている。
だからこそ君に、一度会ってみたかった。君になら、殺されても良いと思った。」
「昔の、話だ。今はこのような任務を請け負う程、堕落した影に過ぎない。」
「君が堕落したんじゃない。堕落したのは契約を引き継いだ術者達だ。
契約の効力を一族全体の為でなく、一部の者の偏狭な考えの為に利用した。」
「契約がある限り、従う。だが、お前を殺すくらいなら、契約ごと、我が消えよう。」
「今此所で、契約を解除する方法がある。」 「まさか、一体どうやって?」
契約の当事者双方が同意しない限り、契約を解く事など。
男は机の引き出しから白木の小さな箱を取り出した。幾重にも施された厳重な、『封』。
「僕たちは史実を伝承するだけでなく、何世代にも渡ってずっと探し続けて来た。
一族の大難を救ってくれた恩に報いるために。 そして去年、とうとう見つけた。
一度は確保しながら、戦いの後の混乱で行方知れずになっていたもの。
あの戦いに協力した土着の術者の家を経て、小さな資料館の収蔵庫に保管されていた。
それが此所にある。失われた、『黒の宝玉』の欠片。
これがあれば、君は契約当時の君ではなくなる。つまり、契約は自動的に失効する。」
既に宝玉と融合した体の変化を解くことは出来ない。
だが、失われた欠片を補えば変化が完成し、変化に許された力を全て使う事が出来る。
確かに、契約も失効する。しかし。
「何故だ?何故最初からその話をしなかった?何故わざわざその命を危険に曝した?」
「...確かめたかった。」 「何を、だ?」
「自分に当主たる器が有るかどうかを。
もし君に殺されるなら、僕には器がないという事だから。」
「変化が完成すれば、お前は絶対に我を殺せない。それなのに。」
「だから言ってるだろ。殺されるのは僕に器がないからで、それは僕自身の責任だ。」
その御方は白木の箱に触れて一気に封を解いた。躊躇無く、その蓋を取る。
「さあ、取り給え。これは、君の物だ。」
「それで、確かめた結果は?」
「...僕に、当主の器があるということなのかな。あまり、気は進まないけどね。」
「気が進まないのでは困る。お前が当主にならなければ、契約は発効しない。」
「え、契約って。それはさっき失効したから君は。」
「新しい、契約だ。お前は美人が好きだと、そして我を美人だと言ったな?」
「確かに、そう言ったけど。」
「ならば、よもや我の願いを断る事はあるまい。」
足下に膝を折り、その御方の左手に口づけた。
「尊き御方。我が名は◎×◇。
貴方様に従い、貴方様を守るとお誓い申し上げる。どうか我を僕に。」
「ええと、その、気持ちは嬉しいんだけど。契約はちょっと。」
「何故?」
「だって、勝手に君の契約を解除して、おまけに君を僕の式にしたと知れたら、
あの人は怒り狂うに決まってる。戦いを終わらせるのがもっと難しくなるよ。
あっさり僕を殺して、少しは溜飲を下げるつもりだったろうから。」
「貴方様の僕になれないなら、我の力は無用の長物。生きる意味も無い。
ならば、せめて戦いを早く終わらせるよう、あの男を」
「待った。契約していなければ僕は血縁相克の大罪を回避できるけど、
あの人を殺したら、君は一族全体の仇として報復の対象になってしまう。
契約した術者を殺すなんて、それは式として絶対に。」
「望むところ。それがどんな相手でも反撃はしない。心穏やかに、座して死ねる。」
そう、この御方が、我に対し反撃の手段を全く用意していなかったように。
「参ったな。正直、君の契約を解いて自由の身にする所までしか考えてなかった。
恐らく君は、愚かな人間達の無益な戦いに辟易しているだろうと思っていたからね。」
「人は愚かかもしれない。だが我はその愛しさに賭ける。我も、かつて、人であったから。」
重い沈黙の後、その御方は深呼吸をした。
「さっき話した問題点を解決して、君の希望を叶える方法は1つしかない。
君が僕の暗殺に失敗して死んだ事にする。『上』を通してそう発表するんだ。
『分家の式が次期当主を暗殺しようとしたが失敗した。式は死んだ。』と。
死ねば契約は解除されるし、契約が解除されればあの人は君の動向を把握出来ない。
暗殺失敗には怒るだろうけれど、それは当然想定すべき結果だ。
でも、君にとっては相当な不名誉だよ。君ほどの式が任務に失敗するなんて。」
「貴方様に負けた。それで良い。名誉など要らぬ。」
「本音を言えば、君が助けてくれるなら本当に心強い。でも、契約するには条件がある。
君は当分対外的な任務には関わらない。出来る限り、君の存在を隠すためだ。どうかな?」
「御意。」
「では、君の新しい呼び名を。ええと。そうだ、
君は決して堕落した影なんかじゃない。だから、みかげ、御影はどうかな?」
「有り難う存じます。」
その御方の、照れたような笑顔が眩しい。
「それで...御影は、出来ればこれからずっとその服でいて欲しいな。凄く、綺麗だから。」
「御意。」 全てこの御方の、仰せの通りに。
今日も水平線に陽が沈む。
夜の帳が下りれば、彼方此方の影に拡散していた我の感覚は1つに繋がり、
この場所を覆う大きな傘となる。この場所から少し離れて、あの御方のお社とお屋敷。
あの御方は本当に、敵対する術者の殺害を我に命じなかった。
あの御方の命を狙い、以前の私を差し向けた、あの狂った男の殺害さえも。
私に与えられた御役目は、『聖域』の境界の守護。
この場所を護り、この場所から『聖域』に侵入しようとするモノを排除する。
ふと、感覚の端に違和感。星影に紛れた、微かな、気配。
「秋津殿、戯れが過ぎると、今に間違いが起きよう。そうなっても、責任は取れない。」
「見破られたか。さすがは御影。これなら『聖域』は安泰。安心して隠居出来る。」
我の前任者、一族の黎明から今までを見守ってきた、最古の式。
「して、本日は何の御用かな?この所、穢らわしい船で近づく不心得者が増えて忙しい。
正直、暇な御老体の相手をしている暇は無いのだが。」
「綺麗な顔をして、相変わらず取り付く島も無い。せめてもう少し愛嬌があればの。」
「もし我に一片の美あれば、それはあの御方のため。他の誰のためでもない。」
「...しかし其方がどれ程想いを掛けようと、あの御方は人の身。
その真心も、美しい漆黒の衣も、報われる事はあるまいに。」
「既に全てが、報われている。それにもし報われずとも、我の心は変わらぬ。」
「まあ良い。美味い酒が手に入った、夜光の杯もこの通り。付き合うてくれ。」
「肴を用意しよう、今の季節なら。」
「錆び鮎の塩焼きかな、茸の蒸し焼きもあれば猶良い。」 「贅沢な年寄りは嫌われる。」
「そう言わずに。ほれ、一献。見よ。望月が美しい。何度見ても、な。」
確かに、何度見ても美しい。これから何百年の後もずっと。だが、何時かあの御方は...
いや、今は考えない。ただ、日々心を込めて、あの御方に与えられた任務を果たす。それだけ。
そう今は、それだけで良い。
下
眼が、覚めた。腕の中の、温かく滑らかな感触。
Sさんか姫、でなければ翠。 そっと抱き寄せて...いや、待て。そういえば昨夜。
一気に高まった鼓動に混じって聞こえてくる、これは、寝息?
その寝顔は何だか可愛くて、安らかで、見ているだけで胸の鼓動が静まっていく。
自分の事だけでいっぱいいっぱいだったから思いが至らなかったけれど、
ここへ来てから御影さんは何時、いや、そもそも寝ていたのか。
『特に寝る必要はない』と管さんから聞いた事がある。『必要ならずっと起きていられる」と。
でも管さんとは違う。『生身の体に化生したのは初めてだ』と御影さんは言った。
それなら、こんな風に眠るのは一体何年振りなのか。
あの四股の効果はまだ続いているから、何の問題も無いのだろうけれど、
それにしてもこんなに無防備な寝顔を。もう少しでも寝てもらった方が。
その時、微かに身じろぎをして御影さんが眼を開けた。
「朝か?」 「いいえ、まだ夜明けまではもう暫く。」
「とても、気持ちが良い。もう少し寝かせてくれ。」 「はい。でも、今日の行は。」
「今日の行は、問題なく」 言い終わらない内に、寝息が聞こえた。
「『寸鉄人を殺す』の例えはこの術が出所だという話がある。
初めは蝋燭の火を消す。かわらけを割れるまでになれば充分。
此所では力が増しているし、恐らくお前はこちらの方が得意だろう。半日もかかるまい。」
言霊に物理的な影響力を与え、必要なら弾や刃としても使えるようにする術。
御影さんの言葉通り、その日の行は滞りなく成就した。
此所を出て力が元に戻れば、多分蝋燭の火を消すのがせいぜい。
でもきっと、依頼人に見せる手品代わりにはなるだろう。
それよりも適性を自分で細かく制御できる技術を習得した事に重要な意味がある。
(もちろんこれも御影さんの受け売りなんだけれど)
翌日は5日め、いよいよ最終日。
『五日行』が成就するかどうかは、最終段階の行の成否による。
ただ、その行は夜が更けてから始まるのだそうで、
御影さんは朝食の後出かけたまま、夕方前まで帰ってこなかった。
夕食の後、風呂。暫く部屋でボンヤリしていると、御影さんに声を掛けられた。
予め指示されていた白い道着に着替え、昨日まで修行していた板の間に移動する。
俺と御影さんは正対する位置で胡座をかいていた。
蝋燭の明かりが、御影さんの端正な顔をゆらゆらと照らしている。
「簡単に説明すると、今からお前はこの庵を出て更に登り、山頂を目指す。
その途中で幾つかの試練が用意されている。
最後の試練は山頂近く、小さな祠の前。其処で夜明けを迎えられれば行は成就。
案内の者が現れる筈だから、その者に着いていけ。」
此所を出るって事は...。
「それだと、御影さんが張った結界を出ることになりますね。」
「当然だ。様々な怪異がお前の行く手を遮ろうとするだろう。
だが、決して振り向くな。そして、引き返すな。何としても最後の試練を乗り越えろ。
もしも、それが...」
「最悪の場合、僕を処理する。そこまでが、御影さんの仕事なんですね?」
あの夜、乾杯した時に俺なりの覚悟はしていた。あれは、水杯。
御影さんは立ち上がり、背後に廻って俺を抱き締めた。
「無事に戻れ、必ず。お前を、殺したくない。」
背中に感じる温もりが急速に薄れ、ぞっとするほど冷たく。
『行け、時間だ。』 太く、低い声が響くと同時に、背中の感触は消えた。
庵を出て、山道を登る。思った程、妖の気配は強くない。
ただ、山道の斜度がきつくて、登り続けるのがかなり辛い。
次第に道も悪くなる。まさかこれが1つめの試練という事は無いだろうが。
暫く上ると道はやや平坦になった。額の汗を拭い、ペットボトルの水を飲む。
濃い霧の中、LEDの小さな懐中電灯が照らす範囲以外は、白い闇に閉ざされている。
一体、道を外れたらそこは。その時、それが聞こえた。俺の背後からやや離れて、足音?
思わず振り向こうとして、御影さんの言葉を思い出した。
『決して振り向くな、そして引き返すな。』
歩きながら耳を澄ます。気配は1つ。しかし、その足音。
少なくとも人ではない。絡まり合った足音に、何かを引き摺るような音が混じっている。
ゆっくりと、ゆっくりとそれは近づいて来た。 もうすぐ後ろ、何だか寒気がする。
ふと、笑みが浮かんだ。これでは、まるで同じだ。何も変わっていない。
子供の頃、夜道を通って家へ帰る途中、怖くて怖くて仕方なかった。
闇の中に、得体の知れない恐怖が潜んでいる気がして。しかし。
『本当に怖いのは、人の心の闇。』
そう、今なら俺は知っている。救いの無い真の闇が現出し得るのは、人の心の中だ。
それに今俺の後ろに感じる気配は、子供の頃に想像した闇に潜む恐怖そのもの。
それに気が付いた時、背後の気配は消えた。
最初の試練は俺自身の弱さが生み出した幻、あるいは俺の弱さにつけ込もうとした妖か。
どちらでも構わない。今はただ、前へ。次の試練へ向かうだけ。
その後も幾つかの怪異が現れたが、俺は御影さんの言いつけを守った。
決して振り向かず、引き返さず、道とも言えぬ細い道をただひたすら前に。
気味の悪い呼び声。助けを乞う血まみれの女性。子供騙し、だと思った。
此の場所に満ちる気で怪異は力を増している筈なのに、こんな。
現れる妖たちが何故これ程見え透いた手を使い、いとも簡単に引き下がるのか。
そう、修行の効果で俺の力が増している。化生していたとはいえ一族最強の式に、
あの御影さんに修行の相手をして貰ったのだから、誰も俺の行く手を阻む事は出来ない。
自信の裏に生じた微かな慢心。思えばその時から、俺は危険な陥穽に踏み込んでいた。
さらに歩き続け、11時を過ぎた頃、辺りの様子が変わった。
LEDライトで周りの様子を確かめる。草一本生えておらず、獣道のような痕跡も見えない。
ライトを右に向け、次に左。視界の端に何か見えた。小さな祠。
此所が、最後の試練の場。
歩み寄り、深く一礼。祠に背を向けて胡座を掻き、目を閉じて心を静める。
...ピチ...キン。冷えた岩が収縮する音。口笛のような高い音は岩の間を縫う風の声。
ゆっくりと、静かに時間が過ぎていく。一体どの位経ったろう。
このまま朝を迎えられればお屋敷へ帰れるし、今後もこの手で翠を育てる事が出来る。
そしてもし、藍や丹が優れた素質を現し始めたとしても、俺の資質が問われることは無い。
翠は、藍は、どうしているだろう。早く、一刻も早く帰りたい。その思いが隙を生んだ。
目の前に並んだ、小さな背中が2つ。見覚えのある、懐かしい景色。
「お父さんがいなくて寂しいね。翠は、お父さんが大好きなのに。」
「あのね、あいも、おとうさんだいすきだよ。」
「藍は男の子でしょ。翠は女の子だから、藍の好きとは違うの。」 「ちがう、すき?」
「そう、翠は何時かお父さんのお嫁さんになる。そして可愛い赤ちゃんを産むんだから。」
酷い目眩。確か、前にもこの光景は。あれは何時だったろう?
「お父さん。」
女の子が立っていた。7・8歳くらい?初めて見る顔と姿。
でも、確かに残る面影。間違いない、翠が成長した姿。
『あの人』の生まれ変わり、しかし宿った肉体が違うのだから成長した姿も「あの人」とは違う。
「修行が上手くいって良かったね。一緒に帰ろう。お屋敷に。」
歩み寄り、話しながらその姿は成長していく。 15・6歳? 綺麗だ。
「お屋敷に帰ったら、私をお父さんのお嫁さんにして。」
目の前に浮かぶ、美しい顔。潤んだ眼と、紅い唇が艶めかしい。
全身全霊をかけて育てる。そう誓った。では、育てた後は?
成長した後も、その願いが変わらないとしたら俺は...
いや、そもそも俺はその願いが変わることを願っているのか。もしも。
「今度こそ、きっと...R、さん。」
一瞬で、俺の心は覚めた。 『あの人』の記憶は完全に封じられたのだから、
翠が俺を『R』と呼ぶことはあり得ない。
御影さんの言った通り、これは俺の弱さと醜さ。
右掌に甦る、柔らかな温かい感触。心のずっと奥、未だ癒えぬ傷口。
分かってる。 助けたかった、叶えて上げたかった。 心残り。
弱く、醜い。 本当に俺が翠の父親としてふさわしいか、それは自分自身で判断すべき事。
もし俺が此所で死ぬのなら、俺には資格が無かったと言うだけ。
肩の力を抜き、深く息を吸う。
『・・・ ・・・ ・・・・・』
雷鳴を、聞いた気がした。 しかし雨の一粒も、黒雲が生む強風も、何一つ。
そして何時の間にか、暁の空が夜明けを告げている。
「まさか今の世に、『五日行』に挑む者がいるとは。長生きはしてみるものよ。」
小さな笑い声。振り向くと、灰色の法衣を着た老人が立っていた。これが、案内の。
「あきづ、だ。おや?」 老人の右半身。輪郭がぼやけて、やがて戻った。
「やれやれ、化生も満足に、年は取りたくないのぉ。さ、ついて参れ。」
発言に矛盾がある気もするけど、『あきづ』って、確か昨夜の。
「既に儂の名を。ふむ...あの唐変木に気に入られたか。何と不思議な。」
やはり、御影さんの記憶にあった一族最古の式。
それからは2人、黙って、険しい斜面を登り続けた。道とも言えないガレ場が続く。
空は次第に明るさを増した。たどり着いたのは少し開けた場所。
相変わらずの濃い霧で様子は分からないが、視界全体がボンヤリと明るい。
周りに明るさを遮る影は見えないから、きっと此所が山頂。
そして、その場所の中央近くに小さな祠。
「千年あまり前、此所に術者を1人案内した。それが、お前達の一族の開祖。」
小さな祠の後ろには大きな岩があり、その脇に...泉?
1m四方ほどの深み。清らかな水を湛え、そこから一筋の水が流れ出している。
「近付いて水底を見よ。ただし、まだその水に触れてはならん。」
険しい山頂に湧く泉、それだけで既に俺の理解を超えている。一体、水脈は?重力は?
『触れてはならん』という言葉には、当然その理由があるのだろう。気を抜くことは出来ない。
慎重に、流れ出しの反対側から泉に近づく。深さも1mくらい?思っていたよりも深い。
水面の反射を避け、ほぼ真上に身を乗り出した時、『それ』は見えた。
水底、他の石とはまるで違う。透き通る濃い黄色という言葉でしか表現できない。
これに比べれば琥珀やトパーズは黄色ではなく、茶色。
今まで、こんな色の宝玉を見たことは無い。そして何より、この形。
「見えるか。」 「はい、今まで見たこともない...何て、言ったら良いのか。」
そう、言葉が無い。俺の適性こそ『言の葉』なのに。
左、右。老人は首を大きくぐるりとまわし、ため息をついた。
「この宝玉が開祖を所有者と認め、代々の世嗣がその力を継承する事を許した。
それがお前たち一族の始まり。以来、開祖を此所に案内した儂は『眼』と称された。
秋津という名とは別にな。それが、あの御方が儂に残してくれた、一番の名誉。」
『眼』、御影さんの記憶に、確かその言葉も。 あきづ=眼=この老人。
何時の間にか、老人は小さな柄杓を手にしていた。泉の水を汲み、それを俺に。
きっとこれは『手水』の作法、正座をして深く一礼、右手で柄杓を受け取った。
今まで数えきれぬほど、体に染み込んだ所作。自然に、遅滞なく体が動く。
その水を口に含んだ時、俺は『五日行』の意味を理解したのだと思う。
そして恐らく、当主様の意図を。
「必要な修練を積まぬままでも、『力』を現し術を使う者は希におる。
術者を鍛え育てる手段を忘れた旧い家系、術者の家系以外でも変わり者は生まれるから。
大抵は極く簡単な術しか使えない、基本的な修練を積めば済む者たち。
しかし『奥義』に近づく事が出来る力となれば話は別。
これは、失われた時を埋めるための行。十数年を五日で、無理は承知の荒行。
例え試練を乗り越えても、宝玉に拒まれれば、灰も残らず焼き尽される。
さあ、戻ろう。既に使者が、いや、迎えの者が待っている筈だ。」
使者、か。この行を成就出来たかどうかを知るための。
それはそうだ。もし俺があの水で焼き尽くされたなら...自然に笑みが浮かぶ。
「まるで、他人事だな。ところで、聞きたいことがある。」 「はい、何でしょう?」
すいすいとガレ場を下るその老人を、遅れないように追いかけた。
「妖が見せた夢だと見破りながら、あの答えを選んだのは何故だ?」
「選んだ訳じゃありません。僕の中の答えは、あれだけでした。」
「...成る程、あの唐変木がお前を。」 「唐変木で、悪かったな。」
俺の右隣を御影さんが歩いていた。下って行く道の先に、あの庵が見える。
「御影さん、有り難う御座いました。お陰様で。」 「うん。」 小さな声、前を見て歩き続ける。
しかし『一族最古』と『一族最強』。 何で俺が、こんな豪華なシチュエーションに。
庵を通り過ぎても老人と御影さんは歩みを止めない。2人の後を追う。
「まさか、御自ら?」 「五日前も、そうだった。そういう、御方だ。」
??? 何の、話?
5日前、此所に来た時車を降りた場所に出た。やはり、あの時と同じ車。
2人が立ち止まり、揃って片膝を着いた。深く頭を下げる。一体、何?
運転席のドアが開き、男性が降りてきた。あの時の、でも今日はマスクとサングラスが。
!! あの時に気付いていた筈なのに、何故? 当主様なら、その気配だけでも俺は。
いや、今はそれどころじゃない。慌てて御影さんの右隣で片膝を着いた。
「まずは御影、Rの行が無事成就したのはお前の指導有っての事。礼を言う。」
「いいえ、私はただ。」 俯いた御影さんの頬が紅に染まっている。とても綺麗だ。
「それで、Rをどう見る?」
「その来歴故、最高位の術者としては未だ非力、心に巣くう虚も看過できません。」
「未だ荷が、重いかな。一族の希望を託すのは。」
「いいえ、時が経てば力は増し、想いが虚を満たしましょう。肝要なのは一途な情。
ならばこの者は一族の宝を託すに最適な術者。
一途な情の織りなす揺り籠、その強さと暖かさは余人を持って代え難し、と。」
「そうか、なら良い。Rにこの行を課した甲斐がある。」
当主様は微笑んで体の向きを変えた。
「さて秋津、何を見た?我が一族の『眼』が見たものを教えてくれ。」
「来たるべき者。既に生まれ、目覚めを待つ者。」
「そう、か...今後私がこの任を担うべき時間は?」
「十二乃至十五年。それまでは、どうか。」
「長いな。それまで私は生きていられるか。」 「いざとなれば...」
御影さんと老人の姿がゆらりと薄れる。
老人の最後の言葉は聞き取れなかったが、当主様は微かに笑みを浮かべていた。
「さて、出発だ。皆も着いた頃だろう。」 当主様は踵を返した。慌てて後を追う。
『皆も着いた頃』って? 皆は今、何処に?
「もしお前を失えばSは正気を保てないかもしれないと、桃花の方が。
それで今朝、皆で私の館へ来るように伝えて置いた。
勿論お前ならきっと成し遂げると信じていたが、
最悪の事態に備えるのが私たちの仕事。気を悪くしないでくれ。」
「気を悪くするなんてとんでもありません。それより運転は、どうか私に。」
「いや、それは危険だ。此所を出れば一気に疲れが出るし、死ぬほど、痛いぞ。」
イタズラっぽい笑顔。 俺は先回りして運転席のドアを開け、膝を着いた。
当主様が乗り込むのを待ってドアを閉め、後部座席に乗り込む。
「あの、当主様、質問があります。」 「御影のことか?」
「はい。御影さんは当主様のことが好きなのに、何故御影さんの気持ちを。」
「御影の心には今もある御方がいて、私にその面影を見ている。
未だ心の古傷が癒えていないなら、心残りに縛られるのも無理は無い。」
そうか、御影さんの記憶。 御影さんの腕の中で息を引き取った、若い男性。
「当主様なら、きっと御影さんの傷を癒やせると思います。」 そう、御影さんは確かに。
「御影に宝玉の欠片を返したのは私の独断、当然異論も有った。
だから万に一つも、誤解を生みたくない。」
「誤解、ですか。」
「もし私が御影の想いを叶え此の場所に通っていたら、誤解する者が出ただろう。
『御影は好きな男のために寝返った。』と。今後も、それだけは避けたい。
私への想いとは関係なく、御影は一族に取って最良の選択をしようとしたのだ。
『●△の大難』を終わらせ、力を持たぬ人々を救うと心を決めた。
だから宝玉の器に変化して敵の主力を単騎で壊滅させ、
更に『●△の大難』の後は自身を式として一族を護ってきた。
その名誉を傷つけることは絶対に許されない。それに。」
一瞬、バックミラーの中から、当主様の視線を感じた。
「御影はお前にも、その御方の面影を見ている。そしておそらくお前の方がその御方に...
傷を癒やすのはお前の方が適任だし、お前が相手なら、要らぬ誤解をする者も出ない。
どうだ、時々は此所で御影と暮らしてみるか?それならあの庵をお前にやろう。」
「いや、でもそれは。あ、済みません。動転して失礼な物言いを。」
「冗談だ、気にするな。御影の傷が癒えれば良いとは思うが、互いの気持ちが最優先。
それに、『代役』が御影の心の傷を癒やせるかどうか、正直分からない。
ただ、癒えぬ傷の痛みに耐える強さを御影は持っている。そしてそれはお前も同じ。
傷の痛みに付け込まれても、闇に飲まれることは無いと自ら証明した。
そして、同じ傷の痛みに耐えている者だからこそ出来る心遣いがある。」
「お前なら、『同情』でなく御影に『共感』できるだろう。
これからはどうか、御影の良き友となってくれ。それだけは、頼む。」
「身に余、あっ...」 全身に激痛、息をするのも辛い。これが。
「境界を越えて体の強化が解けた。打撲の痛み、筋肉痛。
あと疼痛というか神経痛も。暫くすれば薄れてくる、それまではひたすら我慢。」
当主様の口調はいかにも気の毒そうだが、それも、正直少し恨めしい。
それから一時間あまり、俺は後部座席でのたうちまわった。
結
「それで、『来たるべき者』と『目覚めを待つ者』については詳しく聞かなかったのね?」
「はい。話の感じと12~15年っていう期間で、次の当主の事だと思ったんですけど。」
「ええと、翠ちゃんは女の子だから関係ない、と。」 「はい。」
Sさんと姫は黙って顔を見合わせた。 何となく気まずい、間。
「話してなかったから仕方ないけど、当主は男性って決まってる訳じゃ無い。
実際、今までに何度か女性が即位した例がある。
そういう場合は桃花の方を男性が務める。その女性の夫や兄弟、あるいは従兄弟。」
一気に血の気が引いた。 「じゃあ、もしかしてあの話は翠の?」
「それだけじゃない。藍にも、丹にも、可能性がある。」 「そんな、まさか。」
「可能性の話です。つまり、Rさんの行が成就した日にその質問をなさったのだから、
Rさんに関わりが有ると考える可能性が高い。そういう解釈も出来ますから。」
もし自分の子が...いや、慌てる必要は無い。当主様の代替わりは何時か必ず起こるのだし、
一族はそうやって千年余の命脈を繋いできた。それなら。
「その可能性があるとしても、今までの生活を変える必要はありませんね。」
「...どういう、こと?」 呟くようなSさんの声。姫も黙って俺を見詰めている。
「子供たちを一生懸命育てて、その資質が開花すれば、当然術者への道が開ける。
術者として更に成長した結果がどうあれ、受け容れる覚悟は必要です。
もし『それ』が3人の内の誰かなら、僕たち3人が出来る限りのサポートをすれば良い。
SさんとLさんは、あの子たちを産む時に、その覚悟をしてたんでしょう?
お待たせしました。僕もようやく、その覚悟が出来ました。」
2人は代わる代わる俺を抱き締めてキスをしてくれた。
その涙の美しさを、俺は一生忘れない。
そう、必要ならこれからも、どんな行にだって挑むことが出来る。
「ところで、子供たちの教育のために、考えていた事があるんです。」
Sさんと姫は涙を拭って俺を見つめた。
それから一週間程して、俺たちは雪をお屋敷に引き取った。
翠の仲介もあったのか、雪は管さんや鵬とも上手く馴染んだ。
晴れた日の午後、ウッドデッキで日向ぼっこをする狐と巨大な猛禽と秋田犬。
それぞれの大きさからして遠近感が滅茶苦茶な、不思議で心暖まる風景。
もちろん、家族皆が雪を愛し、あの妖が授けてくれた寿命が尽きるまでの2年間、
雪は俺たちに沢山の笑顔をくれた。 そして。
『契(結)』 完
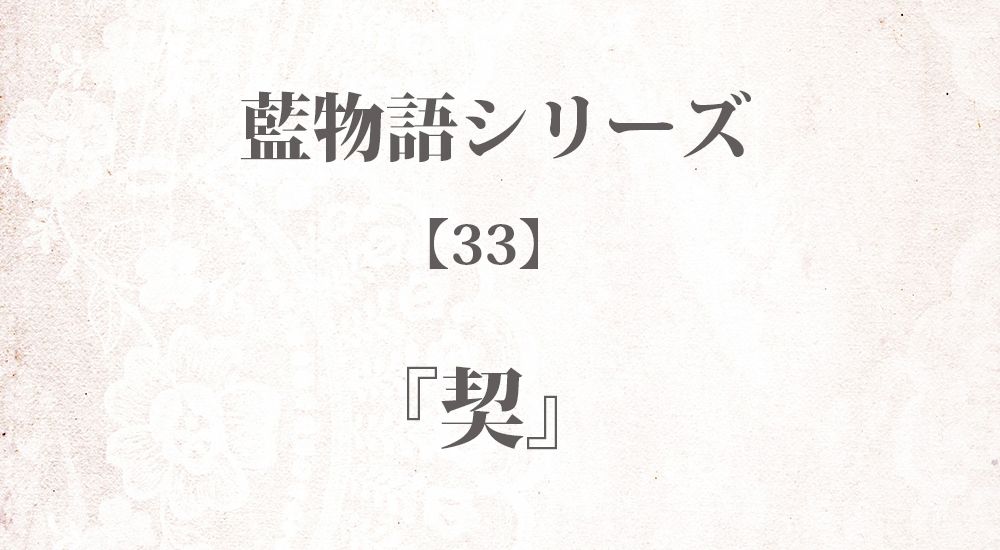
コメント