藍物語シリーズ【16】
『一期一会』
上
少しだけ開けた窓の隙間から吹き込む風は冷たく、冬が近いことを告げている。
翠も藍も暖かい寝床で昼寝をしているが、もう、窓を開けたままで過ごすには寒い。
俺はリビングの窓を閉めてまわり、ソファに戻った。
「本当にあなた達、入籍だけで良いの?式だけでも挙げた方が良いんじゃない?
一生のことなんだし、女の子にとって純白のウェディングドレスは憧れなんだから。」
もちろん身内だけで式を挙げることも考えたが、姫はそれを望まなかった。
姫には両親がいない。Sさん以外に近い親戚がいるという話も聞いてはいない。
根掘り葉掘り聞く気にはなれないし、姫の気持ちに添う形が一番だろう。
俺は両親に式や披露宴はしないと話をして了解をもらっていた。
特に反対もされなかったのは、両親がSさんに遠慮したからかも知れない。
「式を挙げる代わりに写真を撮ろうと思ってるんです。ちゃんとした写真館で。」
「結婚の、記念写真ってこと?」
「はい、親しい人たちには後でその写真を配れば良いかなと思って。」
「...それならまあ、それでL、着物、それともドレス?」
「あの、ドレスにしようと思ってます。着物はいつも着てますから。」
「じゃあドレスは『○×◎』で仕立ててもらえば良いわ。私が頼んであげる。
それに『○×◎』は写真館も兼ねてるからお誂え向き。ふふ、何だか楽しみね。」
Sさんは席を立って玄関へ向かった。早速『○×◎』に電話をかけるのだろう。
姫と俺が予想していた通りの展開。とても楽しそうだし、相変わらず気が早い。
『○×◎』は市内にある洋裁店兼写真館で、一族の人が経営していると聞いていた。
Sさんや姫は昔からお洒落着を仕立てて貰っていたらしい。
Sさんも姫も、普段からほとんど肌を露出しない。
姫も高校生になった頃から、夏でもノースリーブのワンピースをほとんど着なくなった。
今時のデザインから2人の好みに合う服を探すより、仕立てて貰う方が早いのだろうし、
オーダーメイドだからサイズもピッタリで良く似合う。
俺も『○×◎』の服は(というか『○×◎』の服を着た2人が)大好きだった。
その日の夕方、夕食の支度をSさんに任せて翠と遊んでいると玄関の電話が鳴った。
数回の呼び出し音に続いて電子音、さらにFAX用紙が吐き出される音。
「『○×◎』かしら。ドレスのデザインと見積もりを頼んだのは昼過ぎだから、
幾ら何でも早い気がするけど。R君、お願いね。」
「了~解。」 俺は翠を抱き上げて玄関へ向かった。
電話は未だFAX用紙を吐き出し続けている。デザインの候補は何種類かあるのだろうか?
最後のFAX用紙、末尾に記されていた文字と文様。『○×◎』の連絡先ではなかった。
腹の底が冷たくなる。これは『上』だ。つまり仕事の依頼。
俺は慌ててFAX用紙を並べ変えた、最初の用紙に記された件名。
『ポルターガイストに類似した事象に関する依頼について』
「おとうさん、『ぽるたーがいすと』ってなあに?」
「え~っと、これはお父さんとお母さんの新しいお仕事の名前。」 「ふ~ん。」
少し不満そうな翠を抱いたまま、俺はダイニングへ急いだ。
「確かにポルターガイストみたいですけど、これも陰陽師の仕事なんですか?」
「依頼者がキリスト教徒でないなら教会に頼む訳にもいかないし。まあ、仕方ないわね。」
夕食を済ませ、翠と藍を寝かしつけてから、Sさんは俺と姫をリビングに招集した。
配られたコピーを一通り読むと、その依頼の事件は確かにポルターガイストに良く似ていた。
湯呑みとお椀、それに本がひとりでに移動するという。
テーブルの上を動くのではなく、空中を飛んで移動するらしい。それも数mの距離を。
これまでに二度、いわゆる霊能者に依頼したが、霊能者の前ではこの現象が起きない。
取り敢えず祈祷や御祓いをして貰ったが効果はない。まあ、これも典型的だろう。
俺は依頼者の家族構成が気になった。
ポルターガイストが起こる家には、家族に思春期の女の子がいることが多いと聞いた事がある。
「いわゆるポルターガイストは、思春期の女の子と関係してると聞いたことがありますが。」
「5歳の男の子が1人。女の子でも思春期でもないし、この現象との関わりは分からない。
指定された日付けは3日後。物に関わることは私の領域だし、アシスタントは。」
「僕が行きます。Lさんは『○×◎』との相談があるかも知れませんから。」
依頼を受ければ下調べや準備でSさんが外出する事が多くなる。
それは、俺と姫が進めている計画にも好都合だった。
3日後は土曜日、みんなで昼食を済ませた後、俺はSさんを乗せて車を走らせた。
たまたま代理店に在庫があったのを即決で購入した以前と同じ型・同じ色のロータス。
違うのは年式だけ、当然ながら運転していて全く違和感は無い。快適なドライブになった。
依頼者の家は隣の○県△◎市、比較的古い町並みが残る地域。
「資料の住所からするとこの辺りですけど、細い路地が多くて分かり難いですね。」
「ちょっと其処のバス停に停めて頂戴。電話して聞いてみるから。」
依頼者の家は町並みの中でも一層古色蒼然とした小さな日本家屋。
ポルターガイストという言葉とは、どうにもかけ離れた雰囲気だ。
家の中に案内してくれた女性はYさん、ご主人は他県に単身赴任中で息子さんと2人暮らし。
俺たちはこぢんまりとしたダイニングに通された。
居間と土間をあわせてリフォームしたのだろう。4人分の椅子、細長いテーブル。
廊下を隔てた部屋は畳敷きの和室、調度も古びた和風のものが多い。
ふと気配を感じて振り向くと和室の奥に小さな男の子が立っている。
人見知りなのか、俺が振り向くとすぐに奥へと引っ込んでしまった。
Sさんは男の子のいた方向をチラリと見たあと、挨拶もそこそこに依頼の話を始めた。
「資料は全部読みましたが、今の所実害は無いようですね。
現在も変化がないのであれば、特別な対策を講じなくても良い気がしますが。」
Yさんは溜息をついた後、現象が次第に変化していることと、
その現象があの男の子に与えている影響について話し始めた。
「おかしな事が起こるようになったのは今年の8月頃です。
最初は私の思い違いかと思いましたが、9月の始めに本が飛ぶのを見たんです。」
「念のために聞きますが、落ちたというのとは、全然違うんですね?」
「はい、あの本棚からこのテーブルまでふわふわと。時間は2~3秒、だったと思います。」
Yさんが指さした和室の本棚からこのテーブルまではざっと5~6m。
当然、何かの拍子に落ちた本が移動する距離ではない。
「9月中頃からはお椀や湯呑みも移動するようになりました。」
「それも実際に見たことが?」 「はい、息子と一緒に見たこともあります。」
Yさんは一旦言葉を切って俯いたが、やがて、意を決したように顔を上げた。
「一番怖いのは息子のことなんです。息子はお椀が飛ぶのを見てとても喜びました。
そしてそれ以来、ひとりで遊ぶ時間が極端に長くなりました。」
「時間以外に、普通のひとり遊びと違う所がありますか?」
「息子が居間にいる時、他の誰かと一緒に遊んでいるような気がするんです。
話し声がしたり、突然笑い声が聞こえたり。もし何かが息子に干渉しているとしたら、私。」
「実際に誰かと話しているのを見たことはないんですね?」
「はい、私が居間に入るとそれらはピタリと止みますから。」
俺はメモを取りながら黙って2人の話を聞いていたが、突然Sさんに声をかけられた。
「R君、今の話どう思う。これ、本当にポルターガイストかしら?」
「いいえ、ポルターガイストとは違う、ような気がします。」 「どうして?」
「この家に来てから感じる気配が人間のものとは思えません。上手く言えませんが、
僕たちとは異質な感じがします。」
「そうね、確かに異質だわ。人間とは違う、でも動物とも言えない。どちらかというと。
いや、予見を持つのは危険。まずは確かめてみないとね。
Yさん、これからこの家で起きている現象の正体を確かめます。
ただ、依頼を受ける前にも聞いたと思いますが、
これから私たちのすることと、その結果起こることは、くれぐれも他言無用に願います。」
「はい、それは重々承知しています。」 「それでは、まず息子さんを此処へ。」
「剛君、私たちお母さんに頼まれて剛君とお話をしに来たんだけど。」
「僕、何も知らない。この家の中に友達なんていないよ。」
男の子の顔は冷たく強張っていた。おそらく以前に依頼した自称霊能者たちにも
色々聞かれて嫌な思いをしたのだろう。かなり強く心を閉ざしている。
「何かを聞きたいんじゃないの。知らない人たちに色々聞かれて、最近剛君が元気がないから
応援してほしいって、お母さんに頼まれたわけ。私たち、魔法使いだから。」
「魔法使い?」 少しだけ男の子の表情が緩んだ。
「そう、信じられないかも知れないから良い物見せてあげる。」
Sさんは持参したスーツケースから小さな鋏と紙を取り出した。いつもとは違う、黒い紙だ。
鋏で手際よく黒い紙を切り、それを左掌の上に乗せた。
「これ、何だと思う?」 「蝶々。」 「そう、紙の蝶々。ね、右手を出して。」
Sさんは男の子の右掌に紙の蝶々を乗せた。小声で何事か呟く。
男の子はじっと掌の上の蝶々を見ている。
「じゃ、その蝶々、天井に向かって飛ばしてみて。思いっきり強く。」
男の子は力一杯、紙の蝶々を投げ上げた。やはり、これは。
男の子の頭の上を大きな黒いアゲハチョウが一片、優雅に飛び回っている。
Yさんも信じられないという表情で蝶々を見つめていた。
『剛君、これから暫くの間、眠ってて頂戴。』
アゲハチョウはゆっくりと男の子の肩に舞い降り、紙の蝶々に戻る。
同時に男の子の目が閉じ、すうっと体の力が抜けた。
「眠っているだけですからご心配なく。R君、お願い。」
俺は男の子の体を廊下を隔てた和室に運んだ。母親が持ってきた毛布をかける。
「ポルターガイストがその家の子供と関係していたという事例もありますが、
剛君が寝ている状態でも何かが起こるとすれば、剛君は関係ありません。」
「でも、これまで来て頂いた方々の前では何も起こりませんでしたから、今回も。」
「それは、初めからポルターガイストだと決めつけて、その現象を止めようとしたからです。」
「ポルターガイストを止めないんですか?」 Yさんは不安そうな顔をした。
「ポルターガイストかどうか、確かめてみないと分かりません。
それにはまず、この現象の本来の姿を知る必要があります。
だから止めるのではなく、逆にお膳立てをするんです。
何の邪魔も入らない状態で、一体何が起こるのかを見るために。」
下
Yさんが家中のカーテンを閉めてまわる間に、
俺はSさんの指示通り、ダイニングの床に必要な物を準備した。
依頼に応じる際、Sさんが持参するスーツケース。通称『お出掛けセット』。
余程特殊な依頼でなければ、ほぼその中身だけで対応が可能な品々。
まずは白い杯に日本酒を注ぐ。黒い杯、こちらには米粒を盛った。
小さな燭台に細いロウソクを立てる。その間Sさんは鋏で紙細工をしていた。
銀色の星形、金色の半月形、そう言えば昨夜は下弦に向かう半月。
最後に白い紙から小さな鳥の形を切り抜いてテーブルの上に置いた。そして。
Sさんは立ち上がり、暗くなったダイニングの壁に切り抜いた星と月を貼り付けた。
貼り付けた星と月に両手をあて、目を閉じて何事か呟く。
「これで準備完了。ポルターガイストにしろ、何か別のものにしろ、怪異が力を増すのは夜。」
全てのカーテンを閉めきって灯りを消した室内は、昼とはいえかなり暗い。
その中でSさんの眼が輝いている。まるでこれから起こる事を楽しみにしているようだ。
「Yさんはこの椅子に座って下さい。護符を渡しておきますから、何が起きても大丈夫。
ただ、私が良いと言うまで声を出さないで下さい。良いですね?」
「はい。」 YさんはSさんから受け取った護符を首にかけた。
「さて、始めましょう。R君、ロウソクに火を点けて。」 「了解です。」
床に置いた燭台のロウソクにライターで火を点ける。
ロウソクに火が灯ったその瞬間、何故か部屋が更に暗くなった気がした。
俺もSさんの隣の椅子に座り、3人で床の杯とロウソクを見詰める。
白い杯に注いだ日本酒がロウソクの光を反射して妖しく光っていた。
わずか2~3分後。ロウソクの長さもほとんど変わらないうちに小さな物音がした。
食器棚の扉が滑るように開く。息を呑むYさんに、Sさんは『黙って』の合図をした。
開いた扉の奥から花柄の湯呑みが3口、浮き上がった。ふわふわと飛んで床に移動する。
次に木製のお碗が2客、同じように飛んで床に移動した。どれも床からは2cm程浮いている。
湯呑みとお椀は床から浮いたまま、ゆらゆらと揺れながら直径50cm程の円を描いて
ロウソクと杯のまわりを回り始めた。何とも奇妙で信じられない光景だ。
更に本棚から飛んできた文庫版の本が3冊、行列に加わった。
『・・うれし・・・ぬうち・・ひゃくとせ・・・でたき・・・』
微かに音楽が聞こえてくる。まるで祭のお囃子のように賑やかな調子と歌声。
これは..似た光景を以前どこかで見たことがある。
そうだ、付喪神。年を経た古道具が変化した妖怪たち。
顔や手足こそないが、これは百鬼夜行図に描かれる付喪神そのものではないか。
しかし。確かにどれも古そうだが100年も経っているとは思えない。
少なくとも文庫本は100年前には無かった筈だ。
それなら、やはり何者かがこの茶碗や本を動かしていることになる。
それが、ポルターガイストの本体。イタズラ好きの、霊。
その本体である霊を、Sさんは一体どうするつもりだろう。そっと様子を窺う。
Sさんは微笑みを浮かべて道具達の行列を見つめている。
俺の視線に気付くと、Yさんには見えないように、ゆっくりと口を動かした。
す・て・き・ね Sさんの口はそう言っている。素敵?この行列が?
さらにSさんの口が動く。 も・う・す・ぐ これ以上、何かが起こるというのか。その時。
ガタン。廊下を隔てた和室から大きな音がした。
大きな和箪笥、一番上の引き出しが抜け落ちそうな程に大きく開いている。
その中から薄い木箱が浮き上がった。
ふわふわと宙を飛び、お椀や文庫本の行列近くに着地する。
お椀や文庫本の動きが止まった。音楽も聞こえない。
木箱の蓋がパタンと跳ねて開いた。大小様々な油紙の包みが5つ並んでいる。
一番右端の包みがゆらりと浮き上がった。油紙がひとりでにほどける。鋏?
鋏はそのままふわふわと宙を飛び、刃を上に向けた状態で列のほぼ中心に移動した。
お椀や文庫本がゆらゆらと揺れ、行列は再び杯とロウソクの周りを回り始めた。
お囃子と歌声も聞こえてくる。前より音が大きくなっているようだ。
古道具たちの異様な宴に見とれていると、家の彼方此方から音が聞こえてきた。
家鳴りのような大きな音、コップがぶつかり合うような高い音。
まるで家中のあらゆる道具たちが宴に加わろうとしているようだ。
まずい、このままでは収拾がつかなくなる。
すい、とSさんが右手を伸ばした。掌に紙細工の鳥が載っている。
『とう・・こう』小さく呟いた瞬間、掌の上には鶏、赤い鶏冠の雄鳥が乗っていた。
十姉妹よりも小さな、玩具のような雄鳥だ。雄鳥が羽をパタパタと羽ばたかせると、
部屋中から聞こえていた音が一斉に止み、列の動きが止まった。そして、
雄鳥は小さい体に似合わぬ大きな時の声を上げた。
ふらふらと浮いていた道具たちは一斉に床に落ち、湯呑みが1口俺の足元に転がってきた。
そっと拾い上げる。 !? 熱い。 まるで、ついさっきまで熱いお茶が入っていたようだ。
Sさんが俺の手から湯呑みを取り上げて微笑んだ。
「これでお終い。R君、ご指名みたいだから鋏以外のものを片づけて。鋏は私が片づける。」
数分後、カーテンを開け、明るくなったダイニングのテーブルに道具たちが並べられた。
湯呑みが3口、お碗が2客、文庫本が3冊。そして木箱が1つ、その上に鋏が一挺。
「この道具たちに、共通点がありますね?」 Sさんは優しくYさんに問いかけた。
「はい、どれも、祖母が使っていたものです。この家はもともと祖母のものでしたから。」
「お祖母様は、系統は違えど私たちと同業、優れた術者だったんですね。
依頼された弊や代を切っている御姿を、見たことがある筈です。」
Yさんは息を呑んだ。「あの、どうして、それを。」
「まず、この件の依頼です。あなたがどんな伝でこの依頼をしたのかは知りません。
でも、術者に何の関係もない人が、私たちに依頼をする方法は無いんです。
つまりこの依頼をしてきた時点で、あなたは『関係者』。そして。」
Sさんは木箱の上の鋏を手に取った。まず全体を、そして刃の部分をじっくりと眺める。
「この鋏は術者が幣や代を切る時に使っていたものです。おそらく200年位前のもので、
今この型の鋏を作る職人はいませんし、その技術も伝えられていません。
壊れると術者が確実に廃棄しますから、おそらく現存するものはごくわずか。
私も実物を見るのは初めてです。時代の割にとても状態が良いのは、
ここぞという時にしか使わない『取って置き』だったからでしょうね。」
Sさんは大切そうに鋏を油紙で包み、そっと木箱の中に戻した。
「何人かの術者が受け継いできたこの鋏を、縁あってお祖母様が受け継いだ。
そしておそらく今年、この鋏は霊力を得て付喪神に変化したんです。
そして、お祖母様に縁のある古い食器や文庫本たちがその霊力に感応した。」
「じゃあ、今までの...」
「はい、これはポルターガイストではなく、『付喪神の宴』です。
もちろん年を経た道具が全て付喪神になる訳ではありません。
この鋏のように、特殊な用途で使われてきた道具が幾つかの条件を満たした時だけ、
付喪神に変化する可能性があります。百年以上の歳月は、その条件の1つに過ぎません。
私たちの資料でも確実な記録は数件、明治時代初頭の一件以来、約130年ぶりの記録。
極めて珍しい貴重な事例、私たちとしてはむしろこの家ごと保存しておきたいくらいです。」
呆然とSさんの話を聞いていたYさんは暫く黙っていたが、やがて頭を振った。
「いくら祖母の持ち物でも、どれほど珍しい事例でも、無理です。私には...
あの、古道具なら、塚を作って供養出来ませんか。針供養みたいに。」
突然、テーブルの上の木箱が音を立てて揺れた。Sさんがそっと左手で箱の蓋を押さえる。
そのまま、二言、三言。何事か呟いた。 Yさんは怯えた眼でそれを見詰めている。
「その方法も含めて、この現象を鎮める上で幾つか問題があります。
R君、Yさんに説明してあげて。」 「あ、はい。」
俺は必死で以前Sさんから教えて貰った記憶を辿った。
「まず、この鋏は壊れている訳ではないので、塚を作って供養する方法は使えません。
それに、変化した直後の付喪神には人間の霊のような善悪の基準が無いんです。
それまで御利益をもたらしていたとしても、ちょっとしたきっかけで
怖ろしい祟りをなす存在に容易く変化してしまう。そして。」
そう、おそらくYさんに取ってこれが一番大きい問題だろう。
「剛君と付喪神の間には、既に繋がりが出来ています。
おそらく剛君は心の中で付喪神を擬人化し、一種のイマジナリーフレンドとして
とらえている筈です。それをいきなり失えば、剛君の心の平衡が崩れてしまう。
そうなると、どんな影響があるのか全く予測がつきません。」
「でも、このままでは私も剛も...一体どうすれば。」
「私に、引き取らせて頂けませんか。箱ごと、この鋏を。」
「え、引き取るって?」 Yさんは驚いたようにSさんを見詰めた。
「私たちにとってはとても貴重なものです。それに。」 Sさんは木箱の蓋をそっと撫でた。
「私の適性はお祖母様と同じ、これも何かの縁でしょう。
鋏を引き取らせて頂ければ、この件に関して報酬は一切頂きません。
それと、剛君には代わりの『お友達』を作り、暫くの間それを残しておきます。
剛君の交友関係の発展に合わせて、その存在がゆっくりと薄れていくように。
それで全て解決、如何ですか?」
「是非、それでお願いします。」 Yさんはホッとした表情で深々と頭を下げた。
Sさんは白い紙から先程の鋏と良く似た形を切り出した。相変わらず見事な技だ。
大きく開いていた和箪笥の引き出しの中にそれを貼り付ける。
閉じた引き出しの中に感じる気配。1年か、2年か、剛君に本当の友達が出来るまで続く術。
「これで良し。剛君は自然に眼を覚ますまで寝かせてあげて下さい。
その間に新しい繋がりができます。そして今後は、小さな子供に良くあるひとり遊び、
そう考えて見守ってあげて下さい。何の心配も要りませんから。」
「はい。本当にありがとう御座いました。」
「それではこれで失礼します。R君、荷物をお願い。」
「はい。」 『お出掛けセット』は既に片付けてあるし、すぐに出発できる。
「Yさん。最後に1つだけ。」 「はい、何でしょう?」
「この家を含め、おそらくお祖母様の遺品はどれも私たちに取って貴重な資料です。
その管理はあなたには負担だとは思いますが、散逸すれば取り返しがつきませんし、
思わぬ事態を引き起こすかも知れません。もしも今後、この家を手放す事をお考えなら、
その前に是非ご相談下さい。出来るだけのことをさせて頂きます。」
「はい、有り難う御座います。」 Yさんの表情は見違えるように明るかった。
県境に向かう山道、ロータスは快調なエンジン音を響かせている。
「Sさん、質問があるんですが。」 「なあに?」
「あの鋏、どうするんですか?」 「どうするって、私が使うのよ。『取って置き』にして。」
「ちょっと待って下さい。わざわざ付喪神をお屋敷に持ち込むんですか?」
「有るべき所に落ち着いて新しい役目をもらえば悪さはしないわ。
それに、あの鋏が使えたら、いざという時私の術も強化される。式が一体増える程度だし、
翠も藍も式で慣れてるからほとんど影響は受けない。だからお願い、ね。」
Sさんは大袈裟に両手を合わせた。 全く、この人は。
しかし実際、俺はSさんが何体の式を使役しているのかを知らない。
「『上』に止められる可能性は無いんですか?」
「もちろん。だってあれはあくまで道具で祭具じゃない。
それに、今あの鋏を使いこなせるのは、一族の術者の中で私だけだもの。」
思わず笑みが浮かぶ。いつも通りだ。こと『術』に関して、この人の自信が揺らぐ事は無い。
得意そうな、イタズラっぽい笑顔。それが本当に、愛しい。
「仕方無いですね。でも本当に、気を付けて下さいよ。」
「ありがと。あなた、愛してる。」 Sさんは俺の左頬にキスをした。
翌日、朝からSさんは上機嫌だったが、
姫と一緒に出掛けた『○×◎』から帰って来ると、少し不機嫌になっていた。
それは更に翌日の月曜日、今日になっても続いている。
「もう良い加減に機嫌直して下さいよ。僕もLさんも息が詰まりそうです。」
「だって、私、太ってたのよ。新しいドレスの採寸だったのに。ウエストが3cmも。」
家族皆で写真を撮る時のために、Sさんも新しい黒のドレスをオーダーしていた。
「2人目の子供を産んでウエスト+3cmなら奇跡的じゃないですか。
それに、胸も大きくなってるんですから、バランスは崩れてないし。
むしろ僕は今の方が好きです。全然問題無いですよ。」
方便ではない。Sさんは出逢った頃より雰囲気が柔らかくなり、俺はそれが嬉しかった。
「ホントに?」 「はい。3人目も年子、間違いないって感じですね。」 「う~ん、それは。」
ようやく良い雰囲気になった所で玄関の電話が鳴った。Sさんが受話器を取る。
「はい...そうですか。いいえ、潔い覚悟だと思います。私たちにお任せ下さい。」
それから2・3分話した後でSさんは受話器を置いた。
「Yさん、ですか?」 「そう、家ごと手放すから協力して欲しいって。」
今後、あの家とYさんの祖母の道具には『上』の調査が入るのだろう。
もしも貴重な資料が得られれば、それは術の研究に役立てられる。
11月26日、姫の誕生日。朝食の後、俺と姫は役場に出掛けて婚姻届を出した。
一度お屋敷に戻り、今度は家族5人で『○×◎』に出掛ける。
既にスタッフは準備を整えて待っていてくれた。姫のドレスが壁に掛かっている。
姫が選んだウェディングドレスは細いウエストから裾が大きく広がるデザイン。
長身で細身の姫にとても良く似合う。お伽噺から抜け出したような、文字通りの、お姫様。
薄いメイクと着付けを終えた姫の姿を見てSさんは涙ぐんだ。
「素敵。L、あなた、とても綺麗よ。」 Sさんはすっかり母親代わりの気分らしい。
「有り難う御座います。」
「Sさんのドレスも仕上がってますよ。着付けとメイク、今度はSさんの番です。」
「え、だって私は。」
『○×◎』のスタッフがドレスに掛けられていた覆いを取った。純白のウェディングドレス。
Sさんのために俺と姫が相談してオーダーしたドレスだ。
こちらは体のラインを強調した大人っぽい、それでいて肌の露出が少ない清楚なデザイン。
「何かプレゼントを用意してるのは分かってたけど、まさか、こんな...」
「もちろんこれは僕たちからのプレゼントです。
それに、『ウェディングドレスは女の子の憧れ』って言ったのはSさんですよ。」
「おかあさん、ないたらダメ。おいわいだから。」 「そうね。ごめん、ね。」
泣き止んだSさんのメイクと着付けが終わるのを待って、記念の写真を撮った。
(俺もタキシードに着替えて、髪型を整えてもらった。所要時間5分強。)
最後に家族5人で撮った写真は、大きく引き伸ばしてダイニングの壁に飾ってある。
藍を抱いて椅子に座ったSさんの右側に姫。翠を抱いた俺はSさんの左側。
皆の、眩しい笑顔。いつもは写真写りの悪い俺も屈託無く笑っている。
深く強い縁で結ばれた5つの魂。今更にその出会いの不思議さを思う。
Sさん、姫、翠、藍、4人と過ごす毎日を大切にして俺は生きてきた。
家族で過ごす時間は、その一瞬一瞬が愛しく、かけがえのないものだ。
きっと皆も同じだろう。そしてこれからも、お互いを大切にしながら皆で生きていく。
一期一会を、一生のものとするために。そしていつか、新しい家族を迎えるために。
結
「R君、ま~たLの写真見てにやけてるのね?もう夕食の準備をする時間でしょ。」
「良いじゃないですか。RさんはSさんのウェディングドレス姿が大好きなんですよ。」
「おとうさんはみどりもだいすきだよね?」 翠を抱き上げ、深く息を吸った。腹に力を込める。
『うん、お父さんは翠も、藍も、お母さんも、お姉ちゃんも、みんな大好きだよ。』
「わあ、キラキラいっぱい。きれい、これなあに?」
『一期一会(結)』 完

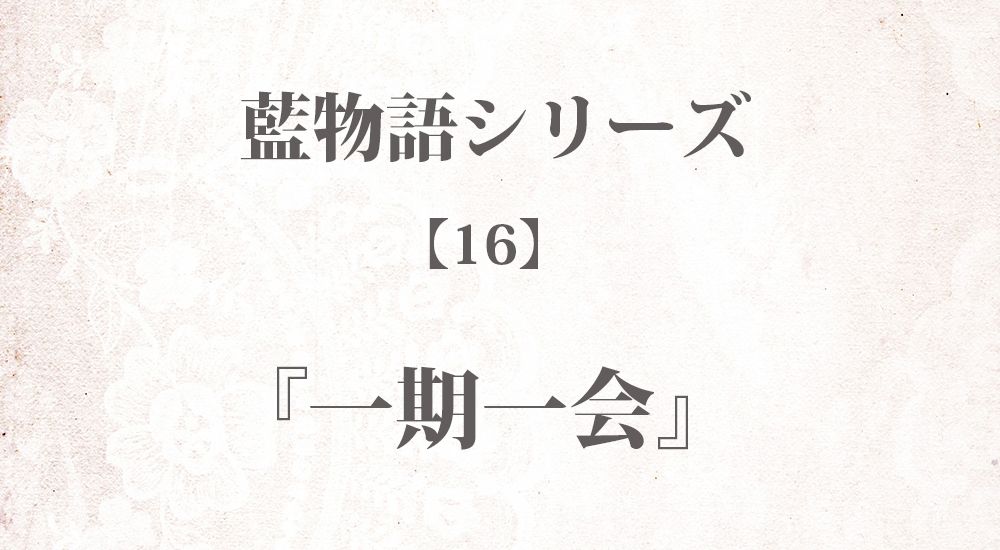

コメント