藍物語シリーズ【40】
『風の花』
「もうすぐ霜月が終わる。なのに何故、今年は未だ雪が降らぬ?」
「雪だけではありません。湖の御神渡りも。このような年はかつて無く。」
「冬が来ないまま新しき年を迎える事など、決してあってはならぬ。」
「左様、かくなる上はあの者達に、依頼する他ありますまい。」
「...一族の陰陽師、か。」
「はい。その神器、『青の宝玉』は天候を自在に操ると。ならばあるいは。」
「致し方ない、すぐに連絡を取れ。報酬も十分に用意せよ。」 「御意。」
『上』からのFAXに眼を通したSさんが、それを俺の手に。
「どう考えても、これはR君の領分だわ。」 そっと重ねた温もり。
「何故、僕の?」 「だって、『釣り』と関わりがある依頼だもの。」
...そうか。『釣り』なら、確かにそれは、俺の領分だ。
その依頼は、遍さん経由だと聞いていた。
それなら、納得出来る。普通の人が術者に依頼する経路は無い。
一族内部の問題か、あるいは古くからの『貴客』。
その依頼を『上』が受理すれば、然るべき術者が指名される。
ただ、内部の問題ならSさんが既に把握していた筈。
つまりこれは『貴客』からの依頼なのだろう。
しかも、それは遍さんに所縁の。絶対に失礼は許されない、という訳だ。
数日後、とあるホテルで依頼人に会う事になった。
Sさんも姫もいないが、遍さんが立ち会って、依頼の内容を確認する。
依頼人に会う時、スーツを着たのは、初めてかも知れない。
自然と気が引き締まる。
思わず眼を、疑った。依頼人は少女、16~18歳位?
美形という訳ではないが、不思議な気品。
年齢に見合わぬ落ち着きというか、どっしりと揺るがぬ存在感。
それより、こんな年端もいかぬ少女の依頼が『上』に? この少女が、『貴客』?
「これが、この件を担当する予定の術者、Rです。
一族最高位の術者の一人であり、何より『海』と『釣り』に縁があります。
きっと、貴方のご期待に添えるものと。」
遍さんの口調はまるで、当主様や桃花の方様に謁見する時のようだ。
『上』の主要なメンバーが依頼の場に同席するだけでも異例なのに。
続いてありきたりの自己紹介。その間中、心の奥で鳴り続く、警報。
危うい。遍さん経由の依頼なら尚更、これは。
俺の懸念を拭うかのように、遍さんは穏やかな表情で言葉を紡ぐ。
「父親の死にともなって、彼女は相当な遺産を相続した。
だから、報酬の用意について問題はない。身元も、依頼人として十分。
そして依頼の内容は、御本人から説明して頂く。」
「父を、成仏させて欲しいんです。その、迷ってしまったみたいなので。」
??? 『迷ってしまったみたいなので』 どういう、意味だ。
「あの、御父上が、何か障りの原因になっているという訳ではないのですか?
正直な所『迷ってしまったみたい』と言うのは、今まで聞いた事がありません。」
死者が迷う事も、それが原因で生者に障りが出る事も珍しくは無い。だが。
「先日、使用人達とともに実家の整理をしておりました。
夕刻になり、作業に区切りを付けようとした時です。
父の書斎に灯りが点いていると、使用人が。
その日は一番に父の書斎を掃除しました。窓を開けて風を通しながら。
その部屋は東向きで、日中に灯りを点ける必要などありません。
窓の閉め忘れとかならともかく、何故灯りが?」
違和感、それとも既視感。その感覚を、何と表現すれば良いのだろう。
たかだか高校生の、この少女の物言いは。
余計な言葉も感情も挟まず、単純に的確に。それは御影さんの話し方に似ていた。
「それで御父上の、書斎に入ったのですね?」 「はい。」 「それで?」
「父が、いたのです。いいえ、父だと、思いました。
私の記憶の中で一番若い父よりも更に若く、まるで少年のようでした。」
「此の世に留まる死者が、自ら望む姿で現れるのは珍しくありません。
しかし、2つ疑問があります。どうして貴女はそれが御父上だと。
そして、その御姿を見て『迷ってしまったみたいだ』と仰ったのも。」
「古いアルパムに、父の写真が残っています。それで。
思わず声をかけましたが、父は怪訝な表情で。私が誰か分からないようでした。
そして『君は誰?』と。父が私を憶えていないのなら、それは...」
その時初めて依頼人は、その少女は感情を露わにした。
零れる涙。嗚咽を堪えて震える、小さな肩。
「先程の話の通り、私は多分、海と釣りには幾許かの縁があります。
しかし、本来の適性は『言霊』。大変失礼な質問かも知れませんが。」
少女は握り締めていたハンカチで涙を拭き、顔を上げた。
俺を真っ直ぐに見詰める。灰緑色の瞳。
「何でも、お答え致します。それが必要な問いであるのならば。」
「生前、御父上は記憶を蝕まれるような病を?
それなら、貴女の事を憶えていないのもあり得ると思うのですが。」
「父の死因は○だと聞きましたから、脳の障害があったとは思えません。
それ以前にも、認知症を疑うような言動はありませんでした。」
「それでは御父上が、迷われたとして、その原因は一体何でしょう?
色々な前例がありますが、この件については、それが御母様だとしか。」
「何故、ですか?」
首筋に、刃を感じた。ヒンヤリと冷たい感触。もちろんそれは幻覚。
だが此処で躊躇えば、この依頼に応える事は出来ない。
静かに息を吐き、心を調える。その後で深く、息を吸った。
「此処まで聞いた内容と関係なく、本来の依頼主は御母様で有るべきでしょう。
しかし、依頼主は貴方。今の今まで、御母様についての言及がない。
それに御父上の霊が貴方を知らないのだとすれば、原因は貴方が生まれる前。
つまり御父上と御母様の関係にこそ、解決の鍵が有る。
一体、御母様は?それが分からないと、依頼を受けるべきかどうか判断出来ません。」
「本物、なのですね。正直私は信じていませんでした。
周りの者の勧めもあり、もしもそれで父を然るべき場所へ。そう思っただけで。」
やはり...息を吐き、そっと額の汗を拭う。
「母は、私を産んだ直後、行方知れずになったと聞いています。
遺書なども見つからず、事故や事件の可能性も無いらしいと。」
「やはり貴女には、御母様に関わる記憶が。」 「はい、全く。」
「それでは何の手がかりも。」 そうだ、この件で俺が選ばれた理由。
『海』と『釣り』に縁がある術者として、俺が指名された。
ならば、ある筈だ。未だ語られていない『海』と『釣り』、そしてこの件の関わり。
「これを、持ってきました。父の書斎で見つけたものです。」
少女がバッグからとりだしたのは、黒い革表紙の古いノート。
「日記、とは違いますが、父と母の関係が書かれています。
どれも釣りと関わる内容なので、釣りに詳しい方なら手がかりが、と。」
そのノートから滲む、濃厚な気配。前にもこんな、しかしあれとは全く違う。
その気配には一切の邪気がない。それは多分、愛情や憧憬に近い、強い想いだ。
「読ませて頂いても?」 「はい。必要な期間、お持ち頂いて結構です。」
そのノートを開く。丁寧に書かれた、几帳面な文字が並んでいた。
『陽光』
冬はタチウオ釣りの季節。
北東の冷たい風に震えながら、未明の波止に立つことも多くなる。
日の出を見る機会が一番多いのは、だから冬。
光を受容する細胞に2種類あると知ったのは高校生の頃。
弱い光の下で「明るさ」に反応する細胞と、
強い光の下で「色彩(光の波長)」に反応する細胞。
だから月明かりや星明かりに照らされる世界には色がない。
太陽の明るい光があってこそ、世界は様々な色彩を纏う。
未明の波止には微かな影の輪郭だけ。
モノトーンの世界は夜明けが近づくに釣れて色彩を取り戻す。
始め、その色彩は古いセピア色の写真のように頼りないが
やがて朝日を受け、驚くほど色鮮やかに、世界は輝く。
逆に夕方の釣りでは、色彩の終焉を見送る。
残照の中で世界はゆっくりと色を失い、セピア色からモノトーンへ。
全ての色は眠りにつき、明日の再生を夢見る。
仕事を終えて釣りに出かける途中、初めて妻をみかけた。
部屋へ帰る途中だったのか、買いものに出かける途中だったのだろうか。
遠目にも、あまりに鮮やかな彼女の美しさ。一目で恋に落ちた。
たまたま彼女が仕事の都合で私の職場を訪れるようになり、
彼女を見かける機会が増えるにつれ、片思いは募っていった。
そしてある日、世界が違っていることに気づいた。
通勤の道程も、いつもの波止も、住み慣れた寮の部屋までもが
なぜか生き生きと鮮やかに息づいている。
彼女の放つ光によって、私の世界が新たな色彩を帯びていた。
その時、私は理解した。あの古い歌の歌詞、その真の意味。
You are my sunshine. My only sunshine.
彼女が話を聴いて笑ってくれるとき、私の言葉は意味を持ち
釣ってきた魚を褒めてくれるとき、私の釣技が価値を持つ。
今まで知らず長い夜の中にいたこと、その夜が明けたことを、私は理解した。
私は出会った。空でなく、この心に輝く、真実の太陽に。
二人で重ねた時間は2年。幸運にも、私は今も変わらぬ眩い光の中にいる。
確かにその文章は、釣り人にしか書けないもの、そう感じた。
そして、1つ1つの言葉は、その女性に対する愛情と憧憬に満ちている。
職業作家の文章かどうかは分からない。しかしその言葉は瑞々しく鮮やかだ。
「確かに、これは日記と言うよりエッセイです。
御父上はこれらの文章を公表されたのでしょうか、例えば釣りの雑誌とか。」
「いいえ、そのような話は聞いておりません。
父は医者で、作家ではありませんでしたし。」
「なら好都合です。御父上の想いが発散していないなら、
このノートに、きっと手がかりを探せるでしょう。この依頼、承ります。」
「それで、何か手がかりはあった?」
Sさんのキス。少しだけ、ハイボールの香り。
「いいえ。お話は40話以上あって、全部読んでみない事には何とも。」
「そんなに沢山、『釣り』と『奥様』に関するお話が?」
「そうなんです。例えばこれ、最初に書かれていた『陽光』という作品で。
暫く、そのノートに集中していたSさんが顔を上げた。
「素敵なお話ね。文体とか色々、思う事はあるけれど。
女として、妻として、こんなお話の主人公になれたら、正直嬉しい。」
Sさんなら、もちろん姫も、きっとそう言うと思っていた。
「でも。」 ああ、やはりそうだ。これも、予想通り。
「視点も言葉も本当に鮮やか。でも、これだけじゃ手がかりがない、何一つ。」
「はい。僕もそう思います。でも多分見つかると、いえ、きっと見つけます。」
「そうね、期待してるわ。」 Sさんは今までで一番優しく、微笑んだ。
『出逢い』
思い切りロッドを振り、びゅーんとキャスト。
眩しいラインの軌跡を残して、ルアーは彼方へと飛んでいく。
ラインに右の人差し指で軽く触れ、糸ふけを最小限に。
ルアーが着水したら素早く糸ふけをとってリールを巻く。くるくる、くるくる。
リズム良くルアーを泳がせる、時折の破調を交えるのが効果的。
くるくる、ぴ、ぴ、くるくる...
一投目。アタリがなくても、何らかの兆しを感じる確率は高い。
運が良ければ、魚がルアーを文字通り引ったくっていく。
ガツン! というアタリの後、強烈な引き込み。
予期せぬ大物のアタリなら体ごと持って行かれそう。
思わずよろめいて頭の中は真っ白。
「よっしゃ!!来たーっ。」
なんて叫んで、悩みだろうがストレスだろうが吹っ飛んでしまう。
静止している(潮で多少は動くだろうが)エサと違い、ルアーは泳いでいる。
つまりラインには常にある程度のテンションがかかっていて、
だから魚がルアーを襲うとき、その衝撃はカウンターパンチのように強烈なのだ。
多分魚を掛けてしまえば、後のやりとりは他の釣りと変わらない。
延々と繰り返される単調な動作の後に、突然やってくる衝撃的な出逢い。
ルアー釣りの魅力はとにかく、その一瞬に凝縮されている。
波止でも、磯でも、パヤオでも。いつも、あの衝撃的な出逢いを求めている。
とはいえ、釣れないのが何倍も何十倍も多いのもルアー釣り、だ。
スレた釣り場で強い北風に震えながら、
「なんで俺、こんなことやってんだろ?」と考え込むこともある。
びゅーん、くるくる、くるくる。びゅーん、くるくる、くるくる。..
うーんキビシイ。
もしかしたら平凡な日常生活の中でも、
人は大切な誰かとの衝撃的な出会いを夢見て
毎日毎日、人はそれぞれのルアーをキャストしているのではないか。
ふと、そう思うことがある。
職場で、街中で、時には見知らぬ土地へ出かけて。
びゅーん、くるくる、びゅーん、くるくる...。
強引に誘われ、初めて行った女の子のいる酒場は、
スレ切った、ゴミまみれの釣り場のようだった。
世間話をし、カラオケを歌い、なんとか女の子の気をひこうとみんな必死。
びゅーん、くるくる。びゅーん、くるくる...
(阿呆か?金払ってるのはこっちだぞ)
それから、そんな酒場で飲んだ事はない。凍える波止の方がどれだけましか。
気心の知れた仲間と居酒屋、それで十分じゃないか。
不相応な金を使うなら、酒を飲むよりも良い竿が欲しい。良いリールを買いたい。
そんな風にルアーにのめり込んでいる頃、彼女と出会った。
彼女と出会ったときの衝撃を、うまく言葉にすることはできない。
当然私は今よりも若く、未だ『女性』を知らなかった。
キレイな女の子にはドキドキ、水着のポスターにも自然に目がいく。
しかし彼女と結ばれてから、なにもかもがすっかり変わってしまった。
彼女以外の女の子はどこかボンヤリとして影法師のように見える。
TVで好みの女優を見かけると、彼女の面影が思い出されて仕方ない。
顔も体も、もちろん心も、世界一美しい女性に、私は出会ってしまった。
その確信は今も全く変わらない。変わるはずがない。
私の周りの、影法師のような女の子。TVの画面には、彼女に少し似た女優。
最初で最後、ただ一度だけ。それが妻との出会い。
どんな出会いも、もう私には必要ない。
「これが、何なの?普通に、良いお話じゃない。」 Sさんは悪戯っぽく微笑んだ。
「はい。良い話だとは思いますよ、僕も。ただ、何だか違和感が。」
「だから、その違和感の原因は何?」
「ええと、あの。同意出来る部分と出来ない部分があって。
例えば、僕もSさんとLさんは世界一綺麗な女性だと思います。」
「あら、ありがと。世界一が二人って矛盾には突っ込まなくて良いの?」
「そうじゃなくて、Sさんが世界一なのは、Sさんがダイヤだからで。」
「ダイヤ?」
「この世で最高の宝石がダイヤなら、Sさんは間違いなく。Lさんも、翠も。」
「なるほど、そういう意味なら確かに、瑞樹ちゃんもダイヤだわ。」
「そう、だから『影法師』という表現には同意出来ません。
自ら望んで汚したのでもなければ、どんな女性も宝石や原石である筈です。
何より『どんな出会いも、もう私には必要ない。』という表現は。」
「世界一美しい女性と結ばれたなら、その娘にも逢いたくなる筈ってことね?」
「はい。」 Sさんは微笑んだ。「とても、興味深い。次の報告に、期待してる。」
そうは言っても、技巧を越え『魂』が編んだ文章を読み、
その真意を理解するにはかなり時間がかかる。勿論えらく疲れる。
しかも抱えている依頼が他にも複数有るし、作業はなかなか進まない。
しかし、やっと見つけた。2人の『馴れ初め』が記された文章。
『第一印象』と『第一投』
例えば、初めての釣り場に立つ。
『第一印象』とは地形や風向き、陽光の方向と角度...
それだけでなく、例えば大量のゴミが捨てられていたら、
その場所での釣果など、普通は期待しない。
しかし、釣り人は業の深い人種だから、それでもルアーを投げる。
「折角、来たんだし。」 その結果が、『第一投』。
ただ、釣り場の『第一印象』と『第一投』は全く違う事があるから厄介だ。
竿を継ぎ、用意してきたルアーを投げる。
それが『第一投』。でも『第一印象』と同じとは限らない。
『第一印象』は最高なのに、全く釣れない事もある。
逆に『第一印象』は最悪でも、思わぬ好釣果があり得る。
他の釣りは殆どしないから、例えば浮子釣りでも同じなのかは知らない。
しかし、ルアー釣りの『第一投』は特別な意味を持つ。
何故なら、一投目にヒットする可能性がかなり高いからだ。
ヒットに至らなくても、一投目で重要な情報が得られることは多い。
ルアーが着水した辺りに不自然な波紋が浮かんだり、
時にはルアーを追ってくる魚の姿が見えたりする。
それらの情報をもとに戦略を練り、しばらくしてからキャスト
狙い通りに即ヒット、というのは良くあるパターン。
逆に数投して何の情報も得られないときはかなりキビシイ状況。
手を変え品を変え探るとは言っても、一日中釣りばかりできる身分ではない。
1日にせいぜい正味一時間ほどの釣りでは、だから
釣り人のテクニックや根気よりも、ポイントの状況や魚の活性が釣果を決める。
いかにも良さそうなポイントで苦戦しているベテランに遠慮して、
少し離れたポイントに立ったビギナーにあっさり良型がヒット、というのも日常茶飯事。
どうしても釣果が欲しいなら、移動しながらいくつかのポイントを手早く探る、
いわゆるランガンスタイルの方が効率が良い、と思っている。
(活性の低い魚を誘って食わす技量がない下手の意見だが)
釣りだけではない。人間関係を築くときにも、
『第一印象』よりも『第一投』の方が大事ではないかと思う。
往々にして視覚的な情報に基づく『第一印象』の後、
その後の人間関係を左右する『第一投』」が必ずある。
休憩時の何気ない世間話だったり、一緒に仕事をしながらのふとした仕草だったり。
将来深い人間関係を築く二人は、たとえ第一印象が最悪であっても
それを覆すような決定的な何かを『第一投』で伝えあい、互いの存在感を増す。
その何かを伝えあえない二人は、どんなに『第一印象』が良くても
次第に互いの存在感が希薄になり、互いがその他大勢の中のひとりになってしまう。
妻と出会った後しばらく、まともに彼女の顔を見ることができなかった。
気軽に話しかけることがためらわれるほど、彼女は美しかったから。
だから当然、彼女から話しかけられても、緊張して無愛想な返事になってしまう。
きっと本来なら、二人の時間が重なることはなかっただろう。
ところが突然やってきたのだ、幸運な『第一投』が。
ある日、無性にインスタント焼きそばとカップラーメンを両方食べたくなった。
買い物袋を抱えて給湯室に入ると、彼女が一人で座っていた。
(二人きりになるのはそれが初めてだった)
ドキドキして食事どころではないが、不自然に部屋を出るわけにもいかぬ。
多目に沸かした湯を、焼きそばとラーメンの容器に注いだまでは良かったが、
やはり動転していたのだろう、湯切りの時に焼きそばの麺を流し台に零してしまった。
思わず「あ~っ!」と声を上げたのが面白かったのか、
彼女は悪戯っぽく「それ、食べられるんじゃないですか?」と笑った。
咄嗟に「空腹は一時、でも、落とした麺を食ったという評判は一生ですから。」
とかなんとか答えたと思う。
この場合、落とした麺を食べたとしても、それを彼女以外見てはいない。
今思えば、それはかなり失礼な物言いだったかも知れぬ。
しかし、それがなぜか大いにウケた。
彼女がこんな、まるで少女のように瑞々しい笑顔で笑うのかと意外だったが、
その煌めく笑顔をできるだけ長く見ていたくて、
残ったラーメンを食べながら懸命に言葉を継いだ。
その事件以降、彼女は何かと笑顔で話しかけてくれるようになった。
零した焼きそばの麺が『第一投』というのはいかにも間の抜けた話で、
その時一体何が彼女に伝わったのか私には知る由もない。
しかしその事件は、私にとって空前絶後の『第一投』になった。
「これなら、私にも分かるわ。あなたの違和感の原因。
本当に世界一の美女だったなら何故?ってことね?」
「はい。でもどうしてそれが?」
「だってホントに『世界一』美しい女性なら何故、その時まで?」
そう。それ程美しい女性なら既に相手がいても不思議じゃ無い。
第一、昼ご飯時にただ一人、給湯室にいた事自体が不自然ではないか。
その女性と誰かが一緒にご飯を食べていたというなら分かるが。
「その、『隠されていた』と考えるしか。」
「『隠していた』のかも知れないわね。もしそうなら...」
残っていたハイボールを飲み干したSさんは、少し緊張した表情。
「今夜この件の話はお終い。」
『天津風』
春も夏も秋も冬も、一年中飽きもせず釣りに出かける。
遠近の磯や、いつもの波止を歩いていると、
心の奥から、かつて口ずさんだ和歌が零れて来る事がある。
何となく理系の大学に進学したものの、高校生の頃はどちらかというと
現代文や古典の成績が良かったし、何より和歌の授業を聞くのが好きだった。
しかし父のたっての希望もあり、そのまま理系の大学院を出て就職。
暫くは仕事に追われ、雅な和歌などは縁遠いものになっていた。
しかし。やがて仕事に慣れると、まるで血に導かれるように海岸に立った。
釣りを再開。季節の移り変わりを肌で感じ、美しい景色を眼にして、
心の片隅に仕舞い込んでいた文学青年気取りの気質が蘇ったのかも知れない。
島の職場に赴任した直後、初めて出かけた磯の、何となく心細い夜釣り。
「和田の原 八十嶋かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ あまの釣り舟」
夜明け前の河口。仕掛けられたカニ網の浮子がボンヤリ見えてくる。
「朝ぼらけ 宇治の川霧 たへだへに あらはれ渡る 瀬々の網代木」
暑い暑い夏の、青く眩しい水平線に海鳥が飛んでいる。
「白鳥は 哀しからずや 空の青 海の青にも 染まずただよふ」
職場の同僚になった妻を、初めて見た時に零れてきた和歌がある。
あまりに美しく、まともに声もかけられないが、勤務時間中なら彼女に会える。
終業時刻が来なければ良いと、願い続ける自分の姿を予知していたのか。
「天津風 雲の通い路 吹き閉じよ 乙女の姿 しばしとどめむ」
この歌を知ったのは高校2年の初夏。古典の授業中、突然歌の意味を問われ、
「天女のように美しい恋人を帰したくないという歌だと思います。」と答えた。
普段は厳しい先生が困ったように微笑んで、それでも何故か大いに褒めてくれた。
本当は、大切な儀式で踊る舞姫を讃えて詠んだ歌だと、知ったのはずっと後のことだ。
妻と逢瀬を重ねるようになってからも時折この歌は心に響き、
少年の日の夢、天女のように美しい恋人をこの腕に抱く幸運を実感させてくれた。
ただあまりに面映ゆくて、この歌のことは妻に話せなかったし、
仕事の都合で暫く釣りから離れている間に、そんな記憶もすっかり薄れていた。
ところが、である。
今年の正月3日、里帰りしていた妻から写真を添付したメールが届いた。
妻は家の事情で毎年11月の半ばから正月にかけて長い里帰りをする。
私の仕事では連続した休みは取れないから一緒には行けない。
電話やメールで『寂しい』と嘆く私を哀れんで、時折写真を送ってくれるのだ。
写真の中の妻は晴れ着を着て、透き通るように笑っている。
何年ぶりだったか、その澄み切った笑顔の向こうから、突然響いてきた。
「天津風 雲の通い路 吹き閉じよ 乙女の姿 しばしとどめむ」
何と美しいのだろう。本当に、これが私の妻なのか。
一瞬でも長く生きて、いや、できれば死んだ後でも、ずっと見ていたい。
そんな自分が可笑しくて、その日は返事のメールを書けなかった。
これ以上の幸せなど、あり得ない。あり得る筈がない。
やっと見つけた糸口。そう思った。
どう考えても、これは普通じゃ無い。
『天津風』。この和歌は特別。作中の言葉通り、あの儀式の舞姫を讃える和歌。
和歌の素養がある人なら、舞姫の美しさを感得出来る人なら尚更、
生身の女性をこの和歌の舞姫になぞらえるのを、本能的に避ける筈なのだ。
(それは畏怖。娘を美神になぞらえて、不幸を招いた王の轍を踏まぬように。)
しかし、この男性は躊躇う事無く、妻を舞姫に重ねた。
この男性の妻とは一体? 心の奥で、Sさんの言葉が響いた。
『隠していた、のかも知れないわね。もしそうなら、その女性は...』
多分、辿り着くべき答への道まで、もう一歩。
『3000回』
ヒマを見つけて毎日毎日波止に通っていると
「よくもまあ飽きずに。」という人がある。
「釣りをしなければ飢えて死ぬわけでもあるまい。」
「第一、魚なんぞスーパーで買った方がずっと安い。」
と続く。まあ、色んな考えがあるわけで、反論しても仕方ない。
しかし、少なくとも「飽きる」ことはない。
釣りを始めて何年になるか、私は未だ釣りに飽きてはいない。
例えば昨夜のタチウオと、今夜のタチウオは違う。
さっき釣ったカマスと、今掛かっているカマスも違う。
別の魚だというのではない、感動が違うのだ。
毎回毎回新しい感動があり、次への期待がある。
そしてごく稀に、期待をはるかに超える大物に出会う事もある。
それなのに、毎日波止へ通う事を、苦労だと感じる訳があろうか。
まして、飽きることなどあろうはずもない。
妻と出会って、驚いた事がある。
毎朝出会うたびにどこか昨日の彼女と違っているのだ。
気があるから、つい視線の端で彼女の姿を追っている。
姿も顔も、全部憶えているはずなのに、次の日はやはりどこか違う。
つきあい始めてからもそれは変わらなかった。
逢う度に彼女の新しい魅力に気づき、想いは募る。
逢う度に彼女に恋をした。もちろん今も。
妻と出会って2年と少し。1日に4回彼女に恋をしたなら、
既に3000回の恋をした計算になる。
やはり、そうだ。その女性はただの人間ではない。
際だって魅力的な人間は確かにいる。並外れた美貌や才能。
しかし、毎日毎日どこか違う、そんな事があり得るだろうか。
まして1日に4回もなんて。『その度に恋をした』というのだから、
仕事の疲れでやつれたと言うような類いの変化ではない。
例えば、朝の出勤時と夕方の退勤時はどこか違っている。違う魅力の一面が見える。
同じ服なのに? 同じ人間なのに? 同じ魂なのに?
...「あの人」、姫の母親に近い事例だったとしたら。
その人はとても美しくて快活で、魅力的だったと聞いた。
原因は分からないが、神に近い魂が人の肉体に宿り、その結果途轍もない力を持つ。
それならあるいは、万華鏡のように変化する無数の魅力を纏っていたのではないか。
しかしその力が生み出す負荷に、人の体では長く耐えられない。
姫の母親はそれを承知で姫を産み、暫くして亡くなった。
今回の件がそれに酷似した事例だとすれば、ある程度理解出来る。
『行方知れず』だと説明したのは、依頼人を気遣っての事だろう。
自分を産むために、母親が亡くなったと知ったら。
しかし俺の予想は、最後に見つけた作品によって覆された。
『海の蛍(仮)』
その光景を見たのは、仲間達と夜釣りに興じていた新月の晩。
漆黒の水面下に伸びている道糸が、淡い光の筋になって見えるのに気づいた。
何かと思って手元の小さな懐中電灯を消した。ゆっくりと、闇に眼が慣れてくる。
闇の中に、ボンヤリと浮かぶ緑色の輪郭が見えた。大きさは10cm位。
細長い輪郭の中に、ときどき強い光がチラチラと明滅する。
それが幾つか、ゆっくりと動いている。気付いた時、思わず息を呑んだ。
魚だ。無数の、小さな光が魚を象って瞬いている。
小さい頃に見た星座の絵のような、それはあまりにも美しい光景だった。
海蛍の光自体は、特に珍しいものではない。
しかし道糸や魚の姿が光って見えるほど、たくさんの海蛍を見たことはなかった。
夜の打ち込み釣りだから、確か夏の最中のことだったと思うが、
たまたま海蛍たちのランデブーの晩だったのか。
あれほどの光景を見たのはその一度きり。
いや、その後一度だけ、似た光景を自分の部屋で見たことがある。
それは妻と正式に付き合い始めて2回目の、正月が開けた夜。
その日恒例の長い里帰りから戻った彼女は夕方から私の部屋を訪れ、
一緒に食事をし、餅を食べながらTVを見て、そして身体を重ねた。
終始にこやかで優しかったが、今思えば、いつもより口数が少なかったと思う。
迷っていたのかも知れない、打ち明けるかどうか。
あの夜、ゆっくりと時間をかけて、話してくれた秘密。
その夜、彼女が私の部屋を出たのは、何時もより随分遅い時間。
秘密を打ち明けた妻にも、それを受け容れる私にも、時間が必要だったから。
深夜、玄関で彼女を見送った後、部屋の灯りを消した。
暫く視界は闇に覆われたが、次第に眼が慣れてくる。
その時だ。
玄関から台所へ、床を彩る微かな光に気付いた。水色の、小さな光。
眼が慣れるにつれ、その数は増えた。椅子の上に、台所のシンクに。
そして手を繋ぎ並んでTVを見た、大きな座椅子とクッションに。
小さな光に導かれるように、寝室へ。眼を、疑った。
ベッドには、無数の小さな光。まるで彼女の面影をなぞるように瞬いている。
あの夜彼女と話した事は (未完)
この描写...これはまるで、『光塵』ではないか。
言わばそれは、残り香のようなもの。
神や高位の精霊と接触した人の体に、接触した場所に、残される光の粒子。
本体の近くでは本体の強い光に紛れて見えない。
本体が去った後で初めて見えるものなのだ。
このお話でも同じ、その女性が部屋を去った後で...いや、待て。
術者で無ければ『光塵』は見えない。この男性に能力があったとしたなら、
その女性を部屋から送り出した夜は毎回それが見えた筈なのだ。
なのに何故、その夜だけそれが見えたのか。一体、その女性は何者なのか。
まさか本当に、化生した高位の精霊がその男性の妻に?
以前『神婚説話』の実例に関わったことがある。
その件の後、俺は一族に残されている記録を出来る限り調べた。
記録によれば、それらの事例は2つに大別できる。
人が異界へ入る場合と、逆に神や精霊がこの世界に入る場合だ。
今回の事例は後者、いわゆる『天女女房系』。
その場合、ほとんどの事例では、婚姻関係は短期間、数年しか持続しない。
人が約束を破ったために破綻する、という伝承が最も多いだろうか。
そして残された子が国の(一族の)始祖となったという記述も一般的だ。
今回の事例でも、その関係が続いた期間は約3年と考えて良い。
(エッセイの記述では2年+妊娠・出産で1年、計3年。)
今回の事例でも、依頼人の父親が原因で婚姻関係が終わったのか。
しかし、一般的な伝承とは異なる記録を、俺は読んだ事が有った。
不思議な婚姻関係が終わった後、相手の女性と再会したという、記録。
その女性が生まれ育った里の寺、過去帳の写し。
それによれば、その女性はある日故郷の里から忽然と消えた。
4年後にひょっこり戻ってきたが、その間の記憶は全くなかった。
(もちろん不思議な婚姻関係のことも、生まれた子供のことも。)
夫であった男性は漁師で、急な嵐に流され偶々辿り着いた里でその女性に再会。
驚いた男性は女性や里人に事情を尋ね、神隠しの件を知る。
その男性はあらためてその女性を嫁に貰ったという。
つまり化生ではなく『憑依』。これこそが、物語の実情に近いのではないか。
想いを遂げるため、ある女性に憑依し、意中の男性と結ばれ妻となる。
憑依される女性の側からすれば酷い話だが、高位の精霊の倫理観は人と違う。
そしてある期間が過ぎると憑依が解け、婚姻関係は終わる。とすれば。
依頼人を産んだ女性は何処かで生きている。憑依されていた期間の記憶を無くして。
それなら、探し出す事も不可能ではない。あの人の力を借りれば。
俺は翌朝一番で榊さんに電話を掛けた。
「その女性の死亡届は出ていないし、捜索願も出ていない。
それについてはR君の予想通り。『憑依』の実例、と考えるのが妥当だろう...」
珍しく語尾をぼかして、榊さんは言葉を切った。受話器の向こう、考え込む気配。
『妥当だろう』とは。何か予想と違う点があるのか。
「ただ、その女性の元の戸籍が見つからない。当然、元の本籍地も分からない。
力業というか、君たちが使う偽装工作の方が丁寧だね。
それで、夫の当時の職場で働いていた女性を全て調べたよ。死亡届や捜索願は皆無。
製薬会社から出向していた職員が2人いるが、どちらも男性。
依頼人の戸籍と出生届には、確かにその女性の名前が記されている。
なのに、その女性が実際に存在していた事を示す書類が他に無い。
調べれば調べるほど、『その女性には辿り着けない』って気がしてくるんだ。
こんなのは、正直、初めてだよ。」
そんな...予想通りどころか、俺の予想を遥かに超えているではないか。
もちろん榊さんの調査結果は信頼できる。
つまり、『天津風の乙女』は娘を産んで亡くなったのではない。
しかし、元の戸籍が辿れないのなら、高位の精霊の憑依という推理も崩れる。
それなら一体、依頼人を、あの少女を産んだ女性とは。
「ああ、そうだ。依頼人の父親が山で遭難したという新聞記事なら見つけたよ。」
??? 依頼人の父親が遭難? 何故。 「新聞って、当時のですか?」
「ああ、2×年前の記事。秋の★山で天候が急変、季節外れの大雪。
捜索隊も出せないような雪だったから、多分駄目だと皆思ってたらしい。
だが怪我一つ無く、2日後に自力で下山してきたそうだ。
これはまあ、参考にならないだろうな。悔しいが、今回はどうやら此処までだ。」
「いいえ、お忙しいのに無理を言って。本当に有り難う御座いました。」
礼を言って受話器を置いた直後。
「探してる女性は見つかった?」
振り向くと、Sさんが立っていた。 優しい微笑。
「いいえ、記録が残っていないそうです。元の戸籍も職場の資料も。」
「依頼人の、父親の幽霊が出るというお屋敷の住所は?」
「○×市です。◎県の。」
「そう、なら一石二鳥ね。間違いなく、私が受けた依頼と関係がある。」
「どういう、事ですか?」
「依頼人と、いいえ、遍さんと連絡を取って頂戴。私が、その依頼人に会うわ。
場所は依頼人の父親の幽霊が現れるという、そのお屋敷。」
別々の、二つの依頼。その垣根をSさんが自ら越えるとしたら、只事では無い。
「Sさんの受けた依頼って。」
「◎県の古い神社から『雪乞い』の依頼、いいえ、『冬乞い』かしらね。」
「どういう、事ですか?」
「初雪が遅れてるのは知ってるでしょ?」 「はい、でもそれは温暖化の。」
「年神様の到着が遅れていて、冬が来ない。その神社ではそう考えてる。」
「年神様?本当に?」
「彼の地の伝承では、そうね。
秋の終わり、年神様の御役目を果たすために★山から◇★神社へ御渡りになる。
そして◇★湖を御通りになる時『御神渡り』が起こる。」
何かが、心の隅に引っかかっている。だが、それが何なのか、もう少しで...
「R君、どうかした?」
「あ、いえ。つまりSさんの受けた依頼は、年神様に早く来て頂くように、と。」
「そう。でも代々彼の地で祀りをしてきた宮司達の声も届かない。
そんな状況で何が出来るか。Lと一緒に、ずっとそれを調べてた。」
Sさんだけでなく、姫も一緒に、それなら。
「『青の宝玉』で?」 Sさんは優しく微笑んだ。
「冴えてるわね。確かにそれで、多分雪は降らせる。
でも年神様に来て頂けなければ失敗。例え雪が降ったとしても。
何とか★山の御社から出ていただかないと。」
!!そうだ、★山。心の隅に引っかかっていた名前。 「あの、Sさん。」 「何?」
「依頼人の父親が★山で遭難したという記事を見つけたんですよ。榊さんが。」
Sさんの瞳が、青白く光ったように見えた。 「それ、何時頃の話?」
「2×年前です。まず助からないだろうって位の大雪だったそうですけど、
2日後に自力で下山してきたらしいです。それも、全くの無傷で。」
「それで繋がったわ、全部。」 「どういう、ことですか?」
「何処で何を調べれば良いのか分かったの。
あなたのお陰で、とても重要な『鍵』を手に入れたから。」
「『鍵』?」 「あなたの依頼人、正確にはあなたの依頼人の母親。」
「あの、あの娘の母親と年神様に関わりが?」
「勿論。だって『憑依』じゃないなら、それは『化身』って事でしょ。」
「あ...まさか。」 「その、まさかよ。」 Sさんは悪戯っぽく微笑んだ。
「年神様は陰神、つまり女性。年神として冬を統べる期間以外は、
化身してその男性の妻として過ごしてた。そう考えるしか説明がつかない。」
!? そう言えば、あのエッセイ『天津風』の中に。
「その女性は毎年11月半ばから正月明けまで長い里帰りをしたと、お話の中に。」
「やっぱり、間違いない。」 Sさんは上機嫌でハイボールの残りを飲み干した。
「さ、もう寝ましょ。明日朝早く、Lと一緒に出かける。子ども達をお願いね。」
Sさんと姫が二人で出かけた日から3日目の午後。
俺たちは家族全員揃って○×市を訪れた。
数ヶ月前、Sさんが購入した7人乗りの大型ワゴン。多分初めての、日本車。
これなら何かの機会(例えば今回のような)に家族全員が乗れる。
ただSさんは自分で運転する気はないようで、姫と俺が運転の担当。
気持ちよい秋風(季節外れ?)の中、2時間程で○×市に到着した。
ただ、そのお屋敷で依頼人に面会するのはSさんと俺。姫と子供達は車の中。
車を出て歩く。Sさんに指示された手順を何度も、心の中で確かめながら。
「わざわざこの家で、私に聞きたい事とは何ですか?」
応接間のテーブルを挟んで向かい合う、依頼人とSさん。
落ち着いた雰囲気の応接間はしかし、怖いほどの緊張感に満ちていた。
「父上がこの世に留まり、探しておられるものについて。
あなたの心当たりを伺いに参りました。」
Sさんの口調も、年下の依頼人に対するものとは違う。
「父が探しているもの...一体何故、父が何かを探していると。」
「父上が迷っておられるのは、この場所に心残りがあるからでしょう。
そしてその心残りはおそらく地図か手紙。それを探しておられる。」
「父が自身の持ち物の在処を知らないなんて。そんな事が。」
「死者は自ら望む姿で現れます。確か父上は若い頃の姿で?」 「はい。」
「そういう変化にともなって、記憶が一部欠けてしまうことがあるようです。
いわゆる『幽霊』が自分が死んだのを理解していない事が多いのも同じ理由。」
「それで父は私の事を?」
「はい。おそらく父上の記憶は貴女が生まれる前までで途切れているのでしょう。
だから父上はその在処を知らない。それで。」
「では、その手紙は、一体誰から。」
チリ...視界の端で、銀色の火花が散った。
Sさんは確かに『地図か手紙』と。しかし今、依頼人は確かに。
「当然、母上でしょう。来たるべき時、お二人が再会するために。」
Sさんの集中力が高まっていく。空気は益々緊張感を増した。
「再会、では既に母も...」
Sさんは真っ直ぐに依頼人を見詰めた。
「心中、お察し致します。しかし今は父上の迷いを解き、
お二人の再会を実現するのが一番の大事。」
「でも、その手紙は一体何処に?」
「ですから貴女の心当たりを伺いたいのです。父上から何か。」
「いいえ、私は」 何かを思い出そうとするような、表情。
依頼人は言葉を切って俯いた。 「私は、何も。」
Sさんの目配せ。 俺は立ち上がり、依頼人の傍らに膝を付いた。
深く息を吸い、下腹に力を込める。
『忘れてしまったのです。もう随分と、昔の事ですから。』
依頼人はハッとしたように顔を上げた。 「忘れて?」
『でも大丈夫。すぐに、思い出します。』
依頼人の目から涙が零れた。成功だ。
「怖かったのです。私は。」 「どうして、怖かったのですか。」
注意深く、依頼人の心から流れ込むイメージに同調する。
「◇、これを読んでみて。」 「これ、なあに?」
「お母さんからもらった手紙だよ。読める?」
「うん、読める。え~と、・・・・・」
「本当に、読めるんだね。」 「だって。」
「ね、◇。約束しておくれ。私が死んだら、この手紙を読んで聞かせるって。」
突然イメージが乱れ、やがて途切れた。
その記憶を、心の奥に封じてしまったのも無理は無い。
愛する父が何時か死ぬ。そして死んだ父にその手紙を読み聞かせる。
母を知らぬ子に、それはどれほど恐ろしいイメージだったろう。
そして同時に、無垢な心は感じ取っていたのだ。
『読めるんだね』 父の、その言葉に潜む意味。
「父が死んでしまう。私、それが怖くて。」
それは無意識の仕草、だったろう。 依頼人は胸の真ん中辺りに右手で触れた。
間髪を入れずSさんが問いかける。
「今、右手で触れたのは?」 「え?」 「その、右手の下にあるもの、です。」
「これは、御守りで。」 「父上から?」
「はい、幼い頃からずっと...あ。」
依頼人は御守りの袋を開き、折りたたまれた紙片を取り出した。
ゆっくりと紙片を広げる指先が、微かに震えている。
広げ終えると、依頼人は紙片を持ち替えて半回転させた。
「読めますか?」 「はい。」
「父上から託された時と同じ、ですね?」 「そう、思います。」
やはり何か、とんでもないものに関わっている。背筋が冷えて、震えが来た。
その紙片、父親から託されたという手紙は、白紙だった。
「父上の迷いを解く方法が分かりました。」 「それは、どんな?」
「7時55分、此処でその手紙を読んで下さい。
一言一言しっかりと声に出して、父上に聞かせるおつもりで。
同時に、私たちはある場所で儀式を行います。
タイミングが重要ですから、7時55分ぴったりにお願いします。」
「本当に、それで父の迷いは...私は未だ。」
Sさんは立ち上がり、テーブルを回り込んだ。依頼人の傍らに片膝を着く。
「我らが一族と、私自身の名に賭けて。ですから、どうか。」
「分かりました。あなた方を信じます。」
約束の7時55分まであと1時間、ワゴンは姫の運転で山道に入った。
子供達の寝息を包み込むように、力強いエンジン音が響いている。
「何故、母親の事を教えて上げなかったんですか?
いや、むしろ彼女も一緒に来て貰った方が良かったんじゃ。」
Sさんは少し困ったように微笑んだ。
「神の子、と言えば聞こえは良い。天女女房系の神婚説話なら、
残された『神の子』は大人物になるのがお決まりだし。」
「それだけじゃない、って事ですか?」
「神の子は、重要な『使命』を帯びて生まれる。そういう意味で伝承は正しい。」
「使命...天命とは違うんですね。」
「私たちが力を持って生まれ、術者になったのは天命。
でもどんな依頼を受け、どんな風に仕事をするかまで決められている訳じゃ無い。
使命はもっと詳細で具体的だとされてるの。
何々の国の王になる。あるいは何々の一族の始祖になる。」
「選択の、余地がないって事ですか?」 「ご名答。相変わらず、冴えてる。」
Sさんはコンビニで買ったコーヒーを一口飲んだ。
「神々の世界と私たちの世界は、重なって存在してる。
神々の世界の一部として私たちの世界が存在する。そんな感じかしらね。
ただ神々と私たちの在り方は違うから、2つの世界の間に時々歪みが生じる。」
「神の子は、その歪みを解消する使命を帯びて生まてくれる、と。」
「そう。生じる歪みを予知し、破綻を防ぐために挿入される、因子。」
世界の歪み。その予知と対策。それは確かに、神々でなければ不可能な、御業。
「だから神の子は王や始祖として人々を導く。」
「そう、あるいはその命を贄として、世界と時の流路を変える。」
「贄?」 「誰にも知られずに、ね。そういう使命も、あると聞いたわ。」
神々の血に連なる命、それを贄として。誰にも知られずに?
Sさんが依頼人に母親の正体を話さなかった理由が分かった気がした。
そして不自然とも思えるほど、礼を尽くして依頼人に接した理由。
Sさん自身が幼くして、両親との別離を体験した。だから。
逃れられぬ『使命』を背負う少女に、心の奥深くで共鳴しているのだろう。
「彼女も薄々気付いている。自分が他人と『違っている』事に。
だけど使命を知るのは、その時で良い。知らなくてもその時は来るのだし、
例え本人が知らないままでも、使命は必ず果たされる。」
世界に生じる歪みを解消するためと知れば、自分の死を受け入れられるだろうか。
しかし『本人が知らないままでも使命は必ず』って...。
神の子の光と影。影も、光と同じだけ存在してきたのだろうか。
「もう1つ、質問があります。」 「何?」
「質問の前に確認を。神の子を産むために神が人と結婚するのだとしたら、
神の子が生まれた時点でその目的は果たされる。だからほとんどの場合、
その関係は短期間しか続かない。そういう理解で良いですか?」
「それで良い、と、思う。」
「それなら妊娠までの期間は、短ければ短い程良い筈ですよね。
何故、この件では妊娠まで2年もの月日が?」
神の化生なら当然、望む結果を実現させるのに十分な力を持っているだろう。
妊娠するのに、2年もの期間など必要ない筈なのに。
子供達は皆寝ている。Sさんは黙って丹の頭を撫でた。
不意に、運転席から姫の声。
「神の子を産むための出逢いじゃなかったから。私は、そう思います。」
「それは、どういう?」
「年神様はその男の人を本当に愛しておられたのでしょう。
だからこそ今、哀しみに心を閉ざしておられる。
死後の再会を誓っていたけれど、何か重大な手違いが起きた。
それでその男の人の魂が迷い、未だ再会出来ないんです。」
「手違い?」
確かに、今までの経験からして、神々と言えど全能ではない。しかし。
「多分、Lの言う通りだと思う。」 「どういう、事ですか?」
「その男の人は昔、★山で遭難したってお話でしたよね?」
「はい。誰もがあきらめていたけれど、全くの無傷で...そうか。」
季節外れの、とんでもない大雪。真冬の重装備でも助かるかどうかの。
しかし、依頼人の父親は助かった。怪我1つなく。それが神様の御加護だとすれば。
しかも年神として冬を統べる期間以外、その神様は★山に祀られている。
おそらく2×年前、その大雪の夜に出逢ったのだ。
「その日、連れて行く事も出来たのに、そうしなかった。
人の世で、その男の人の妻として暮らすことを望んだから。」
バックミラーに写る姫は微笑み、Sさんは小さく頷いた。
「きっと、何か事情が変わったのね。
突然『神の子』が必要になって、その御役目が陰神さまに託された。
既に私たちの世界に降りている神様なら、新たに派遣するよりずっと早いから。」
「そんな事情でも、子供と離れなければいけないんでしょうか。」
だって、今の今まで、俺はただの1つも知らない。
『母親』が最後まで夫や子と一緒に暮らしたという天女女房系の伝承を。何故?
「その男性を愛していたから、当然、生まれた子は愛しい。
でも、むしろそれは稀なケースでしょう。
ほとんどは、神の子を生むための関係ですから。それでも。」
不意に黙った姫に替わり、Sさんが言葉を継いだ。
「どんな、どんな事情があれ自分が産んだ子は、愛しい。」
そうだ、以前も聞いた事がある。神や高位の精霊と、人の倫理感の乖離。
「だからこそ、その愛情が子供の運命に干渉し、『使命』を妨げてはならない。
愛しいからこそ、子供と離れる。そういう、定めなんでしょうね。」
ならば、あの少女も母親に愛されていた、いや、愛されている。そう信じたい。
母親と別離れた定めは、愛されていたから、と。
「あの少女を1人で、一生掛けて育てるために男性は人の世に残った。
そして神様は少女のために、男性が人生を全うするまで待っていた...」
「そうとしか、考えられない。今回の件は、そのために起きた手違い。」
「きっとその男の人は誓いを立てたんだと思います。」 「誓い?」
「その子が一人前になるか、自分の命が尽きるまでは、必ず傍にいる、と。」
「それなら何故、こんな手違いが。」
「幸いにして、愛する『半身』を失う辛さを私たちは知らない。
でもそうなったら、1人で耐えられるかしら。日々の生活に、子育ての重圧に。
子を残して、『半身』の後を追った例は少なくない...もし私が」
確かに。 今、Sさんと姫を失ったとして。それでも俺は子供たちを?
そうか。その男性は自ら退路を絶ったのだ。愛する妻と、娘のために。
「だから『手紙』を娘に託したんですね。再会の方法か、場所が記された手紙。
その指示に従うのは必ず、自分の役目が終わってから、と。」
「そう、その男性は自分の、人間の弱さを良く知っていたから。
でも陰神様は違う。どれだけその男の人を、娘を愛しても、
人間の弱さを正確には予測出来なかった。
弱さを克服するために、人が一体何をするかということも、ね。
間違いなくそれが、手違いの原因。」
その時、俺は理解した。
天女女房系の神婚説話が必ず、人間の『狡さ』や『裏切り』に言及する理由。
倫理の基準は違っても、愛した人間を神々が疑う事はないし、迷う事もない。
しかし、人の心はそこまで強くはない。伝承はおそらく、それを暗示している。
この件も同じ。人の心の弱さゆえに、男性は娘に手紙を託し、娘はその記憶を封じた。
心の弱さは人の欠点。しかしそれが『覚悟』を生むのなら、美点であるとも言える。
その時、滑らかだが無機質な電子音声が響いた。GPSと連動した、最新鋭のナビ。
『次ノ交差点ヲ左折、目的地マデ約2km、デス。』
「さて、いよいよね。翠を起こして。儀式の前に最終確認。」
斜陽に染まる山道の奥、目的地の御社が見えた。
6時半。約束の時間まで、あと25分。
6時45分に姫が『青の宝玉』の力を借りる。それが、儀式の始まり。
御社の周りに雪が降り出したところでSさんと翠が謡で陰神さまの注意を引く。
それから少し遅れて、あのお屋敷では依頼人が手紙を読み上げる。
俺たちには読めない、白紙の、手紙。
それがSさんが指示した段取り。今回、俺は藍と丹の子守担当。
『陰神様が御心を閉ざしたままでは話にならない。』
以前そう言ったのは他ならぬSさん。
宮司たちの声も届かないのにと訝しむ俺に、Sさんは微笑んだ。
『御心を閉ざした神様に振り向いて頂くなら、特に陰神様なら策はただ1つ。』と。
「そろそろ時間。L、お願い。翠も、準備良いわね?」
最終確認の後、Sさんは胸の前で柏手を1つ。それが『始まり』の合図。
首に掛けていた『青の宝玉』を、姫は両掌で捧げた。古い言葉が空に溶けていく。
しん、と、空気が冷えた。
宝玉が漆黒から深い青に色を変え、柔らかな光に包まれる。
何時の間にか、辺り一面を綿雪が舞っていた。 何と不思議な光景だろう。
数多の星が瞬き始めた雲一つない蒼空。そこから舞い降りる風の花。
それらは地面に降りると幻のように消える。
地面の温度が零下でないから融けるのか、あるいは現実の雪ではないのか。
その光景はまるで、御社の周りを祓い清めるかのようだ。
「お父さん。ホントに、雪がふったよ。すごい。」 藍が小声で囁いた。
「そうだね。でも今は黙って、お母さんとお姉さんたちをしっかり見ているんだよ。」
藍が小さく、しっかりと頷いた直後。
『目出度い、今夜は本当に目出度い。』
しっとりと柔らかな、落ち着いた声。Sさんの謡。
『もし、そこな巫女。一体、何がそんなに目出度いと言うのか?』
鈴を振るような声がそれを追いかける。これは翠の謡。
術者に成り立ての頃、古の言葉を聞き取れず、当然その意味も分からなかった。
だが俺の適性と修行の成果か、今はその意味をほぼ理解できる。
ただ、これでは役割が逆ではないか? 本来なら、翠が巫女の役を。
年齢や役割の設定からしても、その方が自然なのに。
俺の些細な疑念をよそに、二人の謡は淀みなく続く。
『その眼は節穴か。この雪を見よ。ようやく年神様が御渡りになり、冬が来る。』
『何を言う。年神様は未だこの御社にお籠もりの筈であろう。』
『天岩戸』の故事をなぞる。 新たな年神様が現れたと偽って、陰神様の気を。
しかしこれは、危うい。確かに、Sさんと翠の2人なら◎命の役を。
だが、僅かに開いた岩戸を押し開く●の命。
もし、Sさんの見込みと違ったら、一体誰がその役を務めれば良いのか。
姫の『声』や俺の言霊はもちろんだが、Sさんですら、そんな力を持ってはいない。
いや何よりも。偽りで神を騙れば、相応のリスクを背負うことになる。
おそらくSさんの策以外に方法はない。それは確かだ。
しかし、神々と人の倫理観は異なる。
再会を媒することが出来ても、それでリスクを避けられるとは限らない。
もしその方便を咎められるとしたら...
!? そうか。だからSさんが新たな神の出現を騙る巫女の役を。
もしもの時は自分一人がその責を負う気で。そんな。
『新たなる神。年神様が、この地に冬をお恵み下さる。』
『新たな年神様とな。ならばそれは、一体どのような神であるか。』
Sさんは右手で大きく撫でるように地を掃き、次いで静かに天を指した。
『その御威光もて冬を統べる、青き龍の神。目出度い目出たい。』
微かに、地面が揺れた。何か途方もない気配が御社の地下から。
姫は微笑んで、宝玉を首にかけた。その色は元の漆黒に戻っている。
それなら今、此処に降っている雪は...
気配は湧き上がるように地下から御社へ。
今、その注意は確実に俺たちに、いや、Sさんに向けられている。
思わずSさんの顔を見た、もしもこの後の筋書きが狂ったら。
「大丈夫、●の命のお出ましだわ。ほら。」
Sさんの視線を辿る。御社の正面に、初老の男性が立っていた。
夜目にも鮮やかな、銀白色に光る髪。
『・・り・・・約束・・・・は・・の・まえ・・・・・・・て・・』
間違いない。男性の声、だ。
気配は今、その男性に注意を向けている。思わず溜め息。これで多分、大丈夫。
『・・・玻璃・・・約束の言葉は君の名前・・・・待たせて・・』
突然流れ込んだ映像と会話が、俺の意識を埋め尽くす。酷い目眩。
足下の地面が消え、地中深く落ちていくような。藍と丹を、強く抱き締めた。
「あの、ね...あ、そうだ。10時からTVで。」
「ふふ。もう5回目だよ。そろそろ話してくれても良いんじゃない?
別れ話だとしても、驚かない。最初から君と僕とでは到底釣り合わないと思ってた。
...もし今度の里帰りで君の御両親から。」
「違う。そんなんじゃない。」 「それなら一応安心。それなら何を?」
「出逢った日の事、憶えてる?」
「初めて君が職場に来た時なら...でもわざわざそんな事、もしかして。」
「もしかしてって、何?」
「職場で出逢う前から、君によく似た人の夢を、見てた。」
「どんな、夢?」 」 「笑わない?」 「笑ったり、しないわ。」
「何だか柔らかくて暖かくて、眠い。その時、眼の前に、女性の顔が。
『寝てはいけない。』って。その女性が君にとても似てて。え、待って、何?」
「3年前、大雪の中であなたを助けた。憶えててくれたのね。」
「あの大雪の...助けたって、どういう事?どうして君が。」
「笑わない?」 「笑わないよ。」
「きっと、信じてくれる?」 「信じる。多分、いや、絶対信じる。」
「私の実家での仕事。少しだけ、話した事があったでしょ?」
「新しい年を統べる神様をお祀りするために、だから毎年秋の終わりから。」
「本当は、私が祀られる立場。」 「...?」
「あの日の大雪は、私が降らせたの。『侵入者』を退けるためには、仕方がなかった。
当然、山の者達は予め察知して難を逃れた筈だったけれど、
どうにも胸騒ぎがして見回りに出た。それで、見つけた。
急拵えの雪洞。その中で雪に埋まっていたあなたを。
私、どれだけ驚いて、どれだけ嬉しかったか...」
「僕は...変、なのかな?」 「どうして?」
「あの大雪を降らせたのも、凍死していた筈の僕を助けてくれたのも、君。
それに、『祀られる立場』って。そのまま受け取るなら、君は神様、だ。」
「その通りよ。私は。」
「そんな突飛な話を、何故か嘘だとは思えない。むしろ、それでやっと納得できる。
あの日すっかり雪に埋まっていた僕が普通に目を覚まし、
凍傷の1つさえ負わなかった訳が。だけど。」
「だけど?」
「何故君みたいに素敵な女性、いや、神様が僕を助けたのか。
助けただけじゃなく、その、こんな風に一緒にいてくれるのか。それが分からない。
僕が、そんな価値のある人間だとは、とても思えないのに。」
「ずっと、ず~っと昔。私とあなたは一つだった。
もうそれが何時だったのか分からない位、昔に。
私とあなたは分離した時に約束した。必ずもう一度、と。」
「僕は君の、欠片ってこと?小さな、小さな。」
「力の大小と、魂の価値は関係ない。旅立ち、成長し、何時の日か還る。
あなたを見つけて、『その時』が近いと分かったけれど、
あの晩は未だ、『その時』じゃなかった。
だから出来るだけ一緒に暮らして、待つつもりだったわ。」
「『だった』って事は何か、事情が変わったんだね。一体何?」
「子供が必要になったの。使命を託すために。」
「君と僕の、子供?」 「そう。」
「一緒に暮らして、子供が生まれるのは自然な事だよ。何故わざわざそれを。」
「...子供に使命を託したら、私は此処にいられなくなる。」
「まるで、天女伝説みたいだ。でも、君を失ってまで、子供を。」
唐突に、目眩と耳鳴りが治まった。
戻ってくる。膝をついた地面の感触と、抱きしめた藍と丹の体温。
「Rさん、最後の仕上げです。」 姫の声に促されて立ち上がる。
既に御社の中の気配はなく、男性の姿も見えない。
雪は降る勢いを増し、白い闇となって御社と俺たちを包んでいた。
片膝を付き、Sさんは小声で何事か呟く。恐らくは『再会』を言祝ぐ言葉。
そのこめかみを伝う、この寒さの中で、冷や汗?
「これで冬が、新しい年がやってくる。」
ゆっくりと立ち上がり、ようやくSさんの表情が緩んだ。
当然だろう。さっきの儀式のリスクは『禁呪』をはるかに上回って。
今更に、Sさんの覚悟を知る。
「さあ、帰りましょう。急がないと私たちが凍えちゃうわ。」
そうだ、この調子で降り続いたら...
ランタンモードにして床に置いていた大型のLEDライト。
そのスイッチを前照灯モードに切り替えた。
俺が藍を、姫が丹を抱く。車を停めた場所までは多分200mと少し。
一歩踏み出した。ライトに照らされて浮かび上がるSさんと翠の後ろ姿。
立ち止まり手をつないだままで、2人は正面を見詰めている。
さらに一歩。横に立って、2人の視線をライトで辿った。
小さな階段。その先の地面には雪が積もっていない。
この雪の勢いで、まさか。
ゆっくりとライトを左右に動かし、辺りの様子を探る。
露出したままの地面は幅10m位。
御社の正面から前方へ、まるで緩やかにうねる道のように。
このまま車まで続いているとしたら長さは200mを越える。
この御社は、数十kmを隔てた◇★神社に正対していると聞いた。
そして、二つの御社を結ぶ線上に◇★湖。
ならばこの『道』は。上空で雪を遮っている『存在』とは。
『みんな、上を見ては駄目よ。さあ、前へ。』
振り向いたSさんは、唇に人差し指を当てて微笑んだ。
それは、雪を遮っている『存在』への敬意。
方便を咎められなかったし、『再会』を媒することも出来た。
そして今、俺たちの帰り道が雪から守られている。
それなら多分、その御姿を見ても咎められる事は無いのだろうけれど。
俺たちは眼を伏せたまま、不思議な道を歩いた。
◇★湖で『御神渡り』が起きたのは、その日の深夜だったと聞いた。
一般に、『御神渡り』が知られている湖はわずか。
ネットの情報では「日本では諏訪湖だけ」というものさえある。
だがこれは正確ではない。氷の体積変化によって起こる現象とするなら、
湖面が全氷結する湖の全てで、それは起こり得る。
ただ、それが『御神渡り』かどうかを神官が認定し、
結果を公表するのが諏訪湖だけ。だから諏訪湖以外で同じ現象が起きても、
本来の意味での『御神渡り』ではない。何よりも。
古い伝承が息づく地域では重要な神事を公開しない場合も多い。
つまり神官が『御神渡り』と認定しても、公表しない事例がある。◇★湖もその例。
諏訪湖より南に位置するが、標高が高いので全氷結する期間がある。
しかし、その現象が起きる事は公にされていない。
かなり人里から離れていて、その痕跡はすぐに消える。
まれにその湖を訪れる旅人がそれを偶然眼にする機会も皆無と言って良い。
多分、◇★湖の他にも
「お父さん。」
心臓が、止まるかと思った。つい、画面に集中してて。
「そろそろ夕ご飯の準備って、お姉ちゃんが。」
するりと、翠は俺の膝の上に座った。
「あ、これ...」 画面右下の写真に見入っている。
『御神渡り』で画像検索して表示された数々の写真。
「お父さん、これ、神様の通った跡でしょ?」 指さしたのはやはり右下の一枚。
「そう、『御神渡り』。でも、他のは違うの?」 「違う。」 「どうして?」
「だってほら、これには神様の色が残ってる。他のはそうじゃない。」
色? 例えばオーラのような?
どの写真の氷も俺には白一色。しかし、翠はその中の一枚に。
「お父さん。お父さんてば。」 「あ、ゴメン。何?」
「通った跡なのに、こう、なってるのは何故?」
翠は両手で大きく山の形を描いてみせた。
「足跡ならへこむはずだよ。なんでかな?」
理由は分からないけど、足跡とは違うと思う。」 「足跡じゃないの?」
「昨日の神様が通った後も、氷がこうなったって、お母さんが言ってたから。」
「...そっか、空を飛んだら、足跡つかないね...」
一瞬で、深い思考に入る。
空気の動きまでも止めるような、翠の集中力はSさん譲り。
突然、空気が動いた。 「分かった!」
するりと俺の膝から床へ。一歩踏み出してから、翠は振り返った。
「行こう、お父さん。遅れたら怒られるよ。」
「翠、ちょっと待って。分かったって、何が?」
「え?」 「神様の通った跡が、こう、なってる理由。」
「翠が思ってるだけで、間違ってるかも知れないし。お父さんも自分で考えて。」
「そんな、意地悪しないで教えてよ。ね、お願い。」
「翠は、お父さんに意地悪、なんか...」 翠の眼がじわりと潤む。
マズい。慌てて抱き上げた。
「ゴメン、言い方が悪かった。翠はお父さんより『見える』からさ。」
俺を見詰める、綺麗な瞳。何とか最悪の事態は免れそうだ。」
翠を抱いたまま、廊下に出る。キッチンへ。
「翠が考えた理由を教えてよ、間違ってても良いから。
もちろんお父さんも自分で考える。それで、どっちが正解に近いか
一緒にお母さんにも聞いてみよう。」
「うん。じゃあ今はお母さんには内緒。」 翠は俺の耳に口を寄せた
「あのね、神様が通るときに、湖から...」
夕食の後でそれを聞いたSさんは、「ほとんど正解」、そう言って翠を抱き締めた。
~風の花~ 完

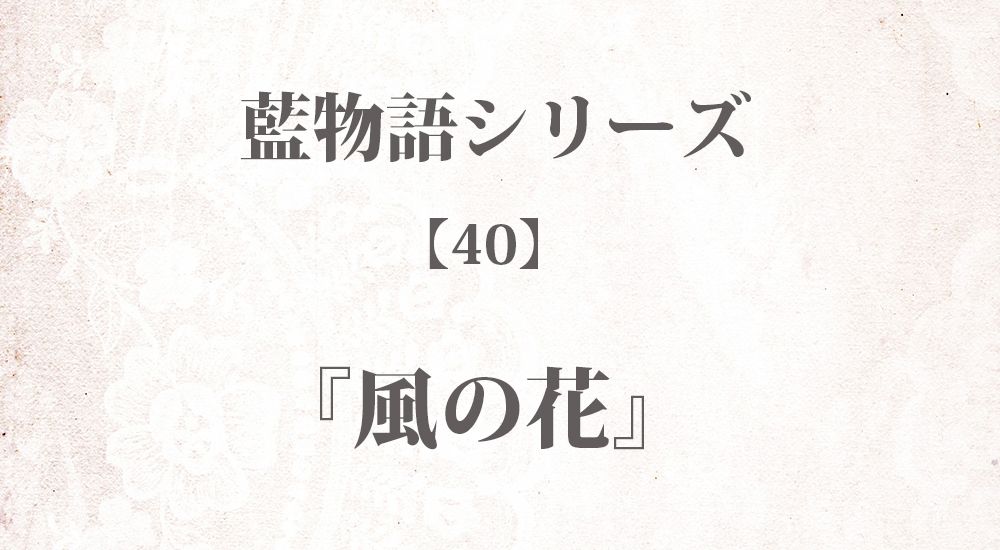

コメント