藍物語シリーズ【7】
『光と影』
上
枕元で目覚まし時計が鳴っている。まだ、眠い。
昨夜、図書室で資料を調べていたら夢中になり、気が付いたら既に明け方。
Sさんや翠を起こしてしまうと心苦しいので、自分の部屋で仮眠を取っていた。
そろそろ、姫を高校へ送る時間。起きなければ...
「起きて下さい。もう、時間ですよ。」
しまった、二度寝したか?
誰かが俺の体に覆い被さっている。毛布越しに感じる体温、右の瞼と頬にキスの感触。
眼を開けると姫が俺の顔を覗き込んでいた。
「今朝は寝坊助さんですね。」 白く細い指が俺の髪を撫でる。
自分の心臓の音が耳の中に大きく響く。姫にも、この音は聞こえているんじゃないのか?
姫の腰に右腕を廻し、体を入れ替える。 「あっ。」
制服姿の姫が俺の腕の中にいた。
「こんな起こし方して。僕が『その気』になっちゃったらどうするんです?」
照れ隠しの、冗談のつもりだった。
しかし、姫は真面目な顔で俺の目を真っ直ぐに見詰めた。
「私は...私はそれでも良いです。」
「え?」 心臓が、止まるかと思った。
「でも、今は駄目。これから、学校ですから。」
ふわり、と、姫は俺の腕をすり抜けた。ベッドの端に座り、髪と制服を整える。
「Rさん、とても眠そうだし、今日はSさんに送ってもらいますね。」
呆気にとられる俺を残したまま、姫はドアを閉めて出て行ってしまった。
暫く動悸が収まるのを待って部屋を出ると、お屋敷の中にはもう誰もいない。
仕方が無いので1人で朝食を食べ、コーヒーを淹れる。
一時間ほどすると、Sさんが翠を抱いて戻ってきた。
「な~んだ。元気そうじゃない。Lが『体調悪そう』って言うから心配してたのに。」
「ただの寝不足ですよ。それより...」 いや、あれ、何て説明すれば良いんだ?
「それより、何よ?途中で止めたら気になるでしょ。」
しまった。つい、口を滑らせた。Sさんが相手では、もう。
俺が話し終わると、Sさんは右手を額に当てて俯いた。
「R君。」 「はい。」
「Lがそこまで思い切ったのに、どうして学校に行かせちゃったの?」
「どうしてって言われても。Lさんは『これから学校ですから』って。」
Sさんは大きく溜め息をついた。
「馬鹿ね。Lが『じゃあ、今、その気になって下さい』なんて言える訳ないじゃないの。
そのまま最後までしちゃえば良かったのよ。L、可哀想に。
もうすぐ就職休みなんだから、1日くらい学校休んでも問題ないでしょ。」
「そんな、だって、Lさんが僕を起こしに行って帰ってこなかったら。」
「ホントに馬鹿ね。私、それ位の気は回るわよ?
こんな時、男の方が主導権を取らなかったら話が進まないんだから。」
「いや、でも。」 「もう、何?」
「僕が、初めての時は、その...Sさんが。」
Sさんの頬が見る見る真っ赤に染まる。
「馬鹿!」 「痛たたたた。」
思い切り左頬をつねられた。
「私は年上だし。あの時は、Lの事もあって。」 「でも。Sさんは」
「もうその話はお終い!今はLの話だから、良い?」 「はい。」
「就職休みに入ったら2人で旅行、良い考えでしょ。前に行った温泉なんてどう?
風情があるし、慣れてる場所ならLもあんまり緊張しないはず。予約はしておくから。」
「2人で旅行って、2人きりで、ですか?」
「あ・た・り・ま・え・です。みんなで出掛けたらLが気兼ねするに決まってるじゃない。
それから、ちゃんと自分でLを誘いなさいよ。私に言われたってのは絶対NG。」
その日の午後、俺はいつものように姫を迎えに出た。
終業のチャイムが鳴り、暫くして裏門から姫が出て来た。車に向かって歩いてくる。
俺は車を降り、姫から鞄を受け取って助手席のドアを開けた。
姫が軽く会釈をして助手席に乗り込む。
ドアを閉めて運転席に戻り、鞄を後部座席、ベビーシートの脇に置く。車を出した。
姫は窓の外を見て黙っている。とてつもなく気まずい時間。
「高校、もうすぐ就職休みですよね。」
「はい。」 姫はまだ窓の外を見ている。
「何日から休みですか?」
「講座があるので、本当のお休みは16日からです。2月16日。」
やはり窓の外を見たまま、姫は小さな声で答えた。
「休みに入ったら旅行に行きましょう。2人きりで。」
「えっ?」 姫は驚いた顔で振り向いた。
「やっと、こっちを向いてくれましたね。ホッとしました。」
「だって、私、今朝あんな事。恥ずかしくて。」
「恥ずかしくなんかありません。嬉しくて、ドキドキしました。」
「そう、ですか?」
「でも、旅行に行くまであれは禁止ですよ?心臓が、持ちませんから。」
「はい。」
姫は一言『嬉しい』と呟いたあと、俺の左肩に頭を預けてずっと眼を閉じていた。
就職休みに入って4日目、旅行の前日。
姫は昼過ぎから夕方まで、嬉しそうに荷物をまとめたり服を選んだりしていた。
今夜は俺が当番。ベビーベッドの中、翠の様子に気を配りながら夕食の支度を進める。
料理が出来たところに姫がやって来たので配膳を任せ
俺は屋根裏部屋の『観測室』にSさんを呼びに行った。
ドアをノックする。 「どうぞ。」
Sさんは天窓から上体を乗り出して夜空を観測していた。
「夕食の準備が出来ました。」 「了解。」
天窓を閉め、Sさんが階段を降りてくる。少し表情が暗い。
「何か悪い兆しでも?」
「う~ん、悪い兆しという程でもないけど。流星が少し、ね。
でも、旅行の時期は変えられないし。」 Sさんは首を振って、ふっ、と息を吐いた。
「Lはもう一人前だから過保護は良くない。大丈夫。」
Sさんは左手の薬指を舐め、何か小声で呟きながらその指で俺の額に触れた。
あ、これ前にも...
「R君、夕食なんでしょ?先に降りるわよ?」
え?今、俺は何をしてた?観測室のドアをくぐるSさんの後ろ姿。
「待って下さい。僕も一緒に降ります。」
2月20日、旅行当日は晴天になった。
2月にしては暖かく、格好の旅行日和だ。
2人分の荷物を持ち、玄関を出ようとすると姫が振り向いた。
「私、先に車に行って待ってます。Rさんは後から来て下さい。」
Sさんと翠に挨拶してから、ということか。胸の奥が、じぃん、と熱くなる。
背後から肩を叩かれた。翠を抱いたSさんが微笑んでいる。
「こんな気遣いが出来るなんて。やっぱり、L、大人になったわね。
R君もLを見習って。間違っても毎晩電話なんてしちゃダメよ。
旅行が終わるまでの4日間、Lの事だけを考えてあげて。」
「でも」
Sさんは俺の唇に人差し指を当てた。
「私は大丈夫。4日間も翠を独り占め。悪い話じゃないでしょ?」
指示通り、黙って翠の頬とSさんの唇にキスをした。
「それとね、これ預かって。」
Sさんは白い布で出来た小さな袋を俺の掌に載せた。
綺麗な刺繍、袋の口を縛る赤い糸。これは、前に何度か見たことがある。
「何か困った事があったら、これをLに渡して。使わずに済むなら良いけど
やっぱり心配だから。使わなかったら後でちゃんと返してね。」
Sさんは軽く俺の背中を押した。
「はい、いってらっしゃい。あんまり待たせちゃ駄目。」
「お待たせしました。出発しましょう。」 「はい。」 姫の輝くような笑顔。
半日かけて車を走らせ、予約の時間より少し早く旅館に到着した。
荷物を持ってフロントへ向かう。自動ドアをくぐり、旅館のロビーに入った。
その瞬間、奇妙な違和感があった。前回来た時とは全然違う。何だ、これは?
素早く『鍵』をかけ、それとなく辺りの様子を窺う。
あれ、か。
ロビーの端、中庭に面した大きなガラス窓の側に
小さな男の子が1人、ぽつんと立っていた。おそらく小学校低学年。
しかし、中庭を向いて立っている後ろ姿は、とても人間だとは思えない。
まるで『空っぽ』。子供服売り場の、良く出来たマネキンが立っているようだ。
すぐ傍のソファに両親らしき男女が座っているが、こちらもどこか影が薄い。
姫が俺の上着の裾をそっと引っ張った。
「そのまま、フロントへ。」
歩きながら小声で尋ねる。 「何故、生身の人間があんな風に?」
「恐らく、何かに何度も深く憑依されて、心が壊れかけているんです。
でも、あれほど酷い状態は初めて見ました。あんな小さい子なのに。」
姫は廊下に視線を落とし、小さく溜め息をついた。
フロントで俺たちに対応してくれたのは若女将のAさん。
AさんはSさんの同期生で親友。大学卒業後、直ぐにこの旅館に嫁いで若女将になった人だ。
Sさんが『鋭い』というほど勘が良い人で、客に対する心遣いがとても細かい。
俺がこの旅館に来るのは3回目だが、Sさんと姫は以前からの常連だったようで
Aさんは姫を『Lちゃん』と呼んでとても可愛がっていたし、姫もAさんに懐いていた。
勿論AさんはSさんと姫の力の事を知っていて、2人と俺の事情も承知してくれている。
それでも俺たちに極々普通に接してくれるので、とても居心地が良い。
俺が宿帳に記入している間に、姫がAさんに小声で話しかけた。
「あの、今ロビーにいる小さな男の子なんですけど。」
Aさんも声を潜めた。 「やっぱり、何か変、よね。」
「はい、かなり深刻です。助けてあげられれば良いんですが。」
姫の表情は暗かった。確かに、姫の気持ちは良く解る。
以前、自殺した女子高生の一件に関わった時、
女子高生の父親は姫の言うことを最初は全く信用しなかった。
今も、両親にいきなり『何度も憑依されたせいで息子さんの心は』なんて言おうものなら
こっちが警戒されるだけだし、下手すると名誉毀損で警察沙汰だ。
何か、とっかかりが無ければ、こちらから関わる事は難しい。
宿帳の記入を終え、部屋の鍵を受け取った時、首筋に冷たい風を感じた。
振り向くと、あの男の子が立っていて俺たちを見詰めている。
『鍵』を掛けていたとは言え、気配が動いたのを全く感じなかった
距離は約3m、一体、いつの間に?
真っ直ぐ俺たちを見詰めたまま、近付いてくる。
「お姉ちゃん、名前、なんていうの?」 乾いた、冷たい声。
すうっ、と姫がかがんで男の子と視線を合わせた。
「私の名前はL、このお兄ちゃんはRさん。君の名前は?」
「僕の名前は...」 言い淀み、眼がふらふらと泳ぐ。
「うん、君の名前は?」 姫が微笑み、重ねて聞く。
「...亨(とおる)。そう、亨。僕の名前。」
「亨、何してるの。いきなり知らない人に話しかけちゃ失礼でしょ。」
母親らしき女性が背後から男の子の手を取って抱き寄せた。
「済みません。この子、少し」
「いいえ、構いませんよ。」
姫は女性に向かって微笑んだあと、また男の子と視線を合わせた。
「私たち、今日からここに泊まるの。また、会うかもね。」
姫が立ち上がって振り向き、俺の腕に手を絡ませる。
「お待たせしました。」 「はい。」
部屋の鍵を開けた。 「どうぞ。」 「失礼します。」
玄関で靴を脱ぎ、部屋の中へ入る。 「素敵なお部屋。」
2人部屋だからいつもより小さな部屋、それでも全然安っぽい感じはしない。
豪華、という感じではないが、とても上品で落ち着いた雰囲気がある。
どうやらSさんは、かなり良い部屋を手配してくれたようだ。
姫が奥の間の障子を開けた。 「綺麗...」
アルミサッシの向こうは良く手入れされた小さな庭。
庭を囲む生け垣の向こうには白い雪を頂く高い山々が見える。
あの山の方角からして、このサッシは東向き。朝陽がさぞかし綺麗だろう。
姫が振り向いた。
「Rさん、私、釣りがしたいです。ルアーで。」 眼がキラキラと輝いている。
「良いですよ。でも夕方は気温が低くて魚の活性も低いと思います。
明日のお昼、天気が良ければ挑戦してみましょう。」 「はい。」
その時、ノックの音がした。
俺がドアを開けると、Aさんが丸い漆塗りのお盆を持って立っていた。
お盆の上には急須と茶菓子、そして湯呑みが3口。
「R君、Lちゃんと2人水入らずのところ申し訳ないんだけど。少しだけ、良い?」
「もちろんです。どうぞ、中へ。」 「御免ね。」
Aさんは部屋に備え付けのポットから急須にお湯を注いだ。
炬燵の上に手際よく3口の湯呑みを並べる。白い湯気、お茶の香り。
3人で炬燵を囲む。一口お茶を飲んだ後、姫が尋ねた。
「さっきの、男の子の件ですね?」
「そう。ホントはこんな事話しちゃいけないんだけど、あの御家族の予約を受けた時から
すごく悪い予感がしてたの。ほら、うちの旅館はいつもなら常連さんばかりでしょ?
でも、ある常連さんから『是非に』という紹介が有って、
それで新規だったけどあの御家族の予約を受けた。」
湯呑みをもつAさんの手は微かに震えている。
「でも、あの男の子の様子はどう見ても普通じゃないし、気になって仕方が無かった。
そしたら、今朝『昨夜変な人影を見た』って苦情が2件あったの。
うちの旅館、今までそんな話は全然無かったのに。」
俺はできるだけ穏やかに尋ねた。 「それがあの男の子と関係していると?」
「わからない。でも、あの御家族のチェックインが昨日だったから
もしかしたら、と思って。それにさっきLちゃんが...」
Aさんは湯呑みのお茶を一気に飲み干して姫を見詰めた。
「Lちゃん、あなたさっき『深刻』って言ったでしょ?ホントのところ、どう?」
「あの男の子の心は、もうかなりの部分が壊れてしまっています。
心が完全に壊れて死んでしまったら、体も、そう長くは保ちません。」
「最悪の事態も考えて心の準備をしなきゃいけないって事ね?」
「そうです。」 「分かった。ありがとう。」
Aさんの手の震えは止まっていた。強い人だ。
Sさんと姫に同行して、俺がこの旅館に初めて来たのは一昨年の5月。
既にその時から女将の具合が悪く、Aさんがこの旅館を切り盛りしていた。
女将の具合はよほど悪いのだろう。俺はまだ女将に会ったことはない。
そんな状態で旅館で何か事件でも起こったら...すごい重圧だろうに。
姫が右手をAさんの左手にそっと重ねた。
「これもきっと何かの縁ですから、私たち、出来るだけの事をします。」
「縁?」
「はい、さっき男の子が私の名前を聞きましたよね。
あんな状態で、縁のない他人に興味を持つはずはありません。
だからきっと、まだ望みはあると思います。」
「ありがとう。でも、絶対に無理しちゃ駄目よ。
あなたたちに何かあったら、私、Sに申し訳が立たない。
それから、必要な物があったら何でも言ってね。必ず用意するから。」
「了解です。」
姫と俺がぴっと小さく敬礼をすると、Aさんはようやく微笑んだ。
中
荷物を解いて服をクローゼットに整理したり、2人で炬燵に入って
地元TV局のCMを見て盛り上がったりしてるうちに、6時55分のニュースが始まった。
「温泉、入りましょうか。」 「はい。」
部屋の風呂にも温泉のお湯が引かれているし大きな湯船も有る。
でも、いきなり2人で風呂に入るのは気まずいし姫にも失礼、何となくそんな気がした。
温泉に向かう途中でフロントに寄り、Aさんに食事の時間を伝える。
「これからお風呂を頂くので、夕食は8時にお願いします。」
「承知致しました。明日の朝食は何時に致しましょう?」
「え?でも朝食は。」 これまで朝食はいつも大食堂で食べていた。
Aさんは俺に小声で囁いた。「話があるの。私が行くから。またまた御免ね。」
俺も小声で答えた「了解です。」
「では、朝食は8時半でお願いします。」 「確かに、承りました。」
温泉には室内の大きな湯船と、少し小さな露天風呂がある。
露天風呂に入っている客も多かったが、
移動する時に寒い思いをするのが嫌なので、俺はいつも室内の湯船に入る。
この温泉は少し温めなので、長い時間入っていても湯疲れし難い。
ゆっくりと温泉を堪能し、浴衣に着替えてからペットボトルの冷たいお茶を買う。
温泉の入り口近くのソファに座り、お茶を飲みながら待っていると姫が出て来た。
「お待たせしました。あ、お茶、私にも下さい。」
俺の手からペットボトルを取ってお茶を飲む。「冷たくて美味しい。」
上気して薄紅色に染まった頬にペットボトルを当てた。
備え付けの花柄の浴衣に、ほんの少し栗色がかった髪が映える。美しい。
「Lさん、浴衣似合ってますよ。とても、綺麗です。」
姫の頬がますます紅くなった。 「有り難う御座います。」
「湯冷めしないうちに部屋に戻って食事にしましょう。」 「はい。」
部屋に戻ってしばらくするとフロントから確認の電話があり、夕食が運ばれてきた。
Aさんと仲居さんが炬燵に料理を並べていく。俺と姫は思わず顔を見合わせた。
とても豪華な料理だ。料理を並べ終わると仲居さんは部屋を出て、Aさんだけが残った。
「何だか凄い料理ですね。ちょっと気が引けます。」
「せめてもの気持ち、気にしないで。板長さんに頼んでおいたから、味は保証付き。」
「あ、R君。」 「はい?」
「お酒も付けたけど、1本だけ。お代わりは駄目よ。」 「了解です。」
まあ、酔いつぶれて寝てしまったりしたら気まずいことになるし。
「じゃ、ゆっくり食事を楽しんでね。」 Aさんは軽く会釈して部屋を出て行った。
さっき、『明日話がある』と言っていたから、きっと心配事がある筈なのに
おくびにも出さない。さすがの気配りだ。
食事を済ませ、食器を片付けてもらうとそれからは2人きり。微妙な空気になった。
「そう言えば、今夜辺りから満月ですよ。」 照れ隠しに奥の間の障子を開ける。
良く晴れた空に、ほとんど真ん丸の明るい月が浮かんでいた。
「すごく綺麗なお月さまですね。」 姫が俺の右隣に並ぶ。
しばらく2人で月を眺めた後、姫の肩を抱いた。ここは俺が、リードしないと。
「そろそろ寝ましょうか?」 ああ、我ながら何て陳腐な台詞だ。
姫が障子を閉じて部屋の灯りを消した。
「あの、私、もう一度シャワーを使います。待ってて下さい。」
1時間位前にお風呂に入ったばかりなのに。舞い上がっているのはお互い様、か。
布団の中で待っていると、五分ほどで姫が戻ってきた。俺の隣に座る。
俺も上体を起こし、姫を抱きしめた。唇にキスをする。
帯を解いて浴衣をそっと脱がせた。姫は下着を身に着けていなかった。
障子越しの月の光に照らされた肌は、まるで新雪のように白く、美しい。
「とても綺麗で、ドキドキします。」
「お月さまが明る過ぎて、恥ずかしい、です。」 消え入りそうな、小さな声。
そっと姫の体を抱く。俺の右手が肩に触れると、姫は小さく身を震わせた。
シャワーを使ったばかりなのに肌がとても冷たい。かなり、緊張しているのだろう。
「Lさん。」 「はい。」 「怖いですか?」 「少し、怖いです。ごめんなさい。」
「謝ることはありません。」 俺は旅行を決めてからずっと考えていた事を口にした。
「安心して下さい。今夜は最後までは、しませんから。」
「そんな。」
「Lさんの心は僕を受け入れてくれていても、Lさんの体は僕が怖いんです。
初めてなんですから、怖いのは当たり前ですよね?」
「でも。」
「だから、Lさんの体に僕を憶えてもらいます。そしたらきっと、明日とか明後日とかには
体の準備もできますよ。最後までするのはそれからでも良いでしょ?
折角2人きりなのに、Lさんが怖かったり痛かったりしたら、僕が辛いです。」
「ありがとう、ございます。」 姫は俺の胸に頭を預けた。
「でもLさん。」 「え?」 「慣れてもらう為には。」 「はい。」
「あんな所やこんな所に触ったり、少~し恥ずかしい格好をしてもらったり、
色々しないといけないんですよ?覚悟は良いですね。」
「...Rさんって、やっぱり『変態』なんですか?」
「僕が『変態』なら男はみんな『変態』ですから。安心して下さい。」
「変な慰め方。」 姫は優しく微笑んだ。
夜中、眼を覚ますと、姫が浴衣を羽織って布団に座っていた。
少し、障子が開いて月の光が差し込んでいる。庭の玉石が光って見えた。
「どうしたんです?風邪引きますよ。」
姫は布団に潜り込んで俺の胸に顔を埋めた。
「Rさん、私の体、本当に準備が出来ると思いますか?」
「出来ますよ。もし、この旅行の間に準備が出来なくても焦らないで」
「嫌!そんなの嫌です!」 「どうしたんです?」
「Rさん、約束して下さい。」 「何を約束するんですか?」
「準備が出来なくても、この旅行の間に、最後までするって。じゃないと私」
姫の頬を涙が伝っていた。キスをして姫の唇を塞ぐ。
「分かりました。約束します。でも、そのためにはまず、勝手に布団から出て
寂しくしていないで、朝まで僕と手を繋いで寝なきゃ駄目ですよ?」
「はい...ごめんなさい。」
「Rさん、Rさん。」
眼を開けると姫が俺の顔を覗き込んでいた。障子がうっすらと茜色に染まっている。
「もう、手を離しても良いですか?」 そういえば昨夜、そんな話を...。
姫を抱き寄せておでこにキスをした。 「はい、これで離しても大丈夫。」
8時25分にフロントから電話があり、朝食が運ばれてきた。
2人の仲居さんは部屋に入らず、Aさんにお膳を渡して戻っていった。
Aさんが炬燵にお膳を並べる。白いご飯、お味噌汁、焼き魚とほうれん草のおひたし。
料理からふわふわと湯気が立って良い香りが部屋を満たした。
「食べ終わったら電話してね。少し、話があるから。」 「了解です。」
食器を片付けてもらった後、3人で炬燵を囲む。
お茶を飲み干してから俺は尋ねた。「Aさんのお話って何ですか?」
Aさんは俺の湯呑みにお茶を注いでから話し始めた。
「まず、あの御家族の事なんだけど。紹介して下さった常連さんに聞いてみたの。」
「何か新しい情報が有ったんですね?」
「男の子は小学2年生。それで、様子がおかしくなったのは去年の夏休み辺りから。
秋からは学校にも行けなくなって、それで常連さんが気分転換に温泉を勧めた。」
「男の子の様子がおかしくなった原因は分かりませんか?」
「それは全然。ご両親が話したがらないみたい。」
原因が分からないのでは対応の仕様がない。
「それとね。」 Aさんは声を潜めた。
「今朝も一件、苦情があったの。」 「昨夜変な人影を見た、と?」 「そう。」
初めて姫が口を開いた。 「人影を見たお客さんに共通点はありませんか?」
「共通点?」 Aさんは何か思い当たることがあったようだ。
「女性、比較的若い女性ね。ご夫婦が2組...それと恋人同士が1組。」
「それは重要な情報かも知れません。そのお客さん達は今夜も宿泊を?」
「今朝苦情のあったご夫婦が1組だけ。今夜は部屋を移って頂くことになってる。」
「その部屋に対策をして置いた方が良いですね。案内して下さい。
それから白米を少し頂けますか?ひとつまみだけで良いですから。」
「分かった。」 Aさんの表情がぴいんと引き締まった。
「どうぞ、この部屋よ。」 Aさんが件の部屋の鍵を開けた。
姫の指示に従い、俺は全ての窓、最後に部屋のドアに手を触れて結界を張った。
「これで大丈夫。夜は出来るだけ部屋から外へ出ないように伝えて下さい。」
「ありがとう。白米はフロントに届けて置くから。」 「了解です。」
「それじゃRさん、部屋で支度して釣りに行きましょう。」
「晴れてるけど、多分まだ水温が低いから釣れるかどうか。」
「今の時期、釣りは難しいわよ。昼ご飯はどうする?」 Aさんは心配そうだ。
「1時でお願いします。」 「分かった。早める時は電話してね。」
支度をして部屋を出た。釣り具はレンタルだから手ぶらで良い。
ロビーを抜けて玄関を抜けると、あの男の子が立っていた。
「おはよう。亨君、1人なの?」 姫が微笑んで視線を合わせる。
「Lさん、と、Rさんは、兄妹?」 「え?」 「それとも、お友達?」
「ふふ、ちょっとショックだな~。私、Rさんのお嫁さんなの。私たち、夫婦に見えない?」
「Lさんは、Rさんが好き?幸せ?」 姫が意味ありげに微笑んで俺を見た。
違和感。普段の姫なら絶対に、こんな大人びた対応はしない。
そうか、そういうことか。俺もかがんで男の子と視線を合わせる。
「僕たち、新婚旅行なんだよ。だから、すごく幸せ。」 「ね~。」 姫が俺の手を取る。
「これから2人で釣りに行くの。少し寒いから、亨君も早く部屋に戻ってね。」
「新婚旅行...」 呟く男の子を残して俺たちは手を繋いだまま釣り場へ向かった。
「もう、そろそろ帰りましょうか?」 姫に声を掛けた。
かれこれ1時間半ほどルアーを投げているが、時折小さなアタリがあるだけで
全く釣れない。やはりまだ水温が低くて魚の活性も上がっていないのだろう。
天気は良いが、気温はそれほど高くない。ずっと風に吹かれているとさすがに体も冷えてくる。
「そうですね。明日はもっと暖かくなるみたいですから、明日に期待しましょう。」
「じゃあ、体も冷えちゃったし、お風呂で温まってから昼ご飯にしませんか?」
「あの、それなら...」 「2人で部屋のお風呂、それでも良いですか?」 「はい。」
フロントでAさんから白米の入った小さな封筒を受け取り、部屋へ戻った。
「わざと、あの男の子を刺激したんですね?」
炬燵で食後のお茶を飲みながら俺は尋ねた。
「はい、あの子の体を使っている人を呼び出したくて。」
「その人、まだ生きているような気がするんですが。」
「私もそう思います。多分『生き霊』ですね。『生き霊』は力が強いし、とても厄介です。
Rさんは何故『まだ生きている』と思ったんですか?」
「何て言うか、もし死んだ人ならもっと、それこそ一日中男の子につきまとうような気がして。
それに旅館のお客さんが人影を見たのは夜だから、昼間働いてる人かな?と。」
「私も同じ意見です。それに、『生き霊』に憑依された人は大きなダメージを受けます。
『死霊』は形を変えて相手の心の隙間に入り込みますが、『生き霊』は形を変えられないから
相手の心を大きく、自分の形に合わせて壊してから入り込むんです。」
「それであの子はあんな状態に?」 「間違いないと思います。」
「じゃあ、あの子がLさんに興味を持ったのは、その『生き霊』が...」
「今夜、それを確かめられるかも知れません。」
姫が立ち上がり、壁にかけた上着のポケットから封筒を取り出した。
奥の間の障子とサッシを開く。庭から爽やかな風が吹き込んできた。
「そのお米、どうするんですか?」
「これで、手がかりを探ってみます。」
姫はサッシの外の濡れ縁と、その下の地面に数粒ずつ、白米を撒いた。
「小鳥が食べちゃったら困るから少し残しておきますね。」
サッシと障子を閉めてから、姫は大きく伸びをした。
「少し寝不足気味なのでお昼寝します。Rさんはどうしますか?」
お互い緊張して気疲れしていたせいもあったのだろう。
俺たちが眼を覚ましたのは夕方5時を過ぎてからだった。
のんびりとお喋りしながらTVを見て、今度は2人で大浴場に出掛けた。
そして今夜もAさんの心尽くし、板長さん特製の豪華な晩ご飯を食べてお腹一杯。
濡れ縁に撒いた白米の様子を確かめて、準備は整った。
「Rさん。」 「はい?」
「あの、折角昨夜約束してもらったのに、申し訳ないんですけど。」
『生き霊』が寄ってくるかもしれない夜、女の子として気分が良かろうはずがない。
「分かってます。今夜は手を繋いでいるだけにした方が良いんじゃないですか?」
姫は俺の胸に顔を埋めて小さく首を振る。
「慣れるだけなら平気です。早く準備が出来るようにしなきゃ。」
満月の光が障子を照らしていた。
「Rさん。」 姫の声だ。
いつの間にか寝てしまっていた。姫の手を握ったまま、眼を開ける。
姫の視線を辿ると、障子にぼんやりと人影が映っていた。やはり、女性のようだ。
姫をしっかり抱きしめて息を凝らす。姫も無言で障子を見詰めている。
「・こに・る ・のおんな・ あ・なにしあわ・そ・に ・たしは
私たちはこ・なに こんなに不幸なのに ・るせない。」
ベトベトと粘り着くように濃密な怨嗟の声。聞くだけで吐き気がする。
気配が近付いてくる。障子に映る影は細部まで判別出来た。
ショートカット、おそらくスキーウェア。ジャケットの襟のファーまで分かる。
気配が更に近付く、もう、濡れ縁に。
「あ」 一言だけ残して、突然気配が消えた。
「凄かったですね。本当に怖かった。まだ鳥肌が。」
姫は俺の腕の中で震えている。
「どうしてあんな風に。あんなに、あんなに人を憎むなんて。」
翌朝。日の出を待って、俺と姫は濡れ縁周辺に撒いた白米を検めた。
濡れ縁の上の白米のうち、3粒が赤黒く染まっている。微かだが、辺りが生臭い。
「これ、血ですよね?」 「はい、素手では触らないで下さい。」
姫がフロントに電話を掛けると、Aさんが割り箸と灰皿を持って来てくれた。
赤黒く染まった米を、俺は慎重に割り箸で灰皿に移した。
灰皿を姫に渡してから、もう一度濡れ縁の下の地面を確かめる。
「大丈夫です。他の米には異常ありません。」 「ありがとうございます。」
姫は庭に降り、濡れ縁の端に置いた灰皿の上に左手をかざして眼を閉じた。
Aさんが息を詰めて姫を見ている。ぴいん、と空気が張り詰めた。
しばらくして姫が眼を開けた。「大体、事情が分かりました。」
深呼吸をして灰皿に右手をかざすと、3粒の米が燻り始めた。
煙と共に異様な気配が立ち上り、Aさんが口を押さえてトイレに駆け込む。
姫は米が完全に灰になったのを確かめてからサッシと障子を閉めた。
「あれは、何だったの?」 Aさんの顔はまだ蒼白い。
「足跡、みたいなものです。あの男の子の心を通路にしてやってきたものの。
焚き上げることは出来ないので燼滅(じんめつ)しました。
『本体』が近くまで来てるみたいで、Aさんには刺激が強すぎましたね。ごめんなさい。」
「私は良いけど...『本体』って。お客様が見た人影、『生き霊』なの?」
さすがに勘の良い人だ。
「はい。これから暫くは飛び込みのお客、特に若い女性は絶対に断って下さい。」
「分かった。フロントにも伝えて置く。」
Aさんが部屋を出て行くと、姫の顔が一気に険しくなった。
その『生き霊』がどんなに強力だとしても、姫はきっと上手く対応出来るだろう。
Sさんに『一人前』と言われた人なのだ。その姫が対応に苦慮しているとしたら。
「その後のことを考えているんですね?」
「はい、正直、まだどうすれば良いのか判りません。あまりにも憑依の段階が深くて、
憑依を完全に解けばあの子の心自体を維持できなくなります。」
「つまりあの子の命も?」 「はい。」
体の組織に深く食い込んだ腫瘍を切除できないのと同じような感じだろうか。
姫は暫く黙り込んでいたが、突然立ち上がった。
「考えるのは後にして、釣りに行きましょう。」
「確かに今日は水温も上がっていそうですが、良いんですか?」
「釣りをしてとっかかりを作ります。協力して下さいね。」
下
今日は曇っているが気温は昨日より高い、水温も上がっているのだろう。
昨日とは打って変わって魚の反応は上々だった。
一時間ほどで既に8尾を釣り上げ、2人分のキープ制限10尾も間近だ。
姫はとても楽しそうにルアーを投げている。
しかし今、釣りなんかしていて本当に良いのだろうか?
その時、首筋に冷たい風を感じた。
振り向くと、あの男の子が立っている。その後ろには男の子の両親。
姫が釣りを中断して男の子と視線を合わせた。
「亨君も釣りにきたの?今日は良く釣れてるの、ほら。」バケツの中身を見せる。
「亨が釣りに行きたいと言い出しまして。その、お二人と一緒に、と。」
小さく頭を下げた後、父親が申し訳なさそうに言った。
「構いませんよ。僕らはルアーなので餌釣りとは競合しませんから。」
姫は俺の右隣で釣りを再開した。正直、あまり男の子を姫に近づけたくない。
男の子の父親は俺の左隣にレンタルの折りたたみ椅子を3つ並べて釣りを始めた。
俺のすぐ左隣が母親、その隣が男の子、そして俺から一番離れて父親。
俺が『競合しない』と言ったものの、釣りをしているのは父親だけだから、
一応俺たちに気を遣っているのだろう。
だとすると父親の精神的な活動レベルはそれ程低くはない。
問題は男の子と、そして母親だった。
父親が魚を釣り上げてもほとんど反応はなく、ボンヤリと水面を眺めている。
男の子は仕方ないとしても、母親の精神的な活動レベルがかなり低い。
男の子の件での心労は大変なものだろうが、それにしても。
これではまるで、母親も憑依されているかのようだ。
30分程釣りを続けただろうか、姫が大きな声を上げた。
「あ、これ、大物かも?」 そんなに竿は曲がっていないのに?
姫が俺から離れていく。取り敢えず玉網(タモ)を持って後を追う。
「な~んだ。あんまり大きくなかったね~。でも掬って、念のため。」
念のためも何も、玉網全然要りませんよね?このチビヤマメなら。
俺が膝をついて小さなヤマメを掬うと、姫が小声で囁いた。
「さっき、気配を感じました。男の子の動きに、注意して下さい。」
成る程、それで。「了解です。」
「全然小さかったです、恥ずかし~。」
姫って...演技派なんですね、Sさんも真っ青の。
元の場所に戻って釣りを再開する。その直後、父親の竿が大きく曲がった。
「お、これは。」 2~3分かけて、父親は40cm近いニジマスを釣り上げた。
母親は相変わらずボンヤリと水面を見ているが
男の子は父親の傍にしゃがんで魚を見ていた。でも、やはり『空っぽ』だ。
仕掛けを飲み込まれていたのか、父親が折りたたみナイフを取り出して先糸を切る。
続けてエラにナイフを入れてニジマスを〆た。かなり、釣りの心得があるらしい。
突然、辺りの空気が変わった。耳がキーンとして、周りの音が、消える。
男の子がナイフを持って立ち上がった。こちらへ向かって歩いてくる。
まるでスローモーションのようだ。父親は呆然と息子を見詰めていた。
男の子が右手に逆手で持ったナイフを母親の首筋に振り下ろそうとするのと
俺が左手を振り上げるのがほぼ同時だった。
男の子の手首を下から掴む。しかし、じりじりと押し込まれた。凄い力だ。信じられない。
痛。ナイフの先端が俺の裏小手に食い込んでいる。
ようやく父親が叫んだ。「亨、止めなさい!!」
母親がゆっくりと振り返る。
「亨、あなた、何故?」 あまりの光景に眼を見張り、我に返ったようだ。
姫が俺の左側にふわりと回り込む。ゆっくりと、風が吹くように。
小声で何事か呟きながら右手の人差し指と中指で男の子の首筋に触れた。
途端に男の子の手から力が抜け、ナイフが地面に落ちた。
ガックリと膝をついた男の子の体を姫が支える。男の子は意識を失っていた。
「亨、亨!」 母親が姫の腕から男の子を抱き起こした。
「今は眠っているだけです。取り敢えず他の怪我はありません。」
母親の背中に軽く触れながらそう言った後、姫は俺の左腕にタオルを巻き付けた。
タオルがゆっくりと血に染まる。「ごめんなさい。ナイフなんて...私の、せいです。」
姫が俯いて、地面にポタポタと涙が落ちる。
思わず姫の肩を抱いた。「大丈夫、大した怪我じゃありません。大丈夫ですから。」
母親が初めて俺を見た。「あなた、お怪我を。申し訳、ありません。」
「ご心配なく、僕の不注意です。でも、亨君がこんな風になったのは初めてじゃないですよね?」
両親は顔を見合わせて暫く黙った。
やがて、口を開いたのは父親だった。 「はい、その通りです。」
「旅館の若女将は僕たちの知人です。彼女の立ち会いの下で、
亨君についての話を聞かせて下さい。」
両親は黙って頷いた。
「無茶しましたね~。ナイフの刃が尺骨に食い込んで止まった場所が良かった。
少しずれてたら神経とか動脈とか、かなり危なかったと思いますよ。」
旅館の医務室で傷口を縫いながら、歳の割には軽薄そうな医者が言う。
それを聞いて、姫の眼からまたポロポロと涙が溢れた。俯いて俺の上着の裾を掴む。
全く、姫の前で要らん事を。大体な、縫う時は麻酔しろって。痛いだろ。
「そう思ったから裏小手で止めたんです。一応、拳法やってたんで。」
「ほ~、空手とか?もしかして黒帯ですか?」
だ・か・ら、無駄口叩かずにさっさと済ませろ。いつまで痩せ我慢すれば良いんだよ。
俺の傷の処置が終わり、男の子を医務室に寝かせたまま
俺と姫は旅館の研修室に向かった。そこでAさんと男の子の両親が待っている。
研修室のドアをノックする。Aさんが直ぐにドアを開けてくれた。
「どうぞ、こちらへ。」 Aさんに促されて両親の向かいに腰掛ける。
両親が立ち上がり、頭を下げた。「誠に申し訳ありませんでした。」
「先程も申し上げましたが、これは僕の不注意です。
でも今後のために、亨君のために、僕たちの質問に答えて下さい。」
「分かりました。何でも聞いて下さい。」
「まず、最初にお聞きします。」 姫の透き通った声が部屋の中に響く。
「『山○黛弓』という名前の女性に心当たりがありますね?」
「何故それを!」 母親が立ち上がって姫を見詰めた。
姫は静かに母親の眼を見詰め返した。
「『山○』はあなた方と同じ名字。彼女はあなたの、妹です。」
ぺた、と母親は力なく椅子に腰掛けた。
「信じるかどうかはあなた方にお任せしますが、
度重なる憑依の影響で亨君の心は壊れかけています。
心が完全に壊れてしまえば体も長くは保ちません。かなり、深刻な状況です。」
母親が息を呑み、父親は天井を見つめて呟いた。「そんな...」
「そんな状態なのに、亨君は私の名前を聞いてくれました。
亨君と私には、おそらく何かの縁があるんでしょう。だから私は亨君を助けたいんです。
もちろんあなた方が私の言う事を信じて任せてくれるなら、の話ですが。」
「色々な病院で何度も診察を受けましたが、亨があんな風になった原因は分からず、
状態は悪くなるばかりでした。今日の事からしても、このままの状態が続けば
近いうちに最悪の事態が起こる。それは私にも理解できます。
あなたの言うことは信じ難いですが、あなたの話の通りでなければ説明できない事を
これまで何度も見てきました。信じて、お任せします。亨を助けてやって下さい。
君も、それで良いね。」 父親の言葉に母親が頷いた。
「昼間、彼女が憑依したままの状態で亨君は眠っています。
だから彼女の体には意識がありません。体はおそらく安全な場所にあると思いますが
不慮の事故もあり得るのであまり時間の余裕が無いんです。」
姫は座り直して母親の顔を正面から見詰めた。
「亨君を助けるために、私が知りたいことは2つあります。
1つは何故彼女があれ程あなたを憎んでいるのか。そしてもう1つは
何故彼女があれ程深く亨君に憑依できるのか。答えて頂けますか?」
母親の顔は蒼白になり、唇が小さく震えている。
「Lさん、貴方、本当に亨を救ってくれますか?」
「もし、質問に答えて頂けるなら、全力を尽くします。」
「質問には、私が妻に代わって答えましょう。」
父親は1つ深呼吸をしたあと、ゆっくりと話し始めた。
「大学生の時、私は黛弓さんの家庭教師をしていました。妻とはその時に知り合ったんです。
彼女の私への想いには気付いていましたが、当然、受け入れることは出来ませんでした。
私たちが結婚した後も彼女の私への執着は強くなるばかりで、
私が彼女を拒絶するほど、彼女が妻を憎む気持ちは強くなりました。
妻が亨を妊娠した時は、暫く妻を友人の所に匿ってもらったくらいです。」
「それが、1つ目の質問の答えですね。2つ目は如何ですか?」
「亨が生まれた後、彼女は突然行方不明になりました。
全くの音信不通で、親族との相談では失踪宣告の話まで出ていました。
また、亨が幼稚園に入る前に私の仕事の都合でかなり遠くに引っ越しをしましたから
彼女との関係もそのまま切れるだろうと楽観していたんです。
でも、亨が小学校に入学して...」 父親が俯き、言葉が途切れる。
「あなた方の前に、彼女が再び現れた。」
姫の声はあくまで穏やかだ。しかし話が進むにつれ、寒気が酷くなり
手が震えるのを止められない。左腕の痛みなど、とうに感じなくなっている。
「はい、2年生の夏休み前、亨の三者面談で私たちが小学校に出掛けた時
黛弓さんが校門で私たちを待っていました。そして妻に言ったんです。
『亨君はもう私のもの。姉さんが私の大切な人を奪ったから、今度は私の番。』と。
彼女は偽名を使って小学校の非常勤講師になっていました。
そして、私たちの知らないうちに亨を、亨を...」
もう止めてくれ、無理だ。これ以上は。
「解りました。そこまでで結構です。」 姫が静かに告げた。
「それで、今後の対応ですが。」 「はい。」
「憑依の段階があまりに深過ぎるので、単純に憑依を解いて
今後の憑依を防ぐだけでは、近いうちに亨君の心が壊れてしまいます。」
「そんな、さっき貴方は。」 母親の顔が絶望に歪んだ。
「さっき言った通り、私は全力を尽くします。私が言いたいのは、
二人とも助けることはできない、と言う事です。
あれ程深く憑依してしまったら、どの道黛弓さん自身も亨君と共倒れになります。
だから亨君を助けるためには、彼女をあきらめてもらうしかありません。」
「幾ら何でも、そんな、惨い事を。」 Aさんが涙を拭った。
「惨い、それは承知しています。でも、これほど深刻な事例で気休めは言えません。」
「Lさん、亨は私の息子だし、黛弓は妹です。どちらか1人を捨てて
どちらか1人を選ぶなんて、それは私たちには、人間には出来ない選択です。」
「お父さんも同じ答えで宜しいですか?」
「はい。」
「分かりました。それではまず、彼女に答えを出してもらいましょう。
そして最終的な答えは、もちろん亨君が出す事になります。」
「黛弓と、亨が、答えを...」
両親が顔を見合わせるのに構わず、姫は続けた。
「Aさん。」 「はい。」
「6時から支度をします。それまでには亨君をご両親のお部屋へ運んで下さい。」
「分かりました。」
「それでは6時、お部屋に伺います。Rさん、部屋に戻りましょう。」
研修室を出た姫の顔に、微笑が浮かんでいるように見えた。
遅い昼食を終え、姫は濡れ縁に座って遠くの山々を眺めている。
一時間ほど経った時、姫が部屋の中に戻ってサッシと障子を閉めた。
「どうするか、決まったんですか?」
「はい、でも足りないものがあって。初めて使う術だから、少し不安なんです。」
「それはどうすれば手に入るんですか?僕に出来ることなら何でも言って下さい。」
「Sさんに、電話してみます。」
Sさんに電話? あ。
「そう言えば、預かったものがあります。『困った時に使って』と。」
俺はクローゼットの中のスポーツバッグから小さな白い袋を取り出した。
「これです。」 姫が袋の封を解き、中身を取り出した。
太陽のような、花のような形の紙片が一枚。
姫はそれを大切そうに両掌で包み、胸に押し当てた。
「私が考えていた術に、必要なものです。これがあれば、大丈夫。」
6時5分前、俺と姫はフロントでAさんと待ち合わせて両親の部屋へ向かった。
ノックをすると父親がドアを開けてくれて、俺たちは部屋の中に入った。
男の子は寝室の布団に寝かされている。
「では準備を始めます。ご両親とAさんは手前の和室で待機して下さい。」 「はい。」
姫は、まず和室に結界を張った。
「少しくらい声を出しても大丈夫ですが、ここからは出ないで下さい。
この中にいれば、彼女からはあなたたちが見えません。」
3人は揃って頷いた。神妙な表情だ。
「寝室には特別な結界を二重に張ります。」
俺は男の子が寝かされている敷き布団の4隅に、あるものを包んだ紙を挟んだ。一重。
それから姫は両足を引き摺るように、時々体を反転させながら
男の子が寝かされている布団の周りを、布団から1mほど離れて、一周した。二重。
「これで全ての準備が整いました。私が封を解くと亨君が眼を覚まします。
くれぐれも結界から出ないで下さい。」
姫が男の子の枕元、外側の結界の中に座った。俺も姫の隣に座る。
気のせいか、空気が重く、視界が少し霞んで見える。
深く息を吸い、姫が左手の甲を男の子の首筋に当てた。
男の子がゆっくりと眼を開ける。感情のない、冷たい眼。
「亨君、眼が覚めた?いいえ、今は『黛弓さん』と呼ぶべきですね。」
「あなた、昨夜の。」 昨夜、障子の向こうから聞こえた、女性の声だ。
「そう。あなたと同じように、私にも他人と少し違う力があります。
今日のお昼みたいな事があると哀しいので、体の動きは封じておきました。
不自由でしょうけど、話が済むまで我慢して下さいね。」
「何故こんな事を?」
「亨君を助けたいから、それだけです。もちろん、あなたの事情もあるでしょうし、
言いたいことがあるのならお聞きします。遠慮無くどうぞ。」
「あなたに、一体、何が分かるって言うのよ?」 女性の声は怒りに満ちていた。
「今朝、あなたの記憶の欠片を読ませてもらいました。
だから、亨君とあなたの関係は大体分かります。
あなた自身が忘れてしまっていること以外なら。いくつかお話ししましょうか?」
「...」
あなたと亨君の出会いはどうです?放課後の音楽室。」
「止めて!」
何処かおかしい。この女性は何故、何を隠そうとしているんだ?
「あなたはずっと前から、自分が『生き霊』を飛ばす事があるのを自覚していた。
だから亨君が生まれた時、身を引くと決めたんです。
愛する人に子供が生まれたなんて耐えられない。けれど、もしそれで『生き霊』が飛び
愛する人の子を殺してしまったら、もっとずっと辛い思いをすると分かっていたから。」
部屋の空気がますます重くなり、時間の流れが止まったように感じる。
「そして全てを忘れるために、遠い土地で新しい生活を始めた。小学校の非常勤講師。
でも、教え子の中に亨君がいた。亨くんの父親が転勤したために起きた、皮肉な偶然。」
「お願いだから、もう止めて。」
「始めはお互い何も知らなかった。教師と生徒。亨君はあなたを慕い、
あなたも真っ直ぐに自分を慕ってくれる亨君が愛しくて仕方がなかった。
だから、ある日、あなたは出来心で亨君の出自を調べた。
そして、亨君が愛する人の子だと知ってしまったんです。」
「...止めて。」 男の子の体から聞こえる女性の声は、弱々しく震えていた。
「復讐するつもりなんかなかった。だからもう亨君には会わない、そう決めた。
でも会いたかった、あなたに会いたいと願う亨君の心の声を無視する事も出来なかった。」
「そうよ!だから、知らないうちに私の半身が亨君に会いに行って、全部、話してしまった。」
「君の母親が私の恋人を奪った。君の父親は私を捨てた。
本当はそんなこと、亨君には話したくなかったのに。そうですね?」
「どうしようもなかった。それでも亨君は私に会いたいと望んでくれたの。
だから私は毎晩のように亨君と同じ夢を見て、夢の中で亨君に会った。
そして亨君は、いつでも私を受け入れられるように、心の扉を壊した。」
「夢の中で何度も心を重ねる内に、あなたは亨君が何故、これ程までに
自分を慕ってくれるのか、その理由に気が付いた。
『本当に亨君を必要としている人間は自分しかいない』のだと。
それに気付いたあなたは憎しみを抑えられなくなって、知らないうちに復讐を」
「仕方が無いじゃない!私の憎しみと亨君の哀しみが重なると抑えが効かなくなって...
本当は、ただ、同じ夢の中で一緒にいられるだけで幸せだったのに。」
姫は俯いて溜息をついた後、顔を上げて話を続けた。
「あなたの度重なる深い憑依、抑えられない両親への激しい憎しみ。
その結果、亨君の心は壊れかけていて、このままでは体も長くは保ちません。
黛弓さん、あなたそれで良いんですか?このまま亨君の命が尽きてしまっても?
もし復讐が叶っても、亨君を失うのでは意味が無いはずです。」
「あなたなら、亨君を助けられる、そう言いたいの?」
「助ける方法は考えましたが、確実に助けられるとは限りません。
亨君があなたを受け入れたまま死ぬと決めたなら、助けることは誰にも出来ませんから。」
「教えて頂戴。亨君を助けられる方法を。」
「今、ここで、あなたの体を、捨てて下さい。
あなたなら、私が言っていることの意味が分かるはずです。」
「...ずっと、このままで?」
「支えてあげて下さい。会えなくても、話せなくても、亨君には分かるはずです。
あなたが自分の中にいる。そしていつも自分を愛してくれている、と。
そしてあなたの憎しみと亨君の哀しみが消えれば、復讐は無意味になります。
ただし、そのあと、亨君がどういう答えを出すか、それは私にも分かりません。」
「Lさん、だったわね。」 「はい。」
「どうしてあなたが見ず知らずの私たちにここまでしてくれるのかわからない。
そんな事をしたら、あなたも無事ではいられないんじゃないの?」
え?姫が無事ではいられないって...
「私の力は、あなたより強いです。この力を、私が正しいと信じる事に使いたい。
そうでなければ、今、生かされている意味がありません。
心はぼろぼろで意識もほとんどないはずなのに、亨君は私の『名前』を尋ねてくれました。
その意味を、私なりに、とても真剣に考えたつもりです。」
「...ありがとう。あなたに会えて、本当に良かった。」
男の子の眼が、ゆっくりと閉じた。
姫はポケットの中から小さな白い袋を取り出した。封を解き、あの紙片を右掌に載せる。
姫が小声で何事か呟くと、紙片が淡い金色の光に包まれた。
「やっぱり、正しかった。 Rさん、亨君の胸を。」 「はい。」
俺は一礼してから布団を捲り、男の子の浴衣の胸をはだけた。
金色に光る紙片を、姫が男の子の胸に置く。
紙片は一瞬強い光を放った後で、男の子の胸に吸い込まれるように消えた。跡形もなく。
俺は男の子の浴衣を直し、元通りに布団をかけた。
気のせいか、男の子の寝顔は安らかで、微笑を浮かべているように見える。
姫は畳に手をつき、深く一礼してから立ち上がった。俺も姫に倣う。
二重の結界を解き、姫と俺は奥の間を出た。
「これで済みました。明日の朝まで寝かせてあげれば亨君の意識は戻ります。
暫くは少し記憶の混乱があるでしょうが、そのうち安定して問題はなくなるでしょう。
そのあと、どう生きていくかは亨君自身が決めることです。」
「私は、黛弓にも亨にも...」 母親の顔は真っ青で視線が定まらない。
「真実はひとつでも、人によってそれぞれとらえ方は違います。
誰の言葉が正しいかを決めるのは、私の役目ではありません。それよりも、
私は亨君に一番良いと思う方法を選んだつもりです。約束通り、全力を尽くしました。
何か問題があればAさんを通して連絡を下さい。それでは、失礼します。」
声もなく呆然と佇む両親を残して、Aさんと俺たちは部屋を出た。
「Lちゃん、あなた、大丈夫?」
Aさんもあの言葉を気にしているのだろう。
「Sさんが力を貸してくれたから、私は大丈夫です。でも、とっても、お腹が空きました。」
「直ぐに夕食を準備させるから、三人前でも四人前でも。
だからお風呂にでも入って少し待ってて。R君、くれぐれもLちゃんをお願いね。」
Aさんは俺の右手を両手でしっかりと握った。
「はい。任せて下さい。」
Aさんは俺たちの部屋の炬燵を大きなものに取り替えて、山のように料理を並べた。
俺たちが釣り上げた魚も見事な焼き魚になってお膳に並び、ぴん、と尾鰭を張っている。
本当に四人前くらいはあっただろう。姫は見ている俺たちが気持ち良くなるくらい
快調なペースで片っ端から料理を平らげていく。
「Lちゃんの食べっ振りを見てるとお腹が空くわね。今夜は私もここで食べて良い?」
「どうぞ、Aさんなら大歓迎です。」
食べるのに一生懸命の姫に代わって俺が答えると、
Aさんは電話で料理とお酒を追加して、気が付けば3人で大宴会状態。
Aさんと俺は姫に負けじと料理を食べ、お酒を飲む。
姫も俺の杯で一杯だけ、お酒を飲んだ。
料理を全部食べ終わってしばらくすると、姫は炬燵に突っ伏して眠ってしまった。
俺が姫を抱いて寝室に運ぶと、Aさんはすっかり安心したのか仲居さん達を呼び、
綺麗に後片づけを済ませて上機嫌で引き上げて行った。
俺はAさんが置いて行ってくれた徳利のお酒を飲みながら
ボンヤリと今日の出来事について考えていた。まるで夢の中の出来事だ。
でも俺の左手には包帯が巻かれ、鈍い痛みが残っている。
『誰の言葉が正しいかを決めるのは自分の役目ではない』と姫は言った。
でも姫は自分が正しいと思った事のためにあの術を使ったはずだ。
なら、姫は誰の言葉を正しいと信じたのだろう?
ゆっくり風呂に入って着替えたあと、左腕のガーゼと包帯を取り換えた。
傷口の縫い目は小さく、細かく揃っている。あの軽薄な医者、かなりの腕らしい。
寝室の障子を開けると黒い雲が月を隠し、生け垣の木の葉が時折激しく揺れた。
天気によっては明日の出発時間を早めた方が良いかもしれない。
姫にもう一枚、薄い布団を掛けてから部屋の灯りを消し、姫の隣で眠りについた。
結
「寝坊助さん、起きて下さい。」
誰かが俺の体に覆い被さっている。毛布越しに感じる体温、右の瞼と頬にキスの感触。
眼を開けると、姫が俺の顔を覗き込んでいた。湯上がりの湿った温もりと、石けんの残り香。
姫の腰に右腕を廻し、体を入れ替える。
「こんな起こし方して...その気になっちゃいましたから、もう逃げられませんよ?」
「夜明けまで、まだ時間があります。約束、守って下さいね。」
アラームが鳴った。7時だ、朝食を食べたら10時頃までには出発の準備。
でも、今はまだ姫を抱きしめたままでいたい、
このまま、初めて2人で体を重ねた余韻に浸っていたかった。
姫が眼を開けた。
「シャワーを使ってきます。直ぐに、戻って来ますから。」
『大丈夫』と姫は言ったが、やはり痛みはあったようだし、出血もあった。
体を洗いたいのも無理は、あ...
自分の顔から音を立てて血の気が引くのが分かる。何て事だ。
避妊を、していなかった。
忘れていた?そんなはずはない。俺はどうかしていたのか?
以前、Sさんに、あれ程強く注意されていたと言うのに。
俺の腕の中で、姫が小さく笑った。
「大丈夫ですよ。」 「え?」
「私、生理が始まってからずっと、毎日体温を計ってて。
それで、Sさんが旅行の間は避妊しなくても大丈夫って教えてくれたんです。」
思い出した。あの日、確かにSさんは言った。『旅行の時期は変えられない』と。
そして薬指を舐めて俺の額に...あの時、俺の意識から。
だから姫は、『約束して』、『この旅行の間に』と言ったのだ。
「相談、してたんですね?僕より先に。」
姫は優しく微笑んだ。「知りません、私。」 ふわり、と俺の腕をすり抜けて立ち上がる。
「シャワー、使って来ます。」
体の力が抜け、呆然と姫を見送る。やがて可笑しさがこみ上げてきた。
我慢できず、俺は声を上げて笑った。
見事に、完全に騙されていた。それが何故か、とても良い気分だった。
「質問があるんです。黛弓さんと亨君のことで。」
旅館を出て車を走らせてから1時間程が過ぎ、県境に向かう山道に差し掛かっていた。
「私に答えられることなら、何でも。」
「あの時、Lさんは両親の話と黛弓さんの話、どちらが正しいと決めることは出来ないと
そう言いましたよね?」 「はい。」
「でも、どちらかを正しいと信じたからこそ術を使った。Lさんは、どちらを信じたんですか?」
「あのお米から読み取った黛弓さんの記憶の断片と、両親の話には
大きな食い違いがありました。所々正反対と言っても良いくらいに。
でも、より、信用できると思ったのは黛弓さんの方です。」
「何故ですか?」
「体を捨てると決めた時、彼女の気持ちには一瞬の迷いも、一欠片の邪気もありませんでした。
だから彼女が亨君を思う気持ちは、純粋だったと思います。代の光の色、見えましたか?」
「はい、淡い、金色の光でした。」
「邪気のない母性は金色に、父性は銀色に見えます。黛弓さんは母親に近い気持ちで、
亨君を愛していたのだと思います。自分自身で産むことは出来なかったけれど、
彼女が体を捨ててくれたから、亨君の心は生まれ直すことが出来ました。
だからもう、黛弓さんは亨君のお母さん、亨君は黛弓さんの子供です。」
俺は慌てて脇道の入り口に車を停めた。不意に溢れてきた涙で運転どころではない。
「それから、亨君がナイフを持った時、見えてしまったんです。
壊れかけた心の中に残っていたわずかな記憶。その中で言い争う両親の姿が。
父親は『黛弓に嫉妬して俺を誘ったくせに』と、
そして母親は『最初から財産目当てで婿養子の座を狙ってたんでしょ』と。
亨君が黛弓さんを受け入れるために心の扉を壊したのは
2人のその言葉を聞いたからだと思います。自分は両親の愛の結晶ではない、
望まれて産まれてきたのではない。その事実は、亨君には辛過ぎたんです。
だから亨君には、もう、黛弓さんしかいなかった。」
「それなら、Lさんは、黛弓さんと亨君を一番理想的な形に結びつけてあげたんです。
あれ以上の結果は望みようがありません。あの術は完璧でした。」
「完璧ではないです。心は元に戻りますが、亨君はこれからもずっと
あの両親の元で暮らしていくんですから。あの時に言った通り、
亨君が生きていくことを選ばなければ、助けることは誰にもできません。」
「『亨君は自分の中に黛弓さんがいるのがわかる』そうですよね?」
「はい。直接に意志の疎通は出来ませんが、確かに感じるはずです。」
「なら、やはりあの術は完璧です。」
「何故、ですか?」
「亨君が死を選べば、自分の中の、愛する人を殺す事になる。
男なら、絶対にそんなことは出来ません。小さくても、亨君は男です。」
「それなら、良いんですけど。」
その時、姫の携帯が鳴った。姫が画面を見る。「旅館から、Aさんですね。」
「もしもし。はい、Lです。大丈夫です、今は走っていないので。はい。え?」
姫の顔色が変わった。黙ったまま、Aさんの話を聞いている。
「いいえ。こちらからは、はい、任せた方が良いと思います。
わざわざありがとうございました。いいえ、では、失礼します。」
「どうしたんですか?」
「旅館から少し離れた山の麓に公園が有って、そこの駐車場に停まっていた車の中から
若い女性の遺体が見つかったそうです。死因はおそらく凍死、と。」
凍死?昨夜の気温でどうして? 俺は、気が付いた。
「それ、もしかして、黛弓さんの。」
「Aさんが、そうだと思うって言ってましたから、多分間違いないです。
警察から問い合わせが有って、情報を提供した方が良いかどうか聞かれました。」
「提供しないで警察に任せた方が良いって答えたんですね。」
「はい。Aさんの勘は確かだと思いますが、多分黛弓さんは...」
「出来れば自分の身元を知られたくない?」
「はい。」
沈黙に耐えられなくなって、俺はもう1つの質問を口にした。
「それから、もう1つ質問があるんです。黛弓さんはLさんの事を心配してましたよね?
『こんな事したらあなたも無事では済まないんじゃないの?』って。あれは?」
「黛弓さんには力があるから、きっと、本能的に判ったんですね。」
「本当に無事では済まないんですか!?」
「人の命や魂を操作する術は、大抵『禁呪』ですから。外法すれすれの。
使えばそれなりのペナルティーが有るのは当然です。」
「ペナルティー、って。一体何ですか?」
「ええと、例えば、寿命が少し。」
「寿命が、縮まったんですか!?」
「少しだけです。」
「お願いですから、そういうことは、事前に話して下さい。」
「話したら、止められます。」
「そりゃ止めますよ!当たり前じゃないですか。」
「でも、術を使う人はみんな同じ。『やらなきゃいけないこと』の為だから。
Sさんだってそうですよ。」
「え?」 目の前が真っ暗になったような気がした。
命や魂の操作が禁呪だとしたら、もしかしてそれは?
「そう、翠ちゃんの誕生に関わる術なんて、禁呪中の禁呪です。ほとんど外法そのもの。」
頼むから、お願いですから、事前に相談して下さい。
「Sさんの寿命も、縮まったんですね?しかも結構大幅に?」
「でも、私も、Sさんも、早死にを望んでいる訳じゃありません。」
「だけど、寿命が。寿命が縮まったら。」
「妊娠して、翠ちゃんを産んだから、禁呪を使って縮まった分より
Sさんの寿命は延びたはずです。今回の私も同じですよ。」
「え?何が、同じなんですか?」
「Rさんが、約束を守ってくれたから、私の寿命も延びました。
だから、差し引きマイナスでもゼロでもなく、少しだけプラスです。」
「今夜も、したら、もっとLさんの寿命は延びますか?」
「いいえ、効果は初めての時の1回きりなので、次に延びるとしたら妊娠した時です。
だから、急がないで下さい。あの...少し、怖いですし。」
ようやく、お屋敷に辿り着いた。
翠を抱いたSさんが玄関先で迎えてくれる。
「おかえり。昼過ぎにAから電話があったわ。大変だったのね。」
「Sさん、私...」
突然、姫の頬を大粒の涙が伝った。
え?あの、姫?
姫はSさんに駆け寄り、Sさんの肩に顔を埋めて泣き出してしまった。
慌ててSさんから翠を受け取る。Sさんは優しく姫を抱きしめた。
「大丈夫、大丈夫よ。電話で聞いたLの対応は何も間違っていないから、ね。」
姫は何度も小さく頷いた。でもなかなか泣きやまない。
「...もしかして。」 Sさんが俺を見る。
射るような視線。体感温度が、多分10℃以上、一気に低下した。
「R君、あなた。Lは初めてなのに、いきなり色んな事。」
「違っ、違います!色々どころか、たった1回だけ。あ、痛たたたた」
涙目で振り返った姫に、左頬を思い切りつねられた。
姫はそのままお屋敷の中に駆け込み、俺は取り残された。
「馬鹿ね。パニクって不用意に口滑らせるの、良い加減に止めなさいよ。」
「だってSさんがあんな事聞くから」
Sさんは俺の唇に人差し指を当てた。
「まあ、素敵なお嫁さんが2人もいて、普段散々良い思いしてるんだから
たま~に、一寸くらい痛い思い、するのは、我慢して、貰わないと、ね。」
翠を抱く俺の左腕、包帯の上から、Sさんは俺の傷口をそっと押さえた。
「怪我、私、驚いて...Lも、可哀想に。」
そうか、姫は。姫とSさんの思いが胸に浸みる。
「大丈夫、腕の良い医者が綺麗に縫ってくれたし、大した傷じゃありません。
それより夕食の準備です。何か美味しいもの、頑張って作りますよ。」
小さく頷いて息を吐き、Sさんは涙を拭った。
『光と影』 完

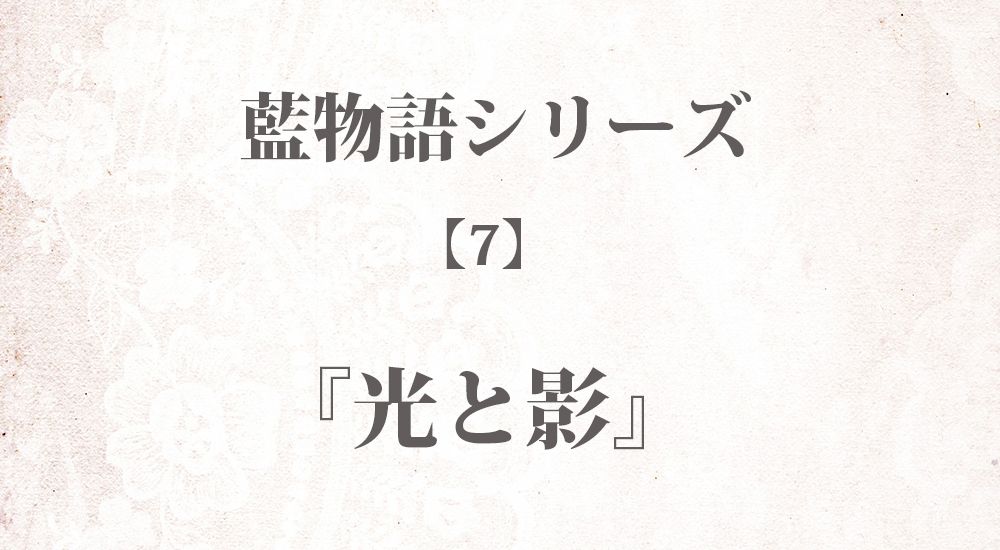

コメント