繰り返す幽霊
第一章
どうやら私は霊に目を付けられやすい体質のようで、しばしば霊的な体験をしてしまいます。
私のほうではなるべく係わり合いになりたくないと思っているのですが・・・
そして同じような体質の人どうしは引き合うみたいなのです。
近畿地方に引っ越してきてからの話なのですが、私が「超師匠」と呼ぶ人と知り合いになったのも、そのせいだと思うのです。
私は怪奇研究部に属していて、部ではミステリーサークルに関する研究や心霊現象の解明、911テロの真相といった論文を制作しては某雑誌に投稿するのを生業としていました。
論文はその雑誌の編集部では高い評価を受けていたのですが、その雑誌は残念ながら政府から非公式の圧力を受けて、廃刊させられてしまいました。
そうした話はおいおいしたいと思いますが、今回の話はそれとは関係ありません。
私達の部では新入部員を獲得するために、プレゼンテとして心霊スポットを探検したビデオを大スクリーンで流すことに決まりました。
そこで予算の都合から、一番身近にある学生寮の屋上を撮影することにしたのです。
そこでは5,6年前に女子学生が飛び降り自殺をして、それ以来目撃談の絶えない場所だったのです。
□ □ □
おっと、タイトルを入れるのを忘れていましたね
私と4人の部員はビデオカメラを持って、深夜の2時に学生寮の屋上に向かうことにしました。
学生寮の部屋は半分くらいが寝泊まりする学生で入室されており、しかも夜中に出かける学生も多かったので、ほとんどの部屋は空き部屋でしたが、私たちは声を出さないようにマスクをして、抜き足差し足で屋上へと向かいました。
臨場感を出すためにエレベータを使わずに、ビデオを回しながら階段を昇りました。
3階分の階段を昇って、廊下を少し渡ると、屋上へと続く別の階段があるのです。
昼間は賑やかですが、さすがに深夜2時ともなると、異様な静けさに包まれます。
夜は電気の節約のために、蛍光灯は廊下の半分だけが点灯していました。
暗いとはいえ、明かりがともっているのがせめてもの救いでした。
そんな状況でも私たちはなんとなく遠足気分で、ときどき忍び笑いを漏らすものさえいたくらいです。
それは部員達が心霊スポットを何度も探検してきた猛者だったからだといえます。
しかし一番後ろを歩く私には、ある気配が感じられて、気が気ではありませんでした。
誰かが私たちの後ろから、付いてくる気配です。
私にはわかっていたことですが、もちろんそれは人間の気配ではありませんでした・・
けれどもほかの部員達は気づいていないようだったので、ここで騒ぎ出してはパニックになるだろうと思った私は覚悟を決めて、口を閉ざしてみんなと行動を続けることにしました。
といっても特に悪い事態は起こらずに、私たちは屋上をひと通り撮影すると、階下に引き上げることにしました。
こうして約十分ほどの撮影が済みました。
それを翌日に部室のモニターで検証することにしたのです。
□ □ □
翌日私たちは部室に集まり、液晶モニターにライン接続をして再生してみることにしました。
映像が始まってすぐに、ヘッドフォンでモニターしている部員が、おかしいぞと言い出したのです。
彼は「人数がひとり多い」と言い出したのです。
彼が言うには、先頭の部員がビデオカメラを回しているのですが、階段の切り替わりや踊り場でいったん後ろの連中が追いつくのを待っています。
そしてみんなが揃うとほんのわずかの時間ですが、全員の足音が止まります。
それなのに「ひたひた」と後ろから追いつく足音が聞こえるというのです。
当然のように、それは誰かの足音が反射したエコーだろうという意見が出されたのでした。
そこで音響研究所の鈴木博士のごとく、その足音をパソコンのソフトで解析した結果、わずかであるが「ひたひた」という音が壁に反響しているということ、つまり問題の足音がエコーではなく、それ自体が音源であること、要するに誰かが私たちの後ろから付いてきているという結論が出されたのです。
女子部員のひとりが「うっそだー、だってオマーン一番後ろを歩いていたじゃん、誰かいたらわかるよねぇ」
と叫んだので、その場にいた全員の視線が私に集中しました。
私が「あの時は言えなかったけれど、ほんとに誰かが付いてきていたよ」というと、一瞬の沈黙のあと、「ぶわははは!」と全員が大爆笑しました。
「またまたオマーンたら、怖がらせようとしちゃって」「ほんとうだってば!」
しかしその笑い声もモニターしていた部員の次の声で凍り付いてしまいました。
「足音が、屋上の階段の手前で、俺達を、追い越している・・・」
もちろん誰一人として、自分たちを追い越した人影を目撃していないのです。
第二章
ヘッドフォンでモニターしていた部員の「足音が俺達を追い越した」という声を聞いて、
私たちは液晶モニターの前に集まり、画面を注視しました。
そこには当然のように、屋上へと続く階段が映し出されるだけで、人影は見えません。
さらに画面は進み、カメラはドアを抜けて屋上を映し出しました。
屋上には私たち以外に、誰もいません。
カメラはゆっくりと見回すように、屋上を撮影していきました。
そのときモニターに再生される映像を見て、私はおかしいと感じました。
普通なら屋上に出れば、遠くの街の明かりや隣の建物の明かりが映りこむはずなのに、それがまったく無いのです。
まるで屋上だけがスポットライトに映し出された舞台のように浮かび上がり、それ以外はまったくの闇なのです。
しかも、カメラが女子学生が飛び降りたとされる場所を映し出したとき、そこにぼんやりと縦長の楕円形の人魂らしきものが浮かんでいたのです。
しかし撮影者はそれに気づかなかったようで、カメラは屋上をひと通り撮影し終わると、階下へと引き上げていきました。
もちろんその場にいた私たちにも、何も見えていなかったのですが・・・
「何か映っていたよ」「見えた見えた」と私たちは興奮しましたが、一部の部員から懐中電灯の明かりがポールに反射したせいだと言われたので、ふたたび屋上に出るところから再生することにしました。
□ □ □
ふたたび再生しようとしたとき、ヘッドフォンでモニターしていた部員がおかしいと言い出しました。
音がまったく聴こえないというのです。
彼が指差す計器を見てみると、録音レベルがゼロになっています。
まったく音を拾っていない状態なのです。
「マイクの調子が悪いんじゃないの?」という声に対して、彼は「カメラが屋上から離れるとちゃんと録音されているのに、おかしいよ」と答えましたが、そのときは私たちはそれほど気にも留めませんでした。
「音はいいから、君も画面に注目して」という言葉を受けて、彼はヘッドフォンをはずしました。
私たちの間では、あの発光体が見えたのか見えないのかということを、まだ言い合いしていたのです。
ですから、ひとりでも大勢に画面を確認してもらう必要があったのでした。
ふたたび、屋上に出るところから、再生が始まりました。
カメラが女子学生の飛び降りたところに近づくと、明らかに白く光るものが映り込んでいたのです。
今度こそ、はっきりと、部室にいる全員の目でそれを確認することができたのです。
「いたいたいたYO-!」「本物だホンモノー!」
部室内はテンションのあがった部員達の、異様な熱気に包まれました。
みんなは顔を赤く上気させながら、いっそう画面を食い入るように覗き込みました。
その発光体は、屋上のふちに、まるで女性が座っている後ろ姿のように見えました。
そして、座っていた女性が、あたかも自分に向けられたカメラに気づいたかのように、こちらをゆっくりと振り返り、ゆらゆらと立ち上がり始めたのです。
さらにカメラの方へ、ずいっと足を踏み出しそうになったところで、画面が闇一色に切り替わりました。
「ずいぶんと、はっきりと、映って、いたね・・?」と、誰かが周りに確認を求めるかのように、言いました。
なぜならこの場面は、最初の再生では何も映っていなかったところだったはず、だからです。
私は、思わず「ありえない・・・」と、つぶやいてしまいました。
そういった瞬間、さっきまでの熱気とは正反対に、部室の中はまるで水を打ったように、シーンと静まり返ってしまいました。
全員の強張った顔を見て、私はみんなが心の中で同じことを考えていたということを悟りました。
私たちはもう一度再生してみたのです。
第三章
目の前で起こったありえない現象に、幽霊屋敷の探検ですらものともしない怪奇研究部の猛者たちも、さすがに顔色を失わざるを得ませんでした。
しかしビデオの再生が終わってモニターが待機状態になり、部室が元の雰囲気を取り戻すと、人間の心理というものは不思議なもので、みんなは今しがた目にしたものを信ずることができず、くちぐちにあれは何かの見間違いに決まっていると言い出したのです。
そしてもう一度ビデオを再生して、今度こそしかと見届けなければならないと言うのです。
私は嫌な予感がするのでやめたほうがよいと忠告したのですが、この怪奇研究部員らしからぬ弱気な発言は、当然のように一笑に付されました。
私には事態のなりゆきが気がかりでなりませんでした。
なぜなら、少し前から部室の外の音が、まったく聞こえてこなくなっているのです。
平日の午後の校内であれば、何らかの物音がしていて当然のはずなのに・・・
まるでこの部室の空間だけが切り離されているような、そんな感覚を感じました。
けれども他の人たちはまったくそのことに気づかないみたいで、ためらうこともなくビデオの再生を始めようとしています。
私は最悪の結果を覚悟しました。
皆がかたずを飲んで見守るなか、みたびビデオの再生が始まりました。
屋上のふちが映し出されると、そこにはやはり座った女の後ろ姿がありました。
うつむき加減のままで、髪の毛の一本一本までが鮮明に映し出されました。
まるでカメラに気がついたかのように、ゆっくりと振り返ると、立ち上がりだしました。
カメラの方に踏み出した足は両方とも、裸足でした。
すでに靴を脱ぎ捨てた後だったのです。
立ち上がった彼女は何かを求めるように、頭を左右に巡らしました。
そして彼女の目線とカメラの目線が、ついに一致してしまいました。
私が心の中で思わず「見つかってしまった!」と叫んでしまった、まさにその時です。
□ □ □
まるで獲物を求めるかのようにあたりを見回した女の視線と、カメラの目線がぴたと一致してしまい、私が心の中で「ああ、見つかってしまった!」と叫んだその時です。
なんと女がカメラのほうに向かって、だだだだっと恐ろしい勢いで走り出してきたのです!
依然として音は全く聞こえてきませんが、その走る勢いが画面を通して伝わってくるかのようでした。
カメラが右に振れると右に寄り、左に振れると左に寄って、撮影されていることをはっきりと意識しているように見えました。
いかにも何かにしがみつこうとするかのように両手を持ち上げて、凄まじい形相をさせて、そのままの姿で画面の奥から手前に向かって突進してくるのです。
これには画面に見入っていた全員がのけぞってしまい、部室内はパニックになってしまいました。
「ビデオを止めて止めて」という声を聞くまでもなく、操作係の部員が慌てて静止画ボタンを押しました。
その瞬間画面の中に流れる屋上の場面が、背景を含めてぴたりと静止しました。
しかし、信じられないことに、女の走ってくる姿は止まらないのです!
女は静止した風景を意に介した風もなく、そのままの勢いで突進してきました。
そしてついに画面に対して、ぶち当たったのです。
十七インチのモニターいっぱいに、明らかに生者のものとは思えない、血の気ひとつ無い青白い顔が、びたり、と張り付きました。
このとき、あまりにもあり得ない現象と遭遇すると、人間の思考力は停止してしまうのだということを、私は知りました。
ここにいる全員が、この信じがたい出来事を目の前にして、画面から目をそらすこともできず、口を半開きにしたまま、呆けたように固まってしまったのです、まるで金縛りにさせられたかのように・・・
画面に張り付いた女は、焦点の定まらない目、いわゆる「幽霊の目」で、みぎひだりとこちらの世界をうかがい始めました。
女がさらに身を乗り出そうとしたためか、その顔がじわりと大きくなりました。
私は動けなくなった身体をこわばらせ、心の中で「出てくる!取り憑かれる!」と悲鳴をあげながらも、覚悟を決めたのです。
その時、部室のドアが勢いよく、ガラララっと開き放たれました。
□ □ □
私たちはヘビに睨まれたカエルのように金縛り状態になり、身動きひとつできなくなってしまいました。
もうダメかと覚悟を決めたとき、ガラララっと部室のドアが勢いよく開け放たれたのです。
入り口に仁王立ちしている人物は怪奇研究部のOBであり、私たちが超師匠と呼ぶ、まさにその人でした。
超師匠はまるで今日のことを予測していたかのようであり、部室内の異常事態を目の当たりにしても顔色ひとつ変えるでもなく、無造作につかつかと入ってくると、「喝ーっ!」と気を放ちました。
ぴくんと身体を震わせた私たちは、そのとたんに金縛りから解放されて、全員が糸の切れた操り人形のように、へなへなと床にへたり込んだのです。
「ああぁ、超師匠、せんぱーい・・・」と皆が涙ぐんだ目で見上げると、超師匠はこう言ったのです。
「おだや、えどろうをね、すべらうさらさせや」
ちなみに超師匠は近畿出身で、生粋の近畿弁を使う人でした。
近畿弁というのはKinki-Kidsがバラエティのアドリブなどで使ったりする方言ですが、およそ日本語とは思えない奇っ怪な言葉です。
関東での暮らしが長かった私は、すぐには聞き取ることができず、適当に相槌を打つのがやっとでした。
超「いささやか、きるみんとこす、あんにもさでいたよおどがや、はがだりすねもち、つくねぎま、」
私「なるほどそうですか」
超「おまん、こうてもさおたも、はげりきぱてりき、さむあいそうでい、あまりもかめりも、さもや、はなちりめん」
私「はいはいはい」
超「おまん、どや、だがや、だーあ」
私「1,2,3、だぁーっ!」
日本語に翻訳を試みると、こうなります。
「嫌な予感がするから、来てみたら案の定だった。おまえたち、とんでもないものに関わってしまったようだな」
「これは後始末をするのも命懸けだが、とりあえず彼女の行きたいところに逝かせてやるしかあるまい」
そう言ったかと思うと、超師匠は再生機からビデオカセットを取り出し、脱兎のごとく部室から飛び出していきました。
「あ、どこへ行くんですか、せんぱーい!」と、私はあわてて超師匠の後を追ったのでした。
第四章
ここからは煩わしいので、ネイティブの近畿弁はあらかじめ日本語に翻訳しておきます。
カセットをつかみ出して部室を飛び出していった超師匠の後を、私は慌てて追いかけていきました。
外はさきほどの部室内で起こった異常事態からは想像できないほどの、穏やかな太陽の陽射しの降り注ぐ、落ち着いた午後の学園生活の日常がありました。
校舎の外に出てみると、学生寮に向かって駆けていく超師匠の姿が見えました。
私が「まってくださーい、せんぱーい」と声を掛けても聞こえないふうに、私たちが撮影をするために昇った階段のほうへと向かっていったのです。
キャンパスを三三五五に散策している学生たちの間をすり抜けるように駆け抜けていった超師匠は、しかし学生寮の階段の前に着くと、ぴたりと足を止めたのでした。
私が息を切らせながら「置いてけぼりにするなんて、ひどいじゃないですか」と咎めだてをすると、
超師匠は「ここからは命あっての物種だからな」と、いたずらっぽく脅すように言います。顔は笑っていますが、ビデオカセットを挟み込んだ両手の指は印を組みながら、両の腕には満身の力が込められているせいか、血管が浮き出ていました。
私は「これでも怪奇研究部員のはしくれ、すべてを見届ける義務があります」と答えはしましたが、超師匠の所作を見て、内心は冷や汗をどっとしたたらせていました。
そして、いままでの勢いはなかったかのように、今度は超師匠は階段を一段一段確かめるかのように、ゆっくりと上がっていくのでした。
□ □ □
階段を昇る超師匠の横についていきながら、私は心に湧いてきた疑問を口に出さずにはいられませんでした。
「屋上まで行くつもりなんですね?なぜ校舎からだと遠回りになるのに、この階段を使うんですか?」
「身投げした女子学生がこの階段を使ったから。だからこの階段でないとだめなんだ」
「なぜ?」
「繰り返しているから」
超師匠は黙祷をするかのように目を軽く閉じながら、続けました。
「彼女は何度も昇っては落ちるを繰り返している。その流れはもはや、彼女の意思とは無関係なのだ」
「結局、女子学生の霊がそのビデオに取り憑いている、というわけですか?」
「取り憑いている、というよりは、シンクロしてしまった、というほうが正確だろうな」
超師匠は閉じていた目を開けながら答えました。
「何度も繰り返しているうちに、彼女の怨念というか残留思念というものが、上書きされ増幅されていき、波動を内包したひとつのリングを構成するようになってしまった」
「けれども、残留思念なんてものは、徐々に弱まって消えうせてしまうものじゃないですか?」
私の問いに答えるために、思案をまとめるかのように、超師匠は少し考えながら返してきました。
「そう、それが当たり前なのだ。時の流れというものは残酷でもあるが救済でもある。
だがこのリングには何らかの原因によって歪み、というかねじれが生じてしまったのだ」
「メビウスの輪・・・ですか?」
「あるいは永遠に回り続けるウロボロスの蛇、ともいう」
そして超師匠はぐるりと頭を巡らせて、上下の階段を見回しながら、言いました。
「オマーンよ、俺達は彼女の怨念によって構成された巨大な蛇の腹の中にいるのだ」
そうこうしているうちに、私たちは屋上へと続くドアの前まで到着しました。
超師匠の返事を聞いても、私には次から次へと疑念が湧き上がりましたが、それを尋ねる前に、両手が塞がっている超師匠の変わりに、屋上のドアを開けようと前に出ました。
すると、屋上のドアがまるで私たちを誘うかのように、ひとりでにすうと開いたのです。
それは傍から見ると、階段を吹き抜けてきた風に押し開けられたかのように見えましたが、さきほどから私たちにまとわりつく不穏な雰囲気を、私たちは見逃すわけにはいきませんでした。
□ □ □
私たちが屋上へ出ようとすると、それを待ちかねていたかのように、ドアがすうと開いたのでした。
それはあたかも階段のほうから吹いた風が押し開けたようでしたが、それはしかし、ありえないことだということがすぐにわかりました。
開いたドアのほうから私たちのほうに、どっと風が吹き込んできたからです。
それは生暖かい、嫌な風でした。
不穏な空気を察した超師匠は私に、「心してかかれよ、オマーン」と声を掛けてくれたのですが、私はカラカラに乾いた口の中の、出ない唾を無理矢理に飲み込みながら、
「わかっています」と答えるのがやっとでした。
目に見えない何かに怯える私の心とは裏腹に、出入り口の手前から屋上を眺めてみると、穏やかな午後の日差しの降り注ぐ、至極当たり前な風景があるにすぎませんでした。
ところがいざ私が一歩屋上に踏み出そうとしたときです。
その平穏な光景が一瞬にして暗転したのです。
すべての背景が闇一色に塗りつぶされ、屋上のコンクリートだけが舞台のように、ぼうっと浮かび上がったのです。
そしてそれまで聞こえていた一切の音が、まったく聞こえなくなりました。
それこそはまさしくビデオを再生したときの光景と同じだったのです。
私はデジャヴを見せられたときのように、軽い眩暈をおぼえながら、立ちすくんでいました。
すると超師匠は、そんなことにはおかまいなしに、私を追い越してすたすたと屋上に向かって歩み出していくのです。
どんどん小さくなっていく超師匠の背中を見ているうちに、急に取り残される不安感が恐怖心に変わり始めたため、私は慌てて彼を追いかけていきました。
「せんぱーい、置いてかないで下さいよー」といいながら、駆け足で追いつこうとしました。
超師匠は私の掛け声にまるで反応しようともせずに、ずんずんと先に進んで行きます。
駆け足の私があと少しで超師匠に追いつきそうになった、まさにそのときです。
□ □ □
ひとり取り残された私は慌てて超師匠を追いかけました。
もう少しで追いつけると思って、さらに足の運びを速めたまさにそのときです。
「しゃがむんだ、オマーン!」という超師匠の声が、私の後ろから聞こえてきたのです。
私がその声にはっとして、しゃがみ込んだのと同時に、胸にばしーんと強い衝撃を受けました。
あばら骨がきしむ痛みに顔をしかめ、目をつぶってしまった私は、後ろからする超師匠の「怪我はないか、オマーン」との声におそるおそる目を開けてみました。
そこには先ほどの暗転した闇の背景は胡散霧消していて、当たり前のように午後の日差しが降り注いでいました。
そして私の眼前の遥か下には、アスファルトの車道と磁器タイルを敷き詰めた歩道が、小さくなって見えていました。
私が胸に受けた強い衝撃は、私が屋上の手すりに勢いよく激突したせいだったのです。
そして私の胸から上は手すりを乗り越えて宙に浮いていたのでした。
もしも超師匠の声に反応してしゃがまなかったなら、私はもんどり打って屋上から転落していたことでしょう。
そのことに気づいたとたん、私の全身から冷たい汗がどっと吹き出してきました。
後から聞いたことですが、どうやら私は超師匠の制止も聞かずにいきなり屋上に飛び出し、女子学生が飛び降りた場所に向かって、後先考えずに駆け出したようなのです。
私の後ろから近づいてきた超師匠が「彼女の呪縛がまだ効いているようだな、つらかったら階段のほうで休んでいてもいいんだぞ」と慰めの言葉を掛けてくれました。
それに対して私は気丈にも「いえ、もう大丈夫です」と答えましたが、さすがに唇のわななきを抑えることができませんでした。

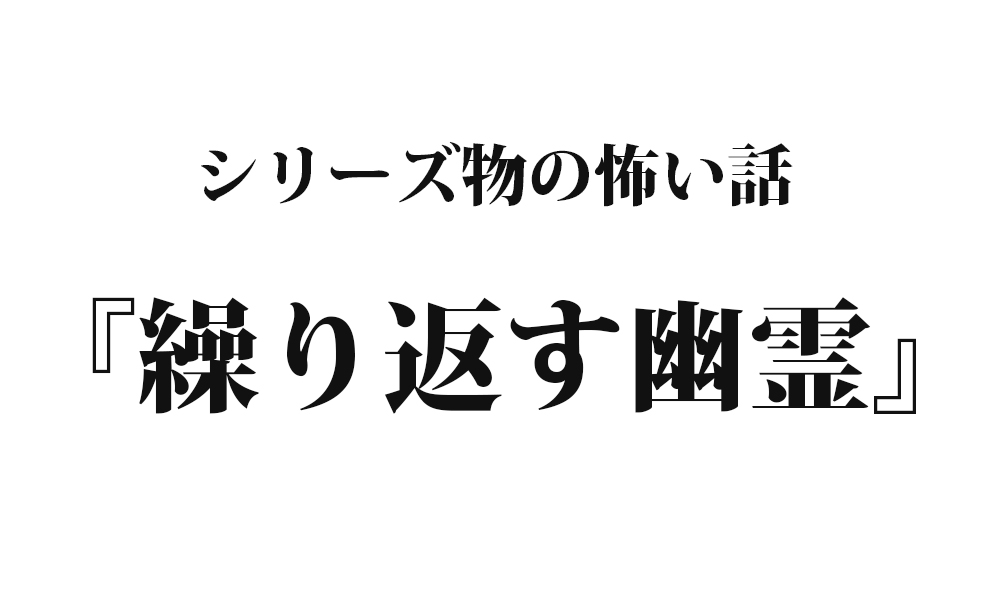

コメント