坂さん
存在しない本
僕の友人に、古美術商を営んでいる人がいる。坂の途中に店があるから、通称坂さん。
友人といっても歳は10歳以上離れているし、月に2、3回会うか会わないかといった程度だから、
僕は彼については、名前と職業とあるひとつの厄介な趣味以外は殆ど知らない。
それで彼の趣味というのが、まぁ予想はついていると思うがオカルトで、
そもそもそれが高じて古美術の名を借りた魔術道具まがいの店を始めたらしい。
おかげで彼の店はいつ行っても不気味な雰囲気が漂っていた。
自称武久夢二の絵なんかも飾ってあるのだけど、明らかに逆効果になってたし。
ある日、彼から電話がかかってきた。凄い物を仕入れたから見に来いと言うのだ。
丁度試験明けで暇だったので、僕は学校帰りに彼の店を訪ねることにした。
□ □ □
彼は年期の入ったレジスターに肘をつき、テレビでワイドショーを見ていた。
「坂さん、こんにちは」
声をかけると、日に当たらないせいで真っ白な顔がこっちを向いた。
「ああ、いらっしゃい」
客商売にまるきり向いていない無愛想な声で坂さんは答えた。
「そこら、適当に座り」
僕が店の空いているスペースに適当に座ると、坂さんはレジスターの下の金庫から一冊の本を取り出した。
古ぼけた洋書だった。日に焼け、虫食いやよく分からないシミがところどころについていた。
金文字のタイトルは読めなかった。
「なんすか、これ?」
「水神クタアト」
「……なんすか、それ」
坂さんの答えに、僕はもう一回同じ質問をした。
坂さんはつまらなそうに説明してくれた。
「ラヴクラフトが小説ん中で言及した魔導書……いや、ラムレイやったかなぁ。
とにかく、現実には存在せん本やね」
「は?じゃあこれは?」
「どっかのマニアが自分で作った同人誌みたいなもんやと思う」
ほら、と坂さんが見せてくれた本のページは真っ白だった。
□ □ □
「装丁作ったんはええけど、内容が分からんかったんやろね。全ページ白紙やったわ」
確かに、おしまいまでページをめくってみたが全く何も書かれていなかった。
一体これのどこが「凄い物」なのか。落胆する僕を見て、坂さんは笑った。
「以上が前の持ち主の説明。そんでこっからが、僕の説明。
なぁ、その本、やたら紙が分厚いと思わん?」
確かに、一ページ一ページがまるでボール紙のように奇妙に分厚かった。
坂さんは僕から本を取り返すと、初めの方の一ページを破った。
そして呆気に取られている僕を尻目に、イカの皮でも剥ぐみたいに、破ったページを剥いだ。
やったことある人なら分かると思うけど、段ボールとかお菓子の箱の紙とか、
薄い紙を何枚も重ねてあるような紙を一枚一枚剥く、あんな感じで。
ただ違ったのは、ページは元々大きな一枚の紙だったものを折って重ねた物だったということだ。
だから坂さんの行為は「剥ぐ」より「開く」の方が正しいのだろう。
開いた中――折り畳まれていた内側を、坂さんは僕に見せてくれた。
□ □ □
くすんだ赤色で書かれた筆記体の文章と、訳の分からない図。
読み取れるものは何一つ無い筈なのに、目にした瞬間に強烈な不快感が体を襲った。
これは見ちゃいけないものだ。本能が僕に訴えかけた。
必死で目を反らした僕を笑い、坂さんは紙をひらひらと動かした。
「反魂の秘術――らしい。ラテン語やからよう読めんかったけどね。
インクに血が混ざっとるみたいやし、少なくとも書いた本人は本気やったんやろ」
君の反応からしたら本物っぽいわ、と嬉しげな坂さんの声を聞きながら、僕はただただ早く帰りたかった。
さて、これだけでも僕にとっては気持ち悪い話なのだけど、実は後日談がある。
□ □ □
本を見せてもらってから一週間ほど経ったある日の朝、また坂さんから電話がかかってきた。
すぐに来いと言われたので、学校をサボって僕は店に行った。
まず最初に感じた異変は臭いだった。坂さんの店に近付くに連れて、魚が腐ったような強烈な臭いがするのだ。
店はもっと酷かった。
引き戸のガラスが割られ、店内は滅茶苦茶に荒らされていた。
自称武久夢二の絵も破かれていたし、テレビは画面が割れてブラウン菅が見えていた。
おまけにバケツでもひっくり返したかのように、店中が濡れていた。
坂さんは相変わらずレジスターに肘をついて、動かないテレビを眺めていた。
僕に気付くと、坂さんはバケツと雑巾を引っ張り出してきて、僕は片付けを手伝わされた。
そのために呼ばれたらしかった。
「なにがあったんすか!?」
「泥棒」
落ち着き払った様子の坂さんに、僕はそれ以上何も聞かなかった。
何が盗まれたのか見当はついたし、誰が盗んだのかは、
床といわず壁といわずこびりついている魚の鱗を見れば、考える気も失せた。
代わりに、壁を雑巾で拭きながら、「意外と早くバレてもうたなぁ」と呟く坂さんとの付き合い方を、少し本気で考えた。
寝室
僕の友人に、古美術商をしている坂さんという人がいる。店が坂の途中にあるから「坂さん」。
30過ぎて枯葉のように生きている半引きこもりだ。
取り扱っているのは一応は美術品や骨董品の類となっているけど、
素人目に見ても価値なんてなさそうなガラクタで店が埋め尽されていて正直言って大分不気味だ。
品数だけはやたらと豊富なので、大繁盛とまではいかないまでも、
食べていくのに困らない程度には客がついている。
だけど、その品揃えの中にいくら探しても見つからない物がある。
美術品としてはポピュラーで、どこの店でも一つくらいはある物が無い。
金はないがコネはある坂さんなら、いくらでも仕入れてこれそうなのに、決してそうしない。
その事を疑問に思った僕に、坂さんはある物を見せてくれた。
□ □ □
坂さんはレジスターの下から15センチ四方の箱を取り出して、僕の前に置いた。
箱の表面にはエナメル細工で出来た小さな薔薇が沢山付いていて、宝石箱のようだった。
「……箱?」
「箱やないよ。寝室やね」
坂さんは人差し指で箱の側面を小さく2回叩いた。
「失礼します」
箱に向かってそう言ってから、静かに蓋を開けた。
箱の内側は赤い布が張られていた。見るからに柔らかそうなその布に包まれて、ソレはあった。
丸みを帯びた、長方形の白い物体。すべすべした表面を見るに、石膏で出来ているようだった。
左右の側面にそれぞれ一つ、底に二つ、上に一つ、嵌込み穴のようなものが開いている。
もっとよく見ようと覗き込んだ瞬間、強烈な吐き気を催した。
次いで首筋に激しい痛みが走り、僕は椅子から転げ落ちた。
痛みは右手、左手にも現れた。鋭い棒で何回も何回も刺されているようで、だけど勿論棒なんか見えない。
というか店の中には僕と坂さん以外には誰もいない。
そうしている内にも両足も痛みだし、立っていられなくなった。
痛みでのたうち回る僕を尻目に、坂さんは箱の中へ向けて小さく呟き、静かに蓋を閉めた。
□ □ □
痛みは急に消えた。床に転がったまま呆然とする僕に、坂さんはため息混じりに言った。
「君がじろじろ見るから、客やと思たみたいやね。ちゃんと言うといたから、もう大丈夫やよ」
「……なんなんすか、一体」
「彼女はウチが気に入ってるから、出ていきたないんやわ」
「彼女?」
坂さんは箱をしまい、僕を立たせてくれた。
「そう。嫉妬深くて執念深くて、おまけに自分にパーツが無いんを気にしてんねや。
新しいのん仕入れても直ぐに自分のもんにしてまうから、ウチじゃもう扱わんことにしとんねわや」
「それってつまり……」
僕は慌てて首に手をやった。ぬるぬるとした血の感触に背筋が凍った。
救急箱から傷薬を取り出し、坂さんは思い出したように言った。
「彼女が君のこと、気に入った言うてんねやけど」
勿論即座に断った。
ついてくる犬
僕がその犬に気付いたのは、店へと続く坂を登っている時だった。
僕の奇妙な友人――古美術店を営む坂さんの店は、その名の通り坂の途中にある。
傾斜が緩やかだとはいえ、距離は結構なものだ。
その長い道のりを、犬は最初から最後までずっとついて来た。
犬と僕の距離は大体3mほど。だけど爪がアスファルトに当たる音や荒い息遣い、
静かに僕の背後を狙う気配は、まるで犬がすぐ側にいるかのようにありありと分かった。
僕は特に急ぐこともなく――そもそも、今回はこれ自体が用事だ――だらだらと坂を登り続けた。
犬は大人しく後をついてきた。途中一度、犬が唸るように鳴いた。
瞬間、背筋が凍るほどの寒気を感じたが僕は振り向かなかった。
□ □ □
店内では、坂さんがにやにや笑いながらレジスターに肘をついて座っていた。
「何もなかったみたいやね?」
僕は適当な所に座りながら答えた。
「当たり前ですよ。アイツは悪いモンやないんですから」
「その根拠は?」
「僕が飼っとった犬なんですから」
坂さんは呆けた顔で僕を見た。
「……どういうこと?」
「一昨日死んだから、坂の上にあるペット霊園に引き取ってもろたんですよ」
坂さんは頷いた。
「確かに、アレが出だしたんは一昨日の夜からやけど……おかしいな、ここらへんにペット霊園なんてないはずやけど」
「はい?」
「大体、坂の上は異人館があるやろ」
そういえばそうだった。この街の坂は、多くが山の手の異人館街に通じている。
この坂だってそうだ。大事な観光地でもあるあそこに霊園なんて、あるはずもない。
「君、騙されたんやね」
坂さんは哀れむように言った。
それ以来、坂を登る度に犬は静かに僕の後ろをついてくる。
頭を撫でることは出来ないが、馬鹿な飼い主にはその資格がないのだろう。
この一件から、僕は坂さんを頻繁に訪ねるようになった。
僕を山に入れなかった理由
僕の友人に、古美術店を営む人がいる。店が坂の途中にあるから通称『坂さん』。
怪しげな道具で店を埋め尽くし、商売する気があるのかどうか甚だ疑問だが、本人は呑気に暮らしている。
瓢々としていてどこまでが本気なのか分からない、そのくせ基本的に無表情で無愛想、人をおちょくるときだけは心から楽しそうに笑う。
こうして書いてみると、本当に坂さんはどうしようもない人だ。一度万力かなにかで矯正した方が本人の為になるかもしれない。
信頼とは対極に位置する性格である坂さんを、しかし僕は信頼している。たとえその言葉や行動が軽薄なものであるとしても。
祖父が死んだのは、僕が中学一年の時だった。当時の僕は病気がちな上によく怪我をする子供で、病院が第二の家のようなものだった。
葬式の為に丹波の山奥にある祖父の家に行くのだって、渋る医者をなんとか説得し、ようやく許可を貰えたくらいだ。
祖父の家は、後に山を背負って建っていた。山の持ち主は祖父だったのだが、危険だからと僕だけは山には入れてもらえなかった。
「なんで僕だけ入ったらあかんの?」と聞く度に、祖父は心底済まなそうに「ごめんな」と呟いていた。
□ □ □
家に着くなり、僕は祖母に離れに呼ばれた。
「じいさんを送らなならん」
祖母は静かに言った。
「うん」
「今から山登って、そこにおる人と一緒にじいさん送ってこい」
それだけ言うと、祖母は僕を追い出した。
意味が分からなかったが、初めて山の中に入れるのが嬉しくて、僕は山道を駆け登った。
何人もが通ったのだろう、細かったが道はあったので、迷うことはなかった。
運動不足の病弱児の息が切れた頃、道は突然終わった。道の終わりには小さな祠が建っていた。
手入れをされた跡のない、今にも朽ち果てそうな祠。僕は不思議な気分でそれを眺めていた。
何故か、ずっと前からその祠を知っている気がしたのだ。初めて山に入ったのに。それにしても、なんてボロボロなんだろう。
「触ったらあかんよ」
不意に声をかけられ、僕は自分が無意識の内に祠に触れようとしていたことに気付いた。
声がした方を向くと、知らない男が立ったいた。無表情な白い顔が僕を見つめていた。
□ □ □
「勇馬くん、初めまして」
男は僕の名前を知っていた。驚く僕に男は笑い、手招きした。
「こっちおいで。一緒におじいちゃんを送ったろ」
そこでようやく、男が祖母の言っていた人物だと分かった。
男の足下には数枚の紙が落ちていた。僕はそれを踏まないように注意して、男の隣に立った。
その場所からは、祖父の家がよく見えた。離れて見る家は、まるで知らない生き物のように感じられた。
あの中には、祖父が横たえられているのだ。蛇に捕えられた蛙のように。
僕は急に怖くなり、思わず後退った。しかし男に肩を掴まれ、その場に留まった。
男は屈んで僕の顔を覗き込み、真剣な口調で言った。
「逃げたらあかん。逃げたら、君はずっと因果に囚われる」
「……因果?」
「そう。例えば僕が紙に火を付ける」
男は足下の紙を一枚取り上げると、懐からマッチを出して火を付けた。
「これが因。そして紙が燃える。これが果」
眼前に差し出されたチリチリと燃える紙を、僕は両手で受け取った。
「因より果が生まれる。そしてその果もまた次の果の為の因になる」
□ □ □
男は僕の頭に手を置き、何事かを呟き始めた。
小さな声で、日本語かも分からない言葉を呟く――いや、むしろそれは唱えるといった方がいいのかもしれない。
奇妙な静寂と緊張が周囲に満ちていた。鳥の声さえ聞こえなくなり、全身から力が抜けていく。
けれどそれは、決して不快なものではなかった。
いつしか紙は燃え尽きていた。
家から棺が出てきた。これから火葬場に行くのだ。
「一番最初の因は、君のおじいちゃんやね」
山を降りながら、男は淡々と語った。
「ある約束を、ある連中とした。それ自体はようあることや。
そやけど君のおじいちゃんは、君を勝手に因果に組み込んでもうた。だから、僕が頼まれた」
「どういうことですか?」
「因果を断ち切ることはできん。ただ、変えることはできる」
□ □ □
葬儀の列の最後尾に加わり、棺の後を追った。
「山ん中でやったことを言うてはるんですか?」
「いや、あれも一つの因や。そして今の君がその果。」
列はゆっくりと火葬場へ向かう。
「そして君は新たな因となり、新たな果を生む。それを繰り返して、少しずつ形を変えていくんや」
「なんかよう分からへんけど、要するに僕の運命を変えにきたいうことですか?」
僕の言葉に男は声を上げて笑った。何人かがこちらを振り向き、眉をひそめた。
僕は小さく頭を下げ、男を睨んだ。男は特に気にしていない。
「坂って、呼ばれてんねやわ」
「はい?」
「僕のことや。古美術商をやってんねんけど、店が坂の途中にあるからいつの間にかそう呼ばれるようになってもうてな。
後で場所教えたるから、今度遊びにきい。君とは長い付き合いになるやろから」
□ □ □
そして今に至る。
あの日以来、僕は特に病気も怪我もしなくなった。代わりに、奇妙な能力(と呼んでいいのかは分からないが)ついた。
第六感に近いそれは、坂さん曰く「悪意を感じとる」能力だそうだ。これも因であり果。
一度だけ、山の祠を見に行った。祠は見るも無惨に壊れていた。扉が砕け、野犬の牙の痕がいくつもついていた。
そして、山の更に奥に向かって伸びる大きな足跡が一つ、残されていた。
今にして思えば、あの祠に奉られていたモノが最初の因であり、祖父が僕を山に入れなかった理由なのだろう。
信頼とは対極に位置する性格の坂さんを、しかし僕は信頼している。
僕に「逃げたらあかん」といった時の目は、本気だった。本気で坂さんは僕の因果を変えようとしている。
おまけに坂さんからは、微塵の悪意も感じられないのだ。
そんな相手を信頼出来ないほど、僕は捻ていない。
坂さんの店に遊びに行く度に酷い目に合っている気もするが、それも因であり果なのだと自分を慰める日々である。
匂い
坂さんは動物が大好きだ。
犬でも猫でも鳥でも、おおよそ生きている物ならなんでも好きだ。
視界に入ると思わず追いかけてしまうほどで、一緒に歩いていて突然いなくなったかと思えば、
路地裏で野良猫に話しかけていた――なんてのはしょっちゅうある。
しかし動物の方は坂さんに決してなつかない。どんなに大人しい犬でも、人に慣れた猫でも、
坂さんを前にすると吠えて暴れて収拾がつかなくなる。
まるでこの世の終わりのような騒乱が起こるので、坂さんの店から
半径5km以内にあるペットショップには立ち入り禁止になっている。
僕が飼っていた犬も、普段は僕の躾のおかげで吠えない噛まない逃げない賢い犬だったのに、
坂さんの前では狂ったように――或いは何かに怯えるように、
力の限り吠え続け、しまいには噛みついてしまった。
幸い傷は浅かったから良かったものの、下手すると大惨事になっていた。
青い顔で救急箱を探す僕とは対照的に、坂さんは涼しい顔で
「君んちの犬、顎弱いなぁ。柔らかいもんばっかりやっとったらあかんで」
とケラケラ笑っていた。スケールの大きさで負けた感じがする。
□ □ □
「原因は匂いやね」
包帯を巻いていると、坂さんはぽつりと呟いた。
「……加齢臭っすか?」
冗談めかして言う僕に対し、坂さんは皮肉げな笑みを浮かべた。
「犬も猫も、人間とは比べ物にならんくらい鼻がええからなあ。
どんな薄い匂いでも気付いてまうんやろね」
試しに僕は、鼻を近付けて坂さんの匂いを嗅いでみた。
……なんてことはない。少し黴臭い、通い慣れた店の中と同じ匂いがしただけだ。
僕にとっては親しみがあって落ち着く匂いだけど、動物はこれが苦手なんだろうか?
納得出来ていない僕を見て、坂さんは手を振った。
「君は長いこと一緒におるから、麻痺してもうてるんやろね」
「けど、初めて会った時から匂いなんてしませんでしたけど」
「ん?……ああ、言い方が悪かったか」
坂さんはすっかり手当ての終わった手で僕の鼻を抓んだ。
「僕が言うとる匂いは、君が感じるところの――悪意やね」
□ □ □
途端に、鼻孔の奥に悪臭が沸いた。肉が腐ったような、胸が悪くなる匂い。
背筋が凍り、頭痛がして気が遠くなる匂い。
脳髄まで犯され、酸っぱい物が込み上げてくる。
僕は坂さんの手を振り払うと、トイレに駆け込み腹の中の物を全て吐いた。
体が震えて止まらない。苦しくて仕方がない。指先から熱が消えていく。
胃液まで吐いても、気分は全く良くならなかった。
便器にすがりつく僕の滲む視界の端に、坂さんの無表情な白い顔が映った。
「……なんなんすか、一体」
どうにか息を落ち着け、僕はどうにかそれだけを絞り出した。
坂さんは答えず、ただ曖昧に笑った。その笑みに、また匂いが沸く。
見慣れた顔の筈なのに、それが恐ろしい。
これは、本当に僕が知っている坂さんなのか?
それとも、僕の知らない一面が覗いたのか?
「悪意を感じるなんて、ただ無防備なだけやな」
哀れむような、悲しむような声がした。
僕は振り返ることも出来ずに、ちからなくトイレの床にへたりこむしかなかった。
□ □ □
僕が感じたのが本当に悪意なら、一体坂さんに何があったのだろう。
無差別に振り撒かれる悪意は、まるで全てを憎んでいるようだった。
坂さんは僕の友人で、古美術商をしている。店が坂の途中にあるから、通称坂さん。
外にあまり出ないせいで日に焼けていない白い顔で、今日もレジスターの前に座り、
壊れたテレビをぼんやりと眺めている。
僕は彼について、名前と歳と一つの厄介な趣味しか知らない。
それ以外を、知る勇気がない。
誰かのお手付き
僕の友人の坂さんは、古美術商をしている。
店が坂の途中にあるから通称坂さん。日々を自堕落に過ごす独身男だ。
坂さんの店には定休日はない。というか決まった営業時間がない。
店主の気まぐれで店を開け、飽きたら閉めるという、
現代日本では到底受け入れられない営業スタイルだ。
最も、最近は坂さんが暇そのものに飽きているので大抵は開いているが。
店主からしてそんなものだから、店内は無法地帯と化している。
来るものは拒まず、去るものは追わず。坂さんに気に入られたら中々逃げられないけど。
ただ、それでも決してしてはいけない事がある。マナーやなんかじゃなく、自衛のために。
その日、僕はテスト明けで久々に坂さんの店に遊びに来ていた。
一夜漬けの一週間を過ごして、睡眠不足はピークに達していた僕は、
坂さんが飲み物を買いに出た時につい眠りこんでしまった。
□ □ □
暗闇の中に僕は立っていた。
周りには誰もいないのに、沢山の視線を感じる。品定でもされているような不愉快な感覚。
背筋が寒くなり、嫌な汗が吹き出る。全てを見透かされているようで、胃袋が引っくり返りそうだった。
――逃げなきゃ。
そう思った瞬間、僕は目の前の暗黒に飛び込んでいた。
どこまで行っても黒い闇が広がっていた。背後に「見えない誰か」の気配を感じる。
息遣いさえ聞こえるような至近距離に奴はいる。
止まれない。止まったら終わりだと本能が叫んでいる。
けど、どこまで逃げればいい?
不意に足を掴まれて、僕は転ぶ。
感触さえない闇の中でひたすらに足掻くが、塗り潰すように黒がせりあがってくる。
無数の手の感触。無数の指の感触。叫ぶことさえ出来ない。
奴が耳元で囁く――
□ □ □
気が付けば、僕は店の床に転がっていた。背中が痛む。打ち付けてしまったらしい。
「大丈夫?」
心配そうに見下ろす坂さんの手には、一つの判子が握られていた。
「……大丈夫っす」
どうにか立ち上がり、坂さんと向き合うように座る。
ズボンをたくし上げてみると、足首からふくらはぎにかけて、無数の黒い手形が付いていた。
「良かったなぁ。もうちょっと遅かったら持ってかれてたで」
「お知り合いですか?」
皮肉を込めて言ったつもりだが、坂さんは悪びれる様子もない。
「うん。普段は大人しいんやけどね、気に入ったもんがあると持ってってまうんやわ」
なにを?とか、どこへ?とか聞きたかったけど、聞かなかった。
なんとなく分かるし、余計なストレスはいらないし。
「やけど妙にきっちりした奴でな。誰かのお手付きやったら手は出さへんねやわ。だから」
ほら、と坂さんは手にした判子を振ってみせた。僕は慌てて壁にかけられた鏡を覗いた。
そこには、額に大きく『売約済み』と赤い印が押された僕の顔があった。
兄からの依頼 前編
落ち着きのなさにかけては西日本でも5本の指に入る三十路、
僕の友人(兼保護者だと本人は言い張っている)坂さんは
時々有り得ない無茶をする。
そして僕はかなりの確率でそれに巻き込まれる。
その日、学校帰りの僕は坂さんに拉致同然に連れ出され、
行き先も知らないままフィアット(後部に嫌な感じの凹み有り)
の助手席に無理矢理押し込められた。
「なにするんですか!」
膝の上に鞄を放り出され抗議の声を上げる僕に、坂さんは瓢々と応えた。
「いやね、最近遊んでやれてへんからドライブにでも連れてったろ思うて」
「せめて事前に言ってください。そんで出来るなら休みの日にしてください」
「休みは寝てたいもん」
「黙れやおっさん。休み関係ないやろ、ニート同然のくせしよって」
悪態をつく僕に構わず、坂さんはやけに楽しそうにアクセルを踏み込んだ。
途端、フィアットはパーキングから非常識な速度で道路に飛び出した。
急激に後ろに引っ張られ、僕は間の抜けた悲鳴を上げた。
「坂さん運転出来るんですか!?」
「馬鹿にしたらあかんで、僕だって免許持ってんねから。
周りは止めるけど」
「降りる!」
「そっち車道やから降りたらひかれんで」
□ □ □
結局目的地に着いた頃には、日はすっかり落ちていた。
僕達は車から降りると、暗闇の中に建つソレを見上げた。
2階建てのアパート――もっとも壁は数箇所に大きな皹が入り、
窓は板が打ち付けられていたりガラスが割れていたり、
明らかに人の住んでいる気配はない。
見ていて気分の良くなるものではない。僕は坂さんに視線を移した。
僕の困惑に気付いたのか、坂さんは静かに語り出した。
「僕の親戚の知り合いの知り合いが持っとる物件なんやけど……
ご覧の通り、人は住んでへん」
「なんかあったんですか?」
嫌な予感をひしひしと感じながら僕は聞いた。坂さんは曖昧に笑う。
不安が増す。
試しに僕は鼻をつまんでみた。途端に鼻孔の奥に臭いが湧く。
獣と――鉄の臭い?
胸が締め付けられるような嫌悪感を感じて、慌てて手を離した。
「帰りましょうよ」
無駄だとは分かっていながら、僕は坂さんに言った。
坂さんは僕の背中を2、3度叩くと、アパートに向かって歩き出した。
妙に楽しそうに。
□ □ □
頭を振り、その後に続く。どうせ坂さんがいないと帰れないんだし、
あの人を一人にしたら何をしでかすか分からない。
何かしらの対策は立てているだろうし、本気でヤバくなったら逃げればいい。
僕はいくつも言い訳を考えながら、アパートに足を踏み入れた。
懐中電灯で足下を照らし、坂さんは舌打ちした。
「見てみ、これ」
中は大分荒らされていた。
煙草の吸い殻やカップ麺のゴミ、はては花火の燃えカスなんかが
玄関に散らばっている。
暇な奴が忍び込んだのだろうが、人の事は言えない。
鼻をつままなくても獣の臭いがぷんぷんする。
僕は知らずに坂さんの服の裾を握っていた。
木張りの廊下を進む。
部屋は3つ並んでいて、それぞれ扉に板が打ち付けられている。
表札は黒く塗り潰され、かつて住んでいたのがどんな人物なのか、
窺えるものは何もなかった。彼らがどんな思いで部屋を後にしたのか。
考えることさえ出来ない。
「……全部閉まっとるみたいやな」
扉を順々に照らしていた坂さんは、
最後に廊下の突き当たりにある階段に光を向けた。
「……上るんですか?」
「当たり前やろ」
そっけなく答え、坂さんは僕の手を引いて階段へと進む――
□ □ □
その時だった。
2階から鈍い音が響く。
さすがに坂さんも足を止め、こちらを振り向いた。
「今のは」
「……知りませんよ」
震える足でやっと立っている僕に、坂さんは苦笑いした。
「ここで待っとくか?」
「そんな!」
「冗談や」
坂さんは僕に懐中電灯を持たせると、後ろに回って背中を押した。
僕はぎこちなく、軋む階段を上り出した。
1階と比べると、2階はまだ綺麗だった。
だがさっきの音のせいで、それがかえって不気味に感じられた。
僕は後ろの坂さんを何度も振り返りながら、一つ一つ扉を確認していく。
「……そういえば、なんでこんなことしてるんです?」
そもそもの基本にたちかえり、僕は坂さんに尋ねた。
坂さんはばつの悪そうな顔をした。
「兄貴に頼まれたんやわ」
「兄弟おったんですか?」
そんな話は初耳だった。
「仲は悪いけどな……宗次郎なんて名前は、次男にしか付けんやろが」
「そういやそうですね」
二つ目の扉にも板が打ち付けられていた。
そして僕らは最後の扉の前で立ちすくんだ。
□ □ □
板が打ち付けられていない。表札もかかっている。
ただ、扉は真っ黒に塗り尽されている。
明らかに他の部屋とは違う。さっきの音はここから聞こえたのだと、
理屈ではなく直感で理解した。
僕はゆっくりとドアノブに手をかけた。震えている。
坂さんを振り返る。
いつもの白い顔が、しかしいつもとは全く違った険しい表情が、そこにはあった。
僕は意を決してノブを回した。カチリ、と手応えを感じる。
そして、吐き気を催す獣と鉄の臭い立ち込める部屋を開いた。
兄からの依頼 後編
臭いが濃い。全身を染められるような気がして、思わずよろめいた僕を、
坂さんが支えてくれた。
黒かった。
ただ黒かった。
壁も天井も床も真っ黒に塗り潰されている。
あるはずの窓は見当たらず、懐中電灯の光さえ飲み込むんじゃないかと
錯覚してしまうような暗黒が、そこには広がっていた。
ただ一点、ちょうど部屋の中心に、白い物体が落ちていた。
懐中電灯の光を投げ込み照らしてみると、それがてるてる坊主だと分かった。
なんでこんな所にてるてる坊主が落ちているんだ?さっきの音はこれか?
それにしては音はもっと重そうだったが――
次々に湧き上がる疑問に混乱しはじめた僕は、坂さんを振り返った。
坂さんの顔は歪んでいた。
怒りとも困惑ともつかない表情に僕は不安になる。
「あの、坂さ」
「勇馬」
語尾を遮り、坂さんは僕を呼んだ。
その声は僅かだけど震えていて、僕の中の恐怖を大きくさせる。
「……なんですか」
「僕が合図したら、部屋ん中突っ込め」
「はぁ!?」
「ええから言う通りにしろ。嫌やったら突き飛ばしたるから」
「坂さんは!?」
「……僕は大丈夫や」
僕の肩を掴み、反論を許さぬ雰囲気に黙らせられる。
□ □ □
眼前には先の見えぬ暗黒が口を開けている。
僕は目を閉じた。その方が落ち着くと思ったからだ。
けど実際には、ただ臭いをより濃厚に感じさせるだけだった。
心音だけが聞こえる。
背中を押され、僕は足をもつれさせながらも駆け出した。
一歩進んだ瞬間から、肌にぬるりとした何かがまとわりつく。
油の中を泳いでいるような不快感に体が重くなる。
「止まんな!」
背後からの怒声に意識を足に集中させる。
頭が痛い。体が寒い。吐き気がする。汗が止まらない。
手足の感覚がなくなっていく。それでも僕は止まらない。
果てはどこだ?いつまで走ればいい?
たかだかアパートの一室を横断するだけなのに、
永遠に走り続けなければいけないような――
悲鳴が聞こえる。気にせず、なおも走る。
何かに足が引っかかる。ギリギリで体制を立て直し、なおも走る。
誰かに制服の裾を掴まれた。必死で振り払い、なおも走る。
込み上げる悲鳴を喉奥に飲み下し、僕は必死で走った。
ピリピリと皮膚が痛み、口の中に鉄の味が広がる。
鉄の味?だとすればあの臭いは、僕が鉄の臭いだと思ったものは。
踏み込んだ足はそのまま飲み込まれ、奇妙な浮遊感が生まれた。
そして僕は意識を失った。
□ □ □
眼前に広がる星空に、去年行ったキャンプを思い出した。
高校生にもなって馬鹿馬鹿しいなんて思っていたけど、結構楽しかった。
キャンプファイヤーで踊ったのはなんだったっけ?
マイムマイム?オクラホマミキサー?
ああそれにしてもなんでこんなに体が痛いんだろう。
僕、なにかしたっけ?
「生きてるか?」
視界に無表情な白い顔が入ってきた。誰だっけこの人?
「おい、なんか反応返せや。寂しいやろが。僕のこと分かるか?」
からかうような軽い口調に、僕は突然に覚醒する。
「坂さん!」
「はい正解」
坂さんは無表情のまま、僕の鼻をつまんだ。
鼻孔の奥に湧き起こる、獣の臭いと鉄の――血の臭い。
僕は跳ね起き、そして愕然とした。
そこには2階建てのアパートなんてなかった。
満天の星空の下、ただの原っぱに犬の死体が散乱していた。
あるものは頭を割られ。あるものは腹を裂かれ。
眼球に何本も釘が刺さっていたり。首と胴体が棒で繋がれていたり。
輪を描くように捨て置かれたいくつもの死体が、腐臭を撒き散らしていた。
その光景のあまりのおぞましさに、言葉を無くした。
□ □ □
「……兄貴は僕を憎んどる」
坂さんは原っぱの中心を睨みながら呟いた。
それは世界の裏側から聞こえる声のようだった。
「原因は僕にあるから、それはええ。
けど、君を巻き込むんはあかんなぁ」
まるで目の前にお兄さんがいるかのような口調を不思議に思い、
僕は坂さんの視線を追った。
死体の輪の中心に、てるてる坊主が落ちていた。
僕が部屋の中に見つけたのと同じ、不自然な程に白いてるてる坊主。
坂さんは暫くそれを睨んでいたが、やがて諦めたように空を仰いだ。
「君を巻き込むんはあかんなぁ」
思い出したような吐き気をどうにか処理し、僕らは車に乗り込んだ。
制服が血で汚れていたから、まずは坂さんの店で着替えてから、
家に送ってもらうことになった。
「上手い言い訳、考えとけよ」
坂さんの言葉に、僕は力なく頷いた。
□ □ □
一週間後、僕は坂さんに呼ばれて店に行った。
坂さんは相変わらずレジスターに肘をつき、壊れたテレビを眺めていた。
違いといったら、白い顔の左頬が赤く腫れていたことぐらいだ。
「あの後、どないやった?」
「めっちゃ叱られましたよ……その顔、どないしたんですか?」
「兄弟喧嘩してきたんやわ」
坂さんはひらひらと手を振った。手首には包帯が巻かれている。
坂さんはレジスターの下の金庫からなにやら取り出すと、
僕に向かって放り投げた。
受け取ったそれは、不自然な程に白く、
違和感を覚える程に重い、小さなてるてる坊主。
小さく悲鳴を上げた僕に、坂さんは薄く笑った。
「心配せんでええ。それはお守りや。
兄貴からぶんどってきた」
「……これのために、わざわざ喧嘩しにいったんですか?」
「僕は君の保護者やからね。おかげで大分男前になってもうたけど」
坂さんは大きく伸びをすると、「やっぱり兄貴は嫌いやわ」と呟いた。
坂さんは時々とんでもない無茶をする。
そして僕はそれに巻き込まれる。
けど今回は怒れない。
原因はどうあれ、坂さんは僕の為に怪我をしたんだ。
それを忘れない為に、僕はてるてる坊主を鞄に取り付けた。
誘導
坂さんに遊びに行こうと誘われたのは、五月の連休の初めだった。
特にこれといって予定のなかった僕は、二つ返事で了解した。
しかしよく考えてみれば、坂さんが事前に連絡してくるなんて珍しい。
嫌な予感を感じながらも、僕は待ち合わせ場所の喫茶店に出掛けた。
変なアロハシャツに色の濃い緑色のサングラス、不精髭まで生やした
オッサンが一番奥のテーブル席を一人で占有していた。
回りの客は明らかに胡散臭そうな視線で見ているのに、全く気にせずに
天井を睨んでいる。
一見しただけで堅気じゃない。
出来ることなら関わり合いたくない感じだが、関わらなきゃ後が面倒だ。
意を決して、僕は坂さんの前に座った。
坂さんはサングラスを外し、いつもの無表情で僕を見た。
「なんつう格好しとるんですか」
「君がオッサンオッサン言うから、せめて服だけでも若くしとこういう」
「Vシネのチンピラみたいっすよ」
僕の感想が気に入らないのか坂さんは小さく唸った。
□ □ □
僕らはハイキング・コースを歩いていた。
リュックサックを背負った家族連れが怪訝な顔をして追い越していく。
無理もない。変なオッサンと幸薄そうな少年が、ろくな装備もなしに山中にいるのだ。
途中、知らないおばちゃんに「まだ若いんやから変な気起こしたらあかん!」
と怒られて、ついでに蜜柑を貰った。色んな意味で酸っぱかった。
「山行くんなら、そう言うてくださいよ」
「言うたら、勇馬は来おへんもん」
坂さんはしれっと答えた。
確かに、幼稚園の時に遠足で山登りに行って死にかけて以来、
無意味な運動はしないようにしている。元来僕は病弱なのだ。
滝を超えた辺りで、坂さんは一旦立ち止まった。
「なぁ、僕が本当にただハイキングに来ただけやと思うか?」
「全然思いませんね」
何やら含みのある言い方に、僕は内心溜め息を吐いた。
「今日はな、宝捜しに来たんやわ」
「……埋蔵金でもあるんですか、六甲山に」
「金銀財宝だけが宝とちゃうんやね、これが」
言いながら坂さんは、どんどんコースを外れて整備のされていない方へと進んでいく。
この辺りは猪が出るし、今の時期なら蜂もいる。僕は慌てて坂さんを止めた。
□ □ □
「ちょっと、危ないですよ!」
「見てみ」
坂さんはすぐ側の木を指差した。
「枝が折れとる」
「それがどうしたんですか?」
「僕の肩くらいの位置や、猪やないな。
熊がおるとは聞かんし、やったらこれは?」
「……人間や、いうんですか?」
坂さんは頷くと、僕を前に行かせた。
「足下に気を付けて。臭いがしたらすぐ言うんやで」
「僕はレーダーちゃいますよ!?」
「後でアイス買ったるから我慢し」
どれくらい進んだだろうか。
自分のいる位置すら分からない。周りは草と木ばかりで、宝なんてありそうにない。
明らかに道に迷っている。僕は坂さんに確認を取った。
「遭難とか、してませんよね?」
「そうなんちゃう?」
思わず坂さんの頭をはたいた。
「人が真剣な話しとるときに!
何が嫌いって、僕はホタテとダジャレが一番嫌いなんや!」
「落ち着け、ツッコミはまた今度見たるから」
疲れと不安で苛立つ僕をなだめつつ、坂さんは携帯をいじりだした。
「……あかんな、僕のは圏外や。君のはどうや?」
言われて僕が携帯を取り出すのと、場違いな着信音が鳴り響いたのはほぼ同時だった。
□ □ □
僕はしばらく鳴り続ける携帯を眺めていた。
タイミングが嫌すぎる。出来すぎている。鼻をつまんでみた――臭いはしない。
「出えへんのか?」
坂さんに促されて、ようやく通話ボタンを押した。
ノイズしか聞こえない。耳が痛くなる雑音に、電話を切ろうとした時だった。
「…………右……」
ひどくくぐもった声だったが、確かにそう聞こえた。
その後にはまたノイズだけになり、やがて通話は切れた。
「どないやった?」
「……右やそうですよ」
僕が答えると、坂さんは笑った。
「向こうから呼んでくれるなんて有難いな」
それから何度か電話はかかってきた。
毎回聞き取り辛い声で僕らの行き先を指示する電話の通りに進んでいくと、
どうやら目的の宝を捜し当てたようだった。
□ □ □
男が首を吊っていた。
臭いがしないところをみると、まだ日は経っていないのだろう。
白く濁った目に見下ろされ、僕は思わずあとずさった。
坂さんは周辺を調べていたが、やがて戻ってきた。
「おい、あんまり見ん方がええぞ」
そして今更のように僕の視界を塞いだ。
けれど白い目は網膜にこびりついて中々消えそうになかった。
「失踪したから捜してくれ、言われたんやけど……こんなことなっとるとはな」
坂さんはどこか悲しそうな声で呟いた。
「……あれ?」
「どないしたんですか」
「いや、こいつ携帯――」
その時、僕の携帯が再び鳴った。
僕は坂さんの手をどけて、通話ボタンを押した。
またノイズ混じりの聞き取り辛い声がした。
「……土の下」
確かにそう聞こえた。
□ □ □
僕らは電車の中にいた。
周りの乗客は胡散臭そうに見ているが、いい加減慣れた。
結局山を降りてから、坂さんが公衆電話で連絡を入れた。
坂さんの携帯はまだ圏外だったし、僕のは電池が切れたからだ。
坂さんの依頼者に死体を見つけた事を。
そして警察に土の中に何かが埋まっているかもしれない事を。
信じてもらえないかもしれないが、その時は僕があの人を見つければいい。
土の下から僕を導いた電話の主を。
それは恐らく僕の責任だろうから。
黙り込んでいる僕の隣で、坂さんはぼんやりと外を見ていた。
「なあ」
「……なんですか」
あまり話したい気分じゃなかったが、一応僕は返事をした。
「アイス、食うか」
僕は坂さんの頭をはたいた。
「アホか!空気読めや!」
「なんや、元気やないか」
坂さんは安心したように少しだけ笑った。
「あんまり気にすんなよ」
「……なんで、坂さんやのうて僕やったんでしょう」
「そら、君やったらちゃんとしてるれる思たからやろ。
僕やったら無視してる」
坂さんはいつもの無表情に戻っていたが、声は少し柔らかかった。
「だから、気にすんな」
僕は少し考えてから、頷いた。
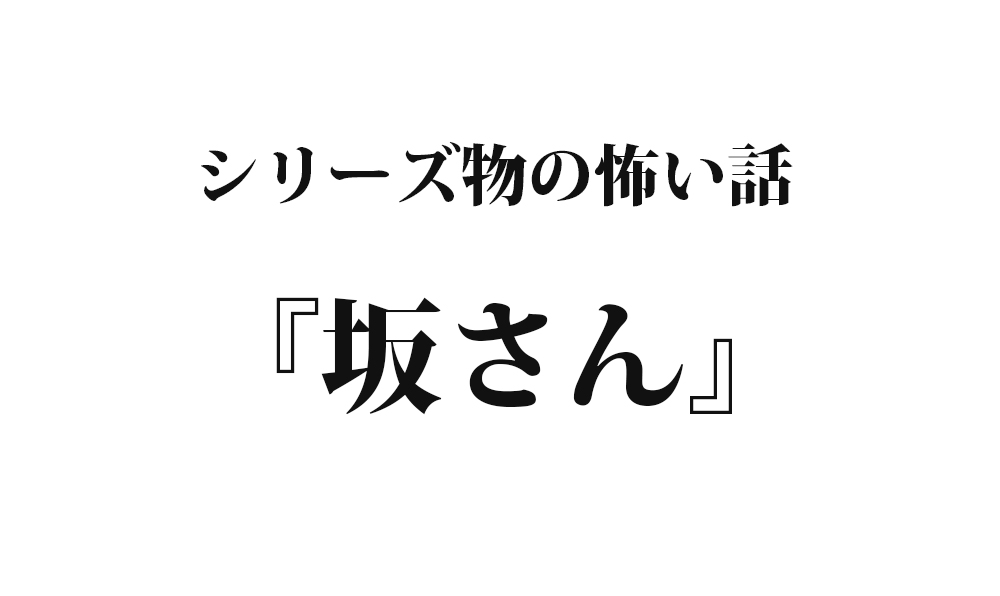
コメント