師匠シリーズとは
主人公の「ウニ」が大学時代に出会った先輩の「師匠」を中心に起こった奇妙な出来事を語るシリーズです。
魅力のある登場人物、読み応えのある話の内容などが読者に受け、洒落にならないほど怖い話を代表する人気シリーズになりました。
師匠シリーズの語り部であるウニ氏は、2003年頃から師匠シリーズを洒落コワに投稿し始め、実は師匠シリーズ以外にも洒落コワに怖い話を投稿しています。
ここでは、師匠シリーズ以外の、語り部(ウニ氏)の作品についてまとめました。
『喫茶店の話』
師匠の部屋のドアを開けるなり、俺は言った。
「い、いました。いました。いましたよ」
師匠は寝起きのような顔で床に広げた新聞を読んでいたが、めんどくさそうに視線を上げる。
「まあ落ち着け。なにがいたんだ。……その前にドア閉めて。さむい」
急いで来たので身体が温まっている今の俺には感じないが、今日はかなり冷え込んでいるらしい。
「いたんですよ」
靴を脱ぎ、ドアを閉めた俺は師匠の前に滑り込むように座った。
「なにが」
「愛想の悪いウエイトレスが」
「へえ、そう」
師匠はまた目を落とし、新聞紙を一枚めくる。
俺は目の前の人間がどうしてこんなに落ち着いていられるのか分からず、苛立ちが足から頭まで駆け回るのを抑えられなかった。
「へえ、そう、って、冷静な振りしても無駄ですよ」
後から考えるとかなり無茶なことを言っていたが、伝えたつもりの情報と相手に伝わった情報の格差のことを考えるゆとりがなかったのも事実だった。
「京介さんのバイト先、見つけたんですよ」
「なに?」
師匠が顔を突き出す。
そして「どこだ」と言いながら新聞を畳む。
「だから、喫茶店です。ウエイトレスを……」
説明も半ばで、師匠は凄い勢いで立ち上がり、その場でぐるぐる歩き回り始めた。
「喫茶店と言ったね。どこだ。入ったのか?」
俺はついさっきあったことを説明する。
美味いという評判のラーメン屋を探して街なかを歩いている時に、通り掛かった喫茶店の前で京介さんらしき人を見つけたのだ。
思わず身を隠してそちらを伺うと、店の入り口のそばに置いてある観葉植物に水を遣っているところだった。
それも、普段見たことのないスカート姿に、白い前掛けをしている。
フリーターをしている京介さんのバイト先は二つあるらしいのだが、どちらも教えてくれなかった。
知ったからといって別に嫌がらせをしに行くわけでもなし、なぜ教えてくれないのか分からなかったが、ずっと気になっていた。
その現場をついに押さえてしまったのだ。
俺はドキドキしながら電信柱の影から様子を見ていると、出入り口のドアが開き、中から客らしき中年の男性が出てきた。
男性は外でジョウロを持っている京介さんに片手を上げて声を掛けた。
京介さんはほんのわずか、そうと言われないと分からない程度に頭を下げてボソリと返事をする。
男性は苦笑するような表情を浮かべて去っていった。
やがて京介さんが店の中に消えると、俺はとんでもない秘密を見つけてしまったような気がして逸る気持ちを抑えきれずに師匠の家まで飛んで来たのだった。
そんなことを身振り手振りで説明すると、師匠は目を輝かせて言った。
「僕は子どものころから、こう言われて育ったんだ。『どんなことでも一生懸命やりなさい。人の嫌がるようなことを進んでやりなさい』ってね」
そこで言葉を切り、迷いのない爽やかな笑顔を浮かべる。
「行くぞ。嫌がらせをしに」
これか。
俺はその瞬間にすべてが分かってしまった。
師匠は急に跳ね上がった異様なテンションのまま部屋の中を這いずり始めた。
なにをしているのかと見ている俺の前で、座布団をめくったり部屋の隅の古新聞の束をどかしたりと忙しなく動いている。
そして台所に置いてあった紙で出来た家を取り上げて覗き込み、吐き捨てるようにこう言った。
「こんな時に限っていないなんて!」
俺はそれを聞いて尻の座りが悪くなった。
畳を叩いて悔しがっていた師匠だが、外から雨音が聞こえ始めたのきっかけに何ごとか悪巧みを練るような顔をしていたかと思うと押入れに首を突っ込んだ。
俺は窓辺に立ち、「ええー。傘持ってきてねぇよ」と呟く。
けれどせっかく水を遣ったのに京介さんも間が悪いな、と思うと少し微笑ましかった。
「どうだ、まだ降りそうか」
師匠が押入れからなにか、けったいなものを取り出してきてそう言う。
「さあ、たぶん」
ふん、と頷くとそれを身に着け始める。
藁で出来た、身体を覆う服。
蓑だ。
それに笠。
いつの時代の人かと思うような奇態な格好だ。
「いいかい、僕はその店に入るなりこれを脱ぐ。それでビショビショのこれを掛ける場所を店内に探す。そしたらやっこさんが『困りますお客様』ってやって来るから、おまえは『この店は雨具を掛ける場所もないのか』って怒鳴るんだ」
「嫌です」
「そうか。では一人で演ずるとしよう」
テキパキと蓑笠を身に着け終った師匠は、踊り出さんばかりの足取りでドアに向かう。
「あ、僕の傘、使っていいから」
俺は、この人を止めるべきか、一緒に楽しむべきか判断に迷いながら部屋を出た。
その店は繁華街から少し外れた場所にあった。
薄汚れた雑居ビルが立ち並ぶ一角で、雨の中にあるとその周囲はすべて灰色のモノトーンに包まれているようだった、
空は一層暗くなり、雨はまだ降り続きそうな気配だ。
俺を傘を持っていない方の手で、その三階建てのビルを指差す。
後ろに立っている人物が頷く。
蓑と笠の風変わりな出で立ちに、通り掛かった人が遠慮がちな視線を向けてくる。
どうぞ見てください。それではっきり言ってやって下さい。おかしいって。
雨脚が強くなった。
ズボンの足元が濡れて来て、嫌な感触が広がり始める。
なんでもいいから早く入ろうと足を速めた時、隣の師匠がハッとしたように動きを止めた。
喫茶店はもう目と鼻の先だ。どうしたんだろうと師匠を伺うと、その顔つきが変わっている。上ずったような熱気が、急に冷めたようだった。
「どうしたんです」
そう問い掛けるのもためらわれるような変化だった。
師匠は喫茶店の店構えを見つめ、それからビル全体を眺める。つられて俺も傘を上げた。
なんの変哲もない雑居ビルだ。
喫茶店は『ボストン』という名前らしく、入り口にそんな看板があった。
すりガラスが嵌っているドアからは中の様子が伺えない。小さな窓はあったが、内側に帆船の模型のようなものが飾ってあって、同じく中は見えない。
ビルの二階の窓には消費者金融の名前が出ている。そして三階にはなんとか調査事務所という控えめな看板が掛かっていた。
「ここなのか」
師匠は呟くように言った。ゆるやかな円錐形をした笠の縁から雨が流れ落ちていく。
その流れの向こうに深く沈んだような瞳があった。
俺は何も言えずに、二人並んで降りしきる雨の中にずっと佇んでいた。
まだ訊けない、重い過去への扉がその向こうにあるような気がした。
『ミケ』
飼ってる猫が人間には見えないものを見つめていたりして、オオッと思うことありませんか?
僕の小学校の頃飼ってた猫が特にそうで、よく何もない壁だとか天井だとかを睨みつけていました。
ミケという名前の三毛猫でしたが、もらい猫だったので避妊が遅れて獣医に連れて行った時にはもうお腹に赤ちゃんがいるということでした。
可哀相でしたが、まだ潰せるということなので御願いしました。
去勢されたあとのミケは空気が抜けたように元気がありませんでした。
ご飯に呼んでも上の空で、目もどこかうつろでした。
しばらくはしかたないと家族はさばさばしていましたが、僕は幼かったのでミケに感情移入し、彼女が心配でなりませんでした。
そしてよく気をつけて見ていたある夜、僕はコタツのしたにうずくまっていたミケが何かを賢明に舐めているのを見たのです。
僕もコタツに潜りこんでみるとそれは赤い肉の塊のように見えました。
しかし、ミケが唸って威嚇したので慌てて顔を引っ込めました。
そしてもう一度そっと覗いてみると、今度は自分の毛繕いをしており肉のような物も何も見当たりませんでした。
僕はその夜寝ながら思いました。
あれはきっと産まれてくるはずだったミケの赤ん坊なのだろう。
ミケはお母さんになりたかったんだなあ、と。
次の朝目が覚めると僕は一番にミケの所に行きました。
するとミケはまた赤い物を舐めています。
それはそれはいとおしそうに舐めているのです。
「ミケ。ミケ。ゴメンな。ゴメンな」
僕は涙がこぼれて止まりませんでした。
それはいつのまに食いちぎったのか、毛がすっかり抜け落ちたミケの尾先でした。
『雲』
不可解な記憶がある。
僕は小学生のころ団地に住んでいて、すぐ近くにあった田んぼが休耕している季節にはそこでよく遊んでいた。
乾いてひび割れた地面からは雑草が顔を出していて、カエルをを踏んづけてしまうこともあった。
独特の生臭いような空気を吸いながら駆けまわった。
僕の原風景だ。
仲良しだったケンちゃんと2人で、夕暮れのなか田んぼでボールを蹴りあっていた時だった。
ケンちゃんがボールを蹴り返してこない。
おーい、ケンちゃん。
と呼んでもぼーとして突っ立っている。
「あれ」
ケンちゃんが僕の後ろを指差した。
ふり返ると真っ赤な夕焼けの向こうに巨大なキノコ曇が立っていた。
山のはるか彼方。
けれど見上げるほど大きい。
僕は驚いてベソをかいた。
ケンちゃんが言う。
「原爆がどこかに落ちたんだよ」
僕は逃げるように家に帰り、布団に頭を突っ込んで泣いた。
いま思い出すたび不思議な気持ちになる。
あれはなんだったのだろう。
『影』
そろそろ怪談いくぜ!
霊体験(ぽいもの含め)はわりに多いのだが、なかでも俺はよく「影」を見る。
始めて認識した心霊体験は小学校3年のころにマンションの駐車場で友達と遊んでた時、夕暮れに解散になって一人で帰ろうとしたら影がついてきた。
走ってる俺の影に、つっ立っている他人の影がかぶさるようにずっとついてきていた。
これにはびびった。
まさに誰そ彼。
その後もたびたび影を見た。
ていうか小学4年に引っ越した家の周りは、夜振りかえったら自転車をこぐ影が見える坂とか、やたら影にまつわる怪異が多いところだった。
そんな話が多いのは、山なんで夜間に明かりが少ないせいもある。
単純な見間違いもあるはず。
しかし俺が体験した最恐の影は見間違いのレベルじゃなかった。
高校3年の夏休みに深夜自転車で帰宅中、近道をしようと開通したばかりのトンネルを通った。
ベッドタウン密集地帯に向うクソ長いトンネルで、通行料とるせいかガラガラ。
ただでさえ一直線なのにライトもやたら明るくて遥か向こうまで見通せた。
入ってすぐに一台だけ乗用車とすれ違ったけど、そのあとは車の音さえしない。
深夜巨大なトンネルの中で音が無いというのははっきりいって怖いよ。
で、かなりハイペースで自転車を漕いでると急に耳鳴りがしはじめた。
静寂で耳がいたいとかいうけど、そんなんじゃない。
あきらかに俺的「出る」時の前兆。
今は勘弁してくれ~って感じだった。
俺はシャンプー中に後ろをふりかえりまくるタイプで、怖い怖いと思ってると見たくも無いはずの異変を探してしまう。
その時も「出るな出るな」と思いながらも前後左右チラチラと見てしまった。
チビッたよ。
その時左側の歩道を通ってたんだけど右側の壁に上半身だけの影が映ってて、すーって進行方向に移動していた。
そこからは全力で逃げまくり。
自分の影かも?とかいう曖昧なレベルじゃない。
めちゃめちゃ明るくて、向こうの壁の小さい案内看板も見える。
歩いてるみたいな人間の影。
でも人はいないし、向こうには歩道さえない。
必死でチャリこいだけどそのトンネルよりによって全長1700メートル。
進んでも進んでも、出口は遥か遠く。
見えてるに。
怪異にあっても逃げ場がないなんてのは始めてだった。
しかも癖でどうしても時々振りかえってしまう。
めっちゃついて来てるし。
生きた心地がしなかった。
途中峡谷があり、一旦空の下にでたが次のトンネルに入るとまた影があらわれた。
何回も魅入られたみたいに振り返ってると下ろしてた影の手が前に伸びてるのに気付いた。
死ぬ気でこいで結局何事もなく出られたが、出口にたどり着くまで自分以外の人や車と遭わなかった。
トンネルを出ると新興住宅地の中だったが、道路脇に地蔵やらちいさい稲荷やら変な注連縄はってある石やらブルータルなものがいっぱいあった。
そんなやばいところにトンネル掘るな!
『猫イイ!』
学生時代に大学のすぐ裏のアパートに住んでいたんだが夏のある夜のこと、暑苦しくて窓を全開にして漫画を読んでたらいきなりその窓から顔面ぐちゃぐちゃの人間が入ってきた。
スカートにノースリーブの服の普通の格好だったから一瞬人が入ってきたのかと思ったけどここは三階だし、なにより輪郭がぼやけてるというか大きくなったり小さくなったりしていた。
ぐわんぐわんと。
身長1メートルくらいから部屋の天井に頭がつくくらいまで。
なんか自分がどういう大きさかわかってないみたいな。
顔もぐちゃぐちゃ動いていたけど、これは傷口が動いてるみたいだった。
こっちにじわじわ向ってきてたけど俺は完全に金縛りみたいになって机の椅子から動けなかった。
そしたらいきなり部屋で飼ってた猫が「フギャアアアア」って叫んで毛を逆立てて威嚇しはじめた。
それで我に返って椅子からずり落ちるみたいに降りてから壁際に寄った。
そいつはふらふらと台所のほうへ消えて行って玄関のドアからすぅっと出て行ったみたいだった。
マジで恐かった。
よくお化けは犬に弱いとか言うけど、猫でも役に立つんだ。
ていうか猫よりヘタレの俺って・・・・
その日の夜、大学構内で自動車部のDQNが酔っ払って暴走中に学部生をはねたらしい。
その女の子は即死。
それ聞いて「やっぱり」って思ったよ。
自動車部は当然ソッコー廃部。
その猫、妙に鋭いところがあって別の日の夜に宗教の勧誘っぽい女がチャイム鳴らして来た時にスゲー吼えだした。
玄関に来客があってものぞきに来ることなんてないのにその時は飛んでやって来た。
女は楽しいサークルがどうとか訳の分らんことを言ってたのでとにかく追い出した。
猫はそいつの後ろになにか見たんだろうか・・・
ちなみにその猫は今このPCの上で寝てる。
『犬』
あれは小学校六年のころ、夏のさかりだった。
僕は母方の田舎に一人で泊まりに来ていた。
田舎のせいか夜することがなくて、晩飯を食ったあとはとっとと寝るのがパターンになっていた。
特に寝苦しかったある熱帯夜に蚊帳の中でゴロゴロしているとふいに
ウウウウウウウウウ
と犬が唸るような声がどこからともなく聞こえてきた。
聞き耳を立てていると シッシッシッシという水を切るような足音が家の前を通り過ぎて行ったみたいだった。
僕は起きだして縁側に出てみると暫くしたら家のブッロク壁の向こうを犬の気配が戻ってきて、そしてまた通り過ぎて行った。
野犬かなあと思いながら佇んでいると祖母もやってきて
「犬じゃろうか。ちょいと見てくる」
と言って、玄関のほうへ行ってしまった。
僕は壁のすぐ向こうが幅広のドブだったことを思い出して、
「ドブんなかを走ってんのか~」
と納得したが、祖母は大丈夫だろうかと心配になった。
それから少しして祖母が帰ってきた。
「どうやった?」
と聞いたが何故か答えてくれなかった。
祖母は僕を座らせて改まってこう言った。
「あれはもののけじゃ。犬の幽霊じゃ。見てはならんぞ」
祖母はよく恐い話をしてくれたので、これも僕を怖がらせようとしているのだなと思い、
「どんな幽霊?」と聞くと
「四肢しかない。首も頭もない。それがドブを走っとる」
僕は想像してゾッとした。
「ええか。あれは昔から夏になると出るこどもをさらう山犬の霊じゃ。こどもを探して一晩中走りまわる。絶対に見てはならんぞ」
都会っこを自称する僕も、そうしたものがあってもおかしくない田舎独特の空気に気圧されてビビリあがってしまった。
僕は祖母の言うとおり大人しく布団に入った。
しかし布団を頭から被っても犬の唸り声がかすかに聞こえる。
何度目かに家の前を足音が通り過ぎた時、ふと思った。
頭もないのにどうやって犬がこどもをさらうのか?
一度気になると止らない。
僕はどうしても犬の幽霊を見たくなった。
そもそもリアルな足音を聞いているのに、それが幽霊だと言われてもだんだんうそ臭くなってくる。
祖母の怪談の神通力も子供の好奇心には勝てなかったらしい。
僕はこっそりと部屋を抜け出して玄関へむかった。
外に出て見ると、街灯の明かりがかすかに側溝を照らしていたが肝心の犬の幽霊は見あたらなかった。
僕はやぶ蚊と戦いながら家の前でじっと待っていた。
なにか餌でも投げたら飛んでやってこないかなあ、と考えていた時「それ」がやってきた。
フッフッフッフと荒い息遣いが左手のほうから聞こえてきて黒い影が見えた。
側溝は大人の背丈ほどもあったので、上にいるかぎり犬に飛び付かれることもないと高を括っていた僕は暗い中でよく見ようと見を乗り出した。
黄色い街灯に照らされて犬の頭が見えたとき、僕は
「やっぱりばあちゃんのホラじゃあ。ただの犬や」
と妙に勝ち誇った気分になった。
が、「それ」が目の前を通り過ぎた時心臓に冷たい物が走った。
犬はなにかを咥えていた。
僕には全く気付いていないのか、犬は血走った目で泥水を刎ねながら走り去って行った。
僕はその一瞬にわかった。
人間の赤ん坊がその顎に咥えられていた。
首がぶらぶらしていて、今にも千切れそうだった。
僕は腰を抜かしてその場にへたり込んだ。
1歩も動けなくなったが、「ばあちゃんはこれ見てほっといたんか」という考えがぐるぐる頭を回った。
大人に教えなあかん大人に教えなあかんと呟いてるつもりがカチカチ歯の根が合わなかった。
そうしているとまた犬の足音が近づいてきて、目を反らせないでいると今度は赤ん坊の首が根元からなくなっていた。
そして犬が走り去って行く時、ちょうど僕の目の前を赤ん坊の首が笑いながらすーっと追いかけて行った。
僕は這うようにして家に戻ると、祖母の布団に潜りこんで泣いた。
祖母は「あれはもののけじゃ。あれはもののけじゃ」と言いながら俺を叱るように抱きしめてくれた。
年寄りの怪談は素直に怖がるべきだということを思い知らされた。
『チョコ』
これも小学校の時の話。
小学校の下校途中で、仲間と騒ぎながら信号待ちをしていると、1人が側溝のコンクリートの蓋の間に覗く100円玉を見つけた。
蓋はとても持ち上がらなかったが意地でも取りたくなって、四車線隔てた向こう側の下水溝から侵入を試みた。
泥だらけになりながらさまよったが結局100円玉は見つからず、かわりに発見した汚らしい包みを拾って外に出た。
相当古そうなそれは、破いてみるとチョコレートだった。
ははあ、バレンタインのチョコが相手に捨てられたんだな、と一同察知してもう一度下水に流そうとすると、腐ったチョコの裏から手紙が出てきた。
ウワー カワイソウと思いながらも興味本意で読んでみると、心臓を掴まれたような寒気が襲ってきた。
「赤い目をした人へ 赤い手をした人へ」
おもわず下水溝の奥の方へ波きりの要領でチョコごとブン投げて全員逃げた。
後から考えてみると絶対変な文面とも言えない気がするが、その時はもうホントに怖くて気味が悪かった。
しばらくチョコ食えんかった・・・・
『怪談の部屋』
かなり昔の話ですが、記憶が確かな限り実話です。
小学校のころ、カブスカウト(ボーイスカウトのひとつ下)の合宿でお寺がやってる山の中の民宿(?)に夏休みに泊まりに行ったときのこと。
そのお寺には珍しい「笑い地蔵」というやつが沢山あって、その笑い顔だけで結構怖かったんだけど、そこの住職が夜に本堂で怪談をし始めてビビリの僕は思わず耳を塞いでいた。
怪談話がやっと終わって就寝の時間になった。
僕たちの班は四人部屋で、2段ベットが2つあるだけだった。
さて寝よう、という段になって部屋の前を別の班の奴らがヒソヒソ話をしながら通りすぎた。
「・・・この部屋よなあ・・」
とか言っていたので気になって問い詰めると、さっきの住職の怪談はこの部屋の窓の真下にある寺の蔵(だったと思う)にまつわる話だったそうで、この部屋にも夜中変なことが起こるとか言っていたそうである。
怖くなって具体的な話を聞かずに部屋に帰ったら、よりにもよって同じ部屋の3人も住職の話に耳を塞いでいたという。そうして怖がり男ばかりの部屋にも引率のリーダーがやってきて「消灯して寝ろ」というのである。
四人とも中途半端に知ってしまってかなり怯えていたが、同じベットで寝るというのも情けない話だったので仕方なくそれぞれのベットで眠りに入った。
僕は寝相が悪かったので下のベットを使っていたのだが、怖くて眠れたもんじゃなかった。しかし昼間さんざん遊びまわっていたので疲れがドッと出てきていつの間にか眠っていた。
で、夜中体に衝撃が走って目が覚めた。
ああ、ベットから落ちたんだと気付いてからのろのろとベットに這い上がろうと手探りしていたら、ない。
ベットがない。
視力が悪い上に暗やみだったので事態を把握するのに時間がかかった。
僕は部屋の両端にある2段ベットのちょうど真ん中、つまり部屋の真ん中の板張りの上にいたのだ。
なんでこんなところに?
あの衝撃は確かに落下した時の衝撃だったのに。
ぼおっとした頭のまま自分のベットにもどるとジワジワと怖さが湧きあがってきて、「おい」という声に心臓が縮み上がった。
「おい、K(僕の名)、起きとるんか・・」
隣のベットのSのぼそぼそとした小声だった。
内心どきどきしながらも「どうした」と2段ベットの上に小声で呼びかける。
「ちょう、来て。頼む」
Sが変に押し殺した声でベットの上からいっていたけれど、こちらは起きてる仲間がいたという安堵感も少しあり、「なんや」と隣のベットに上がっていった。
その立て梯子をのぼる途中でSが言ったのである。
「俺の頭の上のガラス(ガラス窓)、ずうっと叩きよるヤツがおる」
思わず足が止まった。
僕の顔がSのベットに半分ぐらい出たところだった。
Sは窓の反対側で頭からふとんをかぶって震えていた。
そして僕にも聞こえたのである。
コン、コンと。
そっちを向こうにも顔が金縛りのようになって向けなかった。
向いていれば何が見えたのだろうか。
ともかく僕はその時梯子をそのままの姿勢で飛び降りてしまい、うまく着地できずに体をしたたかに打った。
そして気を失った、らしい。
朝気がつくとリーダーとお寺の人が僕を介抱していた。
落ちたときの音では大人たちは気がつかなかったらしく、朝の見回りで床に倒れている僕を発見したらしい。
ちょうど部屋の真ん中だったそうだ。
幸い大した怪我もなく、すぐに普通に歩けるようになったがリーダーが凄い剣幕で住職に食って掛かっていた。
子どもはそういう話に影響を受けやすいから・・ウンたらカンたら。
昨日の怪談話がやりすぎだったと怒っているらしい。
子どもながらに責任転嫁だと思ったが住職は平謝りだった。
あとでSに夜の事を聞いてみたらSは青い顔をして覚えてないという。
食い下がったが結局Sがひどく怯えていることしか分からなかった。
あるいは僕が落ちたのにすぐ助けなかったから気まずいのかもしれないと思った。
かわりに同じ部屋のあとの二人から意外な話を聞いた。
ひとりは「夜中目が覚めて窓のそとに黄色い煙みたいなのを見た」といい、もうひとりは「夜中窓をドンドンと凄い音で叩く音を聞いた」という。
全員が何らかの異変にあっていたのだった。
この話をしていると大人たちが怒るのでほとんど話せずじまいだったが、ひとつ分かったことは昨晩の住職の怪談は「夜中この部屋の下の蔵から女のすすり泣きが聞こえる」という内容だったこと。
それとはあまり関係なかったがとにかく洒落にならない怖い記憶として僕の脳裏にこびりついている体験だった。
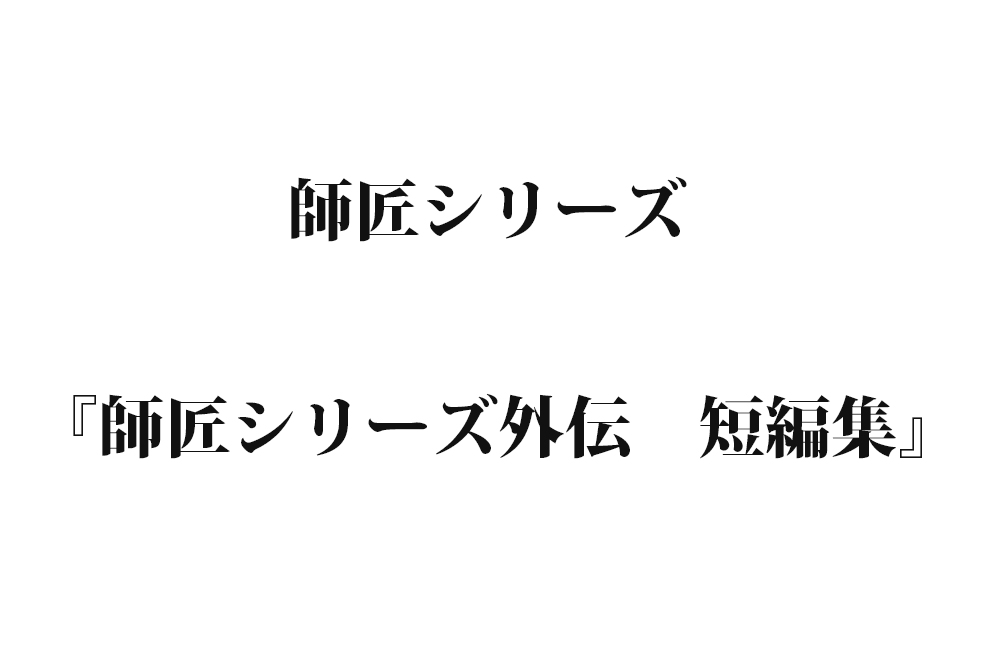
コメント