人が死なない泣ける話 – 感動エピソード【3】
一言だけ
巨人に移籍後、怪我に泣かされるシーズンが続いた清原。
肉体面のみならず精神面の甘えも叩き直したいとの思いで、
ある年のオフ、弟分の広島(当時)金本と共にとある郊外の
寺にこもった。
この寺の修行メニューに、ガンガンに焚かれた火に極限まで
近づいて念仏を唱えるという荒行があった。
屈強で鳴らす清原・金本でさえ、2、3メートル近づくだけで
その熱気にやられ、とても念仏どころではない。
「こんなん無理やで。できるわけないワ」
「なんもこんな思いしてまで修行せんでもええやん」
そんな気持ちにもなり、2人は何をするでもなく火を眺めていた。
ふと見ると、1人の少年が火に向かって歩いている。
驚いた2人はその様子を見守っていたが、少年はまったく
動じることなく、焚き火からわずか1メートルのところまで
近づき、直立不動で念仏を唱えだした。
「たいしたガキやな…」
清原はただ呆然とその姿を眺めるだけだった。
そのあと、清原は寺の住職に例の少年について尋ねた。
「ああ、あの子ですか。あの子は、何百万人に1人という難病に
冒されていて、余命半年もないと医者に言われたんです。
日本中の医者に診てもらったんですが、どの医者もさじを投げ
ました。しかし、彼は生きる希望を捨てなかった。母親とともに
この寺を訪れ、あらゆる可能性を求めて修行しているんです。
あの火の熱さなど、彼がこれまで耐えてきた苦しみに比べれば
生易しいものです」
それを聞いた清原は、次の日から少年の横で念仏を唱えていた。
少年とはほとんど口を聞くこともなかったが、少年の思いは
隣にいるだけで痛いくらいに伝わってきた。
そして開幕してまもなく、その少年は息を引き取った。
清原は葬儀には出られなかったが、その代わりに自分のバットを
彼の棺に入れてもらった。
彼の死に際し、清原は一言だけコメントを残した。
「あの少年には勇気をもらいました。ありがとう」
本心の「ありがとう」
パットともゴルフともまったく関係無い話なのですが・・…
昨日「新潟豪雨」の被災地にボランティアでお手伝いしてきました。
社長命令で社員全員(小さな会社ですが)が行きました。最初は嫌々でした。
ニュース映像を見ているだけでは実際の大変さはわかりませんね。
初老の女性が涙を流しながら僕らの泥だらけの手を握り締めて
「ありがとう、ありがとう」って。
本心からの「ありがとう」を久しぶりに聞いた気がしました。
明日は月例だったのですがたった今キャンセルしました。
これから再び被災地に行って来ます。連休はそこで過ごすつもりです。
着なくなったTシャツやポロシャツ持って。
被害の甚大な地域は洋服なんていくらあっても足りません。
偽善者と思われてしまうかもですが実際にアクションを起こせない方々でも
ハートの中にそんな火を灯せて頂きたいと痛烈に思い書き込みしました。
板違い甚だしくてごめんなさい。
オリンピック?
オーストラリアの乾いた大地を疾走するトラックの車内。
「ところで相棒、バックミラーにかかってるこの銀色のメダルは何なんだ?」
「いや、ちょっとしたお守りみたいなもんさ」
「おい、ちょっと待てよ。これ、本物の銀じゃねえか!」
「そんな目で見るなよ。昔、あるスポーツの大会でもらったのさ。そう、俺はオリンピックに出たんだ」
「オリンピック? 冗談よしてくれ。あれは選びぬかれたスポーツエリートだけが出られる大会だろうが。
お前みたいに一日中トラック転がしてる奴がどうやってオリンピックに出るんだ?」
「それもそうだよな、ハハハ。」
「わははは」
しかし、遠い地平線を見る運転手の青い瞳には、ある一日の光景が焼きついていた。
ありあまる資金で高級ホテルに泊り、薄ら笑いを浮かべながら会場に現れる東洋人の球団。
彼らのほとんどが一年で一万ドル以上を稼ぐプロの選手だという。
若いオージー達は燃えた。そして、全力で立ち向かい、ぎりぎりの勝利を掴みとったのだ。
たいていの人間が野球というものを知らないこの国では、誰も彼らを賞賛しなかった。
しかし、胸の奥で今も燃え続ける小さな誇りとともに。
今日も彼はハンドルを握り続ける。
折り詰めの寿司
酔っ払いの親父が持って帰った折り詰めの握り寿司
帰ってすぐに冷蔵庫に入れたんだろうな
翌朝ご飯も固くなりマグロがどす黒くなってワサビも利かない
太巻きやお稲荷さんも一緒に入っていたかな
そんな寿司をおいしいなぁってニコニコしながら食べた記憶がある
ばあちゃんの巾着
ばあちゃんのぼけは日に日に進行してゆき、次第に家族の顔もわからなくなった。
お袋のことは変わらず母ちゃんと呼んだが、それすらも自分の母親と思い込んでいるらしかった。
俺と親父は、ばあちゃんと顔を合わせるたびに違う名前で呼ばれた。
あるとき俺がお茶を運んでいくと、ばあちゃんは俺に
駐在さんご苦労様です、とお礼を言って話しはじめた。
「オラがちにも孫がいるんですけんど、病気したって見舞一つ来ねえですよ…
昔はばあちゃん、ばあちゃん、てよくなついてたのにねえ…」
そう言ってばあちゃんが枕の下から取り出した巾着袋には
お年玉袋の余りとハガキが一枚入っていて、よく見てみるとそれは
俺が幼稚園の年少のとき敬老の日にばあちゃんに出したもので、
「ばあちゃんいつまでもげんきでね」なんてヘタクソな字で書いてあったものだから、
俺はなんだか悔しくて悔しくて、部屋を出た後メチャクチャに泣いた。
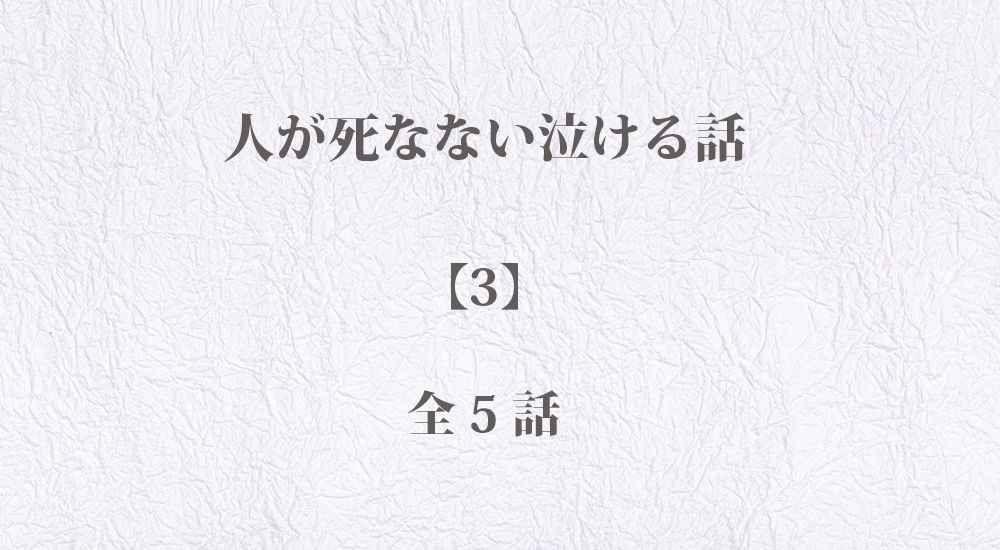
コメント