父親の泣ける話 – 感動エピソード【2】
箱根駅伝
小さい頃、よく親父に連れられて街中を走ったものだった。
生まれた町は田舎だったので、交通量が少なく、
そして自然が多く、晴れた日にはとても気持ちのいい空気が漂っていた。
親父は若い頃に箱根駅伝に出たらしい。
だから走る事が大好きで、息子にもその走る楽しさを教えてあげたかったのだろう。
もともと無口だった親父も、走ってる時だけはずっと俺に声をかけつづけていた。
普段の無口な親父がなんとなく怖かった俺は、その時だけは親父が好きだった。
そしてお袋が作ったタスキを使って、駅伝ごっこをしてりしてた。
今思えば、親父はまだ青春時代に生きていたのだろう。
中学に入った俺は、当然陸上部に入部した。
レースでは結構いい成績で、部活内でもトップレベルだった。
毎回応援に来てくれる親父は、俺がいい記録を出した日には必ず酒を飲んでいた。
そして真っ赤な顔して上機嫌で、俺に毎回同じ事を言うんだ。
「お前と一緒に、箱根走りたかったなぁ」って。
高校にいっても陸上は続けた。
でも思うように記録は良くならず、さらに勉強についていけないのもあってか
俺はいつもイライラするようになった。
勉強の事には口を出さないくせに、陸上のことばかり気にしてくる親父の事を、
鬱陶しく感じてしまうようになるのに時間はかからなかった。
親父が期待してるのは知ってたから、余計に顔を見たくない気持ちだったのだろう。
反抗期、というものだったのかもしれない。
そんなある日、その日のレースもいい記録は出なかった。
理由はわかっていた。
数日前に定期テストの追試のために、勉強を夜遅くまでしていたから体調を崩していたからだ。
一体自分は何をやっているのか、その時の俺は本当に悩んでいた。
そして家に帰って、部屋のベッドでひとり天井を眺めていると親父が入ってきた。
レースの事で何か言われるのかと、正直顔も見たくなかった。
親父は俺の横に座って、長い沈黙の後にこう言った。
「なぁ、お前何の為に走ってるんだ? そんな眉間にしわ寄せてさ。
父さんはな、お前が・・・」
親父がそこまで言いかけたところで俺の気持ちが爆発した。
「うるせえ!出て行けよ!!親父には俺の気持ちなんかわかんねえだろ!!
もう嫌なんだよ!親父の顔を気にしながら走るのは!
勉強だってしなきゃいけないんだ!親父の期待は俺にとって重いんだよ!!」
そう一気に言い切ってしまった俺を、親父は驚いた顔をして眺めていたが、
しばらくすると悲しそうな顔をしながら俺を思い切り殴った。
それからはむちゃくちゃだった。
お袋が止めに入るまで俺と親父は大喧嘩をした。
それ以来、親父と気まずくなってしまい、話す事もなくなり、
そしてすぐに俺は陸上部を退部し、走るのをやめた。
でも別に成績が良くなったわけでも、イライラが消えたわけでもなく、
毎日悶々としていた。
俺が部活をやめて2ヶ月くらいたった頃だ。
親父が急に倒れ、病院に運ばれた。
検査結果は末期の癌で、あと数ヶ月の命だろうということだった。
俺はショックを受けたが、まだ親父とのわだかまりがあり、
お袋に何度も誘われたが、見舞いにはなかなか行けずにいた。
家と仕事先と病院とを行き来するお袋を見て、苦労をかける親父に腹が立ちすらした。
そうしてる間に体力は徐々に落ちていって、
親父はいつ死んでもおかしくないほど弱ってきた。
そんなある朝、学校に行く前にお袋が思い出すように話し始めた。
俺が高校に入ってからも陸上を続けた事を親父はすごく喜んでいたらしい。
だから俺の記録がなかなか伸びなくて苦しんでる時、親父も同じように悩んでいたと。
そしていつか俺が走るの事を嫌いになってしまうんじゃないかって、
すごく心配してたらしい。
なのにあの日俺と喧嘩したあと、一切俺が走らなくなったのに、
なにも言わなくなったのだと。
「あの人も頑固だからねぇ」とお袋は付け足して朝食の片付けをし始めた。
俺はその話に何か引っかかるものを感じていた。
学校に行ってもずっと気になり、勉強どころではなかった。
そして休み時間、友達が「あの先生のせいで数学が嫌いになった」と言ったとき
俺は気付いてしまった。
そうだ、俺はあの日、親父に言ってしまった。
親父のせいで走るのが嫌いになったと、そう言ってしまったのだ。
誰よりも走るのが好きで、そして誰と走るよりも、俺と走る事が好きな親父に。
俺は授業そっちのけで病院に走った。
道路には雪がつもり、何度も転びそうになったけど、
もうしばらく走ってなくて心臓が破裂しそうなくらいバクバクいってたけど、
それでも俺は走った。
走ってる間、あの日俺を殴る前に見せた悲しそうな親父の顔が何度も頭に浮かんだ。
病室に行くと、変わり果てた親父がいた。
ガリガリに痩せて、身体からはいくつかチューブがでて、
大きく胸を動かしながら、苦しそうに息をしていた。
走ってぜぇぜぇいってる俺を見つけた親父は、
「走ってきたのか」
と消えるような声でいった。
うなずく俺に、親父が「そうか」と言いながらベッドから出した手には
ぼろくさい布が握られていて、それを俺の方に突き出し
俺の手にぼろくさい布を渡してきた。
それは小さい頃のあのタスキだった。
「なぁ、走るのは…楽しいだろ」親父は笑いながら言った。
その後すぐに親父の容態は急変して、そしてまもなく死んでしまった。
葬式なんかで慌しく物事に追われ、ようやく落ち着いて部屋に戻った時、
机の上に置きっぱなしにしていたタスキを見つけた。
親父の夢は俺と箱根を走る事だった。そして俺にタスキを渡す事だった。
もちろん一緒に箱根なんて走れない。それは親父が生きていても同じだ。
でも親父は確かに、俺にタスキを渡した。
なぜだか涙があふれて止まらなかった。
そうだ俺は確かに、タスキを受け取った。
冬が明けると俺はまた走り始めた。
小さい頃に親父と走ったあの道だ。
記憶にあるのと同じ木漏れ日、同じ草のにおい、同じ坂道。
ただ違うのは隣に親父がいない事。
今、俺は結婚して子どもが出来た。
いつかこの子に、このタスキを渡したいと思っている。
写真の裏側
俺が小さい頃に撮った家族写真が一枚ある。
見た目普通の写真なんだけど、
実はその時、父が難病(失念)を宣告されていて
もうそれほど持たないだろうと言われ、
入院前に今生最後の写真はせめて家族と・・・と撮った写真らしかった。
俺と妹はまだそれを理解できず、無邪気に笑って写っているんだが、
母と祖父、祖母は心なしか固いというか思い詰めた表情で写っている。
当の父はというと、
どっしりと腹をくくったと言う感じで、とても穏やかな表情だった。
現像してすぐ母がその写真を病床の父に持って行ったそうなんだが、
写真を見せられた父は、特に興味も示さない様子で
「その辺に置いといてくれ、気が向いたら見るから」と
ぶっきらぼうだったらしい。
母も、それが父にとって最後の写真と言う事で、
見たがらないものをあまり無理強いするのもよくないと思って、
そのままベッドのそばに適当にしまっておいた。
しばらくして父が逝き、
病院から荷物を引き揚げる時に改めて見つけたその写真は、
まるで大昔からあったようなボロボロさで、
家族が写っている部分には父の指紋がびっしり付いていた。
普段もとても物静かで、
宣告された時も見た目普段と変わらずに平常だった父だが、
人目のない時、病床でこの写真をどういう気持ちで見ていたんだろうか。
今、お盆になると、その写真を見ながら父の思い出話に華が咲く。
祖父、祖母、母、妹、俺・・・。
その写真の裏側には、
もう文字もあまり書けない状態で一生懸命書いたのだろう、
崩れた文字ながら、「本当にありがとう」とサインペンで書いてあった。
横になったビール
ビールは横に冷やすとうまい、と父は言っていた。
そんなわけはないと言っても聞かず、冷蔵庫に決まって
ビールを横にして冷やしていた。
酒以外煙草もギャンブルやらない親父にとって、
ビールに関してだけこだわりを持っていたのかもしれない。
酒が飲めなかった俺は、一緒に飲むこともなかった。
親父が死んだ時、なぜかそんなに悲しくなかった。
あっけないな、とは思ったが、何か時間が寸断されるような
感覚はなかった。
親戚が自宅にきて、これからのことを話し合っているときに、
ふと何か酒が飲みたくなり、冷蔵庫を開けた。
横になったビールがあった。時間がぎゅっと凝縮されて
思い出すべきことが多すぎて泣いた。
去年3月に定年を迎えた父に兄と私で携帯電話をプレゼント。
退職前は携帯などいらんと言っていたがうれしそうだった。
使い方に悪戦苦闘の父に一通り教えてまずメールを送ったが
返事はこなかった。
その6月に脳出血で孫の顔も見ずに突然の死。
40年働き続けてホッとしたのはたったの2ヶ月。
葬式後父の携帯に未送信のこのメールを発見した。
最初で最期の私宛のメール。
私は泣きながら送信ボタンを押した。
「お前からのメールがやっと見られた。
返事に何日もかかっている。
お父さんは4月からは毎日が日曜日だ。
孫が生まれたら毎日子守してやる。」
私の一生の保護メールです。
心をこめて作ってくれたお弁当
うちの両親は昔すごく仲が悪かった。
母はとても気が強くいつも一方的に怒鳴り散らして父は下を向いて黙ったまま。
そんな光景を何度も見ながら育った。私は父のことがとてもかわいそうに思えて父の味方だった。幼心に”パパとママが離婚したらパパといっしょにくらす!”ってずっと思っていた。
私が通っていた幼稚園ではお昼に給食が出ていたんだけど1ヶ月に一度お弁当を持っていく日があってその時は母がいつも腕を振るってかわいいお弁当を作ってくれていたのでとても楽しみにしていた。
しかしお弁当を持っていく前日、ケンカをした後、母が家を飛び出してしまった。
明日はお弁当なのにどうしよう。と思っていたがそのことを父に言い出せず、そのまま眠りについてしまった。
次の日、目を覚ましたが母はまだ帰っていなかったが父が台所に立っていた。私が起きてきたことに気付いた父が「パパがお弁当作ったから」と言って得意気に私にお弁当箱を見せた。
しかし、中身はパンのサンドイッチがひとつ入ってるだけ。それに妙に腹が立った私は「こんなのお弁当じゃない!ママが作ってくれるのと全然ちがうもんっ!!」って言って泣き出してしまった。
父は始めビックリした顔をしたがみるみる寂しそうな顔になり「ママみたいに上手に作れなくてごめんな」って言って涙をこぼした。
幼稚園に行ってお昼の時間になり、お弁当箱を開けるとパンにイギリスの国旗の旗が刺さっていた。
父なりに工夫をして見た目を良くしてくれたんだと思う。それを見た私は母がいない寂しさや、父が心をこめて作ってくれたお弁当のことなど色んなことが頭に浮かんできて泣きじゃくりながらサントイッチを食べた。
中身はマーガリンに砂糖がかかっている甘いものだったけど涙のしょっぱい味が今でもすごく印象的です。
サンタさんが間違って
クリスマスの朝、昨晩用意しておいた靴下を見てみるとけっこう膨らんでいる。
わくわくしながら探ってみると、1枚の紙切れが。
「あさごはんです」
それを見た後、靴下をひっくり返すとサランラップに包まれた3つのおにぎりが。
それを泣きながらを食べていると玄関から「○○(自分の名前)~!」という
両親の声。
行ってみると父がプレゼントを持っていて、こう言った。
「いやあ~、サンタさんが間違って玄関にプレゼントを置いてったらしいぞ。」
その後、プレゼントを渡され、嬉しくてまた泣いた。
今思えば父の肩には雪が乗っかってた。
おそらく、取り寄せてもらっていたプレゼントを急いで取りに行ってくれたのだと思う。
そんな父は単身赴任の身となり、クリスマスを一緒に過ごす事は滅多にない。
今となっては遅いけど、言わせてもらう。
「ありがとう」と。
そして、小五の妹の為に言わせてもらう。
「靴下に朝ごはんを入れないでください」と。
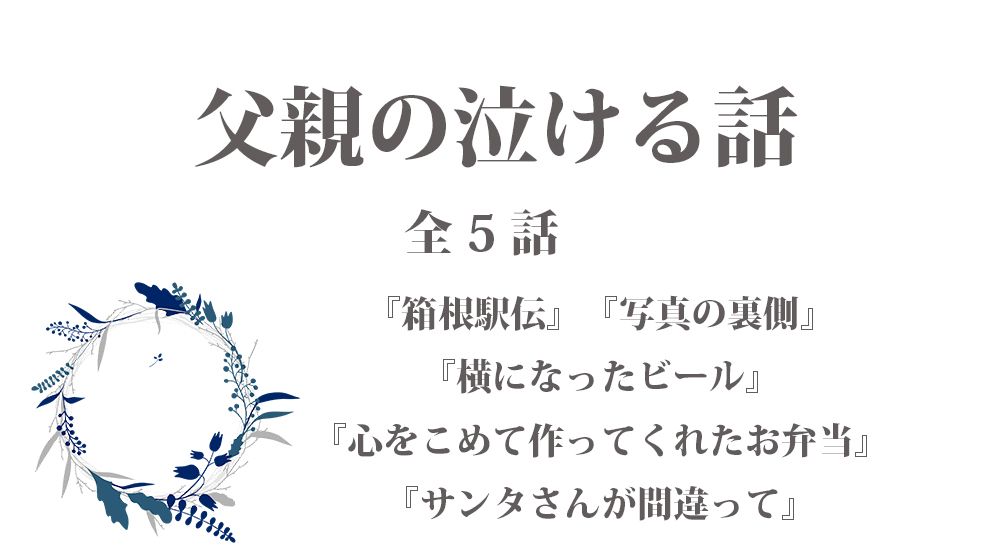
コメント