母親の泣ける話 – 感動エピソード【14】
取っておいてくれたファイル
私は昔から人とコミュニケーションをとるのが苦手で、うまく自分の事を伝えられないし、伝えようとすると妙にドキドキしちゃって自分の意見なんて言えなかった。
自分から輪に入る事もできなくて、みんなと一緒に遊びたくても「私もいれて」の一言が言えない。
うまくおしゃべりできないから、みんなからも楽しくない子!って思われて、学童期はいつも一人で過ごしてた。
いじめられてはないんだけど、学校からは早く帰りたかった。
早く家に帰って絵を書いたり、物語を作ったりしたかった。
普通の子は家に帰ると母親に
「今日、学校でこんな事があったよ」
とか
「○○ちゃんと遊んでね、楽しかったよ」
とか、そんな事話すと思うけど、私の場合、違ってた。
学校での話がない代わりに自分の書いた絵や物語をたくさん、お母さんに上げてた。
なんでだろう。
人とうまくコミュニケーションが取れない歯がゆさが作品を作るという作業にかりたててたのかな。
学校での話を全然しない私をきっと母は不思議に思っていたと思う。
でも、何も聞かなかった。
ただ、私が渡した絵や物語について
「上手に出来てるね。こんなにたくさん書けるなんてすごいじゃない?」
っていつも褒めてくれた。
そんな母の言葉が嬉しくて、気付けば、どんなに適当に書いた絵も内容がない物語でも何でもかんでも母にあげていた。
きっと自分が親の立場だったら、「この子、大丈夫かな?」って思ったりするけど、母はただただ嬉しそうにもらってくれた。
あれから数年、私はすっかり大人になって昔よりは普通に人とコミュニケーションがとれるようになった。
社会に出て働き、年頃になって好きな人もできて、結婚をするって時に、母からこんな手紙をもらった。
「もう結婚する歳になったんだね。本当におめでとう。お母さん、少し寂しいけど、手元にはあなたがくれた沢山の絵や物語があるから大丈夫。これからうんと幸せになってね」
って。
何と母は、私が幼き頃書いていた物を大切に大切に取っておいてくれたのです。
ファイル何冊にもなる量の私にとっては、ごみ同然のものなのに。
実家に帰れば、そのファイルを見る事もできるんだけど、未だ恥ずかしくて見ていません。
あの時のチャーハン
俺が小5の頃、母親が肺癌になった。
人間ドックに行った時に発覚した。
当時、中3の兄と高2の姉には肺癌だと父は伝えていた。
俺には、体調が悪いから少し入院すると父は伝えた。
俺は、母親がすぐ戻ってくると信じていた。
だが、癌の進行が酷く日に日に弱っていく母親が、体調が悪いだけではないと気づいた。
兄は受験もあったので塾に通い勉強に集中してもらった。
姉と俺と父の3人で家事を交代でおこなっていた。
母親が入院してしばらく経ち、姉がお見舞いに、兄が塾に行ってる間に俺と父で晩御飯を作ることになった。
俺はもちろん、父も料理なんてできない。
『とりあえずチャーハンでも作るか』
ということで父と不器用なりにチャーハンを作った。
姉から「電車が遅れてるから、先に晩御飯食べてろ」と電話が来たので先に食べることにした。
父と二人、手を合わせて、いただきますをした。
すると父が俺に
「母は肺癌で余命わずかなんだ」
と俺に言った。
俺は黙っていた。
父は続けて、
「母の前では泣くな。だから今泣け。」
と俺に言った。
俺は泣いた。
父と一緒に。
いつも強面の父が、初めて俺の前で泣いた。
二人で泣きながらチャーハンを食べた。
その時のチャーハンは苦くてしょっぱかったけど、美味しかった。
それから俺は今年20歳になった。
飲食店の、厨房で働いている。
毎日チャーハン作ってるけど、あの時のチャーハンより美味いもん作れるように頑張っている。
兄は弁護士を目指して勉強している。
姉は友達と起業して、なんとかやっているそうだ。
父はテレビ番組の真似事で、各停バスの旅を休日に「母」と楽しくやっている。
あの鍋焼きうどんを
19歳の秋に母は亡くなった。
物心ついた頃から父親は居なく、女手一つで育ててくれた母だった。
環境がそうだったのか、自分の道すら探してる時期は社会に反した生活をしていた。
ある日の昼、一週間くらい電源切ってる携帯に電源を入れた…
その瞬間、コールが鳴った。
画面を見ると、弟からの着信だった。
出るか迷ってたけど胸騒ぎに近いものを感じ、電話に出てしまった。
「お母ちゃん病院に運ばれた!すぐに病院に来い!」
俺は、この電話を受けても楽観的に感じていた…
母は糖尿病の合併症で、腎臓透析など病院に入院したりと運ばれる事が沢山あったからだ。
俺は入院なんだと勝手に思い込み、入院病棟に行き電話をした。
「何階に居るの?」
すると、怒鳴り声に聞こえるような焦ってる声で
「救命センターだ!今意識不明で、どうなるか分からないんだ!冗談言ってないで早く来いよ!」
俺は一瞬、頭が真っ白になりつつ、何とかなるだろとまだ楽観的に感じていた。
救命センターに着くと、治療室の前に慌ただしく駆けまわるナース達が居た。
それを見てると思い出す事があった。
ある日の夜中、家にそっと帰ると待ってましたの如くリビングで1人コーヒーを飲んでる母が居た。
母は俺に
「ご飯食べたの?」
俺は素っ気なく
「食ってない」
すると母は、鍋焼きうどんを作ってくれた。
テレビをつけて鍋焼きうどんを食べ、母と2人の空間が続き、いきなりボソッと言ってきた。
「もしもの事があったら、頼みたい事がある…」
俺は無視してた。
「もしも生死を選択する事があった場合、延命措置をしてほしくない!」
俺は腹が立った。。
「なんで俺に言うんだよ!もしもっていつだ!?」
こんな話を思い出してしまった…
すると、兄貴がおばあちゃんを連れて救命センターに着いた。
兄貴は慌ただしく、兄貴の嫁や叔父さんに電話していた。
おばあちゃんは何も喋らず、下を向き涙を浮かべていた。
するとドクターが扉を開き、ゆっくりと俺達に言う。
「出来る事は全てやり尽くしました…大変言いにくいのですが…これからは延命措置になります…」
おばあちゃんの目が開き
「どう言う事なんですか!?」
俺には分かっていた…
少しでも生き永らえさせるか、殺すか…
おばあちゃんはずっと質問してた
「助からないんですか!?どーしたら良いんですか!?」
俺達は沈黙していた…
おばあちゃんは
「可能性があるのなら延命を…」
と言う途中に俺が、口を挟んだ。
「延命措置は大丈夫です!」
弟が俺を殴った。兄貴は
「ふざけるな!」
と怒鳴った。おばあちゃんは泣き崩れた。
俺は大声で
「お母ちゃんが言ったんだ…。
延命措置してほしくないって…。
死ぬ間際に色んな所に管を繋がれて逝くのが嫌だって。
その時はしょうがないって。
ただ延命されて生きてるなら、楽に逝かせてって…。」
誰も何も言わなかった…
いや…言えなかった。
俺は続けて言った。
[延命措置は、大丈夫です!」俺が母を殺した日になった…
それから通夜の日に、家で仮眠をしていた。
夢なのか現実なのか
鮮明に覚えてるが、母が棺桶から出て来て俺に言うんだ。
「カバン!私のカバンは?」
俺はカバンを取って
「ここにあるよ!」
って言うと少し微笑んで、また棺桶に戻っていった。
俺は眠気からなのか、ボーッとしながらカバンの中身を出していた。
すると手帳を見つけて、何気なく開いた所に
『子供達へ』
と書いてる遺書みたいなのがあった。
俺はそれを見るなり、通夜で人がいっぱい来てるのに人目を気にせず大声で泣いていた。
それぞれ兄弟に宛てた遺書だった。
俺の所は
「子供達へ
葵ちゃんとこれから一緒に暮らして行くのならしっかりしなくちゃね
頑張らないとダメな時に、頑張りきれない所あるからしっかりして
幸せにしてあげるんだよ」
これを見る半年前に別れた彼女との事を書いていた。
これを見てるとき、俺は悔しくなり腹が立ち母が愛おしくなった。
もうどうする事も出来ないけど、最後にあの鍋焼きうどんをもう一度食べたい…
もっともっと、甘えたかった
俺には、3つ違いの弟がいた。
母は「お兄ちゃんだから我慢しなさい」なんて一言も言わなかったと思う。
でも、甘えるの我慢してた記憶はたくさんある。
3歳ながらに「弟はまだ赤ちゃんなんだから」って思ってたんだよなぁ。
親父は出張が多くてほとんど家にはいなかったな。
俺が小学生なって初めての運動会の朝、母は満面の笑みで
「ゆう君(俺)がんばってね!お母さん、かずちゃん(弟)とお弁当持って見に行くからね!」
って、送り出してくれた。
その満面の笑みは、今でもすぐに思い浮かぶ。
しかし、それが俺が聞いた母の最後の言葉だった。
母は自転車の後ろに弟を乗せ、カゴには俺の大好きなものばかり詰まった弁当を乗せて、俺の始めての運動会を見に行く途中、信号無視したトラックにはねられた・・・。
小1の頃の記憶は、ほとんどない。
「お母さん。 お母さん。 お母さん。 お母さん。 お母さん。 お母さん。 お母さん。 」
もっともっともっともっともっと、甘えればよかった。
弟が乳を飲んでいる時にも、「もう片方のひざはぼくのモノ~」って甘えればよかった。
もっともっと、甘えたかった。
甘えたかった・・・・。
あれから20年。
今日の午前2時55分、俺は親父になりました。
俺は、嫁と娘を全力で一生守ります。
誓います。
お母さん、かずあき、どうか天国で見守っていてください。
卒業できました
反抗期はきっと半数以上の人が通る道だろう。
自分も例外ではなかった。
中学まではいい子でいることができていた。
だけど、高校に入って周りの環境が変わり、一つ大人になったような気がして調子に乗っていた。
親の声も疎ましくなる一方だった。
自分の通っていた高校は私立で、バイト禁止だった。
だけど、バイトしている私を、母親は止めなかった。
父親も何も言わない。
なんのキッカケもなく、カッコつけるためにタバコを吸いだした。
その時も一言。
「やめなさい。」
それ以上はなかった。
夜中に家を出て遊びに行くことも増えた。
それでも何も言わない。
電話やメールの一つもなかった。
高校2年生の夏。
学校へ行くのが億劫になった。
それまでだって遅刻や欠席は多かった。
でも、それまで以上に学業に身が入らなくなった。
バイトに行って、その足で悪友と遊びに出かけ、朝方帰って寝るばかりだった。
母親もとうとう何も言わなくなった。
何も言われないことが、幸か不幸かどんどん自分を有頂天へと登らせた。
幸いテストの範囲が分かっていれば、授業は受けていなくても点数は取れた。
テストの点と留年しない程度の出席日数があれば、それでいいと思っていた。
高校3年生の冬。
とうとう欠席可能日数にも残りがなくなってきた時、担任から母親に電話が入った。
あと1日でも休めば留年という通告だった。
それまで何も言わなかった母親が、とうとう面と向かって話を仕掛けてきた。
今までの傾向から見て、きっと一言で済むだろう。
子どもの心配などしていないだろう。
そんなことを思いながら母親と向かい合う。
やはり正解だった。
たった一言。
「高校だけは卒業してほしい。」
いつもなら軽い返事か無視して話を切り上げていた。
でも、この時は様子が違った。
泣きながら、その一言を放っていた。
『何故泣いているのか?』
疑問が頭をよぎった。
ただ、どう声を掛けるべきか悩んだ。
沈黙が続く。
どうしても空返事をすることしかできなかった。
自分に関することで母の涙を見るのが初めてだったからだろう。
「分かってる。」
自分も一言だけ返して母の前を離れた。
その後は、毎日ちゃんと学校に行った。
遅刻も度々したが、なんとか卒業式まで漕ぎ着けることができた。
卒業式が終わった後、親戚やら母の友人やらからお祝いの電話やメールがたくさん入った。
メールを読むと
「あんたのお母さんは会うたびにあんたの話ばっかり。
『高校だけは出ないとこのご時世周りから嫌な目で見られて、
苦労するのはあの子だから卒業だけはしてほしい。
他のことだったらいくらでも変わってあげられる。
でも高校は、あの子しか行けないから。
反抗期で口も聞いてくれなくて、ちょっと寂しい。
でも、あの子は賢くていい子なんだよ』
って、いっつもあんたの事ばっかだよ。
ちょっと涙声でさぁ。
何がなくてもいいから今日は早く帰んなよ。」
届いたメールは、皆、同じ様な内容だった。
目頭があつくなった。
それから、私が家に帰ると誰もいなかった。
テレビでも見ながら時間を潰した。
全然頭に入ってこない。
鍵が開く音がして、母が帰宅した。
恐らく、買い物帰りだろう。
たどたどしく声をかけた。
「おかえり」
「ただいま」
その後少し沈黙が流れた。
重苦しい空気に耐えられなくなって、テーブルの上に置いてあった卒業証書を手に取り、母の前に差し出した。
何か言わなければならない。
とっさに頭の中で思い、やった出た言葉は
『卒業できました。ごめんなさい。ありがとうございました。』
と、ありきたりな言葉だった。
すると、母は
「卒業おめでとう。卒業してくれてありがとう。」
嬉しそうな顔で泣きながら、母は大事なものに触るような優しい手つきで証書を撫でた。
母の泣き顔を見て、自分のしてきた反抗を恥ずかしいと思うと同時に申し訳なくなって母の前で泣いた。
高校卒業と同時に反抗期が終わった。
今ではなんでも話すし、仲も良い。
不甲斐なさでいっぱいになる母の涙はもう見たくない。
もう泣かせてはならないと思った反抗期の最後だった。
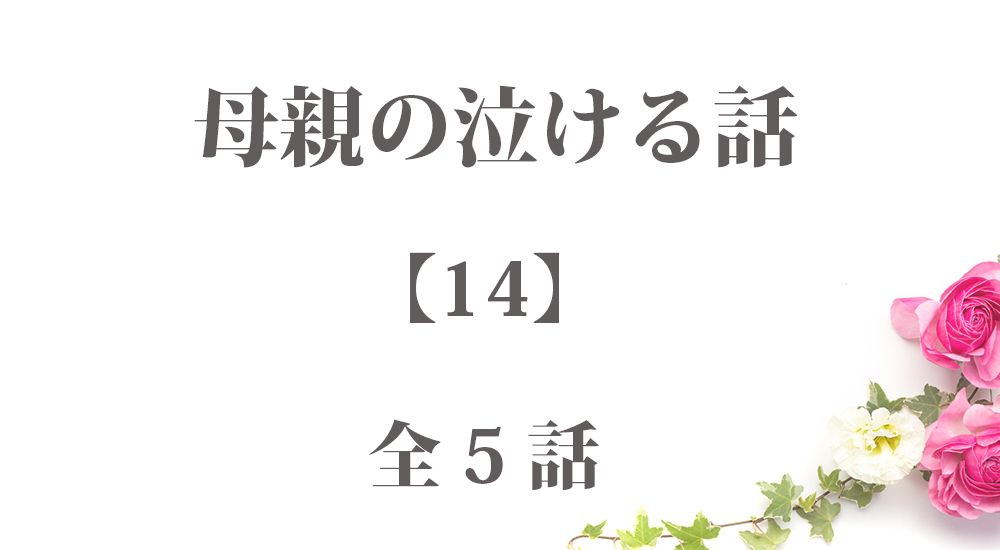
コメント