ナナシ 5 – 10話 【完全版 全29話】
『ナナシ』|1 – 5話|6 – 10話|11 – 15話|16 – 20話|21 – 25話|26 – 完結|
きみが呼び出したかったものは
学生生活も残り半年あまりとなった頃。
その頃すでに僕らは進学組と就職組に別れ、それぞれの勉強を始めていた。
僕とナナシは進学組、アキヤマさんは意外にも就職組で、その頃は次第に疎遠になっていた。
「イイの見つけた。」
その日、視聴覚室に篭って勉強をしていた僕に、青灰色のボロい本を携えたナナシがヘラヘラ笑って近づいてきた。
その本はどうやら図書館の寄附コーナーからナナシがパクってきたらしい。
僕らの地元にあるその図書館は、木々に囲まれた公園の端に建っており、なかなか貫禄がある。
また、よく寄附本が集まり、なかには黒魔術なんかの怪しい本も集まる。
ナナシいわく、その中にたまに「アタリ」があるそうだ。
「で、それはアタリなわけだ。」
「アタリもアタリ、大アタリだ」
ナナシは笑った。
普段はお調子者でヘラヘラしてて、クラスの人気者なナナシだが、ある日を境目にオカルト好きな本性を見せるようになっていた。
「これ、革が違うんだよ。」
ナナシが嬉々として本の表紙を摩った。
僕も触れてみたが、たしかに普通の本よりザラザラした革表紙だった。
「なんだよコレ」
聞いてもナナシは答えなかった。
ヘラヘラ笑いながら、革を撫でている。
そしておもむろに本を開くと、
「さあ、始めようか」
と言った。
ナナシは僕にあの本を渡すと、視聴覚室の隅に立つよう命じた。
僕は今から何が起こるかもわからないまま、素直に隅に立った。
ナナシは本から切り取ったページを片手に、すごい早さで黒板いっぱいに文字を書き出した。
英語なのか漢字なのかわからないが、みたことのない文章や図がズラリと並ぶ様は相当薄気味悪い。
おまけにナナシは一言も喋ることなく、まさに一心不乱といった様子でカツカツと黒板にチョークを滑らせている。
「ナナシ、何だよこれ」
ナナシは答えない。
やがて書き終えたのか、ナナシがこちらに向き直る。
その顔はいつものヘラヘラした笑顔だが、何かが違う気がした。
「それ、読んで。」
ナナシが本を指差す。
雰囲気からして洋書かと思ったが、中は意外にも日本語で書かれたものだった。
なんと書かれていたかは今はもう覚えていないが、なんだか意味を成さないような不気味なものだったと思う。
それでも、怖いもの見たさもあったのか、僕は書かれた文章を読み上げた。
そのとき、聞き慣れた声がした。
「あんたたち何してんの?」
窓枠に寄り掛かり僕らに声を掛けてきたのは、他ならぬアキヤマさんだった。
「面白そうじゃない、あたしも混ぜてよ」
窓枠に足をかけ、中に入ろうとする。
怪しい行為をしていた最中だったのでにちょっと僕もビビッたが、久しぶりにアキヤマさんと話せることが嬉しくて、僕はアキヤマさんに駆け寄った。
そのとき。
「アブないぞ、ソレ。」
ナナシがアキヤマさんを指差した。
そのナナシの物言いにカチンと来た僕は、ナナシに抗議した。
「ソレってなんだよ、おま…」
「よく見ろよ、ソレはどっから来た?」
「どこって窓からに決まって…」
そこで、めちゃくちゃ遅ればせながら気付く。
ここは視聴覚室。
—-3階だ。
『コレ』は、アキヤマさんじゃない。そう気付いた瞬間、「ソレ」は酷く歪んだ笑顔で、体をクネクネさせながら僕に近づいてきた。
白目に赤い筋がたくさん浮かび、それでも口元は笑っている。
「うぁあぁあぁあ!!!!!!」
僕は無我夢中で『ソレ』を払いのけ、外に押し込み、窓を閉めた。
途端、けたたましいくらいにガラスを叩く音がする。
…内側、から。
「ナナシ!!!ナナシ!!」
僕は半狂乱になりながらナナシを呼んだ。
ナナシなら助けてくれる、と漠然に思った。でも、ナナシは僕を見て笑っていた。
「ははははは!!最高だよお前!!!!!」
僕は本気でナナシに殺意を抱いた。
気がついた時、僕は汗だくになって床にヘタリこんでいた。
ナナシが自分のTシャツで汚いものを拭くかのように僕の顔を拭っていた。
「結局、あの本は何だったんだよ」
叫び過ぎて掠れた声で、僕はナナシに聞いた。ナナシはヘラっと笑うと、
「降霊術みたいなもんさ」
と言った。
「会いたいものを呼び出せる呪文と方位がのってる。さすがに犬皮使ってる本だから、ヤバそうだとは思ったけど」
いろんなヤバイモンが詰まってるよ、コレ。
ナナシは笑って言った。
「俺じゃなくて、本持ってたお前の会いたいやつが出て来たのは誤算だったな。まあ、中身は違うけど。お前、よっぽどアキヤマに会いたかったんだな。」
ナナシはそう言うと、またヘラヘラ笑いながら本を抱えて歩いて行った。
ちょうど下校の鐘が鳴って、僕もナナシの後を追う。
前を歩くナナシの背中を見ながら、僕は思った。
『いろんなヤバイモンが詰まってるよ、コレ。』
『俺じゃなくて、本持ってたお前の会いたいやつが出て来たのは誤算だったな。』
そこまでして、ナナシは一体 なにを 呼び出したかったんだろう?
その答えを知ることになるのは、もう少し、先の話。
知らないしあわせ
学生時代、二学期も半ばに差し掛かった頃。
僕らのクラスでは、なぜか『学校の怪談』というアニメが大流行し、今更ながらオカルトブームが訪れていた。
女子はこぞっておまじないなどにハマりだし、男子は肝試しに出掛けた。
僕としては、今まで友人のナナシと体験してきたことのほうがよっぽど怖かったし、当のナナシも今までの体験談を話すこともなく、いつものようにヘラヘラして皆の話を聞いていたから、何も言わなかった。
散々出まくった都市伝説にキャーキャー言うクラスメイトたちを見ていると、『知らぬが仏』って本当に名言だなあ、と思っていた。
そんなとき、唐突に声をかけられた。
「今日、俺ん家来ないか?」
それは、ヤナギと言うクラスメイトからの誘いだった。
ヤナギは、親父さんが貿易だか輸入なんたらだかの会社の社長で、まあ、いわゆるお金持ちだった。
でも金持ちにありがちにな厭味がなく、むしろサバサバして皆から好かれていたし、僕やナナシも仲良くしていた。
「なんで突然?」
僕が尋ねると、
「ウチの親父が、珍品コレクター、っての?なんか不気味なモンばっか集めててさ。いわくありげな物もあるから、見に来ないかなぁと思って」
と、ヤナギは言った。
すると、いつの間にかナナシが僕の隣に立っていて、
「行く行く。ぜひともお邪魔します。俺もこいつも、そうゆうの好きでさぁ」
と、僕の肩をつかんで引き寄せ、僕の意思や意見は完璧無視で誘いを受けやがった。
こうして、僕らはヤナギの家にお邪魔することになった。
「ここなんだよ。」
放課後、馬鹿デカいヤナギの家に着くなり、僕らは地下室に案内された。
地下室と言っても、じめじめした嫌な雰囲気はなく、特に怖いことが起こる予感はしなかった。
正直、ナナシといると変なことばかり起こるので、来るまでは不安だったのだが。
「今日は親父いないから、まあゆっくり見てけよ」
ヤナギが地下室の鍵を開ける。
なんだかんだ言いながら押し寄せていた期待感に心臓をバクつかせていると、ドアが、開いた。
「…ん?」
しかし、中には期待していたようなおかしなものはなかった。
古い本や、ちょっと大きな犬の剥製、振り子時計なんかが置かれているだけだった。
「べつに珍品じゃないんじゃね?」
もっと、こう、動物の生首だとか奇形物のホルマリン漬けだとか、殺人鬼が使っていた刀だとかを想像していた俺は、なかばがっかりしながら言った。
しかし、隣に目をやると、ナナシが笑っていて僕はゾッとした。
いつものヘラヘラした笑顔ではなく、あの不気味な歪んだ笑顔だった。
「まあ、そうでもないんだよ」
ヤナギはそんなナナシの様子に気付くことなく、僕の発言に答える。
「たとえばこの振り子時計。
これは、どっか外国の殺人鬼の物でさ、この扉の中に殺した人間の指の骨を入れて集めてたらしいよ。
こっちの剥製は飼い主の赤ん坊を噛み殺した犬らしいし、この本は自殺した資産家が首をくくるときに踏み台にしたものなんだと。」
ヤナギがスラスラと不気味な話をし出す。
つまりヤナギの親父さんは、そうゆういわくつきの物をコレクションしてるわけだ。
「まあ、本当かどうかはわかんないけどさ。」
ヤナギは笑った。
そのとき、
「なあ、これ、何?」
ナナシが何かを見つけた。
それは、ちょっと煤けていたけど、立派な女の子の人形だった。
フランス人形か何かだろうか、青い瞳を伏せている。
「ああ、それか」
ヤナギが人形を持ち上げる。
「これは特に不気味なもんじゃないんだけど、変わった作りがしてあってさ。」
ココ、と、ヤナギが人形の瞳をつつく。
「なんか、角度や色が細かく計算してあって、絶対に目が合わないようになってんだよ。」
なるほど、確かに目が合う人形は山ほどある、というかむしろ人形とは目は合うものだが、絶対目が合わない人形とはめずらしい。
僕も人形をヤナギから受けとり、目を見てみた。
確かに、微妙に目の焦点がズレて見える。
「へぇ。こいつは面白いな」
僕は人形を色んな位置に移動させて、目を合わせようと試みた。
けど、やはり目が合わない。
どこか違う方を見ている。
そのとき、気付いた。
どんなに移動させようと、角度を変えようと、目の合わない人形。
その人形が、僕から目をそらし、見ている一点。
それは、 ナナシだった。
「え?え?」
僕は場所を変え角度を変え、立ち位置を変え、人形を動かした。
しかし、どんなにそれらを変えても、目の合わない人形はナナシの方を見ていた。
どの位置に立っても、ナナシがいる方に目線が向いている。じっと、睨みつけるように。
おかしい。
オカシイオカシイオカシイ。
僕はパニックになって人形を揺さぶっていた。
怖くて怖くて仕方なかった。
どうしてナナシの方を見るのか。どうして。
そのとき。
「ホラ、いい加減にしろ。」
ナナシが僕の手から人形を奪うと、元の場所に置いた。
僕は汗だくになっていた。
「悪いなヤナギ、こいつ夢中になると我を忘れるから。でも面白いな、親父さんのコレクション」
ナナシがヤナギに詫びを入れ、ほかに話を振る。
ヤナギも特に何か疑う様子もなく、話をしている。
それでも僕は、やっぱり人形を見ていた。
人形は、やっぱりナナシを睨みつけていた。
しばらくお喋りをして、僕とナナシはヤナギの家を後にした。
帰り道、僕はナナシに思い切って言った。
「ナナシ、あの人形…」
「ずっと俺のほう見てただろ?」
やっぱりナナシはわかっていた。
ニヤニヤと不気味な笑みを浮かべながら、僕を見る。
「なかなかお前も、だいぶカンがよくなったじゃねぇか」
俺の教育の賜物だ、などとふざけたことを抜かすナナシに腹を立てつつ、半ば呆れて僕は言った。
「お前、よく怖くないよな。」
するとナナシは、ハッ、と鼻で笑うと、
「俺はお前の後ろに突っ立てた、手足がやたら折れ曲がった女のが怖かったぜ?」
ベキベキベキって、聞こえてきそうでさ。
と、言った。
僕は急速に体が冷えてくのを感じた。
「ん?知らなかった?」
ナナシはケラケラ笑って、
「『知らぬが仏』って、ホント名言だよな。」
と言った。
どこかで聞いたセリフだと頭の隅で感じながら、僕は走ってその場を去った。
それから僕がヤナギの家に行くことは、二度となかった。
きみに出会った春の夕暮れ
ナナシと仲良くなった切欠は、正直なところ覚えていない。
いつのまにか仲良くなり、あたりまえにそばに居るようになった。
しかし、初めてしゃべったときのことだけは鮮明に覚えている。
あれはまだ、入学したての頃のことだったと思う。
僕は飼育係に半ば無理やりさせられて、その日も確か小屋の掃除をするために皆が帰った後も残っていた。引っ込み思案で地味な僕はなかなか友達もできず、毎日が憂鬱だった。そんななかで押し付けられたとはいえ、ウサギや鶏の世話をすることは僕の癒しでもあった。
その日、併設されている小学校の飼育係の子が餌を置いて帰った後、僕は掃除の水汲みのために給水場に行った。あとでウサギたちと遊ぶことに胸をわくわくさせながら。
しかし、小屋の前まで帰ってきて僕は驚いた。
一匹のウサギが横たわって、動かなくなっていたから。
そしてその傍らに、見覚えのある少年が立っていたから。
「なな・・・・・しま、くん」
ナナシマキョウスケ。
クラスメイトで、いつも男女問わず何人もの人に囲まれて笑っている、人気者。お調子者で、先生や先輩にも好かれていて、僕とは真逆の立ち位置にいる人間だった。
だから僕は彼が苦手だった。
僕にないもの、僕のほしいものを全部持っていて、うらやましかった。
あこがれていたクラスメイトの女の子とも、気さくにしゃべっていた彼が妬ましかった。
そんな一方的なねたみから、僕は彼と極力関わらないようにしてたのに、まさかこんなところで逢うなんて。
それも、ウサギのなきがらの前で。
・・・・・ウサギの、なきがらの前に、なんでこいつがいるんだろう。
僕は自分でもわかるくらいはっきりと、鋭い目つきで彼を睨んだ。
「藤野か。」
ウサギを前に呆けていたナナシマは、僕に気付いて声をかけてきた。それが最初の会話だった。
僕は彼がウサギを殺したんだと思った。
いろんなものを持ってるのに、まだ僕から奪うのか。一生懸命世話をして、唯一の友人の一人だったウサギ。
毛の色からして、一番年寄りだったミミ子に間違いない。いつも美味しそうに餌を食べて、僕の足元にいたミミ子を。こいつが。
沸沸と怒りと悔しさがこみ上げてくるのがわかった。そして同時に、彼が僕の名前を知っていたことが何故か嬉しく、そしてそんな自分が余計許せなかった。
ちがう。そうじゃないだろ。
そうぼくは自分をしかった。
こいつが僕の友達を殺したんだ。なにを嬉しがっているんだ。
ミミ子の命はこいつの手によって缶でも握りつぶすかのように奪われたんだ。
友達だったのに。大切な友達だったのに。許せないと思った。この目の前でヘラヘラと笑う男がどうしても許せなかった。
いろんなものを持っているくせに、僕の唯一のものを奪っていったこいつがどうしても。
再び込みあがってきた怒りと、ピクリとも動かない友達への悲しみで、僕の涙腺は粉々に決壊した。ナナシマがギョッとするのがわかった。しかしそんなこと気にしていられなかった。
死んでしまったのだ。ミミ子はもう決して動かない。レタスもニンジンも食べられない。もう二度と、僕の足元で昼寝をしてくれない。
そんな悲しいことがどうして存在するんだ。
声も発せられないまま、僕は泣いた。
すると、
「そんなにショックだったのか?」
と、声がした。もちろんその声の主はナナシマ以外の誰でもない。
僕は耳とこいつの神経を疑った。
ショックだとか何とか、おまえが言えるのか?
おまえが言うのか?
なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんで。
次の瞬間、僕はナナシマにつかみかかっていた。
「おい藤」
「どうしておまえがそんなこといえるんだ!!僕はおまえとは違うんだよ!おまえとは違うんだ!!!友達だったんだ、ミミ子は!!いっつもいっしょにいたのに!!友達だったのに!!」
ナナシマの表情はもう見えなかった。
僕の視界は涙でぐちゃぐちゃに歪んでいた。
「・・・ごめん」
ナナシマが呟いた。
でもどんなに謝られても、ミミ子は帰ってこない。僕が一人ぼっちなことは変わらない。
「どうして・・・ミミ子を殺したんだ?」
僕は呟いた。それだけはどうしても聞いておきたかった。
ミミ子がなぜ
死ななくてはいけなかったのか、どうしても。
しかしナナシマは、驚いたように言った。
「ちょっと待て。俺は殺してない。」
僕はまた耳をうたがった。
この後に及んで何を言うのか。
しかしナナシマはそんな僕にさらに続けた。
「見てみろよ。そのウサギ、どっこも傷ついてないだろ」
言われるがまま、僕はミミ子の体を見た。
たしかに外傷などはひとつもなかった。
「もういい年だったんだろ?そいつ。俺が来たときにはもう死んでたよ」
ナナシマはそういった。
そう、確かにミミ子はもうだいぶ年寄りのおばあさんウサギだった。言い換えれば、いつ死んだっておかしくはない。
なのに僕は、ただそこに居合わせたクラスメイトを、疑ってしまったのだ。普段のねたみもきっと、あったんだろう。
僕は途端に自分の犯した罪に気付いた。
「あ、ご、ご、めん、僕、なんてことを」
「全くだ。動かないウサギがいるから覗いてみれば、ひとを殺人犯呼ばわりか」
ナナシマは怒っていた。当然だ、僕は最低なことをしたのだから。
自分のコンプレックスや嫉妬、そしてその場の状況だけで無実のクラスメイトを疑うなんて、
人間として最も、否、生き物として最も醜いことだ。
普段からドラマなどでそういうことをする人間を見るたびに嫌悪していたのに、結局僕も同じ穴の狢だったのだ。
「でも、大事なトモダチだったんなら、仕方ないよな」
僕は三たび耳を疑った。
「おまえ、暗くて何考えてっかわかんなかったけど。いいやつじゃん。おまえのトモダチになれるやつは幸せだな。」
ナナシマはそう言った。
怒るでもなく、ウサギがトモダチだなんていう僕に引くわけでもなく、
僕という存在を肯定してくれた。
「なあ、墓作ってやろう。俺も手伝うから。」
ナナシマは普段そうするようにヘラヘラと笑った。
ぼくはまた、涙が出てきそうになったが必死にがまんした。
言葉を発すると泣き出しそうで、ありあとうもごめんなさいもいえないまま、僕はナナシマと一緒にミミ子を裏庭の花壇に埋めた。
「ここなら年中花が咲いてるから、寂しくないだろ?」
ナナシマのその言葉に僕はまた胸が熱くなった。
普段の、お調子者でヘラヘラした様子はなく、心から生き物の死を悼んでくれていた。
埋め終わると、ナナシマは帰っていった。
じゃあな、と手を振ってくれたことは今も忘れない。
誰かに手を振ってもらうのなんか、中学生になって、初めてだった。
ミミ子の死はとてつもなく悲しかったけれど、知らなかったクラスメイトのやさしさが、すごく嬉しかった。
それから、僕らがあだ名で呼び合い、周りからも認められるような友人になるまで、そう長くはかかっていなかったように思う。
もうそういう細かいところは、歳をとった今はほとんど覚えていない。
ただ、あの日僕の親友の死が、僕に親友を与えてくれたことは間違いない。
彼女は今も、花の咲く花壇で眠っている。
手向けた花
学生時代、ある夏の終わりのこと。
蝉の死体もいつのまにか少なくなってすこし風も涼しくなってきたその日の夕方、僕は親友と墓場に出かけることになった。
その日は、何も肝試しをしようというわけではなく、数年前に亡くなったという親友の従兄弟の墓参りのために墓場に行くことになっていた。
本来無関係な僕がその人のお墓に出向くというのもおかしな話だが、親友にとってもその従兄弟というのはほとんど逢ったことのない「親戚A」でしかなかったらしく、今回たまたま母方の叔父さんに掃除を頼まれたからでなければ行かなかったという。
そうつまり、僕はお墓の掃除をするのに駆り出されたアルバイトもどきだった。
はじめこそ、親友、つまりナナシと墓場なんて冗談じゃない。今までどんな目にあってきたかと断ったが、
「そう。おまえは困ってる親友を見捨てるんだな。そういうやつだったんだ。」
と、まるで極悪人のような言い方をされては無下にすることもできず、僕はついていくことになった。
その墓場、否、霊園と呼ぶべきか、とにかくそこは以外にも綺麗にされていて、僕らが掃除する必要なんてないように見えた。
しかし、実際ナナシの従兄弟の墓自体は、結構汚れていた。いつ供えられたのかわからないような饅頭のようなものがカピカピになっているし、花は枯れて茎のみになっていた。
「これじゃあこの人も浮かばれないね」
僕は何気なく口にした。
僕だったら、もし自分が死んだらお墓には毎日じゃなくていいから綺麗な花を飾ってほしいし、
供え物なんかなくてもいいから掃除は綺麗にしておいてほしいと思うから。
しかし、隣で黙々とゴミを集めていたナナシは、表情ひとつ変えずに
「死人に花もクソもない。花なんか、生きてる人間の自己満足でしかないだろ。死んで花実が咲くんなら、墓場は今ごろ花だらけだ。」
と言った。その言い方には何の感情もこもっていなかった。ただ冷たく、僕の心の底のほうに突き刺さるだけだった。
なんで?と、僕はおもった。ミミ子が死んだあの時は、ミミ子が寂しくないようにと花壇に埋めてくれたのに。どうしてそんなことを言うのだろう。
それは、今にして思えばナナシが変わり始めていたからなのだろう、とわかる。
少しずつ、ナナシが今までのナナシでなくなっていくサインだったのだろう。けれどそのとき僕はそんなことには気付かず、ただ悲しいとしか思わなかった。
「な、水汲んできて」
「あ、うん」
そんなことを考えていると、ナナシが僕に水汲みを頼んできた。
「終わったらラーメンでも食いにいこう」といつもの笑顔を浮かべたナナシに、僕は少し安堵した。
よかった、いつものナナシだ。さっきのことはもう忘れよう、虫の居所でも悪かったんだろう。僕はそう思い込み、バケツ片手に水汲み場に走った。
水汲み場でバケツに水を貯めていると、あたりが少し暗くなってきたのに気付いた。腕時計に目をやればもう六時に近づいていた。
時間を意識するとお腹も突然すいてきて、はやく終わらせてラーメンを食べたくなった。多分このご褒美にナナシがご馳走してくれるだろうから、チャーシュー追加してやろうかな、なんて考えていた。
そのとき。
「ねえ、ねえ」
後ろで声がした。振り返ると、小学生くらいの男の子がいた。俯いてて顔がよく見えないが、その子は確実に僕に声をかけていた。
「ん、どうしたの?」
「僕ねえ、ひとりぼっちなの」
声を掛けると、男の子はそう言った。迷子になったのかな、と僕は思った。何しろそれなりに広い霊園だし、周りはあたりまえの墓だらけで見渡す限り同じ風景なのだからこんな小さい子なら迷子になっても仕方ないだろう。
「じゃあ、お兄ちゃんがいっしょに行ってあげるよ。」
「・・・本当?」
「うん。きっとママやパパもしんぱ・・・・・」
そこで、僕は息を呑んだ。
嬉しそうな声を出して、僕を見上げたその子の顔は、どうみてもおかしかった。
否、人間のものでは無かった。
顔の半分以上が、目なのだ。
そしてニタアっと大きく口をあけて笑っていた。
「い っ し ょ に い っ て く れ る ん だ よ ね ? 」
男の子はすごい力で僕を引っ張っていった。恐怖で僕は声も出なかった。
必死に振りほどこうとしても、男の子の手はそれを許さなかった。
「や・・・・や、だ、やだああアアああ!!!!」
やっとの思いで悲鳴をあげると、 ぐ る ん と男の子の顔だけがこちらに向いた。
「「「いっしょにいぐっでいっだだだだよねえねねね」」
皺枯れた老婆のような声を発しながら、男の子は僕を見た。
怖くて怖くて、僕は泣き叫んだ。たすけて、だれか、たすけて、ナナシ、ナナシナナシななしナナシ!!!!
何度もナナシの名前を呼んだ。情けないくらい声が震えた。
このまま死んでしまうのかな。つれていかれるのかな。いやだいやだいやだいやだ。
涙で前が見えなくなった、そのときだった。
「放せよ。」
後ろから声がした。待ち望んでいた、聞きなれた声だった。
「放せ。」
ナナシはもう一度言った。さっきとおなじ、冷たい声だった。
男の子は凄まじい目でナナシを見ていた。
そして顔半分の目から、滝のような涙を流すと、
「うそつき」
といって消えた。
僕はその場に座りこんだ。ゆっくりとナナシが近づいてくる。
「大丈夫か?」
「うん」
ナナシが手を差し伸べてくれたが、僕はその手が取れなかった。
あの男の子の「うそつき」は、僕に向けられたものだった。僕は言ったんだ。
「いっしょにいってあげる」って。
男の子が消えたほうを見ると、お墓があった。
そのお墓には、干からびたお菓子と、枯れた花と、すすけたおもちゃがあった。
さっきの、ナナシの従兄弟の墓のように。
「ねえナナシ」
「何」
「もしナナシが死んだら、ちゃんと花もお菓子も供えるからね。」
僕は言った。
恐怖とは違う感情で、ぼくは泣いた。男の子がかわいそうでしかたなかった。
すると、ナナシが静かに言った。
「おまえが死んだら、俺はいっしょにいってやるよ。ちゃんと花も置いたあとでな。」
その言葉に、余計涙が出た。
僕を慰めるための嘘だったとしても、ナナシのその言葉は嬉しかった。
自己満足でもいい。花実なんか咲くはずも無い。それでも、大切な人の眠る場所に花を置く。
それは、とても大切なことだと知った。
僕らは、男の子のお墓に摘んだ花を置いてその場を去った。二人とも何も言わなかった。
その日食べたラーメンの味は、ひどくしょっぱかった。
独白1
平成二十年、一月六日。
僕は二十三歳になった。数人の友人たちや職場の同僚がお祝いの品をくれ、何人かとはパーティもどきのような席も設けた。
おおいに楽しく、シアワセな時間だったが、そこに僕の親友の姿は無かった。あるはずも無いのだが、探してしまうのはいつものことなのでしかたが無いとしか言いようがない。
そしてその姿が無いことにひどく傷つく自分に嫌悪感を覚える。
傷つける立場なのか、おまえは。
そう自分に問い、責める。
本当に傷ついていたのは誰だ。無論僕ではない。
むしろ傷つけたのが僕だ。傷ついていいのは僕なんかではない。
被害者ぶるな。僕こそが、最大の罪人ではないか。
そんなことを考えていると、ヤナギが僕の肩を叩いた。
「主役が一番テンション低くてどうすんだ」
軽口のなかに込められた彼の気遣いに気がつかないほどの馬鹿ではない。
ヤナギの存在と言葉は、いつも僕の支えになる。
僕もあの時、今のヤナギのようにしていたら。
そんな自己嫌悪が再び浮かび上がる。
ネガティブもいい加減にしなくてはいけない。
「俺らトモダチなんだからさあ、なんかあんならエンリョなくいえよ?」
相変わらず表情の冴えない僕に、ヤナギは言った。
ヤナギは決して、「親友」とは言わない。
長い付き合いで、家族ほど仲良くしていても、「親友」ではなく「トモダチ」だと言う。
それは、僕の親友がひとりしかいないと知っているからだ。
ヤナギは、かの親友と僕にあったできごとは何も知らない。
だが、あの「サヨナラ」の日から幾日か過ぎたとき、彼は、かの親友の行方を聞いて、僕に言った。
『おまえの親友は、ずっとキョウスケだけだから、俺はおまえの「親友」にはなれないけど。一番のダチでいさしてくれな』
その言葉にどれほど救われたことか知れない。
そして、何も知らないとはいえ、僕をあいつの親友と認めてくれたことに、
僕はひどく救われた。
同時に浮かぶ罪悪感は決して、生涯消えることは無いだろうけれど、それは僕が彼を忘れていない何よりの証拠でもあるのだろう。
だから、どんなに自分の罪深さに辟易しても、僕は後悔をやめない。
後悔することが、親友へのせめてもの罪滅ぼしだと思うから。
「ホラ、から揚げ無くなるぞ」
ヤナギが僕の手を取り、皆のいるほうへ連れ出してくれる。
心の中で親友に詫びながら、僕はその手を取った。
きみのできなかったことをして、ごめんね。
きみをすくえなくてごめんね。
おとなになって、ごめんね。
でも、
『これからも生きてていいですか?』
親友の残した言葉を、心の中で呟いた。
返事はかえってこなかった。
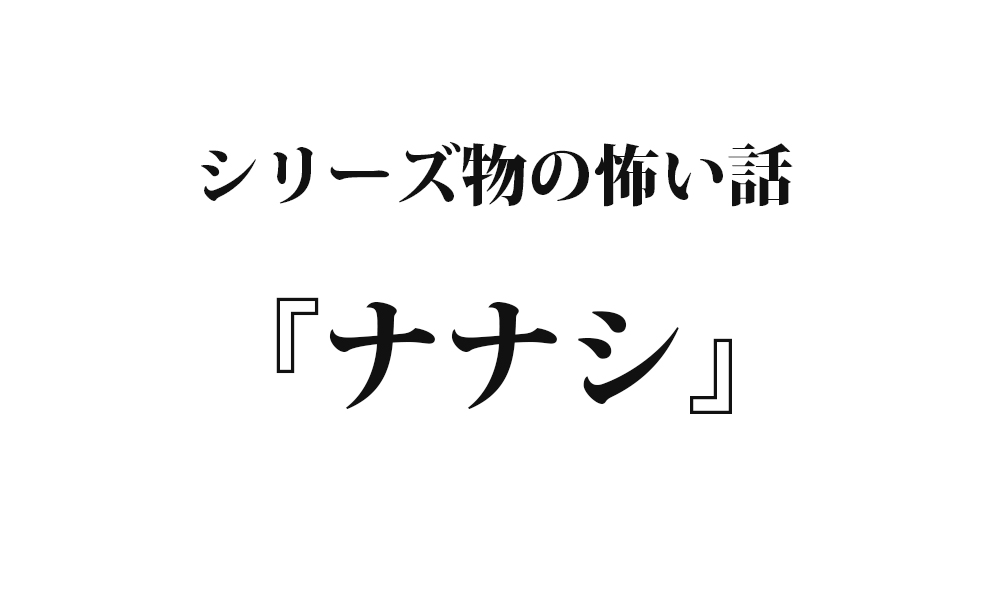
コメント