ナナシ 11 – 15話 【完全版 全29話】
『ナナシ』|1 – 5話|6 – 10話|11 – 15話|16 – 20話|21 – 25話|26 – 完結|
揺れてつかの間
陽の当たる時間が短くなってきた頃の、ある日の夕暮れ。
僕はその日、掃除当番で教室に残っていた。同じ掃除当番だったクラスメイトの女の子はゴミを置きに出ていて、僕はひたすらチリ取りを動かしていた。
そんなとき、
「よお。」
と聞きなれた声がドアの方角から聞こえてきた。振り向かずともわかっていたが、そこにはナナシが立っていた。いつものヘラヘラした薄笑いを浮かべ、買ったばかりだというショルダーバックを振り回しながら彼はそこにいた。
「なんだ、待っててくれたんだ」
とっくに帰ったと思っていたので、予期せぬ親友の登場に僕は嬉しくなり掃除のことはすっかり忘れてナナシに駆け寄った。
「これから時間あんだろ。行こう」
どこへ行くかも告げず、ナナシはニッコリ笑って踵を返した。さすがにゴミだしに行ってるクラスメイトに何も言わず勝手に帰るのは気が引けたので、黒板に先に帰る旨を書き残し、僕はナナシのあとを追った。まだ六時になったばかりだというのに窓の向こうはほぼ真っ暗で、電気がついているとはいえ薄暗い廊下を歩いていくナナシが、なんだか闇に溶けていなくなってしまうような妙な感覚に襲われ、僕はすこし速く歩いてとなりの並んだ。今思うとそれはあながち間違っていない、虫の知らせというやつだったのかもしれない。
そんなことを知ってるのか知らないのか、ナナシは厭味なニンマリ顔で笑うと、
「怖がり」
と僕に言った。聞こえないふりをして校舎を出ると、ナナシはいつもの帰り道とは反対の方向へ歩き出した。
「どこ行くの」
「うん?おもろいとこ」
親友のはぐらかすような物言いには慣れていたので、それ以上なにも言わず後に続いた。
ついた場所は、栄生駅のすぐ近くにある何の変哲も無いマンションの前だった。夏に行ったアパートのように無人ではなく、玄関には明かりもついているし自転車もいくつか止められている。
「こんなとこに何しに来たんだよ」
僕が問うと、ナナシはヘラっと笑い、
「ここな、『首括りの家』って呼ばれてるんだと。横溝正史もびっくりだぞ?この半年で四人だってさ」
何が面白いのかナナシはクックと嫌な笑い声を上げた。第一、どこからそんな情報を仕入れてくるのか。僕には疑問でしかなかったが、それを問い掛ける勇気はなかった。
ていうか、なにが面白いところなのか。いわゆる自殺の名所的な場所にきたわけだ。これまでのことを考えれば、「なにか」あるに決まってるそして、それを正直に言えば僕がビビッて帰るだろうということも、この親友はわかっていたのだろう。だからあんなあいまいな言い方でごまかして、僕を連れ出したんだな、と僕は思った。
しかし、そう短くない付き合いの中で僕も、そういう「なにか」が少し楽しくなっていた。
もちろん怖い、がナナシと共有するこの時間は、なんとなく好きだった。
ナナシはそんなことを考えてる僕にはお構いなしでマンションに入っていく。そして薄明かりのついた玄関を見回すと、エレベーターではなく階段の入り口に立った。
ドアノブを回すと、錆びているのか「ぎぎぎ」と音がした。ドアの向こうには当然ながら階段が続いていた。電気はついてないらしく、しかし所々に設置された丸い窓から月の光と周りの店の看板のネオンが入っていて、薄暗くはあったが視界はそこまでわるくなかった。
「四階で二人、屋上でひとり、管理室でひとり、首吊ったんだってさ」
ナナシは楽しそうに言った。そして、まずは四階にいこう、と言い出し階段を上りはじめた。
僕はため息をついて、しかしやはり怖いのでナナシのショルダーの端をつかみながら階段を上った。
一、二、三、とフロアを通り過ぎて、「4」と書かれたドアの前に僕らは立った。ナナシがノブを回すと、また「ぎぎぎ」と音した。
扉の向こうは、ごく普通のマンションのフロアだった。表札のついたドア、そう広くない廊下、
白い壁。特に変なところなど見当たらなかった。
「なんだ、ふつうのとこじゃん」
安堵して息をつくと、僕は少し調子に乗って先立って歩き始めた。うしろからナナシがついてくるのがわかる。いつも背中を追いかける側の僕としては、ナナシの前を歩けることが些細なことだがひどくうれしかった。
少し薄暗いが割合綺麗なマンションだし、各ドアに飾られたかわいらしい折り紙の細工物や「セールスお断り!」の札などを見ても、とても自殺者のでたマンションには見えないし、今日はハズレだね、と僕は笑って言った。
しかし、
「本当にそう、思うか?」
ナナシから返ってきた言葉は、予想外のものだった。
驚いて振り向くと、
ナナシはひどく真剣な表情をしていた。すこし怒ったような、硬い表情。僕はなにか間違ったことを言ったのだろうか。と不安になった。
するとナナシは次の瞬間、僕の手を引っ張って階段のほうに走り出した。訳がわからず慌てふためく僕に、ナナシは叫ぶように言った。
「 絶 対 後 ろ を 見 る な ! ! ! 」
ナナシの声は、聞いたことが無い怒気をはらんでいた。すこしあせっているようなナナシのその口調が、僕は怖かった。今まで数々恐ろしい目にあってきたけれど、こんなに切羽詰ったようなナナシを見るのは初めてだった。
狂ったように笑うナナシよりも、「あの」ナナシが余裕を無くしていることが怖かった。
けれどその時点で、僕にはナナシがなんでこうもあせっているのかわからなかった。
それもまた、恐怖だった。
階段の入り口までくると、ナナシは蹴飛ばすような勢いでドアを開け、転ばないのが不思議なほどの速さで階段を駆け下りた。握られた手は、ひどく冷たい。なにかに緊張してるのがわかる。
「ナナシ!!ねえナナシどうしたの!!?」
引きずられながら僕は必死にナナシに尋ねた。なにもわからないまま走る恐怖に耐えられなかった。するとナナシは小さな声で、
「足元、見てみろ」
とだけ言った。
そこでようやく、僕にもわかった。そしてその恐怖に悲鳴をあげた。
ぼくらの足元に、影が差していた。
ゆらゆらと、規則的に揺れる、黒い大きな影。
そう、まるで、首を括った人間の体が揺れているかのような、影が。
「ひ、ひ、や、なにこれええぇ!!!」
「考えんな、走れ!絶対ふりかえんなよ!」
泣き出す僕にナナシが怒鳴った。振り返れるはずがない。
なにが揺れているの?
なんで揺れているの?
だ れ が ゆ れ て い る の ?
考えたくないのに、恐ろしい疑問ばかりが浮かぶ。影は止まることなく揺れつづけ、僕らのあとを追ってきていた。
規則的に、ギシギシと音を出しながら、揺れる影は僕らから離れなかった。
助けて助けて助けて。そう叫びながらもつれる足を走らせていると、途端に前が明るくなった。
ナナシが出口のドアを開けたらしかった。
転がるように僕らはマンションを出た。そのまま大通りまで走り、家路を急ぐ人々が見えてきた頃には、もう影はいなくなっていた。
となりで少し苦しそうに息を整えてるナナシに、僕は聞いた。
「あれは、な、に?なんだったんだよ?」
「さあな。今回ばかりは焦ったけど、俺にもわかんないよ。ま、死人は執念深いってことだな」
ナナシはいつもと変わらない口調で言った。とても怖かったけれど、ナナシのその普段どおりの口調に僕はとても安心した。
しかしそのすぐあと、ナナシは言った。
「俺は、気をつけなきゃ。失敗、しないように」
その言葉の意味を知ることになるのは、もうすこし先の話だけど
そのとき、その言葉の意味がわからなくて、
でも、なぜだかひどくぞっとしたのを覚えてる。
なにを、気をつけるの?
なにを、失敗しちゃいけないの?
ねえナナシ、きみは
な に を し よ う と し て い る の
あのとき、聞けていたなら。
狼少年の墓標
それはもう、いつのことだったか覚えていないが、たしか今日のように寒い中三の秋の日だったと思う。
どうしてそんな話が出たのかわからないが、いつもの帰り道、僕と親友の会話に「狼少年」という童話の話がでてきた。
おそらくその数日前に、道徳の授業でメルヘン好きな担任がこの話を朗読していたことから、そういう流れになったんだろう。
「あれは、可哀想な話だな」
親友が呟いた。
「そうかな。自業自得だよ」
と僕は反論した。
自分のたのしみのために嘘をついて皆に迷惑を掛けて、それで信用されなくなってなにもかも失ってしまったわけだから、むしろ勧善懲悪に近い話だと、僕は思ったから。
しかし親友は、ゆっくり首を振るといつもとは少し違った笑顔を浮かべながら言った。
「考えても見ろ。狼少年は野原に一人ぼっちでいたわけだろ。どんな寂しいと思う?
それも、いつ狼がきてもおかしくないような場所に。」
頭を金槌で叩き割られた気がした。
そうだ、言われてみれば、その通りだ。
狼少年は、狼のきてもおかしくないような場所に、ずっとひとりぼっちだったんだ。ずうっと、ずっと。
「どうして大人は、『危ないから行ってはいけない』って、言ってやらなかったんだろうな。羊のほうが、子供より大事なんだろうな、きっと。」
親友はひどく滑稽そうに笑った。
「そりゃ嘘もつきたくなんだろ。だって自分が一言『狼がきた』って言えば、大人は来てくれるんだ。パパもママも皆。いつもは忙しいって構ってくれない大人が、自分の一言で血相変えて飛び出してくれるんだぜ?そんなうれしいことあるかよ。
だから嘘つくんだよ。
たとえ、大人が心配してるのが、自分じゃなくて羊だって、わかってても、な。」
親友のその言葉に、ひどく胸が痛くなった。
たかが童話に、そこまで深読みするなんてばかげてる。でも、事実、そういうことだ。
いつも一人ぼっちの子供。
狼がくるかもしれないような怖い場所で、
だれかのぬくもりを、
たとえ自分に向けられたものでなくても、ほしいとおもう。
それの、なにが罪になるというのか。
まして、大人は結局、最後には彼を見捨てた。
どうせ嘘だろう、と、見捨てた。
それこそが、罪なんじゃないのか。
そう、思った。
それから、親友は何も言わなかった。僕も何もいえなかった。
それからしばらくして、あの事件がおきた。
今ならわかる。
狼少年は、彼だった。
そして、大人は、きっと僕だった。
終わりに近づくそのまえに
[終わりに近づくそのまえに 序]呼吸をするのが苦しくなるようなあの話に移る前に、すこしだけ、
他愛ない普通の中学生だったころの話をさせてほしい。
カウントダウンの、そのまえに。
[終わりに近づくそのまえに 1]ナナシマキョウスケ、というその男は、とても不可思議な存在だった。
背はそれほど低くなく、かといってそう高いわけでもない。顔のつくりはそれなりに整っていたが、学年一の美形だとか王子様なんていうほどでもなく、むしろ「面白い」とか「お調子者」の部類に入っていた。
ヘラヘラとにやけた笑みを口元に称え、いつも回りの中心でいるようで、けれど一歩遠巻きに物事を見ていた。寂しがりのようで何も必要としていない、けれど何かを探しているような男だった。
そして、僕の最初で最後の親友だった。
ナナシ、と彼を呼び始めたのは僕だった。
地味であまり目立たない、暗くは無いが明るくも無い、成績も運動も中の中、嫌われはしないがモテもしない。そんな僕と、人気者の彼がいっしょにいることにクラスメイトたちもはじめは驚いていたが、それがいつしかあたりまえになり、むしろいっしょにいないときなどは
「おまえら喧嘩でもしたの?」
と言われるほどだった。
そこに、いつしかアキヤマさんという女の子が加わるようになった。
もともとアキヤマさんは、ナナシの幼馴染だった。家が近所だったと聞いている。
アキヤマさんは、ほかの女子にくらべて格段に大人っぽかった。顔かたちはもちろんだが、おとなしいというよりはクールな性格で、でも以外と面倒見がよく、男女問わず彼女に相談事をしたりしていた。
長い黒髪と、ちょっと切れ長な目が日本人形みたいな女の子だった。
そして、僕はアキヤマさんが好きだった。
入学式で新入生代表のあいさつをしていたアキヤマさんを見たとき、全力疾走したときのように鼓動が早くなった。そんな気持ちになったのは、初めてだった。小学生の頃からコイビトがいる友人も何人かいたが、僕はそういうことにはテンで鈍かった。むしろ、恋だのなんだのよりも本を読んだり音楽を聞いたりするほうがずっと有意義で楽しいことだと思っていた。
しかし、それは大いなる勘違いだと気付いた。
運良くアキヤマさんと同じクラスになれたときは、今まで見てきたどんな推理小説の結末よりも度肝を抜かれた。まさか、こんな奇跡があっていいのかと思った。
ナナシと親しくなり、そこからアキヤマさんが話し掛けてくれるようになったときは本当にうれしかった。それをナナシに気付かれたときは、ナナシを口封じに殺そうかと真剣に思った。
なんせナナシはお調子者でよくしゃべる男だったから、すぐに噂になるに違いない、そしてナナシは僕をからかって遊ぶに違いないと思ったからだ。
しかし、ナナシはそんなやつではなかった。
からかいはするものの、ときにはさりげなく僕とアキヤマさんを二人っきりにしてくれたり、
アキヤマさんとの会話に僕を混ぜてくれたりした。
「おまえ、ほんっとに手えかかるな」
そうやって笑いながら、そしてときには怖い目にあわせて僕をおどかしながら、それでもナナシは奥手でウジウジした僕を励ましてくれていた。
そうやって、いつしか僕らは「仲良しトリオ」と呼ばれるくらいに、仲良くなっていた。
そんなころ、僕らは天体観測をすることになった。
唐突だとは思うが、実際唐突にそういう話になった。誰が言い出したのか、なんでそうなったのかは今も思い出せない。
ただ、その話が出た翌日にはもう、僕らは夜に集合することになっていた。
前置きがものすごく長くなったが、「あの」話に移るまえに、
僕らが無邪気に笑いあった、恐怖も悲しみもない頃の話を
そしてまず、今も忘れられない、楽しい夜の話を、始めようと思う。
なぜ、そんな話になったのかは今も思い出せない。
ただ、ナナシが「星が見たい」とよく言っていたのは覚えている。ナナシは星が好き
だった。というよりも、いつも決して手に入らないものばかりを欲しがっていたよう
に思う。
昔、たくさんの蛍を瓶に詰めて、最後の一匹が死に絶えるまで大事に持っていたとい
う話を聞いたことがあった。その話を聞いたときは「なんて気持ちの悪い、残酷なこ
とをするんだ」と正直思ったが、ナナシ本人は至って真剣に、
「汚い空気も踏み潰す人間もいなければ、蛍は死なないでずっと光ってると思ってた
んだ」
と言っていた。とても大人びていて、いつもみんなの先を行っていたナナシの、残酷
なまでの無邪気さを、そのとき僕は感じた。
ナナシは、蛍に永遠を感じていたのだろうか。閉じ込めておけば、誰も触れなけれ
ば、蛍は永遠に生きていると、彼は思ったのだろうか。
そしてそうじゃないとわかったから、今度は星を好きになったんだろうか。
誰も触れない、永遠に、そう少なくとも僕らの命よりはずっと長く生きていく星に、
永遠を感じていたのだろうか。
考えても限等無いが、そんなことばかり思う。
前置きが長くなったが、本題に入ろう。
僕たち三人は、どういう切欠かはもう覚えていないが、星を見に行くことにした。も
ちろん天体望遠鏡だとか星座早見なんてものは持ち合わせていなかった。ぼくらが持参したのは
せいぜい財布と時計と少量のお菓子くらいだったと思う。それさえあれば十分だった。
僕らが向かったのは、電車で15分ほど先にある町の林だった。誰もいないし、ネオンも遠いから星を見て騒ぐには最適な場所だった。今も時たまそこを通るが、そのたびにそのときのことを思い出す。
「なあ、あれがカシオペア座とかいうやつ?」
林に到着し、シートを広げて座り込むなりナナシが言った。指差した先には、三つの星が並んでいた。僕は今もその星の名前を知らない。もちろんそのときも知らなかった。
「知らないよ、アキヤマさん、わかる?」
「・・・・あたし、こないだの中間、理科42点だったんだけど」
「あ、勝った。俺37点」
自慢にならないよ、と僕が言う。そして一斉に笑い出した。とてつもなくくだらない話。でもそんなくだらない話でケラケラ笑った。
「なあ、名前なんか知らなくてもさ、綺麗ならよくね?」
「ナナシが聞いたくせに」
「藤野、怒るだけ無駄だって。そういうのは柳谷に聞かないと」
「ヤナギは理科オタクだからな。そういやこないだあいつ、無線でさ・・・」
星はどこへやら、話題はクラスメイトや先生、過去の楽しかったできごとに変わっていた。
僕がハードル走で校内記録をだした話、ナナシが先輩に告白されたときの話、アキヤマさんが調理実習で作ったゲテモノの話、委員長の恋の行方、そんな話をひたすらしていた。
そのとき不意に、進路の話になった。
といっても、どこの高校に行くとか、そんな現実味のある話ではなく「将来のゆめ」を思春期のノリに任せて話しただけだった。
「あたしは、お父さんの店で修行して、パティシェになるよ。あんたたちのウエディングケーキはあたしが作ってあげるからね」
アキヤマさんは笑った。僕も控えめながら、作業療法士になりたいと話した。そのためにはたくさん勉強しなきゃいけないから大変だと話すと、アキヤマさんもナナシも目を細めて笑ってくれた。無言の「がんばれ」だったんだと思う。
そして、ナナシの番が巡ってきた。
「俺は・・・・」
しかし、そこから一向にナナシは言葉を紡がなかった。さっきまで見てもいなかった星空を眺め困ったように笑っている。
どうしたの。と声を掛けようかとおもったとき、
ナナシは言った。
「俺は、これから先の自分が想像できない。どんな自分になって、誰とどうやって生きていくのかなんて、考えてない、でも、
来年も、再来年も、できればいつか死ぬ日まで
おまえらとこうやって、笑って星でも見れてたらいいなあって思うよ。」
その言葉は、すくなくとも僕にとっては、どんな言葉よりも胸にくるものだった。
アキヤマさんも、照れくさそうに笑っていた。言った当の本人は珍しく顔を赤らめて「らしくねえな」と呟いていた。
僕もなんとなく恥ずかしくなり、否それどころかすこし目が潤んでしまい、それを二人に見られたくなくて、空を見上げた。
きれいだ、と素直に思った。
星座の名前なんて知らない。前回の中間テストで理科は51点だった。宇宙の原理だとかガリレオガリレイがどうとかアインシュタインが何だとか、そんなことはどうでもいい。
ただ、できることなら、僕も
いつか死んでしまうときまで、こうしてみんなときれいな星を見て、くだらない思い出話でもしながら、笑っていれたらいいなと思った。
それが永遠に叶わなくなるなんて、このときが、最初で最後になるなんて
考えてもいなかったから。
ねえナナシ、そうだろう。未来が必ずあるってさ、僕らは壊れやしないってさ、思ってたよね。
きみもそう思ってたって、思わせてよ。
きみはきづいていたのだろうか。ぼくらの行く先に。
独白2
電車に揺られて数十分。
窓から見える景色は少しずつ、見慣れた街から知らない景色に変わっていく。
いつしか、目的地に到着する。
いつかの彼の過ごした、僕が知らない街。
駅から降りたところに、見慣れた車が停っていた。
その傍らで煙草を吸いながら遠いところを見つめている男の人がひとりでいる。
「レイジさん、お待たせしました」
声を掛けると、振り向いて笑う。
血の繋がりは伊達じゃなく、やはりあいつとこのひとはよく似てる。
どこか寂しげな微笑も、遠くを見るような目も。
しかし、いくら似ていてもこのひとはあいつではない。
肌はもう少しあいつのほうが白かった。
髪はもう少しあいつのほうが長かった。
背はもうすこし低くて、声はもうすこし枯れていた。
あいつは髭を生やさなかったし、白い服ばっか着てたし、煙草はマイルドセブンじゃなくてアークロイヤルだった。
どんなにところどころが似ていても
このひとはあいつじゃない。
あいつは、もう
「晴海くん?乗らないの?」
「あ、いえ、すみません」
謝らなくていいよ、と笑う。
このひとはいつも笑う。
笑わないでください。
あいつによく似た顔で、
あいつをなくしたぼくのまえで、
あいつを見捨てたぼくのまえで。
笑わないでください。
許されていいんだ、と
勘違いしてしまうから。
「それ、何?」
カーオーディオから流れる歌を口ずさみながらハンドルを動かすレイジさんが、僕の手元の包みを顎で差して聞いた。
「本です」
「本?」
「…誕生日の」
ああ、とレイジさんが頷いた。
そして、感情のない声で言った。
「…いつも悪いね。」
「…いえ」
悪いのは、
罪人は僕だ。
わかってるでしょうレイジさん、
僕があいつを見捨てたりしなければ
別の未来があったんです。
ごめんなさい。
ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい
ご め ん な さ い
何度となく、頭の中に浮かぶ言葉。
消えることのない罪悪感。
ごめんなさいレイジさん、
ごめんなさいナナシ、
ごめんなさい、
「晴海君?真っ青だけど」
不意にレイジさんが言葉を発した。
「…なんでも、ないです」
「そう?………あ」
訝しげに僕を見やるレイジさんが、言葉を切った。
ちょうど、ある曲が流れたからだ。
「太陽…」
あいつが好きだと書き残した、歌だった。
「…いい歌だね」
「…そうですね」
『君のライトが照らしてくれた。
温かくて寒気がした。
光の向こうの君の姿が
永遠に見えなくなってしまった。』
ねえナナシ。
そんな歌詞を持つ歌を
君はどんな気持ちで聞いていたの。
そんなことばかりを、ひたすら思った。
終わりへの秒読
[終わりへの秒読 0]変わり始めたのはいつだっただろう。
終わりを予感したのはいつのことだったのだろう。考えても仕方ないことを考えながら、あのころを思い出す。
外を見れば大粒の雨。
ああ、そうだ。と自分に頷く。
最後の年の冬の、ちょうど今日のような雨の日だった。
白い息も消え失せる土砂降りの雨の日。横殴りの雨に傘も役に立たなくて、ずぶ濡れになりながら家路についたあの日だ。
僕が、変わり始めた君との先に、終わりしかないのだと微かに気付いたのは。
[終わりへの秒読 1]中学生最後の年の冬のその日。
普段滅多に学校を休まない親友が、珍しく休んでいた。
いつもヘラヘラ笑いながら落書きだらけのノートを広げているナナシ、その姿のない机はひどくおおきく見えた。
風邪でもひいたのだろうか、とアキヤマさんに聞いてみても、
「あたしは何も聞いてないよ。藤野こそなにか知らないの?」
と逆に聞き返される。それならば、とHRの為に教室に入ってきた担任に同じことを尋ねるが、やはり知らないという答えしかかえって来なかった。
それもまた不思議に思った。
家庭の事情からひとりで暮らしているナナシは、休むときには必ず僕かアキヤマさんに伝達を頼むか、自分で学校に連絡を入れていた。
無断欠席など、一度もなかったのに。
そう思うと、いよいよなにかあったのではないかと不安になるが、それを理由に早退などできはしないし、嘘が下手な僕は仮病を使ってもすぐにバレてしまうだろうことはわかっていたので、どうすることもできなかった。
また、慌てて駆け付けて本人がケロリとしていたら死ぬほど恥ずかしい。
そうしてたくさんの言い訳を身に着けて、不安を隠しながら僕は授業を受け続けた。しかし、不安というのはそう簡単に隠せるものではない。
早く終わってくれないかな、ナナシが心配なんだ。あいつは自分を大事にしないとこがあるから、もしかしたらご飯を食べてなくて倒れてんのかもしれない。いや、もしかしたら高熱で連絡もできなくて…
と、嫌な考えばかりが巡った。
先生の言葉やクラスメイトたちの声はまさに右から左に流れていく。ようやく全ての授業が終わったとき、どのノートもほとんど真っ白だったのに気付いて少し青くなった。
やけに長い半日が終わり、荷物を鞄に詰め込み始めているとアキヤマさんが声を掛けてきた。
「あいつのとこ、行くの?」
あのアキヤマさんとすら喋るのももどかしく、手を動かしながら頷く。
「でも、家には『あのひと』がいるよ」
ぴたりと自分の手が止まるのを、僕は他人の動作を眺めるように見ていた。
そうだった。あいつの家には、本来いるはずのないひとがいるんだった。本音を言えば二度と行きたくないと思っていた。だからスッカリ忘れていた。
思い出した途端に、不安より恐怖が勝り始めた。
「…取り敢えず、電話だけでもしないと」
「…そうだね。」
アキヤマさんはそれ以上なにも言わなかった。
それから僕はナナシの家ではなく、通学路にある公衆電話を目指して走った。
今日は生憎の雨だが、傘を差すこともせずびしょ濡れになりながら走った。
今にして思うと、なにがそんなに不安だったのかわからない。
たしかに滅多に休まない、それも無断欠席などしたことのないナナシが無断欠席してるのだから、多少心配になるのはわかる。でも、わざわざずぶ濡れになりながら走り回ってまで連絡を取ろうとするなんて、異常としか思えない。
連絡なんて、べつに帰宅してから取るのでも良かったはずなのに。何故かあの時僕はなるたけ早くナナシの安否を知らなくてはいけないと思った。
自分がナナシという親友に依存気味なのは今もあの時も自覚していたけど、それにしてもそのときの僕はおかしかった。
無意識に気付いていたのだろうか。
ナナシが僕とは違う世界に行ってしまうだろうと。
銀杏並木の道を抜けて、地下鉄の駅を曲がり、その次の角にある煙草屋の公衆電話に飛び付き、頭に刻み込まれているナナシの家の電話番号に電話を掛ける。
2回、3回、とコール音だけが響き、7回目に留守番電話になった。
「はい、七島です。ただいま留守に…」
ゾワリ、と肌が泡立つのがわかった。
それは、ナナシの声ではなく、機械の声でもなく、
ナナシのお母さんの声だった。
いつかのあの日、「ありがとう」と僕らに囁いた死者の声と間違なく同じだった。
もちろん、留守電は残せなかった。
仕方なく公衆電話を後にした。しかし、なんとなく真直ぐ帰る気になれなかった僕はまたなんとなく公園に寄って行こうと考え家とは真逆の方向に歩いた。
あたりはすっかり暗くなっていた。
雨に濡れながら歩く僕のような物好きはそうそうおらず、誰ともすれ違うことのないまま僕は目当ての公園についた。
大きな樹があるその公園は、僕がナナシにアキヤマさんへの想いや家族のこと、将来の夢なんかを語るときにいつも訪れる公園だった。
今はもう樹は切り倒され、面影もないけれど、そのときの僕にはとても大切な、心が落ち着く場所だった。
そして、中に入りブランコに腰掛けようとしたとき。
ザク ザク ザク
と、地面を掘るような音が聞こえた。
音のした方向を見てみると、
「ナナシ…?」
かの親友は、そこにいた。
あの大樹の下に。
公園に入ったときは、遠目だったし薄暗かったので見えなかったが
それは間違なくナナシだった。
全身ずぶ濡れで、僕と同じく傘もささずに真冬の寒空の下で、白いカッターシャツとGパンを泥だらけにして、大きなスコップ
でザクザクと地面を掘っていた。
「ナナシ!何してんだよ!」
わりと離れた場所にいるナナシに聞こえるようにと大声をあげたが、車と雨の音でそれは書き消されたらしく、ナナシは振りむきもしなかった。
ただただ、一心不乱にスコップを動かしている。
なんだか怖くなって、ぬかるみも気にせずナナシのもとへ走った。
「ナナシ!ねえ!ナナシ!」
雨と霧で視界がぼやける。不意に足がもつれて、前のめりに転んだ。
痛みにうめきながら顔をあげると、
「ハル?大丈夫?」
ナナシが同じく泥だらけの手を差し延べていた。
「いたいよ…馬鹿」
俺のせいじゃねーじゃん、と相変わらずのヘラヘラ顔で笑うナナシにカチンときた僕は、あらんかぎりの大声でナナシに怒鳴った。
「馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿!!!なんで無断欠席とかしてんだよ!心配するだろ!ちょっとは僕のことも考えて行動しろよ!こっちはもしかしたらナナシが倒れてるかもなんて考えてロクに授業聞けなかったんだぞ!ノート真っ白だよ!これで成績下がったらナナシのせいだからな!!!」
「はいはい。俺が悪かったです。ゴメンねハル」
子どもをあやすような口調と、崩れることのない笑顔に僕はさらに逆上した。
そして、いちばん聞きたかったことを口にした。
「大体なんでこんなとこにいるんだよ!」
-…聞かなければ良かったと、すぐさま思った。
ナナシの笑顔が、泣き出しそうな
それでいてさもおかしそうな、歪んだ笑顔に変わったから。
「な、なし、」
「あのねハル聞いて俺ね?つくりものをしてたんだけどねうん頑張って作ったんだよ材料あつめも大変だったんだよ?」
ナナシはなにも見ていない目を僕に向けて異常な早口でまくし立てた。
「ほんとにいっしょうけんめいいっしょうけんめい作ったんだよ頑張ったよ死ぬほど頑張ってがんばったんだよ俺すごいでしょえらいでしょいいこでしょ褒めてよハルあはははでもね」
唐突に言葉を切った。
「失敗しちゃったから、ここに埋めたんだよ。もう二度と見たくないからね?こんな失敗作」
ナナシはスコップで地面を差した。
僕は悲鳴をあげそうになった。
地面が、ウネウネと動いていたから。
まるで、今にも何かが中から這出してやろうとしているかのように。
「あ、な、ナナシそれ」
「あ…まだ動いてる」
だめだなあ、と笑うと、ナナシは
ザ ク ッ
スコップを、勢いよく振り下ろした。
グチャリ、と嫌な音がした。
泥の音でも、地面の音でもない、なにかやわらかいものが潰れる音に聞こえた。
「だめだなあ、死んでって言ったのに」
ナナシはスコップを引き抜くと、また振り下ろした。
「ナナシ、やめて、やめ」
「失敗失敗失敗失敗失敗失敗失敗失敗失敗失敗失敗失敗失敗失敗作のくせに失敗作のくせに失敗失敗失敗」
「ナナシ…っ!」
ブツブツと言葉を吐きながらスコップをひたすら振り下ろすナナシに、僕はただひたすら怯えた。その背中にすがりついて、やめてくれと叫んだ。
ナナシは何がしたいのか、なにをしてるのか全くわからなかった。
ただただ、怖かった。このままじゃ、どこか遠くに行ってしまうような気がした。
どうしちゃったんだよナナシ。
何してんだよ。やめてよ。元に戻ってよ。
僕は叫んだ。けれどナナシは、やめなかった。
いつもなら、僕が泣いてやめてくれと頼めばやめてくれたのに。
もう僕の声は届いていなかった。
彼は絶叫しながら、なにかに絶望しながらひたすらスコップを振り下ろしていた。
我に帰ると雨は止み、ナナシはもうスコップを持っていなかった。
マメが潰れて血まみれになった痛々しい手で、放心した僕を抱き締めながら
何度も「ゴメン」と呟いていた。
あの夏からおかしかったのには気付いていた。
少しずつ変わっていくのを知っていた。
でも、信じてたんだ。
まだ、君はナナシだって。
僕の親友の、優しくてお調子もので、いつもヘラヘラ笑ってる、ナナシなんだって。
信じてたのに。
「大丈夫だよ」
と彼の背中を叩きながら、
僕は深く静かに絶望していた。
カウントダウンが、始まった。

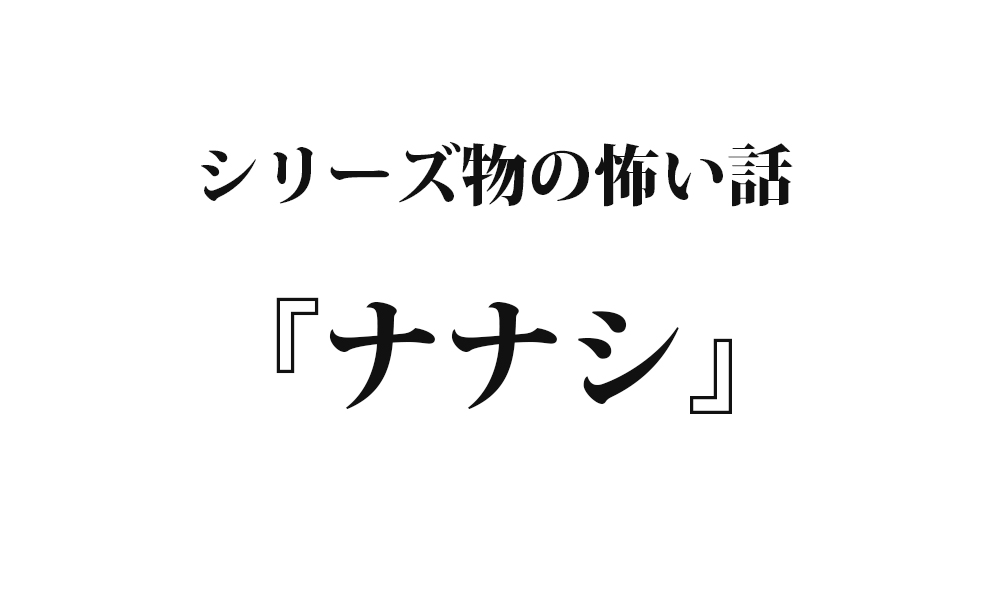

コメント