藍物語シリーズ【19】
『邂逅』
上
「今日、昼前に『上』から連絡が有ったわ。
紫が受けた依頼の件、どんな経緯で持ち込まれたのか判明したみたい。
やっぱり、分家の術者が関わってた。本家に対して特に強い敵対意識を持つ術者たち。
Lの件、対策班の働きでかなり人数は減った筈なんだけど、まだ力が残ってたのね。
まずはその説明を聞いて貰ってから、この件について依頼したい仕事があるって。」
深夜のリビングに、すうっと冷たい風が吹いたような気がした。とうとう来た、この時が。
紫さんと炎さんの事件、経緯が解明されれば、後の対応が必要になるのは予想出来た。
そして事件の規模と深刻さから考えて、事件に分家の術者たちが関わっていることも。
「Sさん、その仕事、私が受けます。」 姫は真っ直ぐにSさんを見つめた。
紫さんと姫の関係を考えれば、姫がこの件に関わりたいという思う気持ちは理解出来る。
Sさんは窓の外を眺めて小さく溜息をついた。
「そうね。Lはきっとそう言うと、思ってたわ。
それに、この仕事、『上』からは是非LとR君に受けて欲しいと指名されてるの。
R君、どう?Lと一緒にこの仕事、受けてもらえる?」
俺の気持ち、というより姫の気持ち。姫が受けるというなら俺もそれで決定。
第一、この仕事を姫1人に任せる訳にはいかない。むしろ、望むところだ。
それに、分家の動きが分からない現状では、
この仕事をしている間、翠と藍を託すとしたらSさんしかいない。
いくらこのお屋敷でも、『あれ』のような存在に対して結界の役割を果たすかどうか。
一番強い力で護るのでなければ、もしもの時に悔いが残る。
一番強い力。それは姫でも、当然俺でもなく、Sさん。それしかない。
「もちろんです。その間、翠と藍を宜しくお願いします。」
「大丈夫、翠と藍は任せて。」
「紫の受けた依頼、切っ掛けはあるTV局に持ち込まれた映像でした。
その映像が持ち込まれた部署のプロデューサーが一族の者だったので、
その映像が『上』に渡った訳です。勿論、一族の者がいる事を事前に調べた上で
そのTV局に映像を持ち込んだんでしょうね。見事に騙されました。大失態です。」
遍さんは苦虫を噛み潰したような表情で言葉を切り、窓の外を見つめた。
中庭に面した窓から爽やかな風が吹き込んでくる。
当主様の館、スズキの調査の件で相談した時と同じ小さな部屋。
恐らくこの部屋は、遍さんの執務室なのだろう。
部屋に満ちた重い沈黙を破り、姫が口を開いた。
「一体どういう口実で、その映像をTV局に持ち込んだんでしょうか?」
「鑑定のためです。その映像が本物かどうか?と。
話を進める前に、LさまとRさんにも件の映像を見て頂きましょう。」
遍さんはテーブルの上にあった封筒の中から小さなディスクを取り出した。DVD?
壁の大きなプラズマディスプレイ、その下に設置された機器にディスクをセットする。
数秒後、その映像が再生された。
画面の下半分はテーブル、その向こう側に座っている人物。
恐らく男性だ。灰色っぽい着物を着て、胸から下だけが見えている。
「私の力が見たい。つまり、そういうことですね?」 「はい、是非見せて頂きたいです。」
「良いでしょう。あなたのような信者に脱会されると一大事だ。」
着物の人物がテーブルの下から白い紙を取り出した。テーブルの上に置く、そして。
右手に持っている鋏、この形には見覚えがある。
付喪神の一件でSさんが引き取ったものと同じ形、術者が代や護符を切り出すための鋏だ。
着物の人物は器用に鋏を使い、人型を切り出してゆく。二枚、三枚、四枚。
そして蝶を二片、大きさはモンシロチョウほど。Sさんが切り出すものよりもかなり小さい。
「では、御覧に入れましょう。手品でないかどうか、良く見ていて下さい。」
着物の人物が左手で人型を一枚取り、それを右掌に置いた...これは。
人型が掌の上でゆらゆらと動いている。まるで踊っているかのように。
右手をテーブルに近づけると、人型は掌からテーブルの上に移って踊り続けた。
着物の人物は次々に掌で人型を踊らせ、テーブルの上に移していく。
次に紙の蝶を左掌に乗せた。投げ上げる、しかし蝶は落ちてこない。
おそらく撮影者のものだろう。深く息を吐くような、感嘆の声。
「如何ですか?ビデオにも映っているはず、手品などではありませんよ。」
確かに、映像として残っている訳だから、幻視を見せられている訳ではない。
「はい、驚きました。確かに手品などではありませんね。」
撮影者と思われる男性の声が聞こえたあと、画面を白い蝶がひらひらと横切る。
その直後、唐突に映像は途切れた。
「この映像には興味深い点、というか、見逃せない点が2つあります。」
「あの鋏、ですか?あれは、術者が使うものですよね?」
「Rさんもこの鋏をご存じでしたか。確かに鋏も珍しいのですが...此処です。」
遍さんは巻き戻していた映像をコマ送りにし、人型が大写しになった場面で一時停止した。
「これは、分家の術者が作る人型です。」 姫の声は少し緊張していた。
「その通り。つまり着物の人物は分家の術者。そしてもう1つ。Rさん、気付きましたか?」
「いいえ、全然。」 あの鋏と人型の特徴、それ以外にも何か。
「術者の薬指ですね?左手の薬指。」
「さすがにLさま。『上』でもこれが一番の問題になりました。」
映像がスロー再生される。術者の左手がもう一枚の人型を取った場面。
何故、気付かなかった?
人物の左手、薬指。第2関節から先が紫色に変色している。
壊死しかかっているようにも見えるが、その動きには特に異状がない。
「これは邪な契約の印。この薬指から力が流れ込みます。契約した邪悪な存在からの力。
分家の術者、そして邪な契約の印。当然放っておく訳にはいきません。
『上』はこの映像を持ち込んだ人物に連絡を取りました。詳しい話を聞くために。その人物は、
『ある新興宗教に入信しているが脱会したい。しかし脱会する話をすると遠回しに脅される。
教祖の力が本物なら怖ろしいから脱会の手助けをして欲しい。』そう、話したそうです。」
「それが、紫さんが受けた依頼なんですね?」
「そうです。Lさまの一件で、『対策班』は分家の術者を2人殺害しました。
分家の中でも、本家に対する敵対意識が特に強く、過激な思想を持つ一派の術者です。
Lさまの件でその一派は優秀な術者を失い、弱体化した筈でした。
しかし、邪な契約を使って術者の力を強化しているのなら、
何かしらの計画を立てているということ。当然何としてもその計画を知らねばならない。
其処に、つけこまれた訳です。まさか本家の術者を呼び寄せるための芝居だったとは。」
遍さんは外した眼鏡をハンカチで拭った。心を静めているのだろう。
俺の心も乱れていた。遠く、辛い記憶。 『あの人』の声、握りしめた手の温もり。
「殺害した2人の術者の内1人がKさん、なんですね?」
姫の中に仕込まれていた術を解き、俺の腕の中で息を引き取った『あの人』。
理屈では分かっている。あの時はそうするしかなかった。姫のために、一族のために。
しかし、『上』がKを殺したことに対して、俺の心の中からわだかまりが消えたことはない。
「いいえ、対策班はKを殺していません。
もちろん『抵抗するなら殺害せよ』という指示は出ていましたが。」
『上』はKを殺していない。それが本当なら、一体誰が?
「あの日、あるビルに対策班が踏み込んで、交戦の末、分家の術者を2人殺害しました。
その後、奥の小部屋でKの遺体を発見したんです。
対策班の指揮を取ったのは炎ですから、報告の内容は正確だと思いますよ。」
遍さんは立ち上がり、部屋の隅にある保管庫から資料の束を取って戻ってきた。
「これが炎の報告書。それと...これです。」
緑色の封筒から取り出した数枚の写真。それを手渡され、俺は思わず息を呑んだ。
透き通るような白い肌、形の良い乳房。そして乳房のすぐ下をえぐる、深く長い傷。
写真に写っていたのは左胸の部分だけだったが、間違いない。『あの人』だ。
その肌に触れた感触が右掌に蘇り、同時に怒りに似た激しい感情が湧き上がる。
『あの人』は、死後、その裸身を人目に晒さねばならなかったのか。どうして、こんな。
思わずその写真をテーブルに伏せた。誰にも、その姿を見せたくなかった。
姫がそっと左手を俺の右手に重ねた。その手に力がこもる。
「心中お察しします。Kが息を引き取った時の状況はSさまから聞いていますから。
しかし、検死の重要性はRさんにも理解してもらえると思います。
また、『上』としても彼女の遺体には出来る限りの礼を尽くしました。
検死をし、遺体を清めたのは女性の術者たちです。
その後、彼女の遺体は聖域内の墓地に、それは丁重に葬られました。
Lさまに掛けられていた術を解いた功労者、偉大な術者ですからね。」
「聖域内の墓地、ということは。」
「はい。当主さまが自らKの叙勲と名誉の回復を宣言なさいました。
ですから我々にとって彼女は既に本家の人間です。分家の人間ではありません。」
翠が生まれた日、俺とSさんの前に現れたKは穏やかな笑顔を浮かべていた。
叙勲を受け、本家への復帰が認められた事は、少しでもその魂の慰めになっていただろうか。
「『上』でないなら、Kを殺したのは分家の術者ということになりますね?」
「はい。それ以外には考えられません。」
「しかし、Kさんほどの力を持った術者がそんな簡単に。」
「結界の影響を受けにくい武器もあると聞いています。それに。」
遍さんは言葉を切り、気遣うような視線を俺に向けた。
「KはLさまの術を解いた直後に襲われたんでしょう。だから対応が遅れた。
恐らく、Lさまに仕込まれていた術の代を持ち出した事に気付かれた。それで。」
頭を思い切り、殴られたような気がした。 視界が白く霞む。
そうだったのか。 なのに、一言も言わなかった。 『あの人』は、それを、ただの一言も。
俺は彼女に『姫の術を解いてくれ。』と頼んだ。 『君なら姫の辛さが分かる筈だ。』と。
彼女は何の見返りも求めずにその望みを叶え、そして。これでは俺が彼女を。
いや、違う。もし彼女が術を解いてくれなければ姫は助からなかった。
もちろん術を解かずにいたら、分家の術者に復讐されることは無かっただろう。
しかし、それでは彼女は対策班と...しかも、その憎しみは解けないまま『不幸の輪廻』に。
『ちゃんと、あの娘を守って、愛して、あげて。』 あの時、彼女は笑顔でそう言った。
姫を助ける事で、自分には許されなかった女性としての生き方や夢を、姫に託したのだ。
そして、Sさんは姫を助けた『あの人』の恩に報いるために、『禁呪の中の禁呪』を使った。
記憶は完全に封印されても、俺の娘として彼女は生きている。翠、『あの人』の生まれ変わり。
さればよし。翠を溺愛し、力の全てを注いで守り育てることこそが、俺の贖罪だ。
そしてそのためには俺たち家族が、そしてこの一族がしっかりと存続し続けなければならない。
涙を拭い、深く息を吸った。
「大事な事を教えて頂き、感謝します。しかし、もう、昔話は止めましょう。
今、僕とLさんに出来ること。今回の件に関する依頼の内容を、教えて下さい。」
中
「当主様の強い御意向もあり、分家との争いを完全に解決するための
計画が進められています。今回依頼する仕事は、その計画の一部。
ですからもう少し、昔話を聞いて頂かなければなりません。
分家との争い、それがどのように生じ、どんな経過を辿ってきたのかを。ちょっと失礼。」
遍さんは立ち上がり、短い電話をかけた。機器から取り出したディスクを封筒に入れ、
他の書類と共に保管庫に戻している途中でノックの音がした。
「どうぞ。」 「失礼致します。」
ドアが開き、少女が1人部屋に入ってきた。
手にしたお盆には涼しげなガラスのポット。それに、氷の入った背の高いグラスが3つ。
テーブルに置いたグラスに薄い黄緑色の飲み物を注ぎ、ポットを置いて少女は出て行った。
その所作は美しく洗練されていたが、俺が裁許を受けた日に見た少女ではない。
「実は緊張していて、飲み物を手配するのを忘れていました。申し訳ありません。どうぞ。」
言い終わると遍さんはグラスの飲み物を一気に飲んだ。深く息を吐く。
姫がポットを取り、遍さんのグラスに飲み物を注いだ。 「これは済みません。」
俺も一口、飲み物を口に含んだ。微かな苦み、良い香り。お茶の一種、なのだろうか。
「Rさん、我々が分家と袂を分かつ事になった原因はご存じですか?」
「はい。Sさんからは、術者を作り出す外法と関わっていると聞きました。」
「その通りです。しかしそれは問題の一面に過ぎません。
この問題の真相は一族のあり方をめぐる内紛。主導権争いです。
分家は元々とても古い、有力な家系。
その長はとても優秀な術者であり、『上』のメンバーでもありました。
しかしその男は、一族の意志決定に術者以外の人間が関わることに不満を持っていたのです。
当然ですが、先の大戦では一族もその影響を受けました。
戦時中の混乱に乗じて、その男は一族の主導権を握るために、
あるいは一族から離脱する事を目指して、行動を起こした訳です。
遍さんはまた一口飲み物を飲んだ。氷の音が涼しく響く。
「私たちの一族が約千年に渡って存続出来たのは、早い段階で当主の世襲制を廃止し、
各家系の代表者と優れた術者で構成される『上』の集団指導体制を確立出来たからです。
それによって術者と術者でない者が互いを信頼し協力し合う関係が構築されました。
先の大戦に伴う混乱と世の中の変化は、私たちには想像も出来ない程だったはず。
一族がそれらに上手く対応出来たのも、互いの信頼と協力があったからです。
一族においてさえ、術者はあくまで少数派。その意見だけが全体の意志を決めるとすれば、
術者でない者はやがて一族から離脱していくでしょう。一族の人数が減少すれば、それは
力を持って生まれてくる子の減少に直結します。それは結局、術者の減少という結果を招く。
それでは一族が世の中の変化に対応し、力を維持することは出来ません。」
一族の人数が減少すれば、力を持って生まれてくる子も減少する。それは必然。
ただし、外法を使えば、生まれてくる子に任意の力を与えることが出来るとSさんは言った。
「もちろん外法を使えば、術者でない者たちが離脱しても必要な術者を作り出せます。
言い換えれば、術者至上主義は外法を使うことを前提にしなければ成立しません。
しかし、事もあろうに『外法を使って術者を作り出す』など。
それは、一族全体として到底受け入れられる考え方ではありませんでした。」
「何故、その家系を放逐したんでしょうね。別の方法も有ったと思いますが。」
「もちろん『その家系を滅すべし』という意見も有ったと聞いています。
しかし当時、当主様も『上』も、その意見を採りませんでした。
大戦中、更に一族の内紛となればこちらにも相当な被害が出るのは間違いありません。
それに、遠からずその考え方は破綻し、分家自体が瓦解すると予想したからです。」
「必要なだけ術者を作り出せるなら、分家と本家の力関係が逆転するのではありませんか?」
「外法には代償が必要です。生まれてくる子に、術者になれる程の力を与えるなら、
その代償は間違いなく代の命。力を持たない人間の命と引き替えに力を持つ人間を作り出す。
そんな外法が分家の全員に支持される、支持され続ける筈がありません。
その点について、最初から分家内部の意見は統一出来ていなかったはずです。
だから当時の当主様と『上』は、分家内の穏健派と契約を結びました。
『分家自身の力で外法を使う者たちを滅することが出来たなら、いつでも復帰を認める。』と。
そして『相互不干渉と敵対行為の禁止』を条件に、その家系の離脱が認められました。
こうして成立したのがいわゆる分家。その後、本家と分家の関係は絶たれました。」
遍さんは一旦言葉を切り、飲み物を一口飲んだ。
「当主様と『上』が予想した通り、分家はゆっくりと瓦解の道を辿りました。
実際に外法を使う段階で反対する者が多く、術者を作り出す計画が頓挫したのか、
外法を使って生み出された術者がいたかどうかは確認されていません。
さらに術者の中からも分家を離れるものが出て、過激派の影響力は低下しました。
本家に保護を求めて来る者、術との関係を断った者、
分家を離れた者たちの末路はさまざまです。」
母から聞いた話の通りなら、俺の曾祖母は分家を離れた術者の1人ということになる。
「僕の曾祖母は分家の出身だと聞きました。外法に反対して分家を離れたのでしょうか?」
「『上』の調査によると、その女性が分家を離れたのは、分家が一族から離脱した直後です。
その時期から考えて、外法を使うという方針に反対して離脱したのは間違いないと思います。
かなり聡明な方だったのでしょうね。もっと後であれば、たとえ分家が離脱を許しても、
過激派は執拗にその女性の監視を続けたでしょう。Kの両親がずっと監視されていたように。」
首筋の毛が逆立つ。ではKの拉致は、そして、もしかしたら俺も。
「Kが拉致されたのは19年前、Kは2歳だった筈です。
その頃、既に過激派は分家の中でも異端として忌避される存在になっていました。
長が代替わりし、分家全体としては一族への復帰を願う意見が大勢を占めていましたから。
しかしその分、孤立した過激派の思想はより先鋭化してしまったということでしょうね。
力を持つ子供たちの拉致はその表れ、Kはその被害者という訳です。
Kが拉致された際、抵抗した両親が殺されました。
しかしKにその記憶があったかどうかは分かりません。」
その記憶があったなら、Kは術者として分家に協力しただろうか?
いや、記憶がなくとも、薄々は自分の境遇に感付いていたはずだ。
だからこそ姫の件で俺に見せた夢が『小さな女の子が拉致される場面』だったのではないか。
俺がその女の子は姫でなくKだと言った時、彼女の体から立ち上った青い炎。凄まじい熱量。
心に秘めていた疑問を不意に突かれて、だからあれ程の怒りが。
「その時、何故『上』はKを取り戻そうとしなかったのでしょうか?」
「あくまで分家の内紛。それなのにこちらが先に手を出す訳にはいきません。
『血縁相克』の大罪では、先に手を出した者が、はるかに重い報いを受けます。
しかも、本家が手を出せば反撃の口実を与えることになり、一族全体の争いに発展する。
Kの両親は、分家を離脱したあと、本家の保護を求めるべきでした。
当時も、そして現在も、本家へ保護を求めて来る者には、相応の対応がなされています。
もちろん外法を使わないという宣誓は必要ですが、それ以外の条件や罰則はありません。
場合によっては、一族への復帰という特例が認められることもありました。
このような対応がなされたのには、先代の当主様の御意向が強かったと聞いています。
『実際に外法を使った者以外に、罰を科す謂われは無い。』、そう仰って『上』を説得されたと。」
「特例として復帰が認められ、その後一族でも重要な地位についた例もあります。
Lさまの母上もそうでした。亡くなるまで、彼女は『上』の顧問として活動していました。」
姫の母親が...つまり、姫は分家の。
K・姫・俺、3人は同じく分家の血に、連なっていることになる。
姫に近い親戚がいるという話を聞かないのは、このあたりの事情によるのだろう。
「私の祖父母が、私の母を先代の当主様に託した。そう、Sさんから聞きました。
『これ程の力を持つ子を、あの者たちに渡す訳にはいかないから。』と。」
「ただ、過激派にすれば、Lさまの母上は『元々自分たちのもの』、そう考えるでしょうね。
彼女が分家に残って術者になっていれば、過激派の運命は変わったかも知れない訳ですし。
だからLさまが生まれ、母上の力の一部を受け継いだと分かった時、Lさまを拉致した。
母上がご存命なら、それは絶対に不可能でしたが...」
遍さんは眼鏡を外し、レンズをハンカチで拭った。
「Lさま、宜しいですか。もう少し立ち入った話を続けても?」
「はい。母のことも、父のことも、特に隠しておく必要の無いことです。」
「もちろんLさまと父上には護衛の術者が付いていました。
しかし、そのお住まいは聖域の中ではありませんでしたし、そして何よりも。」
遍さんはもう一度眼鏡をかけた。レンズの向こう、その眼は鋭く光っている。
「先代の当主様も、『上』も、未だ信じていたのです。『相互不干渉と敵対行為の禁止』を。
しかし、19年前のある日。分家の術者が数人、Lさまと父上のお住まいを急襲しました。
Lさまの父上と護衛の術者を殺し、Lさまを拉致したんです。
その事件を切っ掛けにして、一族の方針は不干渉から敵対へと変わりました。
当主様の裁可を受けた後に『上』は過激派の殲滅とLさまの奪回を決議。
対策班が過激派とそれに連なる者の動きを徹底的に監視・追跡し、Lさまの行方を追いました。
無抵抗の者は引き続き監視下に置き、抵抗する術者は躊躇無く殺害しました。
Lさまを奪回したのは半年後。
その時点で、すでに過激派の術者は残り6人になっていた筈です。
しかし、いずれもかなり強力な術者たちだったため、全員を殺害することは出来ず、
その後、残った術者たちの足取りは途絶えました。」
「5年前、Lさんを再度拉致しようとしたのが、その。」
「そうです。あの事件で2人とK、今回の事件で依頼人を装った1人。
今も残っている過激派の術者は恐らく2人。
TV局に映像を持ち込んだ人物、そして映像に写っている人物。
今日、当主様が御影に2人の居場所の探索を命じました。
それは今日中に判明するでしょう。当然それなりの対策をしている筈ですから、
正確には『御影すら侵入出来ない結界が張られた場所』が判明する訳ですが。
そして、可能であればビデオを持ち込んだ術者を殺害する、その命も下っています。
式を使って血縁を殺害することは禁呪。しかし、この際、止むを得ないとの御判断です。」
「それ程の術者なら、探知されたことを察知して、すぐに移動するのではありませんか?」
実際、Kたちは頻繁に移動していたからこそ、Sさんでさえその居場所の特定に手間取った。
当然あの時も式による探索は行われていただろう。ならば今回も。
「映像に写っている術者は、おそらく今回の事件の首謀者です。
この人物は間違いなく、かなりのダメージを負っている筈。
身動き一つ出来ない状況だったとしても不思議はありません。
本来ならばその命は『あれ』との契約の代償になるはずだったのですから。」
遍さんは立ち上がり、保管庫の中から小さな木箱を取り出した。その箱をテーブルに置く。
「さて、ようやく本題。今回の依頼の内容です。映像に写っている術者を、
御二人に処理して頂きたい。そしてこれは、当主様の御意向でもあります。如何でしょう?」
これまで何度と無くSさんの仕事を手伝ったし、単独の仕事も幾つか経験した。
しかし、俺はこの手で人を殺したことはない。おそらくは姫も。 処理≒殺害、それを俺と姫が。
「その仕事、お受けします。」
凛とした涼しい声が部屋の空気を震わせた。姫は真っ直ぐに遍さんを見つめている。
「Rさんは如何ですか?」
「もちろんお受けします。ただ、Lさんも僕も、Sさんや炎さんのような力を持っていません。
僕たち2人で出来る仕事でしょうか?Lさんだけは絶対に。」
「御心配はごもっとも。そのために、当主様からこれをお預かりしています。」
遍さんはテーブルの上の小箱を姫の前に置き直した。
「どうぞ。Lさまならこの箱の中身が何なのか、お分かり頂ける筈です。」
何の変哲もない小さな木箱。滲み出る気配はなく、かといって結界が張られている様子もない。
姫は無造作に箱の蓋を開けた。細い指が箱の中身を取り出す。
...4つに枝分かれした細い金具が黒い玉を抱いている。玉の直径は約3cm。
金具は金色で、その中心部には2つ連なった小さな環状の金具。
姫はそれをじっと見つめたあと、右手で握り締め左胸に押し当てた。小声で何事か呟く。
微かに、気配を感じたかも知れない。それともあれは、姫の心の動きだったか。
「これは、青の宝玉ですね。号は『碧空』。」
青の宝玉? 姫の右掌の上。それはやはり黒、青い色など見えない。
姫はそれを箱に戻し、蓋を閉めた。
「使い方についてはLさま、そしてSさまの方が詳しいと思います。
御二人の力とその宝玉があれば全てが終わる、当主様はそう仰いました。」
それで当主様は俺と姫を。つまり、分家の血。
『分家自身の力で外法を使う者たちを滅することが出来たなら、いつでも復帰を認める。』
分家の復帰を認めるために、あくまで遠い約束を守る。それが、当主様の御考えなのだ。
お屋敷に戻ると、既に『上』から連絡が届いていた。御影が突き止めた場所は△県。
郊外に建設されたものの、6年前に経営が破綻し放置された老人介護施設。
長期入所に対応した設備はあるが、水や電気が止められているために
対策班の捜索対象から外れていたという。水や食料の持ち込みは容易だろうが、
電気はそうもいくまい。自家発電の設備があったとしてもまともに動くかどうか。
身動きの出来ない程のダメージを負った術者を、一体どうやって世話しているのだろう。
翌日の早朝、俺と姫はその施設に向けて出発した。車でおよそ半日の距離。
多分昼前までには到着。そこから、俺と姫の仕事が始まる。遠い約束を果たすために。
下
その施設に着いたのは11時過ぎ。道路が空いていたので、予定より少し早い。
海沿いの県道から海岸とは反対方向の細い道に入って数百m、人目に付きにくい場所。
施設の門は開いていて駐車場には大型のバンが一台停まっていた。
分家の術者が使っている車だろう。長期間放置された状態には見えない。
つまり残った分家の術者は2人とも、今この施設内にいることになる。
「Rさん、いよいよですね。」 「はい、宜しくお願いします。」
姫は微笑んで右手を差し出した。その手を左手でしっかりと握り、目を閉じる。
じいぃぃん、胸の奥が熱い。俺と姫の心の一部が重なっている。
この時のために、昨夜から2人で準備を整えて来た。
2人の意識を繋げることでお互いの力を共有する。『あの声』と『言霊』。
系統は違うが、どちらも言葉を媒とする力。組み合わせて共有するのは難しくない。
まず俺が車から降り、注意深く辺りの様子を窺う。術者の気配は感じない。結界の、中か。
助手席のドアを開け、姫も車から降りた。手を繋いだまま歩く。
姫の信頼が伝わってくる。俺の気持ちも姫に伝わっている。それがとても心地良い。
大仕事を前にして、俺たちは不思議なほど落ち着いていた。
この仕事に全力であたる。結果はどうあれ、俺たちは最後まで一緒だ。
施設の玄関前まで来た時、スロープの脇に棒のような物を見つけた。
長さは約80cm、先端にバネ仕掛けらしい鎌状の刃。刃渡りは10cmほど。
反対側の端は革巻きの握りになっている。恐らく、仕込み杖のような武器。
「Rさん、あれを。」
姫の視線を辿る。スロープを上り切った所。コンクリートの床に人型の影が焼き付いていた。
大きさから見て、かなり体格の良い男の影に見える。落ちていた武器の持ち主だとすれば。
『残り2人の内1人だ。』
低く太い声が辺りに響いた。この声と気配。あの、最強の式。御影。
『本家からの分離にあわせて、分家の長が雇い入れた術者たちの、最後の生き残り。』
「別系統の術者だと言うことですか?」
『そうだ、一族の血に連なっていないから、血縁相克にもならない。遠慮無く始末できた。
ただし、結界の中にいるのは間違いなく分家の術者。後はお前たちの仕事、心してあたれ。』
床に焼き付いていた男の影は見る間に薄れ、御影の気配も消えた。
遍さんの話の通りなら、この結界の中に御影は入れない。
何かの影に潜んで気配を消し、術者が結界から出るタイミングを待っていたのだろう。
結界の強固さから見て、かなりの力を持った術者だし、それなりの警戒もしていた筈。
なのに仕込み杖の刃を操作するだけで精一杯。文字通り一瞬の出来事だったということだ。
「残った術者はあと1人ということですね。Rさん、行きましょう。」
俺の左手を握る姫の右手に力がこもった。2人、施設の入り口に歩を進める。
自動ドアは反応しなかった。施設内の様子から見ても、おそらく自家発電装置は動いていない。
大きな自動ドアから少し離れた場所にある夜間出入り用のドア。
本来オートロックだろうが、それでは御影が始末した術者も不便だったろう。
ドアノブに手をかけて引くと、すんなりとドアは開いた。やはりオートロックに細工がしてある。
俺が先にドアをくぐり、姫が続く。問題なく結界の中に入った。
分家の血を引く者でなければ、この結界の中には入れない。
結界を張った術者は、当主様が姫を派遣するとは予想していなかったのだろう。
そして姫の他にも俺が、分家の血を引く術者がもう1人いるということも。
姫は迷うことなくロビーを抜け、先に立って非常階段に向かった。
まるで郊外のショッピングモールで買い物をする時のような、軽やかな足取り。
姫にはもう分かっている。最後の術者の居場所。
重なった意識を通して、俺にもその部屋が見えていた。3階、廊下の突き当たり。306号室。
「少し、焦げ臭いですね。」 「はい、火の気は無いみたいですが。」
その部屋のドアの前まで来ると、中の術者の気配が普通ではないことも分かった。
それは確固たる存在と言うよりも、ボンヤリとした雰囲気のような気配。
強い妄執に囚われていながら、人の形を保っていない。
生きた人間の気配がこんな風に拡散しているのを感じるのは初めてだ。
正直、不安もある。しかし、このドアを開けなければ仕事は始まらない。
1つ深呼吸をして、ドアノブに手をかける。鍵はかかっていなかった。
ドアを開けると同時に、激しい憎悪が漏れだしてきた。
かまわずドアをくぐる。始めに俺、次に姫。
黒い霧のような、靄のようなモノが部屋の奥に蟠り、視界を遮っている。
それは飛び回る無数の小さな虫。ショウジョウバエよりもずっと小さな、黒い虫の群れ。
その羽音が重なって、低い唸り声のように聞こえた。いや、これは。
『・・・すこしで、もう少しで、奴らを滅ぼすことができたのに・・・』
『・・・あの、霊剣を持った男さえ現れなければ、契約通り■◆は・・・』
『・・・の命と引き替えに、何としてもKの仇を、復讐を・・・』
部屋の奥に蟠る生きた黒い靄の中に、呪詛の声が重なり合う。凝り固まった憎悪。
姫の眼を見る。姫は優しく微笑んで、しっかりと頷いた。よし、深呼吸。
『憎い敵の術者がこの部屋に入った事にも気付かないとは呆れたな。
闇に魂を侵食され、感覚までも奪われたか。』
沈黙。
その直後、黒い靄は凝縮し、部屋の奥の様子が見えた。
窓際に置かれたベッド。その上に横たわる人物は、
焦げた布の切れ端と夥しい数のガーゼで体中を覆われていた。
わずかに見える皮膚は、まるでミイラのように乾涸らびている。
点滴や栄養補給をしている様子はない。本当に、この状態で生きているのか?
凝縮した黒い靄は、横たわる人物の胸の上でゆらゆらと蠢いている。まるで黒い炎。そして。
人物の左手、紫色に変色した薬指だけが、乾涸らびることなく元の状態を保っていた。
間違いない。この人物こそ、最後の術者だ。
『本家の術者か。私を始末しに来たのだろう。さっさとやるが良い。
ただし、私たちの憎しみは消えることなく、いつか必ず本家を滅ぼす。忘れるな。』
部屋の中に低い声が響いた。術者の胸の上、黒い炎が発する声。
姫がベッドの脇に歩み寄る。俺も姫の横に立った。
『私はL、憶えているでしょう?あなたに聞きたいことがあって、此処に来ました。』
『L。あの時の、娘か...言って見ろ、今更隠すことなど何もない。』
『本家と分家の争い、先に手を出したのは分家の方です。
なのに何故、本家を恨み、滅ぼそうとするのですか?』
姫の声は強い言霊を宿していた。その言葉はきっと男の心に届いている筈だ。
『確かに、先に手を出したのは分家。しかし、そう仕向けたのは本家だ。
当主と『上』は卑劣な分断工作で分家を弱体化させ、滅ぼそうとした。
黙って滅びる選択肢などない。私たちは生き残るために、戦うしかなかった。』
姫は目を伏せて小さく溜息をついた。
『仲間から何を吹き込まれてきたのか知らないが、本家は分断工作などしていない。
お前たちのやり方や考え方に嫌気がさして分家を離脱した者を保護しただけだ。
それも本人が希望した場合だけ。力を持たない者の命を代償にして外法を使い、
力を持つ者を生み出すなんて、そんな考えが分家の全員に支持される訳がない。
だからお前たちは分家の中でも孤立した。その左手、薬指の契約にも耐えられたなら、
お前も相当な力を持っていた筈だ。だが、その力が誰かの命を代償にして
与えられたものだとしても、お前は何も感じないのか?』
『力を持つ者を生み出すためには、それなりの犠牲は必要。当然だろう。』
『だから親を殺して子供を拉致しても良い。拉致した子供に術を仕込んで代にしても良い。
随分と手前勝手な話だな。お前、誰に育てられた?両親の記憶はあるか?
お前自身が拉致された可能性もあるぞ、『あの人』が、Kがそうだったように。』
『Kが、拉致された?出鱈目を言うな。Kを殺したのは貴様たちだろう。
酷い拷問をして代の在処を聞き出し、そのあとで殺した。そんな奴らの言うことなど』
『黙れ。』
腹の底から湧き上がる激しい怒り、しかし俺の声は自分でも驚くほど冷たかった。
『あの人を生かしたまま捕らえるほどの力を持った術者が本家にいたなら、
お前たちはとうに殲滅されていた。それに、お前はあの人の最後を誰から聞いたんだ?
そいつはあの人が拷問され、殺されるのを黙って見届けた後、対策班の手を逃がれたのか?
幾ら何でも不自然過ぎる。良く考えろ、おかしいとは思わないのか?』
『じゃあ誰がKを。それにあの術の代は、絶対に見つからない方法で隠してあったのに。』
『あの人は外法を使う非を悟り、自ら代を持ち出してLさんの術を解いたんだ。
だからそれを知った仲間に襲われた。左胸に大きな深い傷があって、酷い出血だったよ。
間違いなく刃物傷。あれ程の力を持っていた人があんな傷を負うなんて。
どんな武器が使われたのか、心当たりが有るんじゃないのか?』
ふと、施設の入り口近くに落ちていた仕込み杖を思い出した。
その先端に仕込まれた鋭利な刃。あれなら、もしかして。
『貴様こそ、あの場所にはいなかった筈だ。何故、Kの最後を知ってる?』
男の声の調子が変わっていた。
俺の心に浮かんだ映像、あの人の胸の傷と仕込み杖。
間違いない。姫の力がそれらの映像を男の心に伝えた、だから。
『死の際に、あの人がRさんに会いに来たんです。本当に凄い術でした。
あの人はRさんを心から愛していたから、最後はRさんの腕の中で...
とても穏やかで美しい死顔。自分の不幸も、自分を不幸にした人も、全てを許して。』
あの人の最後の微笑み、一筋の涙。その映像も、この男の心に伝わっているだろう。
『...私は、騙されていた、という事か。』
『いいえ、あなたを騙していたのはあなた自身です。心の隅の疑問を、敢えて無視してた。
薄々は気付いていたのに、それを認めるのが怖かったから。』
『その通り、だな。物心付いてからずっと、本家は敵だと信じていた。憎んで、戦うだけの日々。
それは間違っていないと信じることしか、本家の人間を憎むことしか、私には出来なかった。
自分には生きている意味が無いと、認めたくなかった。
そうやって自分を誤魔化し続けて、挙げ句の果てはこの有り様。
自ら動くことも、死ぬことすらも出来ぬ、生ける屍。
Kに両親がいない、その記憶すらない。それも知っていた。もしその理由を調べていれば、
Kの拉致のことも分かった筈だし、Kには別の道を用意出来たかも知れない。
だが、怖かった。Kを失いたく無かった。本当に、私は馬鹿だった。』
そうか、この男はあの人を愛していたのだ。
だからこそ、対策班があの人を拷問して惨殺したという話の嘘を見抜けなかった。
そして、結局は自らの魂と引き替えに、何の救いもない計画を進めてしまった。
本家を、滅び行く自分たちの道連れにする。それが『復讐』だと信じて。
『生きる意味は、誰かに与えられるものじゃない。自分で見つけるものだ。
本家と分家の争いを完全に終わらせるために、俺たちは此処に来た。
当主様は外法を使っていない者の罪を問わず、望むなら本家への復帰を認めると仰ってる。
外法に手を染めた者で、残ったのはお前1人。その薬指、『不幸の輪廻』との通路を
封じることが出来れば全てが終わる。そのためにはお前の力が必要だ、分かるだろう?』
男の胸の上、黒い炎は薄れ、次第にその輪郭を失いつつあった。
『長く続いた争いを終わらせ、皆が一族に復帰する役に立つのなら、
私の命にも少しは意味があったということだ。』
男の乾涸らびた顔に表情は読み取れない。しかし、確かに男は笑っていた。
『まともに話を聞いてくれてホッとしたよ。俺たちの言葉が届くかどうか、正直自信が無かった。』
『『誰に育てられた?』と聞かれた時、お前の話を聞くべきだと分かった。
私は祖父母に育てられたが、父と母の記憶は全く無いんだ。』
祖父母に育てられたのなら、拉致、とは言えないかも知れない。
しかし、恐らくこの男も、長い争いの最中に生まれ、否応なく争いに巻き込まれた被害者。
『今更記憶を辿ろうとも思わないし、罪を逃れようとも思わない。全て、私自身の犯した罪。
有り難い御言葉と御心遣いに感謝すると、当主様に伝えて欲しい。
闇に侵食され、異形に成り果てた私の命で良いの、なら、喜んで...」
部屋の中に冷気が満ちていく。この感覚、迷わず短剣を抜いた。
男の左手、薬指が小さく震えている。何かが通路を使って。
『作り出した術者も、雇い入れた術者も、遂に滅びた。』
違う、先程までの声ではない。嗄れた、呟くような声。
『我が力と知恵の限りを尽くしてなお、一族の運命を変えることは出来なんだ。
しかも、我らが血に繋がる者が幕を引くとは皮肉な事よ。これも、あの女の、描いた筋書きか。
●明が遺言、しかと当主に伝えよ。術者を軽んずれば、早晩一族の命運は尽きる。忘れるな。』
これ以上、聞く必要は無い。一刻も早く通路を封じないと『不幸の輪廻』が。
男の左手を押さえ、薬指の付け根に短剣の刃をあてた。力を込める、硬く乾いた感触。
切り離された薬指は炎に包まれ、灰も残さずに燃え尽きた。
「Rさん、少し離れて下さい。」 姫が俺の真横に立っていた。3歩下がって距離を取る。
金具に皮紐を通して胸にかけた宝玉を姫は両手で捧げ持った。額の前、右掌の上に宝玉。
『青き・・・の・・・・て恵み給え、降らせ・・・清らなる・・・・祓い・・・』
宝玉の色が透き通った深い青に変わった。ボンヤリとした光を放っている。
そして。
ポツリ。水滴が俺の肩に落ちた。部屋の中に、無数の水滴が降り注ぐ。
雨、だ。
コンクリートの天井で空から仕切られている部屋の中に、雨が、降っている。
「Rさん、濡れますよ。一旦部屋の外へ。」
姫に促されるまま、開けたままのドアを2人でくぐった。廊下には雨が降っていない。
振り向くと、部屋は不思議な明るさに満たされ、雨は勢いを増していた。
これは、まるで天泣。屋根の下に降る天気雨。
ふと見ると、男の体の厚みが半分程になっていた。
雨が降り続くにつれ、その厚みはさらに減っていく。
そして、着物の燃え残りやガーゼの色が白く変わっていくのが、遠くから見ていても判る。
どのくらい降り続いただろうか。既に床を濡らした水は部屋の外にも流れ出してきていた。
突然、姫の胸で青く輝いていた宝玉が元の黒に戻った。雨は急激に勢いを弱めていく。
「Rさん、行きましょう。」 「はい。」 もう一度部屋の中に入り、ベッドに歩み寄った。
男の体は跡形もなく消えていた。
ベッドの上に残るガーゼや着物の切れ端は漂白されたように真っ白だ。
穢れを祓い、憎しみと哀しみを清らかな水に流す。それがこの宝玉の力。
そして分家の血に繋がる俺と姫がこの役目を担ったことで、遠い約束が果たされる。
つまり、もう分家は存在しない。
「Rさん、これ。Sさんに教えて貰った通りです。」
姫の指さしたガーゼが微かに動いていた。
そっとガーゼをめくる。 奇麗な、青い金魚。これは。
『もしもその魂が完全に侵食されているなら、相手の肉体は塵一つ残さず消滅する。
でも、もし侵食されていない部分があれば、宝玉はそれを水に関わる生物に再構成するの。』
青の宝玉の力と、その使い方を教えてくれた時、Sさんは俺たちにそう言った。
不思議な雨が降った後に残されたのは、可憐な青い金魚。つまり、そういうことだ。
姫は濡れたガーゼで金魚をそっと包み、ポケットから取り出した小さなビニール袋に入れた。
「これでお終いです。車に戻りましょう。早くペットボトルに移してあげないと。」
「お屋敷に戻る前に、小さな水槽を買わなきゃいけませんね。」
数日後。俺と姫はある場所を訪ねた。こぢんまりとした日本家屋。
俺たちを迎えてくれたのは、かなり高齢の老人。その男性が何歳なのか、見当も付かない。
「良く来て下さった。この日が来るのを、それこそ一日千秋の思いで待っていたのです。」
柔らかな声。老人が淹れてくれたお茶から、良い香りが漂っていた。
「あなたは、私たちと、それからKさんにも縁のある方だと、当主様から伺ったのですが。」
「はい。あなたがRさん、そしてこちらのお嬢さんがLさんですね。
私にとってRさんは曾姪孫、LさんとKさんは曾孫ということになります。」
では、この老人は姫とあの人の曾祖父。だが俺にとっては。
「曾孫はひまごのことですね。でも曾姪孫という言葉は初めて聞きました。」
「Rさんの曾祖母は私の姉です。父の指示で、私は家の中から、姉は家の外から、
外法に手を染めた者たちを孤立させるために活動していました。ただ私たちの力が及ばず、
LさんとKさんには辛い思いをさせてしまい、本当に申し訳なく思っています。
特にKさんには何と...」 老人の目に涙が浮かんでいた。
「何故、外法を使おうという意見が通り、一族から離脱することになったのでしょうか?
それがなければ、このように長く無益な争いは避けられた筈なのに。」
姫の口調は穏やかだったが、その声から深い悲しみが伝わってくる。
この争いが姫から父親を、そして10年以上の子供らしい日常を奪った。
『何故?』という問いは、姫の心の奥底から発せられたものだったろう。
「一族からの離脱を決めたのは当時の長、私の叔父です。名は●明。」
●明、その名はあの時の。つまりあの声の主は分家を離脱させた男。
「一族の中でも一二を争う力を持った術者でしたが、偏狭な考えの男でした。
一族の意志を決める時には、術者の意見を最大限に重視すべきだと考えていましたから、
当主様とも、『上』とも意見が度々衝突し、年を取るにつれますます頑迷になりました。
また、あの男は離脱の数年前から一族以外の系統から強力な術者を呼び集め、
自分に対して反旗を翻す者が出てこないような、一種の恐怖政治の体制を築いていたのです。
取り敢えず●明の決定に従って一族を離れ、その死後に家系の方針を変えて一族に復帰する。
それが嫌なら、身一つで家系を離れ、経済的な基盤のほとんど無い状態で生きていく。
当時の私たちに残された道は、その2つだけでした。」
「では先々代の当主様と復帰の約束をしたというのは。」
「私の父です。●明の死後、父は様々な手段を講じて家系の方針を変えていきました。
長い時間がかかりましたが、外法に手を染めた者たちを孤立させることに成功しました。
本当に、あと一息という所だったんです。Kさんが拉致されたのは。」
老人は言葉を切り、深く溜息をついた。
「追い詰められれば反撃に出るかも知れない。それは予想していました。
しかしまさか同じ家系の者に手をかけて、力を持つ子を拉致するなどとは...。
Kさんの奪回を何度か試みましたが、いずれも失敗。
私たちは数人の術者を失い、大きな犠牲を払う結果になりました。
その後は同じような事が起こらぬよう、残った者たちの身を護るのが精一杯で。」
老人の言葉には、深い後悔と悲しみが込められていた。
「今にして思えば、娘夫婦と相談をして孫を、
つまりLさんの母を当主様に託して本当に良かったと思います。
あれ程の力を持った子を奴らに奪われたとしたら、
この家系だけでなく、一族全体の運命を危うくすることになったのは間違いありません。」
まさにここ。俺がどうしても答えを得られなかった疑問が、これだ。
「あの」「でも」 俺と姫の声が全く同じタイミングで重なった。
姫が俺を見つめている。穏やかな笑顔、なら、これは俺の役目。
「はい、何でしょう?」 老人も俺を見つめていた。
「それ程の力を持った子供を、どうして分家は手放したんでしょうか?
分家から離れるだけならまだしも、本家の、しかも当主様に託すなんて。
分家の長が、それを黙って見過ごすとは、とても思えないのですが。」
「特に、問題にはなりませんでした。あの子は、鬼子だと思われていましたから。」
「鬼子?」 「そう、鬼子です。」 「それは、どういう、事でしょうか?」
「生まれつき、あの子の体には鱗がありました。右肩から背中、左腰から左の太腿にかけて。
母親の胎内で、重すぎる業の影響を受けると、体の一部が異形に変化した赤子が生まれる。
それが鬼子です。稀に、そういうことが起こることは知られていました。
大抵は業の重さに耐えられず、2歳になる前に亡くなる。それを避けるためには、
『分業』の術が必要です。業の一部を別人に分ける、極めて高度な術。
当時その術が使えるのは当主様と桃花の方様、そして●明の3人だけでしたから、
娘夫婦はその術を●明に依頼しました。
業を引き受ける訳ですから、引き受け手は術者でなければなりません。
娘夫婦は自分たちのどちらかで業を引き受けるつもりだったのです。
しかし、『分業』の術は成功率が低い上、業を引き受けた術者が無事に済む保証もありません。
当然●明はそれを断りました。鬼子を助けるために術者の命を犠牲には出来ないと。」
Sさんから聞いた話では、姫の母親は少なくとも21歳までは存命だった筈だ。
「Lさんの母上は、鬼子ではなかった。そういう、ことですね?」
「はい、鬼子の伝承とは異なり、あの子には一向に衰弱する様子が無かったんです。
それどころか、成長は、特に精神的な成長は眼を見張る程でした。
一歳になる頃には母親が歌って聞かせていた童謡を全て諳んじており、
二歳になる少し前には、既に、短い祝詞を幾つか詠唱することが出来ました。」
「諳んじたのではなく、詠唱出来たのですか?たった2歳で。本当に?」
姫が驚くのも無理は無い。本当に詠唱したというなら、その祝詞の効力を。
「はい。不用意に祝詞を詠唱するような子では無かったので問題は起こりませんでしたが。
それで私と娘夫婦は話し合い、あの子は鬼子ではないという結論に達したんです。
おそらく、自らその体の一部を異形に変えて、幼子の体には強すぎる力に耐えているのだと。
そんな伝承は聞いたこともない、しかし他には説明の方法が有りませんでした。
そして、その考えが正しければ、成長につれてあの子の力はますます強くなる。」
もし、そんな力を持っていることを分家の長に知られたら。だから姫の母親を当主様に。
「そこで、私は一計を案じました。●明の取り巻きの術者、その一人を通じて願い出たのです。
『鬼子である孫を本家の当主に託すことを許して欲しい』と。」
「でも、それが簡単に許されるなんて。」
「●明は『分業』の術を断った。それを利用したんです。
『娘夫婦は『分業』の術を断られたことをやはり恨んでいる。
どのみち助からぬ命なら、娘夫婦の願いを叶えることでその恨みを逸らせる。』
『もし当主が引き受けなければ恨みの対象が当主に上書きされる。
引き受けたとしても術の成功率は低い。失敗すればやはり恨みは当主に向かう。
最悪、術が成功しても、鬼子が普通の子に戻るだけ。痛くも痒くも無い。』
そう、取り巻きの術者に吹き込んでおきました。案の定、あっさり許可が降りましたよ。
もちろん●明があの子の状態を確認したいと言えば、最悪の事態になったでしょうね。
でも、そうはならないという確信が私にはありました。」
「それは何故、ですか?」
「●明は力を持たぬ普通の人間を蔑んでいました。
まして鬼子を気に掛ける事など、有るはずが無い。
あの男にとって、鬼子は普通の人間にすらなり損ねた、何の価値もない存在なのですから。」
老人は冷たい微笑みを浮かべた。その裏にあったのは皮肉ではなく、哀しみであったろう。
「あの子を当主様に託して3年後、私たちにもある噂が伝わってきました。
『本家に途方もない力を持つ術者が現れた。
それは僅か5歳の女の子で、しかも本家の当主が何処からか引き取った子。』と。」
「そんな噂が流れたら、貴方たちにも追及の手が。」
「いいえ、それは全く有りませんでした。●明はとても自尊心の強い男です。
私や娘夫婦を咎めれば、自分の失敗を認める事になる。それは許せない。
だから結局最後まで、私や娘夫婦には、嫌味の一つも言いませんでした。
勿論内心では怒り狂っていたと思いますし、それが結局はKさんやLさんの拉致に繋がった。
本当に申し訳有りませんが、あの時私たちには、それ以外の選択肢が無かったのです。
「それなら私の、お祖父様とお祖母様にも、お会いできるのでしょうか?」
老人は暫く姫を見つめ、それから眼を閉じた。ゆっくりと首を振る。
「娘夫婦は、Kさんを奪回しようとして犠牲になりました。
しかし娘夫婦には、きっと思い残すことは無かったと思います。
結果的には、あの時の選択がLさんと、そして一族への復帰に繋がったのですから。」
姫とあの人は又従姉妹、それなら2人が良く似ていたのは当然かも知れない。
あの人も、そして姫も、外法を使う者達にとって是非手に入れたい存在だった筈。
2人は拉致され、あの人の奪回は失敗したが、姫の奪回は成功した。
そして、あの人を奪回しようとして姫の祖父母は命を落とした。
因縁、といえばそれまでだが、何と過酷で不思議な運命なのだろう。
そして俺は、俺の曾祖母は。
「私の曾祖母は家を出て活動していたと仰いましたね。」
「はい、姉は父の知人の養女になり、同じように家系から離れた者たちを支援していました。
彼女の頑張りがなければ路頭に迷う者が少なくなかったでしょう。
父の顧客でもあった彼女の養父は裕福でしたが、それだけで出来ることではありません。
彼女は本当に良くやってくれたと思います。亡くなる数年前までは連絡を取っていましたよ。
彼女が体調を崩して入院してからは、それも難しくなってしまいましたけれど。」
曾祖母は早々に家を離れた、遍さんからそう聞いて以来、正直俺は負い目を感じていた。
しかし、曾祖母も必死に自分の役割を果たしていたのだ。いつか一族へ復帰するために。
今更のように、俺たちの近しい親族が辿った運命の数奇さを思う。
一族全体が時代の変化を乗り越えるためには、どうしても避け得ない争いだったのか。
争いが終わったことで、一族が再びまとまって新しい時代に向かうことができるなら、
この争いで犠牲になった数多の命も無駄ではなかったということだ。
そして、俺と姫の体の中には、犠牲になった人々と同じ血が流れている。
「その通りですよ。Rさん。」 え?今、俺は。そうか、この老人も。
「RさんとLさんは、私たちに残された希望です。
当主様の御慈悲によって、私たちの家系は一族への復帰を許されました。
これからは家を離れていた者たちも少しずつ戻ってくるでしょう。
しかし有力な術者の多くは世を去り、私たちの家系は以前の力を失いました。
もう、以前のような力を持つことはないかも知れません。でも、それで良いんです。
RさんとLさん、これ程優れた術者を生み出したのは、この家系の血。
それは間違いのない事実ですし、この家系の誉れとなるでしょう。
さて、話が長くなりましたが、私たちの家系が辿ってきた道はご理解頂けたと思います。
こんな、お願いが出来る立場でないのは重々承知していますが、
出来れば、これからも時々は、この年寄りに御二人のお顔を見せては頂けないでしょうか?」
姫は立ち上がり、ふわりとテーブルを回り込んだ。床に膝を付き、両手を老人の右手に添える。
「曾御祖父さま、今度は私とRさんの結婚記念に撮った写真を持って来て差し上げます。
その時は、お体に障らない範囲で、母や父、御祖父様や御祖母様の事、お聞かせ下さいね。」
「はい。はい、喜んで...」
南中の太陽を避けて鳴き止んでいたセミが、傾いた日差しの中、再び鳴き始めていた。
「それで、あなたはどう思ったの?何だか納得してないみたい。」
就寝前の一時、ソファで他愛もない話をしている内、何となくその話題になった。
Sさんは俺の左肩に頭を預けたまま、俺の左手に両手の指を絡めている。
『姫の母親は鬼子だと思われていたために、
すんなりと分家を離れて当主様にその身を託すことが出来た。』あの時老人はそう言った。
しかし、本当に鬼子は存在するのか。あるいは存在したことがあるのか。
強すぎる業の影響で体の一部が異形に変化して生まれた赤子、とても信じられない。
「納得していないというか、体の一部が異形に変化した赤子というのがちょっと。
その、例えば鱗だったら遺伝子異常が原因の先天的な症状かも知れないですよね?」
「そういう症状があるのも間違いないけれど。論より証拠ね、ちょっと待ってて。」
Sさんは立ち上がって机に向かった。一番下の引き出しを開けて何かを探している。
「はい、これよ。開けてみて。」
戻ってきたSさんが差し出したのは白木の小さな箱。一辺が5cmほどの立方体。
そっと蓋を取る。箱の底には濃紺の布、そしてその布の上に。これは。
鱗だ。真っ白な鱗がざっと十数枚。大きさは俺の親指の爪くらい。
真珠のような白地、微かに螺鈿のような虹色の光が見える。
形は菱形に近い。中央の筋状に盛り上がっている部分は結構尖っている。
「あの、これ触っても?」 「もちろん、どうぞ。」
鱗を一枚摘んでみる。魚の鱗とは全く違う。何よりもその質感。
かなり厚みがあり、硬く丈夫そうだ。灯りにかざすと光がボンヤリと透けて見える。
こんな鱗は見たことがない。ヘビやワニの鱗なら、こんな風に一枚ずつ分離しないだろう。
もちろん皮膚の異常によって生じたものとは到底思えない。これは、間違いなく鱗、だ。
「Sさん、もしかしてこれは。」
「ご名答、Lの母親の体から最後にはがれた鱗。彼女から譲り受けたの。」
「最後にはがれたって、それはどういう?」
「彼女から直接聞いた話よ。少し残念そうに話してくれたのを良く憶えてる。
鱗が初めてはがれたのは、彼女が引き取られて2年後。だから、4歳になった頃ね。
左太腿にあった鱗の一部がはがれて、はがれた痕はすぐに周りの皮膚と変わらなくなった。」
先天的な遺伝子の異常によるものなら、成長につれて症状が劇的に軽くなることはないだろう。
つまり、成長して体の抵抗力が強くなったから、異形に変化していた部分が
元に戻っていったということだろうか。それなら、本当に業の影響を受けて体の一部が。
「その後も彼女の成長につれて少しずつ鱗ははがれた。太腿から背中、そして肩へと。
彼女は鱗を嫌なものだと感じていなかったし、むしろ綺麗な鱗がはがれたのを残念がって、
はがれた鱗を大切に取ってあったの。これはその中の一部。12歳の誕生日前には、
一枚残らず鱗ははがれた。その時に起こった不思議なことも、彼女は教えてくれたわ。」
「不思議なことって?」 「話を聞くより、実際に感じた方が納得出来るでしょ?」
Sさんは左手の甲に鱗を二列にして並べた。まるで奇抜なアクセサリーのようだ。
「じゃ、右手をこっちに。目を閉じて、良いというまで開けちゃ駄目よ。」 「はい。」
Sさんの右手が俺の手首を取る。やがて指先が硬いものに触れた。
乾いた、さらさらした感触。この感覚は以前何処かで...あれは、何処だったろう。
「眼を開けて、どうだった?」 「この鱗、前にも一度触ったことがあるような気がします。」
「最後の鱗がはがれたのは彼女がお風呂に入っている時。
湯船の底から鱗を拾い集めていたら、彼女のすぐ前に龍が現れた。
白い、小さな龍。あなたも触ったことがある、あの龍。」
そうだ、あの時。以前、Sさんの術で俺は小さな白い龍を見て、そしてその鱗に触れた。
大きさはまるで違うが、この鱗はあの龍と関わりがあるものなのか。
「詳しくは話してくれなかったけれど、彼女はその龍と意志の疎通が出来たみたい。
彼女の鱗が全てはがれて一年後、龍はある領域で眠りについた。
私はこの鱗を譲り受けたから、これを媒にしてその領域と此処を一時的に繋ぐことが出来る。
でも、それだけ。意志の疎通も出来ないし、龍を起こしてその力を借りることもできない。」
「生まれながらにということなら、式とは違いますよね。護り神、なんですか?」
「式とは違うわね。龍が護り神として彼女の体に入り込んでいた可能性は有る。
他にも色々な解釈が出来るけれど、正解は彼女とあの龍しか知らない。
一族の歴史の中で、こんな事例は他に1つも記録に残っていないから。」
「これを、母親の形見としてLさんに渡していないのは何故ですか?」
姫がこの鱗に関わる話を知っていたなら、既に俺には話してくれていた筈だ。
「未だ迷ってるの。あの時私は、Lに渡す時までこれを預かるのだと思ったわ。
『いつかこれをLに渡して。』と言われると思ったのに、そうじゃなかった。
ただ『これをSにあげる。ずっと持ってて。』そう、言っただけ。その意味を、ずっと考えてる。」
Sさんは悪戯っぽい笑顔を浮かべた。
「ねぇ、あなたが答えを教えてくれない?」 「へ?どうして僕が。」
「あなたが赤の宝玉を身につけて」 「駄目です、絶対に。」 「ケチ。」
結
大きく開いた窓から吹き込む風に、未だ昼間の熱気が残っている。
Sさんと姫はダイニングで夕食の準備。翠と藍の子守が、今日の俺の当番。
子守と言っても特に面倒はない。藍は寝ているし、翠は1人遊びの達人。
俺はただリビングで2人の様子を見ながら本を読んでいれば良い。
「ねえ、おとうさん。」
じっと水槽の中を覗き込んでいた翠が突然振り向いた。
「どうかした?」
「きんちゃんは、どうしてときどきしゃべるの?きんぎょなのに。」
「え?」 きんちゃんは、あの日姫と2人で持ち帰った金魚の名前。
当初Sさんは『名前は付けない方が良い』と言っていたのだが、
いつのまにか翠がそう呼ぶようになった。
他の呼び方を思いつかないまま、今はすっかりその名前が定着してしまった訳だ。
「きんちゃんが、喋るって?ホントに?」 慌てて本を置き、翠の隣りに立つ。
「うん、ときどきだけど、しゃべるよ。」 翠はいたって普通の、真面目な顔だ。
「何を、喋ってるか分かる?例えば翠にご挨拶とか?」
この年頃の子供なら、金魚を擬人化し、会話をしている気になるのも珍しくはないだろう。
「しゃべるときは、いつもはじめに『K』っていうの。だれかのなまえかな?」
ざわ、と、首筋の毛が逆立った。 「『K』って...」
「おとうさんが、しってるなまえ?」
「ええと、同じ名前の人を知ってるけど。でもその人は、そう、大人だから。」
「じゃあ、きんちゃんはみどりとだれかをまちがってあやまるんだね。」
「翠に、謝るの?きんちゃんは。」
「うん。『わたしはばかだった、ゆるしてくれ。』って。しゃべるのは、それと『K』だけ。
でも、どうしてあやまるのかな?ふしぎだよね。」
そっと翠を抱き上げた。軽い体、温もり。小さいけれど、確かな、命の感触。
翠を抱いたままソファに戻る。腰を下ろし、翠を隣りに座らせて小さな肩を抱いた。
「翠は『生まれ変わり』って知ってる?」
「しってる。しんだひとのたましいが、べつのひとになってうまれてくるんでしょ?」
「そう。でもね、人の魂が必ず人に生まれ変わるって決まってる訳じゃ無いみたいだよ。」
「どういうこと?」
「とても悲しい思いをした人やすごく辛い思いをした人の魂は、
他の生き物に生まれ変わることもあるんだって。
あんまり悲しかったり、辛かったりすると『もう人間は嫌だ。』って思うのかもしれないね。」
「じゃあ、きんちゃんはとてもかなしいおもいをしたから、きんぎょにうまれかわったんだね。
あやまるのは、そのとき『K』というひとにもかなしいおもいをさせたから?」
「絶対にそうだとは言えないよ。でも、自分だけじゃなく、他の誰かにも悲しい思いを
させてしまったのなら、どうにかして謝りたいと思うんじゃないかな。」
「おとうさん、みどりは、みどりはどうしたらいい?ひとちがいだから、こたえちゃだめ?」
もう一度翠を抱き上げ、頬ずりをして、その髪を撫でた。まっすぐに俺を見つめる、澄んだ瞳。
「翠はどうしたいの?」
「きんちゃんが、かなしくないように、したい。かなしいままなのは、いやだから。」
「きんちゃんは翠を『K』という人だと信じてるんだよね?」 「うん。」
「それなら、お父さんは、答えてあげても良いと思う。」 「なんて、こたえたらいいかな?」
「今、翠は悲しくて辛い?それとも幸せ?」
「しあわせだよ。かなしくないし、つらくないし、みんなみ~んなだいすきだから。」
「じゃあ、そのまま答えれば良いよ。 『私は今、幸せです。安心して下さい。』って。」
「わかった。おとうさん、おろして。また、しゃべるかもしれないから、きんちゃんのことみてる。
『わたしはいま、しあわせです。あんしんしてください。』だいじょうぶ。もう、おぼえた。」
百合の花の香り。振り向くと、すぐ後ろにSさんが立っていた。
「勝手な事をして御免なさい。でも、僕は」
Sさんは人差し指で俺の唇を押さえ、ゆっくり首を振った。
「ご名答。多分これ以上正しい答えはない。ありがとう。」
出来上がった夕食の良い匂い。Sさんは優しく声をかけた。
「翠、夕ご飯よ。こっちへいらっしゃい。」
『邂逅』 完

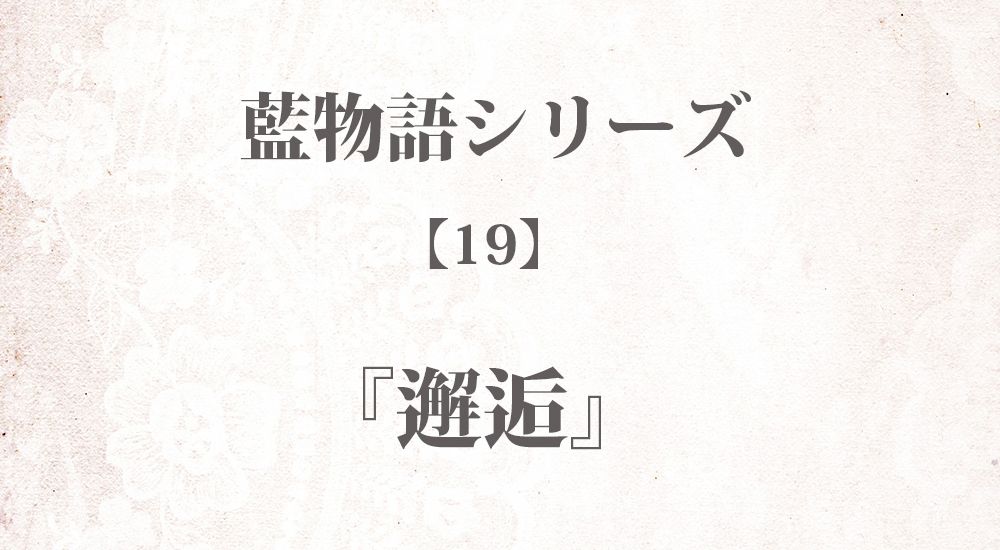

コメント