藍物語シリーズ【22】
『禁呪』
上
窓の外を白いものがひらひらと横切る。雪だ。冷え込むと思ったら、やはり降ってきた。
姫は暖かい上着を着ていったから大丈夫だろうが、滅多にない雪。渋滞も考えられる。
少し早目にお屋敷を出た方が良いだろう。 そんな事を考えている時、ケイタイが鳴った。
見慣れた画面表示、姫だ。 この時間の電話は大抵休講に伴う待ち合わせ時間の変更。
「はい、もしもし。」 「もしもし、Lです。」 「休講ですか?」
「それもありますけど、待ち合わせの場所を変えようと思って。」
??? いつもは大学の第5駐車場。それ以外の場所は初めてだ。妙な、胸騒ぎ。
「どうか、したんですか?」
「ええっと、買い物。そう、買い物です。それで、大学の駐車場じゃなくて
スーパーマーケットの駐車場で。そこでお願いします。時間は、そう3時過ぎに。」
「スーパーマーケットって、▲○■ですか?」 「はい。」
やはり、おかしい。たまに買い物をするその店は大学より遠いのだ。
それなら大学で姫を迎えてからの方が都合が良い。電話では話せない、事情?
「了解です。買い物の相談は後で。」 「はい、後で。じゃ、切りますね。」
ホッとしたような言葉を残して電話は切れた。
「どうしたの?お迎えの時間変更?」 Sさんは藍を抱いて翠と絵本を読んでいた。
「はい、休講と、スーパーマーケットの駐車場で待ち合わせしたいって。」
「スーパーマーケット?変ね、特に買い物の話はしてなかったけど。」
「何か事情がありそうなので早目に出ます。
多分Lさんは大学から歩くつもりだと思いますけど、この雪ですから。」
「そうね。寒いし、スーパーマーケットへの途中で拾えたら良いけど。でも、気を付けて。」
「お父さん、きをつけてね。」 「有り難う。気を付けるよ。」 翠の頬にキスをする。
手頃な上着を羽織り、すぐに車を出した。積もるとは思えないが、念のために、軽の四駆。
姫も免許を持っているが、俺は今でも出来る限り大学への送迎を続けている。
姫の希望もあるし、何より俺自身の希望。2人きり、車中で話す時間が愛しいから。
大学の正門前を通り過ぎる。ここからスーパーマーケットまで車なら5分弱。
出来ればその途中でと思ったが、姫の姿を認めたのはスーパーマーケットの駐車場。
店の入り口近く、歩み寄る俺を見つけた姫は笑顔で手を振った。
特に変わった様子はない。思わず息を吐く。
「無理に買い物しなくて良いなら、帰りましょう。体、冷えちゃったでしょ?」
「はい。少し寒いです。」 車に戻り、暫くの間細い体を抱きしめた。
「温かい。」 「良かった。」 安心して、思わず少しだけ滲んだ涙。そっと拭って車を出した。
「それで、どういう事ですか?こんな寒い日にわざわざ遠くまで歩くなんて。」
姫は俺の左手に右手を重ねた。まだ、少し冷たい。
「今日、告白されたんです、私。」
姫が大学で時々声を掛けられるのは知っていた。しかし、それで何故?
「でも、それだけなら大学の駐車場でも良かったんじゃないですか?」
ストーカーまがいの男でも、いざとなれば姫は自分で身を守るだけの力を持っている。
「相手が幽霊なので、もし駐車場でRさんの前に現れたらまずいかなと思って。」
「幽霊って...」 「はい、タケノブさんって言ってました。」
頭の中が整理できない。普通、幽霊の意識にあるのは過去だけ。
今生きている人に害をなす事があるのも、過去の憎しみや恨みに囚われているからこそ。
幽霊が新しい記憶を蓄積するなんて聞いたこともない。
しかし、その幽霊は姫に告白を。つまりその魂は死後に恋をしたというのか?それとも。
「あの、どういうことなのか全く分からないんですが。」
「はい、私にも分かりません。だから今夜Sさんに。一緒に話をしてくれますか?」
「ミスキャンパスに推薦されたのを断ったと思ったら、今度は幽霊に告白されるなんて。
L姫様は本当にモテモテね。R君も鼻が高いでしょ?」 Sさんはイタズラっぽく笑った。
翠と藍は既に夢の中。深夜のリビング、3人での作戦会議は久し振りのような気がする。
「いやあ、それは何とも。」 それ以外に答えようがない。ホットワインを一口、クローブの香り。
「それで、Lにも事情が分からないとしたら、単純に生き霊とは判断できないって事ね。」
そうか、姫に恋をした男の生き霊。でも、それなら確かに姫が。
「はい。実は『タケノブさん』って幽霊、大学では結構有名なんですよ。
噂では50年位前から現れてるようで、目撃者も沢山いるみたいです。
私も時々気配は感じてたんですけど、この数日急に気配が強くなって。
今日の昼休み、図書館で告白されたんですけど、他の学生には見えていないようでした。」
「もし50年前に入学したとしても、68歳。噂だから10年位の誤差はあるかも知れないけど、
それにしたって幾ら何でも不自然。本当に同じ幽霊?」
「はい、自己紹介で『ちょっと有名な幽霊です。』って言ってましたから。」
「待って。その人、自分が幽霊だって自覚してるって事?」 「はい。」
普通、生き霊としての記憶は本体に残らない。僅かに残ったとしてもせいぜい夢に見る位。
しかも自分が幽霊だと自覚してる幽霊なんて、あり得ない。
「正体が分からないとしたら、Lさんが明日以降も大学に行くのは危険じゃありませんか?」
「そうね。でもLに告白したんだから今の所悪意は無い。
ずっと大学休む訳にも行かないし...Lは何て返事したの?ミスキャンパスの時と同じ?」
「はい。『私結婚してます。御免なさい。』って。」
そう言って、姫を推薦しようとした友人たちを絶句させて以来、
姫に声を掛ける男は減ったらしいのだが、その幽霊はそれを知らないと言うことだ。
「それで、あの。」 姫は言い難そうに俺を見つめた。
「『本当ならあきらめるから、その人に会わせて欲しい。』って言われて。」
「その人にって、誰に、ですか?」
「鈍いわね。R君に決まってるでしょ。本当に夫がいるなら、会えばあきらめがつくって事よ。」
あの電話、姫の声に胸騒ぎを感じた本当の原因はこれか。
その幽霊と面会するのは俺の同意を得てからという、姫の心遣い。
「良いですよ。そういう事なら、僕が直接会って、話してみます。」
「宜しく、お願いします。」 小さな声、姫は俯いた。 胸が、痛い。
幽霊とはいえ、自分に好意を持ってくれた相手を蔑ろには出来ない。
でも、それで俺に面倒をかけるのは心苦しい。だから直ぐには言い出せなかったのだろう。
姫の優しさが胸に染みる。 そんな姫を黙って見つめるSさんも、やっぱり優しい。
しかし、言い寄ってくる相手から妻を守るのは夫の、つまり俺の当然の役目。
面倒どころか、誇らしい。自然と、気合いが入った。
中
翌日の夕方、姫のお迎えで大学に車を走らせる。
いつもより少し早く大学の第5駐車場に車を停めた。20台分程の、小さな駐車場。
車を使う学生は歩くのが苦手。学部の建物から一番遠いこの駐車場はいつも貸し切り状態。
姫は更に遠回りして大学の構内を散歩するのを日課にしているので、
この駐車場が2人の待ち合わせ場所になっていた。
昨日とは打って変わった暖かい日差し。
終業までは間があるが、今日だけは姫を待たせる訳には行かない。
車を出て、駐車場近くのベンチに座る。本を持ってはいるが、単なる精神安定剤。
昼過ぎに姫から電話があり、これから会うことになっていた。そう、『タケノブさん』に。
20分程で姫の姿が見えた。いつもとは反対側。笑顔で手を振り、早足で近付いてくる。
「待たせちゃいましたか?」 「いいえ、そんなには。」 姫も俺の隣に座った。
「それで、場所は此処で良いんですね?」
「はい、『呼んでくれれば何処にでも。』って。大学の構内なら自由に移動出来るみたいです。」
「じゃあ、遅くならないうちに。」 「はい。」 姫は目を閉じて俯いた。
「いや、もう来てますから。」
視界の端に男の足が見えた。グレーのジーンズ、紺のデッキシューズ。
ゆっくりと立ち上がる。その男と視線を合わせた。
爽やかな笑顔、本当に幽霊なのかと疑うほどの存在感。 しかし、この男には影が無い。
軽く一礼。「どうも、Rです。」 男は深々と頭を下げた。
「タケノブです。今日はわざわざ済みません。マドンナの隣に座っても良いですか?」
マドンナ? キリスト教の聖母。 この男が姫をそう呼んでいるなら少し気が楽だ。
「構いませんよ。」 3~4人掛けのベンチ。左端に俺、その隣に姫。少し離れてその男。
「一応、戸籍抄本を持ってきました。」
「いや、お二人の様子を見れば分かります。まさかこんな可愛らしい女性が人妻だなんて、
とても信じられなかったので、どうしても確かめずにはいられなかったんです。
でも、あなたのような二枚目が相手では、僕など勝負になりません。得心しました。
それにRさんも僕と話が出来る人だなんて。何だか愉快な気分ですよ。」
...複雑な気分だが、姫が褒められるのはやはり嬉しい。
「それでは。」 「約束通り、マドンナの恋人になるのは金輪際諦めます。ただ。」
「ただ?」 首筋がヒヤリと冷たくなる。
「Rさんと、もちろんマドンナが許可してくれるなら、これからもマドンナと話がしたい。
僕と話が出来る人は、マドンナがやっと3人目なんです。もう52年も経つっていうのに。」
男は俯いて小さく溜息をついた。深い憂いを含んだ、寂しそうな横顔。
「あなたは本当に50年も前からこの大学に?」
「そう、生きていれば僕は今年の10月に70歳。生きていればね。」
このまま話を続け、少しでも情報を得られたら、今後の方針を検討する材料になる。
そっと姫の顔を見た。姫も俺の目を見て小さく頷いた。
「失礼かもしれませんが、とても70歳には見えませんね。」
「そりゃ僕は18で死んだんだから、これより年取った姿は無理だよ。
服や靴は学生達のを見ればどうとでもなるけれど。」
黒い学生服と革靴...一瞬で。 男は学生帽を取って膝の上に置いた。
「これが当時の制服。僕はこっちの方が好きなんだが、この姿でいると時々騒ぎになる。
話は出来なくても、僕の姿が見える人は結構いるみたいだから。」
いつの間にかタメ口になっているが、考えてみれば大先輩だ。まあ仕方ない。
「あなたには、死んだ後の記憶があるんですか?」
「ああ。僕は生まれつき心臓が弱くて、風呂場で倒れたんだ。あれは、苦しかったな。
『折角大学に入ったのに悔しい悔しい。』って、そればかり考えてる内に気が遠くなって。
次に気が付いたときは此処に居た。ある教室の椅子に座ってたよ。
目の前に松田って親友が座ってて、声を掛けたけど反応が無い。
肩を叩こうと思ったら、こう、すり抜けた。
ああ、僕は死んで幽霊になったんだって、その時に分かった。」
「それで、その後50年間の出来事も憶えているんですか?」
「もちろん。此処でずっと学生や職員の様子を眺めてきた。
学生達や職員達の人間関係、時代につれて移り変わる学生達の気質や習慣。
そういうのを観察しているのは、存外面白いんだ。
ほら、何て言うか、僕はその気になれば大抵何処にでも入れるからね。
言った通り僕は子供の頃から病弱だったから、家の窓から外を眺めるのが好きで、
特に人物を観察するのが大好きだった。まあ、この生活が性に合っていたのかな。
だけどさすがに寂しくなってきた。52年間にたった4人なんて。あ、そう言えば。」
「はい、何か?」
「4人目は君。マドンナと君が2人とも僕と話が出来るなんて奇態だ。
それにマドンナは僕に直接呼びかけることも出来る。一体君たちは、何者だい?」
...とうとう君呼ばわりだ。 それに、『何者だ?』って。聞きたいのはこっちだっての。
幽霊の自覚があって、死後の記憶があって、生きている人間にも関心があるなんて。
「陰陽師なんですよ。2人とも。」 「陰陽師?」 「はい。」
男は額に手を当てて目を閉じた。数秒間の、沈黙。
「確か、アイツもそんなこと言ってたな。2人目の...そう、○▲。面白い男だった。」
思わず姫と顔を見合わせた。 それは、俺たちの一族ではありふれた名字。
「鳩が豆鉄砲食らったような顔だね。どうか、したかい?」
「あ、僕たちの一族ではありふれた名字なのでちょっと。」
「成る程。只の偶然か、もしかしたら君たちの一族と血縁があるのか。実に面白い。」
「それで、その○×って人はどんな?」
「入学式の翌日、僕に気付いて話しかけてきた。驚いたよ。」
男は面白そうに喉の奥で笑った。
「色々話してる内に友達になってね。初めは『いつか成仏させてやるから。』って言ってたけど、
その内『誰にも迷惑掛けないなら、そのままで良いんじゃないか?』って言うようになった。
それで、そのまま卒業。本当に良い加減な奴だよな。」
「それ、どの位前の話ですか?」
「う~ん。30年、いやもう少し前。細かい年代は苦手だけど、頑張って思い出してみるよ。」
「もし思い出したら、聞かせて下さいね。」
まさに破顔一笑、男は晴れ晴れとした笑顔を浮かべた。
「マドンナ、これからもあなたとお話しする許可を頂いたと考えて良いんですね?」
「はい。でも、これからはマドンナは止めて下さい。私の名前は、L、ですから。」
「名前で呼ぶ事までも許して頂けるなんて...本当に嬉しい。有り難う。」
「夫もそれを、許してくれると思いますよ。ね、Rさん?」
かな~り複雑な気分だが、姫がそう言うなら、まあ仕方がない。
その日の深夜、再び作戦会議が開かれた。今夜の飲み物はホットウイスキー。
「大学の敷地に縛られてるなら一種の地縛霊。でもそれ以外、悉く幽霊の特徴から外れてる。
聞いた感じでは人間そのもの。LとR君の話じゃなかったら、とても信じられない。」
「はい。Rさんと話をしているのを見ていても、幽霊とは思えませんでした。
姿を現している間は、気配とか存在感も普通の人と変わりません。本当に不思議です。」
「自分が幽霊だという自覚がある幽霊の記録は残っていないんですか?」
お屋敷の図書室、その中の記録庫には様々な記録が保管されている。
其処になくても、『上』が管理する資料館にならもしかして。
「死後幽霊になり得るのは、限られた霊質をもつ人だけ。前に話したでしょ?」 「はい。」
「その霊質を持つ人の魂も、肉体を失えば存在の仕方が私たちとはズレてしまう。
そのズレのせいで自我を保つのがとても難しい。それが一般的な解釈。
ただ、強く執着してる事については、精神力がそのズレを越えて自我を保つことがある。
R君は幽霊が新しい記憶を蓄積することはないと思ってるみたいだけど、そうじゃない。」
「強く執着したり関心を持った人については、新しい記憶を蓄積することもある。
私たちだって、関心の無い事までいちいち憶えていられないでしょ?
それがもっともっと極端になった状態を想像すれば、分かってもらえるかな。」
そうか、Sさんは幽霊になった女の子の、死後の記憶を念写した事がある。
別の件で、自殺した女子高生の霊が姫を記憶出来たからこそ、姫は彼女と友達になれた。
普段は朧に拡散している意識が何かの条件で凝縮し、その瞬間だけ自我を取り戻す。
そして自我を保っている間だけ、新しい記憶を蓄積する。それは一体、どんな感覚だろう。
「だから、術者が必要な条件を調えれば、その間は幽霊も自我を保つ事が出来る。
自分が幽霊であるという自覚を持ち、私たちと会話し、そして新しい記憶を蓄積する。
幽霊や魂と交信する術はその応用。R君も何度か、使った事があるわよね?」
そうだ、単独での初仕事。俺は交通事故で植物状態になった男の子の魂と交信した。
あの時、確かに男の子は自我を持ち、俺と会話をし、そして両親の様子を気遣っていた。
「だけどLの大学全体に、そんな条件が50年以上も存在し続けるなんて有り得ない。
第一、特殊な条件があるならLやR君がとうに気付いてる。何か、別の理由があるはず。
まあ理由はどうあれ、不思議な幽霊がいてLに好意を抱いてるのは事実。
今の所誰も被害を受けていないし、話し相手をしてる内に何か分かるかも知れない。
取り敢えずは様子見、経過観察ってとこね。」
第5駐車場脇のベンチで姫を待っていると2人連れの姿が見えた。姫と、タケノブさん。
駐車場の入り口手前。姫が小さく手を振ると同時に、タケノブさんの姿は消えた。
タケノブさんは姫の帰りの散歩に同行することが多いが、毎日と言う訳でもない。
実際、ここ一週間程は姫の前に姿を現したという話は聞いていなかった。
「今日は一緒でしたね。タケノブさん。」
「はい、『とても面白い事を見つけたから、暫くそれを研究してた。』と言ってました。」
「研究って、人間関係の?」 「はい、助教授と学生の不倫だそうです。」 「はあ、成る程。」
何処でどんな事をしてたか知らないが、幽霊に不倫の現場を研究されるとは気の毒に。
「私が『そんな話は嫌いです。』って言ったら笑ってました。
それで今度は昔の自分の事を話してくれたんです。出身地とかお家の事とか。」
○×市で代々医者をしてきた家系だそうです。お父さんも医者だったから、
大学生になるまで生きる事が出来たと言ってました。好きな文学を勉強させてくれたし、
本当に感謝してるって。お風呂場で発作を起こして倒れたのは冬休み。
きっとお父さんお母さんが看取ってくれたんでしょうね。それが、せめてもの親孝行。」
助手席から外を見つめる姫の顔は、少し寂しそうに見えた。
「『○△市で代々医者をしてきた家系。本当に、そう言ったの?」
Sさんの目の色が変わった。 「はい、確かに。」 「ちょっと待ってて。」 廊下を走る足音。
本当にせっかちな人だ。今夜の飲み物はカフェロワイヤル、折角の綺麗な炎を眺めもせずに。
結局Sさんが戻ってきたのは20分くらい経ってからで、
俺は新しく淹れたコーヒーでカフェロワイヤルを作りなおした。
「タケノブは名前じゃ無くて名字かも。○△市の武信姓。
その中に、もとは陰陽道、術者の家系がある。うちの一族とは系統が違うけど。」
そうか、呪術医の例に見られるように、古来、術者が医者を兼ねるのはありふれた事だった。
「もしタケノブさんの家が術者の家系だったら、
あの不思議な幽霊が存在する理由を説明出来るかもしれない。」
「もしかして、反魂の術。ですか?」 姫の顔が緊張している。
「反魂の術って、死者を蘇生させる術ですよね?確か、『泰山府君の法』とか。」
「あれは映画の中の話。その術の名前を口に出せないから、Lは反魂の術って言ったの。
一族に伝わる、門外不出の秘術。死者を冥府から呼び戻す、禁呪の中の禁呪。」
「本当に可能なんですか?死者を蘇らせるなんて。」
「全ての条件が揃えば可能な筈よ。」
「じゃあ西行とか安倍晴明の話も全くの作り話って事じゃ無いって事ですね。」
「どちらも半分ホントで半分嘘。カムフラージュのためにフェイクが混ぜてある。」
「フェイク?」 「そう、禁呪の内容や方法を全て語るわけにはいかないでしょ?」
それはそうだ。だが、語られている内容の一部は真実ということになる。
「どこがホントで、どこが嘘なんですか?」
「L、西行の話、説明して上げて。その間にこれ、飲んじゃうから。」
「はい。」 姫は少し考えて、それから話し始めた。
「西行は人骨を集めて人間を再生した事になってますけど、あれは嘘です。
魂を入れないんですから、その術で作れるのは式であって人間じゃありません。
だから感情も言葉も持ってなかった。それはホントです。
骨を並べて云々の記述も、お香の種類や断食の話も、話をそれらしく見せるための嘘です。」
「どうしてわざわざ代に人骨を使ったんでしょうね?Sさんは紙を使うのに。」
「人の姿をした式を作る時、Sさんのように高等な術を使うなら代は紙の人型で十分。
でもそうでない時は人の一部、つまり遺体の一部を使った方が成功率は高くなります。」
姫は言葉を切ってSさんを見つめた。 少し困ったような顔。
「そう、あるいは。」
コーヒーカップを持ったSさんの目がキラキラと輝いている。本当に、綺麗な人だ。
「あるいは、何ですか?気になるじゃないですか。」
「その骨の主の姿をした式を作ろうとした。骨の主は一体誰なのか?
その人の姿をした式を作って何をするつもりだったのか?色々と事情がありそうよね。」
そうか、西行は話し相手欲しさに術で人間を作ろうとした事になっている。
しかし術で作る式は言葉を持たないのだから話し相手にはならない。
つまり話し相手欲しさに人間を作ろうとしたということ自体が、そもそも嘘。
微かな悪寒。ブランデーとコーヒーで温まっていた体が、ゆっくりと冷えていく。
Sさんはカップに残ったカフェロワイヤルの残骸を一気に飲み干した。
「美味しい。じゃ、次は安倍晴明の話。反魂の術を使うには、かなりの力が必要なの。
当然この術を仕える術者は限られる。だからこそ、主人公は安倍晴明って設定。」
確かに、あの話を後世の創作であると考える人は多い。
「あの話、『死者を蘇生させるのに代償が要る。』という部分はホント。
『代償が他の誰かの魂である。』という部分もホント。」
だからこそ病気で瀕死の上人を救うために僧侶が1人身代わりを志願した。しかし。
「2人とも助かったというのは嘘。不動明王が身代わりになるなんて有り得ない。
それに、どんな術者でも代償なしに高位の精霊と契約する事は出来ない。」
「その術は、精霊との契約に基づく術なんですね?」
「そう。まず蘇生させたい人の遺体の前で身代わりになる人の魂を捧げ、精霊と契約する。
ただし、既に遺体の腐敗が進んでいたら契約は成立しない。
だから、この術を使うとしたら、出来れば死亡直後。遅くとも死後1~2時間以内。
もし契約が成立すれば、精霊はその見返りとして遺体の傷や病を癒しその腐敗を防ぐ。
術者は契約が成立した事、つまり遺体の腐敗が進まない事を確認して、
蘇生させたい人の魂を遺体に戻す。それで完成。全てが完璧なら、死者は蘇る。」
治まりかけていた悪寒が再び全身に拡がっていく。
「じゃあ、反魂術が失敗したからあの幽霊が?」
「ご名答。遺体がまだ腐敗せずに残っているなら、その魂と私たちの存在の仕方はかなり近い。
だからその幽霊は自我を保てる。そう考えるしか、あの幽霊の説明はつかない。」
「でも、どうして失敗したんでしょう?契約が成立したなら、後は魂を戻すだけですよね?」
「魂を戻すだけって...そっちの方がずっと難しいの。だからこの術を使える術者は限られる。
というより、特殊な祭具の助けを借りずにこの術を使える術者はまずいない。」
Sさんの知る範囲にいないとしたら。当主様も桃花の方様も、勿論Sさん自身も。
それなら術者の力が足りず、術が完成しなかったのは当然の事だろう。
つまりタケノブさんの体は今も何処かに、当時のままで残っている。
「どう対処するべきなんでしょうね、僕たちは。」
放置するべきなのか。それともタケノブさんの体を探し出して葬るべきなのか。
「今は悪意のない存在でも、今後どう変化するかは分からない。
私の予想が正しいのかどうか、確かめておく必要もあると思う。」
Sさんは向き直って俺を見た。 はい、どうぞ何なりと御指示を。
「さてR君。52年前に何が起きたのか、資料を調べて頂戴。県立図書館なら、多分記録が残ってる。」
「了解です。明日の朝一番に。」 「うん、良い返事。」
下
『師走の怪事!?親子3人行方不明』
地元ではメジャーな新聞の縮刷版で、その記事はあっさりと見つかった。
個人病院を営んでいる医師とその妻、大学生の息子が行方不明だという記事。
半月程の間は細々と続報が載っているが、捜査が進展したという情報はない。
その後の新聞には事件に関する記事は見つからなかった。迷宮入りということだろう。
タケノブさんと、その父母。
何処からか術者を呼び、父母の内どちらかが身代わりになったのか。
いや、3人とも行方不明のままということは...
父母のうちどちらか1人が術者で、残り1人が身代わり。
しかし術は失敗し、術者も力尽きたと考えるのが筋だろう。
52年前に行われた反魂の術、その結果出現した不思議な幽霊。
帰りの車の中。お屋敷に着くまで、俺の心はもやもやと曇ったままだった。
「多分あなたの予想通り。榊さんに調べてもらったけど、やっぱり未解決のままだった。」
Sさんの寝室。就寝前の一時、Sさんと2人並んでソファに腰掛けていた。
藍はベビーベッドの中で寝息を立てている。翠はLさんの寝室。もう、2人とも寝ている頃。
『細かい事情を知りすぎて、もし態度に出たらタケノブさんが不審に思うから。』という
Sさんの判断と姫自身の希望もあり、今後の調査はSさんと俺が担当することになっていた。
「やっぱり行くんですか?予想通りなら確実に死体がありますよ。気が進みません。」
「52年も前だから、きっと白骨化してるわね。それより気がかりなのは白骨化してない方。」
「タケノブさんの体ですか?」
「そう、いつまでも腐敗せずに残っている体は、『器』になる可能性がある。」
「『器』って、入れ物のことですよね?」
「そう、何か悪しきモノがその中に入り込むかもしれない。
体を欲しがっているモノはいくらもいるから。」
「契約した精霊がそれを守ってくれるんじゃないですか?」
「精霊は体の準備を調えるだけ、その後体を守るとしたら別の契約が必要になる。」
「悪しきモノが入り込まないような対策を取る必要があるってことですね。」
「そう。それに、ちょっと確かめたいこともあるし。」
「ええと、これこれ。こっちが門扉の鍵、こっちが玄関の鍵です。
定期的に草刈りはしてますが、マムシやなんかいるかもしれません。気を付けて下さい。」
武信医院の建物は52年前から空き家となり、現在は親戚から委託された不動産屋が
敷地と建物を管理している。Sさんが榊さんに頼んで話を付けて貰ったらしい。
『ある事件の犯人が○×市周辺に逃げ込んだ形跡がある。
空き家に潜伏している可能性があるから捜索させて欲しい。』という設定だった。
Sさんは車で待っている。綺麗な女性を連れた若い刑事なんて誰も信用しないだろう。
鍵を渡してくれたのは人の良さそうな初老の女性。 鍵を受け取って俺は頭を下げた
「有難う御座います。夕方までには鍵をお返しします。」
「ああ、急がなくて良いですよ。持ち主は売りたがってるけど、今の景気じゃ、
こんな寂れた街の土地を買おうなんて酔狂な人はいませんからね。しかも建物は曰く付き。」
「曰く付き?」 女性は露骨に『しまった』という顔をして、慌てて言葉を継いだ。
「あ、いや。その、前にも警察があの建物を捜索した事があって。」
「へえ、それどのくらい前のことですか?」
ホッとした表情。52年前の事件に触れずに済みそうだと思って安心したのだろう。
「私が此処に採用されてすぐだったから、もう30年くらい前ですよ。
その時も凶悪犯が隣の県からこの辺りに逃げ込んだかも知れないって話でした。
それで、2日かけて彼方此方調べたけど何にも分からなかったそうです。
あなたくらいの若い巡査で、『下っ端なんでこんな仕事ばっかりですよ。』って笑ってました。」
30年前...それ、何処かで。
「あの、どうかしましたか?」 「いいえ、何でもありません。有難う御座いました。」
もう一度頭を頭を下げて事務所を出た。
地図を頼りに車を走らせ、10分程でその建物を見つけた。路肩に車を停める。
「何故わざわざ街の外れに病院を建てたのかと思っていたら、この辺りは龍穴なのね。
それほど力の強い龍穴ではないけど、住むにはとても良い場所なのに。」
建物の背後に拡がる森、その向こうに連なる山々が見える。あれが、龍脈。
長い歴史を持つその街は、新幹線や高速道路の整備から取り残され、
ここ20年程ですっかり寂れてしまったと聞いた。
「人間の経済活動は、龍穴の力も及ばない程の力を持ってしまったんですね。」
「じゃ、行きましょう。頼りにしてるわよ。」 「荷物持ちなら、任せて下さい。」 「馬鹿。」
その建物は金網のフェンスで囲まれていた。これは管理の為に取り付けたものだろう。
その内側にコンクリートの低い壁。立派な門柱の看板に『武信医院 内科・小児科』の文字。
朽ち果てたのか、もとの門扉はなくなっていた。門を入ると結構広い庭、
その中を抜ける、ひび割れたコンクリートの小道。建物の玄関に繋がっている。
定期的に草刈りをしているからだろう。 フェンスの門扉、錠前はそれほど錆びていない。
2人で門扉をくぐる。白骨死体と対面するなんて気が進まないが、まあ仕方がない。
「事件の直後、当然警察は此処をしっかり捜索した筈です。ホントに此処ですか?」
「探し方が悪いとは言わないけど、何処にあるか分からないものを探すのと、
それがある場所の見当を付けてから探すのとでは雲泥の差がある。」
Sさんは小道の途中で立ち止まった。建物の中、じゃないのか?
「やっぱり有った。ほら、あれ。術者と医者を兼ねるなら、
それぞれの仕事場を分けるのは当たり前だもの。」
小道からさらに枝分かれする細い道。その先に小さな祠。
Sさんは祠に向かって歩き始めた。慌てて後を追う。
5m四方程のコンクリートの土台。その上には更に木の土台、これは2m四方程。
湿気抜きの為か、コンクリートの土台と木の土台の間には5mm程の隙間が有った。
赤い彩色が残る木製の祠。 個人の庭の祠にしては念の入った作りだ。
Sさんは暫く祠とその周りを調べていたが、やがて祠の裏側から手招きをした。
「こんな所に、どう見ても変よね?」
それは金属製の取っ手。50cm程の間隔をおいて2個。多分真鍮、頑丈そうだ。
「何でこんな所に取っ手が?」 「押すか、引くか、どっちかに決まってる。ね、お願い。」
コンクリートの土台に片膝を付き、まずは引いてみる。
...動かない。全体が少し揺れるような感触はあるが動くとは思えない。それならあとは。
両膝を付き、徐々に力を込めながら押す。 突然、感触が変わった。
僅かだが、確かに木の土台がずれている。 もう一度、力を込める
低く唸るような音を立てて、あっけなく土台は動いた。 隠し扉と、それを挟む2本の浅い溝。
確かその溝は祠の正面にも続いていた。参道を示すしきりだと思っていたのだが。
動きの軽さからして、木の土台の下にはベアリング付きの大きな車輪が設置されている筈。
木の土台の下だから直接風雨に曝されない。単純だが優れた工夫だ。
Sさんは黙って隠し扉を見つめた。少し、目を細める。
「扉の周りに強力な結界が張ってある。かなり力のある術者だったのね。じゃ、扉を開けて。」
「大丈夫なんですか?」 「邪心の無い者には関係ない。開けて頂戴。」
Sさんは俺が持ってきたスポーツバッグの中から懐中電灯と蛍光灯式のランタンを取り出した。
「多分階段、灯りはこれで十分。さ、行きましょう。」
扉を開けて中を覗く。1m50cm程の四角い穴。壁の一方に頑丈な梯子が組んである。
梯子を使って穴の底に降りる。Sさんの予想通り、其処から階段が伸びていた。
懐中電灯で照らしながら慎重に降りる。ランタンを持ったSさんが後に続く。
強い腐臭を覚悟していたのだが、カビ臭ささえ感じない。
微かに風が吹く。ヒンヤリと冷たい、乾いた風。奥に通風口が有るのだろう。
3m程降りただろうか。階段は終わり、開けた場所に出た。コンクリートの床だ。 これは。
男物の靴と女物のサンダル。綺麗に揃って並んでいる。
靴とサンダルの少し先、10cmほどの段差があり、其処からは板張りの床になっていた。
ゆっくりと懐中電灯を前に向ける。 襖だ。無地の、黄ばんだ襖が4枚。ピタリと閉じている。
Sさんが横に並び、ランタンの灯りも加わった。かなり、明るい。
これなら部屋の中の様子も良く見えるだろう。 つまり、いよいよご対面だ。
靴を脱いで床に上がり、襖の前に正座して一礼。 Sさんは床に立ったまま深く頭を下げた。
Sさんが俺を見て小さく頷く。それを確認した後、片膝をついて襖の引き手に右手をかけた。
するすると、思っていたより滑らかに、襖は開く。50年の歳月は感じられない。
Sさんがランタンを掲げる、その表情が変わった。
「これ、どういう事?」
恐る恐る向き直って襖の中に視線を移す。
畳の上に大きな白い布が一枚、丁度横になった大人2人分程の膨らみを覆っている。
Sさんは畳に膝を着き、そっと白い布を捲った。ミイラのように乾涸らびた左手。
薬指に細い金色の指輪。恐らく女性の手だ。つまりタケノブさんの母親、その隣は父親だろう。
「身代わりになったのは母親。だから術者は父親ね。」
白い布を元に戻し、Sさんは立ち上がった。更に奥へ進む。もう一枚の白い布。
一瞬、微かな視線を感じた。横の壁の辺り? しかし棚のようなものが見えるだけだ。
「見て。」 振り向くと、半分程捲れた白い布、そして。
白い布団に横たわる裸身の若い男性。 その、上半身。
Sさんの隣りに膝を着く。蒼白だが、穏やかな顔。間違いない。あの、タケノブさんだ。
確かに、全く腐敗している様子はない。肌にも張りがある。
しかし、違う。 まるで大理石の彫像のような冷たい雰囲気。
「凄い。間違いなく、史上最も完全な永久死体だわ。」
でも、これは...いや、あの冷たい雰囲気。
どれ程完全であろうと、魂を失った体はやはり死体なのだ。
「家の敷地内、まさに死亡直後に術を使える最高の条件。だからこの状態は理解出来る。
でも、分からないのはこれ。」 Sさんは死体の傍らから何かを拾い上げた。
「本物は初めて見たけど、これはあの術を使う時に必要な祭具。
入り口の結界からしても、かなり力のある術者。これを使ったのに、何故失敗したのかしら。」
Sさんは祭具を死体の傍らに置き、白い布を元に戻して立ち上がった。
更に歩を進め、ランタンを奥の壁に...壁が、ない。 ただ、深い闇が拡がっている。
「龍穴に存在する洞窟は、それ自体が特別な力を持つ。だから古来、それは異世界への、
あの世への通路だと考えられてきた。死者を蘇らせるとしたら、これ程相応しい場所はない。」
立ち上がり、Sさんの左隣りに立つ。 深い。懐中電灯の光も、その底に届かない。
この洞窟は一体何処まで続いているのか。
「黄泉比良坂。」
「そう、それもこんな洞窟の1つ。多分この家系は代々この洞窟を守り、その力を借りて
ひっそりと術を伝えてきたのね。洞窟の力と、この冷たく乾いた風のお陰で
タケノブさんの両親の遺体も腐敗を免れた。本人達がそれを願っていたかどうかは別だけど。」
微かな、視線。
そっと囁く。 「Sさん。」 「何?」
「Sさんの右側、壁の方から視線を感じます。気を付けて下さい。」
Sさんは壁に歩み寄ってランタンを掲げた。色々な物が整然と並ぶ棚の様子が見える。
「大丈夫なんですか?」 立ち上がり、懐中電灯を持ってSさんの横に並ぶ。
Sさんの左掌、緑色の人型が載っていた。 半透明の深い緑、やや厚みがある。 翡翠?
「それは?」
「代よ。結界を抜けて入ってきた悪しきモノを始末するために配置されたのね。」
どういう事だ? タケノブさんの父親がこれを配置したなら...
敢えてタケノブさんの魂を体に戻さず、タケノブさんの体を守るための代を配置したことになる。
でも、一体何の為に? それなら何故、タケノブさんの父親の遺体が此処に?
「ふふふ。」 Sさんが、笑っていた。
笑い続ける。この部屋では不謹慎なのではと思う程、本当に可笑しそうだ。
「どうしたんです。何がそんなに可笑しいんですか?」
「これは、父が作った代よ。多分扉の周りの結界も。」
「え?当主様が?」
「タケノブさんの2人目の話し相手、○▲。 それは即位する前の、父の名字。
父と母が出会ったのはあの大学だと聞いていたから、もしかしたらと思ってたの。」
Sさんが言った『確かめたいこと』とは、そういう意味だったのか。
「約30年前。あの幽霊に会って、話をして、当然父も不思議に思った。
そして散々考えた挙げ句、私たちと同じ結論に達した。だから。」
!! 30年程前に此処を捜索した若い巡査とは...
「まずは此処の状態を確かめて、必要な物を確認。そして次の日、必要な物を用意して
もう一度此処を訪れた。2体のミイラを供養して安置し、代を配置するために。」
もしも当主様が此処を訪れていなかったら、きっと此処の情景は...酷い目眩がした。
Sさんは緑色の人型を元の場所に戻して微笑んだ。
「さあ、出ましょう。この代は当分有効だし、私たちに出来る事は残っていない。」
『出来る事は残っていない。』って、そんな。
「あの、Sさん。」 「何?」
「Sさんなら、タケノブさんの魂をあの体に戻せるんじゃないですか?」
「死後49日を過ぎて、死者の魂が幽霊に変化してしまったらそれは不可能。
それで?見ず知らずの幽霊の為に寿命を削るなんて、まさか本気じゃ無いわよね?」
「あ、いや、聞いてみただけですよ。」 「そういう事に、しといてあげる。」
Sさんが階段を上り始めた。 息を吐き、そっと汗を拭う。 危うくとんでもない自爆を。
世界で最も奇妙な墓への出入り口。その階段は、降りてきた時よりも短く感じた。
傾いた日差しの中、お屋敷に向かって車を走らせる。
Sさんは助手席で窓の外を眺めていた。横顔を見る限り、機嫌は悪くない。大丈夫。
「聞きたいことが有るんですが。」 「なあに?」
「どうしてタケノブさんの御両親はあの術を知っていたんでしょうね。門外不出なのに。」
「一族内紛の時代、力を封印して野に下った術者も多い。中には昔を懐かしんで、
その術について語った人がいたかも知れない。勿論詳細はぼかし、フェイクも交えて。」
「でも、それを聞いた相手が術者だったら。」
「そういうこと。フェイクを取り除き、自分で集めた資料と付き合わせれば、あるいは。」
その話を聞いたのが、タケノブさんの父親だった可能性も当然有る。
「タケノブさんの心臓が悪いことは小さい頃から分かってた。
だから御両親はその日に備えて準備をしていた筈。
ありとあらゆる情報を集め、いざとなった時の手順はどうするのか。
誰が身代わりで誰が術を使うのか。何度も何度も話し合って決めていたのね。
家族と離れて隣の県で生活出来る程度には丈夫になったけど、準備は怠らなかった。
帰省してきた息子が倒れた時、慌てず迅速に対応出来たのはそのため。
そうでなければ、短時間で心を決めるなんて出来る事じゃない。
それに、躊躇して時間が経てば経つ程、術の成功率は落ちていく。」
「成る程、納得です。もう1つの質問も、良いですか?」
「質問の仕方が少し気に入らないけど、良いわ。答えてあげる。」
「あの術には特殊な祭具が必要。あの場所にあったのが、その祭具ですよね?」
「そう。」
「確かに特殊な祭具でした。でも、神の血を封じた宝玉とは格が違う。
あの祭具なら、人の力だけで作れる。そんな気がしました。」
「流石ね。その通り、あれを作れる術者は今でも何人かいるはず。」
「それならあの祭具を手に入れるのは不可能じゃありません。
あの祭具があって、そして術師に生き残る気がないのなら、
Sさん程の力がなくても、術を完成させる事が出来る。そうですよね?」
「その通り。術者が死ぬ気なら、ある程度の力があれば完成出来る。例えば、あなたにも。」
「我が子を蘇生させるためなら自分の命を捧げても構わないという親は幾らでもいるでしょう。
例えば両親があの祭具を手に入れて、共に命を捧げればあの術が完成する。
それなら、一族には、あの術で実際に蘇生した人が何人かいるんじゃないですか?」
「あの術は『禁呪の中の禁呪』、そう言ったでしょ?」
「はい。文字通り命と魂を操作する術ですから、それは当然のことで。」
「端から自分の命を捧げるつもりなら、寿命を削られる事なんて関係ない。
この術が禁呪なのは、もう1つのペナルティーがあるからよ。」
ざわ、と、首筋の毛が逆立った。 何だ? この、嫌な予感は?
「そのペナルティーって、何ですか?」
「この術を使って蘇生した者の魂は、死後、中有へ入れない。
永久にこの世を彷徨って、最悪なら悪霊に変化する可能性さえ有る。
ね、それを知っていても、例えば私が死んだ時にあなたはその術を使える?」
使えない。使える筈がない。Sさんの魂が悪霊に変化するなんて、想像することさえ。
「私も使えない。呼び戻してそんな宿命を負わせる位なら、泣いて冥福を祈る方がずっと良い。」
寒気が治まらない。少し震える左手で、ヒーターの温度と風量を少し上げた。
「この術に必要な、特殊な祭具の話を聞いた時、それは『白の宝玉』かと思いました。」
Sさんは窓を開け、吹き込む風に髪を掻き上げた。 「車を停めて。あの、広くなった路肩へ。」
車を停めると、Sさんは助手席から身を乗り出して俺の唇にキスをした。長く、熱いキス。
それから俺の左手を両手で挟み、俺の肩に頭を預けた。 温かい。 寒気は治まっていた。
「相手が本当に大切な人であればあるほど、あの術を使える筈がない。
だから、私もLも、あの術は使えない。」
「じゃあ、どうしてタケノブさんの両親はあの術を?」
「そのペナルティーがあると、知らなかった。だからこそあの術を使い、そして失敗した。
私はそう信じたい。おそらく精霊との契約を終えた後、父親の体に何か異変が起きた。
心臓、かもね。心臓疾患は遺伝することがあるから。」
「『信じたい』って、別の可能性もあるということですか?」
「知っていて、どうしても死なせたくない事情が有ったのかも。
彼は一人っ子。 古い家系、どうしても絶やす訳にいかないなら、
何より大事なのはタケノブさんが生き延びて子を作ること。
タケノブさんの魂は一族を存続させるための犠。」
そんな、馬鹿な。
「ただ、話を聞いた限りでは、タケノブさんは父親が術者である事を知らない。
知っていたら、真っ先に自分の状態と父親が術者であることの関連を考えた筈。
あの術を使ってでも生き残って欲しいなら、そもそも隣の県での進学なんて許すはずが無い。
其処で倒れたら、絶対に間に合わない。そして、タケノブさんは医学部でもない。」
「タケノブさんに最大限の自由を与え、その上で術を使う機会があるなら、それが天命だと?」
「そう。両親はタケノブさんを術者としての跡継ぎにも、医者としての跡継ぎにも
する気が無かった。術者も医者も自分たちの時代で絶える、それで良い。
タケノブさんには何の柵もなく新しい人生を生きて欲しいと考えていたんだと思う。
でも、私たちがどんなに考えたって真実は闇の中。
今を生きている者は、自分の信じたい方を信じれば良い。」
自分の信じたい方を、そうか。タケノブさんには、自分の状態を選ぶ自由すら無い。
「そうですね。タケノブさんの両親はこの術のペナルティーを知らなかった。そう、信じます。
それに、今考えれば、術は失敗したけれど、結局成功するよりも良い結果になったんです。」
「どういうこと?」 Sさんは真っ直ぐに俺の目を見つめた。 視線が、眩しい。
「だってタケノブさんは今年で70歳。蘇生していたとしても、そろそろ寿命が尽きる歳。
成功していても、失敗した今の有り様も、永遠に彷徨うことは変わらない。
それなら、自我を保てない状態より、自我を保てる今の状態はずっとマシです。」
「...そうね。本当に、あなたの言う通り。」
結
その日、朝から妙な胸騒ぎがしていた。
『『不幸の輪廻』の活動が活発化している。』と、警戒の通知が来たのは半月ほど前。
しかし、未だ大した事は起きていなかった。このまま何事も無く、そう思っていたのに。
いつも通りにおやつ、午後のお茶とお菓子の準備をしていたら、地面が大きく揺れた。目眩。
姫の大学は既に春休みに入っていたから、家族は全員お屋敷にいた。まさに不幸中の幸い。
しかし、それを喜ぶ事は出来なかった。TVの画面に次々と映し出される 信じられない光景。
未曾有の大災害。多くの命が失われた。
一族もかなりの被害を受け、それからの数ヶ月、俺たちは多忙を極めた。
葵さんと暁君に翠と藍を預け、『上』の指示で彼方此方飛び回る日々。
久し振りに姫の大学を訪れたのは、姫の休学届を出すためだった。
学務課で書類を提出し、2人遠回りをして車に戻る。
第5駐車場、入り口脇のベンチに男が座っていた。 タケノブさん。
「どうも随分と、酷いことになってるみたいだね。」
第5駐車場脇のベンチ。 タケノブさんは小さく呟いて、目を伏せた。
「はい。それで私たち凄く忙しくて。今日は休学届を出しに来たんです。」
「そうか...でも、仕事が落ち着いたら、戻ってきてくれるよね?」
「私、今度の事で色々考えました。それで、決めた事があるんです。」
「何だい、それは?」
「仕事が落ち着いたら、私、子供を産みます。」
鳥たちの声、昼前の駐車場には、以前と変わらず穏やかな空気が満ちていた。
「そうか。君とその子の幸せを祈ってると、僕は言うべきなんだろうね。少し、寂しくなるけど。」
「○▲、あなたの2人目の話し相手。前に話してくれましたよね?」
「ああ、君たちの一族ではありふれた名字って話だね。」
「その人、私たちのお師匠様のお父様でした。今は私たち一族の当主様です。」
「やっぱり君たちの血縁か。何となく、雰囲気が似てると思ってたよ。」
「だから、寂しくないですよね。」
「え?」
「もし、私がこの大学に戻って来なくても、私たちの子供がこの大学に入学するかも。
そしたらその子達に、この大学や私たちのこと、話してあげて下さい。」
「ははは。なるほど、そうか。君たちの子供、もしかしたら孫も。承知した。
その日が来るのを、楽しみに待ってる。」
お屋敷に向かう車の中、姫は助手席の窓から外を眺めていた。
未だ心臓の高鳴りは収まっていない。 『私、子供を産みます。』 姫はそう言った。
「タケノブさん、きっとあれで納得すると思いますよ。最高の対応でした。」
「納得して貰わないと困ります。ホントのことですから。」
「え?」
「もう少しで仕事も落ち着くし、そしたら子供が出来るまで、夜はずっと一緒にいて下さいね。
Sさんに話したら、喜んでくれましたよ。きっと男の子。何だか、そんな気がします。」
姫がそう言うなら、男の子なんだろう。一緒に良い名前を、考えなくては。
愛が生まれる前に考えた名前の候補を幾つか、ゆっくりと思い出していた。
『禁呪』 完

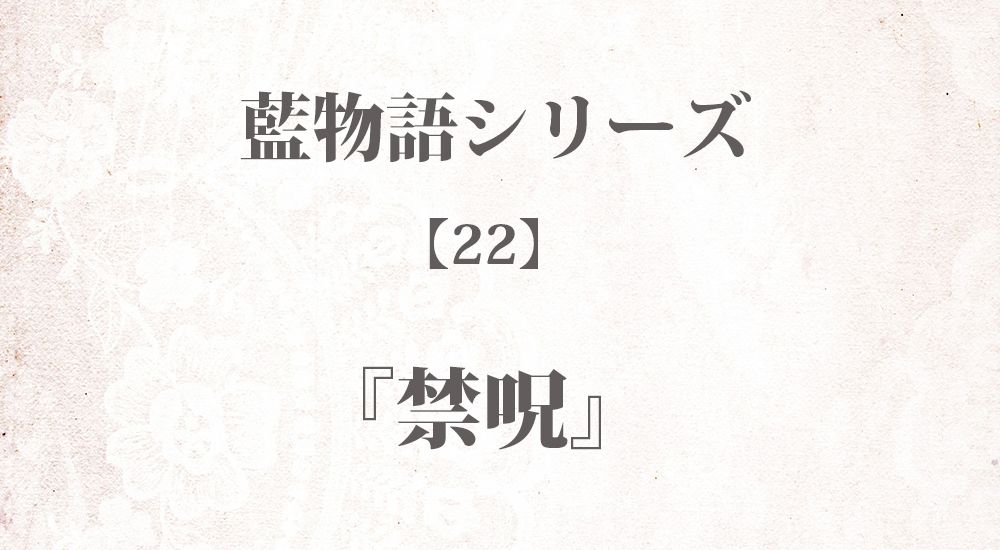

コメント