洞窟
当時の俺は例えば離れている蝋燭に意識を集中し続けて炎を大きくしたり小さくしたりなんてのはごく当たり前のことで誰でもできることだと思っていた。
そんな日常の中で友達の発表会で一発芸も何も出来ない俺がその技を恥ずかしかったが披露したんだ。
驚くことにみんな歓声を上げた。(今では驚くのが普通だと思っているが)
そんなことが子供心に嬉しくて蝋燭以外にもなにか動かせるものはないかと
必死に家中のあらゆる「物」に意識を集中しつづけていた。
だが意識を集中させることは大変神経のいることで、まるで目と目の間に鉛筆でもぶっさしたんじゃないかと思うほど激しい痛みが走るときもあった。
以前はそんなに強い霊感は無かった。幽霊と思える影がちらりと目の端に映る程度。
上記のような日常を繰り返しているうちに段々と「霊」に対する…というか
説明しづらいのだが霊感とか持っている人の特殊な能力が自分にも備わっている
ことに気が付き始める。
その頃だ、俺がO君と出合ったのは。
O君は自分で「霊感がある」と言っていた。クラスの皆は信じていたが
霊感を持っている、という主張だけでクラスの人気者になっているO君を
俺はそんなに好きではなかった。
ある日O君の家に遊びに行った。家族と挨拶したときにふと頭に「本当だったんだ」
という言葉が浮かび上がった。結論から言うとそのO家では遺伝子的に霊感を
持つ家族でお母さんと二人の姉、そしてO君は本当に霊感を持っていたのだ。
なにか魅かれるものを感じ、俺とO君は(家族とも)すぐに打ち解けた。
俺たちは学校が終わると毎日のように遊んだ。
2学期も、3学期も。
そのころには自覚は無かったが俺の霊感は日に日に増して行き、
本能的に軽い浮幽霊なら浄化させて上げられるほどにはなっていた。
O家も俺に霊感(というよりは特殊な何か)が備わっていることは
知っていたし、俺からもそっち系の話題は話していた。
O母が言うには「霊感は共鳴し合い、互いを成長させていく」らしい。
そんあことを幼心にとても感心しつつ聞いていた。
ある日O君が俺を婆ちゃんちに連れてってくれることになり、俺は興奮したのを覚えている。
車に揺られること数時間、子供だった俺たちは友達と遠出というだけで時間を忘れてしまっていた。
婆ちゃんの家はO姉曰く「すごいところ」らしい。なんでもO家の霊感を持ている人は
婆ちゃんの家に行ったから霊感が宿ったそうだ。「あの頃からね…」とO姉は話をしていた。
当然そんな話を聞くとまだ子供の俺は興奮するわけで…
O婆の家が普通の民家だったときの落胆は半端じゃなかった。
大げさだがそこまで期待していたのだろう。
しかし落胆はすぐに興奮へと変わった。「裏に洞窟あるけど絶対近寄るなよ」と
O爺に念を押されたからだ。振り、なんて当時の俺はわかるわけないから
O爺もただ単に行かせたくなかったんだろう。
だが俺は行きたくて行きたくて仕方なかった。O君と河原で遊んでいるときも
婆ちゃんが作ってくれた柏餅を食べているときも「早くあの洞窟に行きたい」
という思いが頭の中をぐるぐるしている。
時間というものは、当たり前だが過ぎるわけであっという間に夜になった。
爺ちゃんと婆ちゃんが「明日もいっぱい遊ぶんでしょ」と言いながら
襖の扉を閉め、1時間は経っただろ!(おそらく10分くらいだが)と思う頃に俺はO君を起こした。
「なになに?」「あの洞窟、行こうぜ!」「んー…」
O君はすこし考えている素振りを見せたがそこは子供、すぐに「よし」と言い懐中電灯2本と手袋を持ってきてくれた。
洞窟、ということで手袋は配慮らしい。
洞窟へは意外と近かった。といっても興奮から時間を忘れたのかもしれない。
それは洞窟というにはあまりに味気ないものだったのが今でも覚えている。
大きく開いた穴、中は何角形かの形をした体育館くらいの広さだった。
O君が先頭で俺が後に続き中に入ろうとした。
いや、入っていた。俺は一瞬で取り残されたため、一瞬理解が追いつかなかった。
O君は洞窟に「すでに」入っていたのだ。
俺は叫ぶ「O-!!どうしてそこに!?」「わからない!助けて!!」
出てくればいいものをO君は必死に叫ぶ。
「わからない!」「出して!」「助けて!」
俺は身動きが出来なかった。今なら確かに見える、洞窟の中の存在に気づいたからだ。
俺はなにもわからなかった。この世にはこんなおぞましい存在がいるのか?
いや、ここはこの世なのか?そう思ったとき「存在」がO君を覆った。
俺は駆け出した。誰か呼ばないと…後ろでO君の叫び声が聞こえる。
「頼む!頼むよぉ!!」「早く助けて!」
婆ちゃんの家が見えた!そのとき…耳元で微かにO君が「もうだめだ」
と呟いたように思えた。
婆ちゃん!爺ちゃん!Oが、Oがぁ~
泣きながら叫ぶと婆ちゃんと爺ちゃんはすぐに駆けつけて
俺から事情を二言三言聞いた辺りから
婆さん、神崎さんに連絡だ
と言い「お前はここを絶対にでるなよ?」優しく、しかし迫力のある声で言った。
そして20分後、神崎さん(今思うと神主さんかも)と爺ちゃんは
見たことも無い格好をして出て行った。上下スウェットに着物みたいなのを羽織った感じ。
婆ちゃんは震えていた。しきりに「大丈夫、大丈夫」と呟きながら…
1時間が経ったところだろうか、爺ちゃんと神崎さんが「○君、頼むから来てくれ…」
と戻ってきた。
俺は正直拒みたかった。まだ震えが止まらない。
神崎さんは明らかに力を失っている。
最初見た背中に現れる黄色いモヤモヤが今は真っ黒になっていたからだ。
もうこの時点で怖くて仕方なかったがO君のことを考えると行かなくては!と思った。
洞窟の入り口。中にはたいまつが置いてあり周囲を照らしていた。
真ん中にO君がいた。思わず駆け寄る。
しかし神崎さんと爺ちゃんに止められてしまう。
「アレを直接見てはいかん」「すぐに閉じ込めよう」「な、なんで?O君は?」
三者それぞれに自分のこれからの行動を予知するように声を絞り出す。
爺ちゃんは「さ、手を貸してくれ」
そういうと俺の手の手首から5センチくらいのとこを掴み握った。
たぶん血を止めてたんだと思う。神崎さんは爺ちゃんの手首を握った。
変な姿勢だがこのまま洞窟の真ん中付近まで移動した。
爺ちゃんが「神崎さん、本当に…済まない…」
意味がわからない言葉を発して神崎さんは無表情のまま「始めるぞ」
ただそれだけ。気が付くと朝になっていて横にはO君が寝ていた。
夢、だったのかな?だがそんなことはなかった。
手首に出来たあざ。
爺ちゃんが握って出来たあざがあった。
俺は飛び起きて、爺ちゃんの部屋に…
「ど、どうなったんですか!?」
敬語を反射的に使う。その後も俺は「どうなった?」に似た意味の言葉を
2,3回繰り返していた。
爺ちゃんはただ一言「業を背負って生きろ○君」
あとで聞いた話なのだが長いから自分なりにまとめる。
・神崎さんはその地方でも有名な神社の神主。昔から祠(洞窟のこと)を守っていた。
・爺ちゃんと婆ちゃん(主に爺ちゃんだが)はその祠を代々管理してきた。
・爺ちゃんたちが駆けつけた時O君は半ば絶望的な状態だった。
・神崎さんは「これも己の業」と言いO君の身代わりになった。
・祠にいた「存在」は神にもっとも近い悪霊らしい(わけわからない)
ちなみに祠の悪霊は誰かを媒体として存在していた。今までは爺ちゃんの弟が媒体だった。
でもO君と俺が近づいたせいで媒体はO君に変わろうとしていた。
しかしそこで神崎さんの行動により媒体をO君→神崎さん に変えた。
記憶が曖昧だがそのときの出来事はこんな感じ。内容が抜けてて矛盾、作り話みたいに
なってるところもあるけど、これは8年前に起きた事実。
その出来事から俺の霊に対する神経は異常なほど発達している。
今でも俺はたまに怪異に会います。
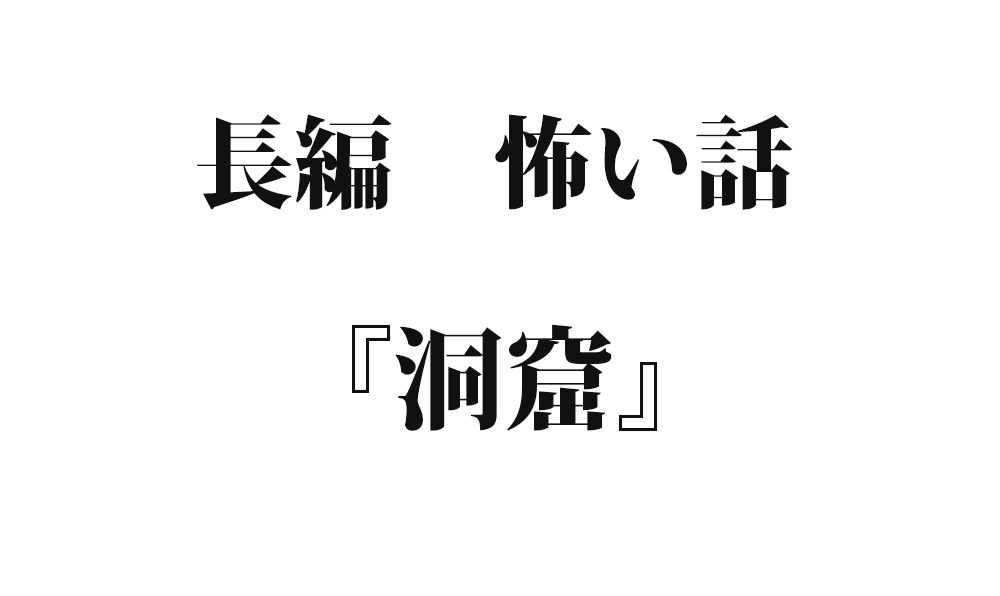
コメント