青い箱
私が住んでいるのは山間にあるよくある住宅地で、家からふもとに下りて、街へと続く国道の脇に、住宅に挟まれてその神社はあった。私は10歳そこらのことである。
子供なので、神社に対するしきたり云々の信仰には全くもって興味が無く、当時の私達には程よい遊び場のようなものだった。
その神社は夏祭りや正月にはお守りを売る巫女姿の店員などがいるものだが、普段では神主は隣接の事務所にいるらしい。
その土地の記念碑なんかもあってプチ観光地的な役割でもあったが基本大人の目もないわけで、堂々と子供は占領できるわけである。
とある日私は他の男女数人のグループに連れられ、その神社へと行った。
大人の目が無いとは言ったものの、当時の私はだいぶ真面目ちゃんの部類に入る子供で、
神社には祭りでもない限り踏み入ったことは無かった。
だが彼らもいつもからここを遊び場にしているわけではない。
つまり、いつもは公園を転々としているところ、気まぐれでここで遊ぶ事を提案した訳だ。
そこで私達が何をしたかというと、宝といっても、そこらへんに落ちている何かを黙々と収集するいわゆる宝探し。
神社なので賽銭のおこぼれの古い銭が当たりであろう。
その他は大人から見ればただの燃えないゴミであろう何かの部品やプラスチックの類、
そんな他愛も無い宝探しだが、子供にとっては燃えるゴミ以外は大抵、
校庭の小さな石だってガラスの破片だって宝石のように大事に見えるのだった。
かくいう私も中休み昼休みになれば校庭の砂利を漁っては爪の垢ほどの色のついた石を集めているクチではあったが、
神社、そう人の敷地であればすこし違った。
他の子供達はともかく、どうも乗り気になれないのが真面目ちゃんで、
神社ともあろう場所からガラクタとはいえ物をもっていくのは泥棒ではないだろうか。
そんな疑心を抱きつつも、臆病者と思われるのもまた本位ではないのでしぶしぶと宝探しに参加していたのである。
敷地の端、木の根の下、そして神社の床下へと手を伸ばしていく。
高床の下は滅多に掃除できるものではなく、つまり宝の山だと考えた。
しかし、思ったよりはあまり目ぼしい物は見当たらず、ただじめじめとした土が広がってるだけだった。
大したものはないなと、そう思い身を引こうと思ったら、
視界に青い物体が目に入る。
サイズ的には小銭なんかとは比べ物にならない大物。
小汚いのも気にせずに手にとってみると、大きさは人形のベッドほどという印象、
中にクッションがつめられた青い箱のようなものである。
何に使うものかは検討もつかないが、何かいいもののような気がするのが子供の感性である。
そして子供達の間でひととおりの発掘の成果をひろげて、山分けして解散した。
私の手には小銭も小石も無かったが、あの青い箱はしっかり持っていた。
しばらくは、少々の罪悪感に悩まされることとなる。
人の敷地、それも神様のいるところから人工物を持ち出してきた、
明らかに神社の備品ではないような箱ではあるが、罪悪感に苛まれている私にはそこまで頭がまわらず、
実は神聖なものではないだろうかとか、そんな窃盗妄想に暮れていたのである。
だが持ってきたものはしょうがない、砂をおとして、それは結局大事にしまわれた。
ワインのコルクや小石や貝殻といっしょに。
しばらくしてからだった。罪悪感も、その箱の存在も度々思い出す程度になったころ、
それはいつものように布団の中にもぐりこんだ時だった。
ざり、ざり。
それはかすかな音だった。
が、しんと静まった部屋の中で、それは確かに聞こえるのである。
私のベッドは2段ベット(と呼んではいるものの実際は机と棚の上にある高床ベット)で、
もし床の畳に布団をしいていたなら、それを本当の耳元で聞かなくてはならなかっただろう。
それは下から響いてきた。
虫だろうか?いや違う。虫は確かに湧くけど、あのような、畳を引きずり這うような音はしない。
ざり、ざり、私の頭の中は様々な思考を布団をかぶったまま巡らしたが、
この状況に対する利口な策を練るわけでもなく、ただ自分の小さな恐怖を拡張したに過ぎなかった。
結局、私はいやな脂汗をかくだけで夜を明かした。
どんなに恐怖しても、いずれは眠れるものである。
きっと、あれは新種の悪夢だったのだろう。
当時の年頃だと、よく悪夢というものも見る。
その類だと頭の中で押し付けるように自己解決した。
しかし、悪夢というのは現実でみるものであると思い知らされるのである。
その後、度々私は布団の中で音を聞くようになる。
乾いた畳の上では、その小さなものが引きずるような音はちゃんと響いては布団越しに耳に届く。
小さな音ほど聞きたくなくても聞こえるもので、時計の乾いた音と共に私の安眠を遮った。
毎日ではなかったものの、私はいつしか布団を深々とかぶるクセがついた。
そしてその音を聞いた後には大抵さらに嫌な夢を見るもので、更に後味の悪い目覚めとなるのだった。
今まで、被った布団をめくれないほどの恐怖を味わったことがあっただろうか、結構あった。
何せ絵になるような古い佇まいの家である、
霊感などは一切自覚はないが、ギシギシだの、ひゅうひゅうだの、そういうのは日常である。
しかしながら、あの音はおかしい。おかしいのだ。
夜な夜な、その音を聞くか聞かないかで恐怖した。
今日は悪い夢を見ませんようにという祈りの変わって、あの音を聞かずに寝れますようにというのが当分の切実な願いだった。
ある日、私は部屋でいつものように遊んでいた。
そしてふと、何気なく宝箱を取り出してきた。つまり、ガラクタ入れである。
小石の詰まったビン、貝殻のふくろ、星模様のついたコルク、
思い出がつまっているのだかつまっていないのだかわからない内容の中、
あの時拾った青い箱を手にとった。
?
手のひらサイズの長方形の箱、中にはクッション。
この宝箱に入れる際は、ちゃんと、土をおとした筈だった。
青い箱の外側は、土ひとつついていない。が、クッションの上に、ふと赤茶のよごれができているのである。
それは微かなヨゴレであったが、妙に生々しい色が印象的だった。
何が生生しいかは説明できないが、
そう、それはそこらの貝殻の土がついたものではなく、まるで、そのクッションに何か置いたような跡。
はじめて罪悪感の他に芽生えた、気味の悪さ。
私はそれ以上その箱に触れたくはなかった。虫でもいたのかもしれない。
その青い箱は、部屋の隅に投げ出されたままにされた。
夜が来た。私は習慣でふとんを被る。
長い間あの音に苛まれている気がするが、実は実際あの音を聞いたのは数回なのかもしれない。
しかし、聞こえることに変わりは無く、夜が昼とは比べ物にならないほど長かったのだ。
私はいつかあの音がぴたりと止むことを望みながら、
心の奥底では静かに実はあの音を待っていたのかもしれない。
しかし、奇怪な音の正体を暴くには、あまりに私の心は震えていた。
布団の暗闇の底に立てこもり、息を殺し、僕はいない、僕はいないと存在を消す。
そして、
ざり
それはいつものように、どこからともなくやってきた。
しかしいつもと違ったのは自分の方で、その音が不意に耳に響いた瞬間、私は小さく反応をしてしまったのだ。
布団が私の身にあわせて擦りあう音は、ざり、ざりという怪音よりよっぽど身に響いた。
子供部屋に、響いた。
這う音は、ぴたりと止まった。
気づかれてしまったのだ。
この些細な失敗にすっかりとりつかれた私は、涙でも流していたのだろうか。
それでも必死に取り繕おうと息を懸命に殺し、そして耳に神経をあつめた。
だが、それ以降、時計が神妙に刻む針の音以外に子供部屋に響く音はなく、
私は序々に平常心と安堵を取り戻す。
驚いたのか、帰ったのか、
まさか布団をめくればそこに顔があるなんてこと・・・・まさか、まさか。
安堵の中で、「お化けなんかいるものか」というか細い安心材料にしがみつく。
やがて、その結論がじわじわと頭になじんだ頃、かいた脂汗をどうにかしたくなった。
疑心暗鬼になっていても仕方なし、とりあえず、布団の外の空気が吸いたい。
そうして、思い切って布団を取り払った。
・・・・目の前には、ただいつもの天井、いつもの壁、何にもありゃしなかった。
まだ夜の最中だというのに、長い長い夜が明けた気になったと共に、
少しばかりのやってやった感。
そして深く息を吐き出たのだった。だが。
・・・り、ざり、ざり
全身を悪寒が駆け巡る。
布団越しでない分いく分かクリアに聞こえる気がするその軽い音が、重く、聞こえる。
身を強張らせ、吐き出したばかりの息も吸えず、ただ目の前の壁から目を逸らせなかった。
耳を塞ぐことも侭ならず、その音を聞き続けるしかないのだ。
しかし、一度極限状態から安堵を潜った精神には、少しばかりの隙間があった。
もしかしたら、これは千載一遇のチャンスなのではないかと。
ここまで来たのなら、最早奴の正体を暴くべきではと。奴の、大したことない姿を。
布団の外の空気を吸って、現実的になった脳で考えた案。
その時は、何だって受け入れることが出来る気がしたのだ。
そして、勢い良く・・・・と言うにはあまりにもぎこちない動きで、下へ首を向ける。
そこには、幾ばかしか散らかったいつもの部屋があった。
・・・・なんだ、と心に安心がもたらされた、望んでいた結果、至極当たり前の結果。
それを飲み込もうとした、その時。
凝らした視界のその中に、それが、蠢いていた。
心臓が破裂せんばかりに飛び上がる。
ざり、ざり、ざり、耳に届く一定の音と共に、それはひとつの関節をめいいっぱい動かしながら畳の目を刻むように進んでいた。
芋虫なんかじゃない!即座に思う。
夜の闇の中、白いそれは尚不器用に動く。そして、闇に慣れた目が気づく。それには―爪があった。
つまり、こうである。夜の闇に蠢くそれは、人の指であると。
人間の第二関節までが、ひとりでに動いていた。
最早肉があるとか骨があるとかかさぶたがあるとかそんなどころではなく、
兎に角その人の指は、断面をこちらに背を向け、ひたすらえっちらおっちらと微々たる歩みを重ねていた。
最早凍りついた思考で呆然と眺めていた。
見ようによっては滑稽な姿ではあるが、それは呪われているとしか言いようが無い光景だった。
指がこちらを向いていないのは幸いであるが(そもそも目なんてどこにあるというのか)、
その猿の手のミイラがずるずると這うのを彷彿させるそれは、一体どこへ向かっているのであろうか。
・・・・気づいてしまった。
指が向かうその先にあるのは、あの放り捨てられた青い箱だった。
ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、
ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、ざり、
もう夜は明けないのではないかと、気が遠くなるような時間が過ぎた。
最早、時計の音すら耳に入らず、指の方へと決して目を向けることなく、
指があの青い箱で何をするかも見ることは出来ず、
指が畳を這う音に耳を傾けながら、
いつしか私は、眠っていた。
その箱を、その後どうしたかは定かではない。
その次の日、わき目も振らずトングでつかんでゴミステーションに捨てたのか、
それともその後の大掃除で他のがらくたと共にゴミ袋へと行ったのか、
僅かな可能性の話だが、倉庫のおもひでダンボールの奥底に眠っているとも限らないかもしれないが。
とにかく今となっては、私の目に見える場所にはない。あの連夜が夢か幻かも確かめる術は無い。
結局あれが何だったのか、分からないのは申し訳ないが、
きっと私が勇気ある少年だったとしても暴く事は叶わなかったのだろう。
何せ指である。聞いて口が聞けたらギャグだ。
しかし、その後御祓いなどをしたわけでもなく、
それ以上の指に纏わる怪現象を体験することはなかった。
あの神社には、夏祭りにでも寄った際、拝殿に静かに手を合わせ、あの指の成仏を願ったのみである。
以上、昔の記憶を書き起こしたものなので多少文章にするにあたり仮構の部分もありますが、
帰省先の田舎の伝説でもなければおどろおどろしい顔の女でもないですが
ここの趣旨に合った話であれば幸いです。
あまりオカルトテイストな文章だと胡散臭いと思ったのですが、
文面に工夫が無くて申し訳ない。
話自体は飛びぬけたものではありませんが、
同じような話があると、面白いですね。長文お邪魔した。もし足元に指がいたらよろしく。

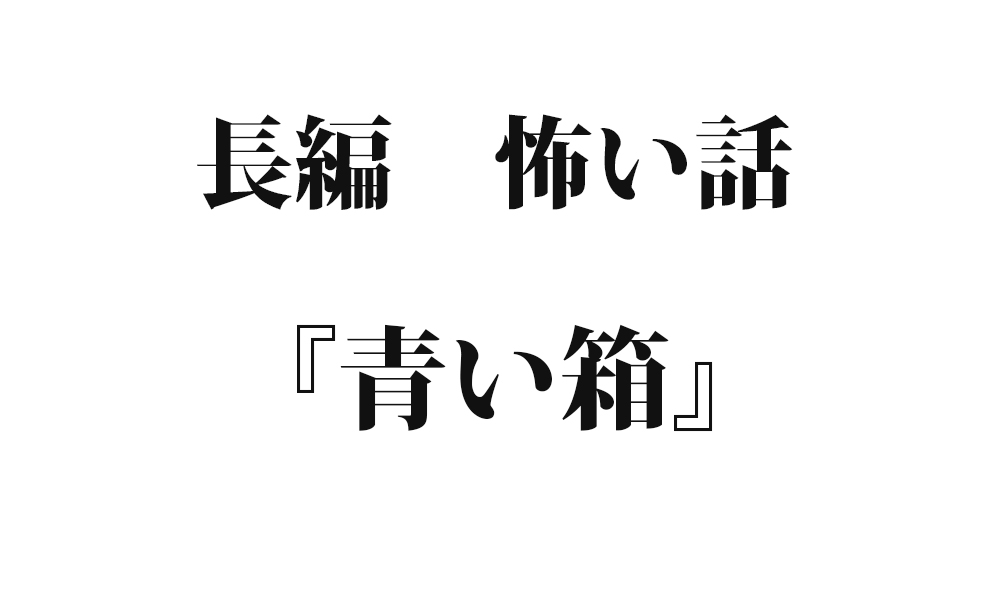

コメント