先輩と葬式
一年の頃。
葬列を見た。
誰かの棺を、何人もの喪服の人が運んでいる。
後ろでは親類らしきおばさんが涙を流している。
皆それぞれに沈痛な面持ちをしていた。
棺を積む霊柩車が止まっている。
俺はそっと親指を隠した。
列の中の一人、小さな男の子がこっちを見ていた。
五歳くらいの、見たことがある子だ。
お父さんが死んだのかな、と、なんとなく思った。
喪服は、日に照らされてとても暑そうに見えた。
「へぇ、どこで」
先輩はペン回しをしながら聞く。
興味があるのか無いのかわからない感じだ。
しかもペン回しは失敗している。
さっきから何度もペンを落としていた。
「あそこですよ。立体交差の所の、床屋の向かいです」
昨日、下校中に見た葬列のことを話してみた。
放課後の図書室は相変わらず利用者が少なく、いつもの眼鏡の図書委員が貸し出しカードの整理をしている。
「ふぅん」
ペン回しを続ける。
一度たりとも成功していない。
くるっ、がちゃん。
くるっ、がちゃん。
出来ないのならやらなければいいのに、と思っていると、先輩の動きが止まる。
□ □ □
「こういう話がある」
先輩はペンを置いて俺のほうを見る。
「葬列が歩いてくるんだ。遺影を先頭に、棺を囲んで。それを男女のペアが目撃するんだ。男の方には遺影が見えないが、女の方にははっきり見える」
俺は聞きながら、昨日の葬列を思い出していた。
遺影は、泣いていたおばさんが持っていたが、それに写っている人物までは見えなかった。
「女は言うんだ。今の遺影、私のだった。これは私のお葬式だったんだ。翌日、女は死ぬ。それから男はまた葬列を見る」
細部までは思い出せないが、男の子の視線だけははっきり覚えている。
どことなく退屈そうな、でも無表情な瞳が俺をじっと見ていた。
「その葬列の先頭は死んだ女だった。その女が遺影を持っていたんだ。その遺影には、男が写っていた」
ひとしきり語ると、先輩はまたペンを持ち、ペン回しの練習を再開した。
俺は必死に昨日の遺影を思い出そうとする。
通りすがりに見ただけだし、細部までは見ていなかった。
どうしても思い出せないでいると、先輩はくすくすと笑った。
「漫画の話だ。お前の見たのは、実際にあった葬式だろう。おかしな所は何も無い。何もな」
俺はほっと息をつく。
この人が言うと冗談に聞こえないから困る。
ありがちな怪談も、語る人間によっては恐ろしい事実に聞こえるのだ。
どうやら俺はからかわれただけらしい。
「必死に考えちゃいましたよ。遺影はあったんですけどちゃんと見て無かったんで。あんまり脅かさないでくださいよ」
先輩のくすくす笑いが止まり、唇の端をぐにっと持ち上げる笑顔になった。
細めた目の奥、瞳が深い色をしている。
嫌な予感がした。
この顔は、良くない。
「そうだなあ、見えなかったなら仕方ないな。そんな通りすがりに見ただけなのに、印象に残っていることは無いかな?俺に話している最中、他が全部あいまいなのにそこだけきっちり描写できた部分は?」
□ □ □
男の子の目が浮かぶ。
はっきりと、脳裏を埋めるように。
「まさか、印象に残っただけでしょう。ほんと、ずっと見てたんですよ、男の子が」
先輩はペンを回す。
くるっと回ったペンは、なにやら複雑に指の間を回り、手のひらに帰って来た。
どうやらとんだ高等テクを練習していたらしい。
「そこじゃない。お前は葬式を昨日の下校中に見たんだろう。なのに何て言ったか。暑そうだった。日に照らされて。昨日は、曇ってただろうが」
記憶を辿るまでもなく、確かに空は重い灰色に包まれていたのを覚えている。
だが、確かに見た。
葬式に参加している人達は、皆黒い喪服で、その喪服が日に照らされて酷く暑そうだったのを。
「一番最近、あそこであった葬式は今年の夏のことだ。確かにあったんだよ、葬式はな。ただ、お前が自転車で走っていたのは、いつだったんだろうな」
愕然としている俺を、にやつきながら見ている。
俺は、いつの葬式を見ていたのか。
俺と自転車は、どこを走ったのか。
「ああ、それとな」
先輩は思い出したように言う。
俺はもはや何かを言う元気が無かった。
「死んだのは、親父じゃない。その夏の葬式、送られたのはあそこの長男だ。お前は知らなかったみたいだが」
確か、えらく高齢になってから出産した子供がいて、その子の歳が五歳くらいだったはずだ。
昔、家の前の道路で遊んでいたのを見たように思う。
その朧な記憶は、どうやら間違いなく昨日の少年と合致しそうだった。
「いやあ、珍しい経験したなあ。時間を越えて、しかも死人に見つめられるとは。すごいなあお前」
笑う先輩を、図書委員がうるさいと叱った。
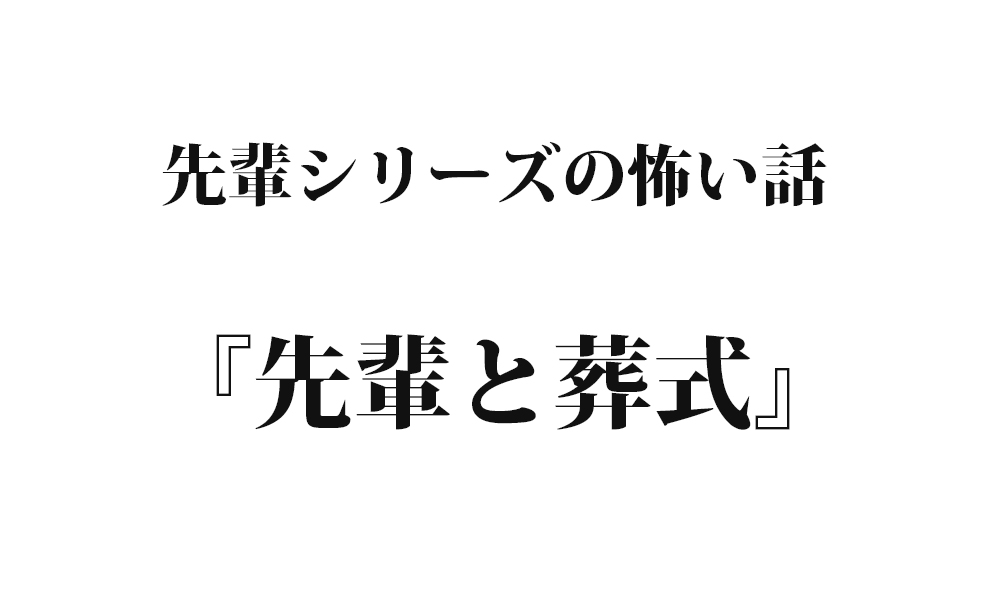
コメント