先輩と飛び降り
二年に上がった年の、梅雨のことだった。
俺の地元では、梅雨とは言うものの雨はほとんど降らない。
期間中に三日降ればいい方だ。
しかし空気は相応に湿っていて、特有の息苦しさを感じるのだった。
そんなある日。
じめじめと鬱陶しい空気の中、じめじめとした表情をしながら自転車をこぐ。
雨は好きじゃない。
雨が降りそうな日も好きじゃない。
必然的に梅雨時期は俺の気分も曇る場合が多い。
学校が終わり、家に帰る道のりで、ビルの前を通る。
都会にあるような高層ビルと比べれば、ビルを名乗るのもおこがましいような慎ましい建物だが、一応、5階まであるビルである。
そこを通った時、不意に上から声が聞こえた・・・・・・気がした。
ブレーキをかけて上を仰ぐ。
口を大きく開いて、「あ」という声が聞こえてきそうな表情をした女性が、
ビルの上から、降ってきた。
□ □ □
「で、落ちたはずの女はどこにも居なかったと」
先輩は楽しそうに俺の話を聞いてくれた。
「はい。まあ、波長があったって奴だと思います。何か知りませんか」
昨日、空から降ってきた女性は最初からいなかった。
俺程度では滅多にないことだが、そういう感覚の強い人はたまに『残留思念』を目撃するらしい。
あれは多分過去にあった飛び降りの映像なんだろう。
「お前はあれだな。ちょっと地元のニュースに目をやるべきだな。ちょっと待ってろ」
押入れに頭を突っ込んで奥を探る。
先輩のアパートの押入れは魔境だ。
よくわからないお札や、まず何なのかがわからない塊なんかが多数入っている。
先輩はその中から、ごく普通のファイルを取り出した。
「何ですか、それ」
先輩はファイルのページを適当に開き、ぱらぱらめくっていく。
「スクラップぶーっく。確か二週間くらい前の記事だ。・・・・・・あった」
小さい記事だ。
28歳の女性が自殺。場所は・・・・・・あのビルだ。
「俺は死亡事故だとか自殺だとかの記事は基本的にまとめてる。たまに役立つこともあるんだ」
一般人に話したら確実に引かれるだろう。
こんなアパートに住んで、食費も徹底的にケチる先輩が、新聞を取っている意味がわかった。
「で、多分この女で間違いないだろう。年齢とか、服装とか、そういう所に矛盾もないだろ」
確かにそうだった。
年齢も多分そのくらいだろうし、俺の見た女性は制服を着ていた。
記事には残業中に・・・・・・と書いてあったので、恐らくその時制服を着ていたのだろう。
「あ、でも」
表情は。
あの表情は、思いつめての自殺では無いように思えた。
どちらかと言うと、驚いているような。
「そうだな。お前の見た女は自殺する時の表情では無かっただろう。まあ、ここでぐだぐだ言っても仕方ない」
先輩は立ち上がる。
「行くぞ、現場」
楽しそうな先輩に続いて、俺も立ち上がった。
□ □ □
「すみません。お聞きしたいんですけど」
滅多に見ない他所行きの笑顔で先輩はビルの受付に話す。
「私、雑誌の記者をやっている者なんですけども、二週間前の事件の取材をさせて頂きたくて伺ったのですが」
出鱈目だ。
普通ならこれは信用されないだろう。
先輩は何事かこそこそと喋っているが、恐らく門前払いだろうと思った。
しばらく話した後、先輩が一礼した。
「では、失礼します」
おい、行くぞと言うと先輩はずんずん階段を登っていく。
俺は慌てて追いかけた。
「先輩、どうしたんですか、今の。まさか本当に信用してくれたんですか」
「いや、幽霊が出るって噂があるって言っただけだ。あのおっさん、そういう話が大好きらしくてな。ろくすっぽ話も聞かずに通してくれたよ」
呆れる話だ。
まあこのあたりは田舎特有の無警戒感があるから、警備もそのくらいなのかもしれない。
「で、何を話してたんですか」
うん、と頷いて先輩は笑う。
さっきの他所行きの笑顔とは違う、いつものにやけ面。
「まず、屋上以外には立ち入らないことを言われた。それから、詳しい話を教えてくれた。彼女、最上階の事務所に勤めてたらしい。明るい子だったからまさか自殺するなんて、だとさ」
なるほど。
「受付のおっさんのお気に入りらしくてね。帰り際なんかにいろいろ話してたみたいだ。例えば、誰もいない屋上から話し声がする」
そうか。
いくら安普請のビルでも屋上で話している声が下階に聞こえるわけがない。
要するに、それが彼女の自殺・・・・・・いや、もしかしたら他殺の犯人かもしれない。
「おい、あのドアが彼女の事務所だ。もちろん天井はそんなに薄くない」
そして、もう一階あがると。
「で、これが屋上へのドア。開けるぞ」
がちゃり。
□ □ □
テンプレートな屋上。
コンクリートの床に、申し訳程度の転落防止用鉄柵。
柵に途切れている部分は無かったが、乗り越えようと思えば子供でも可能だろう。
「思ったより普通ですね。やっぱり自殺だったんでしょうか」
先輩は無言だ。
つかつかと歩き、屋上の真ん中あたりに立ち、手招きをする。
俺は従って隣に立った。
「お前、何とも無いか」
はぁ、と気の抜けた返事をする。
何も見えないし何も聞こえない。
「なるほど、彼女は波長が合ったのか、それともかなり強い人だったのか。とにかくそれなりの才能はあったらしい。そりゃ飛ぶ」
先輩は無表情に言う。
心なしか口調が緊張していた。
「おい、帰るぞ。全部わかった」
先輩は早口に言うと、早足に屋上を去った。
俺はまた慌てて追った。
□ □ □
「で、この話にどうオチをつけるんです」
アパートまで戻って先輩に言う。
「お前には見えなかったみたいだしな。じゃあ説明しようか。あの屋上、どういう因果か信じられない量の・・・・・・色んなモノがいる」
あの、殺風景な屋上に。
俺に見えないような物達がひしめいていたと。
「それこそ立っているスペースが無いくらいだ。彼女は多分、屋上の声を辿って行った結果、そいつを見てしまった」
あ、もしかして。
「逃げたんですか。咄嗟に」
先輩がその通り、と右手で顎をなぞる。
「俺があそこに立った時な。そいつらが急にふくらみ始めた。風船みたいに。俺が帰る頃には、あの屋上からはみ出すほどだった」
俺は想像する。
屋上から聞こえる奇妙な話し声。
暗くなってからの残業で事務所に一人。
気味が悪くなって彼女は奮起する。
『あの声の主を突き止めよう』。
彼女は屋上に上がり、隠れられそうな場所を探す。
もちろんそんな場所は無いが、その間にあそこにいるモノが膨張を始める。
ふと気付くと、得体の知れない何かが自分のすぐ近くに迫っている。
彼女は慌てた。慌てていると、ビルの前の道を車が通る音がした。
それに気付いてもらおうと、鉄柵を乗り越え、身を乗り出した時。
「事故、だったわけですね。それで、驚いた顔を」
「そう、事故だ。ただ、彼女が普通の人間なら起こらなかった事故でもある」
俺は疑問に思った。
何故そんな事を言うのだろう。
先輩だって見える側だし、俺だって多少は見える。
その能力がまるで悪いみたいに。
□ □ □
「お前は多分わかってない。本来見えないモノが見えるっていうのは確かに才能だ。だけどそれは決してプラスに働かない。普通に生きるには、邪魔なんだ。むしろ」
頭の中がフラッシュする。
なんとなく、先輩は自分の才能を誇っているのだと思っていた。
なぜならそれは俺にとって憧れであり、その頃欲しかった物だから。
憧憬があった。
見える人達に、無条件の。
でも、当人達はそれを足枷に思っている。
天地が逆転するような感覚に襲われる。
「お前は俺の後輩だけど、出来るなら俺を追うな。俺の見てる世界は、普通じゃない」
「でも、それでも俺は」
先輩は人差し指を立てて制止する。
「それでも、とお前が言うなら、いつかそれを選択する時がくる。必ず来る。その時お前が、それでも、と言うなら」
続く先輩の言葉を、俺は忘れない。
これから起こる出来事を、先輩は多分予測していたのだろう。
それを知るのはもっとずっと後だけど、その言葉は俺の芯にじくりと染込んだ。
外は薄暗く曇っていて、滅多に降らない雨がぽつぽつと降り始めていた。
俺はお前に、心ばかりのおくりものをしようと思う・・・・・・。
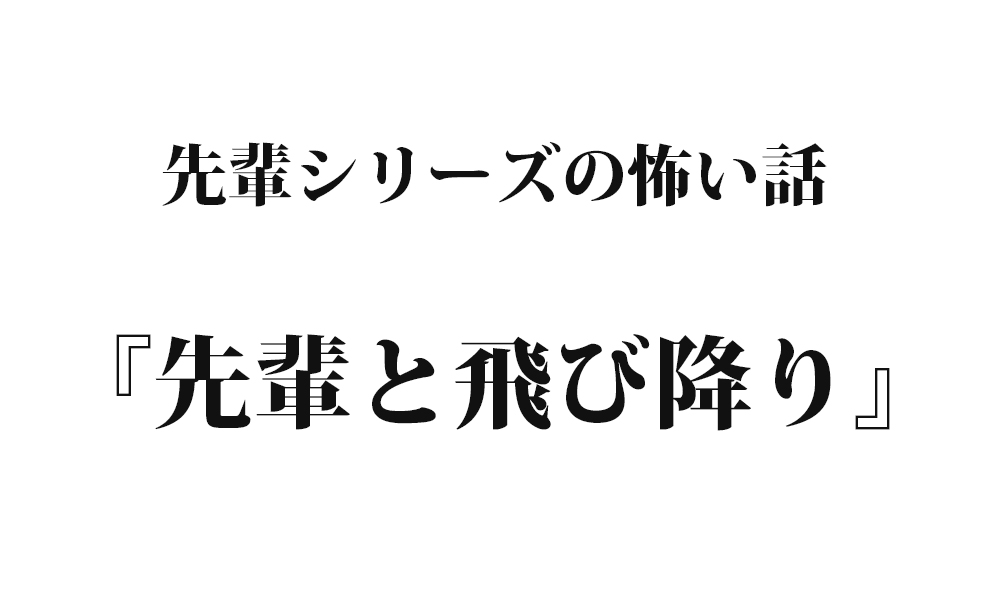
コメント