『心霊写真 4』
157 :心霊写真4 ◆oJUBn2VTGE :2013/03/15(金) 21:47:17.85 ID:ArcSp/qC0
「じゃあ、わしはこれで。でも、加奈ちゃん、頼むよ。ほどほどでね」
住職が襖を開けて出て行こうとする。電球の明かりに、脂ぎったハゲ頭がやけに照り返している。
夏雄とアキちゃんの父、黒谷正月(しょうげつ)は名前のとおり正月が誕生日という生まれついてのおめでたい男だった。
親から寺を継いだものの、除霊だの焚き上げ供養だのといった胡散臭いことに商売っ気を出し、
地元の檀家衆にも呆れられているそうだ。
それだけでなく、麻雀やパチンコ、競輪に競艇といった賭けごとが大好きで、
伝来の仏像を密かに質入れしたことがあるという逸話を持っていた。
また、酒は人後に落ちないほど飲むし、女遊びも大好きというまさに生臭坊主を地で行く男であり、
奥さんにはとっくに見切りをつけられ、離婚こそしてないが別居状態なのだと言う。
小川所長はその奥さんの弟で、所長からすると夏雄は甥っ子ということになる。
「いいから、早く行けよ」
夏雄に邪険に言われ、正月和尚はすごすごと出て行った。
袈裟の裾が襖に挟まり、「あれ?」という声が襖越しにしたかと思うと、
ぐいぐいと袈裟の端が向こう側に引っ張られて消えていった。
その滑稽な動きに、アキちゃんがクスクスと笑う。
ここは本堂ではなく、黒谷家の住居部分の一室だ。庭に面した畳敷きの広い部屋だった。
旅館にあるようなテーブルが真ん中にあり、僕らはそれを囲んで座布団に腰を下ろしていた。
身体が弱いらしいアキちゃんはついさっき正月に見つかり、昼食の後に飲む薬を飲まされて顔をしかめていたが、
機嫌は直ったようだった。
「だめだよ」
正月和尚の足音が去った後で、アキちゃんは笑いながら小さくそう言った。
僕はまた変な感覚に陥る。
さっきヒノキの下で、「またきたね」と言って誰もいない場所を見ながらしきりに頷いていた。それと同じだ。
怪訝な表情を浮かべる僕に、師匠はこう訊いてきた。
「今、この部屋に何人いるか分かるか」
それを聞いて、思わずテーブルについている人間の顔を順番に眺める。
師匠。夏雄。アキちゃん。そして僕。
「四人ですけど」
その答えを確認してから、師匠は夏雄にも同じことを訊いた。
夏雄は、興味なさそうな顔をしながらも、ボソリと言った。
「七人」
はあ?なんでそうなるんだ。
僕は部屋の中をもう一度見回したが、テーブルの回りに座っている人間の他には誰もいなかった。
「惜しいな。八人だ」
師匠はニヤリと笑う。そして僕の方を意味深に見つめる。
霊のことか。
目に見えないそういう存在の数も含めてだと。そういうことなら、僕だって……
視覚ではなく、別の感覚を拡張させ、意識を集中する。
部屋中にその感覚の根を張り巡らせ、人ならぬものの気配がわだかまっているような場所を見つける。
天井付近。なにか、いる。彷徨うものが。
しかし見つけられたのはそれだけだった。僕らと合わせて五人。
しかし夏雄は七人と言い、師匠は八人と言った。これはどういうことなのか。
師匠は続ける。
「と、言いたいところだけど。わたしの答えが正しいとは限らない。さて、おひい様にお訊ねしてみましょう」
慇懃な態度で、師匠はアキちゃんの方に向き直った。そして「今、この部屋には何人いますか」と訊ねる。
アキちゃんは目をぱちぱちとさせ、自分の横にいる夏雄から順に指をさして数え始めた。
「ひい、ふう、みい、よう、いつ、むう、なな、やあ、ここの、とお……」
指先はテーブルから外れ、なにもない壁際まで進んで、また少し角度を変えながら戻ってくる。
「……にじゅいち、にじゅに、にじゅさん、にじゅし……」
二十七のところで僕を指さし、そのままその小さな指は何もない空間に向かって動き続ける。
「ああ、もういい。もういい」
師匠はアキちゃんを止めた。
え?
なにこれ。
僕は尻の座りが悪くなる感じに襲われ、そわそわしてきた。
何を数えた。何を数えたんだ。
古い木造住宅の匂いが満ちる部屋。
庭に面し、窓ガラスの向こうから爽やかな光が差し込む部屋に、全く別の部屋が重なっているような気がした。
白と黒。ネガとポジ。
そこに、何がいるのか。
だが、そのぞわぞわした感覚はあまりに希薄で、
庭に遊んでいる小鳥たちがチチチ……と鳴くたび、僕はごく当たり前の風景の中にいる自分に気づく。
「幽霊を信じない人間は、よくこう言うな。
人間が死んで幽霊になるんなら、そこらじゅう幽霊だらけになってしまうじゃないかって。
……そうだよ。幽霊だらけさ、この世界は。
あとは見えるか、見えないかの問題があるだけだ」
師匠は天井の隅を指さした。僕にも感じられた場所だ。
「ああいう、強いのもいれば、そことか、こっちみたいな弱いのもいる。
残された思念の濃さと、それを受け取る側の精度によって、幽霊と認識されるかどうかが変わってしまう。
ランドルト環って知ってるだろ。視覚検査で使う、Cみたいな形の切れ目のある円だ。
お前には、一番下の列にはただ小さな円か、あるいは点が並んでいるようにしか見えないかも知れない。
けど見える人間には、すべて下向きや横向きのCに見えるんだ」
おい、夏雄。と師匠は僕から視線を外して呼びかける。
「見えてるのは、どれだ」
夏雄はむすっとしたまま、今師匠が示した三ヶ所をなぞるように指さしていった。
天井と、奥の箪笥の端と、押入れに張ってあるカレンダーのあたり。
僕には、天井以外なにも感じられなかった。額から嫌な汗が出てくる。
「四足す三で七人か。惜しいな。箪笥のところは、重なるみたいにしてもう一人いるぞ」
師匠がそう言うと、夏雄は「あん?」と眉を片方上げ、「そうかもな」と欠伸をした。
座布団の上で片膝を立て、腕をその膝の上に乗せている。
客を前にしてするような態度ではなかったが、キチンと座っているところが想像できない男でもあった。
「残された死者の思念に、最初から強い弱いはある。
それだけじゃなく、時間が経つにつれ、だんだんと薄れていく。経年劣化だ。
よほど強い後悔だとか、恨みだとかを持っているやつでも、いずれは消えていく。
逆に言うと、今でも見える古い武士の霊だとかは、マジでやばいやつだ。
でもその消えていく、ってところにこそわたしや夏雄の限界がある」
師匠は部屋中を見渡すように右手を広げた。
「実際には、消えてないんだ。たぶん。ただ受け取り手の精度が低いせいで、見えなくなっているだけだ。
一番下だと思っていたランドルト環の列の下に、まだ列があった。
見えない人間にはただの空白にしか見えないひと列が。
そういう、存在が極めて薄くなった霊が、この世には満ちている」
僕はふと、虹が頭に浮かんだ。
あの七色の虹は、実際には七色にはっきり分かれている訳ではなく、
赤から紫までの滑らかな光のグラデーションで出来ている。
国や地方によって、虹の色を七色と言うこともあれば、五色、三色、そして二色と捉えることもある。
僕はこの部屋のそれを五色と捉え、夏雄は七色、そして師匠は八色に見分けたのだ。
けれどアキちゃんは、僕らが見分けた色と色の間のさらに微細な狭間を見分けている。
それも、とてつもない数にだ。
何十、何百色という極彩色に。
自分を前にして繰り広げられるなにやら小難しい話を、アキちゃんはふんふんと頷きながら聴いている。
あれほど霊感の強い師匠にも見えない霊を、この子は見ているというのか。
そう言われても信じられない気持ちだった。
「例えば、わたしには薄っすらと顔だけが見える霊でも、この子には全身が、それも服の柄まで綺麗に見えている。
何百年も昔の霊だってそうだ。
経年劣化で、ほとんど思念も散って薄くなり、もうこの物質的な世界となんの関わりも持てなくなった霊。
こちらから見ることも触れることも出来ず、あっちから影響を及ぼすこともできない。
そういう存在は、もうこの世から消えてしまったのだと言ってもいいと思う。
でもそういうわたしたち常人の定義する世界と、ほんの薄皮一枚のところに別の景色が広がっているらしい」
常人と来たか。あの師匠が。
だったら僕などなんだというんだ。
「この子の限界がどこにあるのか知りたくて、見えているものを聞き取って似顔絵を描いたことがあるんだ。
片っ端から描いてると、いるわいるわ……日本史の時間で習ったような日本人の古い服装のオンパレードだ。
何百年どころじゃないぞ。確実に奈良時代までは遡れる」
どこまで本当なのか分からないが、師匠は興奮したようにそう言うのだ。
「しかし、古墳時代の霊は見当たらなかった。
単に当時の人口が少ないから、それと遭遇する蓋然性の問題なのかも知れないが、
あるいは、そのあたりがこの子の限界なのかも知れなかった。でもな」
師匠は少し声を落とした。
「似顔絵の中に、土器の時代や、石器時代の人間らしい姿もあるんだ。
それがもし正しいなら、古墳時代の霊だけがすっぽりと抜け落ちていることになる。
これは、非常に興味深いことだ。なぜかわかるか」
「さあ」
素直にかぶりを振った。
「黄泉(よみ)という思想のせいだよ。
これは現代でいう、いわゆる『あの世』とは少し違う。そういう、肉体から離れた魂がたどり着く場所のことではないんだ。
黄泉は黄泉比良坂(よもつひらさか)で葦原中国(あしはらのなかつくに)、
つまり日本国と地続きで繋がっている、もう一つの世界なんだ。
そこは生者の住む国の隣にある、死者の住む国であり、死とは、その移動のことを指している。
つまり、黄泉という思想をメンタリティとして持っていた時代の日本人にとって、
死とは肉体を持ったまま黄泉へ行くことであり、
この生きるものの世界に霊だか魂だかとして迷う、なんていう発想自体がないんだ」
妻であるイザナミを黄泉へ迎えにいったイザナギが、もし葦原中国へ彼女を連れ出すことに成功していれば、
それは肉体を伴った黄泉返り(よみがえり)であり、
死者が生者の世界にやってくることは、すなわち生者になるということだ。
だから幽霊なんていうあやふやなものはありえない。
師匠は秘密を明かすように演技掛かって言う。
「この子の目で見ても、そんな時代の人間の姿がどこにも見当たらないんだ。面白いだろう」
嬉しそうに語る師匠に、夏雄が「ケッ」と言って水を差す。
「用件をとっとと済ませろよ」
師匠には悪いが、僕もこれには同意だった。
興味深い話ではあったが、今はなにしろ今夜九時までに写真のことを調べて松浦に報告しなければならない。
時計を見ると、昼の三時を回っていた。あと六時間か。
師匠は分かったよ、というジェスチャーを返しながら、アキちゃんに話しかける。
「さっきお父さんの袈裟を襖に挟んだのは、お友だちか」
「えー」
アキちゃんは隣のなにもない空間に向かって、イタズラっぽい顔で人差し指を口に立てる。なにかいるらしい。
シーッ、ということか。もちろん僕には全くなにも見えない。
「ひーちゃん、だっけ。夏雄、見えるか」
問われた夏雄も、首を左右に振る。
アキちゃんには、無数に見える霊の中でもひーちゃんという仲の良い友だちがいるそうだ。
もっとも本人は、人間と霊とをあまり区別していないようだったが。
そのひーちゃんは夏雄にも、師匠にも見えないので相当存在の希薄な霊のはずだが、
さっきのように現実に物質的な影響を及ぼすことがあるので不思議なのだそうだ。
そんなことが出来る力の強い霊なら、少なくとも師匠には見えてしかるべきなのに。
「あー、まあいいや。ひーちゃんに、今日はもうイタズラしちゃだめだって言っといて」
アキちゃんは頷いて、顔を横に向けて何ごとか囁いた。
ついさっき、あれほど師匠を嫌っているような態度を取っていたのに、今はやけに素直だ。
後から聞いたのだが、僕という知らない人間が一緒にやって来ていたので、興奮していたらしい。
普段師匠だけで来た時はほとんど喋ってくれないこともあるのだそうだ。
「さて、本題だ」
師匠はそんなアキちゃんの様子を伺いながら、リュックサックから封筒を取り出した。
そして中に入っていた五枚の写真をテーブルの上に並べる。
田村に押し付けられた一枚と、松浦から押し付けられた四枚。
いずれも、数時間前に写真の専門家から心霊写真ではないという結論を下された写真だった。
夏雄とアキちゃんが二人して身を乗り出すように写真を眺める。
「ええと、これはですね」
視線で説明を求められているのに、何も喋ろうとしない師匠に代わって僕が口を開きかける。
しかし、小突かれてそれを止められた。
「細かいことはいいよ」
師匠がそう言うと、夏雄も頷いた。
「ああ。こっちもくだらねえこと聞いて、無駄に関わりたくねえ」
「そう言うと思ったよ。アキちゃん。頼みがあるんだ。あれやってくれないかな。あれ」
師匠はそう言って、右手を写真の上にかざし、撫でるような仕草を見せた。
アキちゃんは師匠と写真を交互に見た後で、夏雄の顔を伺う。
「おい。あれは後から疲れが出るんだよ。簡単に言うな」
夏雄が強い口調でそう言うと、師匠は顔の前で両手を摺り合わせる。
「五枚だけ。五枚だけだから。な、アキちゃん」
そう振られて、アキちゃんは慎重に頷いた。
夏雄は舌打ちをした後、厳しい顔をして、「本当に大丈夫か」と妹に訊ねる。
「最近、元気だし」
黒髪の少女はにっこり笑ってそう言った。
そうしてちらりと僕の方を見て、照れたような表情を浮かべる。
なにをするのだろう。
僕は興味深々で、目の前の展開を見守った。
夏雄は立ち上がり、窓の雨戸を閉め始めた。
師匠は箪笥の上にあった蝋燭を持って来て、マッチで火をつける。
外の明かりを閉め出して、部屋の電気を消すと、蝋燭の光が大きくなった。
重そうな燭台に蝋燭を刺し、それをテーブルの真ん中に移動させる。
襖からの微かなすきま風に火が煽られて、照らされている写真たちが瞬くように揺れる。
なんだかゾクゾクしてきた。
ごく普通の写真でも、こんな風なシチュエーションで見せられたら、なんとも言えず不気味な感じになるだろう。
「じゃあそっちの端から」
ちょうど『写真屋』に見せた時の順に、写真は並べられている。
師匠の言葉にアキちゃんは頷き、少し緊張気味に右手を写真の上にかざした。
飲み会の風景を写した一枚だ。蝋燭の仄かな明かりが小さな手のひらで遮られ、その下の写真は暗くて見えなくなる。
だがそれも一瞬だった。アキちゃんが手のひらを空中で撫でるようにくるくると回したかと思うと、スッと引いたのだ。
蝋燭の明かりの下に写真が再び現れる。
だがその瞬間、なにか力というか、精気というか、そういう目に見えないエネルギーのようなものが、
目の前で消失したような感覚がして、僕はゾクリと鳥肌が立った。
なんだ。
なんだか分からないが、今、確実になにかが起こった。
僕は写真に目を落とす。飲み会の写真に異変はない。一体なにが起こったのか。
「よく見ろ」
師匠が僕の耳に囁きかける。
「一番左の、白髪のおじさん。目を閉じてるだろう」
そう言われてみると、両目を閉じていた。ストロボに目が眩んだのだろう。
しかし次の瞬間、師匠がその写真を手に取ってなにかを振り払うように空中で数回振った。
そしてもう一度、テーブルの上に置く。
やはり写真の中の飲み会の風景に異変はなかった。いや……
僕の目は一番左の人物に釘付けになる。白髪の男性は目を開けていた。さっき閉じていた姿が、まるで嘘のように。
「最初から目は開けてたよ。覚えとけ、そのくらい」
意味が分からない。手品かなにかなのか。
腑に落ちない僕に、師匠は続ける。
「この子の力だ。誰にも真似は出来ない。その一瞬を永遠に記憶するはずの写真に、後から影響を与える」
死者が、目を閉じるんだ。
師匠はそう囁く。
「今現在、死んでいる人間は写真の中で目を閉じる。そして写っているのが霊的なものであれば、ある変化を起こす」
師匠はアキちゃんに合図をする。
アキちゃんは次の写真に手を伸ばす。そして先ほどと同じように手のひらを回して、スッと引いた。
海辺の家族連れの写真だった。
今度も一見なんの変化もない。両親と子どもの顔を見たが、目は開けたままだった。消えた右膝から先もそのままだ。
師匠が頷くと、アキちゃんは次の写真に手をかざした。
アイスクリームを手にピースサインをしているカップルの写真だ。
二人とも目を開けたままで、女性の肩に乗った誰のものとも知れない手にも異変は見られなかった。
次の、家の前で撮影された写真では、母親が目を閉じた。記憶でも確かに目は開けていたのに。
家の窓の内側に薄っすらと写る男には異変がなかった。
顔はなんとなく見えるが、目元がどうなっているか元々判然としていないので、
閉じているか開けているかは分からなかった。
ジジジ……
蝋の匂いに混じって、埃が焼ける匂いがした。明かりが揺らめき、テーブルの上の写真に微妙な濃淡を与える。
蝋燭に気を取られた後で、写真に視線を落とすと、母親の目はいつの間にか開いていた。何ごともなかったかのように。
僕は目を擦る。そうしてぱちぱちと何度か瞬きを繰り返す。
「錯覚だ」
思わずそう呟くと、師匠はおかしそうに頷く。
「そのとおりだ。錯覚だよ。こんな蝋燭の頼りない明かりの下でしか起こらない、幻だ」
心霊写真はなかったな。 師匠はまた囁いた。その、ある変化というのが起こっていないからか。
そして……
僕らの視線は最後の一枚に向けられる。
横浜にあった角南家の別邸の一室で、
『老人』を真ん中に、その彼を慕うようにして十人の陸軍青年将校たちが周囲に座る写真。
情報屋の田村が『近代日本史の闇』と称した、あってはならないはずの一枚。
その写真に、アキちゃんはゆっくりと手を伸ばしていく。
僕の心臓は嫌な音を立てている。一歩も動いていないのに、呼吸が乱れる。
なにか、恐ろしいことが起きる予感に襲われて。
蝋燭の明かりが手のひらに遮られ、そしてまた写真が僕らの眼下に現れる。
精気が、エネルギーが抜き取られるように消えた。
その消失感に僕はゾッとする。まるで自分の血を大量に注射針で抜かれたかのようだった。
写真の中の全員が目を閉じていた。揃って、黙祷でもしているように。寒気がした。
アキちゃんが怯えたような声で呟く。
「閉じない」
そうしてもう一度写真に手をかざす。同じような動きをして、また手を下げる。
「閉じない」
また同じ動作を繰り返した。
「どうして」
声が震えている。僕は思わず写真を食い入るようにして見つめる。
なんだ。いったいなにが。
ハッとした。
全員が目を閉じていると思ったが、それは間違いだった。ただ一人だけ、目を開けたままの人物がいたのだ。
一番左の隅に座る男。その襟には軍隊における階級を表す、五本の縞と三つの星。
正岡哲夫大尉。優秀な軍人で、仲間のうちでも最も昇進が早く、彼ら青年将校たちの間の実質的リーダーだった男。
そして、その写真が撮られる、少なくとも二ヶ月以上前に死んでいた男。
得体の知れない感覚に、体中がざわめく。
どういうことなんだ。
戦時中、大逆事件を起こしたかどで、秘密裏に処刑されたという若き将校たち。
そして角南家の当主として君臨し、政界や財界に影響を及ぼし続けた後、今から十数年前に死んだ『老人』。
それらがすべて目を閉じているのに、なぜ正岡大尉が目を開けたままなのか。
死んでいるはずのこの男が写ってしまっているからこそ起きているこの騒動だというのに。
僕は混乱し、師匠の顔を伺う。
さすがに難しい表情を浮かべていたが、ゆっくりと口を開くと、こう言った。
「こいつは、生きている人間じゃないな」
正岡大尉を指さす。
いや、ちょっと待て。死んでいないからこそ、目を開けたままなんじゃないか。それも一人だけ。
僕の困惑を他所に、師匠は続ける。
「こいつは、死者でも生者でもない。作り物だ。だから、目を閉じない。そうだな?」
確認するように問われ、アキちゃんは首を傾げた後、小さく頷いた。
僕は驚いた。作り物?それはどういう意味なんだ。
写真の偽造のことかと思ったが、写真の専門家があれだけ明確に否定したのだ。それはないように思えた。
ハッとする。人形?精巧な人形が置かれていたのか。
いや、どう見ても普通の生きている人間にしか見えない。そんな人形を作る理由も思い浮かばない。
まさか、この記念写真のためだけに?だったらなおさら座る位置がおかしい。
不慮の事故で、天皇襲撃計画の決行を前に命を落としたリーダーを偲んで、
こうして人形を作り一緒に写真を撮ったというのなら、こんな隅の方に追いやっていいわけがない。
『老人』の隣にいてしかるべきだ。
「Nengraphy……念写だな」
僕は考えがまとまらないうちに、師匠の口から出たその言葉に二の句が継げなかった。
念写だって?あの、ポラロイドカメラを使って目の前にない東京タワーとかを写す手品のことか。
いや、師匠の口ぶりは本当に超能力、あるいは超常現象としての念写を肯定している感じだ。
「そんなことが本当に出来るんですか」
師匠は頷いて、アキちゃんを見た。すると隣の夏雄が強い口調で「駄目だ」と言った。
そのやりとりを傍で見ていて、僕は裏の意味を悟る。唖然としてしまった。
「アキちゃんは、出来るんですね」
「今日はもう駄目だ」
僕に、夏雄の冷たく殺気立った言葉が突きつけられる。
その瞬間、蝋燭の火が消えた。
「あ」
室内は暗くなる。まだ蝋燭の長さは十分にあったはずなのに。
僕は驚いて、一体なにごとが起こったのかと身構える。
闇の中に「ダメだよ」という小さな声が聞えた。ゾクリと、鳥肌が立った。
ついでカチカチ、という音とともに電球の明かりがつく。
師匠が電球の紐から手を離し、すぐさまテーブルの上の写真に取り付く。
姿のない何者かにそれを奪われることを防ごうとするかのようだった。
写真は五枚とも無事だ。
師匠は溜め息をついて、アキちゃんの方を非難するように見た。
「ひーちゃんか。今のは」
ひーちゃんという目に見えない何者かのイタズラだというのか。今の蝋燭が消えたのは。
アキちゃんは頷きながら、疲れた表情を浮かべる。
僕は、さっき蝋燭の明かりの中で見た幻……写真の中の人物が目を閉じるという錯覚のことを思い浮かべた。
あの時、なにかのエネルギーが目の前で消失する感じを受けたが、
あれはひょっとすると、アキちゃん自身の精神力や体力といったものだったのではないだろうか。
テーブルの上の五枚の写真は、なにごともなかったかのように元の姿で並んでいる。
目を閉じていた人物たちは全員目を開いている。『老人』や青年将校たちもだ。
「もう終わりにしてくれ」
夏雄がそう言いながら窓を開け、雨戸を元に戻し始めた。外の光が畳敷きの室内に射し込んで来る。
「自分の部屋に戻ってろ」
アキちゃんは夏雄の言葉に素直に頷き、さして名残惜しそうでもなく立ち上がると、
「ばいばい」と言って僕をちらりと見た後、襖の向こうに去って行った。
『わたしや夏雄なんか及びもつかない、正真正銘の霊能力者だよ』
師匠の言葉が脳裏に蘇る。
僕らにはもう見えない、消えて行く霊を、まるでそこにいるかのように見ることが出来る、底知れない霊感。
死者の見開かれた目を指でそっと閉じさせるように、写真の中の人物にまでそんな影響を及ぼす力。そして念写。
僕は信じられない思いで、その子が去った襖とその先の廊下の方を見つめる。
「もう帰れよ」
雨戸を戻し終わった夏雄がテーブルにそばに立ち、ズボンのポケットに手を入れながらそう言い放った。
「ああ」
師匠は生返事をしながら、青年将校たちの写真に目を落としている。僕も同じように覗き込む。
「念写って本当ですか」
「さあな。可能性の問題だ。人形よりはありえるだろう」
その判断基準が良く分からない。
目を閉じていない正岡大尉だけが、念写によって写しこまれた幻だというのか。実際には彼はその部屋にいなかったと。
そう言えば、今回の五枚の写真では死者が目を閉じるという異常現象は起こったが、
写真の中の霊的なものに起こるという変化は見られなかったようだ。
つまり『写真屋』と同じく、心霊写真は一枚もない、という結論が出たわけだが……
「幽霊が写っていた場合、どうなるんですか」
気になって訊いてみたが、師匠は意地悪そうな顔をしただけで答えなかった。
「どっちにしろ、幽霊でもなく、生きている人間でもない彼は、結局つくりものだったってことだ」
師匠は結論付けるようにそう言ったが、僕は別の可能性を考えていた。
正岡大尉がその時生きて写真に写っていて、その後も現在まで生き続けている可能性だ。
だから写真の中の彼の目は閉じなかった。
だがその場合、
なぜ正岡大尉が死を偽り、あるいは偽られ、そしてその後も姿をくらましたままだったのか、という謎は残る。
正岡大尉が生きていたとして、今一体何歳になるのだろうかと思って、計算をしてみた。
すると、八十過ぎという結果が出た。生きていてもおかしくない年齢だ。
そこまで考えたところで、僕はアキちゃんが僕らに見せた、写真の中の人物が目を閉じるという共通幻想の意味を、
他愛もなく信じていることに気づいて、おかしさが込み上げて来た。
その理由も分かる。師匠がそう信じているからだ。
そこが僕のスタート地点であり、他の道などありはしなかった。少なくとも、そのころの僕には。
「長尾郁子、高橋貞子、そして三田光一……
東京帝国大学の助教授だった福来友吉が、明治から昭和の始めにかけて見出した霊能者たちは、
透視能力だけでなく、念写という能力までも実験によって示そうとした。
そしてその失敗が、念写を、幽霊写真よりも信憑性においてさらに一段下に置く風潮の元になり、
その大衆心理は現代まで連綿と受け継がれている。
どちらも『心霊写真』として括られるものなのに。
福来博士の念写実験の真贋についてはあえて語らないけど、余計なことをしてくれたものだ」
こんな、面白いものを……皮肉さを口元に表して師匠は呟く。
「でもこの正岡大尉の部分が念写によるものだとしても、誰がそれを撮ったっていうんですか」
写真には写っていないカメラマンが、その念写を行った人物のはずだった。
「さあな。家族か、他に仲間がいたのか。この写真では分からないな。
でも福来博士の定義では、念者は乾板に直接作用するので写真機は不要とされていた。
わたしの研究した限りでも、同意見だ。
乾板写真じゃなく、フィルム写真だろうが原理は同じはずだ。
シャッターを押した人間にしか、念写を行うことが出来ないというのは、早計だな」
「では誰が念写を?」
「この中の誰かだろうな。姿の見えないカメラマンを含めてだが。
これが念写だとするならば、欠けた仲間を、あるべき姿として、同じ空間に蘇らせたんだ。
世に大事を成そうというヒロイズムと高揚感、そこから来る連帯感。
そして妄想というか、妄念というか、なにかそういうものがあるような気がする」
そう言われて、僕はもう一度写真の中の男たちの顔を眺めた。そして左隅に遠慮がちに座る正岡大尉の姿を。
もしこれが想定外の念写だというのなら、現像されたものを見て『老人』や青年将校たちは驚いただろう。
死んだはずの正岡大尉が一緒に写っていることに。
そのことは、恐怖よりもむしろ勇気を鼓舞するものだったはずだ。
死してなお、想いを同じくする仲間の姿に、より一層、彼らの団結心は強固なものになったのではないだろうか。
「あ、しまった。こっち見てもらうの忘れてた」
師匠は封筒に残っていた『老人』と青年将校たちの写真のコピーの方を見て、自分のひたいを叩いた。
『老人』の顔が見えない失敗作だ。
『写真屋』のところでもそうだったが、師匠は妙にそのコピーの方にもこだわっている。
きっちりしているのか、なんなのか。なにもおかしいところはないはずなのに。
「夏雄、いまヒマか」
師匠は写真を片付けながら訊いた。
「ヒマじゃねえよ」
「うそつけ。寝癖立ってるぞ」
「おまえもな」
「え、まじで」
確かに少し立っていた。師匠は後ろ髪を触っている。
なんだかこの二人の会話を聞いていると、理由もなくムカムカしてくる自分がいる。
「…………」
師匠はそれから少しのあいだ黙り、そして「またな」と言ってリュックサックを背負いながら立ち上がった。
「ああ」
夏雄は玄関まで僕らを見送った。山門か、せめて参道まで見送るという発想がなさそうな男だった。
師匠が靴を履いて外に出る時も、欠伸をしながら頭を掻いていたが、
僕がそれに続こうとした瞬間、首根っこを凄い力で引っつかまれた。
「おい」
「なんですか」
とっさに睨みつけながら言い返したが、内心はドキドキしていた。
「深入りするな」
ほとんど無表情でそう言われた。
その言葉の意味をどう取るべきか一瞬分からなかった。
師匠に、それも女性としての加奈子さんに近づくな、という脅しなのか。
それとも、この写真にまつわる一件にこれ以上関わるな、という警告なのか。
「余計なお世話です」
それがどちらにせよ、腹を決めたつもりでそう言い返した。
夏雄は「ガキが」と吐き捨てて、僕の腹を殴った。
昨日、石田組のチンピラみたいな歯抜け茶髪に殴られた場所のすぐ近くだった。一瞬息が止まる。
ほんの撫でる程度に力の抜けた一発だったが、
その拳は一体なにで出来ているのか、というくらいの異様な硬さで、まるで腹に石を落とされたようだった。
なにすんだ。
そう怒鳴ろうと、肺をむりやりこじ開けて息を吸い込んだ時、玄関の外から「なにしてんだよ」という師匠の声が聞えた。
「もう四時になるぞ。早く帰ろう」
「……はい」
僕は夏雄を精一杯睨みつけながら返事をし、靴のつま先で地面を叩いた。
「気をつけて帰れ」
夏雄は僕に対する興味を失ったように、ありていな言葉を吐いて家の中へと踵を返した。
「妹さんによろしく」
僕もさっきの腹パンチなんてなにも効いていない、というていで手を振った。そして外に出て、師匠の後を追う。
なんだあの野郎。暴力馬鹿が。ヤクザと変わらないじゃないか。
そんな悪態を心の中でつきながら、師匠の横に並んだ。
「結局よく分かりませんでしたね」
『写真屋』の天野は心霊写真や偽造写真ではないと言い、
アキちゃんの見せた幻からは焦点になっている正岡大尉が、死者でも生者でもない作り物だ、という答えが導き出された。
師匠は念写だと言うが、精巧な人形なのかも知れないし、
あるいは正岡大尉の死という情報が誤りで、その時も、そして今現在も生きている可能性もあった。
「そうかな。念写でいいじゃないか」
いいじゃないか、という口ぶりに、変に他人事のようなニュアンスを感じて、おや?と思った。
問題はそこじゃない。そう言っているような感じ。
僕の疑念に気づいたように、師匠は続けた。
「松浦がこの写真のコピーをわたしに預けた時点で、もう答えは出てるんだ」
「どういうことですか」
「『老人』の、角南大悟の顔が潰れてしまっていて見えないとはいえ、
現存する角南家の別邸で撮影されたと分かる写真に、
消された大逆事件の首謀者たちが集まっているのが写っているんだ。
それだけで、とんでもないスキャンダルだ。おいそれと興信所の所員なんかに渡していいはずはない。
なのに松浦はそうした。脅しつきだったが、そんなものクソくらえだ。
ようするに、この写真自体にもう価値はなかったんだよ。
松浦は正岡大尉の死亡時期の問題だけで、一点突破できると踏んでたんだ。偽造写真だと。
心霊写真だなんていう無駄な説明の必要はない。
そんなものは、蛇足を通り越して薮蛇もいいところだ。
ただ偽造写真だというだけで、この写真の持つ毒性は消えることになるんだから」
だったらどうして松浦は、心霊写真かどうかの鑑定を師匠に依頼したのだ。ふに落ちない。
師匠はしたり顔をして言った。
「そこだよ。あいつにとって重要なのは、こんな無価値な古い写真じゃない。
消えた大逆事件も。そこにいてはいけない、死んだはずの将校も。
『老人』の角南家のスキャンダルも、なにもかも関係ないんだ。
ただあいつは……」
そこまで言いかけたところで、ふと口をつぐんだ。
「まて。おかしいぞ」
師匠は緊張した表情になった。
「ただの無価値な写真……関係ない……大逆事件なんか……死んだはずの将校も……関係が……」
ボソボソと呟いた後で、ハッとした顔をして師匠はいきなり振り返ると走り出した。
参道の石畳を、寺の方に向かって駆け抜ける。
「ちょっと待って下さい」
慌てて後を追ったが、もう姿が見えない。
とっさのことにあっけにとられ、初動が遅れたことと、それ以上に師匠の足が速すぎた。
敷地内にあった黒谷家の住居にたどり着いた時、すでに師匠は玄関に靴を脱ぎ散らかして上がり込んでいた。
僕も靴を脱いで、古い木の香りのする廊下を恐る恐る進んでいると、どこかから声が聞えて来た。
「どうして目が閉じないと、おかしいんだ」
師匠の声だ。どこからだろう。
勝手の分からない、やたらと広い他人の家をしばらくうろうろして、
ようやくたどり着いた時、すでに師匠の用件は終わっていた。
アキちゃんの部屋の前に、本人と夏雄と師匠とが立っていて、
師匠は厳しい顔をしたまま、近づいて来る僕の方をちらりと見た。
「帰るぞ」
そう言って、黒谷家の兄妹に「ありがとう」と頭を下げ、玄関のある方に歩き出した。
アキちゃんは怯えたような面持ちでそれを見送っている。
夏雄は仏頂面だ。その目つきにはどこか殺気立ったようなものも感じられた。
「え、え」
僕はその慌しさに戸惑いながらも、師匠の後について歩き出す。
そうして戻って来たばかりの黒谷家を再び後にした。
夏雄はもう見送りには来なかった。
遠ざかっていく寺を振り返りもせず、杉木立の中の参道を再び通って山門のところまで戻る。
許されざるも山門に入った葷酒は、やはり許されざるも山門を出るのだろうか。
古びた門をくぐりながら、ふと意味のない言葉が脳裏に浮かんだ。
門の外に止めてあった車に乗り込むと、僕は師匠に今のやりとりのことを訊ねる。
しかし、むっつりと押し黙って口をへの字に曲げた横顔を見せられた。
どうして目が閉じないと、おかしいのか。
師匠は確かにアキちゃんに訊いていた。わざわざ家に取って返してまで。
「やっぱりあの正岡大尉には、なにかおかしいところがあるんですか」
「少し黙ってろ」
師匠はなにか難しい問題を押し付けられたように厳しい顔をして、そっけなくそう言った。
僕はそれ以上言葉を継げなかった。
師匠に心霊写真の鑑定を依頼した松浦の真意とやらの話も途中のままだ。
僕はもやもやしたまま、見るからに不機嫌になってしまった師匠の横で、居心地悪く助手席のシートに沈み込んでいた。
[完]
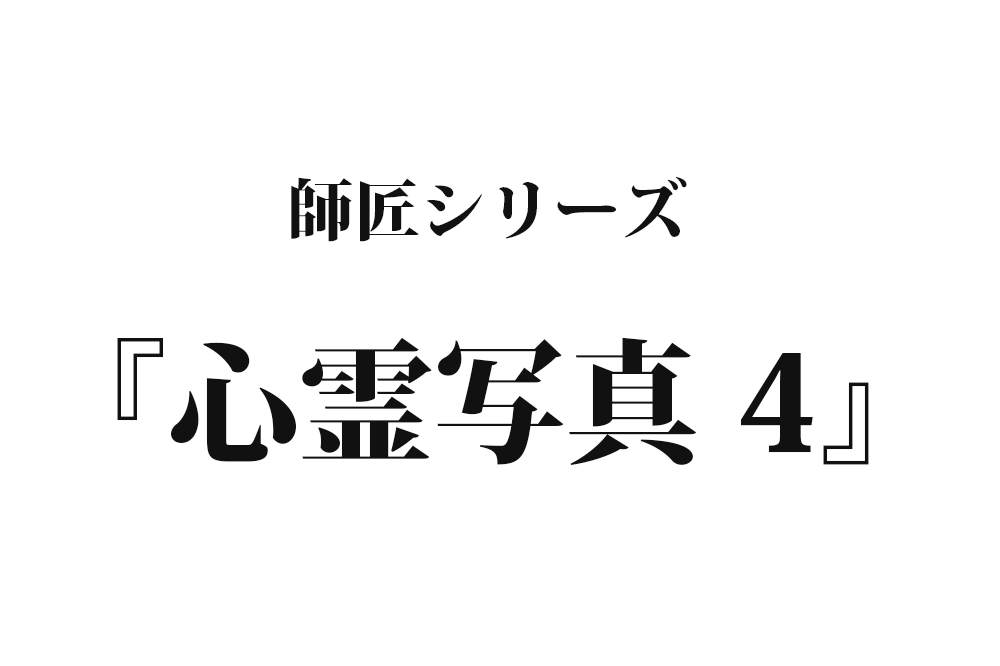
コメント