藍物語シリーズ【21】
『花詞』
爽やかな風が木々の枝を揺らしている。もう秋も深い。翠と2人で辿る、細い散歩道。
...やはり有った。葉脈が深く刻まれた濃緑色の葉と、鮮やかな赤い実。
隣の○×県。『その県民公園には、幼児でも歩ける散歩道が整備されていて、
すぐ脇にその木が何本か生えている。』 事前に調べておいた情報の通りだ。
近づくと、小さな鳥が数羽飛び立った。鳥たちは美味しい実の在処を良く知っている。
「御免よ。少しだけ、実を分けておくれ。」
呟きながら母の口調を思い出す。良く熟した実のついた枝を探した。
鳥たちや散策の人々の取り残しだろう。実の数は少なかったが、これで、十分だ。
蘇る、遠い記憶。
母の白く細い指が水筒の水を赤い実にかけ、ぴぴっと水を切る。
「R。ほらこれ、ガマズミの実。美味しいよ。食べてごらん。」
「がまずみって、へんななまえ...でも、あまくて、おいしい。」
「秋の山には、食べられる実が他にも色々有るから。一緒に、探そうね。」 「うん。」
色とりどりの果実、野趣溢れる甘酸っぱい味の思い出。
幼い頃、父と母は代わる変わる俺を野外に連れ出した。
父は釣りとキャンプ、河や海。母は野原や山、今で言うならライトトレッキング。
父はともかく、頻繁に俺を野外に連れ出した母の意図を、今にして思う。
俺の感覚の一部を封じて、でも季節の移り変わりを感じる感受性はしっかり育てたい。
きっと、そういう思いから。自分の子をもって、初めて知る母の愛情。
「お父さん、どうしたの?」
小さな体を抱き上げる。 「ほら、あそこに赤い実があるでしょ?」 「うん。」
程度の差はあれ、翠も俺と同じだ。翠が一歳半の時、Sさんはその感覚の一部を封じた。
あまりに強過ぎる感受性が、後の災いを招かないように、と。
お屋敷は一種の閉ざされた環境。しかも感覚の一部を封じられて翠は育つ。
もちろんSさんと姫は普段から翠の情操教育に心を尽くしている。沢山の絵本や音楽。
ただ、この国の美しい四季に感じる心を育てるには、実体験が何よりも必要だ。
ある程度の距離を歩けるようになった頃から、
出来るだけ翠を野外に連れ出すように心がけていた。
それは勿論父親である俺に与えられた大切な、役目。
ガマズミの実を一房取り、ペットボトルの水をかけた。ぴぴっと水を切る。
「食べてごらん。甘酸っぱくて、美味しいよ。」 「ホントだ。あま~い。」
何時の日か、翠が子供を産み、その子にこの実を食べさせる日が来るだろうか。
屈託のない笑顔を見ながら、そんな事を考えていた。
「お父さん、これで良い?」 「OK、次はマットレスと毛布を運ぼうか。」 「うん!」
穏やかな日差しの中、お屋敷の庭に翠と2人でテントを張っている。
最近読んだ絵本の影響だろう。翠がキャンプをしたいと言い出し、
どうしてもテントで寝たいと言って聞かなかったからだ。
実家には昔俺と父親が使っていたテントがある筈だが、
取りに帰るとそれだけで丸1日かかる。街で新しいテントを買ってきた。
余裕を見て3~4人用、テントで寝るのは翠と俺だけだから広さは十分。
今夜の天気予報も問題ない。冷え込みに備えて温かい上着と毛布を用意すれば準備は万全。
まずはみんなで夕食、庭に設置してあるグリルで魚介類のバーベキュー。
後片付けをしてから一度お屋敷に戻る。翠を風呂に入れてパジャマを着せた。
その後いよいよ翠と2人、テントでお泊まり。もちろんSさんと姫と藍はお屋敷の中。
テントで寝るとはいえ、トイレや翠がぐずった時にはお屋敷に戻れる。お気楽なキャンプ。
テントの天井から吊したランタンのスイッチを入れた。
勿論ガス式の方が風情は有る。しかし、翠の火傷など万一を考えて蛍光灯式。
LED式は懐中電灯には良いのだが、明るさの割に眩しくて室内の照明には向かないと思う。
テントを張ったのはガレージの裏。初めはウッドデッキの上を提案したが、即却下された。
確かにウッドデッキではあまりに雰囲気がない。やはりこれで正解だった。
広い庭の外れはそれなりに暗いし、これなら翠にとってかなり本格的なキャンプの気分だろう。
「かんぱ~い。」 「乾杯。」
翠は麦茶、俺はビール。 夜食とつまみもあるし、小さなクーラーボックスは満杯。
「どう?もう外は真っ暗だけど、怖くない?」
「ぜんぜんこわくない。とってもたのしい。それにね、もう少ししたらお客さんたちが来るよ。」
「お客さん?」 「そう、山のどうぶつたち。くまさんとか、ぴっぴちゃん(※鳥)とか。」
!? しまった、キャンプしたい理由はそれだったのか。
多分、絵本の内容が幾つか、ごっちゃになってる。
これはさすがに予想してなかった。 ちょっと、マズイ。
この辺りにクマはいない。キツネはいるが、絵本のように訪ねてくる筈がない。
でもそれじゃ翠の機嫌が。一気に大ピンチ、それとなく、客は来ないと説得しないと。
「この辺にクマはいないし、夜は鳥たちも寝てると思うな。
あ、でも前に夕方キツネを見たことがあるよ。山道で自転車に乗っている時。」
「え~、いいなあ。かわいかった?」
「可愛いっていうか、綺麗で、強そうだったよ。目が、きりっとしてさ。やっぱり野生、だからね。」
「じゃあ、こんやのお客さんはきつねさんかな?たのしみだね。」
あ、いや、そうじゃなくて...
相性の問題で、翠には俺の術が効かない。
Sさんにそれっぽい式を寄越してもらうしかないだろう。あとでトイレに行くふりをして。
その時、テントの入り口を叩く音がした。
「やっぱり来た。お客さん。」 「翠、待って!」 慌てて抱き止める。
お屋敷の周りの土地は巨大な結界になっていて、悪しきモノたちは近づけない筈だ。
今頃このテントを訪ねて来るとしたら多分...だが、用心するに越したことはない。
翠の手を握ったままテントの入り口をから様子を伺う。小さな、白い影。やっぱり。
「な~んだ、くださんかぁ。お客さんだと思ったのに。」
「姫、なんだとはあんまりな。管が、せっかくこの仮屋を訪ねて参りましたのに。」
さすがにSさん、用意が良い。まあ、一応キツネだし。
管さんは何故か翠がお気に入りで、しかも敬語だ。俺にはずっとタメ口なのに。
するりとテントに入り込んで入り口のジッパーを閉めた。相変わらず律儀なことで。
「秋の夜は長いもの。退屈しのぎに昔話などお聞かせしましょう。」
「うん、聞きたい聞きたい。はやく、はなして。」
管さんは翠の膝の上に丸くなって話し始めた。
もちろん、管さんの話は面白い。これで翠の気が紛れれば、本当に助かる。
紙コップにチューハイを少し注いで翠の傍に置いた。そういえば鮭冬葉も買ってあったっけ。
あれは小さくちぎって紙皿に。どちらも管さんの好物。
管さんは昔話を続け、翠は眼を輝かせて話に聞き入っている。
既に11時過ぎ。ビールとチューハイが数本ずつ。
陶器のワインクーラーに赤ワインも1本冷やしてあるが、
翠を残してトイレに行くのも気が引けるし、立ちションは教育上宜しくない。酒量は控えめ。
それより問題は翠が一向に眠そうな素振りを見せないことだ。
術で寝かせることは出来ないし、うっかり俺が先に寝てしまったら、
明日Sさんと姫にこっぴどく怒られるだろう。
やはり翠を管さんに任せて、一度Sさんか姫に相談を。いや、2人はきっともう寝てる。
その時、翠が振り向いた。微笑んでテントの入り口を見詰める。
「お父さん、ほんもののお客さんだよ。やっぱり来たね。」
テントの入り口を叩く、小さな音。一体...。
管さんが翠の膝を降り、俺の肩に駆け上がった。小さな声で囁く。
「かなり古い妖だが、意図が読めない。力が強いから失礼の無いように、対応を誤るな。」
再び入り口を叩く音。
「妖をテントの中に入れろ、ということですか?」 「そうでないと収まらん。」
そっと入り口ににじり寄り、声を掛けた。
「はい。どちらさま、でしょうか?」
「○×の山中に住む、◇◆○の使いの者で御座います。
先日お見かけした姫君に是非お目通りしたいと訪ねて参りました所、丁度この仮屋で宴が。
僭越ながら、宴の末席に加えて頂きたく、お願いに上がりました。」
○×? ということは、先日翠と2人で県民公園に行った時か、しかし特に変わった気配は。
「いらっしゃいませ、どうぞ。」 あ、翠、まだ。
するするとジッパーが開き、入り口の布がめくれ上がる。 これは。
狩衣のような着物を着た、小さな、人。いや、人の形をした、一体、何?
それは深く一礼した後、入り口をくぐった。
「有難う存じます。姫君への贈り物と、父君へは酒肴を御用意致しました。」
「ありがとう。」 いや、翠、だからまだ。
まあ、物心ついたときから式を見慣れているから無理もない。
でも、せめてもう少し警戒心ってものが。それとも、これは夢か?
小さな人が手を叩くと、めくれ上がった入り口からもう1人、また、1人。
荷物を捧げ持った小さな人が次々とテントに入ってきた。どれも背丈は40cm程。
先頭の1人は木の枝を捧げ持っている。 満開の白い花、テントの中に微かな芳香が漂う。
素朴な一重咲き、この辺りでは見かけない花だ。 しかし、この香りは何処かで。
続く2人の荷物は小さな三方。でも、それらの背丈に比べればかなり大きい。重そうだ。
三方の1つには秋の果実。アケビとヤマブドウ、ガマズミ?
もう1つの三方には小さな銚子と杯。それと、赤っぽい干し肉。
「大したものでは御座いませんが、どうぞお納め下さい。」
最初のと合わせて小さな人が合計4人(?)、揃って手を付き頭を下げた。
満開の枝を受け取った翠は上機嫌だ。
「きれいなお花、いいにおい。お父さん、これ、いけて。」
陶器のワインクーラーに水を張り、枝を活けた。即席の花器。
白い花弁が一枚、ひらりと散る。 「これ、なんていうお花かな?」
そうだ、まだ花の名を。 「宜しければ、花の名前を教えて頂けませんか?」
「はて、主自ら用意した花ですが名前までは。」 「その花は『さんか』であろう。」
「いや、『さんさ』だ。」 「我らは無粋者にて、花の名は。申し訳ありません。」
さんか? 山花か? 秋から冬の、山の花と言えば...藪椿? 確かに葉は似ているが。
「ボンヤリするな。礼の口上を。」 管さんが囁く。 これは夢じゃ、ない?
「花の名は家の者に聞けば分かるでしょう。」 そう、Sさんなら多分。
「それより、どれも季節の瀟洒な品々。有難う御座います。」 手をついて一礼。
「気に入って頂けて、何より。では、まず父君に。」
「杯を持て。一口で飲み干したら返杯。そうだな、紙コップに葡萄酒を。」
淡く黄色味がかったその酒は甘味が強く、不思議な香りがした。
深い山に満ちる気のようなものが、喉から鼻に抜けてくる。 本当に、旨い。
「これは、美味しいお酒ですね。初めての味ですが、とても良い香りです。」
「椎と栗で醸した酒で御座います。昨年は山が豊かで、殊の外に良い出来でした。」
猿酒、か。手軽に果汁を発酵させた酒でなく、
本来はドングリなどの澱粉から手間暇かけて醸した酒をそう呼ぶのだと、
父から聞いたことがあった。しかし、実際にそんな酒を醸し干し肉を作るとは。
随分と風雅な生活をしているモノたちらしい。返杯の用意を。
紙コップを4つ並べ、少しずつ赤ワインを注いだ。紙皿に鮭冬葉を一掴み。
「では御返杯。舶来の葡萄酒です。皆様、どうぞ。」 「有り難く、頂きます。」
「あま~い。これ、とってもおいしいよ。」 翠が食べているのはアケビの実。
椎と栗で醸したという酒と、赤っぽい干し肉との相性は抜群。
何杯でも飲みたいが、相手の意図が分からないのだから正気を保たねば。
そんな俺を尻目に、翠は果実をほとんど食べ尽くしている。
深夜のテントに不思議な客。奇妙な宴会が続いた。
その酒の醸し方、山の果実の味。話題は尽きない。
一体、どのくらい経ったろう。お客が来て満足したのか、翠がウトウトと居眠りを始めた。
「失礼、娘を。」 翠をマットレスに寝かせて毛布をかける。首筋に、寒気。
振り向くと、小さな4人が揃って翠の寝顔を見詰めている。
「寝てしまわれたか。本当に愛らしく、美しい姫君。」 「未だ幼く、術も修めておられぬのに。」
「既にその御魂も御力も。」 「人にしておくのが勿体ないほどの御方。」
まさか、将来翠を妖の嫁にと。異類婚説話、そんな言葉が頭をよぎる。
「頃合いだ。そろそろ本題に。」 耳許で管さんの声。
確かに、もし翠に聞かせたくない話だとしても、今なら。
「ところで皆様方は、今宵どのような用件でこちらに?」
それらは一斉に俺を見た。まん丸な目、何だか怖い。
「実は、我が主から仕官の件を言付かりまして。」 「仕官、ですか?」
「はい。元々我が主は京の都で高名な術師に式として仕えておりました。
しかし術師の死を境に主は○×の山地に隠遁致しました。もう400年程も前の事です。
時折気が向けば、修行のため山中に入った行者や術師と交わることは有りましたが、
我らがどれ程勧めても、仕官する気にはなれないようで御座いました。
更に時は移り、この数十年は行者や術師が修行に来るのを見たこともありません。
今の世では主が優れた術師に仕えることもあるまいと、我らは常々嘆いておりましたが、
先日姫君と父君をお見かけした主が、突然『是非もう一度仕官を。』と。
気が変わらぬ内にと、慌てて支度を調えましたような訳で。」
俺の知る限り、式には2つの系統がある。
代に術者の力を封じた式は、主に短期間の使役に用いる。
何かの方法で力を補充し続けなければ活動できるのは数日がせいぜい。
当然使役する術者を越える力を扱うことはないし、それ自身の意思もない。
しかし管さんや御影は違う。それらは元々独立した妖で、契約に基づいて術者に仕えている。
自身の意思を持っているから、普通は式の同意を得ずにその契約が成立することはない。
契約の効力によって『良き理』から流れ込む力を使えるようになれば、
式の器によっては、使役する術者よりも遙かに強い力を扱うこともあり得る。
およそ400年もの間、自らの意思で○×県の山中に隠遁していたというなら、間違いなく後者。
そして、初めに『姫君に是非お目通りしたい』と。
「つまりその御方を娘の式に、ということですか?」 「左様、是非そのように。」
さすがに今は危険過ぎる。しかし将来、強力な式を使役出来れば間違いなく翠に有利。
断るのは如何にも惜しい。しかし、素性が分からない妖を俺の独断では。
こんな時、Sさんがいてくれたら。
「その御方は、一体どのような。出来れば、実際に御目にかかってからお話を。」
「我らは主に仕官しております故、このような化生も自在ですが、主はそうも参りません。
今この場で姫君への仕官を許して頂ければ主の化生も叶いましょうが、
例え化生致しましてもこの仮屋に入れるものかどうか。」
どんな大きさ?一体何の妖だよ。それに、もしそんな相手を無下に断ればどんな。
「父親なら、腹を括れ。本意ではないが、ここはお前の判断に従うしかない。」
囁く声。管さんの言う通りだ。深く息を吸い、下腹に力を込める。
『仰せの通り、娘は未だ術の基本も修めておりません。
しかも私たちの一族では、式の使役を許されるのは術者が13歳になってから。
それまでお待ち下さるなら、改めてお話を伺いましょう。それで、如何ですか?』
断るのでなく、何とか話を先延ばしに。それが出来れば、Sさんの意見を聞くことも可能だ。
「あと8年と少し...人の身には長く、あまりに惜しい時間でありましょうに。
しかし、それが父君の御考えとあれば我らに異存は御座いません。」
そっと息を吐き、それとなく額の汗を拭う。どうやら収まりが付きそうだ。
「では、姫君への忠誠の証として、今夜と同じ贈り物を毎年お届け致します。
今夜の約束、どうかくれぐれもお忘れ無きよう。」
『それでは足りない。』
鈴を振るような声。振り返ると、翠がマットレスの上で上体を起こしていた。
「姫君は、今何と?」 『毎年の贈り物だけでは足りない、そう、言ったのだ。』
場の空気が、一瞬で張り詰めた。 違う、これは翠の話し方じゃない。
「心を込めて贈り物を御用意致しましたし、誠を尽くして仕官の御願いを致しました。
これ以上、姫君には一体何の御不満が?」
言葉は丁寧なままだが、篭もる力は先程までと段違い。この後の言葉によっては。
慌てて翠を抱き上げ、膝の上に座らせた。耳許で囁く。
「駄目だよ。お客さんを怒らせちゃ。」
翠はじっと俺を見つめた。吸い込まれるような、黒い瞳。
『私に、任せろ。半端に道を付ければ、むしろこの子に災いを招く。』
言い終えて、ゆっくりと小さな客たちに視線を移した。
ぴいんと伸びた背筋、威厳に満ちた横顔。やはり、翠ではない。
『仕官を望む気持ちが誠なら、お前の名を、名告れ。』
テントの中、彼方此方で、チリチリと金色の火花が散った。鼻の奥で火薬の臭いがする。
管さんは黙って俺の肩から飛び降り、翠の直ぐ横に蹲った。最高レベルの、臨戦態勢。
「御影」や「管狐」はあくまで通称。真の名は、契約した術者だけに明かされる秘密。
それを俺と管さんの前で...もし最悪の事態を招いたら、翠を守る方法は。
『私に仕えるというなら、一族にも忠誠を誓うが道理。
そしてその日が来るまで、私の父母がお前の主。何故隠す必要が有る?
何度も言わせるな。 お前の名を、名告れ。』
新しい絵本を手にした時のように、大きく目を見開いた、翠の笑顔。
何もそんな、挑発的な言い方をしなくても。冷や汗が流れる。
小さな客たちの姿がゆらりと薄れ、蛍光灯式のランタンが頼りなく明滅した。
凝縮する気配...姿は見えないが、間違いなく目の前に、それは、いる。
『我が名を名告れとは。今此の場で姫君と契約を結べとの仰せか?』
テント全体に響く、太く低い声。 もう、俺の手には負えない。しかし、翠は。
『当然だ。契約もしていない妖の出入りを許す法など有るものか。
しかし、此の場で契約を結び忠誠を誓うなら、『良き理』への道が開く。
それで元の姿と力を取り戻すかどうか。全てはお前次第。分かっている筈だ。』
『我が想いを...有り難い。では、我も誠を尽くそう。我が名は。』
目が覚めると、明るい日差しがテントの布地を照らしていた。 朝、か?
入り口に丸くなった管さんの後ろ姿と、紙皿に残った赤っぽい干し肉は、
昨夜の出来事が夢でない事を示している。 一体、あれは?
「やはり○△姫の娘御。大した姫君よ。」
「でも、あれは翠の話し方じゃ。」
「どんな御加護も、御本人の希望がなければ力を持たぬ。
忘れたか?この仮屋で客を迎えるは、姫御自身が望んだこと。」
...あの公園で過ごした時、既に翠には俺に見えないモノが見えていたのか。
その一部を封じてもなお、俺には感知出来ない存在を感知する感覚。
完全に信頼して任せた事ではあるが、やはりSさんの判断は正しかった。
「とまれ、契約は成立した。新たに式を迎えたのは随分と久し振りだ。
まあ、姫君が実際にあれを使役するのは、もう少し先のことになるだろうが、な。」
紙皿に残っていた干し肉の欠片を1つ食べて、Sさんは微笑んだ。
「少し塩辛いけど、美味しい。多分、熊の肉。鹿とか猪の肉とは違うと思う。」
「この辺りにクマはいませんよね。じゃあ、本当に古い妖が○×県から翠ちゃんに?」
「契約していた術者との心の繋がりが余程深かったのね。だから敢えて他の術者との間で
契約の『引き継ぎ』をせず、式としての力を失い、元の妖に戻って○×県の山中に身を潜めた。
素のままでさえ易々と熊を屠るほどの力を持つ妖。
しかし人々に害をなすこともせず、新しい契約を結ぶこともなく、ひっそりと暮らしていた。
そこにR君と翠が。だからこれも他生の縁。きっと、遠い約束の1つ。」
「易々と熊を屠るって、どうしてそんなことが分かるんですか?」
「苦しんで死んだ動物の肉は肉質が落ちるし獣臭がきつくなるって聞いたことがある。
この干し肉、旨味は濃いけど匂いは殆どない。だから。」
昨夜、そんな妖を相手にあの口調で...少し目眩がした。
御加護がなくても、強力な式を正しく使役する。そんな術者に、翠は成長するだろうか?
不安はあるが、正直先のことは分からない。
ただ、翠は式を使役する適性をSさんから受け継いでいる。それは確かだ。
「でも、何故翠なんでしょう?適性は別にしても、未だ式を使役する力は無いのに。」
「一目惚れ、じゃないですか?翠ちゃんはとても可愛いから。」
「へ?一目惚れって。」 少なくとも400年は生きている妖が、3歳の女の子に?
藍を抱いたSさんは優しく微笑んだ。
「有り得るわね。式が仕える術者を選ぶ基準は好き嫌いであって損得勘定じゃない。」
「いや、だからって。翠は3歳ですよ?」
「基本、術者と契約を結ぶような妖は人が好きだし、特に小さい子は好きよ。」
そう言えば管さんは翠がお気に入りで、それに敬語だ。
「もちろん人間の恋愛感情とは違う。自分たちよりもずっと短い命が放つ輝きに、
畏れや憧れを感じているのかもしれない。この花を贈ったのも、きっとそういう意味。」
Sさんはテーブルに散った白い花びらを一枚摘まんだ。ワインクーラーの花器に活けた枝。
「これは山茶花。園芸品種は幾らも有るけど原種は滅多に見かけない。
もとは漢字の通り山茶の花で『さんさか』、それが訛って『さざんか』。受け売りだけど。」
サザンカ。 そうか、この香りは。 一枚ずつ散る花弁、艶のある濃緑色の葉。
八重咲きの、色とりどりの花を見慣れていたから、まさかサザンカだとは思わなかった。
「白いサザンカの花言葉は、確か『理想の恋』。出来過ぎ。偶然、ですよね?」
姫の言う通り。それは、幾ら何でも。
「山茶花は日本が原産だけど、花言葉はそうじゃない。
それに花言葉自体の歴史がせいぜい200年。面白いけど、偶然でしょうね。
さて、400年位前、京の都、高名な術者に仕えていた。手がかりは十分。」
Sさんは藍を姫に託して立ち上がった。行き先は、多分図書室の記録庫。
翠はソファで昼寝をしている。あれだけ夜更かしをしたのだから暫くは起きないだろう。
本人には一体何処まで昨夜の記憶があるのか。さらさらの髪を、そっと撫でる。
10分程でSさんが戻ってきた。A3の紙をテーブルに置く。
大きく、クッキリとした筆文字。かなり古い資料のコピー。
「これかも。もし、本当にこの記録の通りなら、大変だけど。」
『大変』とは言うが、Sさんの目は笑っている。急いで資料に目を通した。
古い筆文字、全て読める訳ではない。しかし、ある文字が浮き上がるように目に入った。
『鵬』
おおとり? それは古来、世界各地で目撃され、様々な名で呼ばれてきた。伝説の猛禽。
確か1800年代の終わりには、日本でも射殺された記録がある。
鵬にしては小型なのかもしれないが、記録によれば体長3m弱、両翼の差し渡し6m強。
猛禽ならば、アホウドリの大型個体の誤認などでは有り得ない。
「でも、この名前じゃありませんでした。確か」
Sさんは俺の唇を人差し指で押さえて首を振った。『黙って』の合図。
「駄目よ。それは翠だけの秘密。気を付けて。」
成る程、『鵬』もあくまで通称。その姿と性質をおおまかに示すだけだ。
それから毎年、決まって10月の終わりには、お屋敷の玄関に贈り物が届いた。
満開の、白い山茶花の枝。山盛りの果実と熊の干し肉。椎と栗で醸した香り高い酒。
そして、その前後数日、お屋敷の遙か上空を舞う巨大な猛禽の影。
それらは、お屋敷に秋の深まりを告げる、新たな風物詩になった。
完

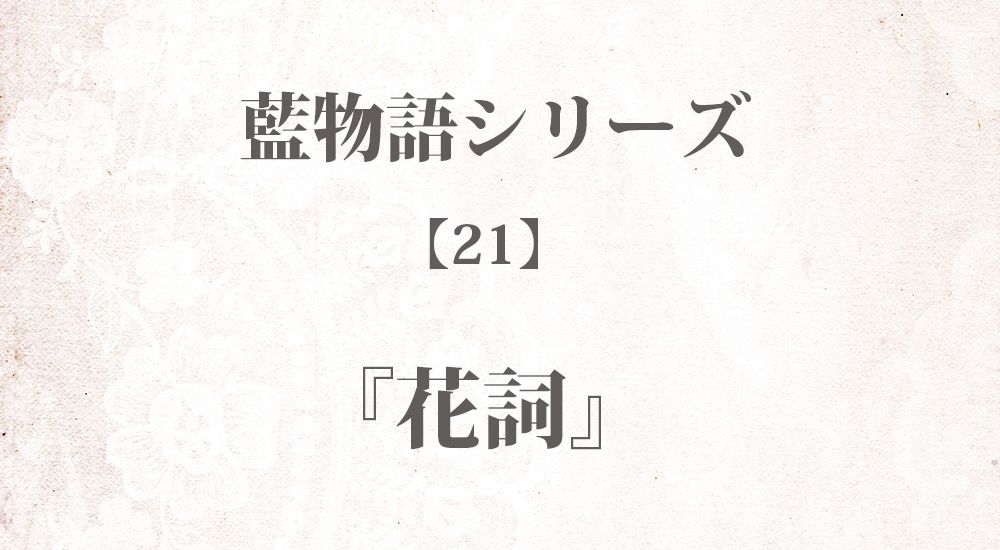

コメント