『ペットの話』
【霊感持ちの】シリーズ物総合スレ19【友人・知人】 970 :ペットの話:2012/03/04(日) 11:18:31.06 ID:C8/Dhig30
京介さんから聞いた話だ。
高校一年生の春。
私は女子高に入ってからできた友だちを、自分の家に招待した。
ヨーコという名前で、言動がとても騒がしく、いつもその相手をしているだけでなんだか忙しい気持ちになるような子だ。
そのころの自分にできた唯一の友だちだった。
私の家は動物をたくさん飼っていて、その話をすると「見たい見たい」と言い出してきかなかったのだ。
「でか。猫でか!」
リビングで対面するなり、ヨーコはそう言って小躍りした。
「名前は?名前」
「ぶー」
「ぶー?」
妹や母親は『ぶーちゃん』と呼んでいる毛の長い猫だ。
アメリカ原産のメインクーンという種類で、子猫の時に知り合いからもらってきたのだが、
元々かなり大きくなると聞いていたのに、さらにこいつは底なしの食欲を発揮するに至って、
実に体重は十キロを超えてしまっている。
『ブマー』というのが彼の本名だが、家族の誰も今はそう呼ばない。
「重っ」
ヨーコはぶーを抱きかかえて嬉しそうに喚いている。
ぶーは身じろぎするのもめんどくさいというように、眠そうな顔をしてされるがままになっている。
その騒ぎを聞きつけて、ラザルスが部屋の中にやってきた。
「あ、犬だ」
ウェルシュ・コーギーという種類で、とても賢い男の子だ。おとなしく、また言いつけをよく聞くので、室内で飼っている。
こげ茶色の背中に、胸は白い。手足が短くてちょこちょこと走るのでかわいらしい。
成犬だけど小柄なので、猫のぶーと同じくらいの大きさに見える。
ラザルスは舌を出しながら、ぶーを抱えたヨーコの周りをくるくると回転し始めた。
ぶーは抱きかかえられたままその動きを目で追っている。
ヨーコは「わわわわわ」と言いながら、同じようにきょろきょろしてはしゃいでいる。
うちには他にも『もも太』という名前の雑種のオス猫がいるが、いつも外に遊びに出ていてあまり家には帰ってこない。
「お姉ちゃん、お客さん?」
いつの間に帰ったのか、妹までも制服のまま顔を覗かせた。
「そうだよ。お前、いいから引っ込んでろ」
友だちに家族を見られるのが気恥ずかしくて、邪険に追い払うと、妹は「べ」と舌を出して顔をしかめて見せた。
そして廊下から首を引っ込める。
ヨーコは驚いて目を丸くしていた。妹の消えた廊下の方を指差して「まじで?」と訊いてくる。「そうだよ」と答えておいた。
それからひとしきりぶーとラザルスに遊んでもらった後、ヨーコは「他には?他には?」と訊いてくる。
「あと、九官鳥の『ピーチ』と、ハムスターを二匹飼ってる」
私がそう言うと、ヨーコは少し顔色が悪くなった。
「ハムスター飼ってんだ……」と、強張ったような表情を浮かべる。
どうしたんだろう。
「いや、子どものころ毒ハムに噛まれてから、どうも苦手なのさ」
毒ハムスター?冗談のわりには嫌に真剣な口調だった。
「好きなんだけどね」と空笑いをしている。よく分からない。
「見るだけ見るか?」と訊くと、「……うん。見るだけ見る」と言うので、隣の部屋に案内する。
棚の上にオレンジ色のケージを置いていて、その中にゴールデンハムスターのつがいを飼っていた。
そのころはなかなか子どもを生まないなあと思っていたのだが、
後に分かったところによると、結果的に両方オスだったので無理からぬことだった。
「かわいいなあ」
ヨーコは部屋の入り口のドアの後ろに隠れ、顔を半分だけ出してそう言う。そんなに離れていたらよく見えないだろうに。
「毒なんてないよ」
人に慣れているから、よほど気が立ってない限り、指を差し出しても噛まれることはなかった。
しかし、そう言って呼んでもヨーコは頭を振る。
後から知ったのだが、ヨーコはハムスターにアレルギーを持っていて、
その抜け毛やフケにも反応して、咳き込んだり発疹が出たりする身体だった。
以前友人の家でハムスターに噛まれた時にはショック症状を起こし、救急車で運ばれることになったのだそうだ。
それでもよほどハムスターが好きなのか、
ヨーコにはその後も、時々市内の百貨店にあるペットショップに行くのに付き合わされた。
そんな時ヨーコは、離れた場所からハムスターのコーナーをじっと見つめていて、
その小動物たちがどんな様子か逐一私に訊いてきた。
そのたびに私は苦笑しながら、エサを食べる様子や小さな手の動きなどを身振り手振りで説明したものだった。
照れくさいというより、正直恥ずかしかったが、嬉しそうなヨーコを見ていると、そんな思いもどこかへ行ってしまった。
「こっちがピー助だ」
私は部屋の隅にいた九官鳥のピーチを鳥籠ごと持ち上げて、ドアの方へ向かった。
ヨーコが部屋の中に入ってきそうになかったからだ。
「わー、かわいい」
そんなことを言うヨーコの脇をすり抜けて、元のリビングに戻る。
ピーチは自分の居城が動き出したことに興奮して、頭を振りながら甲高い声でさえずっている。
背の低いタンスの上に鳥籠を乗せるとピタリと鳴きやみ、
今度はここが城下町かい、とでも言うようなふてぶてしい顔で周囲を見渡した後、またピョロピョロと鳴き始める。
「ピースケちゃん」とヨーコが呼びかけると、ピーチはすぐに返事をする。
「ピーチャン、ピーチャン」
「男の子?」
「そう」
「ソウ、ソウ、ピーチャンイイコ、ピーチャンイイコ」
ピースは鳴きながら鳥籠の中を歩き回る。
「ピー助、ももたろうは?」
私がそう言うと、首を傾げる。
「むかし、むかし、あるところに」
導入部分を口にすると、やがて真似をするように「ムカシ、ムカシ、アルトコロニ……」とやけに低い声で始める。
ピーチはこれが得意なのだ。
「オジーサント、オバーサンガ、スンデ、オリマシタ、ピョロピョロ……」
「すごーい。上手」
ヨーコが手を叩いて喜んでいる。
ピーチのももたろうは、結局猿を仲間にしたあたりでまた最初のムカシ、ムカシに戻ってしまい、
鬼が島までは到着しなかった。
以前父親が頑張って教え込んでいた時には、鬼をやっつけて故郷に凱旋するところまで通して言えたのだが、
少し時間が空くともう忘れてしまうものらしい。
私が分析するに、犬、猿、キジを仲間にする過程で、
焼き回しというか、同じ展開が繰り返されるのが一番の原因ではないかと思う。
「オコシニツケタ、キビダンゴ、ヒトツ、ワタシニ、クダサイナ」という印象的なフレーズがあるが、
犬を仲間にしたあと、また猿の時にも繰り返されるので、そこでわけが分からなくなるらしい。
それでもヨーコは大喜びで、餌をやっていいかとせがんできた。
仕方がないのでオヤツを少しだけあげることにして、
大好きなひまわりの種をいくつかヨーコに持たせ、それを鳥籠越しに手ずから食べさせた。
ピーチがくちばしを伸ばしてくるたびに、ヨーコはきゃあきゃあと騒ぐ。
その騒ぎを訊きつけてまたラザルスが尻尾を振りながらリビングにやってきて、
ふんふんとヨーコの足のあたりを嗅いで回る。
「ねえ、ピースケちゃんはどこかで買ったの?人にもらったの?」
「ああ、親戚からもらった。三歳の時にもらって来て、今二年目だから、四歳か五歳くらいだな」
「ふうん。うちも九官鳥とかオウムを飼いたいなあ」
無邪気にそう言うヨーコに、軽いいじわるのつもりで私はこんなことを言った。
「でも、こいつはたまに気持ちの悪いことを言うぞ」
「ええ?気持ちの悪いことってなに」
「……誰も教えてないこと」
それを聞いてヨーコは少し気味悪そうな顔をした。
そもそもピーチは親戚の家で飼われていたが、その家のお祖父ちゃんが亡くなった後、奇妙な言葉をさえずり始めたのだ。
「メシガマズイ。アジガシナイ。メシガマズイ」
「タバコガナイ。タバコヲスイタイ。タバコスワセロ」
いずれも亡くなる前の入院中に祖父が口にしていたことだ。そんな言葉を生前の祖父は家で口にしたこともなかったのに。
それだけではなく、まるで祖父そのもののように小言めいたことを喋ることもあった。
「トイレノ、トハ、チャントシメナサイ」
「ヤサイハ、サイゴノ、ヒトカケマデ、ツカイナサイ」
などのような言葉だ。
それらだけならば、普段から祖父が口にしていたので、ピーチが覚えていてもおかしくはないのだが、
祖父が亡くなってまだひと月と経っていないころに、ふいにこんな言葉を発したのだ。
「カミダナニハ、チャント、シロイカミヲ、ハリナサイ」
確かにピーチは、神棚に白い紙を貼れ、と言った。
家族は始めなんのことか分からなかったが、あまりその言葉を繰り返すので気味が悪くなり、
近所の年寄りに訊いてみると、それは古来からの風習の一つだった。
神棚封じ、と言って、
その家から人死にが出ると、四十九日があけるまで白い紙で神棚を封じ、拝んだりもしてはいけないのだそうだ。
黒不浄、つまり死の穢れを神棚に近づけないためだ。
しかし、そんなことは家族の誰も知らなかった。そんな慣習を知っているのは、古い人である祖父くらいだったからだ。
ピーチはまるで祖父が乗り移ったかのように、そのことを教えてくれたのだった。
そんなことが続き、気味悪がったその親戚の家は、ピーチを手放すことにした。
そこで動物好きの私の両親の悪い癖が出て手を挙げ、うちにもらわれてきたという経緯だ。
前の家で喋っていたようなことも段々と口にしなくなり、
というよりもうちの家族みんながこぞって好き勝手なことを覚えさせようとするので、トコロテン式に忘れていった。
特に、親戚が怖がっていた、亡くなったお祖父ちゃんのような口ぶりの言葉は、うちに来てからはピタリと止まり、
本当にそんなことを言っていたのかと逆に疑ったものだった。
しかし、親戚の話の裏付けは別のところからやってきた。
ピーチがうちの家族になってから半年ほど経った時、急に「コロシテヤル」という汚い言葉をさえずり始めたのだ。
本人はいたって楽しそうにさえずっているのだが、聞いている方はゾッとした。
誰が教えたのか、犯人探しが行われたのだが、家族みんなが知らないという。私も身に覚えはなかった。
テレビを置いていない部屋で飼っていたので、勝手に覚えることはない。家族の誰かが教えたはずなのだ。
犯人と疑われた妹が憤慨して、プチ家出をしたのを覚えている。
結局どこでその「コロシテヤル」という言葉を覚えてしまったのかは分からなかったが、
ピーチはそのころから時おり、そういう誰も教えていないはずの言葉をさえずるようになった。
「コウエンノスナバ、ポシェットガ、オチテル」
「カキザワサンノ、ゴシュジン、ブチョウニナッタ」
「センキョカー、ウルサイ」
そのほとんどは他愛のないものだったが、みんな全く身に覚えがなく、
それどころか、誰も知らなかったような情報まであった。
例えば、選挙カーがうるさい、とピーチが言った時点では、まだ選挙カーはうちの家のあたりにはまだ来ていなかった。
いったいどうしてピーチがそんな言葉を喋るのか分からないので、気持ちが悪かった。
妹の説では、ピーチは言わば生きたラジオのようなもので、
周波数のあった誰かの意思を受信して、それを自動的に口にしているのではないかとのことだった。
飼われていた親戚の家ではお祖父ちゃんが亡くなったが、その霊魂がまだその家に漂っていて、
時々ピーチの口を借りて喋るのだという。
そんなわけあるか、と言ってやったが、動物は人間よりもお化けに対する霊感が強いのだと主張する。
『猫のぶーちゃんだって、時々なにもない壁を見ている』というのがその補強材料だった。
あれは確かに私もなんでだろうと思ったことがある。
妹が言うには、うちにやってきたピーチは近くにお祖父ちゃんの霊もいなくなったので、
今では近所の人の思念や、浮遊霊の声を受信してしまっているのだ、ということだった。
そんなことを説明すると、ヨーコは嫌そうな顔をして後ずさった。
「うそだあ」
今まさについばもうとしていたひまわりの種を引っ込められたピーチが、
苛立ったように籠の枠を内側から噛んでガシャガシャと揺らせた。
「あたしそういうの苦手なんだから、やめてよね」
「悪い悪い」
私は笑ってそう言いながら、どこか胸の片隅でふと、凍りつくような冷たいものに撫でられたような感覚をおぼえた。
それは妹の主張する怪談めいた話とはまた別の、異質な想像であり、
ある時ふいに自分の頭の中にするりと入り込んだそれは、ある種の茫漠とした不安と、眩暈とを私にもたらした。
それを思い出してしまったのだった。
「ああ、もう」
ヨーコは顔を強張らせた私に気づきもせず、頭を振りながら、ピーチにひまわりの種をもう一度あげようと手を伸ばす。
その足元ではまだラザルスが上目遣いに鼻先を近づけていて、
そうしてあんまり匂いを嗅いでいるのが気になったのか、
部屋の隅で丸くなっていたぶーまでが起き上がって、反対のヒザ側から匂いを嗅ぎ始めた。
「ねえちょっと、なんかさっきからこの子たち、レディーに失礼じゃない?」
立ったまま変な顔をするヨーコに私は笑って言う。
「初めて見るような人には、いつもこうだよ」
「ほんとにぃ?」
「本当だ」
腕組みをしながら私は無駄に力強く断言した。
そんなことがあった数日後。
夜中にふと目が覚めた私は、喉の渇きを覚えて寝床から起き上がった。
いま何時だ?
明りをつけようとしたが、目が眩むのが嫌で、結局そのまま歩いて自分の部屋を出る。
二階の廊下は階段の脇の小さな照明だけがぽつんと点いていて、その明りを頼りに一階に降りていく。
家族はみんな寝ていて、家の中はしん、としている。
私は足音を忍ばせて台所に入り、炊飯器についているディスプレイの青い光を頼りに、冷蔵庫からお茶を取りだす。
コップ一杯を飲みきると一息ついた。
静寂に、耳の奥が甲高く鳴っている。夜中に目が覚めたのはいつ以来だろうかとふと考える。
家族を起こさないようにひっそりと台所を出て、忍び足で廊下を進んでいる時だった。
私の耳は静寂以外のなにかをとらえた。
立ち止まり、それが聞こえた方向に目をやると、居間のドアが少し開いている。
それが微かに揺れた気がした。キィ、という聞こえなかったはずの音を、頭の中で勝手に再生する。
普段から鍵を掛けるわけでもなく、また冷房や暖房をつけている季節でもないので、
ドアが半開きなのはいつものことだったが、私の直感はなにか得体の知れない予感を告げていた。
そっと近付いてドアの隙間を広げると、暗い室内がその奥にのびる。
「ピー助?」
声をひそめながら、九官鳥のピーチをいつもの愛称で呼ぶ。
×××
また、なにか聞こえた。
部屋の中から。
誰かの声だ。
ハムスターの鳴き声とは明らかに違う。人間の声のように聞こえた。
「ピーチ?」
部屋の中に入り込むと、窓のカーテン越しに月の光が微かに差し込み、
海の底のような暗い空間に奇妙な縞模様を浮かび上がらせていた。
×××
まただ。また聞こえた。
部屋の隅にある鳥籠の方から。
鳥籠には黒い布を被せてある。光が入り込まないように。ピーチが寝る時にはいつもそうするのだ。
その黒い布の内側から、ぼそぼそという話し声が聞こえてくる。
ああ、ピーチが喋っている。人の言葉で。
私はわけもなく湧いてくる寒気が、身体の表面を走り抜けるのを感じた。いったいなにを喋っているのだろう。
×××
私はゆっくりと近づきながら耳をすませる。
こんな時間にピーチはどうして起きているのだろう。たまたまだろうか。それともいつも起きているのだろうか。
いつも家族が寝静まった深夜に、小さな籠の中でひとり、私たちの知らないなにかを話しているのだろうか。
妹の言葉が頭をよぎる。
ピーチは、ここにいない人や死んでしまった人の思念を受信して、それを言葉にして囀るのだと。
まるでラジオのように。だから時おり、誰も教えていないはずの言葉を流暢に発するのだ。
今もそうなのだろうか。誰も教えていない言葉を、あるいは家族の誰も知らないはずの話を……
だったら、今この暗い部屋の中には、目に見えない人間の言霊が漂っているのか。
あるいは、見ることも触れることもできない死んだはずの人間が今、この部屋の中に立っているのか。
鳥籠の形をした布の先に手が触れ、私は動きを止める。
妹の主張がもたらしたそんな恐ろしい想像がふいに希薄になり、
また別の想像が自分の中のどこか暗いところから湧いてくるのを感じた。
妹の話をなかば笑いながら聞いた時、私はそれとは全く別の想像をしてしまっていた。
とっさに気味の悪いそれを心の奥に押し込め、忘れようとしていた。今まで。
なのに。
私のした想像。いや、してしまった想像。
それは、
夜中にふいに寝床から起きる私。
しかし私には意識がない。私としての意識が。
夢遊病のように階段を降り、鳥籠の前に立つ。
そしてその中に話しかける。
無意識の私が。いや、あるいは私という器の中に入り込んだ、もう一人の別の私が。
その言葉は、
…………ソウムド…………
耳に入った音に、私は我に返った。
鳥籠の中から声が聞こえる。
押しつぶされたような声。ひどく聞き取りづらい。
私は息を飲んで耳をすませる。
布越しに声は続く。
…………ミツカ…………
…………シキチ…………
…………ルノサン…………
ようやくそれだけが聞こえる。
それで声は止まり、しばらくするとまた同じ言葉が繰り返される。
…………ソウムド…………
…………ミツカ…………
…………シキチズ…………
…………ルノサンポシャ…………
やはり良く聞き取れない。
なぜか背筋がぞくぞくする。
…………ソウムドイ…………
…………ミツカイ…………
…………シキチズ…………
…………ルノサンポシャ…………
四つの言葉が繰り返されているようだ。いったいこれは誰の言葉なのか。
私ではない。そう直感が告げている。
想像してしまっていたように、記憶のない時間、私自身がピーチに教えた言葉などではない。
ピーチ自身の言葉?
いや、それも違う。
イメージが浮かぶ。
鳥の小さな頭は空洞で、遠くから目に見えない波のようなものが押し寄せてきて、
その空洞の中で反響し、くちばしが言葉として再生する。
誰もいない部屋で、誰にも聞かれず。
なぜこんなに怖いのだろう。ガチガチと歯が音を立てる。
悪意。
夜に滲み出る目に見えない悪意が、ほんの気まぐれに寝静まった住宅街を通り過ぎていく。
そんな気がした。
…………キケン…………
…………キケン…………
…………ゼンイン…………
…………ケス…………
最後にそう言って、鳥籠の中の声はぴたりと止まった。
微かな月明かりの中に沈む部屋に、静けさが戻ってきた。
私はハッとして腕を伸ばし、布を取り払うと、駕籠の中のピーチが驚いたように頭を振って小さく鳴いた。
不思議そうに首を傾げながら、口の中で小さくウロウロという低い声をこねている。
それが私には、我に返った姿のように思えた。
仄かな月の光を反射し、ピーチの瞳が一瞬くるりとまたたく。それが妖しく艶かしい黒い宝石のように見えた。
なにか、恐ろしいことが起こる前触れのようだった。
[完]
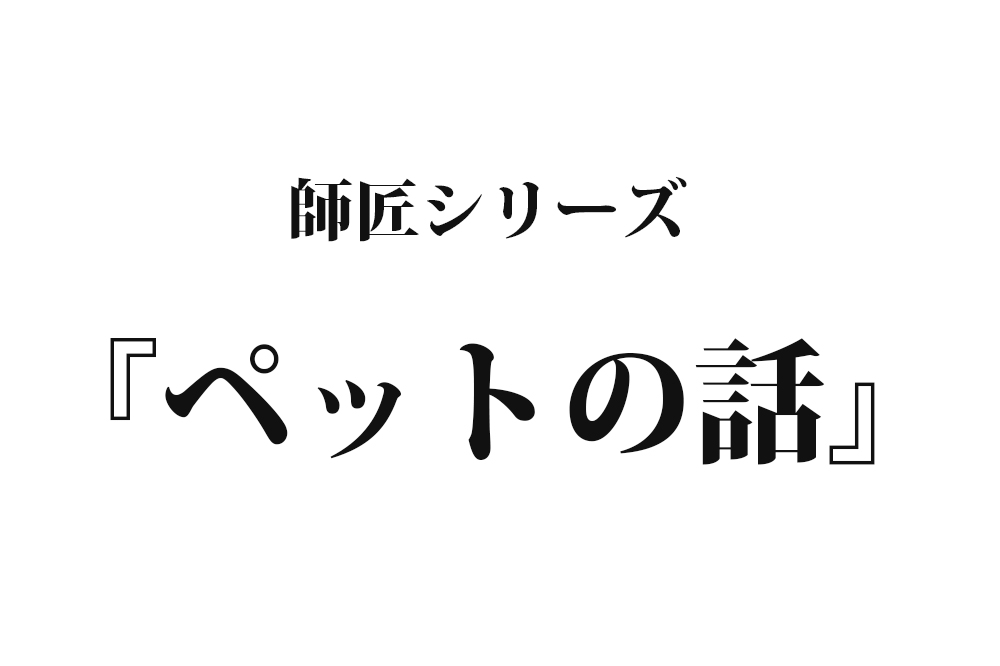
コメント