山にまつわる怖い話【24】全5話
山の女神様
今の年代の人に、狩りをした事のある人は少ないでしょう。
昔、私は祖父に連れられて、狸を捕る為に数度、山にトラバサミを仕掛けに行った事があります。
山にも色々な約束事があります。うろ覚えですが、女山でしたので立ちションベンは、女神様に見える様に頂を向いてする事
(性器を見えないように隠すと女神様が怒って、山に遭難します)とか、お弁当は半分食べたら残りは家まで持って帰る事とか、
狸の後足は、1本は女神様に御供えする事とか、他にも細かな注意が沢山あったはずでした。
ある夏休みの日、祖父の家に遊びに来ていた私は、川に泳ぎに行こうとして、気が付くと何故か山の中に居ました。
昼御飯前に出たはずなのに、あたりは真っ暗で、訳が判らず泣いてしまいました。どのくらい泣いていたでしょう?
辺りがスゥ~っと明るくなって、顔を上げると、目の前に青い光が浮いていました。
その光は優し、暖かくて、何故か彼女が助けてくれるのだと解りました。そして、漂い始めた光に付いて行き、山の麓に下りました。
山の麓には幾つもの懐中電灯の光が集まっていました。その中に祖父の姿を見つけ、「おじいちゃん」と声を掛けると、祖父は飛んで来て私を抱きしめました。
そしてすごい剣幕で怒り始めたのです。私が帰ってきたのは、家を出た翌日の夜でした。その時です。私は変な事に気が付きました。
私はたった今山の麓に降り立ちました。ですが、周りを見回すと、そこは山から1キロ程離れた祖父の家の前だったのです。
青い光は何時の間にか消えていました。
その事祖父に話すと、祖父は宴会をすると言って近所の男の人達だけでご馳走を持って、山の祠の前で宴会をしました。
僕や、従兄弟達、近所の男の子達も付いていきましたが、皆お酒を飲み、歌って楽器を奏で、踊って、大騒ぎでした。
後で聞いたのですが、「女神様が最近、人が山に入らないので寂しくなってお前を呼んだのだろう」と祖父達は言いました。
その後、他にも一晩だけ、山へ消えた男子が出た事から、毎年夏祭りの後には山の祠で宴会をする様になったそうです。
クラウゾ
隠れ里、とか、隠し里、などという場所が時折ある。
実際には「○○の隠れ里」などと言われ、所在のはっきりした場所になっていて
隠れ里どころではなく、それを売りの観光地になって賑わったりしている。
そんな隠れ里と呼ばれる場所の幾つかは実際に村の存在が判明せず
迷信と思われている所もあるようだ。
登山というより、ハイキングの好きな二人組みが、ある山間の地域で
この「隠れ里」の云われがある場所を目指して山に入った。
ただのハイキングコースで、無理なルートを取るわけでもなく
史跡のひとつでも有ればと気軽に歩いていた。
予報では晴天が続くとの事だったが、そこは山の天気。
幾つかの史跡らしきものを回って、そろそろ帰路につく頃になって
にわかに空が暗くなり、大粒の雨が落ちてきた。
雨具は用意していたものの、あまりの雨足に雨宿りをと思い
先ほど見てきた大きめの石碑にかかる屋根で雨宿りをする事にした。
5分ほど木々の中を歩くとすぐにその屋根は見えてきた。
雨の中を歩いたせいもあって、軒先で座り込むと眠気に襲われ
二人して石碑にもたれてウツラウツラとし始めた。
しばらくすると、誰かの話し声に目が覚めた。
辺りを見回すと確かに誰かが居るのは解った。
あぁ、雨も止んだんだな。そう思って少し目を開けると
そこに数人の人影があった。日はまだ高く時間は昼下がり。
ただ、鬱蒼と茂る木々の中なので人影は解っても詳細は見えない。
意識がはっきりしてくると妙な事に気づいた。
話し声は聞こえるのだが、その声は妙に甲高く意味が解らない。
それに、膝を抱えてうつむいてるのに人影の全体が解る。
ハッとなって顔を上げるとそこには、身の丈30cmほどの
見るからに古めかしい格好をした農夫のような男性が3人立っていた。
立とうとしても体が重くて立ち上がれない。コマ送りのように動く3人が
自分達の周りをせわしく動いている。得体の知れない恐怖が襲う。
盛んに棒切れを振り回してこちらに何かを訴えてくるようなのだが
早回しのテープのような声ではっきりとは解らない。
脂汗が止めどなく流れる中、その中の一人がツカツカと近づいてきた。
膝のあたりまで顔を近づけると、やはりテープの早回しのような声で何か叫んでいる。
ガタガタ震えていると、向こうは怒ったような顔で今度はゆっくりとこう言った。
「カ・エ・レ。デ・ネ・バ。ク・ラ・ウ・ゾ。」その瞬間、意識が途切れた。
雨はあがり、嘘のように晴れ渡った空の下で目が覚めた。
嫌な夢を見た。そう思って仲間を起こすと異常なほどに汗をかいて震えている。
「どうした?」その声に飛び上がる仲間。「あれは何だったんだ!?」
夢ではなく、やはり彼も同じものを見ていたのだ。恐怖に駆られて立ち上がると
一目散で元来た道を引き返して町まで帰った。
同じ状況で同じような幻覚でも見たのだろうと、山に慣れた二人は思ったのだが
帰りの車中で、膝に付いた小さな泥の手形を見て、心底震えたという。
隠れ里。その昔、ごう病や奇形の血筋を持った者達が村から追い出され
山中深くに人目を忍んで暮らした場所だとも聞く。
社会から忘れられた人達が今もひっそりと暮らしているのかも知れない。
炭焼き
親父に聞いた話。
30年くらい前、親父はまだ自分で炭を焼いていた。
山の中に作った炭窯で、クヌギやスギの炭を焼く。
焼きにかかると、足かけ4日くらいの作業の間、釜の側の小屋で寝泊まりする。
その日は夕方から火を入れたのだが、前回焼いた時からあまり日が経っていないのに、
どうしたわけか、なかなか釜の中まで火が回らない。ここで焦っては元も子もないので、
親父は辛抱強く柴や薪をくべ、フイゴを踏んで火の番をしていた。
夜もとっぷり暮れ、辺りを静寂が支配し、薪の爆ぜる音ばかりが聞こえる。
パチ・・・パチ・・パチ・・・
ザ・・・ザザザ・・・
背後の藪で物音がした。
獣か?と思い、振り返るが姿はない。
パチ・・・パチン・・パチ・・パチ・・・
ザザッ・・・・ザザ ザ ザ ザ ザ ァ ァ ァ ァ ―――――――――――
音が藪の中を凄いスピードで移動しはじめた。
この時、親父は(これは、この世のモノではないな)と直感し、振り向かなかった。
ザ ザ ザ ザ ザ ザ ザ ザ ザ ザ ザ ザ ザ
音が炭釜の周囲を回りだした。いよいよ尋常ではない。
親父はジッと耐えて火を見つめていた。
ザ・・・
「よお・・何してるんだ。」
音が止んだと思うと、親父の肩越しに誰かが話しかけてきた。
親しげな口調だが、その声に聞き覚えはない。
親父が黙っていると、声は勝手に言葉を継いだ。
「お前、独りか?」「なぜ火の側にいる?」「炭を焼いているのだな?」
声は真後ろから聞こえてくる。息が掛かりそうな程の距離だ。
親父は、必死の思いで振り向こうとする衝動と戦った。
声が続けて聞いてきた。
「ここには、電話があるか?」
(なに?電話?)
奇妙な問いかけに、親父はとまどった。。
携帯電話など無い時代のこと、こんな山中に電話などあるはずがない。
間の抜けたその言葉に、親父は少し気を緩めた。
「そんなもの、あるはずないだろう。」
「そうか。」
不意に背後から気配が消えた。時間をおいて怖々振り向いてみると、やはり誰も居ない。
鬱蒼とした林が静まりかえっているばかりだった。
親父は、さっきの出来事を振り返ると同時に、改めて恐怖がぶり返して来るのを感じた。
恐ろしくて仕方が無かったが、火の側を離れる訳にはいかない。
念仏を唱えながら火の番を続けるうちに、ようやく東の空が白んできた。
あたりの様子が判るくらいに明るくなった頃、
祖父(親父の父親)が、二人分の弁当を持って山に上がってきた。
「どうだ?」
「いや、昨日の夕方から焼いてるんだが、釜の中へ火が入らないんだ。」
親父は昨夜の怪異については口にしなかった。
「どれ、俺が見てやる。」祖父は釜の裏に回って、煙突の煙に手をかざして言った。
「そろそろ温くなっとる。」そのまま、温度を見ようと、 釜の上に手をついた。
「ここはまだ冷たいな・・」そう言いながら、炭釜の天井部分に乗り上がった・・・
ボゴッ
鈍い音がして、釜の天井が崩れ、祖父が炭釜の中に転落した。
親父は慌てて祖父を助けようとしたが、足場の悪さと、立ちこめる煙と灰が邪魔をする。
親父は、火傷を負いながらも、祖父を救うべく釜の上に足をかけた。
釜の中は地獄の業火のように真っ赤だった。火はとっくに釜の中まで回っていたのだ。
悪戦苦闘の末、ようやく祖父の体を引きずり出した頃には、
顔や胸のあたりまでがグチャグチャに焼けただれて、すでに息は無かった。
目の前で起きた惨劇が信じられず、親父はしばし惚けていた。
が、すぐに気を取り直し、下山することにした。
しかし、祖父の死体を背負って、急な山道を下るのは不可能に思えた。
親父は一人、小一時間ほどかけて、祖父の軽トラックが止めてある道端まで山を下った。
村の知り合いを連れて、炭小屋の所まで戻ってみると、祖父の死体に異変が起きていた。
焼けただれた上半身だけが白骨化していたのだ。
まるでしゃぶり尽くしたかのように、白い骨だけが残されている。
対照的に下半身は手つかずで、臓器もそっくり残っていた。
通常、熊や野犬などの獣が獲物の臓物から食らう。
それに、このあたりには、そんな大型の肉食獣などいないはずだった。
その場に居合わせた全員が、死体の様子が異常だということに気付いていた。
にも拘わらす、誰もそのことには触れない。黙々と祖父の死体を運び始めた。
親父が何か言おうとすると、皆が静かに首を横に振る。
親父は、そこで気付いた。これはタブーに類することなのだ、と。
昨夜、親父のところへやってきた訪問者が何者なのか?
祖父の死体を荒らしたのは何なのか?
その問いには、誰も答えられない。誰も口に出来ない。
「そういうことになっているんだ。」村の年寄りは、親父にそう言ったそうだ。
今でも、祖父の死因は野犬に襲われたことになっている。
ヤマセ
民話収集してるが、岩手は遠野市に通いつめる渓流釣り師、その内の、少なくとも二人から聞いた話は印象に残っている
遠野市の山峡には時折ヤマセがやって来るが、このヤマセの中で、ときたまざわざわとした何者かの声を聞くという
ヤマセとは、春~夏に太平洋側からやって来る冷湿な風で、このヤマセが来ると遠野盆地は
まるでドライアイスの煙の中に沈んだように、とっぷりと白く覆い包まれる。特に標高の低い谷川などには滞留するそうだ
日によっては手を伸ばすと掌が見えなくなるほど霧が濃い場合もあり、遠野に通う釣り人には、これに出会って山中に立ち往生を余儀なくされた人も多い
そして、このヤマセの中では人の声が聞こえる場合がある、という。自分が話を聞いた二人の話に共通しているのは、それが決して薄気味悪いものではなく、
どちらかというと賑やかで、大人数の人間が寄り集まって祝宴を開いているような音なのだという
自分が話を聞いた一人は、釣りをしている最中にヤマセに会い、クルミの木に背を預けてじっと霧をやり過ごしている最中、
がやがやとした人の声、カチャカチャと食器がこすれ合う音、神楽囃子の音が聞こえてきて、正気を保つのに必死だったという
また別のひとりは、ヤマセの中で一心不乱に釣り続けている最中、やはりこそこそと話し合う複数の人の声を聞いたそうだ
声の主が冗談を言い合ってくすくすと笑いあう声まで聞こえたそうで、彼はこの声の主を山の精霊であろうと言っていた
声の主の素性、発生条件等はわからないが、なんだかちょっとロマンあふれるなぁと思った話
ヤマセは一体何を運んでくるのだろう
梅の香り
友人の実家の持ち山の中に、1本だけ、黄色い花の咲く梅の木がある。
黄桜より濃く、福寿草より淡い色のその花は、決して蝋梅などではなく、
柔らかなまろみを帯びた花弁も、気品溢れるその香りも、まさに梅以外の
何者でもない。
ただ、その在り処が定かではない。
毎年、山を見回りに行った親父さんが見つけるのだが、歩いている途中に
ふと出会い、一枝そっと折り取って来るらしい。
後から見当を付けて出向いてみても、何処にも梅の木なんぞ有りはしない。
その年の花が、大きければ畑の作物が、数が多ければ稲が豊作だと言う。
不思議な事に、持ち帰ったその枝を地面に刺して根付かせても、世間で
ありきたりの紅梅か白梅にしかならない。
その不思議な黄梅に、今年は友人が出会ってしまった。
たまたま休みに実家へ戻り、親父さんと山を歩いていた時に、どうした訳だか
はぐれてしまい、気が付けば目の前に、馥郁たる香を放つ満開の黄梅があった。
子供の頃から馴染んでいた不思議なそれとの出会いに、友人は感動し、手折る
事なく道を戻った。
はぐれた事にさえ気付いていなかった親父さんは、彼の話を聞いて一言
「世代交代、だな」そう寂しげに呟いた。
友人は、この3月一杯で都会を離れ、実家へ戻る。

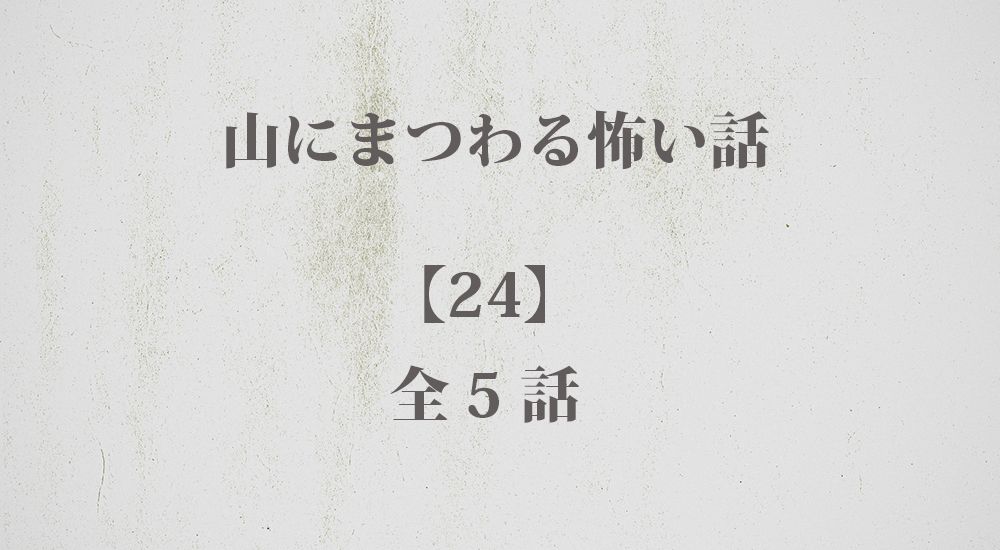

コメント