『空を歩く男』
【霊感持ちの】シリーズ物総合スレ20【友人・知人】 668 :空を歩く男 ◆oJUBn2VTGE :2012/09/01(土) 23:03:50.75 ID:itFWmvQ50
師匠から聞いた話だ。
大学一回生の春だった。
そのころ僕は、同じ大学の先輩だったある女性につきまとっていた。もちろんストーカーとしてではない。
初めて街なかで見かけたとき、彼女は無数の霊を連れて歩いていた。
子どもの頃から霊感が強く、様々な恐ろしい体験をしてきた僕でも、
その超然とした姿には真似の出来ない底知れないものを感じた。
そしてほどなくして大学のキャンパスで彼女と再会したときに、
僕の大学生活が、いや、人生が決まったと言っても過言ではなかった。
しかし言葉を交わしたはずの僕のことは、全く覚えてはいなかったのだが。
『どこかで見たような幽霊だな』
顔を見ながら、そんなことを言われたものだった。
そして、綿が水を吸うように、気がつくと僕は彼女の撒き散らす独特の、そして強烈な個性に、思想に、思考に、
そして無軌道な行動に心酔していた。
いや、心酔というと少し違うかも知れない。ある意味で、僕の、すべてだった。
師匠と呼んでつきまとっていたその彼女に、ある日こんなことを言われた。
「空を歩く男を見てこい」
そらをあるくおとこ?
一瞬きょとんとした。そんな映画をやっていただろうか。いや、師匠の言うことだ。なにか怪談じみた話に違いない。
その空を歩く男とやらを見つければいいのか。
「どこに行けばいいんですか」と訊いてみたが、答えてくれない。
なにかのテストのような気がした。ヒントはもらえないということか。
「わかりました」
そう言って街に出たものの、全く心当たりはなかった。
空を歩く男、というその名前だけでたどりつけるということは、
そんな噂や怪談話がある程度は知られているということだろう。
正式な配属はまだだが、すでに出入りしていた大学の研究室で訊き込みをしてみた。
地元出身者が多くないこの大学で、同じ一回生に訊いても駄目だ。
地元出身ではなくとも、何年もこの土地に住んでいる先輩たちならば、そんな噂を聞き及んでいるかも知れない。
「空を歩く男、ねえ」
何人かの先輩をつかまえたが、成果はあまり芳しくなった。
なにかそんな名前の怪談を聞いたことがある、というその程度だった。内容までは分からない。
所属していたサークルにも顔を出してみたが、やはり結果は似たりよったりだった。
さっそく行き詰った僕は思案した。
空を歩く、ということは空を飛ぶ類の幽霊や妖怪とは少しニュアンスが違う。
しかも男、というからには人間型だ。
他の化け物じみた容姿が伴っているなら、その特徴が名前にも現れているはずだからだ。
想像する。
直立で、なにもない宙空を進む男。
それは、なにか害をもたらすことで恐れられているようなものではなく、
ただこの世の理のなかではありえない様に対してつけられた畏怖の象徴としての名前。
空を歩く男か。
それはどこに行けば見られるのだろう。空を見上げて、街じゅうを歩けばいつかは出会えるのだろうか。
近い怪談はある。例えば部屋の窓の外に人間の顔があって、ニタニタ笑っている。あるいはなにごとか訴えている。
しかしそこは二階や三階の高い窓で、下に足場など無く、人間の顔がそんな場所あっていいはずがなかった、というもの。
かなりメジャーで、類例の多い怪談だ。
しかし、空を歩く男、という名前の響きからは、なにか別の要素を感じるのだ。
結果的に空を歩いていたとしか思えない、というものではなく、
空を歩いている、というまさにその瞬間をとらえたような直接的な感じがする。
…………
そらをあるくおとこ。
そんな言葉をつぶやきながら、数日間を悶々として過ごした。
「知ってるやつがいたよ」と教えてくれたのは、サークルの先輩だった。
同じ研究室に、たまたまその話を知っている後輩がいたらしい。
さっそく勢いこんで研究室に乗り込んだ。
「ああ、空を歩く男ですよね」
「知ってる知ってる」
僕と同じ一回生の女の子だった。それも二人も。どちらも地元出身で、しかも市内の実家に今も住んでいるらしい。
優秀なのだろう。うちの大学の学生で、地元出身の女性はたいてい頭がいいと相場決まっている。
女の子だと、親があまり遠くにやりたくないと、近場の大学を受けさせる傾向がある。
その場合、本来もう少し高い偏差値の大学を狙えても、地元を優先するというパターンが多い。
そんな子ばかりが来ているのだ。
つまりワンランク上の偏差値の頭を持っている子が多いということになる。
「なんだっけ。幸町の方だったよね」
「そうそう。うちの高校、見たって子がいた」
「高校に出るんですか」
「違う違う。幸町だって。高校の同級生がそのあたりで見たの」
バカを見る眼で見られた。説明の仕方にも問題がある気がするのだが。
とにかく聞いた話を総合すると、このようになる。
『空を歩く男』はとある繁華街で夜にだけ見られる。
なにげなく夜空を見上げていると、ビルに囲まれた狭い空の上に人影が見えるのだ。
おや、と目を凝らすとどうやらその人影は動いている。
商店のアドバルーンなどではない。ちゃんと、足を動かして歩いているのだ。
しかしその人影のいる位置は周囲のビルよりさらに高い。
ビルの間に張られたロープで綱渡りしているわけでもなさそうだった。
やがてその人影はゆっくりと虚空を進み続け、ビルの上に消えて見えなくなってしまった。明らかにこの世のものではない。
その空を歩く男を見てしまった人には呪いがかかり、
その後、高いところから落ちて怪我をしたり、
もしくは高いところから落ちてきたものが頭に当たったりして怪我をするのだという。
「その見たっていう同級生も怪我をした?」
「さあ。どうだったかなあ」
首を捻っている。
どうやら最後の呪い云々は怪談につきもののオマケようなものか。
伝え聞いた人が誰かに話すとき、そういう怪異があるということだけでは物足りないと思えば、
大した良心の呵責もなく、ほんのサービス精神でそんな部分を付け足してしまうものだ。
ツタンカーメン王の墓を暴いた調査隊のメンバーが次々と怪死を遂げたという『ファラオの呪い』は有名だが、
実際には調査隊員の死因のみならず、死んだということさえ架空の話である。
その『呪い』はただの付け足された創作なのだ。
発掘調査に関わった二十三人のその後の生死を調査したグループの研究では、
発掘後の平均余命二十四年、死亡時の平均年齢七十三歳という結果が出ている。
なにも面白いことのない数字だ。
しかし、そんな怪異譚を盛り上げるための誇張やデタラメはあったとしても、
ハワード・カーターを中心に彼らが発掘したツタンカーメン王の墓だけは真実である。
空を歩く男はどうだろうか。
そんな人影を見た、ということ自体は十分に怪談的だけれども、どこか妙な感じがする。
因縁話も絡まず、教訓めいた話の作りでもない。
そこから感じられる恐ろしさは、その後のとってつけたような怪我にまつわる後日談からくるものではないだろうか。
なんだか本末転倒だ。
つまり肝心の前半部分が、創作される必然性がないのである。
すべての要素が、こう告げている。
『空を歩く男は、実際に観測された』と。
その事実から生まれた怪談なのではないだろうか。
錯覚や何かのトリックがそこにはあるのかも知れない。
話を聞かせてくれた二人に礼を言って、僕は実際にその場所へ行ってみることにした。
平日の昼間にその場所に立っていると変な感じだ。
繁華街の中でも飲み屋の多いあたりだ。
研究室やサークルの先輩につれられて夜にうろつくことはあったが、昼間はまた別の顔をしているように感じられた。
表通りと比べて人通りも少なく、店もシャッターが閉まっている所が多い。道幅も狭く、少し寂しい通りだった。
なるほど。どのビルも大通りにあるビルほどは高くない。良くて四階、五階というところか。
聞いた話から想像すると、この東西の通りの上空を斜めに横断する形で男は歩いている。
恐らくは北東から南西へ抜けるように。
その周囲を観察したが、特に人間と見間違えそうなアドバルーンや看板の類は見当たらなかった。
当然昼間からそれらしいものが見えるわけもなく、僕は近くの喫茶店や本屋で日が暮れるまでの間、時間をつぶした。
太陽が沈み、会社員たちが仕事を終えて街に繰り出し始めると、このあたりは俄かに活気づいてくる。
店の軒先に明かりが灯り、陽気な話し声が往来に響き始める。
その行き交う人々の群の中で一人立ち止まり、じっと空を見ていた。
曇っているのか月の光はほとんどなく、夜空の向こうにそれらしい影はまったく見えなかった。
仮に……と想像する。
この東西の通りでヘリウムが充満した風船を持ち、その紐が十メートル以上あったら。
その風船が人間を模した形をしていたら。
そして紐が一本ではなく、両足の先に一本ずつそれぞれくっついていたとしたら。
下から紐を操ることで人型の風船がまるで歩いているよう見えないだろうか。
今日と同じように月明かりもなく、下から強烈に照らすような光源もなければ、
周囲のビルよりも遥かに高い場所にあるその風船を、本物の人影のように錯覚してしまうことがあるのではないだろうか。
その人影に気づいた人は驚くだろう。
そしてそちらにばかり気をとられ、その真下の雑踏で不審な動きをしている人物には気づかないに違いない。
誰がなぜそんなことを?という新たな疑問が発生するが、とりあえずはこれで再現が可能だという目星はついた。
結局その後小一時間ほどうろうろしてから、飽きてしまったのでその日はそれで帰ったのだった。
次の日、師匠にそのことを報告すると、呆れた顔をされた。
「情報収集が足らないな」
「え?」
「風船かも知れないなんて、誰でも思いつくよ」
師匠は自分のこめかみをトントンと指で叩いて見せる。
「だいたい人影は、最終的に通りのビルを越えてその向こうに消えてるんだ。下から操っている風船でどう再現する?」
あ。
そのことを失念していた。今さらそれを思い出して焦る。
「ちゃんと噂を集めていけば、
その人影を見た人間が呪われて、高い所から落ちて怪我をするというテンプレートな後日譚が、
別の噂が変形して生まれたものだと気がつくはずなんだ」
「別の噂?」
空を歩く男の話にはいくつかのバージョンがあるのだろうか。
「あの通りでは、転落死した人が多いんだよ。
飲み屋街の雑居ビルばかりだ。
酔っ払って階段から足を踏み外したり、低い手すりから身を乗り出して下の道路に落下したり。
何年かに一度はそんなことがある。
そんな死に方をした人間の霊が、夜の街の空をさまよっているんだと、そういう噂があるんだ」
しまった。
たった二人から聞いて、それがすべてだと思ってしまった。
怪談話など、様々なバリエーションがあってしかるべきなのに。
あと一度しか言わないぞ。そう前置きして、師匠は「空を歩く男をみてこい」と言った。
「はい」
情けない気持ちで、そう返事をするしかなかった。
それから一週間、調べに調べた。
最初に話を聞かせてくれた同じ一回生の子に無理を言って、その空を歩く男を見たという同級生に会わせてもらったり、
他のつても総動員してその怪談話を知っている人に片っ端から話を聞いた。
確かに師匠の言うとおり、あの辺りでは転落事故が多いという噂で、
それがこの話の前振りとして語られるパターンが多かった。
実際に自分が目撃したという人は、その最初の子の同級生だけだったが、あまり芳しい情報は得られなかった。
夜にその東西の通りでふと空を見上げたときに、そういう人影を見てしまって怖かった、というだけの話だ。
それがどうして男だと分かったのかと訊くと、『空を歩く男』の怪談を知っていたからだという。
最初から思い込みがあったということだ。
暗くて遠いので顔までは当然見えないし、服装もはっきり分からなかった。ただスカートじゃなかったから……
そんな程度だ。
見てしまった後に、呪いによる怪我もしていない。
ただ記憶自体はわりとはっきりしていて、彼女自身が創作した線もなさそうだった。
その正体がなんにせよ、彼女は確かになにかそういうものを見たのだろう。
これはいったいなんだろうか。
本物の幽霊だとしたら、どうしてそんな出方をするのだろう。地上ではなく、そんな上空にどうして?
霊の道。
そんな単語が頭に浮かんだ。霊道があるというのだろうか。なぜ、そんな場所に?
少しぞくりとした。
見るしかない。自分の目で。考えても答えは出ない。
僕はその通りに張り付いた。日暮れから、飲み屋が閉まっていく一時、二時過ぎまで。
しかし同じ場所に張っていても、周囲を練り歩いても、それらしいものは見えなかった。
焦りだけが募った。
死者の気持ちになろうともしてみた。あんなところを歩かないといけない、その気持ちを。
気持ちよさそうだな。
思ったのはそれだけだった。
目に見えない細い細い道が、暗い空に一本だけ伸びていて、その道から落ちないようにバランスをとりながら歩く……
落ちれば地獄だ。
かつて自分が死んだ汚れた雑踏へ急降下し、その死を再び繰り返すことになる。
落ちてはいけない。
では落ちなければ?
落ちずに道を進むことができれば、その先には?
人の世界から離れ、彼岸へ行くことができるということか。
そんな寓意が垣間見えた気がした。
その通りに張り付いて二日目。
僕は少し作戦を変えて、飲み屋街のバーに客として入った。
そこで店を出している人たちならば、この空を歩く男の噂をもっとよく知っているかも知れないと思ったのだ。
仕送りをしてもらっている学生の身分だったので、あまり高い店には行けない。
女の子がつくような店ではなく、
カウンターがあって、そこに座りながらカクテルなどを注文し、
飲んでいるあいだカウンター越しにマスターと世間話が出来る。そんな店がいい。
このあたりでは居酒屋にしか入ったことがなかったので、行き当たりばったりだ。
とにかくそれっぽい店構えのドアを開けて中に入った。
薄暗い店内には古臭い横文字のポスターがそこかしこに張られていて、
気取った感じもなくなかなか居心地が良さそうだった。
控えめの音量でオールディーズと思しき曲がかかっている。
お気に入りのコロナビールがあったのでそれを注文し、
気さくそうな初老のマスターにこのあたりで起こる怪談話について水を向けてみた。
聞いたことはあるという返事だったが、実際に見たことはないという。
入店したときにはいたもう一人の客もいつの間にかいなくなっていたので、仕方なくビール一杯でその店を出る。
それから何軒かの店をハシゴした。
マスターやママ自身が見たことがあるという店はなかったが、従業員の中に一人だけ目撃者がいた。
そしてそれとなく店内の常連客に話を振ってくれて、
「そう言えば、昔見たことがあるなあ」と言う客も一人見つけることができた。
しかし話を聞いても、どれも似たり寄ったりの話で、結局その空を歩く男の正体もなにも分からないままだった。
せめて、どういう条件下で現れるのか推測する材料になれば良かったが、
話を聞いた二人とも日付や天気の状況などの記憶が曖昧で、見た場所も人影が進んだ方角もはっきりとしなかった。
ただ、夜中に足場もなにもない非常に高い上空を歩く人影を見た、ということだけが一致していた。
そして特にその後、事故などには遭わなかったということも。
一軒一軒ではそれほど量を飲まずに話だけ聞いて退散したのだが、聞き込みの結果が思わしくなく、
ハシゴを重ねるごとに酔いが回り始めた。
何軒目の店だったか、それも分からなくなり、
かなり酩酊した僕がその地下にあったロカビリーな店を出た頃にはもう日付が変わっていた。
「ちくしょう」という、酔っ払いが良く口にする言葉を誰にともなく吐き出しながら、ふらふらと狭い階段を上り、地上に出る。
空を見上げても暗闇がどこまでも広がっているだけで、何の影も見当たらなかった。そのときだった。
「にいさん、にいさん」
そう後ろから声を掛けられた。
振り返ると、よれよれのジャケットを着た赤ら顔の男が手のひらでこちらを招く仕草をしている。
「なんです」
このあたりでは尺屋という、民家の一室を使った非合法の水商売があるのだが、一瞬、その客引きではないかと思ったが、
しかしこう酔っ払っていては仕事になるまい。
「さっき、中であの怪談の話をしてたろう」
ああ、なんださっきの店にいた客か。しかしどうしてわざわざ店を出てから声をかけてくるんだ?
そんなことを考えたが、それ以上頭が回らなかった。
「だったら、なんれす」
ろれつも回っていない。
「知りてえか」
「なにお」
「空の、歩きかた」
男は酒焼けしたような赤い顔を近づけてきて、確かにそう言った。
「いいですねえ。歩きましょう!」
「そうか。じゃあついてきな」
ふらふらとしながら男は、まだ酔客の引かない通りを先導して歩き出した。
五十歳くらい、いやもう少し上だろうか。
変なおっさんだ。
さっきロカビリーな髪型のマスターが他の客に声をかけても、誰もそんな怪談話を知らなかったのに。
なんであのとき黙ってたんだ。あれ?そもそもあんなオッサン、店にいたかな。
そんなことを考えていると、おっさんが急に立ち止まり、また顔を近づけてきてこう言った。
「あそこにはな、道があるんだ。目に見えない道が。でも普通の人じゃあ、まずたどり着けないのさあ」
おや?
おっさんの言葉ではなく、なにか別の、違和感があった気がした。
正面から顔を見ると、頬は肉がタブついていて、はみ出した鼻毛と相まってだらしない印象だった。
しかしどこか愛嬌のある顔立ちだ。
そのどこに違和感があったのだろう。
まあ、いいや。
アルコールがいい感じに脳みそを痺れさせている。
「周りのビルより高い場所だ。そんなところに道なんてあるわけがない。そう思うだろ。
でもなあ、そうじゃあないんだ。あの道はな……」
「北の通りの、高層ビルからでしょう」
おっさんは驚いた顔をした。
「おおよぅ。わかってんじゃねえか兄ちゃん」
そうなのだ。
この東西の通りに面したビルは高くとも四,五階だ。
しかし離れた通りのビルにはもっと高いものがある。
その北の通りに面した高層ビルから伸びているのだ。その空の道は。
酔いにかき回された頭が、ようやくそんな単純な答えにたどり着いていた。
そしてもっと南の通りにも高いビルがある。
そこまで伸びているのか。あるいは、そのまま人の世界ではない、虚空へと伸びていく道なのか。
「霊道なんでしょう」
負けじと顔をおっさんの鼻先に突き出す。しかしおっさんは、にやりと笑うと「違うねえ」と言った。
「本当に道があるんだよ。いいからついてきな。
知ってるやつじゃなきゃ絶対に分からない、あそこへ行く道が、一本だけあるんだ」
そしてまた頼りない足取りで繁華街を進んでいく。
なんだこのおっさんは。意味がわからない。しかしなんだか楽しくなってきた。
「さあ、こっちだ」
おっさんは三叉路で南に折れようとした。
「ちょっとちょっと、北の通りでしょ。そっちは南」
たぶん目的地は北の大通りの、屋上でビアガーデンをやっているビルだ。方向が違う。
しかしおっさんは不敵な笑みを浮かべて人差し指を左右に振った。
「北に向かうのに、そのまま北へ向かうってぇ常識的な発想が、この道を見えなくしてんだよ」
そんなことを言いながらふらふらと南の筋に入り、
やがてその通りにあったビルとビルの隙間の細い路地へ身体をねじ込み始めた。
太り気味の身体にはいかにも窮屈そうだった。
だめだ。酔っ払いすぎだ、これは。
「いいから、ついてこい。
世界は折り重なってんだ。
同じ道に立っていても、どこからどうやってそこへたどり着いたかで、
まったく違う、別の道の先が開けるってこともあるんだ」
うおおおおおおおおお。
そんなことを勢い良くわめきながら、おっさんは雑居ビルの狭間へ消えていった。
なんだか心魅かれるものがあった僕も、酒の勢いを駆ってついていく。
それから僕とおっさんは、
廃工場の敷地の中を通ったり、
古いアパートの階段を上って、二階の通路を通ってから反対側の階段から降りたり、
居酒屋に入ったかと思うと、なにも注文せずにそのまま奥のトイレの窓から抜け出したりと、
無茶苦茶なルートを進みながら、少しずつまた北へ向かい始めた。
ますます楽しくなってきた。街のネオンがキラキラと輝いて、すべてが夢の中にいるようだった。
気がつくと、また最初の幸町の東西の通りに戻っていた。随分と遠回りしたものだ。
「どうやって知ったんですか、この空への道」
「ああん?」
先を歩くおっさんの背中に問い掛ける。
「おれも、教えてもらったのよ」
「誰から」
「知らねえよ。酔っ払った、別の誰かさぁ」
おっさんも別の酔っ払いから聞いたわけだ。その酔っ払いも別の酔っ払いから聞いたに違いない。空を歩く道を!
その連鎖の中に僕も取りこまれたってわけだ。光栄だなあ。
僕も空を歩くことができたら、今度は師匠にもその道を教えてやろう。
そんなことを考えてほくそ笑んでいると、おっさんは薄汚れた雑居ビルの階段をよっちらよっちらと上り始めた。
ほとんどテナントが入っていない、古い建物だった。
最上階である四階のフロアまで上がると、奥へ伸びる通路を汚らしいソファーやらなにかの廃材などが塞いでいた。
「おい、通れねえぞ」
おっさんがわめいて僕に顎をしゃくって見せるので、仕方なく力仕事を買って出て、障害物を取り除いた。
また気分よくおっさんは鼻歌をうたいながら通路を進む。
やけに長い通路だった。さっきの東西の通りから、一本奥の通りまでぶち抜いているビルなのかも知れない。
その鼻歌は何か、酒に関する歌だった。
どこかで聞いたことはあるが、世代の古い歌だったので、タイトルまでは思い出せなかった。
なんだっけ?
酒の、酒が、酒と。
そんなことを考えていると、ふいに、頭に電流が走ったような衝撃があった。
あ。
そうか。
違和感の正体が分かった。
急に立ち止まった僕に、おっさんは振り返ると「どうした、にいちゃん」と声をかけてくる。
そうか。あの時感じた違和感。おっさんが僕に顔を近づけて、『あそこには目に見えない道がある』と言ったときの。
あれは……
足が震え出した。そしてアルコールが頭から急に抜け始める。
「どうしたぁ。先に行っちまうぞ」
その暗い通路は左右を安っぽいモルタル壁に囲まれ、遠くの非常灯の緑色の明かりだけがうっすらと闇を照らしていた。
おっさんはじりじりとして、一歩進んで振り返り、二歩進んで振り返り、という動きしている。
僕はアルコールが抜けていくごとに体温も奪われていくのか、猛烈な寒気に襲われていた。
そうだ。
おっさんは、息がかかるほど顔を突き出したのに、酒の匂いがしなかった。
あの赤ら顔で、千鳥足で、バーから出てきたばかりなのに。そのバーに、そもそもあのおっさんはいなかった。
今日ハシゴした他の店にも。
客からあの話を訊くことも目的だったので、すべての店でどんな客がいるか観察していたはずなのだ。
なのに、おっさんは僕が空を歩く男の話を訊いて回っていたことを知っていた。
まるで目に見えない客として、あのいずれかのバーにいたかのように。
「どうした」
声が変わっていた。
おっさんは冷え切ったような声色で、「きなさい」と囁いた。
ガタガタ震えながら、首を左右に振る。
通路の暗闇の奥で、おっさんの顔だけが浮かんで見える。
沈黙があった。
そうか。
小さな声がすうっと空気に溶けていき、その顔がこちらを向いたまま暗闇の奥へと消えていった。
それからどれくらいの時間が経ったのか分からない。
金縛りにあったかのようにその場で動けなかった僕も、外から若者の叫び声が聞こえた瞬間に、ハッと我に返った。
酔っ払った仲間がゲロを吐いたという意味の、囃し立てるような声だった。
僕は気配の消えた通路の奥に目を凝らす。
そのとき、頬に触れるかすかな風に気がついた。その空気の流れは前方からきていた。
三メートルほど進むと、その先には通路の床がなかった。
一メートルほどの断絶があり、その先からまた通路が伸びていた。
ビルとビルの隙間に狭い路地があった。長く感じた通路は、一つのビルではなく二つのビルから出来ていた。
崖になっている通路の先端には、手すりのようなものの跡があったが、壊されて原型を留めていなかった。
向こう側の通路の先も同じような状態だった。
知らずに手探りのまま足を踏み出していれば、この下の路地へ落下していただろう。四階の高さから。
生唾を飲み込む。
最後に「きなさい」と言ったおっさんの顔は、あの断絶の向こう側にあった。
そうか。僕は導かれていたのだ。折り重なった、異なる世界へ。
ビルとビルの狭間へ転落する僕。
そして別の僕は、自分が死んだことにも気づかず、そのまま通路を通り抜け、
導かれるままに秘密の道を潜り、あの空への道へと至るのだ。
高層ビルの屋上から、足を踏み出し……
そこは壮観な世界だろう。
遥か足元にはネオンの群れ。大小の雑居ビルのさらに上を通り、酔客たちの歩く頭上を気分良く歩いて進む。
夜の闇の中に、目に見えない一筋の道がある。それは折り重なった別の世界の住民だけにたどることの出来る道なのだ。
はあ。
闇の中に冷たい息を吐いた。
僕はビルの階段を降り、通行人の減り始めた通りに立った。
もう夜の底にわだかまった熱気が消えていく時間。人々がそれぞれの家へ足を向け、ねぐらへと帰る時間だ。
遠くで二度三度と勢いをつけながらシャッターを閉めている音が聞こえる。
そして僕は振り仰いだ星の見えない夜空に、空を歩く男の影を見た。
「殺す気だったんですか」
師匠にそう問い掛けた。
そうとしか思えなかった。師匠はすべて知っていたはずなのだ。かつての死者が新しい死者を呼ぶ、空へ続く道の真相を。
いくらなんでも酷い。
そう憤って詰め寄ったが、そ知らぬ顔で「まあそう怒るな」と返された。
「まあ、ちゃんと見たんだから合格だよ。優良可でいうなら、良をあげよう」
なんだ偉そうにこの人は。ムカッとして思わず睨むと、逆に寒気のするような眼に射すくめられた。
「じゃあ、優はなんだっていうんですか」
僕がなんとか言い返すと、師匠は暗い、光を失ったような瞳をこちらに向けて、ぼそりと囁く。
「わたしは、空を歩いたよ」
そして両手を、両手を羽ばたくように広げて見せた。
うそでしょう。そんな言葉を口の中で転がす。
「臨死体験でもしたって言うんですか」
僕が訊くと、師匠は「どうかな」と言って笑った。
[完]
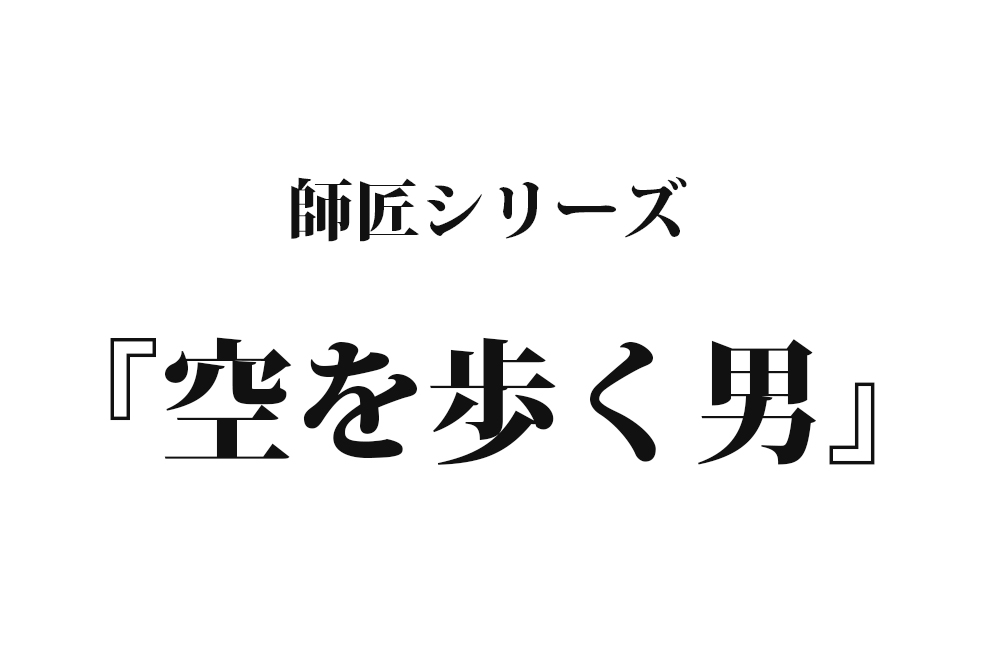
コメント