藍物語シリーズ【17】
『玉の緒』
上
微かに、女性の悲鳴が聞こえたような気がした。
俺は暗闇の中にいる。此処は、あの悲鳴は、俺の見ている夢なのか。
「止めて!どうしてこんなこと。」 もう一度、ハッキリ声が聞こえた。 これは、Sさんの?
何故こんな切羽詰まった声を。 その直後、いきなり視界が開けた。 これは。
目の前の床に血の海が拡がっている。その中に俯せに倒れている女性と小さな女の子。
女性は抱きかかえるようにして小さな女の子に覆い被さっていた。
視界がぐるりと動き、壁際に蹲る女性の姿が見えた。俯いて赤子を抱きかかえている。
目の前に腕が現れた。男の腕。刃物を握っている、これは、あの短剣だ。一体何故?
男の腕が視界の右側に消え、女性の姿が大きくなった。女性に、近づいているのか、俺は。
女性がこちらを向いた。蒼白い顔。 まさか、Sさん。 では、この赤子は藍?。
右手に微かな痺れを感じた瞬間。
視界の右側から男の腕がSさんに短剣を振り下ろすのと、
Sさんが藍を庇うように左手をかざすのが見えた。
右手に嫌な感覚が残り、足元に真っ赤な血飛沫が散る。
Sさんの左手は力なく垂れ、それでも必死に藍を庇おうと動いていた。
信じられないというような表情。頬を伝う涙。
「あなた、どうして...」
思わず飛び起きた。 図書室? あれは、夢か。
全身に冷や汗をかいていた。 右手を確かめる、大丈夫だ。 血の跡などない。
窓の外、空はうっすらと明るい。 昨晩、俺は資料を調べるために夜更かしをしていた。
そのまま居眠りをしたのだろう。でも一体何故あんな夢を。
感覚は鈍かったが、あれはおれの腕だった。 そして、川の神様に授けられた短剣を。
思い出しても身震いする。俺がSさんと藍に斬りつけるなんて。
あの状況が、全く理解出来ない、待て、血の海に倒れていた女性と小さな女の子は。
姫と、翠だ。あれ以前に、俺は2人にも手をかけたのか?
図書室を飛び出して廊下を走った。階段を駆け上る。
...大丈夫。Sさんの寝室、ドアの向こうから4人の気配を感じる。
ぐっすりと寝ているようだ。ノブにかけた右手をそっと離した。
ただの悪夢。わざわざSさんや姫を起こす必要はない。俺は自分の部屋で服を着替えた。
今日は土曜日、姫の送りも仕事の予定もない。少し眠れば気分も良くなるだろう。
しかしベッドに入った後も、右手に残る嫌な感触と、あの時のSさんの表情が忘れられない。
結局、それから朝食の時間が来るまで俺は一睡も出来なかった。
「また欠伸、4回目よ。体調悪いの?」
「いいえ、大丈夫です。ちょっと寝不足なだけで。続きをお願いします。」
俺の『勉強』の時間、Sさんが様々な系統の術を基本から教えてくれる。
その間、翠と藍の面倒を見てくれるのは姫。当然俺の『勉強』は土日か休日。
「直接の身体接触を通じて掛ける術は、単純だけど効果が大きい。
簡単な行動の強制くらいなら相手の意識がなくても可能だし、
相手には術を掛けられた記憶さえ残らない。
霊質の関係で、ごく希にこの系統の術が効かない人がいるけれど、
それだけ気を付けていれば、費用対効果が抜群に良い術なの。」
そうだ、あれは藍が生まれた時。
O川先生と看護師さん、3人の視覚と記憶を操作するために、Sさんはこの術を使った。
しかし、看護師の◎内さんには術が完全には効かず、それを補完したのが姫の術。
おそらく事前にSさんは◎内さんの霊質に気が付いていたのだろう。
だから姫に出産の立ち会いを頼んだ。そして、あの時『頼りにしてる』と。
あらかじめ相談が出来ていたとしても、本当に見事な連携プレーだった。
「ちょっと、R君。今度は何?」 目の前でSさんの掌が揺れている、まずい。
「あ、いや、この術。僕にも効くのかなと思って。」
「僕にも、って。私、前に掛けたことあるでしょ、あなたに。忘れたの?」
「え~っと、言い方が悪かったです。僕が僕に掛けても効くのかな、ということで。」
Sさんのキョトンとした表情。 「あなたがあなた自身に? この術を?」 「はい。」
「効く、でしょうね。でも、術を掛けたこと自体忘れてしまうんだから、意味が無いでしょ?」
「そうですね。でも、この術の練習には丁度良いです。他の人には影響が無いですから。」
目を閉じて、言葉を練る。 俺の無意識に語りかける、出来るだけ簡潔な指示。
『もし俺が家族を傷つけようとしたら、すぐに自分自身を始末する』
今朝方見た夢、あんなことが絶対に起きてはならない。そのために、この術が使える。
練り上げた言葉に『力』を込め、血液に乗せて左の薬指に送り込む。そんなイメージ。
目を開けて左手の薬指を舐めた。あとはこの指を額に。
「待って! 何するの。」 Sさんが両手で俺の手を止めた。 とても冷たい感触。
Sさんは両手で俺の左手を掴んだまま、何事か小声で呟いた
やがて、俺の薬指の先端に、小さな紫色の光が現れた。まるで、紫色の火花。
それは、一度強く輝いた後、ゆっくりと降下し、テーブルの上で小さく跳ねて輝き続ける。
もう一つ、また一つ。次々と小さな光がテーブルに舞い降りてゆく。
呪力を光の粒子に還元する、極めて高度な術。『○◆の雪』。
光が現れなくなると、Sさんは両手を離した。
「馬鹿!」 平手、俺の左頬が派手な音を立てる。痛。
「自分自身を始末するなんて、術を、そんな風に。」
「御免なさい。でも、有り得ない指示なら害はないかな、と。」
「有り得ないって...始末ってことは自殺、なのよ?万が一。」
「その前です。例えば僕がSさんを傷つけようとするなんて、絶対に有り得ません。
僕はSさんが大好きだし、それに。」
「それに?」 Sさんの表情は少し緩んだが、眼差しは鋭いままだ。
「もし僕がおかしくなって、翠や藍を傷つけようとしたら、
Sさんは僕を止めてくれますよね?その、例え僕を殺してでも。」
Sさんはテーブルを回り込んで俺の右隣に座った。
「R君、どうしたの?あなた、今日はおかしいわよ。何故そんな事言うの?」
「夢を見たんです。」 「夢?」 「はい、僕が短剣、川の神様から授かった短剣で...」
俺が話している間、Sさんはじっと俺の眼を見つめていた。
「あんな夢を見た自分が許せなくて。」 本当に、許せない。
「夢、なのよ。そんなに思い詰めることないわ。」 「でも。」
Sさんは俺の膝の上に座り、真正面から俺の唇にキスをした。熱く、長いキス。
「逆夢かもしれないでしょ?」 「逆夢、ですか。」
「そう、もしかしたら家族が増えるかも知れない。私とLが同じ時期に妊娠するとか。」
「そりゃ、絶対無いとは言えませんが」 Sさんは人差し指で俺の唇を押さえた。
「それにね。私、もし殺されるなら、あなたに殺して欲しい。
他の誰かに殺されるなんて絶対に嫌。」 Sさんはもう一度俺にキスをした。
言われてみればその通りだ。俺だって殺されるならSさんに殺して欲しい。
「御免なさい。変な事言って。でも、僕はSさんが、みんなが大好きだから。」
「もう良い。そんなの分かってる。だからこの話はお終い、ね。
それより、痛くない? ホントに御免なさい、事情も聞かずに叩いたりして。」
Sさんはそっと俺の頬を撫でた。眼にうっすらと涙が浮かんでいる。胸が痛い。
「僕が悪かったんです。それに、こんな美人にお仕置きされて、ちょっとドキドキしました。」
「もう、心配してるのに。」 Sさんの笑顔。俺の心もすっかり軽くなっていた。
俺とSさんがリビングに戻ると、藍を抱いて翠と遊んでいた姫が顔を上げた。
「あれ?何だか2人、良い雰囲気ですよ。『お勉強』の時間の筈なのに。妬けちゃうな~。」
決して後ろめたいことはないが、やはりドキッとする。相変わらず鋭い人だ。
「R君が変な夢見たって落ち込んでたから慰めてあげたのよ。
夢の中で私やLに意地悪したんですって。」
「意地悪?Rさんが、私とSさんに?そんなの有り得ない、確かに変な夢ですね。」
「おとうさん、だめ。おかあさんとおねえちゃんにいじわるしたら、だめだよ。」
「いや、だからホントのことじゃなくて、夢の中の話だよ。」
「ゆめのなかでも、いじわるしたらだめ~。」
「そうだね。お父さんが悪かった。もうしないから。」 「うん。」
満足そうな翠を抱き上げて頬ずりをした。 翠の言う通りだ。二度とあんな夢は見たくない。
その時、玄関の電話が鳴った。
電話を終えたSさんの表情は硬く、緊張していた。
これは仕事の依頼ではない。間違いなく何か、悪い知らせ。
昼食を終え、翠と藍が昼寝をしている間に、Sさんは俺と姫をダイニングに招集した。
姫が黙って紅茶を淹れてくれる。冷たく張り詰めた空気に、白い湯気が溶けていく。
紅茶を一口飲んでから、Sさんは話し始めた。
「術者が一人、業に呑まれた。」
俺と姫は顔を見合わせた。姫の顔も緊張している。
しかし、正直なところ、事態の重大さが俺には想像出来ない。
「術者の出自が特殊だから、『上』も事後処理に追われてるみたい。」
業に呑まれた術者は処理、つまり殺すしかないと聞いていた。
当然、処理にあたる術者は相手よりも...腹の底がヒヤリと冷たくなる。
「あの、もしかしてSさんが、その術者を?」
「ううん、もう術者の処理は済んでる。派遣されたのは『炎』、憶えてるでしょ?」
もちろん覚えている。というより、あの男を忘れる事など出来ない。
時代の流れに抗い、力を持つ子供を人為的に産み出そうとした人々。その計画の『最高傑作』。
俺が裁許を受けた日。聖域の参道で俺とSさんの前に現れた分身は、
その男の並外れた力量を如実に物語っていた。
「あの男が派遣されて、処理が済んだなら一件落着、ではないんですか?」
「処理された術者は炎の妹なの。母親は違うけど。」
「『紫(ゆかり)』さん、なんですか?本当に?」 姫が息を呑んだ。
「紫が受けた依頼。その打ち合わせ場所で、依頼人の遺体が見つかったの。
紫が自分の部屋に戻っているのは間違い無いけど、連絡が取れない。
『上』の調査では、依頼人の魂はおそらく『不幸の輪廻』に飲み込まれた。だから、ね。」
Sさんが言葉を濁すのは滅多に無い、しかしそれも当然だろう。
あの男は、腹違いとはいえ妹を、自分の手で殺したということなのだから。
しかも異母妹ということは。そうだ、さっきSさんは言った。その術者の出自が『特殊』だと。
「もしかして、その人もあの計画の?」
「そう、あの計画の結果生み出された術者の一人、彼女もかなりの力を持ってた。」
「しかし幾ら何でも...妹の処理に兄を派遣するなんて、『上』は酷過ぎる気がしますが。」
「炎が志願したの。いや、あの家系の意志で炎に志願させたというべきかしらね。
『上』が黙認していたとは言え、あの計画への疑念を持つ人は今でも多い。
この件を切っ掛けにして、計画の結果生み出された術者は危険だという流れになるのは、
あの家系としても避けたいでしょうから。それで。」
「危険なのはその人だけで、他の7人は安全だと」
「R、さん。」
小さな声。俺を見つめて首を振る姫の両目から、大粒の涙が溢れた。
「紫はLより2つ年上で、何度か一緒に舞を奉納したことがあるの。
とても素直で、良い娘だった。数少ない、Lの友達。 なのに何故?今でも信じられない。」
「Lさん、御免なさい。事情を知らなかったので酷い言い方を。」
「いいえ、事実は事実ですから...私。」
姫は席を立ち、リビングを出て行ってしまった。一体、俺はどうすれば?
「R君、これから暫く夜はLと一緒に居てやって。あの子、かなり辛いと思うから。」
「でも、さっき僕があんな言い方を。」
「今度の事はあなたのせいじゃないでしょ。あなたからその話題に触れなければ良いの。
今、Lを支えられるのはあなただけ。頼んだわよ。」
その夜、姫は俺の腕の中で、何度か涙を流した。
その度、姫を抱きしめたり、背中をさするくらいしか俺には出来なかったが、
それでも姫は少しずつ落ち着いているようだった。
翌日は日曜日、まだ少し元気の無い姫をSさんに託して川の神様のお社に参内した。
最初の頃は必ずSさんか姫が付き添ってくれたが、この頃は一人で参内することも多い。
2人ともすっかり川の神様を信用して(ちょっと失礼だが)安心しているのだろう。
最後に掃除を終え、参道の脇に停めた車に乗り込む。
廃村を抜けてしばらく走ると、廃村へ通じる道と山道の交差点。大きくて丈夫な門扉がある。
門扉を開けて車を出し、再び門扉を閉めて鍵を掛ける。いつも通りの手順だ。
ふと、蝉の声を聞いたような気がした。 真冬に蝉?耳鳴りか。
車に乗ろうと振り返った瞬間、車を隔てた向こう側に男が立っていた。
黒いスーツ、俺より背が高い。これは...あの時の男、『炎』。
「炎さん、ですね?」
「俺の名を。Sから聞いていたか。」
「つい最近も、聞いたばかりです。でも、わざわざ此処まで分身を...要件は何ですか?」
「お前と話がしたい。2人きりで。」 「でも、此処では。寒いし、すぐに日が暮れます。」
「もちろん此処ではない。場所はこれから指示する。」
「僕はまだ行くと決めた訳ではありませんが。」
「お前は必ず来る。『上』の指示が出る前だったから準備も上手く行った。」
「『上』の指示って、どういうことですか?」
「今朝、『上』が臨時の会議を開いて決めた。
今後、俺を含む7人の術者には特別な監視が付く。7人、どういう意味か分かるな?」
あの計画で、生み出された8人の術者達。処理された1人を除いた7人、ということだ。
「では、準備というのは?」
「万が一にもお前に断られると困る。だから人質を用意した。」
ぞく、と、背筋が冷たくなった。まさか、いや、Sさんがいるのだからそれはない。
「人質って、誰なんですか?」
「来てもらう場所は、ある『範士』の屋敷だ。そう言えば分かるだろう。」
その瞬間、セーラー服を着た少女の姿が目に浮かんだ。
自分はカミンチュだと言い、ノロになると言った沖縄出身の少女。名は瑞紀。
『高校はもうすぐ就職休みなので、少しずつ沖縄に帰る準備をしています。』
美しい字で近況を綴った葉書がお屋敷に届いたのは、つい先日の事だった。
「Sと『上』には俺から連絡しておく。お前は直ぐに出発しろ。
電話や寄り道をしてると人質の無事は保証できない。では、待っている。」
次の瞬間、男の姿は消えた。
まるで最初から、其処には誰もいなかったかのように。
あの日、『はい。相談します。』と言ったあの子の笑顔が目に浮かぶ。
あの子の優れた資質や素直な性格は、早くから一族の中で話題になっていた。
「早速縁談が有ったわよ。当然あの子は断ったけど。」去年の暮れ、Sさんからそう聞いていた。
あの子の噂は当然あの男の耳にも入っただろう。あの子と俺たちの関係についても。
だからあの男は『お前は必ず来る』と言ったのだ。
Sさんや姫、そして俺があの子を見殺しには出来ないと分かっていたから。
しかし何故、俺なのか?それが全く分からない。
あの男はおそらくSさんに恋愛感情を持っている。
例えばあの子を人質にSさんを呼びつけ、そして。もちろんSさんが言いなりになる訳はない。
下衆な考えとは言え、それならまだ納得出来る。何故、Sさんでなく俺なのか?
たとえ俺を殺したところで、あの男自身が『上』に処理されれば、その想いは叶わない。
しかし、考えている暇はない。薄暗くなりかけた山道、指示された場所に向けて車を走らせた。
中
範士の屋敷に着いたのは6時過ぎ。玄関の灯りが点いているのが見える。
門の前に立つとひとりでに門扉が開いた。門をくぐると門扉が閉じる。あの男の仕業だ。
玄関まで歩き、ドアの前に立つ。 深呼吸。本当に俺はこの屋敷に入るべきだろうか。
相手の意図が分からない。既にあの男が業に呑まれている可能性もある。そんな状態で。
だが、さっきの口調には悪意を感じなかった。それにSさんと『上』に連絡するということは、
この件に対して『上』に対策を取らせるということだ。もちろんSさんも必ず此処に来る。
そっと上着に触れた。布越しの硬い感触、あの短剣。お社に参内する時は常に帯剣している。
最悪の場合、Sさんたちが到着するまで時間を稼ぐ。この短剣があれば何とかなる筈だ。
その時、ドアが開いた。少女が立っている。
「いらっしゃいませ。お待ちしておりました。どうぞ、中へ。」
所作は洗練され、服装や髪型も見違えるようだが、間違いない。これは、あの少女。
今、この少女を抱き上げて車に走れば。
いや、駄目だ。あの門扉を忘れたのか。当然結界が張られているだろう。
それに、少女以外にも屋敷の中には人がいる筈だ。その人達はどうする。
自問自答しながら少女の後を追う。案内されたのは広いリビングルーム。
テーブルの上には料理の皿とワインの瓶、それにワイングラスが2つ。
しかし肝腎の、あの男の姿がない。
「来て、くれたんですね。」 少女が体の向きを変え、正面から俺の眼を見つめた。
「嬉しい。来てくれないんじゃないかと、私、心配で。それに、とても怖かった。」
少女が歩み寄り、俺を抱きしめた。左肩に顔を埋めている。
温かい吐息を感じるが、逆に俺の心は冷えていった。
「趣味の悪い術ですね。少し、見損ないました。」
ふっ、と、少女の体から力が抜けた。しっかり抱き止める。
いつの間にか奥のソファにあの男が座っていた。テーブルからワインの瓶を取る。
「完全に気配を消したと思ったが、会話だけで術だと見抜いたか。
Sに師事しているとはいえ、大したものだ。それでこそお前を呼んだ甲斐がある。」
俺は少女の体をソファに横たえ、脱いだ上着を着せ掛けた。
少女の隣りに座る。あの男の斜め向かいの席。
あの男は2つのグラスにワインを注ぎ、1つを俺の前に置いた。
「良く来てくれた。まずは一杯。さっき此処のセラーで見つけた、85年のラフィット。
かなり良いワインだ。前に飲んだのは、3年前だったか。
それと、待ってる間に料理も準備した。その子はなかなか料理が上手い。助かったよ。」
あの男はワインを一気に半分程飲んだ。
「パーティーをしに来た訳ではありません。僕を呼んだ理由を教えて下さい。
それに、当然瑞紀さんは返してくれるんでしょうね?」
「その子も他の者たちも寝てるだけだ。お前が来てくれたから、もう用はない。
あとはお前と話をすれば済む。」 言い終わってワインを飲み干し、もう一度ワインを注ぐ。
緊張して喉がカラカラだ。俺も一口だけワインを飲んだ。当然、味などまるで分からない。
深呼吸、腹に力を込める。何とか少女を無事に。
「何故こんな事をしたんです。まず人質を解放して、話はそれからでも良いじゃないですか。
そうすれば『上』だって、荒っぽいことはしないでしょう。」
あの男の左頬がピクリと動いた。微かな笑みが浮かぶ。
「これが、言霊、か。俺がどうしても会得できなかった術を大した修行もせずに。
本当に、いちいち気に障る。だが、それでなければお前を呼ぶ意味がない。
お前の言葉は確かに俺に届いている。俺の言葉は紫に届かなかったが。」
違和感。 何故、今、妹の話を? もしかしてこれは何か別の...慎重に言葉を選ぶ。
「『言の葉』の適性。それが、他の人でなく、僕を呼んだ理由ですか?」
「それもある。そしてもう1つ、その剣。お前の適性と、その神器が必要だ。」
「あなたがその気になれば、僕はこの剣に護ってもらうのが精一杯。
これを使って彼女を助け出すことなど出来ませんよ。」
男はまた一口、ワインを飲んだ。穏やかな笑みを浮かべている。
「あたりまえだ。たとえ俺の意識がなくても、お前はその剣で俺に触れることさえ出来ない。」
『俺の意識がなくても』...やはり何かある。恐らくこれは謎かけだ。
しかしこの男は心に幾重にも鍵を掛けている。伝達の手段はただ会話のみ。
それも、直接には口に出せない『何か』を俺の適性で感じ取れという、この男からのメッセージ。
「さっき、妹さんにあなたの言葉が届かなかったと、そう言いましたね?」
「ああ、俺が行った時、紫はもう俺の事も分からなくなっていた。
会うなり俺を本気で殺そうとしたよ。以前はあんなに慕ってくれていたのに。」
男の表情は変わらない。しかし、その言葉から深い悲しみが伝わってくる。
「Sが俺との縁談を断ったのを知った時、紫は『自分を妻に』と言った。
計画のためでなく、俺を男として愛してくれていたと知って驚いたが、やはり嬉しかった。」
現代の倫理や法律には反するが、一族の中で兄妹・姉弟の結婚それ自体は禁忌ではない。
実際そういう組み合わせの夫婦を俺も知っている。しかし今、何故、俺にその話を?
「だが、俺は憶えていない。気が付いたら紫は床に倒れていて、既に死んでいた。
どうやって俺は紫を殺したのか?あんなに慕ってくレた妹を殺したのに、憶エていナイんだ。」
時折男の声の調子が外れる。それはまるで、錆びたドアがきしむ音のように聞こえた。
そして、錆びたドアの向こうの微かな、それでいてとてつもなくおぞましい気配。
それは、いつか呪物のトランプを手にした時の感覚に似ていた。
ドアの向こうで目覚めた『何か』が、僅かに開いたドアの隙間から俺の様子を探っている。
まずい。これは、俺の手に負える事態ではない。しかし、もう、止められない。
それに、この男は俺の適性に期待して俺を呼んだのだ。
もし他の、例えばSさんを呼べば、更に悪い事態になると分かっていたから。
だとすれば、この男が俺に伝えたい事、それは。
そう、念のためにもう一言、あと1つヒントがあれば確信出来る。
「妹さんの術で記憶が飛んだのではありませんか?
『不幸の輪廻』から流れ込む力で妹さんの術が力を増していたとしたら。」
「もしそうなラ、死んでいタのは俺ノ方ダ。そレに紫は、紫ハ業に呑マレてなド、イなカッタ。」
間違いない。この男が俺に伝えたかった事、それを感知出来た。
「先程の失言を許して下さい。やはりあなたは偉大な術者だ。そしておそらくは妹さんも。
必ず、僕が皆に伝えます。あなたと妹さんは業に呑まれたのではなかった。
それは、今あなたの中に潜んでいる『何か』に関わっていたのだと。
そしてもし、この怖ろしい災厄を祓うことが出来たなら、その功績と栄光は、
命を賭けて『何か』の存在を知らせた、あなた方2人の魂と共にある、と。」
「アりがトう。こレデ、アトハ、オマえシだイ。マカセ、た...」
突然、リビングルームに冷気が満ちた。そして、心が挫けそうになる程の、圧倒的な気配。
笑い声や言葉こそ聞こえないが、『何か』は確かに俺と炎さんを嘲笑っていた。
『気付いたとしても、人間には為す術がない。せいぜい足掻いてみせろ。』 そんな風に。
『何か』は俺の反応を楽しむようにゆっくりと、その姿を現そうとしている。
炎さんの体がぐったりと背もたれに沈み、のけぞった顔が天井を向いた。
体が大きく震え、口から赤黒い液体が溢れる。赤ワイン、そして血の臭い。
始まった。どうすれば良い?
炎さんの中に容易く入り込む程の力、俺の術など効く筈が無い。恐らくSさんや姫の術も。
だが今ならこの剣で。いや、『意識が無くても』と、炎さんは言った。あれは警告だ。
不用意に斬りかかれば『何か』は躊躇無く俺を殺すだろう。剣の刃が届く前に。
それに、どうにか時間を稼ごうにも、あの少女が狙われたら俺に為す術は無い。
考えろ。今、姿を現そうとしている『何か』、その目的は一体何だ。
もしやこの剣、しかしこの剣を俺以外が持てば...そうか。
あの夢は逆夢ではなく、予知夢だったのだ。俺がSさんに斬りつける場面が目に浮かぶ。
しかし、この予知夢を完成させてはならない。絶対に、あんな場面を現実にはしない。
それなら、俺に出来ること、するべきことはただ1つ。短剣をゆっくりと抜く。
『何か』の気配が大きく揺らぎ、リビングの中に冷たい風が吹いた。
そう何者も、この短剣を目の前にして、ちっぽけな俺の意図や術を感知するのは無理だろう。
昼間の空、太陽の光のもとでは、星の光を見ることができないように。
抜き身の短剣をゆっくりとテーブルに置きながら、言葉を練る。簡潔に、そう、単純に。
炎さんの口と鼻から、白く濃い煙のようなものが立ち上った。エクトプラズム、もう時間がない。
言葉に『力』を込め、血液に乗せて左手に送り込む。
目を閉じ、薬指で、しっかりと額に触れた。
重い音がした。我に返る。男の体が向かいのソファから床にずり落ちていた。
あれは...あれは、業に呑まれた敗者、だ。まだ、生きている。息の根を止めなければ。
俺はゆっくりと立ち上がった。全身の感覚が妙にボンヤリとして体がふらつく。
テーブルの上の短剣。そう、この短剣であの男を。
そうすれば俺は一族でも有数の術者を倒した勝者。皆が俺を讃えるだろう。
それにこの剣なら、あの女どもを殺せる。S、そしてL。ついでに子供も始末すれば良い。
これまで何度と無く、『不幸の輪廻』の邪魔をしてきた厄介者たち。
そして俺が望めば当主との面会も叶う。そうすればこの一族も...そう、契約は成就する
その後は仲間たちの、思わず笑みが浮かぶ。 右手で短剣を取る、早く、あの男を。
? 足が動かない。 そして、左手がひとりでに動いて短剣の刃を握った。
ゆらりと右手が離れて短剣を持ち変える。さらに左手を添え、両手が逆手で短剣を握り締めた。
何故だ、何故俺の両手がひとりでに?
次の瞬間、両手は短剣を俺自身の腹に突き刺した。激痛、足から力が抜け、床に膝を着く。
凄まじい悲鳴。薄れていく意識の中、男の、呟くような声を聞いた気がした。
夢を見ていた。 俺の体は暗闇の中をゆっくりと沈んでいく。
腹の真ん中あたりに鈍い痛みがある。いや、かなり強い痛みだ。 腹に、傷?
その時、微かに俺の名を呼ぶ声がした。女性の声。
ああ、俺は知っている。 これは、誰の声だったろう。
『いた。見つけたぞ。』 やはり、若い女性の声だ。
続いて背中に何か温かいものが触れ、俺の体が沈むのは止まった。
『そうか、間に合ったか。』 こちらは男性の声。落ち着いた、渋い声だ。
『○瀬の主、祭主殿を見つけたぞ。全く、■◆が絡んでいるのだから
さっさと助ければ良いものを。お主が硬いことを言うから我らの仲人殿が死にかけた。
もし、手遅れになったらどうするつもりだったのだ?』
『人が、人同士が自分たちの力で難局を乗り切ろうとしている時に、安易に助ければ
魂の堕落を招く。我が祭主であれば尚更、この試練は大いなる成長の機会となる。』
『それにしても仲人殿は無茶をしたな。神器で自らの腹を貫くなど、前代未聞だ。』
『神器を持ってはいても、祭主殿が■◆を滅ぼすには、あれしか策はない。
あの術を使わねば、その意図は■◆に読まれたろう。
そうでなくとも、家族への未練や痛みへの怖れで躊躇し、機を逸したかも知れぬ。
力と術への敬意が無意識のうちに正解を探り当てる。あの港で私を助けた時もそうだった。』
ボンヤリとした頭で俺は不思議な会話を聞いていた。これは川の神様と、そして。
『お主、怪我をしたのか。右手。そうか、あ奴の顎門、2人の魂を救い出した時に。
しかしどうして2人の魂を? 妹の体は既に無く、兄の体も長くは保つまいに。』
『気高く戦った魂、あ奴には絶対渡したくなかった。
それに、どのみち『血』が必要なのだから、この傷、丁度良い。』
『急いだ方が良さそうだ。祭主殿の力が弱くなっている。』
『うむ、では我が祭主を此処へ。』
数秒の後、俺の腹を温かいものが濡らした。
次第に腹の痛みが強くなる。思わず唸り声を。
痛みのあまり目が覚めた。見慣れない天井、そして。
「おねえちゃん、おとうさんがめをあけたよ。」 駆け寄る気配。
「Rさん...」 姫が俺の顔を覗き込んだ。 体を起こそうとした途端、腹の激痛。
「動かないで下さい。お腹の傷が酷いんです。でも、本当に、良かった。」
俺の肩をそっと押さえた姫の左手、指先が小さく震えていた。
翠の前だからだろう、懸命に感情を抑えているのが分かる。
「おとうさん、やっとめがさめたね。みんな、しんぱい、したんだから。」
ようやく声を絞り出す。「ありがとう。御免よ。」
「Sさんは藍ちゃんとお屋敷にいます。夕方には来てくれますけど、
Rさんの意識が戻ったことはすぐに知らせておきますね。」
「今日は、何曜日なんですか?」 「あれから3日目、水曜日です。」
記憶が混濁している。俺が範士の屋敷に行ったのは日曜日だったか。
だとすれば、俺は丸々2日は意識が無かった事になる。
それにしても、あの出来事。
夢を見ていたような気もするが、腹の傷とその痛みはそれが現実だと教えてくれる。
人質になった少女は無事だったのか。あの男、炎さんは...。
炎さんの中に潜んでいた『何か』は、一体どうなったのだろう。
炎さんが命を賭してその存在を俺に伝え、
それに対処する一縷の望みを俺の適性と短剣に託した、あのおぞましい存在。
意識がまだ朦朧としているのは、痛み止めの麻酔のせいだと姫は教えてくれた。
腹をほとんど貫通する程の深い傷で、俺の苦しみ方が酷かったらしい。
なら、この痛みはまだマシなのか。そんな事を考えている内に、俺は再び眠りに落ちた。
また、痛みで目が覚めた。もう窓の外は薄暗い、既に夕方。
姫が用意してくれた飲み物を飲んでいると、暫くして姫が立ち上がり翠の手を取った。
「翠ちゃん、そろそろ時間だから一緒にお母さんと藍ちゃん迎えに行こうね。」 「うん。」
姫と翠が病室を出て行って10分程すると廊下から足音が聞こえ、
磨りガラスの向こうに人影が見えた。控えめなノックの音。間違いない、Sさんだ。
「どうぞ、起きてますから。」 ノブが回り、ゆっくりとドアが開く。
Sさんは無言で歩み寄り、ベッドの脇に膝をついた。
俺が差し出した右手を両手で握り、頬ずりをしながら、声を殺してSさんは泣いた。
何と声を掛けて良いのか分からない。Sさんの嗚咽、俺も必死で涙を堪える。
Sさんが一人で病室に来たのは姫の配慮。Sさんの泣き声が藍と翠を不安にさせないように。
どれくらいそうしていたのか。ようやくSさんは顔を上げた。涙でぐしょぐしょの笑顔。
「泣いたりして御免なさい。私、きっと、大丈夫だと思っていたのよ。なのに涙が、変なの。」
「心配掛けて済みません。言い訳したいんですが、まだ頭がボンヤリしてて、どうにも。」
「言い訳なんかしなくて良い。あなたは精一杯頑張ったんだから。」
Sさんは俺の唇にキスをした。長く、熱いキス。
「顔が涙でぐしょぐしょ。御免ね。」 ハンカチで俺の顔をそっと拭い、そして自分の頬を拭う。
それから姫に電話をかけた。家族が全員揃う。何故かとても、懐かしい気分だ。
俺が薄いお粥のような夕食を食べ終えると、Sさんは翠と藍を連れてお屋敷へ戻った。
俺が入院した日から、姫がずっと泊まり込みで付き添いをしてくれていたらしい。
「大学、休んだんですね。この時期に、大丈夫なんですか?」
「ほとんどの科目はテストが終わってるし、平気です。」
「済みません。もう少し元気になるまで、宜しくお願いします。」
「お願いされなくても、ずっと付き添いますよ。だって私、Rさんのお嫁さんですから。」
姫の言葉に込められた深い想い、Sさんの涙に秘められていた激しい感情。
そしてさっきこの手に抱いた翠と藍の温もり。
ボンヤリしていた意識も次第に澄み、俺は自分が死地をくぐり抜けたことを実感していた。
翌日、昼食を食べ終えて暫くするとノックの音がした。
Sさんだ。翠の手を引いている。あれ、藍は?
そう言いかけた時、Sさんが押さえたドアをもう一人の女性がくぐった。藍を抱いている。
人質になったあの少女。良かった、無事だったのか。本当に、良かった。
「また助けて頂いて、ありがとう御座いました。」 少女は深く頭を下げた。
「いや、俺を呼び出すために人質にされたんだから、謝るのは俺の方だよ。」
「それを言ったら、瑞紀ちゃんをあの家に紹介した私にも責任が有る訳だから。
もう、その話は無し。それよりどう?瑞紀ちゃん、見違えたでしょ?」
「はい、服がすごく似合ってて。初めは別人かと思いました。」
服のせいか、あの日範士の屋敷で会った時より、少女は大人っぽく見えた。
「服を褒めるなんて、全く気が利かないわね。でも、確かによく似合ってる。
この服、私のお下がりよ。サイズ、ほとんどそのままでOKなの。」
「あの、お下がりって?」 そう言えば、何故少女は藍を?
「ふふ、あの晩から瑞紀ちゃんにはお屋敷に来てもらってるの。
Lがあなたの付き添いしてるから、家事とか手伝って貰って大助かりだわ。」
Sさんが努めて楽しそうに振る舞っているのが分かる。
それなら、炎さんは。 姫かSさんが話してくれるまで、その質問はしない。そう、決めた。
記憶が未だ曖昧な所も、今無理して思い出す必要はない。とにかく俺は生きている。
今はもう暫く、この賑やかな病室の中で、暖かな幸せに包まれていたい。
少女が俺の横に寝かせてくれた藍の頭をそっと撫でた。
下
その日は朝から、俺の病室の中だけで無く、病院全体の空気がピリピリと緊張していた。
彼方此方から伝わってくる気配。そのどれもが間違いなく、かなりの力を秘めている。
おそらく病院の出入り口などの要所に、式や術者が配置されているのだろう。
今日、当主様と桃花の方様がこの病院に、俺の病室に御出になるからだ。
『見舞い』と言えば聞こえは良いが、『上』のメンバーも一緒。つまりこれは調査。
紫さんの件に続いて炎さんと俺。あの禍々しい存在と接触して生き延びたのが
俺一人だとすれば、俺の状態を『上』が調査するのは当然の事だろう。
昨夜、姫は今日に備えて幾つか重要な事を教えてくれた。
「分かってると思いますけど、炎さんは助かりませんでした。
Sさんと他の術者たちが範士の屋敷に到着した時、既に全てが終わっていたそうです。
瑞紀ちゃんや他の人質は全員無事だったけれど、
リビングの床には大怪我をして意識の無いRさん、それと炎さんの遺体。
そして、屋敷に残っていた痕跡から、怖ろしい事が起きたと分かったんです。」
姫はSさんから預かったという一枚の写真を俺に手渡した。
リビングの絨毯が黒く、大きく焦げている。ある動物を思わせるその形。
写真を見ているだけなのに、全身の毛が逆立つような寒気を感じる。
「これは、一体何ですか?何かが焼けて、絨毯が焦げた跡みたいですが。」
「Rさんの傷から吹き出した血が、多分あの短剣の力で焼き尽くされた跡です。
いいえ、Rさんの中に入り込んでいたモノが、焼き尽くされた跡といった方が良いですね。」
炎さんの中に入り込んでいたモノは俺の中に、そしてあの短剣の力で焼き尽くされたのか。
「ただ、それがあまりにも強力な存在なので、『上』は疑っています。
既にRさんの魂が『それ』に穢されているとしたら、後々災いの種になるから。それに。」
姫は一度言葉を切り、温かいお茶を一口飲んだ。
「炎さんが死に、Rさんの記憶もかなり欠落していて、あの晩何が起きたのか分かりません。
実際、Rさんのお腹の傷も、未だ原因が特定出来ていないんです。」
俺はあの夢を思い出した。川の神様と、それからあの声は。
「この傷は僕が自分で刺したものだと、あの、夢の中でそういう風に。」
「Rさんの手にも、炎さんの手にも、血痕はなかったそうです。
それに、あの短剣は鞘に収まった状態でテーブルの上に置かれていて、
短剣の鞘にも柄にも血痕は残っていなかったと聞きました。」
俺で無いなら、しかし、あの剣を俺以外の人間が持てば...訳が分からない。
「Rさんの状態、事の経緯を知るための調査ということですね。
魂が穢れているかどうかを確実に判別出来るのは当主様と桃花の方様だけですから、
調査に伴って御二人もこの部屋へ御出になります。
御二人がこの部屋へ。あのおぞましい存在との接触で、俺の魂は穢れてしまったのか。
ふと、あの怖ろしい夢の場面が目に浮かんだ。俺はあの短剣でSさんを。
...そういえば、俺は炎さんを殺そうとしたのではなかったか、あの短剣で。
曖昧な記憶を辿る。そうだ、確かに俺は。ではその後何を?
駄目だ。どうしてもそこから先を辿れない。まるで術で記憶が、もしやこれも。
「あちこち記憶が無いのは、僕の魂が穢れているからですか?」
「Rさんは大丈夫。私は信じています。それに、私とSさんがRさんを守ります。
どんな手段を使っても。そう、たとえ『上』に背く事になるとしても。」
つまり、俺の魂が穢れているとしたら『上』は...。
『背くことになるとしても』
その言葉の重み、そして姫の胸中を思うと、もうそれ以上の言葉が出なかった。
「顔を上げなさい。」 病室に涼しい声が響いた。桃花の方様の声。
顔を上げると、ベッドの脇の椅子に当主様が座っていた。その右斜め後方に立つ桃花の方様。
さらに後方、病室の壁際に直立不動で立つ2人の男性。
1人は知っている顔、遍さんだ。もう1人は知らない顔だが、この2人が『上』の代表。
俺の枕元で姫が跪いている。Sさんはこの階のロビーで翠と藍の相手をしているはずだ。
建前とはいえ、『上』の前で親子が揃えば要らぬ疑いを招きかねない。
ただ、『上』の二人には見えないだろうが、俺のベッドの下には管さんがいる。
Sさんは管さん経由でこの部屋で起こることをリアルタイムで知る事が出来る訳だ。
「本日はわざわざ御出頂きありがとう御座います。」
「大変だったな、R。もう少し回復してからとも思ったが、これも公務だ、許せ。」
もし、俺の魂が穢れているなら、当然、回復する前に対応すべきだ。
「もし私の魂が穢れているなら、全てを当主様にお任せ致します。」
「そうなって欲しくはないが。」 桃花の方様が跪き、細長いものを当主様に手渡した。
桃花の方様の身長よりもはるかに長い、白い布の袋。当主様が袋の口を開く。
姫から聞いていた通りだ。神器、『梓の弓』。 もの凄い存在感が病室を満たす。
そしてもう一つの神器。弓の半分程の長さの筒、その中に納められている筈の『破魔の矢』。
筒の中から伝わってくる気配、こちらの存在感も尋常ではない。
当主様が立ち上がり、桃花の方様の肩を借りて弓の弦を張った。
続いて桃花の方様が筒の中から矢を取り出し、それを当主様が受け取る。
左手で弓と矢を交差させるように持ち、右手を弦にかけた。
鏃は未だ鞘で覆われている。しかし必要があれば恐らく左手の一振りで
「参る。」
ぴいいぃん。不思議な音が病室の空気を震わせ、俺の中に染み込んでくる。
神器の弓を半分程に引き絞り、弦を放す時に発する音。『寄絃』の儀式。
穢れた魂の持ち主は、この音を聞いて意識を保てない。姫からそう聞いていた。
2度、そして3度。弓と弦の発する音は、響きの調子を変えながら病室の空気を震わせた。
姫が息を潜めて俺を見ているのを感じる。大丈夫だ。何ともない、俺は。
「宜しい。皆、見届けたな。Rの魂、穢れてはいない。
憑依されていた時間が短くて幸いだった。」
当主様が小さく息を吐く。壁際の遍さんともう1人の男もホッとした表情を浮かべた。
続いて矢を桃花の方様に返し、弦を外して弓を白い袋に戻した。
しかし、未だ事情聴取は終わっていない。当主様はもう一度椅子に腰掛けた。
「さて、R。当主として、私は知らねばならない。あの晩何が起きたのか。
特に会話だ。お前と炎の会話、あの晩お前達が何を話したのか。それが、知りたい。」
「全てお話ししたいのですが、記憶が途切れ途切れで、ご期待に添えるかどうか。」
「それは承知している。無理をすれば体にも障るだろう。桃花の方、あとは頼む。」
「はい。」 当主様の足元に控えていた桃花の方様が立ち上がり、俺のすぐ前に立った。
「R、右手をこちらへ。」
そっと右手を伸ばす。緊張で手が震える。桃花の方様は両手で俺の右手を包んだ。温かい。
「あの晩、お前が炎にかけた最初の言葉を憶えていますか?」
「はい、『少し見損ないました』と。その前の炎さんの術が、その、気に入らなかったので。」
桃花の方様が目を閉じた。ゆっくりと、深く息を吸う。誰も喋らない。病室の中に満ちる静寂。
『気配は完全に消したと思ったが、会話だけで術だと見抜いたか。
Sに師事しているとはいえ、大したものだ。それでこそお前を呼んだ甲斐がある。』
男の声が静寂を破った。間違いない。これは、炎さんの声だ。
桃花の方様の口から炎さんの声、あの晩の言葉がそのままに再生されている。
これは、術?確かSさんが同じような、そう、『声色』。おそらくあれと良く似た系統の術。
『パーティーをしに来た訳ではありません。僕を呼んだ理由を教えて下さい。
それに、瑞紀さんは返してくれるんでしょうね?』
少し声の質が違うが、この話し方は間違いなく俺だ。
桃花の方様の術が、俺たちの会話をありのままになぞっていく。
『何故こんな事をしたんです。まず人質を解放して、話はそれからでも良いじゃないですか。
そうすれば上だって、荒っぽいことはしないでしょう。』
『これが、言霊、か。俺がどうしても会得できなかった術を大した修行もせずに。
本当に、いちいち気に障る。だが、それでなければ呼ぶ意味がない。
お前の言葉は確かに俺に届いている。俺の言葉は紫に届かなかったが。』
当主様は腕を組み、眼を閉じたまま、俺たちの会話に聞き入っている。
遍さんともう1人の男も、姫も、そして俺自身も、息を詰めて耳を澄ませていた。
『さっき、妹さんにあなたの言葉が届かなかったと、そう言いましたね。』
『ああ、俺が行った時、紫はもう俺の事も分からなくなっていた。
会うなり俺を本気で殺そうとしたよ。以前はあんなに慕ってくれていたのに。』
再生される会話を聞くうちに記憶の断片が繋ぎ合わされていく。
新たに思い出した断片も加わり、朧気ではあるが、あの晩の記憶が甦りつつあった。
『だが、俺は憶えていない。気が付いたら紫は床に倒れていて、既に死んでいた。
俺はどうやって紫を殺したのか?あんなに慕ってくレた妹を殺したのに、憶エていナイんだ。』
『妹さんの術で記憶が飛んだのではありませんか?
不幸の輪廻から流れ込む力で妹さんの術が強力になっていたとしたら。』
『もしそうなラ、死んでいタのは俺ノ方ダ。そレに紫は、紫ハ業に呑マレてなド、イなカッタ。』
桃花の方様は一旦言葉を切って大きく深呼吸をした。
『先程の失言を許して下さい。やはりあなたは偉大な術者だ。そしておそらくは妹さんも。
必ず、僕が皆に伝えます。あなたと妹さんは業に呑まれたのではなかった。
それは、今あなたの中に潜んでいる『何か』に関わっていたのだと。
そしてもし、この怖ろしい災厄を祓うことが出来たなら、その功績と栄光は、
命を賭けて『何か』の存在を知らせたあなた達2人の魂と共にある、と。』
『アりがトう。コれデ、アトハ、オマえシだイ。まカセ、タ...』
そうだ、確かにこの言葉を聞いた事は憶えている。しかし、この後が全く。
『この剣を持ったら、自分の腹を突く。』
姫が息を呑んだ。
これは...俺の声。 そうか、思い出した。俺の術。
口に出してはいないが、心の中で必死に練った言葉。あの術を俺自身に掛けるために。
俺の術など効く相手ではない。剣で斬りかかれば、刃の届く前に俺は殺される。
だが、俺の体に潜み、一族に害をなすのが相手の目的なら、あの術が使えるのではないか。
術を掛けたこと自体を忘れるのだから、俺の意図を相手に感付かれることもない。そう思った。
細かな操作は難しいだろうが、狙いを外す訳にはいかない。自分で見える大きな的、腹。
相手が俺の中に入り込み、誰かに害をなそうとしてあの剣を持てば、多分この術が発動する。
自信など全くない、しかし、それしか策がなかった。
今回は何とか術が発動し、相手は剣の力で焼き尽くされた。 本当に、信じ難い程の幸運。
桃花の方様の唇が小さく動いている。この後にもまだ言葉が?
『紫、見たか、やったぞ。これで...いや、Sは、上は何をしてる。遅い、このままでは...』
桃花の方様が目を開けた。俺の手をベッドに戻し、労るようにさすった。
静かな病室の中に当主様の声が響く。
「R、誠にお前は言祝ぐ者。お前の言葉通り、炎も紫も偉大な術者だ。
紫は炎に、炎はRに■◆の存在を伝え、そしてRは自らの体を代として■◆を誘い込み、
神器の力で焼き滅ぼした。3人の献身に対し、一族の祭主として心から礼を言う。
残念ながら炎と紫は犠牲となったが、お陰で一族を危うくする大難は祓われた。」
その重さを良く理解出来ないまま、俺は当主様の言葉を聞いていた。
「炎と紫を先達の偉大な術者の列に序し、その魂を祀って功績を讃えよう。社へ戻る。」
当主様が立ち上がる。遍さんが慌てたように病室のドアを開けた。
「当然特別な監視の件は撤回させる。そして紫が受けた依頼が持ち込まれた経緯と
それに関与した者達の徹底的な調査。恐らく、『不幸の輪廻』の活動が活発になっている事と
関連が有る筈だ。今後のために、全てを明らかにしておかねばならない。」
当主様はドアの前で立ち止まり、ゆっくりと振り返った。悪戯っぽい笑顔。
「R、傷が癒えたらまた会おう。今度はゆっくり、話がしたい。」
言い終わると当主様は踵を返してドアをくぐった。足音が軽やかに遠ざかっていく。
遍さんともう1人の男も慌てて当主様の後を追った。
病室の中には俺と姫、そして桃花の方様。昨夜姫から聞いた段取りの通りだ。
「L、では、あれを。使わずに済んで、本当に良かった。」
姫は一礼して立ち上がり、壁の棚の中から白い布の包みを取りだした。
桃花の方様の前で跪き、白い包みを両手で捧げる。
「お陰様で心安らかにこの日を迎えることが出来ました。心より感謝申し上げます。」
桃花の方様が頷いてそれを受け取り、そっと着物の袂に納めた。
包みの中身は黒檀の小箱。その小箱の中に純白の宝玉、号は『深雪』。姫からそう聞いた。
黒檀の小箱には封印をしてあるらしく、白い布包みを見ただけでは
その中身が一族に伝わる宝玉であるとはとても思えない。
もしもの時のためにSさんがお願いをして、その宝玉を当主様から借り受けたと聞いていた。
俺の魂が穢れていたら、その宝玉を使うということだ。しかし、どんな風に使うのかは知らない。
『Rさんがそれを知る必要はありません』と姫は言った。
『もし、これを使う必要があるなら、その時Rさんの意識が無いということですから。』と。
もちろん包みが解かれることはなく、黒檀の小箱すら見ることは出来なかった。
魂の操作を伴う術は『禁呪』。Sさんや姫の命を削る術は絶対に使って欲しくない。
そう思ったが、昨夜はどうしても適当な言葉が見つからなかった。
逆に、姫は俺の心を見通したように微笑んだ。
「翠ちゃんと藍ちゃんには『父親』が必要です。忘れないで下さいね。」
「L、Sとともに、Rの世話にはよくよく心を尽くしなさい。
Rの傷が癒え、体が本復するのには未だ時間がかかります。」
涼やかな、心地良い声で我に返った。桃花の方様の声。姫は深く一礼し、病室のドアを開けた。
神器の弓と矢、そして白の宝玉を携えた桃花の方様が、ゆっくりとドアをくぐる。
「良かった、これで。」
ドアを閉じて振り返った姫の笑顔に、ようやくいつもの温もりが戻っていた。
数日後、自宅療養の許可が出て、俺と姫はお屋敷に戻った。
その晩、翠と藍を寝かしつけた後、俺たちはリビングでお茶を飲んだ。
いつも通り、穏やかなお屋敷の夜。それがとても懐かしく、そして愛おしい。
いつもと違うのは俺の傷を心配してハイボールがお茶に変わったこと。
そして此所には3人ではなく4人、あの少女も一緒にいること。
「本当はお酒で乾杯したいけど、それはもう少しお預けね。」
「瑞紀ちゃんの卒業式まであと3週間。その夜は乾杯出来るかも知れませんよ。」
Sさんも姫も、すっかり落ち着きを取り戻していた。もう、不意に涙を零したりはしない。
確かに、とても大きな災難だった。俺は深い傷を負い、Sさんと姫は酷く心を痛めた。
しかし、それを乗り越えつつある今、3人の魂を結ぶ絆は以前にも増して強くなっている。
その絆を頼りに、きっと俺は『日常』に戻ることが出来る。そう思った。
「そう言えば、もうすぐ川の神様のお社に参内する日ですね。」
少なくとも今回は、姫かSさんに代理を頼まなければならないと、そう思っていた。
すると、Sさんが少女を見つめて微笑んだ。はにかんだような少女の笑顔。
「R君、それがね、暫くあなたは立ち入り禁止みたいよ。川の神様のお社。
瑞紀ちゃん、一昨日のこと、R君とLに話してあげて。」
「はい。ええと、一昨日の3時少し前でした。翠ちゃんと藍ちゃんは昼寝をしていて、
私とSさんはおやつの準備をしていたんです。そしたら急に翠ちゃんが立ち上がって。」
Sさんは堪えきれない様子でくすくすと笑った。
「眼も開けずに『傷が癒えるまで参内は禁止する。Rに、そう、伝えよ。』って言ったんです。」
「じゃあ、川の神様が。」
「私もそう思ったから翠の前に跪いて、『では私がRの代理で参内致します。』と、
そう申し上げたのよ。そしたら、ね。」 Sさんはもう一度少女に微笑みかけた。
「『Rは近々此処へ戻るから、そなたにはRを頼む。
大丈夫だ。社の心配は要らぬ、手は足りている。』って、そう言った後、
またパタンと横になって寝ちゃったんです。本当に、びっくりしました。」
「寝惚けた顔だし、声は翠のままなのに、殊更に芝居がかった調子でそんなこと仰るのよ。
有り難いけど、もう、私、可笑しくて可笑しくて。」
でも、何で翠に?それは俺の夢でも充分なのに。
「私たちを笑わせて、元気づけようとして下さったのでしょうね。」
話を聞いていた姫が真面目な顔でそう言うと、Sさんは小さく頷いた。
三月一日、少女の卒業式。朝から曇り空。
今にも泣き出しそうな天気だが、少女は輝くような笑顔で玄関を出た。
化粧はせず素顔のまま、長く伸びた髪を首の後ろで軽く束ねている。もちろん、セーラー服。
スカートの丈はやや長め、膝にかかる位。初めて会ったあの日とはまるで別人。
正直これは、ストライクど真ん中...まずい、クラクラする。
「もう、邪道だなんて言えないわね。というより、王道一直線かな?」
Sさんはイタズラっぽく笑い、ガレージに向かって歩き出した。
成る程、Sさんの。道理であまりにも俺の嗜好に、いや待て、そんな事考えてる場合じゃない。
気を取り直して、Sさんの運転する車に乗り込む少女を見送る。おめかしした翠も続く。
翠は少女に良く懐いていて、一緒に卒業式をお祝いするといって聞かなかったのだ。
去っていく車を見送りながら、俺は姫が高校を卒業した日の事を思い出していた。
あの日も朝は曇り空。俺の車に乗り込んだ姫の眩しい笑顔。そして
「Rさん。体調は、もう随分良いんですよね?」
姫の卒業式、その追憶は、他ならぬ姫の言葉で中断された。
「あ、はい、今月中には川の神様のお社に参内できると思います。」
実際、傷の具合はかなり良い。表面の傷口は完全に塞がっている。
それにその日の夕食後、少女の卒業を祝う乾杯では、お酒が解禁になる予定だった。
何かの拍子にくしゃみや咳をするとかなり痛むが、これはまあ仕方ない。
「明日、私とSさんは朝早くから出掛けます。翠ちゃんと藍ちゃんも一緒に。」
ということは。
「あの、じゃあ明日、お屋敷には。」
「はい、Rさんと瑞紀ちゃんが二人きり。私たちは当主様と桃花の方様にお目通りする、
瑞紀ちゃんにはそう話してありますけど、方便です。分かりますよね?」
「あの子に何か良い思い出を、そういうことですか?」
何故か小声になってしまう自分が少し情けない。
「何か特別な事をする必要はないです。夕方までRさんの世話を瑞紀ちゃんに任せるだけ。
一日中二人きりで過ごす、きっとそれだけで十分です。瑞紀ちゃんはRさんのお嫁さんに」
「ちょっと待って下さい。あ痛たたたた。」
「何を慌ててるんですか。瑞紀ちゃんがRさんのこと好きなのは皆が知ってるのに。」
「だ・か・ら、僕はあの子のこと」 「何とも思ってないって言いたいんですね?」
「そうです。」 姫は小さく溜息をついた。
「今度のことがあっても、考えは変わらないんですか?」 「ええと、どういうことですか?」
「長生き出来ないかも知れないのは、術者でも術者でなくても、同じだってことです。」
不意に、胸の奥が痛んだ。何故、急にこんな。
「瑞紀ちゃんが本当にノロになって、Rさんのお嫁さんになるかどうかなんて、
そんな未来のこと、誰にも分かりません。でも、大事なのは『今』瑞紀ちゃんがRさんを
好きだということ。そのためにノロになる決心をして、実際に歩き始めたということ。
すごく遠くて辛い道ですが、少しでも目的地に近づいて欲しい、そう、思いませんか?」
「もちろん思いますよ。でも、それと彼女をお嫁さんにすることは。」
「もう、瑞紀ちゃんのことになると、不思議な位鈍いんですから。
例えば沖縄に帰った後、瑞紀ちゃんが事故や病気で亡くなったらどうなると思いますか?
瑞紀ちゃんはもちろん、Rさんにも悔いが残りますよ。『こんなことならあの時』って。
だから明日1日、瑞紀ちゃんをお嫁さんだと思って接してあげて下さい。恋人でも良いです。
とにかく、できるだけ悔いの残らないように。お願いしますね。」
少女に悔いが残ると言うのは分かる。しかし、俺にも悔いが残るというのは?
しかし、藍を抱いた姫はさっさと自分の部屋に戻ってしまい、
昼食の前にはSさんと少女も帰ってきたので、それ以上この話は出来なかった。
翌朝、朝食も食べずに4人は出掛けていった。
少女と2人の朝食。『悔いの残らないように』と姫は言ったが、やはり気まずい。
俺の事を好いてくれる少女に、気のあるような素振りをするのは正直気が引ける。
少女を嫌いな訳ではない。家事を手伝っている姿や翠と遊んでくれる姿を見てきて、
むしろ今は素直な良い娘だと思っている。でも、それはSさんや姫に対する感情とは違う。
それなのに、お嫁さんや恋人だと思って接するなんて...心の隅に蟠る罪悪感。
朝食を済ませ、ぐだぐだ考えながらリビングで本を読んでいると、
窓から明るい日差しが差し込んできた。何だか久し振りに見る太陽の光。
その時、ふと俺の心も晴れたような気がした。
俺の適性が『言の葉』なら、まずは話をしてみるべきだろう。
後の対応をどうするか、会話の中で答えが見つかるかも知れない。
「瑞紀ちゃん。」 思い切って、キッチンで昼食の準備をする少女に声をかける。
「はい、何ですか?」 少女はタオルで手を拭きながら駆け寄ってくる。嬉しそうな笑顔。
「空が、急に明るくなってね。だから、一緒に庭の梅を見に行こうと思って。どう?」
「行きます、一緒に。火を消して、すぐに戻りますから。」
ガレージの裏側には梅の木がある。白い花の木と紅い花の木が一本ずつ。
盛りは過ぎていたが、まだかなりの花が咲き残っていて、良い香りが漂っていた。
俺たちは暫く黙ったまま、並んで梅の花を眺めた。赤と白のコントラスト、飛び交う小鳥たち。
「奇麗だね。」 「はい、とっても奇麗です。」
「この時期だと沖縄は桜も終わってるよね。梅の花はいつ頃咲くの?」
「お正月が終わった頃に咲いているのを見たことがあります。
でも、沖縄では梅の花をあまり見かけません。もともと数が少ないんでしょうね。
それと、私が見た梅は全部白い花でした。紅い花の梅は見たことが無いです。
その代わり、沖縄の桜はこの梅みたいにピンク色ですよ。私、本土の桜を初めて見た時
あんまり違うので驚きました。ソメイヨシノっていう品種なんですね。」
「そう、沖縄の桜は山桜に近い緋寒桜だって聞いたから、全然違うだろうね。」
それから、また暫く黙ったまま花を見つめた。
「Rさん、体が冷えると傷に悪いと思います。もう、戻りましょう。」
「瑞紀ちゃん、御免。本当は車でドライブとか出来たら良いんだけど。」
「いいえ、私、今日はとても楽しくて嬉しいです。まるでRさんのお嫁さんに...
御免なさい、私、勝手にお嫁さんとか。」
「まあ、それは構わないけど。ノロになる理由を話したらお祖母さんに怒られないかな?」
「私も、怒られるかもって思ってました。でも、笑われました。」 「え、笑われたって?」
「去年の夏休みに、一週間お休みを頂いて沖縄に帰ったんです。その時、祖母に話しました。
そしたら『瑞紀はあの人に似たんだね。』って。その後で色々な事を話してくれたんです。」
「『あの人』って誰のこと?」 その人はこの少女とどう関わっているのだろう。
話の続きはリビングのソファで、少女が淹れてくれた温かいお茶を飲みながら。
「その人は、祖母の夫です。祖母はノロだから籍は入れなかったそうですけど。」
「じゃあ、瑞紀ちゃんのお祖父さんでしょ?『祖母の夫』って、何だか他人行儀だね。」
「早くに亡くなったから私はその人の顔も知らないんです。
でも、祖母の話を聞いて。その人のことが好きになりました。
その人は祖母に『自分は必ず村で一番の漁師になるから、そしたら自分と結婚して下さい。
絶対にあなたに恥ずかしい思いはさせません。』って言ったそうです。
『貧乏だから勉強では身を立てられない。でも必ず村一番の漁師になって、
あなたがノロを辞めてからも良い暮らしが出来るようにしますから。』って。」
勉強と漁師、そのうち漁師を選んだと言うことは。
「もしかして、その人は年下、だったのかな。」
「はい、3つ年下だって言ってました。父親から習ったり、自分で必死に工夫したり、
19歳の時には、もう村で一番の漁師と言われるようになったそうです。」
「それでお祖母さんに結婚を申し込んだ?」
「はい、村中大騒ぎだったって言っていました。それで5人の子供に恵まれて。
その人は早くに亡くなったし、結局籍は入れられなかったけれど、とても幸せだったって。」
「後継者がいたら、ノロを辞めて籍を入れられたかも知れないね。」
「はい。でも、その人が亡くなった後、自分がノロを続けていて良かったと、
後継者が現れなくても自分は死ぬまでノロを続けようと、そう思ったと言ってました。」
「お祖母さんはどうしてそんな風に?」
少女は俺の眼を真っ直ぐに見つめて微笑んだ。
「その人は病気になったあと、ずっとあの集落の海岸を恋しがっていたそうです。
入院してからも『元気になって集落に戻り、せめてもう一度海岸を歩きたい。』と。」
「もしかして、お祖母さんは自分の手で?」
「はい、その人が生まれて育ったあの集落と、その人が大好きだったあの海岸を
死ぬまで守ると決めた、そう言って笑っていました。」
「じゃあ、瑞紀ちゃんはお祖母さんにも似たんだね。」
少女はにっこり笑って頷いた。
「ノロになるための修行を始める前に、祖母とそんな話が出来て本当に良かったです。
好きな人のために、好きな人の暮らす土地を護るために、私はノロになりたい。
それは決して間違っていないと、自信が持てましたから。」
何と爽やかで、そして鮮やかな覚悟だろう。その言葉を聞いているだけで胸が震える。
俺は、間違っていたのかも知れない。
最初の頃の悪い印象をいつまでも引きずって、今の少女の姿を見ようともしなかった。
少女は真摯な態度で範士に師事し、新たな覚悟で『今』を生きてきたというのに。
これが、姫とSさんが俺に伝えたかった事。少女の気持ちを受け入れるにしろ拒むにしろ、
少女の『今の姿』を見てからにするべきだ。そうでなければ悔いが残る。
後で気が付いたとしても、取り返しがつくかどうかは分からないのだから。
「すごいな。瑞紀ちゃんは本当に変わったね。初めて会った頃とはまるで別人。
今の瑞紀ちゃんはキラキラ光って見える。何て言うか、すごく素敵だよ。」
「ありがとう御座います。とても嬉しいです。
でも、私はSさんやLさんのように奇麗じゃないし強くもないですから、未だ全然。
あ、もうこんな時間。すぐにお昼ご飯準備しますね。」
キッチンに向かう少女の後ろ姿に、何故か桃花の方様の後ろ姿が重なった。
Sさんよりもむしろ姫に似た細い体に、あのお方は一体どれ程の力を秘めているのだろう。
以前Sさんから聞いた事がある。『桃花の方様は一族最強の術者であることが珍しくない。』
鬼門を封じ、当主様を御護りする最高位の術者。
確かに、当主様に匹敵する力を持っていなければ務まる筈がない。
御二人は大恋愛の末に結ばれたと、遍さんは話してくれた。
もちろん大変な資質を持っておられただろう。しかし、その資質も磨かなければ光らない。
それどころか、相応の修行をしなければ、強すぎる力はむしろ災厄のもとになる。
桃花の方様になると決めた時、そのために厳しい修行をなさった時、
やはり当主様への愛情が一番の力になった筈だ。
好きな人への想い、こうなりたいという夢が力になる、それは決して悪いことではない。
ならば今、少女の気持ちを拒むと決めて、その夢を断つのは正しいことだろうか。
以前、Sさんが『お勉強』の時間に教えてくれたことがある。修行を続ける上での注意点。
例え叶わずとも、強い夢は力になる。しかし、夢を見ている自分に酔ってはならない。
ふと、姫との初めてのデート、あの海岸へドライブした時の情景が浮かんだ。
『Rさんに好きと言ってもらえるなら、私、騙されていても構いません。』
この一年余りで少女は精神的に大きく成長し、それでも真剣な気持ちで俺を好いてくれている。
なら俺も、心に芽生えた彼女への『好き』を認めれば良い。
『妹』か、『恋人』か、それは全く別の話だ。
『やっと、分かってくれたんですね。瑞紀ちゃんのことになると、ホントに鈍いんですから。』
耳許で囁く、姫の声が聞こえた気がした。
昼食の後、一緒に食器を洗ったり、テレビを見ながら他愛のない話をしたり。
時間は穏やかに過ぎて、4人が帰ってくる時間が近づいていた。
「もうすぐ、皆が帰ってくる時間ですね。」
「外で帰りを待とう。もう一度、梅の花を見ながら。」
「それは良いですけど、暖かい服を着て下さいね。」 「分かった。」
俺たちは並んで梅の花を眺めた。傾いた日差しの中で、梅の花は輝くように美しかった。
「さっきの話だけど。」 「はい?」
「『私はSさんやLさんのように奇麗じゃないし強くもない。』そう言ったよね?」 「はい。」
「それは違うと思う。瑞紀ちゃんはとても奇麗だし、強い。
そしてこれからもっと奇麗になるし、もっと強くなれる。」
「でも、Rさんは...」 「瑞紀ちゃんが、君が、好きだよ。」 「え?」
「今日、俺は君が好きになった。でも、好きになったばっかりで、
それがどういう『好き』なのかまだ分からない。
友達として好き、う~ん、これは違う。妹として好き、近いかも。でも、正直分からない。
だから、そうだな。瑞紀ちゃんが沖縄に戻っても、時々は一緒に暮らそう。
俺が沖縄に旅行しても良いし、夏休みに瑞紀ちゃんが此処に来てくれても良い。
これから過ごす時間の中で、お互いの『好き』を確かめて、それをゆっくり育てていきたいから。」
「ありがとう、御座います。とっても、嬉しいです。私。」
「25歳じゃなくても良い。ノロになれたら、直ぐに相談においで。
もちろん良い返事が出来るとは限らないよ。どんな返事になるのか、
そもそも僕がその時まで生きていて返事が出来るのか、それは誰にも分からないから。」
「はい、私、必ずノロになります。ノロになって...」
何の躊躇いもなく、不思議な程スムーズに俺の体と両腕が動いた。
少女の正面にまわり、その体をそっと抱きしめる。微かに、薔薇の花の香りがした。
少女の髪も上着も、ひんやりと冷たい。しかし、抱きしめていると、胸の奥が温かくなる。
あの晩、炎さんの術で操られたこの娘が俺を抱き締めた時の感覚とは対極の、温もり。
「修行、頑張って。いつも、応援してる。」 「はい。」
少女の涙が乾ききらないうちに、聞き慣れたエンジン音が聞こえた。近づいて来る。
俺は少女の手を取って玄関先に戻った。白いマセラティがガレージに滑り込む。
ガレージの中からドアの閉まる音と翠の声が聞こえた。
どのみち姫とSさんは俺と少女の『成り行き』を知りたがるだろう。
だが、それを口に出して説明するのは照れくさい。それならいっそ。
ガレージの入り口に4人の姿が見えた。
左腕を少女の肩にまわし、しっかりと抱き寄せる。それから4人に大きく右手を振った。
「Rさん、みんなが。」 「疚しいことじゃないし、これなら後で説明する必要がないからね。」
姫とSさんの驚いたような笑顔。 翠が駆け寄ってくる。
「おとうさん、おとうさんもみずきちゃんとなかよくなったの?」
「そう、瑞紀ちゃんは素敵な女の子だから、お父さんも瑞紀ちゃんが好き。
翠も瑞紀ちゃんのこと、好きでしょ?」
「うん、みどりも、みずきちゃんだいすき。だ~いすき。」
結
少女が沖縄に帰ってから暫くの間、お屋敷の中は少し寂しくなった。
しかし日が経つにつれ、少女を恋しがってぐずりがちだった翠も少しずつ元気になり、
俺の傷も順調に回復して、お屋敷は元の賑やかさを取り戻しつつあった。
そして、庭の桜が咲き始めた頃。久し振りに川の神様のお社へ参内すると決めた。
立ち入り禁止期間に参内を休んだのは3回。皆で相談して参内するのを決めたのは一昨日。
その後も翠が神託を受けなかったのだから、既に立ち入り禁止は解けているのだろう。
俺が軽の4駆を運転し、Sさんと二人で出発した。車の運転は本当に久し振りだ。
Sさんは助手席の窓を全開にして、山道の景色を眺めている。 少し寂しそうな横顔。
「炎さんと紫さんのことを考えてる。そうですよね?」
Sさんは俺の顔を見て少し笑った。「正解。じゃ、どんな風に考えているかは?」
「もう少し炎さんに、優しくすれば良かった。あの縁談も、もう少しちゃんと聞けば良かった。
こんな感じ、で、どうですか?」
Sさんは眼を丸くして俺を見た。「驚いた。術も使ってないのに、どうして?」
「炎さんはあの晩、僕に紫さんの事を話してくれました。
どんな内容だったか、桃花の方様の術をSさんも聞いていたんですよね?」
Sさんは小さく頷いた。
「『Sが俺との縁談を断ったのを知った時、紫は『自分を妻に』と言った。』
紫さんはずっと炎さんを愛していたのに、何故縁談を持ちかける前でなく、
Sさんが縁談を断ったのを知った後で『自分を妻に』と言ったんでしょうね?
もし、Sさんが縁談を承知したら、自分の想いは永遠に報われないと分かっているのに。」
Sさんは黙ったまま、俺の横顔をじっと見つめている。
「答えは簡単です。Sさんに縁談を断られて、炎さんはとても落ち込んだんですよ。
他の人には弱みを見せなかったでしょうけれど、
紫さんはとても炎さんの様子を見ていられなかった。
だから、秘めてきた自分の思いを思わず口にしたんです。
Sさんもそこに気付いて、炎さんが自分に恋愛感情を持っていたことを知った。
それなら、もう少し炎さんに。あの縁談も。そう思うのは当然だろうな、と。」
そう、炎さんの気持ちを知ったのならそれは当然。もちろん俺自身を卑下しているのではない。
あの縁談には術者を生み出す計画だけでなく、炎さんのSさんに対する恋慕の情が
含まれていた。今回の事でそれがSさんに伝わった。むしろそれが嬉しいと思う。
自分たちの出自が特殊であること、それ故に大き過ぎる期待を背負って生きること。
炎さんたちは常にそれらと向き合って来たのだろう。
せめてその気持ちだけは、Sさんに知って欲しいと思う気持ちになっていた。
Sさんは右手をそっと俺の左手に重ねた。
「半分正解。私、もう少し炎に優しくすれば良かったって、縁談もちゃんと聞けば良かったって、
確かにそう思った。でも、そう思っただけ。今と違う自分を望んではいない。
炎と紫の魂が『不幸の輪廻』に取り込まれたとしたらとても悲しいし、
何か自分に出来ることはないかと考えるわ。きっとあなたも、Lも同じ気持ちだと思う。
ただ、炎にもう少し優しくしていても、ちゃんと縁談を聞いていても、何も変わらない。
私の答えは1つ。何があっても、私には、あなただけ。」
「有り難う御座います。Sさんはそう言ってくれると思ったから、嫉妬はしませんでしたよ。」
「ふふ、やっと、自分に自信を持ってくれたのね、嬉しい。
でも、答えは未だ半分残ってる。残りの答えを聞かせて頂戴。」
Sさんも俺と同じ疑問を持った筈だ。Sさんなら疑問の答えが分かるかも知れない。
「どうやって紫さんは炎さんに『あれ』の存在を伝えたのか。それを考えていた。どうですか?」
「お見事、正解。」 「Sさんならその方法に心当たりが?」
「いいえ。紫の適性もあわせて考えて見ても、思い当たる術は無い。
炎と紫の絆が鍵だと思うけれど、その場の経緯が分からないとそれ以上は。」
「紫さんの件についての調査は進んでいるんでしょうか。」
「まだ調査は継続中だけど、おそらく『あれ』は依頼人の中に潜んでいたのね。
一族に害をなすには、力のある術者の中に潜み、機会を待つのが早道だから。
紫の中に入り込んだ『あれ』は依頼人を殺し、その魂を『不幸の輪廻』に送り込んだ。
当然、紫が業に呑まれたと誰もが思うし、紫より力のある術者が派遣される。」
「じゃあ、最初からそれが。」
「そう、『あれ』は宿主の力を自分の力の触媒として使う。
だから、どれだけの力が使えるかは宿主の力の強さに依存する。
炎クラスの術者が宿主なら、どんな術者にも力で劣ることはない。
それに、休眠を続けていれば、何時かは当主様に接触する機会も巡ってくる。
炎の中で休眠し、チャンスになれば目覚めるようにトリガーをセットしてあった。完璧な計画。
でも、どうしてか、紫は『あれ』の存在に気付いてそれを炎に伝えようとした。
そして、炎も気付いた。自分の中に『何か』が入り込んでいる。
しかも、自分が全く気付かないうちに。それなら入り込んだのは間違いなく『あれ』。
そうでなければ、そんなに容易く入り込まれる筈がない。
ただ、気付いたとしても、どう対処すべきか。炎は焦ったでしょうね。」
「たとえば炎さんがその存在を『上』に伝えようとすれば、『あれ』が目覚める訳ですね?」
「そう、その名やその存在を口にすれば、『あれ』が目覚めて自分は完全に乗っ取られる。
炎の力を触媒にすれば、『あれ』は一族を壊滅させるほどの力を使えたでしょうね。
だから、炎は必死で考えた。その答えがあなた。人質を取ってでもあなたを呼ぶ、と。」
心に幾重にも鍵を掛けたまま、それでも会話を通して『あれ』の存在を感知出来る適性。
さらに『あれ』を滅ぼすことの出来る神器の持ち主。 だから、俺。
そう思ったから、炎さんは俺の適性とあの剣に全てを賭けた。
もちろん俺がそれに気付いた瞬間、自分の命は無いという覚悟の上で。
しかしその存在に俺が気付いた時、『あれ』は俺と炎さんを嘲笑っていた。
「どうして『あれ』は、さっさと僕を殺さなかったんでしょうか?」
「まずは様子見。炎とあなた、どっちの中に潜んでいるのが有利なのか。
次に油断、『たかが人間に何が出来る』。そう、見くびっていたのね。」
此所まで話してくれたのだから、もう1つ、質問しても良いだろう。
「ずっと、疑問に思っていたんですが。」 「何?」
「炎さんは、僕があの術で『あれ』に対処すると予想していたんでしょうか?
もしそうなら、僕があの術を使える事を、あらかじめ知っていた事になりますね。
Sさんは暫く窓の外を見つめた後、小さく溜息をついた。
「今考えれば、あなたが対処する方法はあれしかなかった。
でも、それはあくまでも後知恵。私があなたの立場だったとして、
あの術をあんな風に使って対処する方法を思いついたかどうか分からない。
炎がそれを期待していたとしたら、あなたと炎には共通点が有ったということ。
術に対する感覚、極限状態での行動や考え方、そしてその覚悟も。」
言われてみれば、炎さんも俺も、Sさんを好きになった。確かに似ている部分がある。
あの晩、炎さんは俺を『いちいち気に触る』と言った。
あれは、一種の近親憎悪から出た言葉だったのだろうか。
「私の得意な術。だからとうにあなたには教えてある、炎がそう予想してもおかしくない。
でも実際には、私があなたにあの術を教えたのは事件の前日、ギリギリのタイミング。
私、ずっと考えてたの。どうしてあの日、あなたにあの術を教えようと思ったのか。
でも、分からない。不思議、としか言いようが無い。それにもっと不思議なのは。」
「その前の晩、僕がどうしてあの夢、予知夢を見たのか、ですね?」
「そう、その夢を見たからあなたはあの術を試す気になった。まるで予行演習。
一度も試した事がない術が、精神的に追い込まれた状況で成功する確率はほとんど無い。」
確かに、偶然で片づけるにはあまりにも。その直後、ある名前が脳裏に浮かんだ。
『憶えておいて欲しい』と言われ、一生忘れないと誓った名前。
何故その名前が浮かんだのか、全く分からない。
だが、その名前を思い出したのだから、俺は大丈夫。そう思った。
俺の魂が穢れているなら、その名前を思い出せる筈がない。
『本当は俺の魂は穢れている。しかしSさんと姫の気持ちを汲んで、
当主さまと桃花の方様はそれを『上』には隠したのではないか。』
心の隅にずっと蟠っていた不安が跡形もなく消えてゆく。そう、俺は大丈夫。
だが、一連の信じがたい幸運を『御加護』とし、単純に喜ぶことはできない。
もう1つ、最大の疑問が残っている。
「今回の幸運は偶然が重なった結果だったのか、あるいは御加護があったのか、
それは確かめようがありません。でも、絶対に確かめておかなければならないことが有ります。」
「何故『あれ』が現れたのか、どんな経緯で、誰が関わっているのか。そうでしょ?」
「はい、ただでさえ数少ない『あれ』の記録は、どれも200年以上前のもので、
しかも遠い昔に、神さまの御加護を受けた術者達によって、全て封じられている筈ですよね。」
あれから何度も、俺なりに図書室の記録を調べてみた。
『あれ』は悪霊というより、邪神に近い存在。高位の精霊が人間に害をなすように変化したもの。
だが、それらは既に封じられ、200年以上もその活動は確認されていなかった。それなのに。
「血眼になって『上』が調査してるのも、まさにそれよ。
『あれ』が封じられている場所を全てあたって、封印の状況を調べている途中。
その封印を破り、邪な契約を結んで一族を壊滅させようとした者がいる。
そう考えるのが一番単純な解釈だから。 それに『あれ』が焼き尽くされたということは、
契約は完成していない。契約の対価となる命を受け取るべき『あれ』が滅びたのだから。
つまり『あれ』の封印を破った者は、未だ生きている可能性がある。」
そこまで話すと、Sさんは微かな笑みを浮かべた。
「ただ、どんな力を持っていても、そう何度も封印を破ることは出来ない。
生きているとしても、今回の失敗でかなりのダメージを負っている筈。
あの後『不幸の輪廻』の活動は通常のレベルに戻ったみたいだし、取り敢えず一段落。
それは間違いないと思う。ただ、念には念を入れて、そういうこと。」
封印の場所を知り、それを破る力を持った者。
一族に害をなす計画を立て、術を使って『あれ』と契約した者。
依頼を装い、疑われることなく紫さんを呼び出した者。
Sさんは敢えて口にしなかったのだろうが、それらの条件を満たすのは術者だけだ。
しかも依頼の経緯を考えれば、1人で実行出来る計画だとは思えない。
一族に縁の術者たちか、あるいは別の系統の術者たちか。
どちらにしても、『上』の調査の結果によっては、今後更なる対応が必要になる。
大がかりで、しかも、かなり気の重い。いや、今それを考えるのは止そう。
全ては『上』の調査次第。その結果が出ない限り、俺たちに出来ることはない。
ただ、細心の注意を払って日々を過ごし、自分自身と家族を守るだけだ。
車を停め、久し振りに参道の入り口に立つ。 俺は息を呑んだ。
2月の2回。3月の1回。計3回の祭祀と掃除の日は『立ち入り禁止』で参内していない。
あちこち、たくさんの落ち葉が積もっているだろうと思っていたのだが...
参道にも、手水舎とその周辺にも、全くと言っていい程落ち葉は落ちていない。
そして、いつも俺が落ち葉を掃き集める場所に、落ち葉の山。
「これ、どういうこと...一体誰が?」 Sさんも落ち葉の山を見つめている。
強い風が吹けば、直ぐに落ち葉の山は崩れる。ということは。
「Sさん、ちょっと拝殿と本殿の様子を見てきます。」
俺は小走りで拝殿に向かった。もしかしたらまだ。
拝殿、瑞垣の外から様子を見る。やはり落ち葉は落ちていない。本殿は?
本殿の正面。瑞垣の中に入ると、女の子の声が聞こえた。
「兄様、こっちよ。」
「もう、お仕事は済んだのだから、早く帰らないと。」 「嫌だ。少し遊びたい。」
パタパタパタ、軽い足音が本殿の右側から近付いてくる。
「あっ!」
小さな、5~6歳の女の子が、俺の右側、3m程先で派手に転んだ。
白い着物。少しの間を置いて、大きな泣き声。
思わず駆け寄ろうとしたが、何とか立ち止まった。
女の子の後を追ってきたのだろう。12~13歳の少年が女の子を抱き上げる。
「だから言ったろ。お社で走ってはいけないと。」
次の瞬間、女の子を抱いた少年と目が合った。女の子と同じ、純白の着物。
少年は、俺の目を真っ直ぐに見つめた後、深く頭を下げた。
「このお社の祭主様だよ。紫、ご挨拶なさい。」
...やはり、そうだった。あの夢の中の会話が鮮やかに蘇る。
少年が女の子の涙を袱紗で拭う。女の子は一度鼻をすすってから小さく頷いた。
「祭主さま、紫と申します。今日はお仕事を仰せつかったので、兄様とこちらに参りました。」
2人に歩み寄り、ゆっくりと跪く。 少年と女の子は澄み切った笑顔を浮かべている。
「ご助力頂き、心から感謝致します。今後機会がありましたら、是非よしなに。」
一礼して顔を上げる、既に2人の姿はない。
立ち上がり、振り返ると、すぐ後ろにSさんが立っていた。
「Sさんの答えは正しかった。僕は、そう思います。」
Sさんは大きく、何度も頷いた。奇麗な眼が赤く潤んでいる。そっと、小さな肩を抱いた。
「あの晩の出来事。眼が覚める前に不思議な夢を見たんです。
川の神様が2人の魂を救って下さる夢、それはきっと正夢だと、ずっと信じていました。」
「もし、私が炎を受け入れていたら、こうはならなかった。
あの縁談を断って、あなたと出会えたから、あなたを愛したから、こんな風に。
炎と紫にとっても、これはハッピーエンド。ね、そうでしょ?」
「はい、間違いなくハッピーエンドです。」 「後でLにも話して上げなきゃね。」
「今日は久し振りに僕が夕食を作ります。腕によりを掛けて。
みんなで美味しいものを一杯食べて、元気出しましょう。」
鎮守の森、廃村の跡、彼方此方で桜の花が咲き始めていた。
厳しい冬が終わり、もうすぐ新しい春がやって来る。Sさんと、姫と出会って5度目の春。
家族5人。そして、沖縄に帰りノロになるための修行を始めたあの少女。
それぞれの胸の中に、きっと、暖かい春の風が吹いている。
『玉の緒』 完

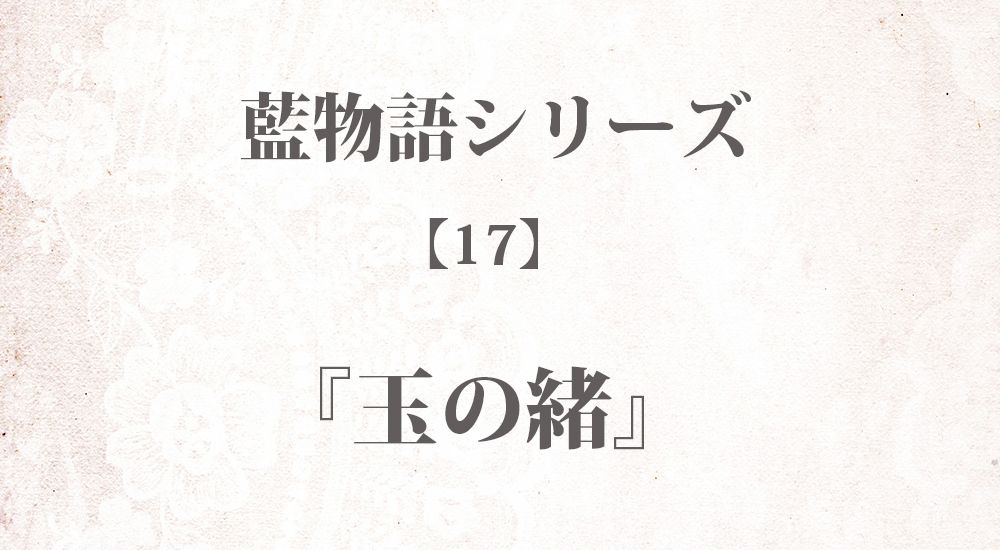

コメント