山にまつわる怖い話【65】全5話
誰かいる
この休みに友人たちと、ようやく花が満開になった梅林へ出掛けた。
いつものように、売店のある広場の隅でバーベキューの支度をする。
炭がちゃんと熾こるまで、少し暇がかかるので、焚き火職人をその場に残し、
近くで何枚か写真を撮った。
もう良かろうと戻ってみると、そいつが何ともいえない顔をしている。
「どうした?」
おかしな事に、途中の村営のスーパーで仕入れた具材のうち、本日のメイン
“山女”だけがきれいさっぱり消えている。
「あ、生で食っちまったのか?」
「食ってねえ、食ってねえ」
焚き火職人はぶんぶん首を振る。
彼が言うには、一生懸命火の世話をしていると、後ろから、俺たちの中の誰かが
呼びかけた。
「おい、買って来たぞ」
オレ、何か頼んだっけ?そんな事を考えていると、もう一度声がした。
「これ、ここでいいのか?」
「うん?」振り返ると、そこには誰もいない。
「あれ?」じゃあ、今の声は誰だ?
聞き覚えはある。だが、誰の声だったかわからない。
そんな馬鹿な…首を捻りながら前を向くと、山女だけが1匹残らず無くなっていた。
みんなで顔を見合わせたが、そうしていても始まらない。
「…まあ、山の中だから」
「しょうがねえなあ」
「次からは、火の番は2人だな」
そんな事を言いながら、もう一度車で買出しに出かけた。
富士山の山開き
昔、八ヶ岳にある宿泊施設のレストランでバイトをしていた時のこと。
職場は牧場の上にあり、赤岳を背に、周囲の山々を見渡せる眺めの良いところだった。
夏のある夜、二階のレストランのベランダで、シルバー(スプーンやフォークのこと)を磨いていた。
月もない夜空には満天の星。
仲間達と馬鹿話をしながらふと見上げると、空の一角にぽつんと赤い光が見える。
星にしては赤すぎる。それに周囲には、他に星がない。
真っ暗な空の一角に、小さい、赤い光が浮かんでいる。
何かな、と思っているうちにその光はどんどん増えていった。
無秩序じゃなく、斜め上に向かって伸びていく。
ゆっくりだけど、確実に増えて行く。
だいぶ長い間見ていたと思う。
仲間達が騒ぎ出し、厨房の人間も出てきた。
いったい何の光なのか、まったく分からなかった。
UFOなんて信じていなかったけど、納得したい気分になった。
赤い点の増殖はどんどんすすみ、空の一角で突然折れた。
同じ角度で、反対側に昇り始める。
少しずつ、確実に。
みんなで大騒ぎしていたせいか、外には滅多に顔を出さないコック長も出てきた。
で、ひとこと呟いた。
「富士山の山開き」
青い実
昔々、ある所に小さな村があった。
四方を山に囲まれ、どこに行き来するにも森深い山道を通らなければならなかったのだが、山中に人食い山んばが出るようになり、往来も途絶えがちで、寂れる一方の村だった。しかし村の子供達は、山の木々に生る果物や木の実目当てに、明るいうちだけおそるおそる山の中へと遊びに出かけていた。
そうした木々の中に、ひときわ大きな柿の木があった。毎年たわわに実をつけるので、子供達はちょうど良い熟れ具合になるのを待ち、木によじ登っては実をもいで食べた。
この柿の木、下の方は早々に熟し柔らかく甘くなる。少し上はやや熟すのが遅く固いがやはり甘い。が、てっぺんに生る実はいつも熟しきらず、青いまま季節を終えてしまうのだった。
そこで子供達は、毎年食べられる実を食べ切ってしまうと、「食べられもせぬのに実ばかり生りよる、役立たずの実じゃ」と、下から石を投げて青い実を打ち落としてしまっていた。
さて、その年もそろそろ柿の実の熟す季節、子供達はみんなして集まると、大人の目を盗み山の中へ入って行った。ところが途中、急に激しい雨が降り出した。子供達は雨宿りの場所を探して山中を走り回り、偶然見つけた小さな無人のあばら家に逃げ込んだ。
やまぬ雨に暇を持て余すことしばし、子供達の一人が何気なく土間を覗くと、炉の中にはたきぎの代わりに骨がくべてある。隅にはいくつものしゃれこうべが転がっていた。
「ここは山んばの小屋だ!」子供達はみな仰天した。山んばが戻ってくれば生きたまま食われてしまう。子供達は降りしきる雨の中に飛び出し一目散に駆け出した。すると、後ろから恐ろしげな唸り声が追いかけてくる。山んばが戻ってきたのだ。子供達は必死で逃げ続け、いつしかあの柿の木の真下まで来ていた。
他に逃げる所もなく、みな柿の木をよじ登り始める。すると山んばも追ってよじ登ってくる。子供達は手元の熟しきった柿の実を山んばに投げつけた。しかし、柔らかな実は、山んばに当たってもぐちゃっと音を立ててつぶれるだけだった。
山んばは「当たれど痒し、熟れすぎ柿の子」とせせら笑った。子供達はさらに高い所に逃げ、手元の実をもぐと山んばに投げつけた。しかし山んばは、投げつけられた実をむしゃむしゃと食べてしまうと、「当たれどうまし、熟れたる柿の子」とゲラゲラ笑った。
とうとう子供達は木のてっぺんへ追い詰められた。「さあ、観念しろ」山姥は足元から迫ってくる。子供達はみな泣き出しそうになった。手元には青く硬い柿の実が残っているのみ。子供達はその実をもぐと、ままよとばかり山んばに投げつけた。すると山んばは、「当たらば痛し、熟れざる柿の子」と悲鳴を上げると、木からまっ逆さまに落ちて死んだ。
以来、子供達は熟しきらぬからといって青い実を落とすことはしなくなった。
霧の中のハイカー
就職も決まり、どうしても学生時代と決別したくて初冬の南アを縦走した。
縦走3日目 昨日からだれとも会わない。
夜明けから霧が濃い。体感気温はおそらく0度以下。モノトーンの世界。
足元を見ながら歩いていると、楽しくかつ切なかった4年間の思い出が走馬灯のように脳裏をよぎる。
突然 霧の中からハイカー 中年の夫婦とおぼしき2人連れ。
「やあ、おはよう。」「おはよーございまーす。」お決まりの山の挨拶。
でも 挨拶を返そうとして止まってしまったオレ。
だって二人とも夏山の装備。ブランド品のポロシャツ。新品のニッカボッカ。おまけに流行遅れのチロル帽。
霧の中に消えるまで 2人とも絵に描いたような夏山を楽しむ中年夫婦だった。。。
霊感0のオレの唯一の不可思議な山の体験。
つぶて
友達の友達の友だt(ryから聞いた話
去年のお話
Aは秋の小さな連休に実家帰った
そこは何も無い田舎で、遊び盛りのAは暇を持て余していた。
余りににも暇なためAは、仕方ないから近くの山まで散歩をする事ににした
Aが、山の麓についた時、山の奥から不穏な空気が漂ってきた。
しかし霊や化け物を信じないAは、気にせず山に一歩踏み出した時
「コツッ」
と頭に何かが落ちてきた。
近くの地面を調べると栗が落ちていた。
Aが入ろうとしてる山は針葉樹林が大部分を占めている。
上を仰いでも、栗の木何て無い。
「?」と思いもう一歩踏み出そうとしたら
目の前に[いが付きの栗]が落ちてきた。
流石にそれは当たるのは痛いだろうからAは山に入るのを諦めたそうだ。
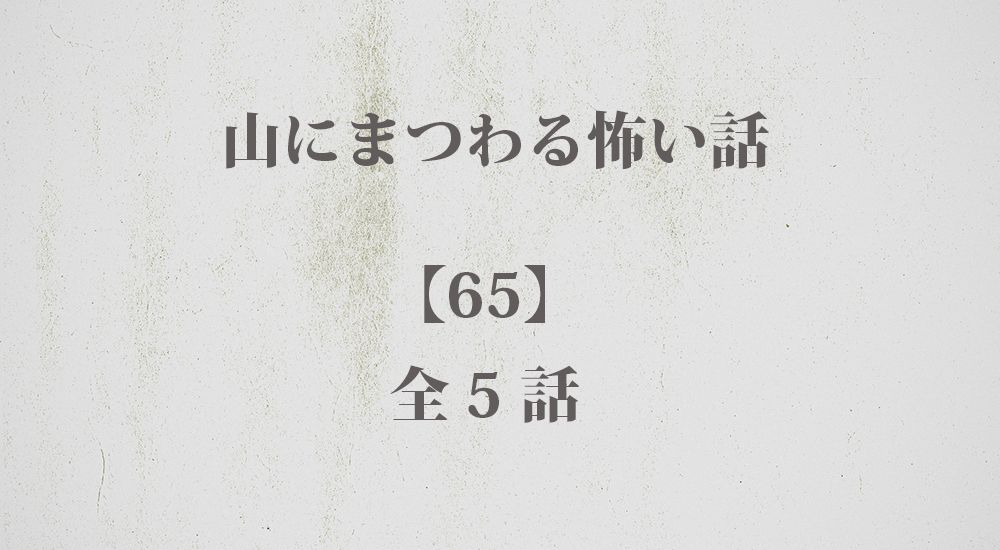
コメント