藍物語シリーズ【39】
『鬼』
これで、終わりだ。そう、何もかも、終わり。
大学の仲間と、初めて登った山。登山道から少し外れた所に洞窟がある。秘密の、隠れ家。
雨を避ける間タバコを吸い、他愛も無い話を。 そうだ、亜△に告ったのも此処だった。
もうケチる必要は無い。残っていた○×を全部掌に、思い切り鼻から吸い込む。
はじめは割の良いバイトだと思ったし、半年位は最高だった。
来た...手足の先端からビリビリと、神経を流れる電気が体を突き抜けて、空気に溶ける。
この感覚はあの時と変わらないのに、何で俺はこんな。俺だけが。
そう。アイツ等だ。
仲間に引き込んで、ヤバくなったら、全部俺に押っ被せて。
タカシからの電話。『追われてる。』って。 アイツ、やっぱり馬鹿だ。
もし『販売網』が潰れたら、当然△◆会は。いや、何で俺が...そうか。
いい気になって、全然気付かなかった。 亜△との別れ話も。
そりゃ、俺が売った○×で何人も、破滅した奴が何人も...それは仕方ない、自業自得だ。
なのに、何でアイツ等はのうのうと。全部俺に、本当にこのままで。
くそ、心臓が。こめかみの血管が膨らんで、眼が眩む。 痛ぇ。
このまま、俺は死ぬのか。 せめて、アイツ等だけは。この手で。
『永かった、本当に。待ちくたびれたぞ。ようやく、贄が。』
耳の奥に響く声。 「に、え?」
『そう、贄。その憎しみこそが、操者の資格。
その命と引き替えに、敵を殲滅出来る。さあ最初は誰だ?』
嘘のように、気分が良い。眼を開けると、薄暗い天井が見えた。
不思議だ。体に、力が漲っている。上体を起こし、立ち上がった。
トンネル? 遠くに灯りが見える、非常灯か。
少し歩くと、出口を塞ぐ鉄条網。 こんなもので俺を? 何故か、確信があった。
右手を伸ばし、手をかける。 力を込めると、鉄条網はあっけなく倒れた。
俺は自由、そう、自由だ。 自然に、笑みが浮かぶ。
この体、この力があればアイツ等を。
「榊さん、これ...。」
『分署』の窓から吹き込む乾いた風が梅雨明けを告げている。
しかし、この写真は。爽やかな風にふさわしいとは、とても。
「今朝発見された遺体だ。死亡推定時刻は昨夜遅くから今日の未明。
急に来てもらって申し訳ないが、それを見れば納得してくれるだろ?」
そう、これまで幾度も、榊さんの仕事を手伝ってきた。
公にはなっていないが、いわゆる猟奇殺人者が関わった事件もあった。
しかし、この遺体の惨状は、幾ら何でも。
「傷口から見て、凶器は刃物じゃない。獣、例えば羆が食い千切ったとしても、
断端はこうならない。それに、決定的なのは、この写真。これは、R君たちの領分だ。」
千切れた、右の二の腕。肩の付け根に残る、赤黒い痣。それは...指の、跡?
「素手で引きちぎればこうなるかも、鑑識はそう言ってる。
まあ実際、爪の痕も牙の痕もない訳だが。しかし、信じられん。」
一切の道具を使わず、素手で人の体をここまで?
「被害者の、身元は?」
「大学生、○△大の。部下達が被害者の身辺調査をしてる。」
榊さんの横顔、その表情が事件の重大性を告げていた。
分署から帰ると姫が身支度をして俺を待っていた。
「招集です。『上』から。さっき遍さんから電話がありました。大至急との事で。」
嫌な、予感。何故姫が?俺と姫が招集されたのは、『分家』の始末に関わる件だけだ。
「じゃあ、出ましょう。これ、Sさんが作ってくれたサンドイッチです。車で食べてくださいね。」
透き通る笑顔、姫の横顔は本当に美しかった。
薄暗い中、フェンスで閉鎖されたトンネルの入り口のようなものが見える。
映像がかなり荒いのは監視カメラの映像だからだろう。
「此所からです。」 遍さんの声。 突然、フェンスが揺れた。 内側、から?
その後フェンスはトンネルの中に引き込まれるように大きく歪み、呆気なく壊れた。
開いた入り口に現れたのは、黒い着物。
これは人? いや、薄闇に光る両眼は、まるで夜行性の獣ではないか。
それがゆっくりと、カメラに近付いてくる。 その表情は、笑って。
え...? その頭。 次の瞬間、それは身を屈め、画面から消えた。
「今の、一体何ですか?」
映像が再生された後の重い沈黙に耐えられず、俺は口を開いた。
「ある場所の、トンネル工事現場で撮影されたものです。
記録を基に以前から警戒していましたし、情報も直ぐに入ったのですが...」
遍さんは言葉を切り、外した眼鏡をハンカチで拭いた。
「間に、合いませんでした。まさか、その夜の内に活動を始めるとは。」
「あれが活動を始めたら術者でも対処出来ない筈、責任は誰にも。」
姫の声が緊張している。 遍さんは小さく溜め息をついた。
「Rさん、あれは古の術で作り出された怪物てす。一般的には『鬼』と呼ばれていました。」
鬼? では、あの映像で見えたような気がしたのは、やはり角? まさか。
「鬼って。本当にそんなものが。どうして。」
「一種の生体兵器、対術者用の兵器だと、聞いた事があります。
ほとんどの術に耐性を持ち、有力な式の力もこれには届かないのだと。」
「そう、Lさまの仰る通り。『刀や弓矢、種子島でも滅することかなわず。』という記録も。
人外の力と速度。術者でも武人でも、それに対処することは極めて困難。
ただ、消費するエネルギーが半端でないので、活動できる期間はせいぜい合計一週間。
故に現存するものは乾涸らびてミイラ化したものか、その断片だけ。
しかし稀に、特殊な維持装置と共に封じられたものが完全な状態で見つかることがあります。
それ等が封じられたという記録の有る場所については厳重な監視の対象とし、
探索して見つけたものも、偶然見つかったものも処理して来ました。しかし、今回は。」
遍さんの、暗い表情。
突然、思い出した。榊さんに見せてもらったあの写真。
「あの、今日僕が受けた依頼の件で、もしかしたらそれが。」
「今朝発見された遺体の件ですね?既に情報は入っています。
遺体の状況からして、あれが関わった...いや、殺したのは間違いないでしょう。」
「術でも、式でも、武器でも駄目なら、一体どうやってそれを滅すれば?」
「それにダメージを与えられるのは、唯一、神器による物理的な攻撃だけです。ただ。」
「ただ?」 何だろう、この感覚は。 あの短剣なら? でも、そんな怪物を、俺では。
遍さんは眼鏡を外して、丁寧にハンカチで拭った。溜め息。 嫌な、予感。
「委任されたとしても、梓の弓と破魔の矢を扱えるのは『武』の特性を持つ術者だけ。
しかし現在、条件に見合う術者がいません。既に『武』で身を立てる時代が終わって久しく、
神器を扱えるまでに『武』の修行をする術者は、さすがに...。」
首筋から背中に、鳥肌が立つ。
神器の主、当主様と桃花の方様なら、当然扱える。
しかし、一族の祭主たる御二人が直接事にあたることはない。万が一御二人の身に。
なら今日、姫と俺が招集されたのは? 他の術者では無く、俺たち二人が。
「そろそろ本題に入りましょう。先刻の会議で、『上』は対応策を決定しました。」
部屋の温度が一気に、下がったような気がする。
「御影を憑依させ、『武』の適性を持つ術者を化生させます。
ただし、並外れた身体能力を持つ術者でなければ、御影の武を活かせない。」
「まさか...。」
「まさか、ではありません。身体能力、性別、L様以上の適任者はいませんから。
それに、御影が心を許しているRさんは、御影の補佐として最適。」
しかし、それで、もし姫の身に。
待て、確か遍さんは言った。『鬼が活動できる期間には限りがある』と。
それなら、その期限を待てば...いや駄目だ、活動する期間の分だけ、命が。
「分かりました。私の身体、御影さんとRさんに委ねます。」
涼やかな声が部屋の空気を震わせた。
そうだ、姫ならきっと同意する。 『上』はそれを分かっていて。
「数多の命を犠牲にして、『期限』を待つわけにはいかない。そうですね?」
「はい、初めのうちは操者の意思に従い敵を攻撃しますが、
やがて操者の心は鬼に呑まれ、見境無く殺すようになる。
そうなれば、『期限』までにどれだけの犠牲が出るか見当もつきません。
更にそれが『不幸の輪廻』と繋がれば、『期限』すら無効になる可能性すら。」
「際限なく、敵でない人たちまで殺すということですか?どうして、そんな。」
「...あれが、『殺すために作られたもの』だからです。」
「まるで、術者の影、のような存在ですね。」 姫は、微笑んでいた。
「そうです。術者がいなければ、おそらく、あれが作り出されることも無かった。」
矛盾、か。 文字通りの矛と盾、人を襲う怪異と、怪異から人を護る術者は、
言わば果てのない軍拡競争を繰り広げてきたのだろう。 哀しい。
すい、と、遍さんは立ち上がった。ゆっくりと眼を閉じる。
「聞いていたな、御影。」 部屋の中に冷たい風が吹いた。
『応。』 低く太い、声。 最初から、この部屋の中に。
「それで、御前の意見は?」
『それ以外に策はない。しかし、神器だけでは不足。』
「『梓の弓』と『破魔の矢』でも不足とは?」
『マタギだけで熊は狩れぬ。少なくとも勢子が要る。鬼が相手なら尚更。』 「勢子?」
『弓矢に必要なのは距離。構え、射るまでの時を稼ぐ者が要る。
術の心得は必要ない。『武』の適性を持つ者ならば役に立つ。』
「Rさんが?そうか、あの短剣を使うのなら。」
『...いや。Rに、そこまで『武』の適性はない。』
あの霊域で直接指導を受けた時に、それは理解していた。 俺は不肖の弟子。
しかし、答の前の間。その言葉に籠もる気遣いが、胸に痛い。
「しかし、それ以外の適任者は。」 『案ずるな。心当たりがある。』
その声を最後に、御影さんの気配は消えた。
「これで良いと、思うけど。私も、この術は初めてだから。」
Sさんが立ち上がる。図書室の奥、板張りの床に正座した姫は、眼を閉じたまま。
「ただ、期限は最大でも十日。相性が良いからかなり長いとも言える。
でもそれ以上は、Lの体が負荷に耐えられるか分からない。
耐えられなくなったらどうなるのか、それも前例の記録が無い。」
姫の体が? それだけは絶対に、避けねばならない。 しかし、たった十日?
「じゃ、R君。お願い。Lに、いいえ、御影に呼びかけて。君の『言霊』が、この術を全うする。」
少しだけ、Sさんの声が震えていた。無理も無い、俺だって。だが、これは、俺の役目。
呼吸を整え、心を静める。 深く息を吸い、下腹に力を込めた。
『眼を、開けて下さい。御影、さん。』
静かに時が過ぎていく。もし、『言霊』が届かなければ、それは。
何秒経ったろう、いや何分か? 穏やかな声が重い空気を吹き払う。
『見事な術。流石は氷の姫君。』 ゆっくりと姫は、いや、御影さんが眼を開いた。
見慣れた、美しい顔。でも、姫とは違う微笑。 安堵と不安が同居する、この感覚は一体?
「久しいな。R。」
ああ、そうか。 透明な笑顔と柔らかな声の、奥にあるものは同じ、なのだ。
自ら望んだ訳でなく、しかし『持って生まれたもの』に対峙する、覚悟。
だからこそ姫はこの役目を。
『御前は本当に、良い妻を持った。少々、気に触る程に。』 立ち上がる。
だって、それは俺が望んだ訳では...いや。
『はい。ですから決して、この件でSさんとLさんに障りが出る事だけは。どうか。』
『承知している。我に、任せろ。』
ドアを開けて、御影さんが帰ってきた。
被害者が通っていた大学の近く。地方都市のホテル。
事は一刻を争う。だから昨日、御影さんが目覚めた後、すぐに移動した。
遺体の発見現場と大学の両方からそう遠くない場所に、それは潜んでいる。
それが榊さんの見立てで、御影さんも同意した。
今日は朝から、榊さんと一緒にあちこち調べていた筈だ。
「御影さん...それ。」 口元に、白く細い棒、ペロペロキャンディー?
きっと小脇に抱えた紙袋の中身も、大人買いか。
「今日は、あちこち調べるって、まさかそんな物食べながら。もっと真面」
次の瞬間、キャンディーは俺の口に押し込まれていた。手品?
「五月蠅い。朝から気を張っていたのだ。菓子くらいで罰が当たる訳ありません。」
??? そう言えば姫はお菓子、甘いものが。しかし。
ある程度の『共振』があるのか、それとも姫の記憶に接触できるのか。
話し方や行動に少々混濁があるようだ。
御影さんはソファに腰掛け、地図を広げた。
「面倒だな。あれが相手でなければ、こんなものに頼らずとも...」
市内の地図、しかしこの縮尺? ああ、榊さんが拡大コピーを。
赤い丸印が4つ見える。1つは被害者の大学、もう一つは遺体の発見場所。
なら、あとの2つは?
「二人目の被害者です。昨夜見つかったのだと、榊が。」
榊? 呼び捨ては、いや御影さんの方がずっと年上か。榊さん、どんな顔してたんだろう?
「それと、興味深い話を聞いた。」 「興味深い、話?」
「大学の、茶屋で話しかけてきた男から。」 「大学の茶屋って、被害者の大学ですか?」
「そう。『黙ってお茶を飲んでいれば話しかけてくる男がいる』と榊が。
その通りだったから驚いたぞ。ああ見えて、榊は中々切れる男だな。」
少し、目眩がした。まさか被害者の大学、ナンパさせて情報を?
「適当に相手をしていたら、はぁぶの話になって。」
はぁぶ? って、ハーブ...ドラッグか?
「阿片か、その類いだろう。大学にも使ってる奴がいるから気をつけろ、と。」
御影さんは小さな声で笑った。
「初見で馴れ馴れしく話しかけてくる男を避けていれば、そんな災いには縁が無いだろうに。」
「榊さんが、その件を調べてるんですね?」 「そうだ。思い当たる節があるらしい。」
「しかし喋り方ひとつにも気を...とても疲れました。少し寝る」
ああ、その話し方はそれで。
1時間程すると御影さんは眼を覚ました。
シャワーに入り、身支度を調えるのを待って、遅い昼食に出かけた。
『どうも、今の世の味には馴染めぬ。』 大儀そうな表情。
和食だから洋食よりはましだろうが、あの時御影さんが作ってくれた料理とはかなり...。
しかし、食べてくれないと姫の身体に障るし、結果、御影さんの能力にも影響が出る。
「さて、部屋で少し休んだら夜は街へ出よう。場所は調べてある。」
「街へ出るって、何しに。」 「勢子、だ。使い物になるかまだ分かりませんが。」
夜9時前、とあるビルに着いた。
その場所は、あの地図に記されていた赤い丸印の1つ。
大きな自動ドアを潜り、御影さんは廊下を奥に進む。慌てて後を追った。
エレベーターのボタンは3F、エクササイズジムの表示がある。受付は若い女性。
「あの、電話で見学と体験をお願いしたRです。彼女が、その、体験希望者で。」
打ち合わせ通り。 御影さんの妙な喋り方で不審に思われるのはマズい。
真新しいジャージと運動靴の御影さんをちらりと見て、受付の女性はにこやかな笑顔。
「はい、あと5分程で通常のレッスンが終わります。中のベンチでお待ち下さい。」
ドアを開け、エクササイズルームに入った。 軽く頭を下げる。
涼しくて快適、軽快な音楽。 ボクシング? 思っていたより女性が多い。
上級者クラスなのか、皆、中々の動きだ。やがてゴングが鳴り、音楽が止まった。
「OK、皆さんお疲れさま~。」 「ありがとうございました!」 「あざっした!」
生徒達の前で見本を見せながら、時折熱心な個別指導をしていた青年。
二十歳そこそこに見えるが、爽やかな営業スマイル。さすがにプロ。
突然、耳元の囁き。 『R、あの男の声を聞け。心の声を。』 「心の、声?」
生徒達は談笑しながら次々にエクササイズルームを出て行く。
あの男って、トレーナーっぽい笑顔の青年? あ
全く息が弾んでいない、汗も...一気に集中力が高まり、チャンネルが同調する。
最後の生徒がエクササイズルームを出た直後。
『これで良いのか、オレは。』 『いくらジムが繁盛しても...』
溜め息。暗い、自虐的な笑顔。それは術者でなければ気づかぬほどに微かな。
ゆっくりと後退る。ガラス張りの壁に近付いて護符を貼り付けた。
これで、今後エクササイズルームの中に注意を向ける者はない。
後は御影さんに任せるだけ。
「溜め息なら、未だ希みはある。」
青年は驚いたように振り返った。 御影さんも立ち上がる。
「ああ、体験の方ですか。」
「体験...そうだ。◎の家が継承してきた武を貴様に。それが、◆秀の遺志だから。」
青年の顔色が変わった。
「祖父の名を...成る程、アンタ達は一族の術者か。噂は聞いてるよ。
だが、オレなりに頑張って一族に貢献してる。咎められる筋合いはない筈だ。」
「なら何故、溜め息を?」 「それは...」
「分からないなら教えてやる。『つまらない』からだ。その生き方が。」
「つまらないって、オレは毎日。」
「武門に生まれた者が満足できる訳が無かろう。毎日が体育の指導では。』
「体、育?」 「見学した限りでは、体育。それ以外に言葉がない。」
すい。御影さんは屈んで運動靴を脱いだ。姫と寸分違わぬ優雅な仕草、なのに。
一歩、踏み出した素足が柔らかなマットを掴む音に、腹の底が冷える。
「最初はこう。」
両の拳を顔の前に。左足が一歩前。 「そして、こう。」
きゅ、と、床を蹴る破裂音が聞こえた。
拳が小気味よく風を切る、左・左・右。右・左・右。すっ、と体が沈み、弾ける体。
ごう、と右拳が天を突く。 アッパーカット?
「左右入れ替えれば、こう。」 さっきとは完全に反転して、そして更に速く。
「アンタ、どこでボクシングを?」 「此所で。先刻、見学したから。」
「そんな、幾ら何でも...たった数分で?」
「疑うなら、自分で確かめろ。立ち会えば、直ぐに分かる。」
「馬鹿言うな。何でオレが女と。」
『○雷』
その名に籠もる力が、エクササイズルームの空気を震わせた。
「本来、それは貴様が継ぐ筈だった。一族最強の武を背負う号。◆秀の孫、◆成。
時代が変わったとは言え、その号が絶えてしまう事を、
◆秀は心の底から悔いていた。先達に申し訳ない、と。」
「アンタ、一体?」
「我が名は御影。当主様の命を受け、この体を借りて化生した。」
「『御影』って、まさか。」
「借りた身体の能力は極上、我が人であったときと遜色ない。
つまり貴様は運が良い。今、貴様の眼の前にいるのは、紛れもない『○雷』。
勿論尻尾を巻いて逃げるなら好きにしろ。止めはしない。」
意地の悪い、笑顔。 何故そんな挑発を、もし事故があれば姫の体が。
「良いだろう。ただし、女の子相手。俺は『当てない』。大人気ないからな。
当たった、と、アンタが納得すれば終わり。それが条件だ。」
「構わん。それで、我は当てても良いのか?」 「好きにしろ。出来るなら。」
青年は浅く息を吸った。
そのまま左足を一歩踏み出そうとした瞬間、御影さんの身体がゆらりと。
直後、青年は右足を前、両拳を顔の前に。
「おや、女子相手に本気とは。確か先刻大人気ない、と。」
「馬鹿言え。『△歩』を使う相手、女の子だろうが此処からは全力。悪く、思うな。」
「それでこそ、だ。」 御影さんは微笑んだ。空気がぴいんと張り詰める。
ペタ、と、青年は尻餅をついた。
御影さんは右掌を前に...近い、青年の胸を?
多分、そうだ。ハッキリとは見えなかったが。そうとしか。
「ぼくしんぐ。それが長い時をかけて練られた体系なのは知っている。
しかし、あくまで規則の下で『競い合う』ためのもの。『武』とは違う。
『武』の目標は必勝、競い合いではない。故に、打たせてはならぬ。
力や体格で上回る相手なら、まぐれ当たりでも、当たれば敗ける。」
「...でも、あんな、体重移動。化け物め。」
御影さんは微笑った。姫と同じ顔、でも姫とは違う、笑み。
「利き足と利き手に切り換えたのは中々の嗅覚だし、
初見で体重移動の違いを見抜いたなら、褒めてやろう。」
「初見じゃない、思い出したんだ。
全く同じだよ。一度だけ、祖父さんに稽古をつけて貰った、あの時と。」
「長い長い時を費やして先達が積み上げた技術を基に、
辿り着いた極致。その速さ故に継承者は『○雷』と号される。
だがこれは『出発点』。貴様が望むなら、立て。我が◆秀の遺志を継ごう。」
数分後、青年は仰向けに倒れていた。 マットに力なく伸びた手足、息も荒い。
「くそ、こんなにも差が...オレは一体今まで何を。」
俺自身、あの『霊域』で経験した感覚。 きっとそれは、心の底から絞り出した、言葉。
「貴様、笑ってるぞ。」
「そうさ。女の子に、良いようにあしらわれて、悔しくて堪らない。なのに。」
青年はゆっくりと上体を起こし、胡座をかいた。
「ゾクゾクする。心底、楽しい。何で?」
「貴様の体に流れる血故。それはかつて◆秀の、そして我の体に流れていた血だから。」
「ならオレはもっと強く、なりたい。俺の身体に流れる血の限界まで。」
「その言葉に、偽りはないか?」
「ない。」 一瞬の躊躇もなく青年は答えた。心地よい言霊。
「身体能力は申し分ない。ただ、稽古だけで『武』は身につかぬ。」
「それなら、どうすれば良い?教えてくれ。」
「我等は明日にでも『鬼』を狩る。我も1人では手に余る、羆並みの怪物。」
「いきなり羆...オレが、その怪物を相手に?」
「限界を知りたいなら、望外の相手だろう。勿論、無理強いはしない。」
「祖父さんが悔いていた、アンタはさっきそう言ったな?」
「ああ、我は其所にいて、その声を聴いた。」
御影さん自身が望んで、血縁の武人の臨終を看取ったのか。
それとも今際の際、その武人が御影さんに呼びかけたのか。
「アンタでも手に余る相手。もしオレが生き残ったら、祖父さんの心残りは消えるかな?」
「『○雷』の号を志す者が現れるなら、それこそが〇秀の望み。」
「なら、オレを使ってくれ。頼む。」 青年は居住まいを正し、深く頭を下げた。
「良い、心がけだ。」 御影さんの声は優しかったが、その眼は笑っていなかった。
幾ら何でも、心が折れてしまうのではないか。
その青年が『武人』の血を継いでいるのであれば尚更、
あの時の俺とは比較にならない程の屈辱だろうに。
それ程、容赦のない稽古が続いていた。営業前のエクササイズルーム。
だが青年はその度に立ち上がり、構えを取った。
十何回目、いや何十回目だったろう。
すい、と一歩踏み出して、御影さんは青年の右手を取った。
両手で青年の右掌を広げる。無言のまま、手の甲をそっと撫でた。
「あの、師匠?」 戸惑ったような、青年の表情。
「右拳だけで、何人倒せる?相手が普通のぼくさーだとして。」
「...アマチュアで階級が同じなら、まあ、5人は。」
「なら左拳だけで2人、両拳を使えるとして5+2の倍、14人。」
くるりと踵を返し、一歩二歩。御影さんはもう一度振り向いて胡座をかいた。
つられるように、青年もその場で胡座をかく。 正対した2人は師匠と弟子そのもの。
「確かに貴様の身体能力は別格。しかし実際には10人でも無理だろう。」
「そんな、どうして。」 「右掌に、骨折の痕がある。」 「え?」
少しだけ黙った後、御影さんは奥の壁を指さした。
壁には高名なボクサーの写真。サイン入りのグローブ。
「あの大仰な籠手を使っても拳を壊すことがあるのだろう?
もし3人目で右拳を壊したら、残りは利き手ではない左拳だ。ならせいぜい2人、計5人。
しかも『実戦』であんな籠手を使う訳にはいかぬ。」
「だから師匠は拳を握るな、と?」
「そう。打撃で使うのは掌底、そして手刀、2つだけで良い。
掌底は顎や水月への打撃、手刀はこめかみや首、肋への打撃。」
「首、って。反則じゃ」 「実戦に規則はない、当然、反則も。」
「じゃあ、眼は。」 「的は小さく、指を痛める危険もある。狙う意味はないが、もっとも。」
「はい?」
「抵抗できなくなった相手や死体の眼を抉り出すのを好む奴等なら幾らも見た。」
「死体の眼って...」 「敵に敬意を持たぬ外道も確かにいる。始末する他ない。」
「殺す覚悟が要る、って事ですか。」 「そうだ。」 御影さんは静かに息を吐いた。
「オレ、人を殺せるかどうか。」
「外道を見つけたら必ず始末する。放っておけば『鬼』にされかねん。」
「これが、破魔の矢。我も、手にするのは初めてだ。」
あの時、その鞘が取られることはなく、幸運にもその鏃を見ずに済んだ。
やはり、御影さんも鞘を取らない。 それが許されるのは、使う理由がある時だけ。
「日月一対。我が知る限り、神器の中でも最強の武器。」
「ええと師匠、オレでもその矢がとんでもない武器だってのは分かります。
でもオレが相手にしてる間に、それで鬼を射るって言ってましたよね。
一対ってことは2本ある筈なのに、何故1本?動いてる的をたった一本の矢で。
いや、師匠を信用してますが、相手は『鬼』ですよ?1本より2本の方が絶対。」
この青年の言うとおりだ。それに。
「確かにこれを委任されたが、人の身では一射が限界。身体も心も。』
「それなら鬼が近づいてくる所を遠くから、で。本当にオレ、必要なんですか?」
「鬼の頭にある角は、知っているのだろう?」 「え?もちろん。それが鬼の。」
「あれは鬼と操者を結ぶ通い路であり、優れた感覚器。」
噛んで含める。そんな言葉が浮かんだ。
微笑む御影さんはまるで、弟を優しく諭す姉のように見えた。
「はぁぶを売り捌いていた者共は、黒幕の手の者に追われ姿を隠していた。
しかし黒幕の手の者も、榊でさえその行方を辿れぬうちに、鬼は4人を殺した。何故だ?」
「角を使えば、殺したい相手の居場所が分かる?」
「恐らく、造作も無い。そんな感覚を持つ相手に。」
「分かりました。その弓矢を準備して待っていたら、感付かれる。」
「弓の心得はあるが、正当な所持者でない我に、神器の力の全ては引き出せぬ。
そうだな、射程は十間。それより遠ければ望みは無いだろう。」
「じゅっけん、って?」 御影さんは困った顔で俺を見た。
ああ、以前は俺も知らなかった。この青年には、出来るだけ直感的に。
「野球の、マウンドからホームまでと大体同じだよ。18mと少し。」
青年は御影さんと俺の顔を交互に見詰めた。
「師匠と2人で鬼を待つ、現れたらそこでオレが。」
「そう、君が時間を稼ぐ間に御影さんが神器の封を解く。
その準備が整うまで時間を稼ぐ、それが君の役目。倒すのは無理、何とか逃げ回って。」
「人と同じ体重の羆が相手だとして、1ラウンド。3分逃げ切れば合格かな?」
「あの鐘、『始め』から『止め』までの間か...
その半分で良い。今、貴様に死なれては◆秀に申し訳が立たん。」
青年の、不満そうな表情。1ラウンドも持たないと言われれば当然プライドが傷つく。
浅はかと言えばそれまでだが、無理も無い。この青年はまだ『人外』を知らないのだ。
「羆並みって言っても、体格も体重も人と大して変わらない。だったら。」
「確かに羆並みとは言ったが、ただの獣ではない。人の智恵を持つ羆。
だからこそ貴様が必要なのだ。並の武人なら一撃で殺される。」
「人の智恵を持つ...でもオレが。師匠、分かりました。全力で1分半、稼ぎます。」
あーあ、どん底から天国まで。 それはそうと。
「師匠、段取りは分かりました。ただ本当に鬼が来るかどうか。」
まさに其処だ。俺も青年と全く同じ疑念を。もし鬼が来なかったら。
「来る、榊の言うとおりなら。」
胸の奥に燻る疑問を、俺はどうしても振り払えなかった。
夢を、見ていた。
古いお屋敷の庭、緑濃い生け垣全体を彩る紅い花々。咽せるような香り。
どこか懐かしい、既視感。
するり、と、腕の中に潜り込んできた温もり。これは。
「御影さん、何、してるんですか?」 「この方が良く眠れるから。」
「いや、マズいですよ。」 まあ、パジャマ着てるからあの時より、いや、そんな問題じゃない。
「妻と同衾するのに不都合があるのか?」 「いや、だって今は。」
「何にしろ。」
漆黒の、大きな双眸。見詰められると吸い込まれそうな。
「我に、聞きたいことがあるのだろう?」 どうして、それを。
「正直に、顔に出る。好もしいが、術者としては。
まあ良い。大事を前にして、味方の不信は命取り。聞こう。」
「ええと、あの人、◆成さんを巻き込む必要が本当にあったのかな、と思って。」
「やはり、そうか。御前の剣を借り受ければ、我1人でも鬼を狩れるのでは、と?」
「はい。◆成さんも言ってた通り、チャンスがたった一度きりでは、心許ないですから。」
御影さんは寂しそうに微笑んだ。
「『上』でもその策を推す声が多かった。最強の神器を委任するのを躊躇うのは当然。」
「ひっくり返した、ということですね。当主様が。御影さんが当主様に進言して。」
「そうだ。」 「何故、ですか?」
「鬼は一体一体異なる。それ自体の資質、そして操者の能力。
この身体に何の不足もないが、それでも勝てるとは限らない。
そもそも、神器の剣を委任されたとして、鬼を倒すまで、その剣を扱えぬなら意味が無い。」
「だからって、◆成さんを囮にしなくても。僕は喜んで。」
「未熟だが、『○雷』の血を継ぐ者。それでなければ鬼を欺けぬ。」
ふう、と御影さんは、溜息をついた。自分の血に連なる青年を、一体どんな気持ちで。
御影さんも、あの青年も。その『武人』としての覚悟。俺には到底理解できない次元。
もう良い、話題を変えよう。
「あと一つだけ、質問を。」 「何だ?もう、眠いのだが。」
「一体誰が、何のために『鬼』を?術者でなければそれは不可能ですよね?」
「ああ、かつて『力』でこの国を我が物にしようとした、馬鹿者共がいた。
もう、600年程も前の事だと、聞いている。」
「『力』でこの国を?」
「そう。幾度も我等に挑み、その度に敗れた旧い一族。
しかしその結果、奴らは、あのおぞましい手段を産み出した。」
「おぞましいって、どういう?」
「術も、式も、通常の武器も通じない化物、それを産み出すとしたら、必要なのは?」
「まさか、そんな。」 御影さんは俺の胸に顔を埋めた。
「人は愛しい。しかし時折、絶対に許せぬ者共がいる。何故だ?」
俺の寝間着。胸を濡らしていくのは、涙? 姫と同じ、綺麗な顔で。 胸の奥が、痛い。
「あの化物を作るのに必要なのは数多の体と魂。人と、必要なら各種の獣も使う。
優れた資質を持つものたちを材料とする。文字通りの、外道。
しかも奴らはその術の一部を公開し、在野の術者も数多の『亜作』を作り出した。」
「でも、一族はそれに対処出来たんですよね?だから。」
「そう。ただ、数が多過ぎて、『首謀者』を取り逃がした。それは仕方ない。」
「それで、残された『鬼』を見つけ次第処理してきた、と。」
「『首謀者』を...」 そのまま御影さんは翌朝まで、眼を覚まさなかった。
「今、奴がアパートを出た。バイクだ。
灰色のスウェット、角はニット帽で隠してる。じゃあ、後は任せたよ。」
榊さんから電話があったのは夜10時過ぎ。移動の時間を考えれば、約30分後か。
件の大学が所有するセミナーハウス。
榊さんが予め調べて手を回してくれた。今夜宿泊する団体はないし、管理人も不在。
いや、この事件の当事者たちが所属していた登山サークル。
親睦会を兼ねて、次の登山予定を話し合う会議が今夜此処で開かれる。
一昨日、そういう筋書きのメールが会員全員に配信された。
勿論、当事者以外のメンバーには事情を説明するメールも。
人目を避け、鬼を滅する。
セミナーハウスの広い中庭は、これ以上無い舞台。しかし。
「師匠、ホントに欺せるんですか?もし見破られたら。」
そう、今夜逃げられたら、『期限』まで無差別な殺戮を止める方法はない。
「そういえば、鬼には殆どの術が効かないって。それなのに、どうやって。」
あの時、確かに姫はそう言った。鬼は術者に対抗するために造られたから、と。
「効くさ。これは鬼でなく、人の心に掛ける術だから。」
御影さんは寂しそうに微笑み、左手首に視線を落とした。
巻き付けた白い紙縒り。中にはある女性の髪が縒り込んである。
「でも師匠、もう人の心が消えてしまってる可能性もある訳でしょう?」
「いや未だ、操者は未だ人だ。」 「でも、それには何の保障も。」
その青年が饒舌なのは、実戦を目前にした心の高ぶり故だろう。
「既に4人殺されたが、全て男。つまり女が『最後』。
例え裏切られたと思っても、愛する者を殺すのを躊躇う。それが人の心。」
「なるほど、確かに。」
その、亜△という女性はセミナーハウスの中。厳重な結界を張った部屋で保護されている。
「分かったら無駄なお喋りは止めろ。為損ずれば、死ぬぞ。」
その時。遠くからバイクのエンジン音が近付いてきて、消えた。
「来たな。」
中庭を挟んで反対側、閉じた門の外に異様な気配。
高さ2m近い鉄の扉は施錠されている。しかし、鬼なら錠前を破壊するのに十分な、力が。
しかし、それは門扉の上端に手を掛け、軽々と飛び越えた。
「師匠、あれ、ヤバいですね。」
そうだ。鬼であろうと、操者はただの人間。短時間なら対応可能。
それが作戦の前提条件。しかし、あの身のこなしは明らかにただの人間ではない。
そう、かなりのアスリートか武術家でもなければ。
しかし最初の被害者、その遺体は子どもがいたぶり殺した虫のようだった。
武術家なら、あんな風には。一体、鬼にどんな変化が起きたのか。
「実戦に、多少の見込み違いはつきものだ。
作戦変更、先手を打つ。全力、殺すつもりでやれ。」
「殺すって、人は鬼を。」
「あれは貴様が武人だと知らぬ。悟られるな。機会は一瞬、一度きり。
貴様の先手で人の心は絶える。その後の相手は、正真正銘の鬼。」
それはゆっくりと中庭を横切り、2人の座るベンチに歩み寄る。
「怖いなぁ。」 「貴様、笑ってるぞ。」 始まる。
「...亜△。」
ベンチから少し離れた植え込みの陰で、俺はその声を聞いた。
底知れぬ威圧感。不吉な、調子。
「あんた誰?○樹に、頼まれたのね?」 「...」
「警察から聞いたわ。あんたがやったんでしょ?
ホント卑怯者よね、自分のしたことは棚に上げて復讐なんて。
それで、最後は捨てた女の所まで。最っ低。」
鬼は、ゆっくりと息を吸った。
「亜△、熱くなるなって。コイツ呼び出したらオレたちの役目は終了。
あとは警察に任せろ。卑怯者の元カレのせいで怪我なんて馬鹿馬鹿しい。
さ、もう行けよ。ほら、刑事さん達が来る。おっと。」
青年は立ち上がった。御影さんを追おうとした鬼の正面。
「どけ。」 「ムリ。元カレと違って、オレは卑怯者じゃないから。」
御影さんが植え込みの陰に駆け込んで来た。
「油断するな、必要なら剣を。」 「はい。」
手早く弓の弦を張る、手筈通りに肩を貸した。見事な手際。
いや、一瞬たりとも無駄に出来ない。 矢を取り、鏃の鞘を払うのを確認して走る。
所定の位置で短剣の柄を握った。もし青年が為損じても、御影さんが矢を射るまでは俺が。
背後で、御影さんの気が満ちていくのを感じる。もう少しで。
その気配に気付いたのか、鬼の注意が逸れた。その刹那。
鬼の顎に、青年の一撃。 嫌な、音。 続いてこめかみ、そして首。
鬼の体からがくんと力が抜け、両膝を付いた。
人間なら間違いなく致命傷、しかし青年は数歩離れて構えを取る...やはり。
数秒後。軽く首を振り、鬼は立ち上がった。回復している。もう、奇襲は通じない。
流星を、見たと思った。
スローモーションのように、一筋の青白い光が鬼へ向かっていく。
色とりどりの、数知れぬ光の粒子がそれを追いかける。
ああ、この矢は『月』だ。御影さんはあの時破魔の矢は『日月一対』だと。だから。
ぞっとする、うめき声。
鬼の胸に刺さった矢が、青い炎を吹いていた。思わず膝から力が抜ける。これで。
「おかしい。耐性、『真作』か?」 背後から御影さんの呟きが聞こえた。
「真、作?」 鬼が右手で矢を握った。微かな煙、肉の焦げる臭い。
そのまま、傷口近くから矢を折る。掌に焦げ付いた矢軸を振り捨てた。
青い炎が、消えかかっている。痛みを堪えるように、鬼は背中を丸めた。
まさか...矢は一本だけ。これで滅せないのなら、もう。
構えたまま、青年が後退る。目の前、俺を庇うように。
「Rさん。師匠を。」
鬼が、地面すれすれを跳んだ。
躱しきれず、青年の体が浮く。そのまま俺もまとめて、弾き飛ばされた。
途轍もない力と速度。受け身を取る間もなく、背中から地面に。
隣に、青年が倒れている。動かない、あのタックルをまともに受けたら...
そう言えば、鬼は? 3m程先に、倒れていた。ダメージはあるのだろうが。もし。
温かな手が、俺の頬に。覗き込む冷ややかな表情。御影、さん?
「緊急事態です。剣の委任を、△木野之主様に。」
「ああ、御影さんがこの短剣で...」 後頭部を打ったせいか、意識が。
「Rさん、早く。もう、鬼が。」 !! そうだ。委任の申告。
差し出した短剣を、柔らかな手が取った。 「有り難う、御座います。」
鞘が俺の手に、え? 視界の端、後ろ姿と、長剣。 ああ、神器に決まった形は無い。
御影さんが必要だと想えば...待て、さっき『Rさん』と、ならあれは。
何とか体をひねる。既に鬼は、立ち上がっていた。
あの構えは、確か『烈風』の型。 一度だけ、見た事がある。 まさか?
怯んだ鬼に向け、一直線。速い。
右からの袈裟懸け、間髪を入れず左下段から斬り上げる。
鈍い音がして、腕が地面に落ちた。鬼の、右腕。
タイミングからして、斬り上げた剣。斬れるなら、未だ望みがある。
しかし、御影さんは片膝を付いた。息が荒いし、動かない。
そうか、神器。一射で限界の矢、その後であの剣を。これ以上は、もう。
鬼が、右腕を拾い上げた。そのまま体を低く、攻撃態勢。
まずい。膝を付いた状態であのタックルを受けたら、いくら御影さんでも。
第一、体は生身。そしてその身体は姫の。
「間に合いましたね。御英断でした。」
「何年ぶりかな、貴方の運転は。速いが、目が回る。」
「今更そんな弱音を。さあ、御役目を。」
場違いな、穏やかな会話。夢か、しかしこの声は。
「相手が違うぞ、狙うべきは私だろう?」
夢ではない。明るい声。空気が軽く、乾いていく。
攻撃態勢の鬼へ、軽やかに歩み寄る後ろ姿。 !! 当主様、どうして!?
「やはり『真作』。よくもまあ、こんなおぞましいモノを。」
「当主、か。」
「そうだ。当代随一の武人。最高位の術者と式。桃花の方も。指揮は私。
旧い敵に、最大限の敬意を表した。これ程の布陣なら、思い残す事もあるまい。
『真作』も『亜作』も纏めて、哀しい因縁は今夜限り。」
鬼が攻撃態勢を解いた。真っ直ぐに当主様を見詰める。
「力が、欲しくはないか?」
滑らかな口調。これが、真の操者。そして、鬼を作った。
「ありふれた『亜作』などとは比較にならぬ、真の鬼。
破魔の矢一対でようやく。それ以外、どんな術者も武器も、式ですら無力。」
それは、低く湿った声で笑った。
「全てを水に流し、手を組もうぞ。御前達の術に、これが加われば文字通りの無敵。
楽々と天下を取れる、富も栄華も思いのまま。」
「何人必要だった?」 「何、だと?」
「その化物を作るために、何人殺してその体と命を使った?
あえて半端な術を広め、作らせた数多の『亜作』にも。一体どれだけの人と獣が。」
「性懲りも無く綺麗事を。力こそ、勝者こそ正義。正直になれ。
これを手に入れれば、身内の術者を敢えて危険に晒す必要もない。
さあ、その手でこの矢を抜け、それを契約の証としよう。」
「虐げ、奪い、殺す。本当に、それが楽しいか...
当時の当主に代わり、心から謝罪する。
魂が化物に逃げ込むのを防げなかったばかりか、化物の行方をも見失った。
そして終に、腐った性根を叩き直せなかった事を。」
「愚か者。この『力』を、我等の術の粋、これを無に帰すなど。」
「術の粋...なら、おぞましい化物を始末するのが我等の術」
「この矢、『月』でさえ始末出来ぬものをどうやって。」
「喋り過ぎだ。」 「何?」
「『破魔の矢一対でようやく』、予想通り。あれから我等は探し続け、手に入れた。
当時我等の一族が所有していなかった、『陽』を。」
鬼が攻撃態勢を取る前に、当主様は軽く右手を挙げた。
深い深い憂いを含んだ、寂しい微笑。
雷のような、閃光と轟音が俺の上を奔った。
それは当主様の右肩をかすめて鬼へ。
数秒後、それが立っていた場所に残ったのは、小さな灰の山。
歩み寄り、当主様が拾い上げた2つの鏃。それは恐らく、破魔の矢の本体。
「『真作』と分かっていればこれ程の...酷い事をした。」
「責めてはなりません。御自分も、周りも。皆、できる限りの事をしたのです。」
「しかし...いや、皆の手当を頼む。特にLは。」 「御意。」
『特にLは』って。じゃあ、あれはやはり御影さんでなく。
夢を、見ていた。
古い、大きなお屋敷の庭。俺の手に一本だけ、大きな、紅い花。
その花々が生け垣全体を彩っていた時には気が付かなかった、控えめで清らかな香り。
既視感。腕の中の温もり。深い光を湛えた双眸が、真っ直ぐに俺を見詰めている。
「どっちなんですか?今、あなたは。」 その美貌は微かに笑った。
「御影、だ。」 「じゃあ、あの時、剣を取ったのは。」
「本当に御前は良い嫁を持った。嫉妬で、この身が焼かれる程に。」
「冗談は止めて下さい。御影さん程の、なのに嫉妬だなんて。」
「この術に体を委ねている間も、周りの事情を把握できる。それは知っていた。
しかし、術の力を越えて体の制御を取り戻すなど、出来る筈がない。
なのにあの時、術も我も全くの無力だった。御前への、想いの前で。」
ああ、恐らく『禁呪』。しかも飛び切りの。
嬉しくないと言えば嘘になる。しかし反面、それで姫の寿命は縮んでしまうのだ。
「Lさんは『あの人』の娘です。少し位、他の術者と違っていても。」
「少し位?それがどういう事か、男には分からぬか。我がどれ程...」
「教えて下さい。どうすれば、御影さんの心が安らぐのか。
今回は、Lさんの力、御影さんの力、どちらが欠けても解決出来なかった。
当主様と桃花の方様が間に合ったのは、2人の力があったからです。」
数秒。唇を噛んで、ようやくその表情が緩んだ。
「朝まで、このまま寝かせてくれ。術が解けるまで。」
「分かりました。つまりLさんもそれを許して」 「黙れ。」
それからは時折、不思議な事が起きた。
例えばSさんが仕事に出て、姫と2人で子守をしている時。
丹を抱いて、姫はその寝顔を見詰めていると思ったのに。
「愛しいもの、なのだな。幼子とは。」 穏やかな呟き。 何時の、間に。
姫と遊んでいた翠が、呼びかける声に驚くこともある。
「みーちゃん、それ、違うよ。ほら、こうやって。」
どうやら2人は、もう術とは関係なく入れ替わる事が出来るらしい。
もちろん2人の同意が必要なのは自明だが、それがどんなタイミングで成立するのか、
そもそも2人がどうやってコミュニケーションを取っているのか、俺には分からない。
「相性からして『生まれ変わり』と言って良い程に他生の縁が深く、
あの術が2つの魂の垣根の一部を取り払った。そう考えるしかない。」
そう言ってSさんは笑った。「別に良いでしょ。特に困ることもないんだし。」と。
確かに、2人の感情表現は以前より豊かになったように感じる。
時を越え、それぞれに別々の旅路を生きる魂が成長できるなら、それは『良縁』。
しかし、俺が知らない内に2人が入れ替わるのは...
いや、俺の懸念など、『良縁』の前では取るに足らない事なのだ。
『鬼』 完
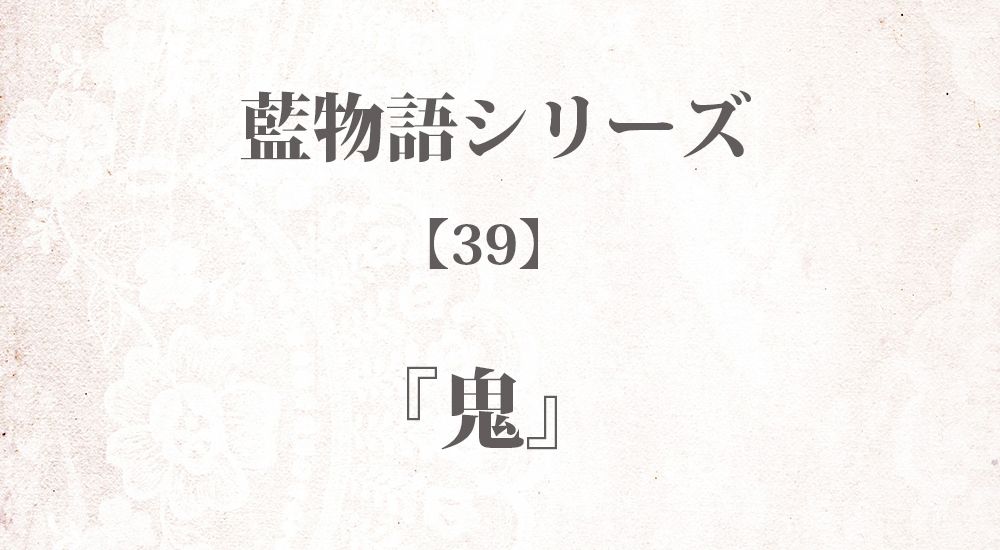
コメント