彼女は怪訝そうに眉をひそめた。 「何が『やっぱり』なの?」
「前に干渉された時の幻視で、幼い女の子を俺は見た。『L』と呼ばれていたが、違う。
確かにあの子にはLさんの面影があった。でも、あの子はLさんじゃない。」
「それで?」 彼女の顔色が蒼白く変わり、眼には刺すような光が宿っていた。
「あれは、あの女の子は、君だ。幼い頃、Lさんと同じように肉親を殺され、君は拉致された。」
彼女が左手を握りしめた、その手が小さく震えている。
「同じ哀しみを経験した君なら、Lさんの辛さが判るはずだ。頼む、彼女の術を解いてくれ。
術を解いてくれるなら、俺はどうなっても」
「...黙りなさい。」
少女の全身から、青い炎がユラユラと立ち上るのが見えた。
熱い。まるであたりの空気が燃えているようだ。チリチリと俺の髪と服が焦げる匂い。
「不愉快ね。」
「あなたの欲望に細工をすれば簡単だと思ってたけれど、それじゃ気が済まない。」
少女は俺を見下ろして微笑んだ。
「あなたの気持ちを変えるより、彼女の気持ちを変える方が面白そうだわ。
あなたの目の前で散々慰み物にされても、彼女は気持ちを変えずにいられるかしら。
どのみち妊娠の心配は無いし、楽しみね。」 腹の底から怒りが湧き上がってきた。
「やめろ!やめてくれ。そんな事をして何になる。不幸と憎しみの連鎖を生むだけだぞ。」
「『力』が手に入るわ。長い間、虐げられてきた私達の望みを叶える『力』が。」
「それは君達の組織の望みであって、決して君自身の望みではない筈だ。
他人の心や命を犠牲にしてまで叶える望みなんて、哀しすぎる。間違ってるよ。」
「あら、あなたはあの娘を救うためなら、私たちを犠牲にしても良いとは思わないの?」
「まあ、今はそんな事どうでも良いわ。そろそろお楽しみの時間よ。ほら。」
2人の男が部屋に入ってきた。ゆっくりと部屋の奥に歩いていく。
その時、俺の背後、手首の上で何かが動いた。
ふわふわの毛と、ロープを齧るような感触。管さん?
ロープが解けた。
俺は跳ね起きて走り、男たちに飛び掛った。管さんはシェパードほどの大きさになって
大蛇と睨み合っている。俺は何発か殴られたが、怒りのためか痛みは感じなかった。
1人を殴り倒し、もう1人に飛び掛った。倒れる男になぎ倒されるように少女も倒れた。
馬乗りになって殴り続けると、やがて男は動かなくなった。
菅さんは大蛇を部屋の外に追い出したのか、双方とも姿が見えなくなっている。
管さんのお陰で形勢は一気に逆転していた。
床に倒れた少女は上半身を起こしているが、男たちはぴくりとも動かない。
少女が悔しそうな表情でこちらを睨む。倒れた拍子にスカートが捲れたのか
白い太腿が露になっている。少女を見下ろしていると、激しい怒りに眼が眩む。
「Lさんにしようとしてた事、君にしてあげようか。どんな気持ちかな、自業自得だね。」
少女は俺の視線を辿り、あわててスカートを整えた。怯えた眼で俺から距離を取ろうとする。
俺は少女を押さえつけ、馬乗りになってセーラー服を引き裂いた。
下着をずらすと形の良い乳房が露わになる。少女は小さく悲鳴を上げた。
白く美しい裸体が目の前で震えている。激しい怒りが、暗く歪んだ欲望に変わっていた。
少女の乳房に手をかける。 「お願い、止めて。許して。」
一筋の涙が少女の頬を伝った。
その時、俺の心の中で何かが崩れた。俺は、一体何をするつもりだった?
それこそ、不幸と憎しみの連鎖を生むだけだ。狂った欲望は、既に哀しく醒めていた。
俺は少女から離れてのろのろと立ち上がり、上着を脱いで少女の体に掛けた。
「嫌な思いをさせて悪かった。あの娘を助けられれば、俺はそれで良いんだ。
君を酷い目に合わせるつもりなんて、全然無かった。本当に済まない。」
俺は部屋の奥に向かって歩き出した。姫が寝かされているソファへ。早く姫を。
「ふふふ。」背後で笑い声が響いた。
少女が、俺の上着を肩から羽織って立ち上がっていた。
「もう少しだったのに。あなた、面白いわね。」
激しい眩暈がして床に手をついた。
そこは俺の部屋で、目の前に着替えが散らばっていた。
壁の時計を見ると、どうやら「それ」は僅か1~2分間の出来事だったようだ。
幻視から醒めても、眩暈は一向に治まらなかった。
廊下を走る足音が近づいてきて、Sさんが俺の肩に手を掛けた。
「大丈夫?今、アイツの気配を感じたから。」 「...今回のはキツかったです。」
遅れて駆けつけてきた姫に俺を任せて、Sさんはホットウイスキーを作ってきてくれた。
それを飲むと眩暈が少し治まったので、リビングに移動してソファで横になった。
俺の顔色が相当に悪かったのか、あるいは夕食のためにダイニングへ移動しようとして
再びよろけて転んだのが悪かったのか、涙目の姫を説得することができず、夕食は
リビングのソファに横になったまま、姫に一匙ずつ食べさせて貰う羽目になった。
Sさんは姫と一緒に「はい、アーンして。」とか言って面白がっていたが、そのうち
先に1人で部屋に戻ってしまい、今回は俺の幻視の内容を聞かれる事はなかった。
俺は自分で食べられる事を何とか姫にアピールしたかったのだが、一生懸命で必死な
姫の顔を目の前にすると、先ほど判明した自分のセーラー服嗜好が後ろめたくて、
結局「スプーン食」を完食した(させて頂いた)。照れくさくて、辛い罰ゲームだった。
翌日、朝食後のコーヒーを飲みながら、Sさんが言った。
「昨夜の侵入経路を辿って、アイツ等の居場所を特定したわ。
既に『上』にも報告済みだし、今日中に対策班が踏み込むでしょうね。」
「アイツ等の計画は挫折して、Lさんを守りきれる、という事ですか?」
「対策班がアイツ等を完全に始末できれば良いんだけど、アイツ等だって
何とか逃げ延びて計画を完成させようとする筈だわ。だからおそらく今夜までが
山場になる。もう侵入の痕跡を残すのを怖れる必要も無いし、
一か八かで、R君に最大の干渉を仕掛けてくる筈。」
「だから罠を掛ける。」とSさんは言った。
「夕方から夜にかけて敢えて意識のコントロールを外す時間を作り、
アイツからの干渉を待って反撃する。」と。
「怪しまれませんか?第一、最大の干渉に僕の意識が耐えられるかどうか。」
前回の干渉を受けた時のダメージを考えると、正直全く自信が無かった。
「コントロールを外す時間をランダムにすれば怪しまれないし、
今度は私が付いてる。君の意識に私の意識を繋げておいて、
干渉があった瞬間に全力で反撃する。一気に決着を付けるわ。」
「干渉があるまでは、待っていなければいけないのでしょう?」 姫が問い掛ける。
「当然、そうなるわね。」 「じゃ、私の意識も繋げてお手伝いします。
そういうのは得意だし、2人より3人の方が、お互いの負担は小さくなりますよね。」
「あの、SさんとLさんの意識を僕の意識に繋げたとしたら、干渉を受けた時の、え~と
その、幻視は2人にも見えるんですか?」 もしそれだと俺のセーラー服嗜好が2人に。
「見えるけど、君が見ているものと全く同じかどうかは...」 Sさんが口ごもる。
「全く同じように見えた方が好都合ですよね。その方が反応し易いし。」 姫が微笑む。
これはもう覚悟するしかないんだな、と心を決めた。そう、色々な意味で。
昼食を済ませた後、俺は部屋で本を読んでいた。ふと、時計を見る。
2時40分だ、俺は読みかけの本を置いて部屋を出た。いつも3時頃には
皆でお茶かコーヒーを飲むことになっていて、その日は俺が当番だった。
リビングでカップやポットの準備をしていると、Sさんが駆け込んできた。
「あれ?」 「え?」 「君、何ともないの?」 「はい。」 Sさんは戸惑った顔だ。
「何かあったんですか?」 「確かにアイツの気配を感じたんだけど、おかしいわね。」
「僕は何も」と言いかけてハッとした。いつもなら俺の当番を手伝ってくれる姫がいない。
「あああ、あの、姫、いやLさんが。」 Sさんがものすごい勢いで走り出した。
俺も慌てて後を追う、姫の部屋へ。何故俺ではなく姫が...
Sさんがドアをノックして「L!L!」と呼び掛ける。返事がないと見るや
Sさんはドアを開けて中へ飛び込んだ。俺も続いて部屋の中に入る。
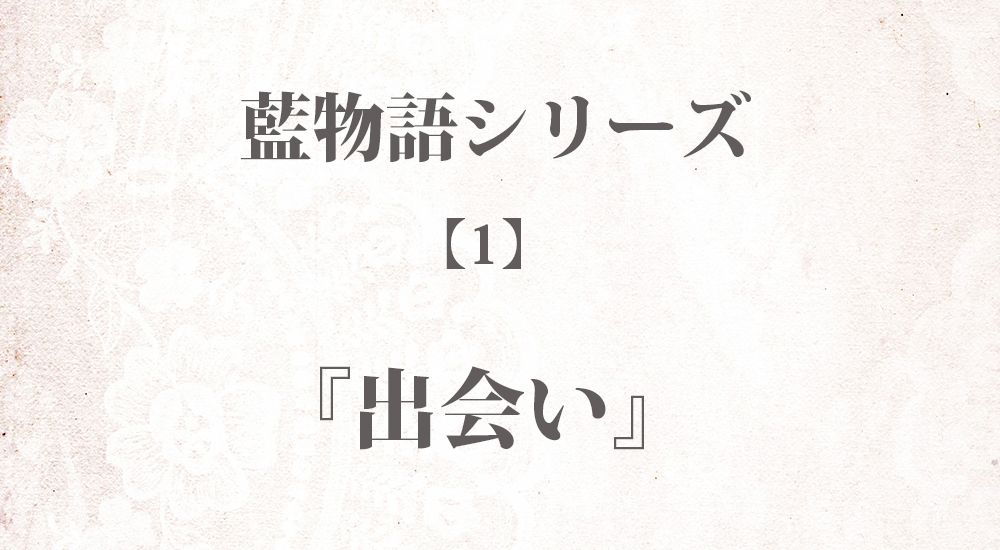
コメント