姫はベッドに横たわっていた。顔がいつにも増して蒼白く見える。
俺は姫のベッドに駆け寄った。寝ているだけか、息はしているか。
俺の頬に姫の吐息を感じた、息をしてる。大丈夫、なのか?
「息をしてます。」 「そうね、良かった。」 姫が身じろぎをして眼を開けた。
「あれ、Rさん。Sさんも。私、寝過ごしちゃいましたか?」
「L、あなた何ともない?」 Sさんの顔はまだ緊張したままだ。
「本を読んでいたら急に眠くなって、いつの間にか寝ちゃいました。
でも、何だかすごく良い気分です。」 姫は小さく伸びをして体を起こした。
「とってもお腹がすきました。昨日のケーキ、残ってましたよね。」
俺とSさんは顔を見合わせた。Sさんは一言だけ「どういう事?」と呟いた。
俺とSさんはホットコーヒー、姫はミルクティーと大きく切り分けたケーキ。
お茶の時間を終えて暫くすると、いよいよ俺たちはリビングで臨戦態勢に入った。
姫は未だ眠気が完全に覚めていないのか、時々小さく欠伸をしていたが、
Sさんの指揮の下、皆で「気配」が侵入してくるのを待ち続ける。
意識をコントロールする時間、コントロールを外す時間。ランダムに繰り返す。
ひたすら繰り返し、そしてKが干渉してくるのを待つ。只、じっと待つ。
何度それを繰り返したのか、不意に姫がSさんを人差し指でそっと突付いた。
「さっきから微かに気配を感じます。それに、段々気配が濃くなってる気がします。」
「多分、間違いない。...R君、あと2分経ったらコントロールを外して。」 「了解。」
Sさんが眼を閉じて深呼吸をする。意識を集中し、『力』を貯めているのが分かる。
じりじりと時間が過ぎていく。あと1分30秒、1分、30秒、20秒、10秒。
時計の秒針が直立した瞬間、俺は辺りに漂う気配に注意を向ける。『鍵』を外した。
通い路が開き、イメージが一気に流れ込んで来る。
その時、Sさんが叫んだ。「駄目、『鍵』を掛けて!アイツはもう」 しかし、遅かった。
そこは暗い部屋の中ではなく、草原の中の小さな公園だった。青い空が眩しい。
目の前に彼女、Kが立っていた。白いワンピースに麦藁帽子、
両手を腰の後ろで組んで、黙って俯いている。
「そうしていると、区別がつかない。君はあの娘と、どんな関係なんだ?」
麦藁帽子を取り、彼女はゆっくりと顔を上げた。真っ直ぐに俺を見つめている。
前回の少女の姿ではなく、成人した大人の女性の姿だ。言葉を失うほど美しい。
「今日も私を、『君』と呼ぶのね?」
「年下の女性は皆、『君』と呼ぶ事にしてる。今日は年上みたいだけど。」
「年上でも年下でも、私はあなたの敵なのよ。」
「この前は済まなかった。つい、逆上した。
でも、それぞれの生まれを選べない以上、敵対するしか無かった。」
「生まれが違っていたら、敵対する事は無かったと言うの?」
「絶対無かったなんて言えない、でも、出来れば君とは敵対したくない。
この前、君の肌に触れ、涙を見た時に、俺はそう思った。君は?」
彼女は傍らのブランコに乗り、もう一度俯いた。ブランコが静かに揺れる。
「何故、私はこんな風に生まれたのかしら?」
「何故、あの娘はあんな風に、生まれたのかしら?」
「何故、あの娘だけが、あなたに守られて、幸せに、なるの、かしら?」
「今の、あの娘の状態は、君が一番良く知っている筈じゃないのか?
あの娘だって、長い長い不幸な時間を過ごして」
「止めて!」
「あの娘は、あなたに会えたし、あなたに愛された。 私は、会えなかった。」
「私は、愛され、なかった。 誰にも。」
彼女の激情がチリチリと空気を焼く。しかし、それはあっけなく、弱まっていく。
ああ、そうだったのか。君は。涙が溢れてきた。
「もう、無理しなくて良いよ。今の君に、俺が出来るだけの事をさせてくれ。」
暗い小さな部屋で、体の半分を血に染めて、彼女は冷たい床の上に横たわっていた。
眼を閉じたまま、もう、呼吸音は途切れ途切れで、左胸から出血が続いている。
これではもう、助かるはずがない。静かに、彼女の傍らに膝をつく。
「こんな状態で、何故、無理をしたんだ?俺たちが罠を仕掛けている事くらい、
君なら予想できた筈なのに。どうして?」 涙が止まらない。
震える右手で彼女の頭を支え、左腕をゆっくり背中に廻して上半身を抱き起こした。
左掌で彼女の胸の傷を押さえ、小さな肩をそっと抱き締める。
彼女は目を開いた。「どうせ、死ぬのなら、あなたに、もう一度だけ、会いたかった。」
「お願いが、あるの。」 「何だ?何でも言ってくれ。」
「寂しい、の。私と、一緒に来て。あの娘の術は、もう、解いた、から。」
「私の事、愛してくれなくても、良い。一緒に来て頂戴、お願い。」
小さく咳き込んで、彼女は真っ赤な血を少し吐いた。
俺はシャツの袖口で彼女の口元を拭った。おそらくは、深く傷ついた肺からの喀血。
幼くして肉親を殺され、自分は拉致され、自分の生き方を選ぶことも出来ず
術師として生きてきて、年頃の女性らしい楽しみや幸せを感じる事も出来ないまま
それでも、凛として「悪趣味な術は使わない」と言い切った、誇り高く美しい人。
そんな人が、俺みたいなさえない男に、こんな事を...
何故、この人は、最後までこんな辛い思いをしなければいけないのか?
分からなかった。どんなに考えても、俺には分からなかった。でも、もう時間が無い。
恐らく、彼女に残された時間はもう極く僅かだ。俺は涙を拭った。
自分の顔に微笑が浮かぶのを感じる。
「分かった。行くよ、一緒に。」
息を呑んで彼女は俺の眼を見詰めた。沈黙の中、静かに時間が過ぎていく。
「馬鹿、ね。本気でそんな事、言うなんて。ちゃんと、あの娘を守って、愛して、あげて。」
彼女が僅かに左手を持ち上げた。その手をしっかりと握る。
ぎゅ、と俺の手を握る彼女の左手に力がこもった。
次の瞬間、景色が元に戻っていた。眩しい青空、草原の中の小さな公園。
彼女は微笑んでいる。「綺麗ね。 こんな場所で、あなたに、出会いたかった。」
俺は彼女の耳に囁いた。「.. ..... ......」 彼女だけのための、言葉。
彼女はゆっくり目を閉じた。目尻から一筋の涙が流れて、 ふっ と左手の力が抜けた。
何時の間にか、俺はリビングのソファに座り、じっと両手を見つめている。
べっとりと俺の両手と左胸を染める真っ赤な血。彼女の血。
「やっぱり、幻視じゃ無かった。」 俺は呆然と呟いた。
「こんな事って。」遠くでSさんの声が聞こえた後、
俺の意識は深い闇に吸い込まれた。
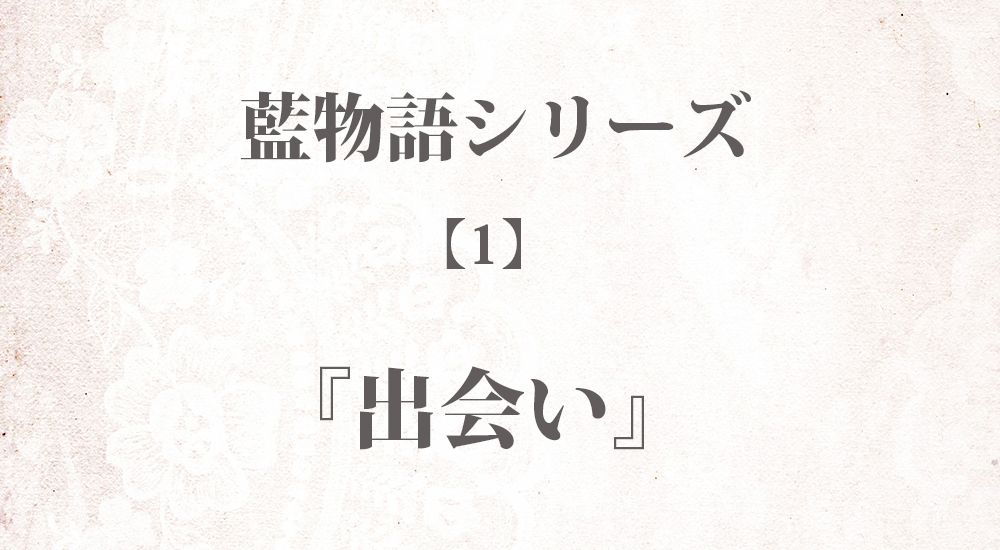
コメント